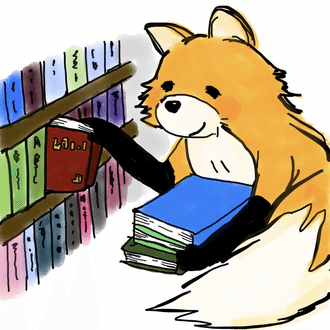“情報断捨離虎の巻”《マガジン“新書沼にようこそ” vol.17》
『情報の「捨て方」』/成毛眞
人生も仕事も、どう“情報を捨てるか”で質が決まる。「良い情報はどこ?」などと考える前に、疑え、見極めろ、距離を置け。人、街、テレビ、ネット、スマホ……知的生産をするための、「情報活用」以前の教科書。
成毛眞さんといえば書評サイト『HONZ』の代表。
本を読むプロ中のプロのお一人。
そんな方が教える情報活用のための取捨選択方法。
触れる情報と、触れない情報を、意識して区別する。端的に言えば、私に不要なくだらない情報をシャットアウトします。こうすることで、時間の浪費を極力、防いでいるのです。
ここで重要になるのは、何を「不要な情報」と考えるかでしょう。
私に不要な情報とは、私から遠いところにある情報(また、私に関係なさそうな情報)のことではありません。私に害を与える情報のことです。遠いところにある情報は知っていても損はせず、むしろ役立つこともあります。しかし、害を与える情報は、知っていて得をしないどころか、知ってしまったことを後悔するし、害を与える情報を好む人たちを引き寄せることにもつながり、まさに、百害あって一利なしの情報です。
ダメ情報、すなわち、間違いであっても、面白おかしく消費できればいいという考え方もあるかもしれません。
でも、本当にそうですかね。私はそうは思いません。ダメ情報はその存在を知っただけでよからぬダメージを受けると思っています。
なぜなら、ダメ情報に接し続けると、ダメ情報への免疫ができてしまい、ダメ情報を見分ける能力が著しく低下するからです。
「自分に不要な情報」と言い切れるのが羨ましい。
でも実際、ネットやSNSには、目にするだけで気持ちがざわざわするニュース多いですよね。つい気になって見てしまって、その後しばらく引きずるなんてこともままあります。
そうなるくらいなら見ない方がいい。
反面、最近、自分が知らないことを切って捨てる風潮があることに違和感を覚えはするのです。
たまに「趣味は映画鑑賞!でもヒッチコックとか知らない」「読書好きだよ!え?松本清張?誰それ?」とか聞きませんか?
「知らない」ことを貶すつもりはないのですが、自分が知らない=価値がないと突き放すのも違うのではないかなと思う。
今や「これが一般常識」というのも難しい時代だなと痛感するのです。
なので、その辺はバランス感覚かと。
「知らないと恥ずかしい」という感覚も大切。
でも情報に振り回されたり、傷ついたりするのも違う。
たくさん情報に溢れているし、知ろうと思えばいくらでも探せる今の時代だからこそ、情報の取捨選択能力は必要だと痛感します。
私は本を読むと、すぐにその内容を忘れてしまいます。たいていの場合、読んでいる途中で、前のほうに書いてあったことを忘れます。それでは書評が書けないので、付箋を貼りながら読んでいます。付箋を貼るのは、忘れることを前提とした作業なのです。
面白かった本を本棚に入れておくのも、忘却を織り込んでの行為です。そこに私の脳の外部記憶装置として本棚があり、本があるから、安心して忘れられると言えます。
成毛さんをして、そんな本の内容忘れるとかないと思うのですが!
でもご謙遜だとしても、そう聴くと多少慰められます。
(自分、読んだ本の内容覚えたためしがない)
ここに面白いこと書いてあるぞと、マーキングする気持ちで私もせっせと付箋を貼りながら読んでます。
(どちらかというと、結果、リスがどんぐり埋めるみたいになりがち←忘れる)
成毛眞さんを最初に知ったのはこちらの本
↓
10冊くらいにしておかなきゃな
(自分、もはや何冊併読しているかわかりません…)
最後までご覧下さり、ありがとうございました。 どうぞ素敵な読書生活を👋📚
いいなと思ったら応援しよう!