
電子音楽を聴く②
例によって?アンビエント系を除いた、テクノ/ハウス/エレクトロニック系アルバムの記録です。ちょっと書いては放置を繰り返したので、ほとんど半年以上前に聴いてたものの記録になってしまった。以下はこれまでの記事のまとめ。ゆるりとどうぞ。
Soul II Soul / Club Classics Vol. One (1989)

「いきなり電子音楽っぽくないんじゃないの!?」というツッコミはやめてください。良いじゃないですか、ソウル〜ファンク〜ディスコ〜ハウスの流れを汲む一世を風靡したダンスミュージックなんですから。
時は1980年代後半、UK発のグラウンド・ビート(ネオアコとかと同じく日本のみの呼称らしいので海外では通用しないみたい)と呼ばれる音楽が流行っていたらしい。その中心にはJazzie Bというドレッドヘアーの男がいた。Soul II Soulは彼のサウンドシステム(というからにはルーツはジャマイカ・レゲエ?)を母体に発足した音楽グループで、特にこのアルバムのM1「Keep On Movin'」はグラウンド・ビートを代表するクラシックとして親しまれている。
さて、完全後追いの自分にとって、この名盤はどこか古臭くも懐かしい感じのするR&B/ハウスミュージックという印象で、特に半分はダンスミュージックですらなく、むしろ打ち込みのR&Bというイメージだ。でも多分本作の影響は大きかったんだろうなと思うのが、これを聴いていてPrimal Scream「Screamadelica」や、Massive Attackなどのトリップホップ勢を思い出したこと。The Stone Rosesとも共振するかもしれない。だからか、このアルバムを聴いてると、この頃のUKに起きていたロックとクラブカルチャーの融合の片鱗に触れられた気分になる。
確かに人気のM1も良いんだけど、M5 "African Dance"の粘っこいグルーヴと暴れ回るフルートの旋律や、これぞハウスクラシック風なM8 "Hapiness (Dub)"が個人的には好きです。
Autechre / Amber (1994)

説明不要、IDMの巨人Autechreによるトルコのカッパドキアのパノラマ写真をジャケにした2ndアルバム。今後、更に研ぎ澄まされ、硬質に無機質になっていく彼らの音楽だけど、Amberはまだアンビエント感や繊細さ、柔らかさが強い作品だと思う。そして、メロディが顕著にあるので(彼らの作品にしてはという注釈付きだけど)聴きやすくもある。ただ、オウテカですから簡単な音楽では決してないですね。リズムは複雑だし、音色は多種多様。例えば、M2 "Motreal"ではフローリングでビー玉を転がしたような音がとても印象的だし、M6 "Piezo"なんかはファミコンでよく聞いたようなチープな音がこの不穏なトラックに絶妙にマッチしている。本当によくできた電子音楽で、よくもまあ1994年にこんなものをリリースしているなと感心するよ。
Oval / 94 Diskont (1995)

FenneszやJan Jelinekの元祖とも言えるグリッチ/エレクトロニカ/アンビエントの名盤。Ovalは元々ドイツ3人組の音楽ユニットだったが、このアルバムのリリース時にはMarkus Pop一人のプロジェクトとなっている。CD盤面にマジックで書いたり傷をつけたりしてわざと音飛びさせる手法、スキップノイズを駆使するなど、実験精神旺盛な姿勢が結実しており、美しきエレクトロニカ的ドローン/アンビエントに、所々ではさまれるブツブツ音が心をざわつかせる。これ95年リリースはなかなか先取りしてる感あるな〜。凄い。
いきなり20分にも及ぶ長尺トラックのM1 "Do While"はガチアンビエントだけど、全体通して聴くとアンビエントというよりエレクトロニカに括った方が良さそうに思ったので、この記事での紹介です。
Aphex Twin / Richard D. James Album (1997)

Aphex Twinのアルバムで初めて聴いたのはこれだったはず。まずジャケットのインパクトがヤバい。この歪んだ笑顔がドーンと置かれてるんだからシャイニングもびっくりですよ。当時流行していたドリルンベースがベースにあるんだけど、どこか悪趣味な要素が散りばめられ、Selected Ambient Worksの洗練されたアンビエントテクノはどこに行ってしまったのかと、リアルタイムで追っていた人はさぞ驚いたんじゃなかろうか。自分はこれから入って次にSelected Ambient Worksを聴いたから逆の意味で驚いたけど・・。
この悪趣味さはどこからくるのだろう。まず、ドリルンベースって攻撃的で破壊的なイメージが強いけど、そこに牧歌的で童謡的な要素を組み合わせちゃったのが本当に気持ち悪い。美しいメロディや子どもの歌声で郷愁を漂わせておきながら、強烈で複雑な高速ブレイクビーツで一気に台無しにする。人を良い気分にさせておいて一転地獄に突き落とすみたいな展開なのに、各所で大絶賛され、自分も結局心を掴まれている・・・。いやはや、リチャードDジェームスは天才というか鬼才だ。
Vladislav Delay / Multila (2000)

フィンランドの電子/音響系を代表する音楽家、Sasu Ripatti。Moritz Von Oswald Trioのひとりでもあり(2015年まで)、ハウスプロジェクトであるLuomo「Vocalcity」はPitchfrorkの00年代ベストでも43位に位置付けられていた。それくらいレジェンド級の人だと思うが、Sasu Ripattiにとって最も中心的プロジェクトであるVladislav Delayは、例えばインディーロック等をはじめとした他ジャンルをメインに聴く層に対してはイマイチ浸透していない気がする(実際に自分が知るのも遅かった)。
本作は、ダブテクノの始祖Basic ChannelのレーベルであるChain ReactionからリリースされたEP「Huone」と「Ranta」をまとめたコンピレーションで、間違いなくミニマルダブ/ダブテクノの名盤。ひたすら霧がかかったディープなサウンドスケープはまさに近年のダブ・アンビエントにもつながっていくものだし、重たいキックはボディブローのようにジワジワと、そして確実にリスナーの体内にダメージを与えてくる。息苦しくなるほど濃密な世界。そして、白眉は20分超えのダブテクノトラックM3 "Huone"。これをスモークかかった箱で聴けたら脳まで溶ける。
Dntel / Life Is Full of Possibilities (2001)

Dntelはアメリカのアーティストで、00年代の名盤ランキングでよく見るThe Postal Serviceの中の人。全然知らなかったんだけど、ドリームポップ/シューゲイザーっぽい、なんなら最近のダブアンビエントとも共振するようなサウンドスケープに、野太いローや実験的なグリッチノイズが配置されていて、もうめちゃくちゃ好み。また、ゲストも多数で、Death Cab For CutieのBen Gibbardが歌うM9はなかなかにエモく、まさに本作のハイライトでしょう(どうも本作でのコラボがきっかけで、Ben GibbardとThe Postal Serviceをやろうってことになったみたい)。
そもそもこの人を聴こうと思ったのは、West Mineral系統のダブアンビエントをやるPicnicの2021年にリリースされたアルバムで、Huerco S.やuonと並んでリミックスをしていたからなんだけど、このアルバムを聴いてその人選にはかなり納得。全体的には00年代のエレクトロニカっぽさが強いんだけど、既に書いとおり、所々で最近のサウンドへの影響を感じられ、改めて再評価されても良いんじゃないかと思う。
Caribou / The Milk of Human Kindness (2005)

カナダの音楽家Dan Snaithもとい、Caribouとの出会いは2010年の名盤「Swim」であり、当時インディーロック小僧だった自分にかなりの衝撃を与えた。のちに知るArthur Russellのようなユーモア溢れるダンスミュージックに完全に恋に落ちてしまい、鬼のようにリピートした。その後の「Our Love」、「Suddenly」は自分の観測範囲でも多くの人に絶賛されていたように記憶しており、もちろん自分にとっても大好物だった。ということでCaribouは自分の中では「間違いのない音楽家」の一人だ。
そんなCaribou名義では初となるのが本作「The Milk of Human Kindness」。断っておくと、Caribouの作品ということで本記事で取り上げてしまったが、本作は一般的にイメージする「電子音楽」ではない。Manitoba時代にリリースした前作「Up In Flame」の続編のような、サイケデリック、フォーク、エレクトロニカのごった煮サイケポップである。本記事で取り上げちゃってすみません。
本作は本当にカラフルな楽曲で占められていて、M4のビートがヒップホップのブレイクビーツっぽいと思えば、M5ではノイ!を思わせるハンマービートソングになったりする。M10はFour Tetの楽曲と間違えるレベルの美しいフォークトロニカだし、なかなか意味がわからない。それでもアルバム通して統一感を感じるのは、Caribou自身から隠しきれない愛くるしさが滲み出ちゃっているからに他ならない。もうCaribouは絶対に良い人。間違いない。
Daniel Avery / Drone Logic (2013)
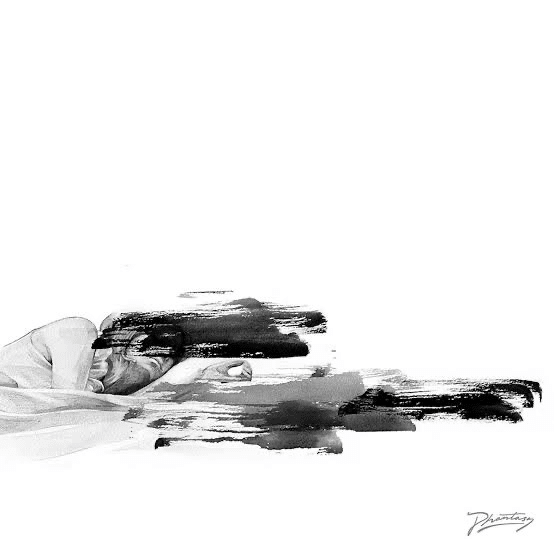
UKボーンマス出身のエレクトロニックミュージシャン、Daniel Averyのデビュー作。ロンドンのトップDJであるErol Alkan主催Phantasy Soundレーベルからのリリースだそうだ。Chemical BrothersやUnderworldのような大きなビートからは、ミニマルテクノやポストダブステップ的な潮流とはまた異なる流れを指向している。といっても古臭い音かといえばそんなことは全然なく、そのサウンドは、スペーシー/コズミックだったり、ノイジー/シューゲイザーだったりと多彩、かつ余白を意識した音作りが有効に機能していたりと、大きなキックだけでなく、リスナーをダンストリップに導く仕掛けが満載だ。そうだな・・・、なんならWarpのLFOに似たかっこよさを感じる。
とにかく今回のラインナップの中ではもっともテクノ/レイブしており、フロアライクなトラックが多くを占めている。たまにはこういうのを摂取することも大切だよね。
Moritz Von Oswald Trio / Sounding Lines (2015)

ダブテクノの始祖Basic ChannelのMoritz Von Oswald、アンビエントハウスの代表格Sun ElectricのMax Loderbauer、上述のとおり、LuomoやVladislav Delayとして活躍するSasu Ripattiの3名で活動していたMoritz Von Oswald Trioだが、本作の前にSasu Ripattiが脱退、その代わりにアフロビートのレジェンドTony Allenを招いての2015年作である。ここまででも有名人の名前しか出てこないが、今作のミックスはRicard Villalobosが担当。なんともまー贅沢である。
まず、印象的なのはTony Allenの禁欲的で性格無比なドラムで、Von OswaldとMax Loderbauerの無機質で呪術的な電子音との絡みが想像以上にマッチしており、単なるミニマルテクノの域に収まらない多層的な作品に仕上げることに貢献している。なんというかTony Allenの凄さを改めて実感したよ。特にM6、M7なんかはアフロビートと電子音楽の素晴らしき邂逅と言ってもいい出来栄え。そして、Villalobosのミニマルなミックスは、曲によっては「Villalobosの作品かな?」と思わせるくらい、彼の色を感じる瞬間がある。
特にそれぞれの曲に固有の名前はついていないことと、アルバム全体として抑揚のついたメリハリ効いた展開からは「アルバム通して聴いてほしい」という本人たちの意図を感じる。なんとも上質な49分間。
Shinichi Atobe / From the Heart, It's a Start, a Work of Art (2017)

この日本人プロデューサーはかなり謎に包まれた存在であるが、その名が広まる最初のきっかけはChain Reaction(この記事で何度この名前を書いたことか)から2001年にリリースされた「Shin-Scope」。そのディープで繊細なサウンドに界隈では大きな話題になったらしい。そして次のリリースである2014年の「The Butterfly Effect」で、名実ともにダブテクノ界隈の優れたプロデューサーの一人として名を馳せるようになった。今作は「Shin-Scope」よりも前、2000年ごろに作成されたトラックと、新曲が混ざったアルバムで、Demdike StareのDDSレコードからリリースされている。
このミニマルディープテクノの何が良いって、ストイックながらメロディアスに響かせる展開の妙でしょう。日本人らしく謙虚で実直な姿勢と美的センスが結実した素晴らしいダンスミュージックだと思う。ちなみに次作の「Heat」はさらに素晴らしい内容なので、これを気に入った人はそっちもぜひ聴いてほしい。というか他も含めて全部必聴!
