
2024年年間ベストアルバム25
今年も恒例の年間ベストを何とか書いたぞ。
2024年は下半期がアホほど忙しく、コロナ禍で激増したリスニングタイムもまた改めて激減してしまい、ここ数年と比較したら明らかに新譜を追えなかった年だった。ただ、それでも2024年の前半はルーツレゲエ/ダブを掘り進んでみたり、トータルではここに挙げたような素晴らしいアルバムたちと出会えたり、振り返ると普通に良い年だったとしみじみと思う。
では、これが自分の2024年を象徴する25枚です。
25. Floating Points / Cascade

今年はFour Tet、Caribou、Kelly Lee Owens、Jamie xxなどのビッグネームがこぞってアッパーなダンスレコードをリリースしたが、その中でも個人的にはFloating Pointsのアルバムに一番惹かれた。Floating Pointsは繊細な電子音楽家なイメージが強い気がするが、元々はバリバリのフロア向けダンストラックをバンバンリリースしていた人であり、実は初期のEPも好きな自分にとっては驚きつつも結構好ましい変化であったりした。というかね、流石にここまで全曲キラーチューンで構成するとは想像もしてなかったですよ。まずキックの圧が強烈。これまでの作品の中でも一番効いてるのでは?一方では、彼のこれまでの経験で培ってきた繊細なエレクトロニクス使いが変に俗っぽいトラックに陥ることを防いでいて、あくまで上品なダンスミュージック集に仕上げていると思う。彼が未だに一級のテクノ/ハウスプロデューサーであることを証明する作品。
24. K. Freund / Trash Can Lamb

オハイオのマルチ奏者Keith Freundのソロ新作。<Soda Gong>からのリリースは、グリッチノイズとエレクトロニカをベースにピアノ、サックスといったジャジーな音色が彩りを与えることで上質な空間を演出した実に優雅な一枚だった。コーヒーにも合うし、ウィスキーとかも合う。とにかく、なんかそういった類の飲み物を片手に快適な部屋と高品質のスピーカーで聴く音楽として2024年ナンバーワンだった。ちなみに家には高品質のスピーカーもないし、ウィスキーも飲まないので全ては妄想なんだけど、まぁそんな感じです。
23. Jasmine Wood / Piano Reverb (2024)

アイルランド・ダブリンを拠点とするピアニスト/コンポーザーであるJasine Woodの今作は、廃墟となった教会にグランドピアノを持ち込んで、そこで充満した和音・単音を丁寧に録音して持続音だけを残したという。たぶんアルバムジャケが教会内で、この茶色いクラシックなピアノを使って録音したんだろう。個人的にこのアルバムの好きなところは、和音ドローンとノイズ混じりのドローンが混在しているのと、時にクラシカルなピアノが良いアクセントになっていること。そして、アルバム全体としてコンパクトにまとまってるのも聴き疲れしなくて自分のリスニング環境によく合った。
22. Not Waving & Romance / Infinite Light (2024)

今年の「天に召される系アンビエント」のベスト。そもそも他にこんな感じのを今年の新譜では聴けてないというだけではあるかもなんだけど、Stars of the LidやJulianna Barwickとかが好きな人には全力でオススメしたい。Not Wavingは全然知らなかったんだけど、Romanceは一昨年にその存在を知ってから自分の中でかなり好きなアンビエント作家の一人になった。とにかくボーカルサンプリングの使い方が面白いんだよね。大胆でエモーショナルだけどアンビエントとして機能する形は完全にRomanceの シグネチャーになっていると思う。
21. Dialect / Atlas of Green

菅弦楽器が中心となったこの音楽作品はチェンバーポップと紙一重だなとも思うけど、おもちゃ箱をひっくり返したかのように多彩な音を鳴らしつつ、電子的なエフェクトを巧みに使うことでアンビエントとして機能させる手腕に拍手。牧歌的でノスタルジックな世界観は、今年割と忙殺され気味だった自分の癒しになってくれた。ちなみに今年はリバプールに旅行に行ったんだけど(プレミアリーグとビートルズが目的)、Dialectもリバプール出身だと知ってからこの作品がさらに身近に感じられるようになり、余計に好きになった。
20. LI YILEI / NONAGE (2024)

中国出身でロンドン拠点のLI YILEIは、2021年のアジアン・アンビエントの傑作「之/OF」が最高すぎたけど、2022年の「Secondary Self」は正直そこまでピンとこず、突き刺すようなサウンドデザインがどうもハマらなかった。そんな中で、今年2024年リリースの今作は良い。テーマは子供時代のようで、おもちゃのピアノ、手回しオルゴール、鳥の口笛、壊れたアコーディオンなど、子供時代を回想するにふさわしいサンプルや音源が用いられているそうだ。メランコリックな音使い、モコモコしたシンセで楽曲が柔らかい雰囲気、適度に実験的なトラックと、バラエティは豊かだが、一本筋が通っているように聴こえる。あと、この人はフィールドレコーディングの素材の使い方が上手だなと思う。それ一辺倒になりすぎず、かといって存在感はしっかりある。そんなバランス感覚が特に好ましく思う理由かもしれない。
19. Clara La San / Made Mistakes

インターネット(Soundcloud、Youtube、TikTok)などで注目を集めていたUKシンガー、Clara La Sanのデビューアルバム。自分のライブラリーを彼女の名前で検索してみると、Bicepの2021年作で2曲、Jam Cityの2023年作の1曲目でゲストボーカルとして参加していた。一聴すると、Boomkatでも言及されているように、まるでBurialのトラックに載せても全く違和感のないような、幽玄で艶のある歌声が強力に耳に残る。そして、USカルチャーとUKカルチャーがこの上ないくらいに自然に溶け込んだ説得力のあるR&Bサウンドが素晴らしいと感じた。お気に入りトラックはクセになるメロディの乗せ方をしているトラップビート使いの"Runnin" 、エモーショナルなメロディと歌声にグッときてしまう"Made Me Soul"。やはりUKミュージックは夜が圧倒的に似合う。
18. Chihei Hatakeyama & Shun Ishiwaka / Magnificent Little Dudes, Volume 01. (2024)

天に召されるような上質なアンビエント/ドローンを奏でる日本を代表するアンビエントアーティスト畠山地平と、くるりやKID FRESINOのゲストドラマーとしてもよく耳にする新進気鋭のジャズドラマー石若駿によるコラボ作品。一般的にはアンビエントにリズムはない(あったとしてもごく僅か)ので、アンビエントとドラムの組み合わせはミスマッチなようにも思われる。ただ、この作品のハーモニーは完璧と言っても過言ではないほどで、畠山地平の極上のサウンドスケープを全く損ねることなく、石若駿のドラミングが映えるという、絶妙なバランス感覚を発揮している。シカゴに出張に行った際に、都会の水辺でこれ聴きながらボーッとした時間は今年の個人的ハイライトの一つ。
17. Actress / Statik (2024)

まるでAphex TwinのSAWを思わせるような甘美なメロディとActressらしい繊細な電子音の広がりの妙か、これまでのActress作品の中でも最も聴き心地の良い作品に仕上がった。Kelly Lee Owens、Carman Villain、Perilaなど、近年特に良作を連発しているノルウェーの<Smalltown Supersound>のリリースということが影響しているのか、本作は過去作のダークな世界観が少し柔和になった雰囲気を感じている。なんとなくどこか「淡く丸い」のである。ビートやノイズは普通にあるもののメインを張るというよりはアクセントとして機能している印象で、幾重にも丁寧に重ねられたレイヤーが全体の雰囲気を決定づける中心として機能している。ドローン曲もあり、全体的にアンビエント的側面が強い。そんなトーンだからか、個人的にはこれまでの作品以上に日常のあらゆるシーンで重宝し、必然と再生回数が重ねられ、2024年の愛聴版の一つとなった。
16. Skee Mask / ISS010

我らがSkee MaskのISS(Ilian Skee Series)の最新作。彼らは他に「Resort」というちゃんとしたアルバムもリリースしているんだけど、個人的にはそちらよりもこっち。今作では昔FFKTで観た超アグレッシブなプレイを思い起こさせるレベルで圧の強いダブテクノを展開しており、BPM140台のアタッキングテクノ集はあまりに痛快。Resortのアンビエントもテクノもある総合的な作風よりも、この一貫した作品に自分は心底ハマったし、気持ちをアップリフティングしたい時にはよくこれを聴いたな。
15. KMRU / Natur
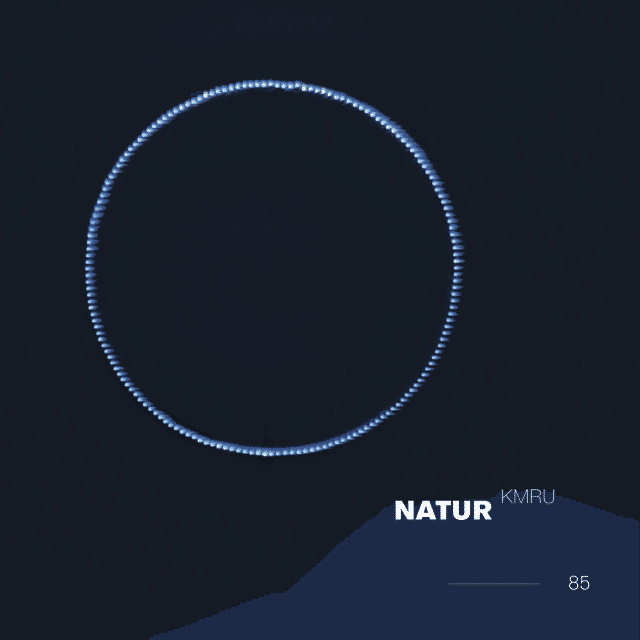
ケニアナイロビ出身の20年代最も素晴らしいアンビエント作家の一人といえばこのKMRU。多作すぎる彼の今年のリリース作の中で最も心に響いたのが、Fennesz作品で特に有名な英国<Touch>よりリリースされたこの「Natur」だった。彼の大傑作「Peel」(2000年)がケニアナイロビのアルバムであるならば、本作は移住先ベルリンのアルバムと言えそう。いかにも<Touch>と感じる微細な電子ノイズであり、無機質なドローンサウンドは「Peel」と比較しても、明らかに硬質で鋭利のような尖っている。この辺りは昼も夜も境目がよくわからない人工的な都市風景にインスパイアされたものなんだろうと思う。今作を聴いていると、人工的な風景に浸かりきってしまった自分の環境を今一度見つめ直したら?と言われているような、そんな気分になってくる。とにかく「Peel」とはまた異なる、機械電子音響ドローンの世界に没入したければ本作を聴くべし。
14. Charli xcx / BRAT (2024)

PCミュージック、SOPHIEの意思を継いだバブルガムサウンドと元より持っていた抜群のポップセンスを掛け合わせた2024年最高のポップアルバム。全曲キラーと言っても過言ではないような仕上がりっぷりには、普段「どポップ」な音楽からは結構離れてしまってる自分でも土下座をせざるを得なかったです。一聴しただけで虜になるような即効性だけでなく、スルメのようにジワジワと後から効いてくる側面も持ってるのがあまりに強い。また、各曲2-3分と短く、なんかエレクトロパンクっぽいのも良かった。リミックス盤も面白かったし、各メディアのリストを見ても分かるとおり、完全に今年の顔だった。
13. MIZU / Forest Scenes (2024)

ニューヨークのチェリスト、MIZUは今年知ったアーティストの中でも自分的に大ヒット。実験的な電子音と環境音の上で踊るチェロのメロディがなんとも印象深く、何度も何度も聴いた。気に入ってるポイントは全体的に躍動感があること。電子音もチェロもスウィングしており、まるで生命や自然の美しさや移り変わりに対する喜びを表現するかのようだなと思う。10分超えの最後の曲"Realms of Possibility"の鼓動のような低音と優雅なチェロの響きのコラボレーションは至高の領域にあり、まさにその感覚を体現する曲。
12. Shabaka / Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace (2024)

楽器をサックスから尺八に持ち替えたShabaka Hutchingsによるソロ名義のファーストアルバム。完全にスピリチュアル/ニューエイジなアルバムで、Suns of Kemet、Comet Is Comingみたいなエネルギー溢れる音楽を期待して聴くと完全に肩透かしを喰らってしまうが、ここ2、3年でアンビエントがかなり好きになった自分にとってこのモードのシャバカは実に心地よく、興味深く聴ける。哀愁漂うクラリネットの音色と、壊れてしまいそうなピアノの旋律、繊細なエレクトロニクス、これらの絡み合いを聴いてると必然的に内省の旅へとワープさせられる。本作のハイライトはFloating PointsとLaraajiをfeatureしたM7 "I'll Do Whatever You Want"であることに間違いないが(フルートはAndre 3000)、その他M6"Body to Inhabit"でE L U C I Dが参加してたり、M8 "Living"で印象的なボーカルを聴かせるEskaの存在感だったりと、多彩なゲストの活躍も印象に残るアルバムだ。今年はニューヨークのBlue NotesでShabakaのライブを観る機会があったのもこのアルバムを一際思い出深いものにしてくれた。
11. chantsss / Shyness

イタリアベースのChantsssのデビュー作。Huerco S.周辺に近しいダブアンビエント的テクスチャと室内楽音楽が合わさった、アンビエントとドリームポップの中間のような音楽だなという印象で、当然のように好みだった。曲によっては不整脈かのように不規則に鳴らされる鼓動のようなキックが入ったり、幽玄なボーカル曲があったり、アコースティックなチェンバーアンビエントがあったりと幅は広く、コンパクトなアルバムながら飽きずに何度も楽しめるやつ。アルバムジャケットもサウンドを体現していて好き。
10. Loidis / One Day

ローファイハウスの騎手としてデビューしたHuerco S.による極上のハウス集で、Huerco S.大好きマンとしては当然のように推さざるをえない。彼独特のアナログな質感はどこまでいっても最高で唯一無二。なんだろうな、丸みを帯びた説得力のあるキックが心の臓まで貫いてくるのが堪らなく気持ちがいいのよ。彼のシグネチャーでもあるオブスキュアなウワモノも言うことないし、2024年で最も聴いてて心地よく、かつ身体が踊り出すダンスレコードだった。
9. Shinichi Atobe / Discipline

日本のテクノミュージシャンで一番好きと言っても過言ではないShinichi Atobeの新作がこの年末にドロップ。まだ聴き込み不足ではあるけど、大傑作「Heat」に引けを取らないレベルで気に入ってる(まぁ「Heat」と同等はちょっと言い過ぎかもしれない)。Shinichi Atobeの何が好きかって、ストイックなビートと日本人的メランコリーな感覚が同居している点にあって、Discipline(キングクリムゾンのアルバムからっぽい)と銘打たれた本作も規律的なリズムパターンと情緒に働きかけるようなウワモノが有機的に絡み合って一つの生き物のように動き回るテクノで最高。最後のM8なんかはBPMを少し落としたハウス調の曲で新機軸だなーとか思った。
8. Mount Eerie / Night Palace

凄まじい大作。これはUSインディー好きはもれなく歓喜する類のアルバムだ。とりあえず静から動への切り替わりがすごい。すべての音に緊張感が宿っていて、大袈裟だけど息をするのも忘れてしまうくらい。この半年アメリカに住んでその広大な土地と多様な社会を目の当たりにして、良くも悪くもアメリカって強いなと思うことが多かったんだけど、そんなUSの厳しさやなんでも飲み込んでしまう包容力を総括しているように感じる。それは荒野で吹き荒ぶ風の音だったり、激情を表すような歪んだギターやノイズだったり、Mount Eerieの優しいボーカルワークだったり。1分程度の小品から10分越えの大曲まで様々な表情を見せつつアルバムとしてのまとまりがちゃんとあるのも素晴らしい。M7 "I Walk"中盤の転調の瞬間などは個人的2024ベストモーメントのひとつ。
7. Shuta Hiraki / Lyrisme Météorologique

よろすずさんことShuta Hiraki氏の新譜。正直素晴らしいことこの上ないドローンミュージック。ドローンというと果てしなく続く持続音が微妙に変化していく様を楽しむものという認識が個人的にあるんだけど、本作は持続音が基本といえども切り替えが頻繁に起こったり音の揺れが大きかったりするので、ドローンというよりは室内楽コラージュ的アンビエントな捉え方をした方がしっくりきた。どこかアナログっぽい懐かしい質感もあるけど、どうもインドのドローン楽器であるシュルティボックス(初めて聞いた)とシンセサイザーを連動させて作ったようで、特にシュルティボックスの役割が大きそう。
よろすずさんはnoteやTURNに寄稿している音楽記事などの文章もめちゃめちゃ面白いし、本アルバム以外の楽曲も白眉な出来のものばかりで本当に信頼できる音楽家です。別途11月にリリースされた新曲"Graveyard"は、アルバムとはまた異なり、暴力的な金属ノイズから静寂へと移行するダイナミックな展開が別の意味でヤバすぎたのでこちらも必聴です。
6. Ulla & Ultrafog / It Means A Lot (2024)

柔らかなアンビエントといえばUllaの右に出るものはいないのではないか。アメリカのアンビエント作家と日本のUltrafogのコラボ作は、2024年で一番優しく包み込むような作品だった。グリッチ、ASMR、シューゲイザー、カットアップされたボーカルなど、様々な要素が顔を出しては霧の中に消えていく。ウォールオブサウンド的なアンビエントではなく、霞のような音の断片が混ざり融解していくコラージュサウンドであって、サウンドと余白の使い分けが抜群である。あと、地味にブォーンって感じのダブっぽい低音が効いてるのがまた良いんだよな。ここ数年自分が心惹かれ続けているサウンドってこういうのだよなと改めて思う。
5. Kim Gordon / The Collective (2024)

ヒップホップのビートと持ち前のエクスペリメンタルなノイズサウンドを組み合わせて、齢70を超えてなお自分の表現を更新しにかかるKim Gordon姐さんの姿勢とカッコよさに感服。M1"Bye Bye"の踏切音のイントロからして緊張感とクールネスに溢れており、その張り詰めた空気が全編にわたり全く損なわれることがない。また、グランジやオルタナティブロックさながらなかっこいいギターがスパイスのようにエモーショナルに鳴り響き、そこがまた身体の芯まで痺れる。こんなカッコよく歳を取りたいと誰もが思うだろうベテランからの会心の一撃。
4. Watson / Soul Quake 2

言葉をダイレクトに脳に響かせられるラッパーって稀有な存在だ。日本語ラップシーンのことを全然わかっていない自分でも、Watsonは間違いなくそんな希少なラッパーであると感じる。なんだろう、昔悪いことしちゃってたけど別にそれをひけらかす感じではない、その等身大のリリックがいいのかね?また、今回のアルバムは10曲26分というコンパクトさと、ゲストは一切なしでWatsonがマイクを一人で握ってるのが個人的には良かった。前作も
好きなんだけど、こっちの方がずっといい。ダレることなく、何度も何度もリピートできる。この中だと、"阿波弁"、"Tokushima"といった地元モチーフの曲が特にお気に入り(阿波弁のMV最高)。自分は地元ヤンキーたちのあの感じにあまり馴染めなかった人間なので地元リスペクトする人間では全くないんだけど、Watsonの地元リスペクトには好感が持てる。あと、アッパーもメロウでチルイのもイケちゃう、こしあっつーでお馴染み?のKoshyの仕事っぷりが素晴らしい。KOHHこと千葉雄喜のアルバムでの仕事っぷりも最高だった。
3. Nicolas Jaar / Piedras 1 & 2

なんとなくメディアでもTwitterでも無視されてるような気がするNicolas Jarr氏の4年ぶりのアルバム。なんか聴けば聴くほど凄いアルバムなのではと思うようになってきた。Nicolas Jaarが育った国、チリの独裁者ピノチェトによる軍事政権下で行われた数々の人権侵害、抑圧の犠牲者を追悼する作品とのことで、2022年からラジオ劇中に用いられた新曲が収録されている。「Piedras 1」の方は彼の呪術的で色気のあるボーカルが全面的にフィーチャーされた作品で、一方で「Piedras 2」の方は実験的アンビエントといってもいいビートレスの曲が中心。一聴して、いくつかの曲では音がぶつ切りになったり右に左に不規則に振れたりと、その極端で断片的なサウンドデザインが強く印象に残ったが、本アルバムの舞台が「ネット遮断され、DIYラジオでしか情報を入手できない世界」ということで、とても腑に落ちるものがあった。そんな中で自分の心を掴んでやまないのが、Against All Logicでの経験を血肉化したような実験的ダンストラック。「Piedras 1」のM6 "Viento"や「Piedras 2」のラスト3曲のカタルシスたるやたまらないものがある。この辺の起伏のあるアルバム構成は劇中曲ということが関係しているんだろうな。意識するまでわからないような中南米的なエッセンスの盛り込み方は相変わらず他と一線を画しているし、彼の集大成として控えめに傑作と断じていいと思います。
2. Clairo / Charm (2024)

リリース当初はいいアルバムだなーくらいの感想だったのが、この3ヶ月で徐々に自分の中で評価が高まり、最終的にはこんな順位に。まさか自分がClairoをこんな順位に置くことになろうとは。Clairoに対してはこれまでそこまで興味がなかったので過去作とかも対して聴いてないんだけど、今作はバッチリ自分にハマったね。アナログで適度にレイドバックしたサウンドと、Clairoの艶やかだけど儚さのあるボーカルのブレンド感が絶妙。サウンドだけでなくレトロ趣味なジャケット(80年代の日本のアイドルみたいだ)まで完璧。何よりメロディメーカーっぷりが開花してるのでは?とにかく今作はどの曲も芯がしっかりしてて思わず鼻歌を歌っちゃうくらい脳に残る。しかも全然飾らない、自然体な姿から発せられるメロディであることがよくわかり、そこがまたなんだか胸を打つ。個人的に特に好きな曲はM1"Nomad" 、M2"Sexy to Someone"、M4"Slow Dance" 、M7"Juna"あたり。間違いなく長い年月にも耐えうる強度を備えたアルバムで、70年代のソウルアルバムと並べて聴きたい。
1. Jlin / Akoma (2024)

米北西部インディアナからフットワークの新星としてデビューアルバム「Dark Energy」をリリースしてからはや9年、Jlinはここまで進化した!と言わんばかりに痛快な内容だと思う。元々あった実験性はもちろん引き継ぎつつ、より外に開けたような解放感を感じる。そう感じるのはダンスミュージックとしての機能性が高まったからだろうか。とにかく全体的にローがマジで太い。なんだこれ。パッドの連打もヤバく、もう否応なしにアガってしまう。不穏な空気感を維持しつつも疾走感のある曲展開もあまりに好みすぎる。全曲必聴なレベルでかっこいいんだけど、その中でも白眉はPhilip Glassを流用したM11 "The Precisiooon of Infinity"かな。ピアノ流麗な旋律とポリリズミックなパーカッションが新感覚。凄いアルバムですよ。
来年の目標は少しでもライブに行くことです。
良いお年を。
