
言語学版 ガリレオ ch.4
第4章 分けたがる言葉
タイトルだけを見ると言語とは関係ない本のように思えるだろう。

ゴリラ研究の第一人者で京大総長の山極さんと『バカの壁』でおなじみの解剖学者の養老さんの対談である。
この本には言語を考える上で有益な洞察が多い。
とくに、二人とも「本来は違うものを同じカテゴリーに入れる」というのが言葉の特徴であることを指摘している。
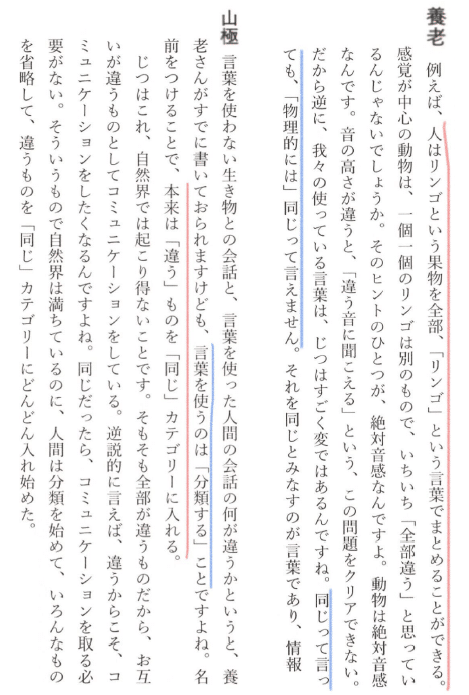
たしかに、「イヌ」といってもいろんな犬がいる。

改めてじっくり見てみると、ブルドッグとハスキーなんかは「同じ」犬とは思えないほど違っている。
「何をもって「イヌ」とみなしているのか」というのは「実に興味深い」。
さらに言葉には「逆」の側面もある。
つまり、言葉は「同じものを違うカテゴリーに入れる」ものでもある。
たとえば、英語のproblem, matter, issueは日本語では「問題」という1つの単語でまとめられる。
(『ビミョウな違いがイラストでわかる!英単語類義語事典』 佐藤誠司 著より)

このように、「同じもの(「問題」)」であっても言葉をつけることによって「違うもの(problem, matter, issue)」として分類される。
言葉は分けたがるのである。
そして、どのように分けるかは言語によって異なる。
まさに言葉は「気まぐれ」なのである。
これをソシュールは「言葉の恣意性」とよんでいる。
(『哲学用語図鑑』 田中正人 著より)

英語では「野ウサギ」はhare、「ペットとして飼っているウサギ」はrabbitとして区別するが、日本語ではどちらも「同じ」ウサギである。
つまり、どのように分けてもいい。そこには理由はない。
『実に非論理的だ』
ことばは論理だけで説明できるものではないのだろう。
しかし、解剖学と言語は「分類する」という点でつながっているというのは「実に面白い」視点である。

To be continued.
