
えっ!!コミュニケーションでカードを1から順に100まで揃えろ!?日本人に知っておいて欲しい知識をゲームにしてみた(笑) ~参考ゲーム「ザ・マインド」~
皆さん、こんにちは!
まったり投稿のゆうきです。(目次の部分は★の所がタイトルになります)
皆さんは「ゲーミフィケーション」って言葉をご存知でしょうか?
今回の記事ではゲーミフィケーションという言葉の意味を理解してから読み進めていくと分かりやすいと思いますので、まずは簡単に説明させていただこうと思います。
★ゲーミフィケーションとは?
ゲーミフィケーションとはゲームデザイン要素やゲームの原則をゲーム以外の物事に応用することを言います。
これでは「なんのこっちゃ?」になるので、具体例を挙げると
・進研ゼミ「歴史人物つながりバトル42」(ゲーム×教育)
・くら寿司「ガチャポン」(ゲーム×ガチャ)
・パソコンゲーム「ChoreWars」(ゲーム×雑務)
・オンライン講座「Khan Academy」(ゲーム×講座)
etc...
上記の共通点は「ゲームの要素×○○」というところです。つまり、ゲーミフィケーションとはゲームの要素を抽出して、それらを何かに掛け合わせるということです。
ゲームの要素の定義はゲーミフィケーション デザイナー Lv98 岸本好弘氏によると「能動的参加・称賛演出・即時フィードバック・自己表現・成長の可視化・達成可能な目標設定」の6つの要素に分けることができ、これが組み込まれていればゲーミフィケーションとして確立することができると述べています。また、ゲーミフィケーションは顧客サービスの一環として取り入れている会社もあり、新しい技術や能力をゲームを通して楽しく習得させる目的があるそうです。
まぁ、、、、なんやかんやで意外に身近なものがゲーミフィケーションと呼ばれるものはあるそうですよ~~~(笑)
★今回考えたゲーミフィケーション概要
ゲーミフィケーションの意味が分かったところで、今回考えたゲーミフィケーションの概要について説明させていただきます。
まず私たちが掛け合わせるのは「ゲーム×教育」です。そして、最終的な学びのゴールが
SDGs3「すべての人に健康と福祉を」
SDGs4「質の高い教育をみんなに」
です!!


「えっ!?SDGsって何?」と思った方は下記の外務省のHPを参照してください。
すべての人に福祉と健康を、、、それは後に登場するとして、、、
質の高い教育、、、それは全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果をもたらすことを意味します。
これを聞くと日本と海外の教育状況を比べがちになりますが、今回は日本人の教育について少し触れたいと思います。
現在日本の教育カリキュラムは授業数はほとんど変わらないのにも関わらず、プログラミングの必修化や各科目における様々な改善項目が設定されています。
これでは先生の負担が大きく、今後社会や日常生活で必要となる知識が小・中・高で教えられない可能性が高くなります。
しかし、、、ここで疑問に思うことはありませんか???

「今後必要とされる知識って沢山ありすぎて、何を学べばいいの?」
う~~む、、、それを言われるとやばいなぁ💦💦
というわけであまり知られていないような問題と知識を焦点にて・き・と・う・に検索してみました(笑)
そうしたら厚生労働省が提唱する生活習慣病予防のHPにあたりました。それを読むと、生活習慣病は健康に生きるための最大の邪魔な要因となっていて、国民の医療費にもかなり負担をかけているそうです。
「へぇー、、、」と思いながら、HPを見てみると6項目の対策方法がありました。それが「運動施策の推進」「栄養・食育対策」「たばこ対策」「アルコール対策」「睡眠対策」「女性の健康づくり」です。
リンクを読み進めていくと「難しいこと書いてあるなぁ~~」と思いました。これではほとんどの方が読まない、、、というか厚生労働省のHPさえレポートや論文で書く際の参考文献以外には使わないと思います。(私はレポートや論文を書く際偶に参考にします)
「もうちょっと分かりやすくすれば皆興味を持つのに」
そこで私はSDGs3「すべての人に福祉と健康を」が達成できないか考えました。
考えた結果、私は・・・・

「ゲーミフィケーション使えばいいんじゃね?」
とそんな安易な結論に至りました(笑)
でも、、、これが案外嵌ったらしく自分でも驚くほど調査をすることができました。友達にも協力してもらって情報提供してもらい、自分達でも「へぇ~~そうだったんだぁ~~」と全く知り得なかった情報を知ることができたので、色々と学びを得ることができました。
そして、、、いざゲーム制作!!と思った時に、、、
「あれ💦💦何のゲーム作れば良いんだ???」となりました(笑)

ずご~~~~~!!!
「何も考えていないんかい!!」と思わず突っ込みました、、、
ゲーミフィケーション教材は基本お金をかけない場合だとボードゲームにする場合が多いので、私はボードゲームにした方が良いと考えたのですが、いかんせん人生ゲーム程度しかやったことがない始末、、、
そこで、、、とにかくボードゲームで遊ぶことにしました!!!(それはもう沢山、、、むしろそれがメインとなるくらいまで遊びました(笑))
そして、、、私が友達とやって面白く感じてかつゲーミフィケーション教材になりやすいゲームを発見することができました。
それが、、、「ザ・マインド」です!!
★ザ・マインドとは?
ザ・マインドとはドイツのボードゲームで「ドイツ年間ゲーム大賞2018のノミネート作品」となっているほどの作品です。

※遊びゴコロさんの画像を引用させていただきました
ゲームのルールはシンプルで1~100まである数字の中から各自山札から1枚ずつ引き、それらを出し切ることを目指す協力型のゲームです。
「はじめしゃちょーの畑」や「ガキ使いやあらへんで」といった大物のYouTuberやTVで紹介されるほどですので、そちらを見ながらルールを覚えた方が良いでしょう。
★作ったゲーム「THE・ヘルス」

試作品「THE・ヘルス」
それでは本題に戻りまして、、、これをどのようにしてゲーミフィケーションに利用するのか?
それは、、、ずばり!!
「栄養・食育対策」「たばこ対策」「アルコール対策」「睡眠対策」「女性の健康づくり」に関する数字を1~100まで調べ、それをカード化する
です。
再度になりますが、私たちの目的は生活習慣病の実態を知ってもらい、その対策方法は何かを知るといった人々に興味・関心をもたらせることが最終的なゴールとなっています。
つまり、厚生労働省が提唱する生活習慣病の予防対策をザ・マインドの数字に書き換えることによって絶妙なコミュニケーションを発生させるのです。また、ザ・マインドのルールと同様、、、
ヒントとなる情報を喋ってはいけない
となっております。これによって、例えば参加者4人に以下のカードを配り、ヒント一覧表というA3の紙を見ながら進めてもらいます。
「カードの内容:対応する数字」※○が対応する数字となっている。
1枚目「1日あたりの食塩の摂取量(男)○g:8」
2枚目「1日の水分摂取量○ℓ:2」
3枚目「1日カルシウムの摂取量○0g:70」
4枚目「糖尿病患者の2014年~2019年までの増加人数○万人:12」
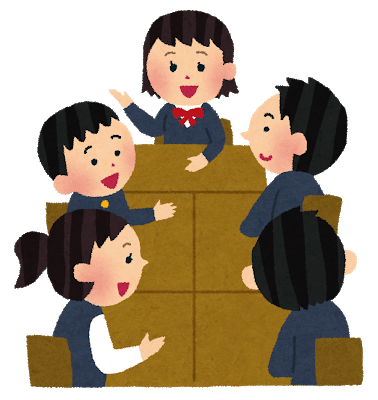
※( )は心の中の声
ヒント一覧表に置かれた駒を見て、それぞれがどんなカードを持っているかを把握。
女1「(私が持っているカードは"1日あたりの食塩の摂取量(男)の数字")」
男1「(僕が持っているカードは"1日の水分摂取量の数字")」
女2「(私が持っているカードは"カルシウムの摂取量の上2ケタの数字")」
男2「(僕が持っているカードは"糖尿病患者の2014年からの増加人数(万単位)"だ!)」
女1「(女2のカルシウムの摂取量の上2ケタの数字って何かしら?)」
男1「(多分僕の数字が1番低いと思うんだけど、、、)」
女2「(おそらく私のカードはこの中でもかなり大きいと思うわ)」
女1「(私の食塩の摂取量は、、、中々数字が低いと思うわ」
男2「(12かぁ~~、多分男1がもっているカードが一番低いと思うんだけどなぁ~~)」
全員「う~~む」
こんな感じで心の中で自分なりの結論を出し、参加者の中で一番低い数字を持っていると感じたら出します。相手の表情や動きから心理を読み取る力と生活習慣病に関する知識量の2つが必要となってきます。
これを繰り返すことによってヒント情報と数字を関連して覚えることができるので、ゲームを楽しみながら学習効果の向上が期待されます。

「俺、、、結構天才じゃね?」と調子に乗ってしまいますね(笑)
こんなの誰でも思いつくことだ。思い上がるな!!、、、そんなことを言われてしまいそうです(笑)
というわけで、最後まで付き合ってくださった皆様に面白そうだと思ったら、是非この記事に「いいね👍」をしてください。
もっと改善した方が良いと思う方は「いいね👍」をした後、Twitterやブログのコメント欄にてメッセージを送ってくださると幸いです。
★作ったゲームのデータ
(カードデータ、ゲームの流れ、説明書)
ゲームのカードデータを下記に載せておきますので、遊びたい人がいましたら、ダウンロードして紙に印刷してみてください。
カードゲームのデータ
ゲームの流れ
説明書
