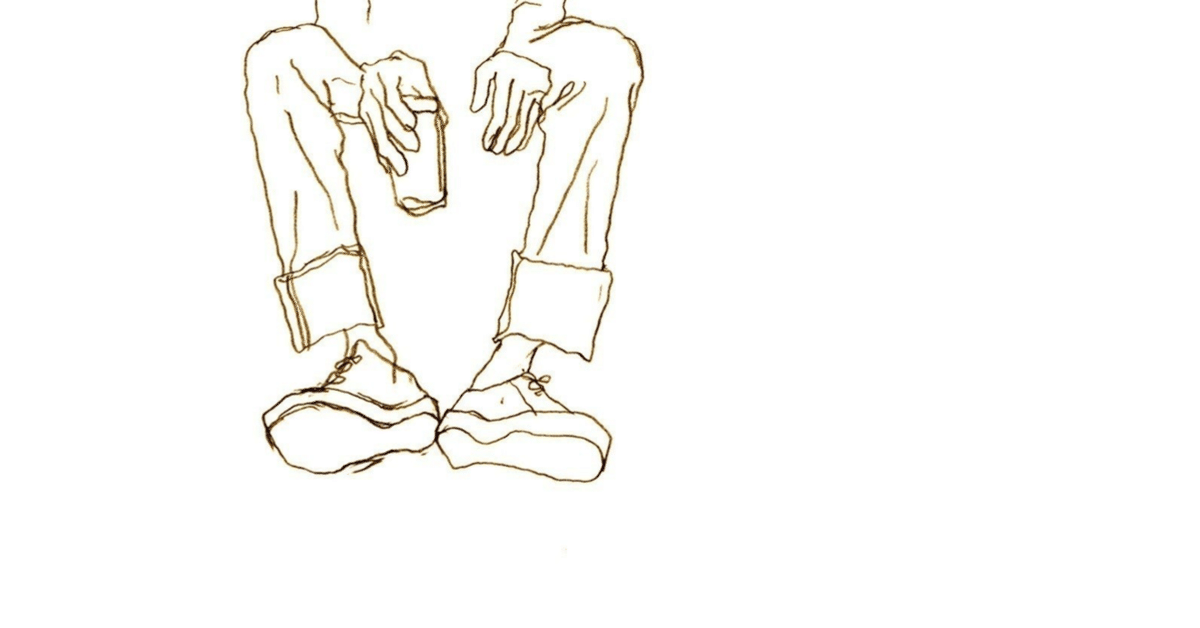
Photo by
m_oonote
公園と缶コーヒーと
ここに来ることは5分前に決まった。
せっかく夏が来そうだっていうのに
君がレジ袋から取り出したのは
温かい方の缶コーヒー。しかも微糖。
そういうとこだ、そういうところが
前からズレている。
「私微糖は苦手って言ったじゃん。
覚えてないの?」
「…そうだっけ?ごめん微糖しか買ってない。」
「いいよ、飲む。」
全く微ではないこの甘ったるさと熱さと、
髪の先まで纏わりつくようなぬるい風。
今から始まる話題を予感させるような
気怠い感触だった。
しばらく口を開いたのは私だった。
「で、どうしよっか。」
何も答えが無い。
数週間前のことだった。
この人が突然留学したいと言い出したのは。
2年も会えないことをいきなり告げられた。
私からは待っているとは言えない。
グレーに染まっている二人の未来を
ハッキリとさせて
相手や自分を縛ることも、
突然失うこともできない。
きっとこの人も同じだ。
同じことを考えている。
「頑張ってくる。今はそれだけ、考えたい。」
しばらくしてから返事が返ってきた。
「そっか、わかった。頑張ってきなよ。」
口が勝手に動く。
「ありがとね。…じゃあ。」
そうして空になった缶コーヒーがひとつ、
ベンチに置いてけぼりになった。
私の手の中にいるもうひとつの缶コーヒーは、
もうすっかりぬるくなっていた。
甘ったるさがいつまでも喉にこびりついている。
あの人の、決定的なことは言わない甘さも、
手繰り寄せてはくれない甘さも、
私の、本音を言えない甘さも、
恰好つけて大人ぶってしまう甘さも、
微かなフリをしてきっといつまでもこびりつく。
「あーーなんか、後味悪いなあ。」
ため息ともに足元の石を蹴飛ばしてみたら、
カン、と空虚な音を立てて鉄棒に当たった。
こういうときに限って、乾いた風が吹く。
去年よりも隙間だらけの夏が近づいていた。
