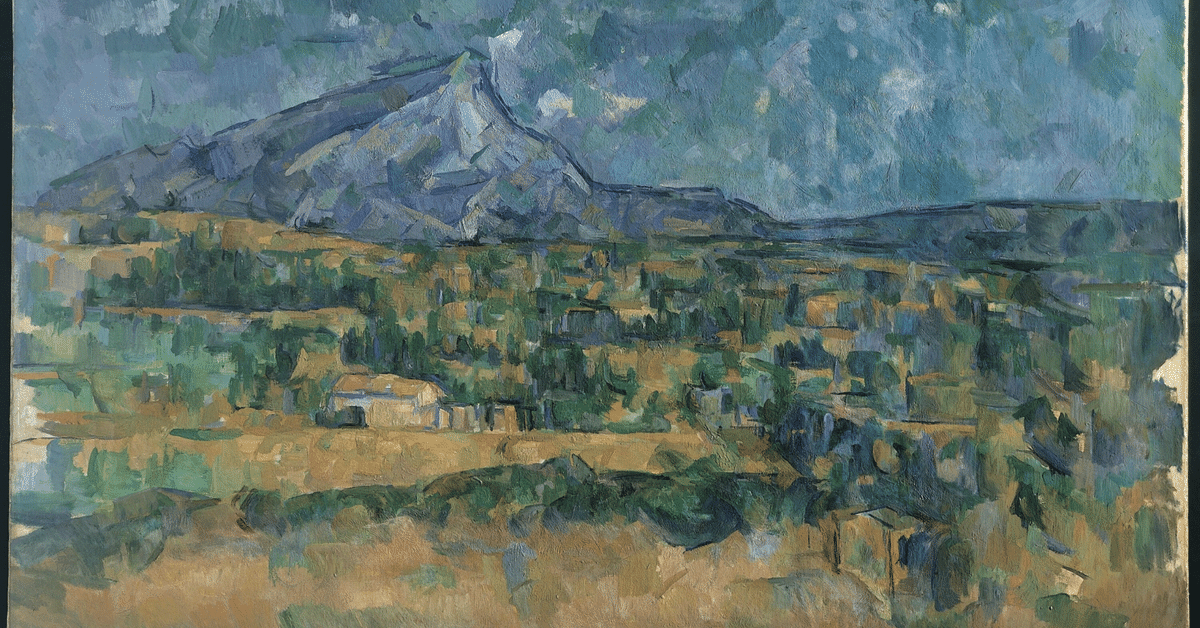
(小説)星の降る街 6
私は嫌な夢の虜になっているためか、目に入る風景も音も匂いも何も興味は持てなくなっている。カフェオーレとクロワッサンを手に持ち、かろうじて庇で守られた外の席に座った。雨合羽を着たアジア人がひとり外の席でコーヒーを飲んでいる様はさぞ奇異に見えているに違いない。店内から出てきて帰路に就く何人かに声を掛けられた。「雨に打たれなくても店内の席が空いているよ」と言われたのだろう。
「仕事終わったばかりだろうけど、すまん。ホテルに入ってすぐに寝たら嫌な夢をみた」
私は日本時間の午後七時を待って阿部に電話した。
「いや構わん、俺も電話しようと思っていたところだ」
仕事は順調に終わったのか、しっかりとした声で返って来た。
「何か手掛かりがあったのか」
私は思わず大きな声になった。
「マッサはもう有里がどこかで生きている、とか思ってないよな」
テレビのニュースで何度も津波直後の中継や、その後毎日のように流されていた日和山からの映像を観ている。生存しているとはすでに考えてはいない。私が行った直後の惨状は絶望的だった。四月下旬ですら市内は崩壊したままだった。
「ああ、記憶喪失になっていてもいいからどこかで生きていて欲しいと期待はしている」
行方不明者を出した家族や知人はみんなそう思っているに違いない。
「実は昨日の夕方な、渡波の沖合で有里の車が見つかった。ボランティアのダイバーが車の中にあったハンドバッグを引き上げてくれたよ。免許証の入った財布はあったけど携帯電話はなかったということだ。無論、有里の姿は車中にも、車から二十メートル四方も捜索したそうだが見つからない、窓が空いていたので遠くに流されたか、自分で出て、車から離れたところまで行ったのではないかというのが警察の判断だよ。今日は早退して今家だよ、これから行ってみる」
いつも明るい阿部も、くぐもった声だ。
「そうか」
私は声をまともには出せなかった。それだけを絞り出すように言った。あの日の翌日、石巻のはるか東海まで雪は降りしきっていた。テレビ画面はそう映し出した。黒ずんだ海に雪が溶け込んでいた。か細い有里の体をどこまで運んだのだろうか。
「お前が巡礼に出たから見つかったんだ。そう考えよう。体は大丈夫か、ゆっくりでいいから力強く歩けよ。薬はちゃんと飲めよ」
「ああ」
私は何も言葉は出なかった。
「携帯電話は見つかっていない。もしかしたら、有里は携帯だけを握りしめて窓から脱出して、それから流されたとも考えられるな。これまで携帯を握りしめた御遺体が何人もいたそうだ。警察の人がそう言っていたらしい」
「そうか」
行方不明のままがよかったのか、こうして車だけでも見つかって心底から弔らえられるのか。これから先の心境を想像したが何も浮かばなかった。
「カンちゃんにも電話しておいたよ。お前を心配して、仲のいい同僚がパリ支社にいるらしく泊っているホテルに行かせるって言っていたから後で電話があるだろう」
「そうか」
私は力なく返事をした。
「しっかりしないかマッサ。生返事ばっかりするな。そんなことでは癌が大きくなるよ。有里も喜ばない。何をやってんだパリまで行っているのに。強い気持ちを持てよ」
めったに怒らない阿部が怒鳴った。電話の傍に奥さんがいるのか、「あなた雅春さんも辛いのよ」と言ってたしなめられているのが聞き取れた。
「大丈夫、有里の夢を見て、あまりにもタイミングが合っているから驚いただけだ。ところで、携帯の最後の発信が消防か警察ならいいな」
「どういうことだ」
阿部は優しげな声に変わった。
「だから有里の携帯電話のことだよ。助けを求めるのが精いっぱいなら苦しんでいる時間は少ない。もし、最後の発信が俺やみんなだったら死ぬまでに時間的な余裕があると思う。それでは可哀相すぎる」
私は声をまともに出せなくなっていた。
「思いはみんな同じだ。有里はいろいろあったけど、最後はっていうか、最近はずっと好きだったおまえと付き合って将来の夢を見た。いいじゃないか、それでいいじゃないか」
阿部は電話の向こうで咽んだ。
「遺体が上がったらどんな時間でも連絡してくれよ。頼むな」
私はそれだけを言って切ろうとすると、
「マッサ、今さらだけど本当に七百キロ以上も悪路を歩けるのか、途中でバスやタクシーに乗ったりしても誰も責めないぞ、無理だけはするなよ。日本じゃずるしても分からないしな」
急に笑い声で言われた。
「おたづなよ、このう」
勢一杯の声で返した。
「おお、その調子だ。石巻弁が出れば大丈夫だ。なめてないぞマッサ、がんばっぺ」
私は電話を切った後、目頭を拭った。
しばらくすると菅野からも電話が入った。今度は落ち着いて話した。
「マッサ、俺はな、有里が行きたがっていた巡礼路をマッサに歩き切って欲しいだけだ。こっちのことは心配するな、アベッツとちゃんとやっておく。とにかく体だけは無理をさせるな。それに胸に何か異変があったら困るだろう。信頼のおける同期の笹井君を向かわせたので、打ち合わせをしてから出発してくれ」
私はひとりで落ち込んでいるのが恥ずかしくなった。みんなを心配させている。
翌朝、勤務時間中にも関わらず笹井がホテルを訪ねてくれた。
「菅野君に頼まれていた資料です。巡礼路で病気になった時に対応してくれる病院をリストアップしておきました。大きな町ばかりです。大抵は英語も通じます。専門用語など多いでしょうから、もしお困りになったら電話してください。生意気なようですが、電話で通訳します」
生真面目そうな人だった。
「ありがとうございます。菅野君から聞いていますが、笹井さんはクリスチャンだそうですね。サンティアゴ巡礼は行かれましたか」
「ええ、でも全行程の半分にも満たないブルゴスまでです。パリ支社に赴任している間に全行程を歩き切りたいんですけどね。パンフレットなども一式揃えておきましたが、出発が明日なら今夜は食事でもしませんか。巡礼路のアドバイスの一つでも出来るかもしれません」
「それは助かります。予備知識もあまりなくて心細い限りなんです」
笹井は午後七時に迎えに来ると言って、市内中心部のコンコルド広場近くにあるという会社に向かった。時差調整だけのためにパリで二日間の余裕を見ていたのでとくに何もやることはなかった。差し出すことなく、石巻の有里の部屋にあった私宛の十二通の手紙を読むつもりでいたが、ホテルで読むと確実に阿部との電話の時のように取り乱すと思い外に出た。
雨は明け方まで降ったのか路面は濡れていた。晴れ間が覗き気温は二十度近くまで上がったのだろうか、薄手のジャンパーで快適だった。
駅の北側に行くとオフィスビルが立ち並ぶ地域と住宅街が綺麗に分かれている。
住宅街は、いかにも昔からの人しか住んでいないという古めかしい町並みは静かで心地よかった。ひとブロック歩いたところに崩れかけたレンガ作りの建物が中世の風情を醸し出している。上の階はすべて住宅のようだ。一階に小さなカフェがあった。外の席は三席しかなかったが、客は誰もいない。
珈琲を注文して、有里からの一通目の封を切った。
マッサへ
━━やっぱり癌だったよ、有里。
何年ぶりでしょうか、小、中学生の時は呼び捨てだったのに、大学生になって再会した時から有里さんとしか呼ばないマッサが、私を呼び捨てにしました。子供時代以来の呼び方でした。あの長い電話の中で一度きりだったので、マッサの狼狽ぶりが伝わってきて涙が止まりません。癌におびえる姿が伝わってきます。
お医者さんの言うとおり手術を受けて欲しいし、あらゆる治療をしてもらいたい。けれどもしないというマッサの思いもよく分かります。でもね、私はエゴイストと言われても許さないし、許したくないの。そう思うのは私だけじゃないと思うのです。きっと息子さんたちやお兄様も同じだと思います。こんな周囲の人の気持ちも分かって下さい。
それに、二十四歳のあの日のように、また一人にするの?
私はこれから説得に何度でも東京に向かいます。
この間、私の部屋で過ごした五日間は生涯で最も穏やかで温かく、幸せを噛みしめられました。もう後戻りはしたくないの。
今日は二月二十六日です。マッサから電話があって、すぐに書き始めています。これから石巻にいる日は手紙を書きます。そして、マッサが手術をする決心をした日に渡したいと思います。
白石島はあまりにもたおやかで楽しい時間でした。ご家族との会話、小さな出来事は過去の私を洗い流すのに十分でした。こんなに癒されていいのでしょうか、こんなに至福の時間の中にいて私は幸せすぎないかしら、何度も自問自答しました。
検査結果が悪かったせいか、マッサは私とのお付き合いを遠慮しようとしているのは伝わってきます。でも、癌になると確実に死ぬのでしょうか。癌ならば愛し合ってはいけないのでしょうか。仮にマッサが末期になったとしても私は傍に最期までいます。大丈夫です、安心してください。
私は何を書いているんでしょう。まるでマッサが死んでしまうようなことを、ごめんなさい。でも明日からも正直に気持ちを書いていきます。
好きだよマッサ
有里
苦いブラック珈琲を飲みながら、甘酸っぱい気持ちになった。
出発間際までやっていた仕事を思い出した。七十歳の婦人が書いた「亡きあなたへ」というラブレターのような自伝だった。十歳年上の御主人は若い頃から女遊びが激しく随分辛い思いをしたようだ。寝たきり状態になって五年目に「こんな俺を見捨ててくれ」と言われたが、その時に「この五年間が一番幸せだ」と伝えたと締めくくっていた。
「この五年間のあなたは私以外の女性を知らない。だから本当に幸せ」
そんな内容で、なんという話だと思ったが、案外本心だったのかもしれない。有里もその御婦人に似ているのではないか、男としてはなかなか理解しがたいが、少し分かった気がした。
セーヌ川の中州にあるシテ島はかつてのパリの中心部で、貴族の館が立ち並んでいたところだという。今も中世の名残を留めるパリの観光中核地区の一つだ。有里が行きたがっていたノートルダム寺院もこの地区にある。ほど近いところの重厚な建物の中のレストランに笹井は案内してくれた。
「ここはゾラやベーコン、ピカソやマルローなど錚々たる近代の偉人達がよく食べて語った店らしいですよ。実は仕事でこの店をよく使うんですよ。魚介類のスープはお勧めです」
笹井さんは得意げに解説をしながら次々に注文をしてくれた。私はそんなことに興味はなく、私にとっては曖昧模糊とした巡礼という行為の話を聞きたかった。キリスト教、カソリック信者の神聖な行事に門外漢でしかも外国人がどういう心持ちで挑むべきなのか気になっていた。観光地を巡るわけではない。
受け売りですよ、と前置きして笹井は語り始めた。
「巡礼に肉体的な不安は持つ必要はないんですよね。サンティアゴに通じる道が運んでくれるし、漂う空気が体を起してくれる。一人でも大勢でも宇宙の中では塵のひとかけら。その宇宙は神が司り、私たちは抱かれている。その中で生きている、その体験が巡礼の間に違う形で再現されるっていうんですね。それで歩いている間に罪は赦される。帰りは神の祝福を受けて心にも体にも新たな力が宿る、と社会人になった頃に通っていた東京の教会でフランス人の神父さんに教えられましたね。もう三十年も経っているのに私は、まだ贖宥状はもらっていません。いい加減な信者です」
記憶の底を探るように笹井はゆっくりと話す。この手の話は普段なら興味もないし、誰かが話していたらその場から逃げるだろう。いろいろな宗教に巡礼はあり、一生に一度は、とよく言う。イスラム教のメッカ巡礼もそうだ。日本人にも身近な四国巡礼はもちろんのこと、秩父の巡礼もある。お伊勢参りも似たところはある。巡礼とは呼ばないが、高野山に上る道も似た教えだ。
九度山の慈尊院から大門に上る九度山町石道がある。起点になっている根本大塔から慈尊院まで一町(百九メートル)ごとに鎌倉時代に作られたという石作りの五輪塔婆形が百八十ヵ所置かれ、その都度手を合わせるのが作法だった。さらに奥の院まで三十七ヵ所ある。この世界を表しているという。
