
【10万字一挙版/「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」を解く最低限の魔法のスペル/「感動した、泣いた」で終わらせないために/本当はエロくて怖い『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』/あるいは隠れたる神と奇蹟の映画/検索ワード:批評と考察】
こんにちは。京アニのほとりのひと、ユルグです。
「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」
本稿はこの一見へんてこな〈謎〉にひとつの答えを提示するための少しばかり長めの読み物です。
その結末までには題名にあるように、以下の四章をたどっていただくこととなります。
「第Ⅰ章.エロス篇」ではヴァイオレットとギルベルトそれぞれのエロスを探究していきます。「そのエロスってエロいの?」という疑問はひとそれぞれだろうと思います。
次の「第Ⅱ章.残酷篇」では『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』に潜む意外な「残酷さ」をえぐり出してみます。「えっ、そんなお話でしたっけ?」との声が聞こえてくるのは百も承知なのですが、広い心でお付き合いいただければ楽しめるはずです。
さて、結論の手前は「第Ⅲ章.奇蹟篇」として「この映画が描いた奇蹟とは何か?そしてこの映画自体が奇蹟であるとはどういうことか?」を前のふたつの章をまとめるかたちで物語っていきます。
そして終章では「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」に再び出逢って答えを出します。肯定的にせよ否定的にせよ「なん…だと…!?」となることは保証します。
果たしてこのレヴューでも解説でもいわゆる考察でもない、いささか奇妙な読み物にどういった価値があるのかはわかりません。
筆者が云えることは『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』から受けた圧倒的な衝撃をそのまま衝動として打ち返したらこうなったということです。
ただひとつ言えることは、これはヴァイオレットへの愛が書かせたものであるということに間違いはありません。(ここ重要です)
ということでジャンルとしては批評ということになりますしそのつもりで書きました。決して適当な自分本位な暗号文を書きなぐったわけではなく徹底的に他者が読むことを心がけました。当初予定していたよりも遥かに分量的にも執筆にも推敲にも長くかかってしまいましたがその間は楽しい時間でした。
おそらくこの文章を最後まで読み通す方は存在しないだろうと思いますが――目次だけでも見ていってやってください――もしそんな方がいらっしゃいましたらTwitterなりここなりに何でもいいので意見をいただければ感謝に堪えません。もちろん途中までの感想も大歓迎です。
ではこの手紙の封を切るかもしれない方へ。
以降があなたへのメッセージです。
・本文はすべて「です・ます調」ではなく「だ・である調」を用いる。
・本稿は『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』及び『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 永遠と自動手記人形 』並びに同TVアニメシリーズを鑑賞視聴済みであることを前提としているため、あらすじやストーリーをなぞることは省いている。
・セリフとカットの指定は『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデンSTORYBOARD』から、画像は『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 永遠と自動手記人形 』Blu-ray及び『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HP、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterから、ともに著作権法第32条1項に則り引用させていただいた。また入場者特典の画像はすべて筆者所有のものである。
・その他引用・参考文献の書影はAmazon及びhontoから、その他画像、語句のリンクは利便性を考えWikipediaを主に用いた。
・本稿では重要な意味合いを持つ花々に触れる場合でも花言葉には一切言及しない。
▼第Ⅰ章.エロス篇
『劇場場ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は”違和感”に満ちた作品だ。
違和感の豊穣さこそこの作品の最大の魅力であるといってもいい。
本論の読者はこれから何度もこういったそれ自体に違和感を覚える”断言”や”憶断”に出逢うことだろう。煙に巻くような言い回しは避け率直に文意を補足していこう。
「どういう違和感か?」はひとそれぞれであろうし、まったくないというひともいることだろうが、それを列挙するのではなくひとつに集約して提示しよう。
それは「ヴァイオレットがこれまでの彼女と違って見える……」というものである。
その原因は本作ではじめて代筆者としてではない手紙の書き手となったというだけではなく、彼女がどこまでもギルベルトという特異点に収斂していくという視野狭窄な展開にある。
そしてそれが本作で描いたものであっていいのである。
それを本論は「ヴァイオレットが醸すエロティシズム/ヴァイオレットの意志するエロス」に起因するものであることからはじめる。
ヴァイオレットのギルベルトへの抑えられないエロスの結末――。
それこそが本作の”違和感”の正体である。これをベースに本作を紐解いていこう。きっと密かな”違和感”など吹き飛ばしてしまう彼女に出くわすことになるはずだ。
◆
完結編である本作において、筆者が目にしたヴァイオレットという女性の最後の姿は、一般的に評される「メロドラマ的な予定調和的展開を圧倒的なアニメーション技術によって力技でねじ伏せた」というだけではなかった。
それとは別のもう一つの主旋律、あるいは副旋律にこそがこの作品が作り上げてきた圧倒され息を呑むような真の凄みであることを伝えたいと思う。
まずは、本稿「第Ⅲ章.奇蹟篇」にたどり着くための条件の一つとして「ヴァイオレットとギルベルトのエロスとは何か?」からはじめよう。
ここでいうエロスの定義であるが
・一般的な形骸化した性的欲望
・ギリシア神話の愛の神が象徴するもの
・フロイトのタナトス(死の欲動)に対してのエロス(生の欲動)
のいずれも含んでいるが、なにより
・あまりに美しいプラトンの『饗宴』のエロスで描かれたある対象へ恋い焦がれる熱情がもっともふさわしい。
結論としては
1.ヴァイオレットのエロスは無垢(イノセント)である
2.ギルベルトのエロスは背徳である
となる。
それではまずヴァイオレットから見ていこう。
第1節.ヴァイオレットのエロス
まず『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』という作品、そして主人公であるヴァイオレット及びギルベルトの関係を、『源氏物語』の五十四帖の巻名のひとつである第5帖『若紫』を想起しないでいることはできない。
西洋での書簡をとおしての恋愛といえば、まず書簡体小説のモデルともなった『アベラールとエロイーズ』が連想される。こちらの宗教的モチーフは本作に大いに通底している。
しかしそれ以上に、光源氏が若紫(のちの紫の上)を見初めた年齢が満11~12歳であることからも、いわゆる光源氏計画をダイレクトに踏まえていることは明らかだ。
若紫の英訳は〈Young Violet〉である。
・第ⅰ項.燃え立つ情欲の赤とイノセントの白
ヴァイオレットのうちに燃え上がっている火を戦時下での殺傷行為への罪責の隠喩ではなく(それはテレビアニメ版において一応の解決が済んでいる)ギルベルトへの慕情としてとらえる。
それこそがヴァイオレットが唯一囚われ燻り続けている熾火だからだ。
ギルベルトの生存の可能性を知らされ、ヴァイオレットは豹変する。一気に火がつき、抑えきれないほどに燃え上がる。
次の「2.ギルベルトのエロス」で述べるギルベルトの熾火とはあまりに対照的だ。
ここでのヴァイオレットの衝動は慕情という静かで穏やかな言葉を超え出る。
ギルベルトへの愛の執着の強さは、焦燥、抑えがたい衝動、駆り立てる激情であり、さらには、渇望、突き動かす情念、そして、貪婪、情欲だろう。
ずっと溜め込まれ堰を切ったように溢れ出るそれは、無軌道ながら決して淫奔ではない。赤色の炎の熱度が高まれば白色となるように真っ白な無垢だ。

(『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』 第4弾 入場者特典 クリアファイル 筆者所有品を撮影)
イノセントなエロス。
それがヴァイオレットだ。
(石立太一監督は舞台挨拶で「京都アニメーション内ではヴァイオレットのことを“真っ白な人”と呼んでいる」と発言。井中カエル氏による評を参照)
・第ⅱ項.〈水〉に濡れるヴァイオレットの裸身
『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』全作をとおして、ヴァイオレットのエロティシズムが直接的に表現される場面はほとんどない。
例外的にエロティックなシーンは、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 - 永遠と自動手記人形 -』でイザベラ・ヨークとともに入浴するヴァイオレットの裸身だろう。(以下画像を参照)
〈雫〉の滴る嬌態


(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 永遠と自動手記人形 』Blu-rayより)
ヴァイオレットが起草した「海への讃歌」も〈水〉とエロスの視点で見ると示唆的である。
"恵みの海よ
全て世界に繋がる海よ
カモメは舞う あなたの空を
魚は泳ぐ あなたの中を
貝は潜む あなたの底に
あなたは光を与う
あなたは命を育む
あなたは愛を注ぐ
あなたに寄り添い続ける 果てるまで
今も過去も未来も包み
たゆたうあなたに身をゆだねて”
『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデSTORYBOARD』(京都アニメーション、2020年)、pp.89-90
官能性は本作の劇場版で〈水〉の多用によって象徴的に表現される。
ではなぜ〈水〉なのだろうか?
次項においても詳しく見るが、いうまでもなくヴァイオレットは〈花〉である。
〈花〉を咲かせるために必要なものとして真っ先思い浮かべるものは〈水〉と太陽光であろう。
浴槽に浸されランプの灯りに照らされるヴァイオレットという花――。
そしてエロスの側面から〈花〉を見るならば、なによりそれを〈鑑賞する人〉そしてその〈芳香と蜜〉に魅了されるものがいなければならない――。
ここでの〈水〉以外の〈光〉と〈魅了されるもの〉たちは本論の端々に現れることになるはずである。
なお、海辺でのクライマックスのエロス的意味については「Ⅲ.奇蹟篇」で語る。
※イザベラとの入浴はエロスとは別に「Ⅱ.残酷篇」でも重要な意味を持つ。
・第ⅲ項.〈花びら〉とヴァイオレットの〈衣装の襞〉
『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は花々で彩られている。
ヴァイオレットをはじめとした登場人物の名前だけでなく舞台の隅々にもいつも咲きこぼれている。
しかし花開く前の蕾が印象的に登場することはない。
蕾はヴァイオレット自身だからだ。
彼女の極度に肌を隠した衣装が閉じられた花弁だ。
ヴィクトリア朝期の性的禁欲を示すようにピシッと倦むことのない普段のヴァイオレットの腰より下、その背面――。
そこでは蕾がほころんでいる。
白いスカートのプリーツのヒラヒラとした褶曲が実に蠱惑的だ。
(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)
白から覗く色彩。
“身体の中で最もエロティックなのは、
衣服が口を開けている所ではなかろうか。"
”……エロティックなのは間歇である。
二つの衣服(パンタロンとセーター)、
二つの縁(半ば開いた肌着、手袋と袖)の間に
ちらちら見える肌の間歇。”
”誘惑的なのはこのちらちら見えることそれ自体である。
更にいいかえれば、出現―消滅の演出である。”
(強調は筆者による)
ロラン・バルト、 沢崎 浩平訳『テクストの快楽』(みすず書房、1977年、原著1973年)、p.18
ヴァイオレットの世界に密生した爛熟した花々に対して、秘された蕾とそのほころび。(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 永遠と自動手記人形 』Blu-rayより)
もはや贅言を要しないだろう。花とその襞が何を象徴するものであるか。
花は誘う。蜜で誘う。
ヴァイオレットはエロティックに誘惑する。
誘われた蝶や蜂、バッタを狩るのがカマキリである。
カマキリは花粉や蝶の鱗粉で汚れたみずからを拭うという。
次のギルベルトのエロスに移ろう。
【第1節.ヴァイオレットのエロスのまとめ】
【ⅰ】白く高まったギルベルトへのイノセントな情欲。
【ⅱ】花(ヴァイオレット)を育てる〈水〉の官能性。
【ⅲ】蕾のほころびで誘惑するヴァイオレットの妖花の蠱惑。
第2節.ギルベルトのエロス
現在時のヴァイオレットは誘惑する攻めのエロスである。対してギルベルトはどうだろうか?
ギルベルトのエロスは現在だけでなく過去との対比が重要である。
・第ⅰ項.ギルベルトの貞潔・清貧・従順と背徳
「第1節.第ⅰ項.」のヴァイオレットの溢れんばかりの熱情に対してギルベルトが忍ばせている情念の火、熾火は対照的だ。
現在のギルベルトの内面の化身のようなエカルテ島。
緑の少ないむき出しの地面に岩肌。
表立ってではないが、本シリーズには作品背景として明確にキリスト教的モチーフが自然に溶け込んでいる。
劇場版においては(ヴァイオレットの自室、エンディングクレジット後の窓の木枠が十字架とし表現されているなど)、特にエカルテ島では、それがより濃密である。(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.27)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.32)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.44)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)
荒涼としたエカルテ島に隠棲するかのように暮らすギルベルトはさながら修道士のようだ。ぶどう畑などはあからさまな表徴だといえる。
修道士の三つの誓願は貞潔・清貧・従順だ。
ヴァイオレットを遠ざける貞潔。日々の暮らしの清貧。軍人として一度は背いた従順は自罰と償いの堅持である。
(※エカルテ島のモデルがギリシャのフォレガンドロス島であるとの指摘については虫圭氏の記事を参照。長めの記事のため目次から「▪️エカルテ島聖地特定及び考察」で飛んで欲しい。これも後に重要な要素となる。)
ギルベルトは島の老人の助言やホッジンズとヴァイオレットをあくまでもはねのける。
なぜそれほどまでに頑ななのか?
戦後のギルベルトの生は贖罪に捧げられている。それを脅かされたからである。それをおそれたからである。
なぜそれほどおそれるのか?
それはギルベルトのエロスが背徳的だからである。
ギルベルトのエロスはエカルテ島での暮らしのなかの贖罪と対立し、相克する。
だからこそ彼のエロスは背徳的なのである。
ストレートでイノセントなヴァイオレットのエロスと対照的なのはこの点である。
・第ⅱ項.ギルベルトの淫靡な背徳的禁忌と侵犯へのおそれ
ギルベルトはヴァイオレットを拒絶しなければならない理由となるおそれが2つある。
【①】ギルベルトは罪を償わなければならない。
その罪とはもちろんヴァイオレットを戦争の道具とした過去である。
その贖罪の失敗とはどうなることか?
ヴァイオレットを愛すことである。
【②】ギルベルトはこれからのさらなる罪を犯さないようおそれなければならない。
その罪とはヴァイオレットのエロスを「愛を受け入れること」ではない。
そうではなく能動的にヴァイオレットを愛することを許すこと、愛に溺れることだ。
それが新たな罪であり。絶対に峻拒しなければならないおこないである。
なぜか?
ギルベルトにとってそれが最高のよろこびだからである。
もしヴァイオレットを愛することが自身を傷つけ、背負わなければならない重荷、負債であったならギルベルトは迷わずその責務をになったであろう。
しかし、現実はまったくそうではなく、それはギルベルトにとって最大の幸福であるとわかっていたからこそ、もっともおそれなければならない最大の罪なのである。
ここを見逃すとギルベルトの言動にちぐはぐな評価を抱くことになる。
ギルベルトはヴァイオレットを絶対に拒絶しなければならない。
もしもギルベルトがよろこびに満ちて勇んでヴァイオレットと再会したならば、それこそ恥知らずな犬畜生にも劣る人間ということになるだろう。
この映画は、ギルベルトが生きていてはならない映画なのではなく、むしろ生きていなければならない、そして絶対にヴァイオレットを愛してはならない、愛することのできない映画なのである(※この重要な点の展開は「第Ⅲ章.奇蹟篇」で検討する)。
本来は〈花〉であるヴァイオレットを健やかに育てるための〈水〉をブクブクと煮えたぎらせるほどの強く燃え続けるどうしようもない彼女へのエロス――。
それは端的にあからさまに提示されていた。
(以下の画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.111)
この問いにどうこたえればよいだろうか?
過去において、どうしてギルベルトはヴァイオレットを自分のもとに置き、手放さず、結局のところ人殺しをさせたのか?
それはあどけない少女の美しさに、少女が無表情に血に塗れる姿に、空白の内面のままに熟れる様に魅了されたからに他ならない。
それが背徳的なものであることを知りながらそう望んだからだ。
これが過去での背徳的エロスだとすれば次は現在の堕罪のエロスだろう。
つまりさらに決定的になるのは、ギルベルトはドールとなり成長したヴァイオレットがいまや自分を愛していることをわかっていることである。
ヴァイオレットの生存がもたらした意味――。
それはよろびながらも、よろこびだからこそ、おそれなければならなかった。
ヴァイオレットに逢うことは即、破滅を意味するほど罪深いことだった。
だからこそギルベルトはヴァイオレットに逢わないのである。
それは保身だとか利己的だとかいうことではない。
この点も勘違いしてはならない。ギルベルトはヴァイオレットを不幸にすることを、失望を与えることをおそれたのではない。まったく違う。
重要な点であるのでくりかえそう。
ギルベルトは自身がどういう状態であったとしても、ヴァイオレットが自分を愛していることをわかっていた。
そうでなければ、ギルベルトはヴァイオレットに潔くすんなりと会っていたはずである。
それがヴァイオレットの自分に対する責めや決別、新たな旅立ち、巣立ちのための言葉を受ける再会であったならば――。
しかし過去でギルベルトが別れ際に残した「あいしてる」という言葉の意図のとおり(?、この点も「第Ⅲ章.奇蹟篇」で最重要項目となる)期待したようにその欲望は現実になり、渇望は最大限に高められた。
叶えられてはならなければならないほどより高まるエロス――。
そんな涜神的ともいえる淫靡な姦計だからこそ、ギルベルトの愛、エロスはどうしようもなく行き場を失うのである。
ギルベルトが修道士のように生きていることを思い出してほしい。
彼がヴァイオレットに逢わないのは、こうしたよこしまな欲望の自戒、自己抑制なのだ。
(※これまでではまだギルベルトへの不信は残るであろう。「結局すべては身から出た錆ではないか」、「過去の過ちがいまになってヴァイオレットを悲しませているではないか」と。この点も「第Ⅲ章.奇蹟篇」でより深めたい。)
禁忌の愛。迷路に迷い込んだエロス。破壊的なエロス。破滅的なエロス。背徳的なエロス――。
それがギルベルトのエロスである。ヴァイオレットへの愛である。
イノセントなヴァイオレットと対照的なギルベルトのエロス。
それこそがこの作品で描かれたものである(そしてもちろんこの先の展望こそが重要である。例によって「第Ⅲ章.奇蹟篇」を待たれよ)。
◆
ジョルジュ・バタイユのエロティシズムに関する古典ともいえる『エロティシズム』は
”エロティシズムとは、死に至るまで生を称えることである”
という名高い定義がある。これは冒頭であるが末尾ではこうである。
”まさにこの侵犯の運動においてこそ、唯一この運動においてだけ、存在の頂点はその全貌を明らかにするのである”
ジョルジュ・バタイユ、 酒井 健訳『エロティシズム』(ちくま学芸文庫、2004年、原著1957年、p.16、p.470)
ギルベルトの禁忌とその侵犯――。
それがこの論考の行く末で「あいしてる」という「存在の頂点」を明らかにしていくことになる。
【第2節.ギルベルトのエロスまとめ】
【ⅰ】ギルベルトのエロスはイノセントなヴァイオレットのエロスと対照的に背徳的である。
よってエカルテ島において修道士の如く貞潔・清貧・従順を守って抑え込まねばならない。
【ⅱ】ギルベルトは背徳的な禁忌のエロスへの侵犯と堕罪をヴァイオレットがもたらすことをおそれている。
▼第Ⅱ章.残酷篇
ここでは「第Ⅰ章.エロス篇」のエロスとともに「第Ⅲ章.奇蹟編」の奇蹟を考える上で必須の構成要素である「残酷」を見ていこう。
結論から云おう。
『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』において、「残酷」としてもたらされるのは〈ユリスの死〉である。
どういうことか?
それは〈ギルベルトの生存〉こそがユリスを死に至らしめたからである。
ユリスはギルベルトが戦火から生還し、ヴァイオレットと再会するために〈犠牲に供される〉のである。
あまりに突拍子もなくにわかに理解し難いかもしれない。(本稿にたびたび提示される一見飛躍した修辞は、だんだんとその意味が明らかになるのでご容赦願いたい。)
ここではまず、ユリスの死は絶対に必要なものではなく、他の人物の別のエピソードであっても本作は成り立つ、というものではないことを心に留めておいてもらいたい。
ユリスの死は『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』にとって非常に重要な構造的な意味を持っているマイルストーンなのである。
決定的に重要なのは絶対的前提として「ユリスが死ぬのはなぜなのか?」に思考を巡らせて解き明かすことである。
そこから何がわかるか?何が新たにもたらされるか?
それを問題としたいのである。
第1節.なぜユリスは死ぬのか?〈分身するキャラクターたち〉
それではまずは『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』におけるキャラクターの重ね合わせである〈分身関係〉と〈予示と反復〉の構造について考えてみよう。
ここで触れるキャラクターを列挙しよう。
本作だけでなく『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 - 永遠と自動手記人形 -』からもふたり登場願おう。
ヴァイオレット / テイラー・バートレット / リュカ
ギルベルト / イザベラ・ヨーク / ユリス
以上の6名である。
そして上段の3名がともに〈予示と反復〉の構造と〈分身関係〉にあり、下段の3名も同様である。
これより一人ひとりどのように〈分身関係〉になっているかの根拠を述べていく。
これらは相互参照する再帰的循環関係になっており、誰が誰の分身であるかの根拠を列挙をどこからはじめるか、どの順番とするかは本来ランダムである。
2組3名づつの対応関係は徐々にその結合度合いがましていく構造になっているのがわかってくるだろう。
ゆえにひとつひとつは些細な類似関係であるものもある。
(※念の為断っておくが、ここでいう〈分身関係〉とはあくまでもキャラクターと作品間の類似を外在的な関係として抽象したものであり、キャラクターたちが内在的に、つまりキャラクター同士がそう認識し得る、しているといったようなものではもちろんない。)
・第ⅰ項.ヴァイオレットはテイラー・バートレットの分身である
【①】ヴァイオレットもテイラーも戦争孤児であり、ともに大切な存在となるギルベルトとイザベラ(エイミー)にそれぞれ育てられた過去がある。
さらに両組ともに戦争が原因で離れ離れになる点も共通している。
【②】『劇場版』でヴァイオレットはギルベルトに手紙を書きメッセージを伝える。
『外伝』のテイラーも同様にイザベラ・ヨークにヴァイオレットの助けを借りてメッセージを伝える。
【③】ヴァイオレットもテイラーもともにメッセージを伝えるための障害があるがそれを乗り越える。
【④】テイラーは後にヴァイオレットと同じエヴァーガーデン姓となる。
【⑤】『外伝』でテイラーはベネディクトがイザベラに手紙を渡すシークエンスでイザベラに逢うことなく、その様子を花々の中から見守る。
そこでヴァイオレットの色である紫の花とイザベラを象徴する白薔薇に囲まれるカットがある。(白薔薇は薔薇戦争においてランカスター家の赤薔薇に対してのヨーク家のシンボルである。)(以下画像を参照)


(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 永遠と自動手記人形 』Blu-rayより)
もしテイラーとヴァイオレットの〈分身関係〉が成立するのであればこの花の配色でテイラーとイザベラの関係を暗示していることになる。
これにより、後で見るようにもしギルベルトが白薔薇と関係があるイザベラと〈分身関係〉があれば、テイラーとイザベラを表す花々が間接的にヴァイオレットとギルベルトも表していることになる。
つまりここでは
テイラー ≒ヴァイオレット(紫の花)
(画像参照、テイラーはここではイザベラが白薔薇を表すので紫の花)
↕(手紙) ↓(手紙)
イザベラ(白薔薇)≒ギルベルト(ヴァイオレットとの関係から白薔薇)
(〈分身関係〉?)
(※もちろん通常ギルベルトの花は赤いブーゲンビリアである。)
(※以降矢印の記号はメッセージの送り手から送り先を示している。)
以上をヴァイオレット≒テイラーの〈分身関係〉の論拠とする。
・第ⅱ項.テイラーとリュカは〈分身関係〉にある
【①】この6名の関係式内ではテイラーとリュカの髪の色は類似している。
(以下画像を参照)


(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)
【②】テイラーはまず手紙をイザベラから受け取る役割をにない、また成長して送り手にもなる。
リュカはヴァイオレットとテイラーとは逆に送り手ではなく、受け取る側であるが後述の「なぜユリスは死ぬのか?(分身するキャラクターたち)まとめ【①】メッセージの授受と分身関係」でその役割の位置の逆転の意味が説明される。そのため、ヴァイオレット≒テイラー≒リュカの分身関係は整うことになる。
以上をテイラー≒リュカの論拠とする。
・第ⅲ項.ヴァイオレットとリュカは〈分身関係〉にある
【①】ユリスの家族宛ての手紙を書き終えたヴァイオレットが、ユリスとリュカについての話をするシーンは、ギルベルトがヴァイオレットに逢えない理由を告白する〈予示〉になっている。
なぜか?
もしギルベルトとユリスの〈分身関係〉が成立すると、ヴァイオレットが〈予示〉としてユリスにギルベルトを重ね合わせて、いまだ生存を知り得ぬギルベルトに向かって語りかけているという構図になるためである。
よってこの場合、ユリスがギルベルトと入れ替わっているのだから、逆のヴァイオレットとリュカの置換も成立しえる。
だとするとここで不在のリュカがあらかじめヴァイオレットをとおしてユリスにコンタクトを訴え促しているという構図になる。
ここでヴァイオレットはユリスに「伝えたいことは出来る間に、伝えておく方が良いと思います。」と促す。
つまりこれはヴァイオレットがギルベルトにそう伝えているとともにリュカがユリスに云ってもいるということである。(以下の画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.75)
【②】ヴァイオレットがユリスの入院する病院から出るシーンで彼女はリュカと邂逅しかけるが、ドッペルゲンガーを避けるように果たされない。
そしてこのシーンでヴァイオレットは〈分身関係〉暗示するように夕焼けの光でオレンジに染まる。(※オレンジはテイラーとリュカの共通の髪の色であり象徴するカラーである。後述も参照。)(以下の画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.77)

(『劇場版 ヴァイオレット エヴァーガーデン』 入場者 特典 第3弾 35mm コマフィルム 筆者所有品を撮影)
このヴァイオレットとテイラーの出逢い損ないの意味とは「分身関係にある両者がメッセージを贈り合う関係にあるものと同時に同一の空間を占めることはない。また役割を重複するものが同時に存在することはないという法則」があるためである。
抽象的な表現となるためこれにどういう効果があるかを説明しよう。
つまりこれはいま物語の焦点がどこにあたっているかということを明確にするためである。そこがブレないための処置となる。
〈分身関係〉にあるものを同時に存在させるとその焦点がブレる。
また無駄な複雑化も防ぐ効果がある。
〈予示と反復〉構造はあらかじめ何らかの作品内(間)でのキャラクターの役割を暗示しているということであるからこれは必然的な措置である。
なお前段は4者の関係であり後段は2者関係を表している。
【①】の病院のシーンではユリスとヴァイオレットに焦点があたっている。
そしておもにユリス≒ギルベルトの〈分身関係〉と〈予示と反復〉が示されている。
よってユリスのいるところには当然〈分身関係〉になるギルベルトは登場しないし役割も重複しない。
そして、ヴァイオレットがいるのでその〈分身〉のリュカもここで登場してこないのである。(※【②】のケースは登場しかけることでより明確にそれを示している。)
もう少し詳しく説明しよう。
ここでヴァイオレットだけは特殊である。
なぜなら彼女だけは主人公であるため常にこの作品から退場することがないためである。
ゆえに手紙を書くという役割は彼女が陰に陽に常にその存在を彼女が占めている。
また彼女は代筆者としての役割を演じながらも常にギルベルトへの手紙を書くものであるという二重の役割をになう存在である。
しかし物語の構造として代筆と彼女自身の手紙の執筆は混在しないし、してはならないのである。
なぜ混在してはならないのだろうか?
もしこの段階でユリス≒ギルベルトとリュカ≒ヴァイオレットの4者2組の〈分身関係〉が映画内で場を占めるとヴァイオレット→ギルベルト、ユリス(ヴァイオレットの代筆)→リュカの2つの授受関係も混在してしまうからである。
よってまだここではユリス≒ギルベルトの〈分身関係〉だけに焦点が当たるようになっているのである。
つまりここはユリス≒ギルベルトと代筆者としてのヴァイオレットの役割が物語内を占めている段階である。
ヴァイオレットがリュカと邂逅しない理由はリュカ≒ヴァイオレットの〈分身関係〉の前景化を押し止めるためということになる。
これによりここでは〈分身関係〉がダブって存在することはない。
(※これはあくまで同一時空、同一シーンのみであることに注意してほしい)
【②】のヴァイオレットとリュカのすれ違いをもう一度かんたんに確認してみよう。
ヴァイオレット(≒リュカ)←ユリス≒ギルベルトの前者はそもそもヴァイオレットがリュカに会っていないのでこの〈分身関係〉は同時に同じ場所に存在していない。(よって件の法則は守られている。)
さらにリュカはわざわざ最低限存在が希薄になるように描写されている。
また『外伝』の以下のケースもより単純にそれが示されている。
(ヴァイオレット≒)テイラー⇔イザベラ
ヴァイオレットは両者に会っていてなおかつ両者の手紙も書いているが、3年の時間で隔てられている。
つまりヴァイオレットがイザベラの代筆者であるときはテイラーは3年後までヴァイオレットとの〈分身関係〉にはならないため、後段の「役割を重複するものが同時に存在することはない」のイザベラ→テイラーの2者関係のみとなり以上を満たしている。
そしてヴァイオレットがテイラーの代筆者である時点ではイザベラは3年の月日が彼女の行方を消しているため、ヴァイオレット≒テイラーの分身関係は未来でヴァイオレトがギルベルトに手紙を送るという〈予示〉になっているが、前段の「分身関係にある両者がメッセージを贈り合う関係にあるものと同時に同一の空間を占めることはない。」の4者関係を満たしているのである。
つまり
(ヴァイオレット)≒(テイラー)
↓ ↓
(ギルベルト) ≒(イザベラ)
以上の4者2組関係は全面化せず一方は常に隠れており前景化せずに暗示するという効果がある。
またこのあと確認するギルベルト≒イザベラ≒ユリスの〈分身関係〉であるが、ギルベルトが他の二人とそもそもそれぞれと同一作品、同一時空に存在せず、またこちらはギルベルト←ヴァイオレットが最後に残った関係性のため、このとき〈分身関係〉は一応の役割をすでに終えている。
テイラー⇔イザベラ、リュカ←ユリスという2組の〈分身関係〉の予行演習が最後のヴァイオレット→ギルベルトの〈予示と反復〉構造ということである。
【③】もし後述するギルベルトとユリスの〈分身関係〉が成立するとすれば、自動的に両者に対応するヴァイオレットとリュカの〈分身関係〉が成立する。
以上をヴァイオレット≒リュカの〈分身関係〉の論拠とするが、このふたりのケースは手紙の授受関係にあるヴァイオレット→ユリスのなかにヴァイオレットと〈分身関係〉にあるリュカがすんでのところで入り込んでしまいそうになるという例外的な事例といえよう。
・第ⅳ項.テイラーとリュカはヴァイオレットの分身である
【①】ヴァイオレットがはじめてユリスの病室に入った際、彼女を出迎える薔薇の色はオレンジである。
これはリュカの色であると同時にテイラーの色でもあり、それをヴァイオレットに重ね合わせるのを指示する符牒である。(このオレンジ色の薔薇ははすぐさま萎れた白薔薇へと挿し替えられる。)(※以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.50)
ヴァイオレット≒テイラー≒リュカの3者の〈分身関係〉の論拠は以上とするがこれまでの2者関係の論拠(ユリスの病院を出るヴァイオレットを染め上げるオレンジの光など)から推移的に示されているだろう。
・第ⅴ項.ギルベルトはイザベラ・ヨークの分身である
【①】ヴァイオレットとテイラーの〈分身関係〉と対称的に、両者は戦災孤児としてそれぞれを引き取る決意をしてともに暮す。
【②】①に加え、ヴァイオレットとテイラーの〈分身関係〉と対称的に、ギルベルトとイザベラの物語内の役割は手紙を受け取る立場である。(※イザベラは手紙の授受の双方の担い手であるが重みを持つのはやはり受け取り手としてだろう。)
【③】両者ともに相手を遠ざけなければならない過去である――ギルベルトは戦争での罪責をイザベラは出自に縛られた――役割を持つ。
【④】ヴァイオレットとの関係――。親密な関係――。
ギルベルトはヴァイオレットにとってはじめての「あいしてる」ひとであり、イザベラははじめての「ともだち」である。
【⑤】「第Ⅰ章.エロス篇第1節.ヴァイオレットのエロス第ⅱ項.〈水〉に濡れるヴァイオレットの裸身」で触れたように、ヴァイオレットはイザベラとともに入浴し肌をはじめて晒す。
『劇場版』の肩を出したこれまでにないエロティックな第1弾キービジュアル(以下画像を参照)は明らかにギルベルトへの媚態である。
ギルベルトとの再会の過程が終始、〈水〉の中で繰り広げられるように、『外伝』の入浴での〈水〉とエロティシズムはこれの〈予示と反復〉である。(※この〈水〉が海水に変わる意味とヴァイオレットという〈花〉の回開花に必要な〈光〉が〈月光〉となる意味は結末近くで述べる。)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)
以上をギルベルト≒イザベラの〈分身関係〉の論拠とする。
・第ⅵ項.イザベラとユリスは〈分身関係〉にある
【①】イザベラとユリスはそもそも眼鏡に髪の色という外見的特徴(以下画像を参照)がそっくりである。
またイザベラは喘息を患っておりユリスは病人である。


(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)
【②】イザベラとユリスはヴァイオレットと物語の途中で別れる。
その後ふたりの意思とヴァイオレットの代筆した手紙は第3者によって彼女の〈分身〉であるテイラーとリュカに届けられる。(※正確にはもちろんリュカへの手紙は書かれることはなく電話がその役割を代替する。)
また、その仲介をするのはいずれもベネディクトである。(※ユリスとリュカの場合は手紙が電話にかわったようにアイリスの方に比重が置かれる。)(以下の画像を参照)


(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
以上をイザベラ≒ユリスの〈分身関係〉の論拠とする。
・第ⅶ項.ギルベルトとユリスは〈分身関係〉にある
【①】指切り
云わずもがな。
ユリスとの離れた小指はラストでギルベルトと結ばれて終わる。
(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.73)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.160)
【②】ユリスの病室でヴァイオレットを捉えるギルベルトの視線
ユリスがヴァイオレットに指切りを教え、指をつないでいるシーンで、まるで誰かがユリスの背から眼鏡越しにうつむいたヴァイオレットを見ているように、彼女を捉える大変印象的なカットがある。
(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.73)
これはユリスの死を暗示する枯れて萎れた白薔薇のアップの直後のカットであり、まるで後のギルベルトとの交代を〈予示〉するかのようである。(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.73)
つまりこの病室にはギルベルトが居る。(※この意味は「第Ⅲ章.奇蹟篇」で説明する。)
ユリスの背後に透明で……。幽霊ように……。ギルベルトが――。そう見える。
ヴァイオレットを収めているのはユリスの左の眼鏡の内側からであるが、なぜか?
ギルベルトに右目はない。
【③】ヴァイオレットがユリスに掛ける言葉
「第ⅲ項.ヴァイオレットとリュカは〈分身関係〉にある【①】」を参照。(※「伝えたいことは出来る間に、伝えておく方が良いと思います。」というセリフ。)
ヴァイオレット≒リュカの〈分身関係〉が成立していればギルベルト≒ユリスの〈分身関係〉が成立すると仮定できる。
【④】ユリスとリュカの電話での会話
リュカ「会いたくないって言われて……悲しかったけど、きっとユリスはその方がいいんだって思ったから、ガマンした……。」「けど……どうしてもガマンできなくて……何度か病院に行ったんだ……。」
ユリス「ゴメン……ひどい……こと、言って……。」
リュカ「ううん……。僕、全然怒ってなんかないよ。」「……ユリス、僕たちずっと友達だったろ……。これからも、ずーっと友達でいようね。」
ユリス「……うん……うん……。……よかった……。……ありがとう……。」
(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』pp.130-131)
以上の会話を「第ⅲ項.ヴァイオレットとリュカは〈分身関係〉にある【①】」の論拠からヴァイオレット≒リュカの〈分身関係〉としてリュカをヴァイオレットに置換する。
そしてギルベルト≒ユリスを求めているので、ユリスのセリフをギルベルトのものと考えてみる。(※引用部のリュカをヴァイオレットのセリフとしてユリスをギルベルトのセリフとして置き換えてみる。)
そうするとこの会話はそのままヴァイオレットとギルベルトの会話の〈予示〉となっているのがわかるだろう。
以上をギルベルト≒ユリスの〈分身関係〉の論拠とする。
・第ⅷ項.イザベラとユリスはギルベルトの分身である
【①】「第ⅴ項.ギルベルトはイザベラ・ヨークの分身である」と「第ⅵ項.イザベラとユリスは〈分身関係〉にある」、「第ⅶ項.ギルベルトとユリスは〈分身関係〉にある」から、ギルベルト≒イザベラ≒ユリスの〈分身関係〉は妥当である。
【②】ギルベルトには兄のディートフリート、イザベラ(エイミー)は妹のテイラー、ユリスは弟のシオンと3組ともにきょうだいがいる。
〈きょうだい関係〉(※矢印は手紙の送付先を示す)
ギルベルト*ディートフリート
| |
イザベラ ⇔ テイラー
| |
ユリス → シオン
左の縦列において3者が対応することがわかる。
※ギルベルトは弟なので逆位置ではないか?と思われるかもしれないが、上図の右列の3者には左列の3者とは違い〈きょうだいを持つ〉以外の共通性はない(あっても微弱な)ため、あくまでも左列の〈きょうだい関係〉の属性を抽出する役割しかない。
またこれは、エカルテ島での再会時のディートフリート(兄)からギルベルト(弟)への決別のメッセージがユリス(兄)からシオン(弟)へのお別れのメッセージと重なっており、手紙の授受という本作の構造とはまた別の〈予示と反復〉になっている。
以上をギルベルト≒イザベラ≒シオンの3者の〈分身関係〉の論拠とする。
【第1節.なぜユリスは死ぬのか?〈分身するキャラクターたち〉まとめ】
【①】〈メッセージの授受と分身関係〉
・ヴァイオレット≒テイラー≒リュカ⇒分身関係
・ギルベルト≒イザベラ≒ユリス⇒分身関係
ヴァイオレット→ギルベルト(弟という属性)
| |
テイラー ⇔ イザベラ ↕(属性の反対の関係がメッセージ
| | 授受関係の反転を示す)
リュカ ← ユリス (兄という属性)
整理すると上図のようになる。
このように
【1】テイラーがヴァイオレットの〈分身〉であるならば、ユリスとリュカだけ矢印の向きが逆になっていないか?
【2】ヴァイオレットの〈分身〉をリュカではなくユリスに設定するか、リュカが手紙を送る物語にしたほうが整合性が取れるのではないか?
と思われるかもしれない。
この点を説明しよう。
【1】まずこれはギルベルトは弟であり、ユリスは兄であるという〈兄弟関係〉での属性を明確するためである。
そしてギルベルトの弟、ユリスの兄という属性が反対であるようにメッセージの授受関係も反転しているのである。
よって妹という属性を持つテイラーは双方とも違う授受両方の役割をになう。
【2】では、もし本作がリュカ→ユリスへとメッセージを送る物語だったとしたら?そちらの方がきれいな関係図式にならないか?
それは無理なのである。
なぜなら問題はリュカではなく、ユリスの弟のシオンが稚すぎるということだからである。
『外伝』でテイラーが3年の成長時間があったのに対してシオンにはない。
つまりユリスの家族構成ではシオンは手紙を書けないので、必然的にユリスが手紙、電話、メッセージを送る側になるしかなく、受け取る側となることはできない。
リュカがユリスに手紙を送ることはできる。しかしシオンはユリスに送れない。だからユリスは受け手側ではなく送る側なのだ。
いや、リュカがヴァイオレットの〈分身〉なのだとすれば、ユリスはリュカに対しては受け手となり、シオンに対しては送り手側にもできたのではないか?
しかしそうすると今度は先に説明した、ユリス(兄)のギルベルト(弟)との〈兄弟関係〉の反転がもたらす対照性(※ギルベルトの弟であり受け手とユリスの兄であり送り手という対照的な〈分身関係〉のこと)が意味をなさなくなるので、本作における〈兄弟関係〉という軸がぶれてしまう。
さらにユリスとリュカが双方ともに授受両方の属性を持つというのは作品の構成として無駄に煩雑となり、かつ『外伝』のテイラーとイザベラの相互授受という特徴と重複してしまう。これもまた対照性が持つ効果も免じられてしまうだろう。ブレる上に単調では意味がない。
なによりヴァイオレットとギルベルトの〈分身関係〉としての〈予示と反復〉構造と一致しなくなってしまう。
【②】〈予示と反復〉の構造
ここまで詳述してきたように、『外伝』と『劇場版』からは髪の色などの見た目や生い立ちなどの背景、家族構成などの属性、薔薇などの花による象徴によるキャラクターの〈分身関係〉を取り出すことができる。
そしてさらに、そうして成立した〈分身関係〉は、先行するキャラクターの言動の意図に、他の分身を前もって暗示する〈予示〉を、それをくりかえし変奏する〈反復〉をもたらしている。
各キャラクターは〈分身〉を持つことで、それぞれが違う役割を持ち独立しながらも他のキャラクター間に影響を与え合い、作品自体にもダイナミックな推進力を与えている。
『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の一見静かな文芸作品のような面持ちの裡に作動している機構の力学は、優れた推理小説のように読むことでこれほどまでに精密でスリリングになるのである。
◆
※観客の一部の声として作劇法のセオリー的に、ヴァイオレットと新たな愛を交わす相手としてディートフリートやホッジンズを望む声があるが、これまでの〈エロス〉や〈分身関係〉、〈予示と反復〉の物語の構造分析からも、それはありえないことがわかる。
第2節.承前 ユリスはなぜ死ぬのか?〈残酷〉
さて、本章の冒頭に「〈ギルベルトの生存〉こそがユリスを死に至らしめた」〈残酷〉であり、「ユリスはギルベルトが戦火から生還し、ヴァイオレットと再会するために犠牲に供されるのである。」と述べた。
まずは先述の「分身関係にある両者がメッセージを贈り合う関係にあるものと同時に同一の空間を占めることはない。また役割を重複するものが同時に存在することはないという法則」の発展的解消をもたらすユリスの〈死〉にどのような〈残酷〉な機能があるのか確認してみよう。
・第ⅰ項.ユリスの〈死〉の機能【物語の分岐点】
『劇場版』も後半に入ってくると、おもに(ギルベルト)≒ユリスの〈分身関係〉と代筆者ヴァイオレットという3人の構図が解かれ、最終的な段階へと遷り変わらなければならなくなる。
つまりヴァイオレット→ギルベルト/リュカ←ユリスの4者関係として全面化しないために2組同士がそれぞれはっきりと浮き上がってから分離し後者の1組が決着する。(※これが発展的解消の謂である。)
その分岐点となるのはギルベルトの生存がヴァイオレットにほのめかされるところである。
そうすることでヴァイオレットはユリスのもとから離れることとなり、ユリスのメッセージの受け手となるリュカが前景化する準備が整う。
ややくりかえしになるが、以後詳しく述べると、ここでいままで背景に退いていたギルベルトとリュカがせり出してくることによって、ヴァイオレット≒リュカ、ギルベルト≒ユリスの2組の〈分身関係〉が同一の舞台に上る。
よって「同一の空間を占める」ことになり、また「重複するものが同時に存在すること」になり法則に反する。(※もちろんここで法則と呼んでいるのは前にも述べたように恣意的なつじつま合わせではなく、物語が収束していくに連れて伴う必然的な「整理」と「刈り取り」の謂である。)
よって物語の進行はまずヴァイオレット→ギルベルト、ユリス→リュカのふたつの関係性をはっきりと分ける。そのために舞台もまた遠く隔たったエカルテ島と二分されることになる。
そして物語の位置の前後関係は当然ユリス→リュカが先に置かれることとなる。
前後関係が決まるということは物語上のそのエピソードの機能も決定するということである。
この決定が先にあってそれからこの物語『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』ははじまっているのである。
ユリスの死の意味のひとつはこの決定がもたらしたものだ。
この観点からはユリスは病気だから死ぬのではない。
後述するように死ぬことで〈分身関係〉と〈予示と反復〉の構造を活かすことになる。(※ユリスの死の真の意味は本稿の末尾近くで明らかとする。)
物語はここから完全にヴァイオレットとギルベルトに焦点が移る。
そういう物語だからこそ、ユリスは死ぬ。
これによってヴァイオレットはユリスの代筆者という手紙の書き手としてもリュカという〈分身〉からも解放されて素肌をさらし、みずからの欲望の赴くままにエロスを全開にすることが可能になる。
ユリスが死ななければ、物語が先に進まない。
これは〈残酷〉だろう。
(※ヴァイオレットがユリスの代筆者の役割を途中で離れ、遠くギルベルトへと旅立つというのはこれまで一度もその依頼を完遂させないことがなかった彼女にとってはじめての異常事態であるといえる。この点をぜひ熟読玩味して欲しい。次項でまたすぐに触れる。)
しかし〈残酷〉の意味はただこれだけではもちろんない。
これではまだギルベルトの生存と引き換えであるという点がいささかも論じられていない。
それは次項に譲ろう。
ただここでこうは云える。
〈分身関係〉と〈予示と反復〉という構造がなければユリスの死は必要なかったのかもしれない。
あるいはただの物語のひとつの挿話の演出上の死とすることもできた。
しかしもしそうであったとすれば本作『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は、芯のない泣かせのための泣かせ作品、通俗的な恋愛劇に堕したことだろう。
ユリスの死に集約する構造と〈残酷〉の意味があればこそ、本作は「第Ⅲ章.」に見る〈奇蹟〉が宿る作品になるのである。
・第ⅱ項. ユリスの〈死〉の機能【残酷な効果】
前置きが長くなった。では「第1節.なぜユリスは死ぬのか?【分身するキャラクターたち】」の〈分身関係〉と〈予示と反復〉の構造がもたらすユリスの死の意味を踏まえて、ここでは本格的に〈残酷〉の内実に迫ってみよう。
次のシーンを思い出してほしい。
危篤のユリスのもとに駆けつけた彼とアイリスとの会話である。
ユリス「ヴァイオ……レット……?」
アイリス「かわりに来たアイリスよ。ヴァイオレットは今、遠くにいるの。大切な人とやっと会えて……」
ユリス「あいしてる……を、教えてくれた人……?」
アイリス「……うん……。そうよ。」
ユリス「……生きてたんだ……よかった。」
アイリス「……」
(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』pp.126-127)
このシーンは意味深長であろう。
ヴァイオレットは依頼人であり短いながらも親交を深めたユリスの臨終に居合わせない。
ここで観客は少なからず、あるいはユリス以上に落胆を覚えたかもしれない。
ヴァイオレットは明らかにリュカへの手紙を書くという仕事をやり残している。そして代わりにヴァイオレットは死が間近に迫ったユリスを置いて遠く不明のひとを探しに行っているのである。
これもひとつの〈残酷〉だろう。
このシーンは前項で論じたヴァイオレット≒リュカ、ギルベルト≒ユリスの〈分身関係〉の紐帯が緩みヴァイオレット→ギルベルトへと遷移する接線、リミットである。
あたりまえなのだが、上記の会話でユリスはヴァイオレットにとって「あいしているを教えてくれた人」ではないし、ユリスにとってもヴァイオレットは交換可能な相手であり必要なのはリュカにメッセージを残すことであることを印象的に表現している。
さらにギルベルト≒ユリスという〈分身関係〉の亀裂を、これから死ぬユリスの声で「……生きてたんだ……よかった。」と云わせることで、みずからがスケープゴートであること、ギルベルトの罪を贖う贖罪の羊であることを、これ以上ないほど強烈に暴露したかのようである。
ユリスとギルベルトの〈分身関係〉はまさに身代わりになるためのものであったかのように――。
〈分身関係〉の亀裂を〈死〉をもって鮮明に描くことで、逆にその構造を確かにするために、ただただヴァイオレットのギルベルトへの執着をより強く表現するために、ギルベルトの生存を彩るために、ユリスは死ぬのである。
観客を落涙させるためではない。
くりかえそう。
ユリスはギルベルトの〈分身〉として代わりに犠牲となった。
そしてギルベルトは贖罪と命を得ることになったのである。
これが〈残酷〉の意味、実相である。
その後も確認しよう。
ヴァイオレットはホッジンズから聞かされる。
ホッジンズ「……ユリス君が大切な人に会えたこと……喜んでいたって……。」
ヴァイオレット「……。」
ホッジンズ「……。」
ホッジンズ「朝になったら、もう一度、あいつの所へ行こう……。出てこなかったら、ドアをブチ破って、あいつをぶん殴ってでも……。」
ヴァイオレット「いいえ……。」
ヴァイオレット「少佐を殴るのでしたら、私が……。」
(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』pp.134-135)
もはや説明の必要はないだろう。
このヴァイオレットのこれまで見せることのなかったドキリとさせるいささか場違いともいえる発言は、彼女が自分と会わないギルベルトにたいして向けたものではない。
ユリスが死すものとして存在すること自体への怒りなのである。
そしてここではじめてヴァイオレットは、これまでイノセントでしかなかったギルベルトへの想い、エロスが彼とともにユリスの死を招来したかもしれないことに気づいたかもしれないのである。(※もちろんキャラクター自身がそう感じているということではない。)
【第2節.承前 ユリスはなぜ死ぬのか?〈残酷〉まとめ】
【ⅰ】ユリスの死は物語の〈分岐点〉として、ヴァイオレットを〈分身関係〉と〈予示と反復〉の構造から解放し、ギルベルトへの裸身のエロスを全開にして高めるためである。
【ⅱ】
・ヴァイオレット≒リュカ、ギルベルト≒ユリスの〈分身関係〉はユリスの死によってその紐帯が完全に解かれる。
以後ヴァイオレット→ギルベルトの物語の核心へ進む。
・ギルベルト≒ユリスの〈分身関係〉が成立しているからこそ、ユリスの死は犠牲としての意味をもち、ギルベルトの生存と贖罪を可能とする。
・ヴァイオレットとギルベルトのエロスが相互に向いている以上、ユリスの死の責任はヴァイオレットのエロスにも混濁する。
(次章への導入として)
ユリスの供犠という〈残酷〉により、ヴァイオレットとギルベルトのエロスはその成就を〈不可能〉なものにする。
同時に〈奇蹟〉として(によってのみ)結びつく可能性が生まれる。
▼第Ⅲ章.奇蹟篇
まえがき
〈奇蹟の映画/映画の奇蹟〉
『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』
『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は〈奇蹟の映画〉である。
〈奇蹟〉に分析と説明の手は届かないが、これまでに思考した材料を頼りにできるだけそれに迫れることを祈り、記す。
あらためて、何が〈奇蹟〉であるか?
具体的にはヴァイオレットとギルベルトの〈愛が成就すること〉、その一点である。
この愛とは何かについての詳細も後に語ることにあるだろう。
この映画を観ることで、われわれはすでに〈奇蹟〉を目撃してしまっている。
だからそれが〈奇蹟〉であったことがもうわからない。
この〈奇蹟〉は劇的でありながら同時にひっそりと生じた。
あたかもそれが必然であったかのように。
それが起こることがあり得なかった世界を思い描くことができなくなるかのように。
できないのはこの〈奇蹟〉が起きなかったと〈いま〉思い描くということではない。
それができないのは〈奇蹟〉が起こり得なかったという〈いま〉がもはやどこにも存在しないからだ。
そのときの〈いま〉はどこにもないのだ。
その〈いま〉とは〈奇蹟〉の〈根拠〉のことだ。
そして〈奇蹟〉に〈根拠〉はない。
云い直したほうがいい。
〈奇蹟〉の〈根拠〉がわからない。
なぜ、ヴァイオレットとギルベルトの〈愛の成就〉という〈奇蹟〉があり得たのかがわからない。
もし私たちがあの〈奇蹟〉に心を打たれたのだとすれば、それが〈奇蹟〉によるものだったのだとすれば、それは〈奇蹟〉であったことの〈痕跡〉を触知したからだろう。
だから〈奇蹟〉の〈根拠〉がわからなくても、〈奇蹟〉の〈痕跡〉を寄せ集めることはできる。
〈奇蹟〉の〈痕跡〉は〈奇蹟〉の後に残るだけでなく事後的に〈奇蹟〉の前にも存在していたことになるだろう。
なぜ起こったのは〈奇蹟〉だとわかるのか?
それが〈ありえないこと〉だったからだ。
「ヴァイオレットとギルベルトの〈愛の成就〉はありえないことだった」
本章ではこの〈愛の成就〉=〈不可能性〉=〈奇蹟〉という観点から論じていこう。
そうでないのなら、
ありえないことでないなら、
〈奇蹟〉でないのなら、
では『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は何だというのか?
第1節.『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のいくつかの欠点?
あらためて、本作を〈奇蹟の映画〉としてみるために、くれぐれも気をつけないといけないことがある。
それは、ギルベルトが生存している点、そしてヴァイオレットとギルベルトの両者が互いのその愛の対象となること、この2点を本作にとっての瑕疵、欠点、短所であるとみなすことである。
『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の否定的な感想、評価としてよく耳にするのは、
・「ギルベルトが生きていないほうが良かった」
・「時間的にそれを織り込むことは不可能であるとしても、ヴァイオレットがギルベルトの死を乗り越えていく物語のほうが、制作の背景を勘案すれば、優れた作品になった」
・「ヴァイオレットはギルベルトの生死に関わらず、彼以外との未来を生きるべきだった」
というものである。
これらの意見はドラマツルギーとしてはよくいって良識的、悪く云えばありきたりなものである。
この作品がなぜこういった展開とならなかったかはこれまでにも言及した。
それをいまここで一言でいうならば「奇蹟が起きたから」である。
「奇蹟が起きるため」「奇蹟を起こすため」ではない。
それではまるであらかじめ〈奇蹟〉を待ち望んでいるか〈奇蹟〉がなにかわかっているかになる。
どちらにしても〈奇蹟〉を念頭に置いてしまっている。
そうではないのだ。
それが起きたからこそ遡及的にこれまでがその準備であったかのように見えるのである。
いや見えるのではなくそうなるのである。
しかし重要なことは、その〈奇蹟〉の〈痕跡〉を触知するにはこれらの作劇的困難を正しく認識していなければならない。
これは断言しておく。
もしこのような否定的視点からだけで見るならば本作は、ただ退屈で平凡な悪い意味でのメロドラマに堕することを免れないだろう。
だが同時にそう見ないならば〈奇蹟の映画〉であることがわからなくなってしまうだろう。
いま云えることは、この映画の〈奇蹟〉に気づくにはギルベルトは生きていなければならなかったし、ふたりは結ばれなければならなかったということである。
それが〈不可能〉であるがゆえに。
〈不可能な愛〉であると認識していなければ〈奇跡〉は起きない。
つまり〈奇蹟〉とはそれを目撃する観客とのインタラクションによって起こりえるということだ。それを忘れないでほしい。
もうひとつ。
より多く仄聞するのはいわゆる「ギルベルトの弱さ問題」といったものだ。
つまり「ギルベルトが情けない」「ギルベルトは利己的、自己陶酔している」ゆえにヴァイオレットにふさわしくないというなんとも感情的な反応があるようだ。
これらの見解は、本作を極めて表層的というよりはほぼ見ていないに等しい反応でしかない。
これが当のヴァイオレットがそんなことをまったく思いも感じもしていないだろうということ踏まえたうえで――つまりヴァイオレットをとおして彼をみるのではなく彼女を自分で上書きして――のものであるとすればギルベルトの背徳的なエロスにたいしてこれまた良識的な感覚を示しているとはいえるかもしれない。
ギルベルトの逡巡の重みを正しく捉えることがいかに重要となるかは後述していくことで明らかになるだろう。
第2節.ギルベルトの生存の意味とは何か?死に損なった男のエロス
第1節.で挙げた本作の作劇的「ありえなさ」である「ギルベルトが生きてヴァイオレットとの愛を成就させる」という物語こそが〈奇蹟〉の〈痕跡〉であった。
そして観客がそのように見なすという相互作用によって〈奇蹟〉が見えるのであった。
では次にその「ありえなさ」がなぜ〈奇蹟〉の〈痕跡〉だと云えるのかを追ってみよう。
まず最初に作品外的アプローチから。
(※〈奇蹟の痕跡〉とは〈奇蹟〉を目の当たりにするためのヒントのことである。)
・第ⅰ項.ギルベルトは生きていたほうが良かったのか?作品〈外〉からのアプローチ
ギルベルトは生きていることがありえない。
なぜか?
なぜなら生きているのは作劇的に安易でありセオリーから外れていると思われるから。
さらにギルベルトの死をヴァイオレットが受け入れる喪の作業はテレビアニメ版ですでに描いているはずであるから。
これで生きていてはそのエピソードが台無しになってしまう。
このように考えられる。
しかし逆にこうも云えよう。
ギルベルトは生きていないことがありえない。つまり死んでいるはずがない。
なぜか?
なぜならこちらもすでに済ませているギルベルトの喪の作業をもう一度くりかえし描くのは作劇的にありえないから。
つまり劇場版をやる上で、ギルベルトの死の受け入れはもうできないはずである。
またヴァイオレットが亡きギルベルト以外の相手と築く未来の話もありえない。
なぜなら後述する彼女の狂信的なエロスをこそ本作がまずは描かなければならないものであるからだ。
新しくはじまるギルベルト以外との恋愛劇に彼女の烈しいエロスはそぐわないだろう。
こうなってしまっては〈奇跡〉が起きない。
(※〈奇蹟〉は起こすものではないが、しかし一度それが起こってしまったのであるからには事後の視点から可能であった〈奇蹟〉ではない展開を追う必要は今回はないだろう。)
最後に、そういった原作の改変は端的に、ない。(※身も蓋もない理由であるが。)
さらに生死の問題の副次的な展開として、ギルベルトが生きておりかつ彼と「再会するかしないか」を焦点とする話を描く、というのも〈奇蹟〉の未発であるからには上記の理由から排除される。
つまり、〈奇蹟〉であるのは――ギルベルトの生死を作品外からのアプローチから考えた場合、彼が生きていたからでもそうでなかったからでもなくその両者がどちらもありえない二律背反にもかかわらず――「ヴァイオレットとギルベルトの愛が成就した」ことにある。
・第ⅱ項.ギルベルトは生きていたほうが良かったのか?作品〈内〉からのアプローチ
次に作品内の物語の論理からまとめてみよう。
ギルベルトの生存がこの物語にもたらしたものとは何か?
それはエロスである。
過去と現在におけるヴァイオレットへのエロスが焦眉となる。
(※本論でのエロスの定義を見失いかけている方へ。エロスとは古代ギリシャにおけるプラトン的な「ある対象へ恋い焦がれる熱情」のことであった。)
ギルベルトのエロスは背徳的であった。
歪で倒錯した光源氏計画――。
殺人マシーンであることで際立つ少年兵ヴァイオレットの蠱惑的な美に滲む妖艶なかわいらしさ――。
その魅力に溺れた代償としての失った右眼と手――。
失わせた両腕――。
それが物語の求心力となるギルベルトの生存の意味である。
(これは「第Ⅰ章.エロス篇第2節.ギルベルトのエロス」で述べた。)
ギルベルトの生存が引き換えにした代償はそれだけではなかった。
それが「第Ⅱ章.残酷篇」で述べたユリスとの〈分身関係〉による彼の死であった。
ではギルベルトの生存は彼のエロスを、ひとりの少年を犠牲にしてにまで満たすための物語に帰結するということだろうか?
本作の結末は、〈奇蹟〉としての〈愛の成就〉とは、少なくともギルベルトにとってはそういうことだったのだろうか?
「違う」「そうではない」と一蹴してしまうのは容易い。
ではギルベルトの〈愛〉とは何なのか?
〈エロス〉とは?
ギルベルトの「あいしてる」とは何なのか?
そしてヴァイオレットの「あいしてる」は?
本稿では一貫して〈愛のエロス的側面〉を手放すことはない。
そうでなければ本作を〈奇蹟の映画〉などと呼称することはないだろう。
ギルベルトの「あいしてる」とヴァイオレットの「あいしてる」の相克のドラマとして本作を論じること。
「第Ⅰ章.エロス篇」と「第Ⅱ章.残酷篇」はその準備であった。
半死半生の愛、死の愛、そうした崩壊した瓦礫のなかにしか〈奇蹟〉はありえないだろう。
それは〈不可能なもの〉だからだ。
淫靡なギルベルトのエロスの行方を追うこと。
それが〈奇蹟〉の〈痕跡〉にたどり着くひとつの道程である。
背徳と死を引き連れたギルベルトの生――。
死に損なった生命――。
徹底的に否定的な存在として生きてしまったこと――。
彼をそう見なすこと――。
では彼を「あいしてる」ヴァイオレットにとってギルベルトはどのような存在としてあったのか。
ここで新たな疑問が胎動してくる。
そもそも私たち観客は彼と彼女のことをどれほど知っているのか?
ギルベルトはヴァイオレットの、ヴァイオレットはギルベルトの何を知っていて、どう理解し、どう思い、どうしようとしていたのか?
これらがこの「第Ⅲ章.奇蹟篇」の主題のひとつとなるだろう。
次節ではまずギルベルトがなぜヴァイオレットを拒絶したのかを詳細に確認してみよう。
第3節.ギルベルトの〈エロス〉/〈過去〉の罪と〈未来〉の罪/ひとつ目の〈不可能性〉
それが不可能であるからこそ〈奇蹟〉なのだと論じてきた。
ヴァイオレットとギルベルトの「叶わぬ願い」――。
それに向かって本作では一歩一歩と前進していく。
幼き日のヴァイオレットを重ねただろうか。
ギルベルトがエカルテ島の子供に頼まれ代筆することになる届く宛のない手紙が皮肉にもヴァイオレットに彼の居場所を知らせることになる。
この何重もの反転はこれも〈奇蹟〉の予兆だったと云えるのか、ただの偶然か。
エカルテ島へとたどり着き、ギルベルトの生存が確定し、居場所がわかり、ホッジンズが会話を交わしたところで尽きる先の〈奇蹟〉の予兆――。
ここで本作は〈不可能性〉のアンチノミー(二律背反)の領域に足を踏み入れることになる。
正しく把握することも説明することも困難な、まして解決することが〈不可能〉に見える問題だ。
・第ⅰ項.ギルベルトはヴァイオレットの「あいしてる」を知っていたのか?
「第Ⅰ章.エロス篇第2節.ギルベルトのエロス第ⅱ項.」で、なぜギルベルトのエロスは背徳的なのかについて「決定的になるのは、ギルベルトはドールとなり成長したヴァイオレットがいまや自分を愛していることをわかっている」からだと記した。
いまからこれについてを考えてみたいのだが、まずこういった意見があるだろう。
「それはおかしい!ギルベルトはヴァイオレットの手紙の最後の一文「わたしは、少佐を愛しています」を読むことではじめてヴァイオレットの真意を知り、だからこそ駆け出したのではないのか?」
(※最後の一文の解読については虫圭氏の記事を参照)
もっともである。
とは云えない。そうではないのだ。
ギルベルトはヴァイオレットの手紙を読んでヴァイオレットの気持ちを知ったのではない。
もしそうであったならばこの物語は成立すらしないのだ。
知っていたからこそギルベルトとヴァイオレットの〈愛の成就〉は不可能なのであるし、また〈奇蹟〉という圧倒的な強度をもたらすのだ。(※このテーゼは本論の始めから終わりまで何度も一貫してでてくることになるだろう。)
もしあの手紙ではじめて知ったのなら、そのように理解されているのだったら、本作の強度は著しく下がる。まったく別物になってしまう。
そうであろう。もう一度考えてみてほしい。
どうしてギルベルトはヴァイオレットに逢えないのか?逢おうとしないのか?
きちんと説明できるだろうか?
〈愛の成就〉という〈奇蹟〉の〈痕跡〉とは〈不可能なこと〉であった。
しかし本節の〈説明不可能性〉とはこの点――どうしてギルベルトはヴァイオレットに逢えないのか?逢おうとしないのか?――ではない。
それはこれからなすように説明できる。
本当に奇蹟的なのは
「ギルベルトがヴァイオレットの愛を知っているにもかかわらず愛が成就したこと」
である。
これが説明不可能なのである。
まずは説明可能な問いから答えよう。
「もしギルベルトがヴァイオレットの愛を知らなかったならば彼女と逢わない説明がつかない」以外にもさらに他のギルベルトが彼女の愛を知っていたとする根拠はあるのか?
ある。
私たちはその根拠を実際に見て知っている。
思い出してほしい。次のシーンだ。
「第Ⅱ章.残酷篇第1節.第ⅲ項.ヴァイオレットとリュカは〈分身関係〉にある」で「ヴァイオレットが〈予示〉としてユリスにギルベルトを重ね合わせて、いまだ生存を知り得ぬギルベルトに向かって語りかけているという構図になるためである」とした。
さらにこれは「伝えたいことは出来る間に、伝えておく方が良いと思います」といってからヴァイオレットがあらかじめギルベルトに伝えたいことをユリスに話すシーンであると論じたのだった。
ヴァイオレットとユリスの会話はこう続いている。
ユリス「……そうかな……。」
ヴァイオレット「はい……。私は……全てを聞くことも……伝えることも出来ませんでしたが……。」
ユリス「……誰に……?」
ヴァイオレット「……私に……あいしてるをくれた方です……。」
ユリス「……そのひと……死んじゃったの?」
ヴァイオレット「……私は、どこかで生きていらっしゃると信じております。」
ユリス「……その人に、何を伝えたかったの?」
ヴァイオレット「……。あいしてるも……少しは分かると……。」
ユリス「……分かっただけ?」
ヴァイオレット「……。」
(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.75)
この後ヴァイオレットの沈黙が続く。
ト書きには「考え続けるヴァイオレット」「一生懸命考える」とあり、ユリスの「微笑し、少し落ち着く」となってユリスがリュカと逢わない理由を話す。
(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.76)
「第Ⅱ章.残酷篇第1節.第ⅶ項.ギルベルトとユリスは〈分身関係〉にある【②】ユリスの病室でヴァイオレットを捉えるギルベルトの視線」においてこのシーンで「この病室にはギルベルトが居る」と述べた。
そしてその説明を予告しておいた。下画像のシーンである。

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.73)
これが根拠である。
つまりギルベルトはユリスとして、自身の身代わりとして死ぬ少年をとおして、ヴァイオレットの「あいしてる」を知っているのだ。
※あるいは読者が知っていることは登場人物も知っているという文学的修辞法でも構わない。
こういった作品の内と外を行き来する映像とテクストの解釈空間が成立していることを察知できなければ本作を構造的に把握することはおぼつかないだろう。
ましてや〈奇蹟〉を見ることは決してかなわない。
ここからさらに一度おさらいしてから敷衍してみよう。
・第ⅱ項.観客は云う「あなたはヴァイオレットに逢ってはならない」
それではまずは何が〈奇蹟〉という不可能なことであるのか、それは確かなことかをおさらいしてから、それがどれほど不可能なことであるかを敷衍してみていこう。
【おさらい】
〈奇蹟〉はそれが〈不可能〉であるから〈奇蹟〉である。
〈奇蹟〉はそれがなぜ起きたのかをどれだけ根拠を並べ立てても、証拠を集めても論理的に説明することはできない。
よってわれわれに可能なのは〈奇蹟〉の〈痕跡〉であろうものを見逃さないことである。
〈奇蹟の痕跡〉とは〈不可能〉な事態である。
『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の〈奇蹟〉の分水嶺となるのは「ギルベルトがヴァイオレットと逢うことは不可能」(これは〈不可能〉な事態ではなく説明可能なことである)であるということである。
もしヴァイオレットが自分を愛してることをギルベルトが知らなければ、逢わない必然性がなくむしろ不自然ですらある。(※知らずに逢わない理由があるとしてもそれは必然的ではない。逢わない必然性を帯びるのは知っている場合である。)
そして実際に逢おうとはしなかった。
【結論】
よってギルベルトはヴァイオレットがおのれを愛してることを知っていると考えるのが妥当である。
傍証としてヴァイオレットとユリスの会話をギルベルトはわれわれと一緒に聞いている(もちろん作品内のキャラクターが物理的に聞いているのではない。念の為)。
※ここまでで頻出する「〈奇蹟〉と〈奇蹟の痕跡〉の違いとは何ぞや?ややこしい」という方のためにもう一度整理しておこう。
〈奇蹟〉とは「ギルベルトがヴァイオレットの愛を知っているにもかかわらず愛が成就したこと」という〈不可能なこと〉――説明できないありえないことが――であるにもかかわらず実際に起ったことであり〈愛の成就〉と表記する。
〈奇蹟〉の〈痕跡〉とは端的に不可能なこと自体を指しそれが跳躍して可能になる前のことである。
〈不可能性〉や〈説明不可能性〉、この後では〈決定不能性〉、〈不確定性〉、〈ブラックボックス〉等とも表記される。
これも前に述べたが、〈痕跡〉に焦点を当てるのは〈奇蹟〉の起きた根拠はわからないとしか云えないため、それに迫るために何が不可能なことであるかを精緻に分析することにより〈奇蹟〉へ至る一筋の光明が差し込むことに〈賭ける〉ためである。(※この〈賭け〉もすぐさま重要なキーワードとなる。)
【敷衍】
先に「本当に奇蹟的なのはギルベルトがヴァイオレットの愛を知っているにもかかわらず愛が成就したことである。これが説明不可能性なのである。」と述べた。
前者の「ギルベルトがヴァイオレットの愛を知っている」は説明した。次にいよいよ不可能性という〈奇蹟〉の接線にまで迫っていこう。
〈愛の成就〉というこの不可能なことが可能となるためには準備として、いかにそれが不可能なことであるかから確認しなければならない。
まずはじめに不可能なこと。
ギルベルトがヴァイオレットと逢うことである。
そもそもギルベルトがヴァイオレットに逢えない理由はなにか?
もしギルベルトがヴァイオレットからの手紙ではじめて彼女からの愛を知ったのだとすれば、あたりまえだがそれ以前はヴァイオレットが何のために自分に逢いに来たのか、何を考えているのか、自分にたいしてどう思っているのかを(完全には?ほとんど?)わかっていなかったということになる。
しかしこれだと彼女と逢うための障害はほとんどないように思われる。(※だからこそここで否定する前提――ギルベルトはヴァイオレットの想いを知らなかった――からすれば「さっさと逢え!」という少なくない感想があるのだろう。)
「いや障害がないなんてことはない。ヴァイオレットが生きてドールとなっていることがわかっても逢いに行こうとはしなかったのだから逢いたくない理由があるのだろう。」
そうかも知れない。
いやそうだろうか?逆ではないか?(ヴァイオレットが自分を愛しているということを)知っているからこそ障害になるのであって知らないゆえの障害など何があるだろうか。
1つ。もう目の前に来ているのだ。常識的な感覚としてまだ遠くにいるのであれば、ヴァイオレットへの少なからぬ罪悪感からいろいろと心の整理をする時間が必要であったとみるのは通常の感覚だろう。
この場合ギルベルトが即会いに行こうとしなかったからといって彼女に絶対に会うつもりがなかったとは云えないだろう。
しかし遠方よりわざわざ逢いに来た目の前の相手に会わないというのは相当の理由があると考えるべきだろう。
2つ。まずヴァイオレットへの罪悪感のために後に彼女から距離を置くことにするにしても、離れ離れになって意識を取り戻した後、真っ先に彼女の生死を確認しようとするのが普通ではないのか?
むしろそれすらしないというのはこれはあまりにも異常ではないのか。
その異常性を説明できるだろうか?
そこでのその最初の徹底した拒絶こそが数年経ったエカルテ島における彼女への拒絶の等根源的理由だろう。
それともその描写がなかっただけであろうか?とてもそのようには思えないのだが……。
やはりこれは酷薄なことと感じるかもしれないが、ギルベルトはヴァイオレットは死んでいるものだと思おうとしていたと考えたほうが自然である。
そうであるからより彼女を受け入れることに抵抗感があったのだろう。
そして死なせてしまったという思いがますますおのれを罪のループにさいなませることになったのだろう。
そしてこれは矛盾しないのだが、同時に彼女は自分と関係なく生きていると思いたかったはずであり、なかばそう思っていたはずである。
しかし自分と関係なく生きているはずのヴァイオレットが逢いに来てしまったからその現実は否定されなければならなかったのである
※また後述する重要な論点として、ここでは彼は真の意味ではまだ戦争から生きて返って来てはいなかったのである。
またギルベルトはずっと前からヴァイオレットの生存は知っていた、あるいは作中のエカルテ島の描写においてはじめて知った、というのはどちらでも良い。
しかし逢いに来たヴァイオレットをあれほどまでに拒絶する理由をギルベルトが作中で述べた理由からは導き出せない。(※くりかえすがそれがわからないからギルベルトの逡巡にいらだち納得がいかないひとが出るのであろう。)
なぜなら扉越しに、ヴァイオレットの声と何を伝えたいかは、そのときにほぼすべて伝わっているからである。その前のホッジンズの訪問からだけでも十分だったろう。
これによりギルベルトは彼女が逢いに来た理由の確定的な答え合わせとなった。よっていままでは不確定であったとは云える。云えるだけで実際にはギルベルトはすでに充分知っていただろうが――。
考える時間は丸一日あった。その上でそれでも拒絶したのである。それほどまでに逢ってはいけない理由とはなにか?
罪悪感だけでは足りない。というよりもそれより遥かに大きな理由があるではないか。おわかりであろう。
彼女と愛し合うという禁忌である。
戦争に駆り出し腕を失わせたという罪悪感などではない。
それは〈過去〉の罪であり罪悪感である。
ギルベルトはこれから犯そうとする罪をおそれているのである。
〈未来〉の罪を――。
すでに犯した罪に対する罪悪感ではなくこれから犯すことになるより深い罪――。
ヴァイオレットから愛されること、彼女を愛することはひとりの幼い少女を殺人機械として使い、最後にはその人殺しさえできない身体の欠損をもたらしたことより人倫に悖る所業となる大罪であり、二度とくりかえしてはならないことである。つまり愛することだけで十分余りある罪ということだ。
このポイントを見過ごしてしまえばヴァイオレットを退けるギルベルトの過去の罪への悔恨をも結局はなかったものとしてみていると云わざるを得ない。
これから犯す罪を見逃し、彼の後悔、悔悟をなかったものとしてみる視点からは当然「さっさと逢え」という反応が出てくる。
ではそのようにギルベルトがヴァイオレットに逢った場合にどういう展開がありうるのか考えたことがあるだろうか?
そのギルベルトは過去の罪にすら囚われてはいないと云わざるを得ない。
これはダブルスタンダードだろう。その二枚舌の観客は過去の罪を認めているとうそぶきながら、逢うこと、愛し合うことも求める。いやあろうことかそんなウジウジしたやつはヴァイオレットにふさわしくないにまでいたるのだ。
もしギルベルトの倫理観と罪責感を本当に理解するのであればギルベルトはヴァイオレットと逢ってはいけない、もしくは逢えそうにないと考える以外にない。それしかないはずである。
ここではっきりとわかることだが、ギルベルトがヴァイオレットの「あいしてる」を知るのはやはり少なくとも手紙の最後の一文ではないことである。
ヴァイオレットと愛を交わすことが罪であり禁忌であるのは彼女の愛がわかっているからであろう。
当然のごとくギルベルトはヴァイオレットの生存を知ってからも彼女に逢おうとはしない。すぐそこまで来ても、その声を聞いても、何を伝えに来たのかを知っても一命をとりとめたそのときからみずからに科した戒律を守り通す。
いや、むしろそうして彼女の存在が近くなればなるほどより深くその思いを強くしたことだろう。
彼女の声を聞けば聞くほど「ああやっぱりか」ともっともおそれていたことが現実になってしまったとそれを過去に犯した罪への罰のように感じたことだろう。
彼にできることはこれから犯す罪となるヴァイオレットに背中を向け続けること、その声に打たれ抉られる劫罰に耐えることだけだ。
(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
さて、ギルベルトはヴァイオレットに逢うことは可能だろうか?
不可能である。
なぜならギルベルトが何があってもヴァイオレットに逢うつもりがないからである。
彼女の生死を知ろうとしないほどそれは徹底している。
そしてそれを私たち観客が共有することで決定的になる。
彼らは逢ってはならない。逢って良い理由がない。
もしギルベルトがヴァイオレットに逢おうとするのならばそれこそ彼は彼女にもっともふさわしくない人間である。
【結論】
ひとつ目の〈不可能性〉とはギルベルトは絶対にヴァイオレットとは逢ってはならないという論理的、倫理的な帰結である。
これは作品外の私たちが作中のギルベルトと共有してはじめて〈不可能性〉となる。
この〈不可能性〉の共有がなければ、登場人物はどんなでたらめな言動も、首尾一貫しない変節をくりかえすこともありになってしまう。
それでそのままなし崩し的に〈愛の成就〉がなされてもそんなものは〈奇蹟〉でもなんでもない。
これを安易に見過ごしてしまうとこの物語が崩壊する。
次節はふたつ目の〈不可能性〉を論じるための準備としよう。
(※おさらい。〈不可能性〉とは〈奇蹟〉の〈痕跡〉であり〈奇蹟〉へ至るために注視観察する本論の最重要項目、キーワードであった。)
第4節.狂気の愛とエロスの映画
前節ではギルベルトがヴァイオレットと逢えない(逢ってはいけない)ことを論じた。
それはひとつ目の〈奇蹟〉の〈痕跡〉である〈愛の成就〉を〈不可能〉にするものであった。
そしてそれが〈不可能性〉であるのはギルベルトのヴァイオレットにたいする罪の重さが〈過去〉に起因するもの以上に〈未来〉に犯すことになる罪――つまり彼女と愛し合うこと――がまさにそのことの方があまりに罪深く背徳的な禁忌であるからであった。
この結論が妥当であるのはあくまでもギルベルトがヴァイオレットをどこまでも愛してしまう場合である。もし愛していないならば、それを自制したり忘れ去ることが可能であるならば当然まったく別のお話になる。
離れ離れになってからはじめよう。まず、彼は彼女の生死を確認しようとするだろう。生きていたならば何がなんでも会いに行き心から謝罪しただろう。たとえヴァイオレットが自分をどう思っていたとしてもである。
どんな言葉も受け入れたことだろう。もしヴァイオレットに愛してると伝えられてもギルベルトが彼女を愛していなければまったく違ったかたちでそれを受け入れることができただろうし、その愛はひな鳥の刷り込みのようなものだと諭し終わらせることもできたはずだ。
もし死亡していたならばそのときはじめて真の意味で彼は懺悔して泣くだろう。(※つまり彼は最後まで実は本心から悔いていないのだ。だからこそ罪深いのである。これは後述する。重要な点であるので覚えておいてほしい。)
しかしそうではなかったのだ。ギルベルトは彼女をどこまでも愛していた。ずっと変わらずである。それは間違ったものだった。
間違った愛(それをエロスとして「第Ⅰ章.エロス篇」で論じた)から始まる物語――。
間違った愛から始まりその軌跡とともに歩み、間違った愛の終着に至る。
それが『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』なのである。
(※急いで付け加えたほうがいいのかもしれない。重要なのは間違った愛の終着とは何かである。そのルートでしかたどり着けないものにこの先で出会うことになる。)
本作はたとえ間違った愛から始まったのだとしても最後にはその誤りが正されたり消え去ったりする物語、ではない。
逆に徹底して最後に向かうまで背徳的なエロスが高まり続けていく物語なのだ。それを見過ごさないでほしい。
再び「第Ⅰ章.エロス篇」で引いた言葉を玩味しよう。
”エロティシズムとは、死に至るまで生を称えることである”
”まさにこの侵犯の運動においてこそ、唯一この運動においてだけ、存在の頂点はその全貌を明らかにするのである”
ジョルジュ・バタイユ、 酒井 健訳『エロティシズム』(ちくま学芸文庫、2004年、原著1957年、p.16、p.470)
ギルベルトの深淵に潜み蠢き這い出てくる情欲とヴァイオレットという妖花の香気と嬌態が、禁忌の交わりを果たそうと、一方が仕掛け一方はかみ殺し抑制することで綾なされる、エロスを通奏低音とした物語――。
物語という内容を入れられたエロスの形式は、時と媒体を変える言葉の律動、陰影に富む映像のリズムによってじわじわと確実にクライマックスへと昂ぶらせていく。
『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』はどこまでも美しい相貌のうちにこうしたファナティックでエロティックなパッションがみなぎり渦巻いている狂気の愛の映画なのだ。
(※これもまた一部から、ギルベルトのヴァイオレットへの愛は家族愛みたいなものだと思っている、思っていた、ゆえに~という感想を聞いて筆者はたいへん驚いたものである。家族愛ではこのような映画にはなりえないだろう。何がそういった見方につながるのかの基因はそれはそれで興味深いものではあるが……。)
間違った愛――。
そうであるならば――ギルベルトがヴァイオレットを愛しているとしても、その愛が叶ってはならないものであるというならば――ヴァイオレットに直接会って突き放せばよかったではないかと思うかもしれない。
しかしそれはできないのだ。
ギルベルトが情けない人間だからではない。罪深い人間だからだ。
これ以上罪を重ねることが不可能なほどに罪を犯しているからこそ上辺だけ取り繕ったり内心と真逆の虚偽を口にすることはできないのだ。
もしそれをすればそれは欺瞞の罪だろう。それはさらなるヴァイオレットへの侮辱だろう。
ギルベルトにできるのはただ自らの沈黙の拒絶によるヴァイオレットの悲しみを罰として受け入れるだけである。
思い出してほしい。あのときギルベルトは決して嘘を云っていない。むしろ本音を絞り出している。(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
「帰ってくれ」と二度くりかえし「今の君に私は必要ない」と断じる。
ここに嘘はない。
このギルベルトの本音は「私は君が必要だ」と云ってしまわないための代替表現だろう。
続けよう。
「それに……君がいると、私は思い出してしまう……。幼い君を戦場に駆り出したこと……君が……私の命令を聞いて……両腕を失って……。」
(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』pp.112-113)
そこでギルベルトの前で燃え盛る薪が過去の戦火に転じ、彼は血を流した幼いヴァイオレットが見つめる姿を幻視しているのだ。(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.113)
こう云いながら法悦しているのだ。
ギルベルトが抑え込もうとする燃えさかる情欲はヴァイオレットのエロスの表現であった〈水〉を泡立たせるほど激しく沸騰させている。
戦火に佇む幼き少女――。(以下画像を参照)


(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
何度この秘めやかなイメージを反芻しては罪悪感とともに恍惚に耽ったのか――。
何ということだろう。
これは確定的だ。
これこそがギルベルトが追い払えない罪の責め苦であると同時に求め手に入れたものであることの証しなのだ。
ギルベルトはこのあまりに倒錯した美しさとかわいらしさに囚われているのである。
この本音は実質、罪の告白、懺悔であると同時に「それが望みだったのだ」という欲望の披瀝でもあった。
そしてヴァイオレットはギルベルトのこの想いを何も理解していない。それがわからない。
そう、ヴァイオレットはここまでさんざん論じてきたギルベルトが彼女と逢えないという〈不可能性〉をまったく意に介すことなく彼を誘惑し続けるのである。
ここでふたつ目の〈奇蹟の痕跡〉である新たな〈不可能性〉が現れる。
ヴァイオレットの場合だ。
ギルベルトに加えて〈ヴァイオレットの愛の不可能性〉が顕在化したこのとき、〈不可能性〉は極まる。
ではこの究極の〈不可能な愛〉が何をもたらしたかを確認していくことにしよう。
第5節.崩壊する『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の構造/〈分身関係〉と〈予示と反復〉の〈逸脱〉
ヴァイオレットとギルベルトの〈愛の成就〉が〈奇蹟〉であった。
〈奇蹟〉は〈説明不可能〉である。
よってその無限小にまで近づくことしかできない。
それは〈不可能なもの〉を見つけて抉り出すことであり私たちの途上のことである。
ギルベルトの次に見るヴァイオレットの〈不可能性〉とは何だろうか?
本節では本論のハイライトともいえるそれを少々詳しく論じていこう。
・第ⅰ項.謎めいた予言から
ひとつ目の〈不可能性〉は、ギルベルトのヴァイオレットへの愛があまりに背徳的であるゆえに――観客とのインタラクションと協働して論理的、倫理的に許されず――成就不可能であるということであった。
ここで――ヴァイオレットとギルベルト扉一枚を隔てた最接近において――ヴァイオレットの声が時を超えた蠱惑となってギルベルトをくすぐり、彼のエロスの防波堤を決壊すれすれにまで追い込んで最高潮にまで高めていることを見逃してはならない。(以下画像を参照)


(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
もしこの再会の場面の意味の重みを等閑視した所見であれば本作は自堕落のそしりを免れないかもしれない。
だからここが見逃してはならないひとつ目の〈不可能性〉の極限、際なのだ。
そしてこのひとつ目の〈不可能性〉があるがゆえに新たに生まれた〈不可能性〉がヴァイオレットのエロスの〈説明不可能性〉なのである。
そう、〈奇蹟〉とともに〈奇蹟の痕跡〉もまたここで〈説明不可能〉な未曾有の領域に足を踏み入れるのだ。
※おわかりだと思うがここで〈説明不可能〉は〈奇蹟〉を示す場合とその〈痕跡〉を示す場合に共通して使われている。
両者は微妙に違うニュアンスを含んでいる。
そしてその差異と同じ言葉で表すことができているということこそ〈奇蹟〉そのものに迫ることができているという一縷のアリアドネの糸なのである。
つまり今後、〈奇蹟〉とその〈痕跡〉は近づいてゆく。(ここがポイント)
これを念頭に置いた上で本論のその筆致を注意深く見守りながら読み進めていってほしい。
逆に〈奇蹟〉、〈痕跡〉、〈不可能性〉、〈ブラックボックス〉などの言葉の概念の明確な識別、定義の区別を気にかける必要はない。そこはお気軽に。
〈説明不可能〉な〈奇蹟〉という〈ブラックボックス〉――。
それに迫るための〈奇蹟の痕跡〉であるヴァイオレットの〈ブラックボックス〉という問題がここで前景化するのである。
そう、〈ヴァイオレット〉が〈ブラックボックス〉なのである。
〈ヴァイオレット〉が〈ブラックボックス〉であるとはどういうことか?
それによって何がもたらされるか?
それを確かめる前に本項の題名にあるように予言めいたエピグラムをもって次項に譲ろう。
「最後に私たちはギルベルトとともに〈死〉に、ヴァイオレットを〈見失う〉。その死は〈堕罪〉か〈新生〉か?」
・第ⅱ項.テイラーの〈未来〉とユリスの〈死〉から離れて/「〈いま〉届く〈手紙〉」
〈愛の成就〉という〈奇蹟〉の消息を追うことが目的であった。
〈奇蹟の痕跡〉という〈不可能性〉のひとつ目をギルベルトの背徳的エロスに求めた。
そしていま追っているのはふたつ目の〈不可能性〉であった。
それをヴァイオレット、彼女自身の〈ブラックボックス〉に照準を定めた。
これを論じることで〈奇蹟〉に迫るために必要なふたつの〈不可能なもの〉を見定めたことになる。
そして最後になぜこのふたつの〈不可能なもの〉を〈可能なもの〉にすることができたのか――。
〈奇跡〉が起こったのか――。
そこに至ることができる。
では〈愛の成就〉という〈奇蹟〉の一歩手前、ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉がもたらす〈不可能性〉を探っていこう。
まず、ファーストステップの重要な下ごしらえからはじめよう。
それは「第Ⅱ章.残酷篇」で詳細にたどった〈分身構造〉と〈予示と反復〉構造の綻びと〈逸脱〉である。
ヴァイオレット≒テイラー≒リュカ及びギルベルト≒イザベラ≒ユリスの類似が〈分身構造〉でありその関係項であるキャラクターがときに〈予示〉となる属性や役割を物語のなかで〈反復〉するように担っているというものであった。
そしてギルベルト≒ユリスであることからユリスはギルベルトの生存の代償となる犠牲の羊として〈死〉ぬのであった。
このギルベルトの生存より後払いの供犠はヴァイオレットがユリスのもとから離れギルベルトを探しに行くことで捧げられたのであった。
これが前章までに論じられた「見立て」であった。
しかし『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』はここから、これまで論じた〈予示と反復〉構造と〈分身関係〉が綻び、〈逸脱〉する。
切断と断絶によってバラバラに散らばる断片――。
そしてそれらが衝突して新しい構造が織りなされていく――。
ここから未曾有の領域に突入する。
〈奇蹟〉の時空へ――。
まずは、〈予示と反復〉構造の綻びと〈逸脱〉を示す事例をあげていこう。
〈類似性〉ではない、〈反復〉しない、〈逸脱〉する〈予示〉だったものたち――。
同じものが反復しないことで1回限りの特異性として新たに現れる。
様々なバラエティがある。
もうひとつの予示ではない予示だったもの。
もうひとつの反復されない予示だったもの。
ズレて反復される予示だったもの。
あるいは同じ〈予示と反復〉が〈逸脱〉という視点に力点をおいて観ることで変化するものたち。
そこにあったもの。その意味が崩壊する。変わっていく――。
※つまり何らかの通常の〈予示〉や〈反復〉として読み取れるもの――象徴やメタファーという機能のこと――から〈逸脱〉するものの例をこれからいくつか提示するということである。
※※ここでいう〈逸脱〉とは本来想定される象徴やメタファーの指示の対象とは違うものを指し示しているということである。もちろんある程度のズレはメタファーの本来の機能においても含んでいるがここではその差異により強く焦点を当てる。
〈逸脱〉する予示1
【エカルテ島の頭をヴェールを覆った届かない手紙を頼んだ子供と抱きつく子供】
ギルベルトに戦争に行って帰ってこない父への手紙の代筆をお願いするエカルテ島の子供は――幼いヴァイオレットの〈反復〉であるが――ドールであるヴァイオレットと反転しているという点で〈逸脱〉している。
(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.57)
子供の代筆者となったギルベルトは――過去のヴァイオレットのドールへの成長を〈予示〉とするならば――最終的に手紙を受け取る側となる点でこれも〈逸脱〉している。
つまりキャラクターが〈過去〉―〈現在〉―〈未来〉それぞれで〈手紙〉との関わりと〈子供〉という属性の位置を替え往還することで様々に転変する。(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.58)
さらにその手紙が意図した相手に届かず偶然にもあるいは運命的にヴァイオレットの来訪を招くという意味で手紙の意図も〈逸脱〉した効果を持つ。
◆
島での「海への讃歌」の儀式のあとに「大好き」といってギルベルトに抱きつく子供は――ヴァイオレットとギルベルトの出逢いを〈反復〉しているが――明らかにニュアンスの差異が際立つ〈逸脱〉である。
これも過去のヴァイオレットのほうが〈予示〉となっている。
(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.91)
〈逸脱〉する予示2
【三度鳴く犬】
ギルベルトがいる学校にヴァイオレットとホッジンズが訪ねるシーン。
ホッジンズが木製の門をくぐったあと、遅いノックのように犬が三回鳴く――。
これを聞いた瞬間、筆者は本作が纏うこれまでの舞台の描写と雰囲気から新約聖書の〈ペトロの三度の否認〉を即座に連想した。
〈ペトロの否認〉とは云うまでもなくイエスが捕まったあとにイエスが事前に「今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度わたしを知らないと言います」(新共同訳聖書 新約聖書 マタイによる福音書 26章34節)と予告したようにペトロがイエスを三度「知らない」と応えたことである。
この犬の鳴き声はホッジンズが学校内を進んでいく際にも聞こえるため、学校で飼われている犬であろうと推測されるが、どこか違和を感じさせる。
犬といえばヴァイオレットのぬいぐるみが思い出さる。これが思考に反響するのであるが、生命なきものが「吠える」という不気味さとともに生命の吹き込みの〈予示〉も感じさせる。(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
これが〈予示と反復〉の〈逸脱〉であるのは鶏が犬に変えられているというところよりも「鳴く前」ではなくあらかじめ三度「鳴かせている」という点であろう。ここで三度の否認が成立しないことがわかる。
つまりペテロことギルベルトは一度目のホッジンズ、二度目のヴァイオレットの否認ではなく拒絶をへて、次のヴァイオレットの〈手紙〉によって覆るのである。
◆
そしてこれはいささか余談ではあるが、本作に新たに登場するキャラクターや舞台がユリスやリュカ、ジルベールなどフランス系の名称と読み方が採用されているのに対して、ユリスの弟はシオニズム(ユダヤの復興運動)の語源ともいえるシオン(フランス語読みならスィヨン)と名づけられている点も気になったところである。
これはギルベルト≒ユリスであり、ペテロが否認したその舞台がエルサレムのシオンの丘の大祭司の屋敷であることを考えれば――ギルベルト≒ペテロ≒ユリス――これらはユリスのシオンへの気持ちが素直に伝えられなかった経緯を表しさらにそれはギルベルトとディートフリートまで反響されうるだろう。
〈逸脱〉する予示3
【カマキリ】
ギルベルトのメタファーとして登場したカマキリのその後の消息を追うと、草むらにただ打ち捨てられているワンカットがあるだけである。
(以下画像を参照)
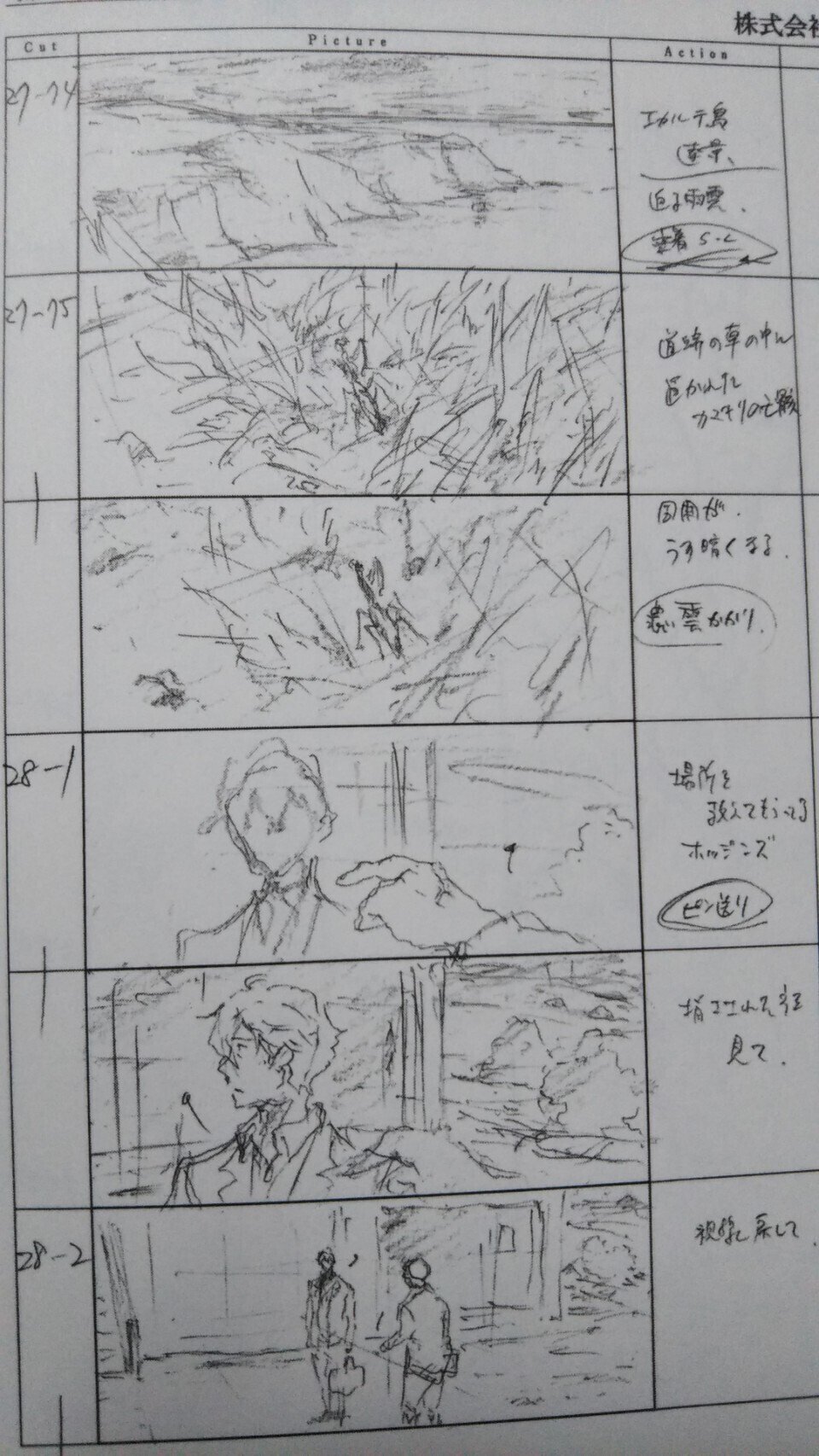
(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.99)
このわざわざ挿入されるカットの意味が何かを考えてみよう。
(※もちろんカマキリがギルベルトのメタファーなのであれば生きながら死んでいるいまのギルベルトの現状を表しているのは明らかである。)
このカマキリの〈予示と反復〉からの〈逸脱〉は埋葬されず死んでいるということにあるだろう。
オスのカマキリといえば交尾時にメスに食われて栄養となることで有名だが、ただ打ち捨てられるこのカマキリは生殖に資さない不能性を示すものといえる。
まずこれが本来性からの〈逸脱〉である。
※さらによりギルベルトの象徴のこの死骸についての言及を先取りしてここで記すと〈ギルベルトは死んでいるのだが復活する〉のである。
詳しくは後述するので確かめてもらいたい。
またこのカマキリの死骸はギルベルトが修道会の病院の庭で見た兵士の亡骸にも通じ、それが土壌を肥やす糧になる――ギルベルトとヴァイオレットの未来への道を作るという意味を示唆するものでもあるだろう。(※もちろんこれは新約聖書「ヨハネの福音書」第12章24節の「一粒の麦」のたとえである。)(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.102)
〈逸脱〉する予示4
【曇天と大地との切れ間から現れる陽の光、あるいは四元素】
この『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』という映画のもっとも美しいシーンは、ギルベルトに拒絶されたヴァイオレットが嵐の中を駆け出し転び、身を起こすも崩れるシーンだ。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
それは美を超越した荘厳さ、崇高をも顕現させている。
なによりそこではヴァイオレットを支える大地、全身を打擲する雨風、そして遠くの海と曇天との合間には神々しい陽の光芒という「火」「風(空気)」「水」「地」が一気に集中して渦巻いているのだ。
四元素といえば紀元前5世紀の古代ギリシャの自然哲学者エンペドクレスが提唱したことでよく知られる。
元素を結合させる「愛」の原理と分離を促す「憎」の反復による離散集合による事象の生成――。
このシーンにみなぎる緊迫感は世界の没落と次の世界の生成への〈賭け〉によるものなのだ。(※〈賭け〉という重要なキーワードが再び現れたが覚えておいでだろうか?)
ここでの〈予示と反復〉の〈逸脱〉とはこの悲壮の極みにあるシーンにおいて、いずれ訪れることを示す光という〈予示〉が〈反復〉を拒否するところにある。(ああ、とてつもなく崇高なエピファニー!)
〈逸脱〉する予示5
【嵐の後の朝】
雨粒に濡れ、朝日に輝く緑と夕日の前の一粒のぶどうのカットは前者が後のクライマックスの月の光の前哨であること、後者は逆に二粒(ヴァイオレットとギルベルト)を連想させる指標である。(※一粒のぶどうはもちろん前記の「一粒の麦」からの〈逸脱〉した〈類似〉である。)
(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.137)
〈逸脱〉予示6
【ヴァイオレットをめぐる兄から弟への言葉】
「今は麻袋に詰め込んで……お前をヴァイオレットの前に放り出したい気分だ……。」
(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.141)
すべてのはじまりであるヴァイオレットとギルベルトの出逢いがディートフリートによるものであったことの〈反復〉を示唆する発言。
もちろんこの一度目が〈予示〉となることはない。
(※ディートフリートのここでの前回との役割の差異には以下のようなものがある・一度目との対照性・助言と決別の言による促し・あるいはいかなる意味も持たない・そのいずれでもある。)
このように〈予示と反復〉構造の〈逸脱〉の時系列の事例はどれもエカルテ島で起こっていることがわかる。
◆
次に〈分身関係〉の綻びと〈逸脱〉は何をもたらすだろうか。
『外伝』のテイラー⇔イザベラの手紙の相互授受関係は、テイラーが〈未来〉でイザベラと逢うことを示唆する。
リュカ←ユリスはユリスの〈死〉を背景にした関係性の挿話であった。
ではふたつの〈分身関係〉から解き放たれたヴァイオレット→ギルベルトの消息は?
それが〈奇蹟〉であるならば――先の二組の彼女ら彼らと断絶した――別の、あるいは〈関係なく類似した関係性〉を開くことになるだろう。
それがテイラーとイザベラの〈未来〉で会うことでも、リュカとユリスの〈死〉を介した想いの伝達でもないヴァイオレットのギルベルトの〈いま〉における再会だ。
〈愛の成就〉という〈奇蹟〉は、「第Ⅱ章.残酷編」で論じた〈予示と反復〉の構造が揺らぎ〈分身関係〉がその紐帯を解かれることで準備されていたという前提をまず置いておきたい。
本節ではふたつ目の〈不可能性〉であるヴァイオレットの〈不可能性〉、〈ブラックボックス〉を論じる前の準備として本作を構成している〈予示と反復〉の構造と〈分身関係〉をほぐすことで新たな別の作用とパースペクティブを得ることを試みた。
それはひとつの映画、ひとつのテクストを賦活し〈多義性〉をもたらすものである。
新たに得たこの視点と力能を持っていよいよ本論の核心に迫っていこう。
第6節.ヴァイオレットの〈解体〉/〈懐胎〉/エロス/手紙/ブラックボックス/ふたつ目の〈不可能性〉
「第Ⅱ章.残酷篇」の再検討の次は「第Ⅰ章.エロス篇」である。
こちらを〈逸脱〉に対応する〈解体〉にさらすことによって、ヴァイオレットの〈説明不可能性〉、〈ブラックボックス〉が〈懐胎〉し浮き彫りになってくるのである。
ではヴァイオレットの〈解体〉/〈懐胎〉に触れていこう。
・第ⅰ項.ヴァイオレットのわからなさ
結論をあらかじめ云っておこう。
ヴァイオレットのギルベルトにたいしてのエロスを再検討することで、それがイノセントで盲目的で〈両義的〉/〈不確定〉な狂信性があらわになる。
その〈不確定性〉が〈ブラックボックス〉である。
そして〈ブラックボックス〉の〈両義性〉とは
「ヴァイオレットはギルベルトを理解していない/しようとしていない」
かつ
「ヴァイオレットはギルベルトを理解している/しようとしている」
である。
どちらかがわからないのだ。
この問題の焦点を定めておこう。
これはどちらもイノセントなエロスなのである。
前者のイノセントなエロス――「ヴァイオレットはギルベルトを理解していない/しようとしていない」――についてもう一歩踏み込んでみれば、ヴァイオレットはギルベルトがいかなる人間であるかどうかなど何の意味を成さないほどのそれ以前の熱情を持っているということだ。
反対に徹底してギルベルトを熟知しようとする後者の欲望もまたひとつのかたちのイノセントなエロス――「ヴァイオレットはギルベルトを理解している/しようとしている」――であるが、これは前者とは質的に違うものであることは間違いない。
よってここではヴァイオレットには具体的にギルベルトの背徳的なエロスを知らない場合のエロス、知っている場合の2種類のヴァイオレットのエロスのかたちがある。
ギルベルトがおそれた〈未来の罪〉である彼を決定的に〈堕罪〉させるエロスはどちらか?
ヴァイオレットが知らないのであればそれはより多くギルベルトに責があるといえる。
しかしもし彼女が知っていたのだったとしたら?
この点はヴァイオレットの内心をひとつの〈謎〉と〈秘密〉として読み解きたくなる誘引である。
これはギルベルトがヴァイオレットの自身への愛を知っていると断じたこととまったく対照的である。
ヴァイオレットとギルベルトのエロスの差異、非対称性を追究していきたい。
もしヴァイオレットがギルベルトのエロスを熟知していながらそれを知らないかのように振る舞い彼を誘惑しているのだとすれば――。
あるいはギルベルトの背徳のエロスを知ったことが彼女にとっていかなる意味ももたない些事なのだとすれば――。
彼女は彼の共犯者となることを欲しているという可能性が生じる――。
これが前前節、前節で予告されてきたヴァイオレットの(エロスの)〈不可能性〉である。
それは彼女の内心の〈両義性〉と〈決定不能性〉としてある。
これではどうあっても〈愛の成就〉はない。
「理解していない、知らない」の場合はギルベルトの背徳的なエロスの〈不可能性〉を強化するので〈愛の成就〉はない。(※何も知らない彼女と愛し合えるだろうか?)
しかし「理解している、知っている」も今度はヴァイオレットはある意味ではギルベルト以上の背徳性を背負うことになりより〈不可能〉である。
袋小路である。
しかし現実にこの映画ではふたりは愛を成就させたはずだ。
ここで〈奇蹟〉の〈説明不可能性〉は極まる。
アポリアに陥った可能性はいくつかある。
1つ、これまでの解釈に論理的瑕疵がある。
2つ、作品に論理的瑕疵がある。
3つ、この作品は〈堕罪〉の作品であるからどちらであっても問題はない。
4つ、このままこの袋小路を認める。そしてそこに解決の糸口を見つける。
もちろん本稿では4つ目をとる。しかしそれは実は3つ目も排除しない。
その可能性はある。
なぜならこの〈不確定性〉と〈両義性〉はどちらもが同時に成り立つことであるからだ。
そしてそれをヴァイオレットの〈ブラックボックス〉と〈不確定性〉が秘める〈可能性〉として捉える――。
この〈不確定性〉があるからこそ〈不可能な愛の成就〉を突破して別の〈愛の可能性〉が――〈奇蹟〉は起きたのではないか?
・第ⅱ項.あなたの知らないヴァイオレット
あらためて述べるまでもないことだがそもそもなぜヴァイオレットにこのような〈わからなさ〉があるのかといえば、端的に彼女のモノローグがないからでもある。ナレーションもない。もちろん多弁でもない。
本作で彼女はギルベルトへの〈手紙〉を何度か書くが――そしてそれを読み上げる声はあるが――それではいまポイントとしていることが確定できないのだ。
実際にはことさらこのヴァイオレットの内心を探らなくても、本作は疑問を抱くことなく観られるようにできているようである。
そもそもフィクションのキャラクターが「本当はなにを考えているか」と問うてもそもそも決定的な答えはないといえる。
しかしギルベルトがヴァイオレットの「あいしてる」をあらかじめ知っていたのかどうか、そして「ヴァイオレットはギルベルトを理解しているか、理解しようとしているか」というのは一度その問いを立ててみれば、その前とは一変して、その考え方のいかんによって作品の見え方が根本的に変わりうる重要な問題であろう。
実はヴァイオレットの内心がわからないのはこの作品にとって必然的であるといえる。
なぜなら本作は〈手紙〉の物語だからである。
〈手紙〉をとおして、「ひとの心がわかるというのは、実は人の心がわからないということをわかること」なのだ。
そしてヴァイオレットがだんだんと人の心をわかっていくということは、彼女の心が本当はわからないということに、私たちが気づかなければならないということだ。
ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉は私たちのヴァイオレットへの〈思い込み〉を逆照射する。そして打ち砕く――そのようなものとしてある。
第7節.彼岸にある映画
以降はヴァイオレットの〈ブラックボックス〉に入力するキーワードとそれから出力される内容を多角的に見ていこう。
今後の論旨を追うための参考に、ヴァイオレットという〈ブラックボックス〉に入力するキーワードと出力する中心的なキーワードをあらかじめいくつか列挙してみよう。
既出のもの――予告しておいたもの、ほのめかされていたもの――まったく新しいものがあるが、ここまででしっかりと準備は整えておいたつもりである。
ここではキーワードたちをちらっとでも目に触れておくだけでこの後に十分有用となろう。
これらである。
・ヴァイオレットの〈成長〉
・〈堕罪〉
・ヴァイオレットの〈解放〉
・〈手紙〉
・〈カオス〉
・ギルベルトの〈賭け〉
・ヴァイオレットの〈私秘性〉
・〈幽霊〉
・〈過去〉に届く〈手紙〉
・〈復活〉と〈新生〉
・ただの「あいしてる」
・〈狂気〉
・〈アガペー〉
・〈エクスタシーの神学〉
出力されたキーワードは次に入力のキーワードとして用いられもする。
すべての出力が終わったとき、「第5節.第ⅱ項.テイラーの〈未来〉とユリスの〈死〉から離れて/〈いま〉届く手紙」で「第Ⅱ章.残酷篇」の〈予示と反復〉の構造の〈逸脱〉から〈奇蹟〉に迫ったように、最後に「第Ⅰ章.エロス篇」が完全に解体されることで、ギルベルトとヴァイオレットのふたつの〈不可能性〉からどのようにして〈奇蹟〉が生じたのか、さらに〈奇蹟〉がもたらしたものがなんであったのかがわかるだろう。
さて具体的に見ていこう。
これからいくつかの重複する記述を行ったり来たりくりかえしながら螺旋を歩むように進んでいくことで、その言葉たちが描く軌跡は、いつしか〈奇蹟〉という〈ブラックボックス〉を透過する輝線となることだろう。
・第ⅰ項.私たちはヴァイオレットを見ていたのか?
【入力ワード:ヴァイオレットの〈成長〉】
本作においてヴァイオレットの〈成長〉が端的には、ユリスの危篤を知ってエカルテ島を離れようとした描写に如実にあらわされていると見なすのが普通なのかもしれない。
ではそうでないとしたら何を意味するだろうか?
ギルベルト≒ユリスの等式があれば明らかだろう。
※〈分身関係〉はもう解体されたのではなかったのか?と思われるかもしれないが、先に示した〈逸脱〉は〈多義性〉のパースペクティブでありそれらは――つまり〈分身関係〉とその〈逸脱〉の双方は――重ね合わされ同時に存在している。
これは重要なポイントである。
それは茫然自失となったヴァイオレットが生存と居場所を確認し自分を拒絶したギルベルトから死の淵にあるもうひとりのギルベルトであるユリスへ――。
つまり彼女は過去の戦争で経験した別れをやり直そうとする衝迫に導かれたのである。
そしてもうひとつ。
嵐の後の郵便社への帰途もまたギルベルト陥落への長期的戦略――。
(※『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデSTORYBOARD』には「嘘はついていない」とある……。天性の魔性というのは手垢のついた表現となるが……。)
この視点から見るときヴァイオレットはユリスの死の罪(※思い出そう、ユリスはギルベルトの生存と引き換えに死ぬのである)と責任を、そうでなくとも約束を違えた少なからずのやましさ抱えてしかるべきであろう。
しかしそれを歯牙にもかけないイノセントで残酷なエロス――。
それがヴァイオレットのエロスであった。
だがそれだけなのだろうか?
ヴァイオレットの〈成長〉といわれているものには他にどういう意味がありうるのか?
それを彼女のエロスの〈変容〉――その〈可能性〉のなかに見てみたい。
それはいずれヴァイオレットの〈解放〉も意味することになる――。
ヴァイオレットの〈解放〉は嵐が打ち据える大粒の雨とともにあらわれる。
それは〈水〉とともに表現された彼女のエロス――裸身の露出であり――まさに誘惑者としてのヴァイオレットの媚態である。
その裸体のエロスによってヴァイオレットはギルベルトに迫り続けるのだ。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
その大粒の雨と彼女の〈涙〉によって彼女のエロスは――〈解放〉の萌芽という別の意味を帯びる。
ひとの心がわかるという内心が獲得されていくとともにその内心が不透明になり、やがて〈ブラックボックス〉となる。
そしてもしヴァイオレットがひとの心がわかっていったとすれば当然なによりもギルベルトの心がわかっていったということになる。
つまり背徳的なエロスを――。
そうであるにもかかわらずますます愛していくのだとすればヴァイオレットのエロスのイノセントの意味が変わる――。
盲点だった。驚きである。
〈過去〉と、出会ったころと〈いま〉ではひとの心がわかった分、当然愛の意味、彼女のエロスも変わるはずだからである。
同じままであると思っているのは観客である私たちが彼女を理解できていないことの証左である。
しかしその視点からエロスの〈変容〉がどう変わったのかは依然〈ブラックボックス〉である。(※当然まったく変わってないという可能性を排除するものではない。)
ただこうはいえるのではないか。
「わたしたちは彼女を理解できないしそれをおそれている」
もしかしてここで――ヴァイオレットは私たちが知らないだけで――実は一方的にギルベルトと共犯となって〈堕罪〉しているのではないか?
しかしそれは私たちの思考をあまりに置き去りにしてしまっている。
ヴァイオレットという女性を見失ってしまっている。
私たちが見失ってしまった以上もう〈堕罪〉とは呼べない。
呼ぶものがいない。
ヴァイオレットは私たちの手から離れる――。
【出力ワード:ヴァイオレットの〈消失〉/〈堕罪〉?/〈解放〉】
・第ⅱ項.ふたりの亡霊、ヴァイオレットとギルベルト
【入力ワード:〈幽霊〉】
前項ではヴァイオレットの〈消失〉と〈堕罪〉が出力された。
本項ではいささか唐突かもしれないが、これまでもバックグラウンドで密やかに薄っすらとほのめかされていた〈幽霊性〉あるいは〈亡霊性〉を前景化してみたい。
ヴァイオレットのエロスは〈水〉とともにあるのであった。
では打たれる雨に比してみずからの船から海への飛び込みを〈自己洗礼〉という観点から見ることで別の意味を持ちうるのではないか?
つまりヴァイオレットのエロスの〈水〉は生まれ変わりの〈洗礼〉となるということである。
生まれ変わるということは一度死ななければならない。もしくは死んでいなければならない。
そう、ヴァイオレットは――いやなによりもギルベルトもまた死んでいるのである。
戦争によって――。
ヴァイオレット ≒ 幽霊 ≒ 亡骸 ≒ ドール
であり
ギルベルト ≒ 修道会の病院で見た兵士の亡骸 ≒ 幽霊
である。
では彼女たちを〈幽霊〉であると見なしてみよう。
いつからか?
彼女たちが離れ離れになり腕を失いベッドの上で目を覚ましたときからである。
ヴァイオレットは自室のランプの灯りに照らされ〈過去〉のギルベルトに魅入り――ギルベルトは炉の火に焦がされて戦時に戻る。
(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
彼女たちは死ぬ前の世界を思い出す――。
〈幽霊〉がこの世に未練を残すように――。
彼岸の太陽――死者の目を開かせる――が炉とランプに灯る光なのである。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
そしてそれは最後にヴァイオレットの〈自己洗礼〉とギルベルトの〈賭け〉によってやがて月の光へと変わるのであるが――。
やや先を急ぎすぎた。
〈幽霊〉であることによってなにがもたらされるか?
エロスの背徳性の無効化である。
なぜならあの世に漂うふたりはこの世の戒律に縛られないからである。
ここでもこの映画のなかには彼岸と此岸が重ね合わされ同居している。
その〈両義性〉と〈不確定性〉を見抜くことが肝要であることはこれまで何度も指摘してきたとおりである。
ヴァイオレットとギルベルトの出逢いから――別れと〈死〉から〈新生〉の物語へ――。
この観点からの『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』とは――ふたりは死んで離れ離れになり再会することで甦った――〈復活〉と〈新生〉の物語である――。
【出力ワード:〈復活〉と〈新生〉】
・第ⅲ項.屍人のエロス
【入力ワード:ギルベルトの〈解放〉】
「本節.第ⅰ項.私たちはヴァイオレットを見ていたのか?」でのヴァイオレットの〈解放〉とは――ギルベルトの〈堕罪〉をともにすることでの――私たちの彼女への思い込みの暴露にあった。
彼女は私たちの考えの及ばないところにある――。
ではヴァイオレットの目論見――ギルベルトの〈背徳〉のエロスをともにする〈堕罪〉――からそれる彼はありえないのか?
ギルベルトにとっての〈解放〉――私たちとヴァイオレットからの――があるとすればそれは何か?
それは罪からの〈解放〉にあるかもしれない。
それが可能であるとすれば――。
見てみよう。
ここまでではまだギルベルトとヴァイオレットのふたりの〈不可能性〉は背徳と〈堕罪〉にとどまるのであった。
※確認しておこう。
ギルベルトは――彼のエロスは〈背徳〉である。
これでいいだろう。
ヴァイオレットの場合は、
彼女の
「〈不確定性〉が〈ブラックボックス〉であり、
〈両義性〉とは
「ヴァイオレットはギルベルトを理解していない/しようとしていない」
かつ
「ヴァイオレットはギルベルトを理解している/しようとしている」
である。」
であり、
どちらにせよギルベルトとの共犯による〈堕罪〉という袋小路であった。
もしこのままであったとすれば、本作のふたりの再会という愛の抱擁の意味は――過去の戦争での罪責とユリスの犠牲という〈残酷〉だけでなく――これからの愛の生活という背徳によってヴァイオレットとともに決定的に〈堕罪〉するということになる。(※「そんなものを見たのではない」というほぼすべての方は本当にそうか、なぜそうでないのか確かめてみてほしい。)
この場合、ギルベルトはヴァイオレットの〈ブラックボックス〉とは関係を持たない。
具体的には、観客とともにあるままの――つまり私たちから逃れ去ってない――〈解放〉されていない――ヴァイオレットの「あいしてる」と同根の――ギルベルトの「あいしてる」も彼のエロスの思惑のまま変化していないということである。
これではまったくふたりは関係を結べていない。
すれ違っているというより同じ地平にそもそも両者が現れていない。互いが互いのなかでのみ存在する相手を求めているというだけのことである。
これはギルベルトの〈堕罪〉のエロスとヴァイオレットのイノセントなエロスの仮初の野合である。
ただ最後の抱擁と「あいしてる」は〈両義的〉で〈不確定〉な重ね合わせの複数の意味を併せ持つ。
よって先のエロスの野合の側面もまた確実にあるということである。
これがいままで背徳的エロスと呼称してきたエロスのひとつのあり方であり〈堕罪〉ということである。
ふたりの〈不可能な愛〉がこれで成就したといえるだろうか?
している。
というよりはこれしかないのである。
一方通行な仮初な愛こそが絶対的な〈不可能性〉の前でかろうじてありえる愛のかたちなのである。(※さてあなたの愛はどうだろうか?)
しかし私たちはすでに違う道筋も見出しつつある。一条でもないいくつかの――。
まずヴァイオレットの〈消失〉、〈解放〉の側面を確認しよう。
これは私たちが把握し得ない〈ブラックボックス〉としてのヴァイオレットがギルベルトの背徳的なエロスを熟知し、私たちと一緒にギルベルトも知らないところで包み込み、ともに〈堕罪〉するということであった。
これがもはや〈堕罪〉といえないのはヴァイオレットが私たちから〈解放〉されその罪悪を判定する物差しが無意味になるからであった。(※もちろんどこまでも彼女に追いすがることもできるだろうが――。)
次はギルベルトである。
彼が修道会の病院で目覚めたときに死していた――という〈幽霊〉であること――。
これを〈分身関係〉の〈逸脱〉だとすると――ギルベルトのユリスの病室での出現と憑依の意味は〈分身関係〉から〈幽霊性〉に席を譲ったということである。
※正確にはギルベルトのユリスに対する〈分身〉/〈幽霊〉の二重性の〈不確定性〉に彼を置くということである。
ユリスの〈幽霊性〉とはもちろん彼は死ぬものだからである。
これは『外伝』のイザベラ/エイミーという名と彼女の〈死〉/〈隠遁〉の存在の二重性による重ね合わせの〈不確定性〉と類比的である。
なぜなら――覚えておいでだと信じているが――ギルベルトはユリスだけでなくイザベラとも〈分身関係〉にあったのだった。
この〈変容〉の影響は甚大である。
これまで「第Ⅱ章.残酷篇」で導いたユリスの〈死〉の意味はひっくり返り灰燼に帰す。
ユリスの(背徳性はなくなり)死に意味はなくなる。
つまり彼は贖罪の羊ではなくなる――かわりに〈幽霊性〉を共有する。
よってギルベルトのエロスの背徳性はその分免じられるだろう。
しかしヴァイオレットに対するエロスの背徳性はそのままではないか?
それでいいのである。
このひと粒の変化が決定的に重要なのだ。
〈幽霊〉となった(つまりそう解釈されることによってこそはじめて)ギルベルトはヴァイオレットの〈ブラックボックス〉に向き合うことができるのである。
ただ彼女への罪が逆説的に彼を――私たちと同様に〈不確定〉であらかじめ〈想定不可能〉となった――彼女に再び出会わせるのである。
その〈可能性〉が開かれる――。
ギルベルトの〈復活〉と〈新生〉――。
【出力ワード:ギルベルトの〈復活〉と〈新生〉】
ここまででヴァイオレットとギルベルトの〈解放〉と〈新生〉が出力され出そろった。
ここで別の側面からアプローチするためにも一旦節を新しくはじめることにしよう。
第8節.おそれとおののき/ヴァイオレットの〈手紙〉の〈ミステリー〉
・第ⅰ項.ヴァイオレットを見失うということ
【入力ワード:ヴァイオレットの〈手紙〉】
これまで〈不可能〉な〈愛の成就〉――〈奇蹟〉への接近を、ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉から――彼女の密やかな〈堕罪〉の共犯、彼女のエロスの変容、ふたりの〈幽霊性〉――〈復活〉と〈新生〉として素描した。
ところで
〈幽霊〉は互いに出逢えるのだろうか?
〈幽霊性〉をこの物語に導入することは様々な〈可能性〉を新しくもたらしてくれる。
それはこういうものだ。
〈幽霊〉であることでギルベルトはユリスを犠牲とすることはなくなった。(最初から死んでいたのだ!そして現在にいたるまでずっと――。)
〈幽霊〉だからこそヴァイオレットはギルベルトを理解していない。
できない。
ヴァイオレットはギルベルトを感知していない。
〈幽霊〉であるのだから――。
そうあるとしてこれは問題だろうか?
いや、〈不可能な愛〉に他者を完全に理解すること――ひょっとしたら少しでも理解すること――は関係ないのである。
そもそもそんなことはそれこそ〈不可能〉なのだ。
逆である。
理解できないということ――他者の――相手の心がわからないことをわかること――。
それが重要なのだ。
ヴァイオレットの心の〈わからなさ〉――〈ブラックボックス〉をさらに考えてみよう。
ヴァイオレットは私たちが知らないことを知っている。
彼女が他者の心の理解とともに彼女自身の心を獲得している間に――その反対にぼーっとそれを見ていた私たちは――彼女を見失っていたのだ。
ここから今度はヴァイオレットと私たちの関係がひっくり返る――いや、はじめて関係が結ばれる。
「われわれはヴァイオレットを理解しているのか?なにを知っているのか?そもそも私たちは何を見ていたのか?理解したつもりになっていたのか?」
これらを彼女が何を考えているのかがわからないことでやっと気づく!
ここから遡及的に『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のすべては最後まで私たちのただの思い込みであったかもしれないことを突きつけて終わる。
推理小説のようには解けない〈謎〉を残して終わる。(※もちろん本論はここで終わらない。ひっくり返したものはもとに戻らないようにまたひっくり返すつもりである。どのようにかはこの先で――。)
そしてそもそも誰がこの〈謎〉を〈謎〉として眺めていたことだろう?
この〈謎〉こそが彼女の真の〈解放〉――ヴァイオレットにとっての〈新生〉――〈水〉=エロスと〈洗礼〉の〈不確定性〉である。
これは以前にも述べたとおりだ。
ではなにから〈解放〉されなくてはならなかったのか?
作品を編む幾重もの〈間接性〉――内心、心の声、〈ブラックボックス〉――ナレーションとモノローグの不在――義手で書かれる〈手紙〉――。
その〈手紙〉が伝えるものとは何か?なにが本心か?そもそも本心を伝えるものなのか?伝えたいことを伝えることは可能なのか?本当はなにを伝えるのか?
ここで〈手紙〉についてあらためて考え直そう。
この物語はなによりも〈手紙〉の話だったのだから――。
ヴァイオレットの〈手紙〉は何だったのか?何をもたらしたのか?
〈手紙〉そう、これが『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の、彼女の〈ブラックボックス〉が象徴していたものだ。
本作が〈手紙〉の物語なのだとすればそれは同時に〈ブラックボックス〉の話なのだ。
〈手紙〉=〈ブラックボックス〉
どれだけの人がそれに気づいているだろうか?
それも宜なるかな。
なぜならこれはヴァイオレットの観客からの分裂、独立、自律であり、彼女から疎外感すら感じるということであるからだ。
正しく現状認識ができているのであればこちらの安全安心が脅かされるということだからだ。
これが彼女のイノセントであると同時に盲目的で狂信的なギルベルトへのエロス――それに彼女が囚われているかのように感じる正体でもある。
だが、観客はここでギルベルトとともに彼女を愛する(知る)〈可能性〉が開かれる――まだ〈不確定〉な端緒に過ぎないが。
いや、待って欲しい!ギルベルトはヴァイオレットの自分への想いを知っている。だからこそ逢わないのだとさんざん云っていたではないか!
そう、それは知っている。しかし問題は「あいしてる」ではなく「あいしてる」とは何か?なのだ。
ヴァイオレットはギルベルトを「あいしてる」――なぜか?それはどういうことなのか?――それがまったくわからない。
この深淵のおそろしさ――「あいしてる」の〈ブラックボックス〉――にたじろいだのだ。
ギルベルトがおのれの〈背徳〉のエロスにおののいているうちはまだのどかだったのだ。
しかしヴァイオレットが実際に目の前に現れ、自身のエロスに何ら障害がないことを確信したとき、もうひとつの本源的な、エロスをたじろがせるがゆえに禁忌の侵犯としてよりエロスを亢進させる――ヴァイオレットの〈未知〉が現れたのだ。
そしてその〈未知〉は私たちの〈無知〉でもある――。
ヴァイオレットが何を考えているのかを理解できないことに気づくことで、つまりギルベルトとともに私たちは〈無知〉であることが露呈する。
しかしギルベルトは〈無知〉の前で――ここでこそ一人果敢に――彼女の前に立つのである。
そこではもはや彼の背徳的なエロスのその成立根拠は無効になるのだ。
それは直ちに彼のエロスが背徳的なものでなくなるということではない。そうではなく彼女に審問されるということだ。
彼女の〈ブラックボックス〉という真空のなかにサスペンドされるということ――。
〈不確定〉な彼女のなかの自分と向き合うということだ。
ヴァイオレットは何を考えているのか――何を望んでいるのか――彼女とは何なのか――まったくわからない彼女に自分のエロスを、自分自身を――査問にかけるということだ。
それで自分がどうなってしまうのか、これまでと変わってしまう恐怖――自分が壊されてしまうリスクを負って〈未来〉を迎えるということなのだ。
このギルベルトの〈賭け〉が〈不可能性〉が失効する〈奇蹟〉の場を開く。
ヴァイオレットの〈私秘性〉〈私秘的愛〉〈手紙の私秘性〉〈私秘的な手紙〉――。
これがギルベルトの〈不可能性〉を揺るがせ〈奇蹟〉を追い越すものである。
ヴァイオレットが私たちからもギルベルトからも遥か遠くに歩みを進めていた――いつからか、あるいははじめからそこにいた――からこそ、彼はその遠点に旅立ち飛翔することが可能になった(そういう物語であるのかもしれないのである)。
【出力ワード:ギルベルトの〈賭け〉】
・第ⅱ項.私たちは知り得ないということ、そのこと
【入力ワード:ヴァイオレットの〈私秘性〉】
ヴァイオレットの〈私秘性〉――〈手紙〉これが〈ブラックボックス〉であった。
そしてこの〈私秘性〉こそがギルベルトの背徳的なエロスとヴァイオレットの〈未知〉という〈不可能性〉から彼を引き離し〈奇蹟〉を、〈愛の成就〉を可能とする〈賭け〉に向かわせたのだった。
〈私秘性〉は重要な概念である。
しつこいようだがどういうことであったか繰り返そう。
ヴァイオレットの〈私秘性〉をこれまでいくらか触れた〈両義性〉、〈不確定性〉とすり合わせていこう。
それはまったくの無規定であるかもしれない。どこにも何も決まっていないかもしれない。
たとえばこういうことだ。
ヴァイオレットはギルベルトを最後まで理解しようとしない。
していないというならば「少しはわかる」とは何だったのか?
つまり彼女がわかるということをそもそも私たちがわかっていたのか?
そんなことがそもそも〈可能〉なのか?
私たちはメタ的に、彼女にもひとの心がわかるようになったと思っていた――しかし、彼女の心がわからないことで決してそれがわかっていないことに気づかされる。
彼女は興味なさげに無言で(いやそもそも私たちは彼女といかなる意味でも関係していない、ゆえにこちらが勝手に追いすがって夢想しているのであるが)「あなたは私を理解しているの?」と思い知らせてくる(いまやそうなった)。
彼女が興味あるのは最初からギルベルトだけだ。
そして私たちはそこで彼女を見失う。
ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉という〈不確定性〉――。
そういうことだった。
これがひとつのヴァイオレットの〈私秘性〉である。
あるいはヴァイオレットはギルベルトのエロスを理解していたのかもしれないという〈不確定性〉もあるだろう。
「少佐、私はあなたのあい(エロス)を知っています」
慄然とするセリフであろう。
そんなはずがない?
彼女がそれを知らないと、云うはずがないとなぜ私たちは知っているのだろう?
これもヴァイオレットの〈私秘性〉である。
あるいはすべてがそこから生まれてくる〈カオス〉といってもよい。
ヴァイオレットの〈私秘性〉を前にしたギルベルト、〈カオス〉に触れた彼に何がもたらされたのかだろうか?
ヴァイオレットの〈手紙〉が意味をなすのはここである。
決してそこではじめてギルベルトへ「あいしてる」を伝えたのでも、ギルベルトにとって既知のそれをくりかえしたのでもない(重要なのでくりかえそう)。
それでは本作に、彼に、何の転機ももたらしはしない。
ヴァイオレットの〈手紙〉が伝えたのは彼女の〈私秘性〉であり〈カオス〉であり擾乱である。
その〈両義性〉、〈決定不可能性〉である。
この以前以後において――ギルベルトは罪の意識に苛まれたエロスを拒む、拒まないという位相にある主体ではなく――新たな選択、決断、〈賭け〉を担う主体として生まれ変わったのである。
ヴァイオレットの〈手紙〉という入力から〈ブラックボックス〉が吐き出したものは
①自分を理解していない彼女をただ愛するという決断であり、
②自分のエロスを知っている彼女を受け入れるという〈不確定性〉であり、あるいは
③まったく〈想定不可能〉な〈未知の他者〉としてのヴァイオレットへ再び、そしてはじめての、矛盾した「あいしてる」を伝えるという選択と決断の〈賭け〉であった。
では以上をもたらした〈手紙〉とはそもそも何か?何を伝え、何を伝えないのか?
ギルベルトの〈決断〉の誘引はその前史がある。まず
①伝聞、新聞記事、間接的なヴァイオレットの生存によってエロスは再びさらに大きく燃え上がらされ、
②ヴァイオレットの来訪による声、口頭によって己の中のヴァイオレットとの答え合わせがなされた。
そして
③〈手紙〉により再び〈謎〉にかけられる――〈未知〉に対する〈無知〉――。
「わたしは、少佐を愛しています」
最後の一文はヴァイオレットの本心が伝わったのではなく、〈謎〉としてギルベルトを惹きつけた――恐怖とともに――からこそ彼を動かした。
ただ動いたのである。
〈手紙〉は本心が書かれそれが伝わるものではない。
よって〈手紙〉には後史がある。
④ヴァイオレットとギルベルトの〈再会〉である。
あの長い長いのヴァイオレットの云いよどみ――口で直に伝えることと〈手紙〉との乖離。
ここにこそヴァイオレットが何を云いたかったのか――何を知っているのかが不分明であることが――これ以上なく露呈している。
〈手紙〉はそれがそもそも届かないこと――必ずしも目的の相手に届かないこと以外にも意図したことが誤読されること――何が書いてあるかわからない――という〈秘密〉を宿すミステリーであった。
〈手紙〉のミステリーにギルベルトは誘引されたのである。
ここではヴァイオレットとギルベルトの間だけでなく彼女たちと私たちの間でも決して解かれることのない〈謎〉が提示されているのだった。
本作『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』が最後に残すのは――ずっと彼女を見守りそのすべてを知り尽くしているかのように見ていた私たちから――それがそもそも最初から思い込みに過ぎず――逃れていくという彼女の〈解放〉と〈再生〉と〈新生〉の物語であったということである。
彼女のことは知り得ないということ――。
それがあるということを強烈に印象づけられる。
迫ってくる。
そしてこの〈謎〉が決して解かれえないのはヴァイオレットが私たちの手を離れてしまったからであった。
【出力ワード:ヴァイオレットの〈手紙〉の〈ミステリー〉】
さて、そろそろ終盤である。また節をあらためよう。
第9節.ヴァイオレットもギルベルトも知らないこと、私たちしか知らないこと
私たちはここまで、ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉から彼女の〈私秘性〉、〈手紙〉、〈カオス〉をへて、ギルベルトの決断としての〈賭け〉にいたり――それが両者の〈幽霊性〉からの〈復活〉と〈新生〉であるさまを概観してきた。
このような〈新生〉はヴァイオレトとギルベルトを見失いつつも捉えるという読解を試みることで私たちにもともにもたらされるものであることが〈奇蹟〉への予兆となるだろう。
ではここで再び〈予示と反復〉の構造と〈分身関係〉の綻びと〈逸脱〉の最後にして最重要な例を示そう。
それは本作『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』を縦糸の〈手紙〉とともに横糸として織りなす〈過去の追憶〉――〈回想〉である。
【入力ワード:最後の〈予示と反復〉としての〈過去の追憶〉】
作中の〈過去の追想〉を――数え方にもよるが――ディートフリートやエリカなど、あるいはヴァイオレットとギルベルトに帰属しないと考えられるものを除き――ヴァイオレットが6回、ギルベルトが4回ととりあえず数えることとしよう。
以下のようになる。
(頁数は前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』より)
【〈過去の回想〉】
〈ヴァイオレットの回想〉 全6回
・pp.14-15(ギルベルトとの出逢いの抱擁。抱きすくめられる。内面描写なし。)
・p.21(ライデン市長の「軍人として」の発言に反応する戦時の自分3カット。内面描写なし。)
・pp.22-23(ギルベルトにブローチを買い与えられる。内面描写なし。)
・pp.27-32(自室でランプの灯りの中で義手の整備からの回想。)
(以下の画像を参照)
(戦場でギルベルトが撃たれる。いまに一瞬戻る。再び回想が続きギルベルトを背負って逃げる。また一瞬戻る。回想のギルベルトの「心から愛してる」。自室に戻ってからギルベルトへの手紙を書く。内心の代わりに手紙の文言が読まれる。)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
・pp.116-118(スミレの花を見るギルベルトと蝶を見るヴァイオレット。本を読むヴァイオレット。戦場で兵士に飲まれるヴァイオレットをギルベルトの手が引く。内心描写なし。)
・p.155(ギルベルトとの月夜の再会。抱擁から過去の最初の抱擁の追想。)
〈ギルベルトの回想〉 全4回
・pp.102-103(修道会の病院のベッドで目覚める。兵士の亡骸をみる。)
・pp.105-107(最後の戦場――ヴァイオレットの落ちた腕――ギルベルトを見るヴァイオレットの顔。)
・p.113(扉を境にしてヴァイオレットの声を聞きながら4カット、火の粉の舞う中で血に濡れたヴァイオレット。)
・不分明に混じり合う回想pp.142~144(ディートフリートと対峙しつつ――ヴァイオレットとの出逢い。蝶を追うヴァイオレットを見るギルベルト。続いてヴァイオレットの手紙を読みながら――最初の抱擁――ヴァイオレットの手を引き抱きしめる。手紙の文面とともにふたりが経験した様々な追憶。最後にヴァイオレットとの別れ際で穏やかに微笑む。)
ここで注目するポイントは3点ある。
【①】
これらの回想自体が作品にたいして持つ意味である。
あらためて振り返ってみると例に挙げたものだけでもわかるように、まずこの多さに驚く。
それだけで本作において〈回想〉の持つ機能がいかに重要であるかがわかる。
本作『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は〈過去〉へと届く〈手紙〉の物語と云える。
また、ヴァイオレットとギルベルトの〈幽霊性〉の観点からすれば――〈過去〉に生きる亡霊たちの話であり――〈過去〉という亡霊に取り憑かれた者たちの〈復活〉と〈新生〉の物語なのであるが――それは決して〈過去〉が消え去ってしまうというようなことではない。
〈過去〉を再び生き直す、受け取り直す話である。
それをこれから確かめよう。
本作のふたりの〈回想〉は――モノローグもナレーションも付されない〈過去の再現〉として描かれるため――どちらのものか判然としないものがあるのだがそれゆえに――〈手紙〉と同じく〈不確定性〉にたゆたっており本作を読み解く上で最大のヒントになる。
本作はこの〈不確定な回想〉の多用により〈過去〉と〈現在〉を行き来しながら進行していく構造になっている。
最初はヴァイオレットの〈回想〉が4度続く。
そしてギルベルトが3度。
そのあとヴァイオレット、ギルベルト、最後にヴァイオレットとなる。(前述のようにとりあえずである。)
当たり前であるが彼女たちが再会するどころかギルベルトの生存が(ヴァイオレットに)確定される前にも〈回想〉は行われる。
つまり彼女たちは直接に再会する以前から〈回想〉というかたちで想い伝えていた。
しかし重要なことはそれは互いに一方通行なものであるということである。
一方通行な〈回想〉=〈手紙〉の一方通行的性格ということとなる。
ヴァイオレットもギルベルトも同じ出来事を明らかに違った解釈で〈現在〉から〈回想〉し当時の差異をより強化したかたちで再演している。
観客はそれを彼女たちとは異なる時空から、外側から覗き見ている。
【②】
〈過去〉の追想の重要な機能のふたつ目は観客だけが知る特殊な〈回想〉についてである。
最後のギルベルトの〈回想〉――ディートフリートとの対面とヴァイオレットからの〈手紙〉を読みながらの〈回想〉である。
まず兄との会話では幼いヴァイオレットが空を舞う蝶を眺めている姿を〈回想〉する。
これはその前のヴァイオレットの5回目の〈回想〉と同じ出来事であり対応している。
同じ出来事を互いが別の角度で〈回想〉している。(以下画像を参照。一枚目がギルベルトの、二枚目がヴァイオレットのものである。)
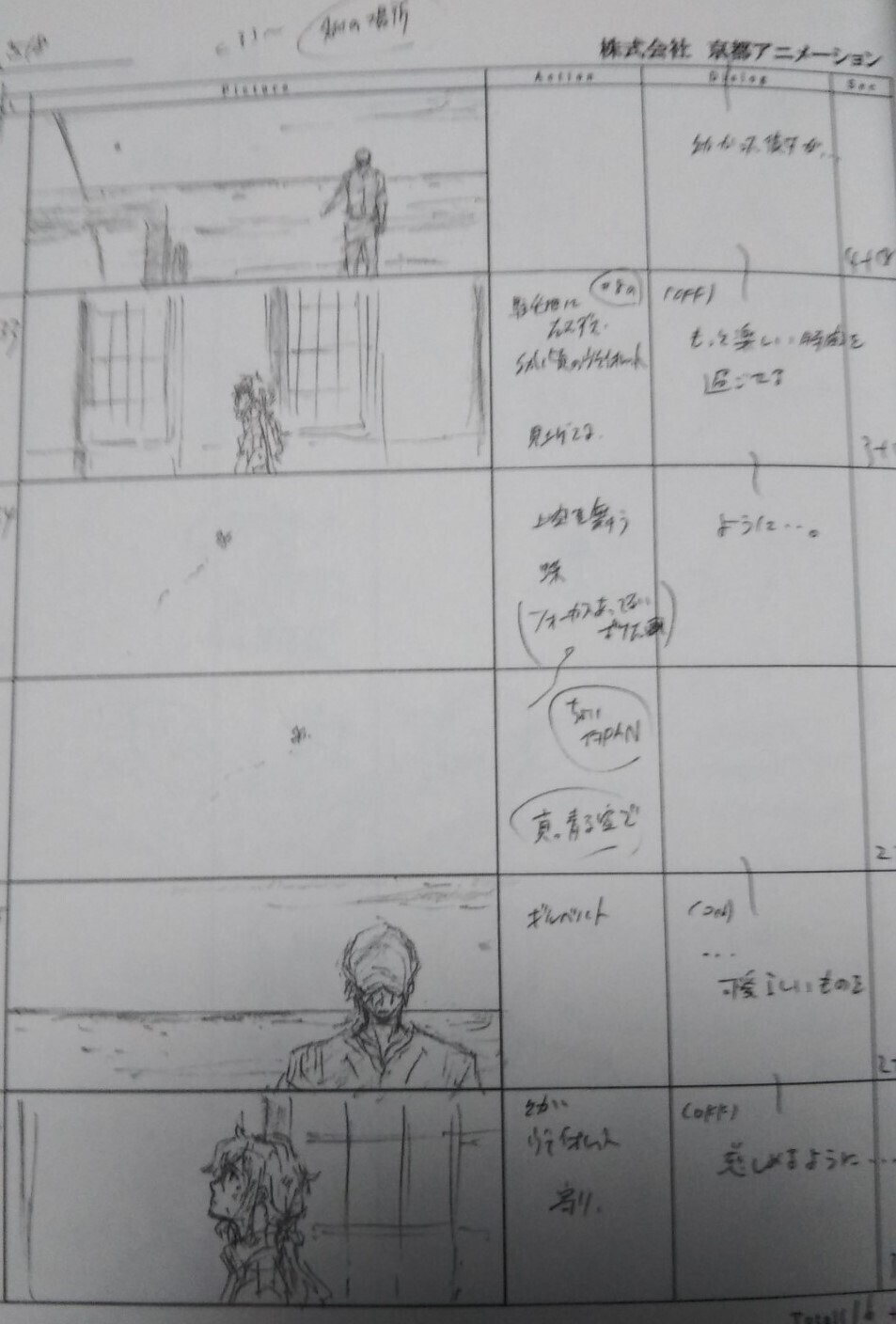
(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.142)
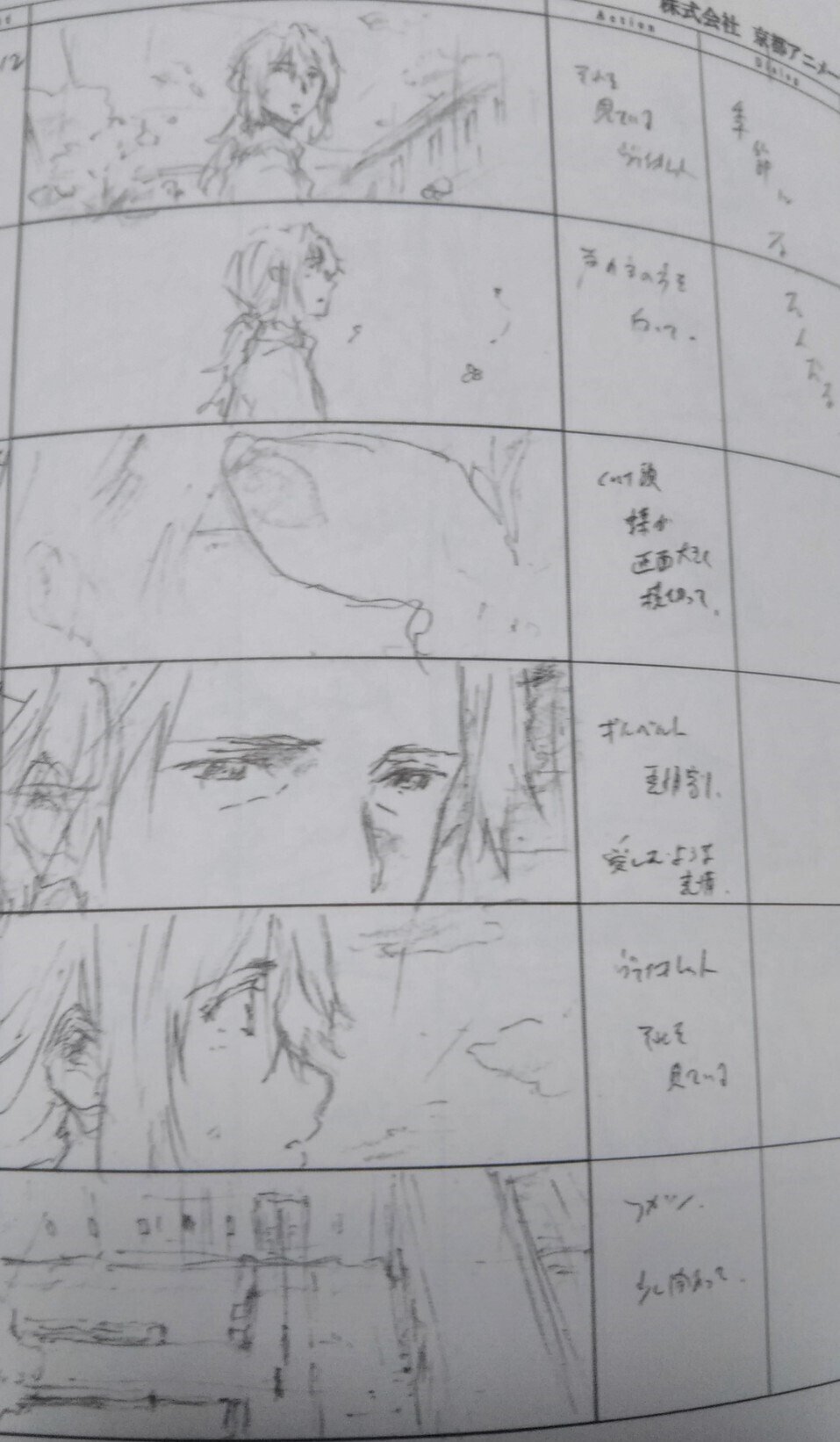
(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.116)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
ここでヴァイオレットの方はギルベルトが何を考えているのかがわからない(わからないというよりそれを知りたいと思うこと以前の段階かもしれない)といった意味合いで思い出されているように見えるが――ギルベルトはその悔恨の言葉で自身の背徳的なエロスを確認しているように見える。
次にディートフリートに促され、〈手紙〉を読みながらの〈回想〉であるが――最初はギルベルトから〈回想〉に入っていくのであるが――〈手紙〉の文面がその〈回想〉シーンに重ね合わされていくためそれがギルベルトのものであるかヴァイオレットのものであるのかが混ざり合ってわからなくなる――〈決定不能性〉――のである。
ここにギルベルトのヴァイオレットとの出逢いの抱擁のシーンの〈回想〉が含まれる。(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.143)
これはヴァイオレットが1回目と最後で〈回想〉するのと同一のシーンである。
(以下の画像を参照。一枚目が1回目の、二枚目が最後の回想となる。)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.15)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.155)
つまり映画のリニアな順番は
ヴァイオレット→ギルベルト→ヴァイオレット(月夜の海での――映画のクライマックスでの――二人の抱擁の直後に、最後の〈出逢い抱擁〉の〈回想〉が置かれていることに注意)
と、このように同一の出来事――出会いの抱擁――の〈回想〉がくりかえされている。(※最後の回想をふたりの〈回想〉あるいはギルベルトのものとるとそれぞれ別の解釈が可能となるがここではヴァイオレットのものとする。)
さて、ディートフリートを前にしたギルベルトの〈回想〉の続きである。
最後は戦場でギルベルトとヴァイオレットが別れるシーンになるのであるが、必死さと当惑を浮かべる幼いヴァイオレットの表情と対照的な穏やかに微笑むギルベルトの表情で終わる。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
このギルベルトの〈回想〉が重要なのは、彼の「あいしてる」を云った場面で――彼の声はなく――ヴァイオレットの〈手紙〉(ヴァイオレットの声で読んでいる)が重なっていることである。(以下の画像を参照.一枚目と二枚目は連続したカットである。二枚目の「あいしてる」はヴァイオレットの手紙の文面であることに注意。)


(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.144)
これは誰の視点の〈回想〉なのだろうか?
本当にあったことなのだろうか?
そうであるとしてギルベルトの微笑みは何を意味しているのであろうか?
このあとの文面は「……愛してる……を……ありがとうございました」が続き、現在のギルベルトはなんともいえない崩れた表情をすることになる。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
このギルベルトがヴァイオレットとの別離に残した微笑の〈回想〉の意味は〈多義的〉であり確定させるのが難しい。
スタンダードな見方は絶望的な状況でヴァイオレットに安心と最後の祝福を願いそれを彼女に伝えようとしたというものである。
問題はそれをここで〈回想〉する意味である。
実はこれと同じシーンをヴァイオレットが4度目に〈回想〉している。
一度目は別れのシーンでギルベルトの声で「あいしてる」を聞く。
そして同じシーンを続けて〈回想〉するのであるが、今度はギルベルトの「あいしてる」はない。
かわりにギルベルトの微笑みの後に発するのはヴァイオレトが書く〈手紙〉の彼女の読み上げである。
「……『あいしいてる』……。その言葉を与えて下さった……。だから、こうしてまた手紙を書いてしまうのです……。」
(以下の画像を参照。それぞれ一度目がギルベルトの声での「あいしてる」であり二度目はヴァイオレットの手紙の文面であることに注意。)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.31)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.32)
このギルベルトが「心から愛してる」を伝えるシーンで彼の――負傷した右目を隠すためか――表情は半分しか映されていない。
これも時系列は
【1】4度目のヴァイオレットの〈回想〉(①ギルベルトがヴァイオレットに「あいしてる」を伝える②ギルベルトの最後の微笑みのあとにヴァイオレットが手紙を書きつつ「あいしてる」を声に出す)→
【2】→ギルベルトの〈回想〉(ヴァイオレットと同じ状況を〈回想〉)→
【3】→ヴァイオレットの〈手紙〉(「あいしてるをありがとうございました」)となる。
【2】と【3】は連続しており、ギルベルトの〈回想〉に続いてのヴァイオレットの〈手紙〉の文面の声となる。
くりかえすが、ここではギルベルトが別れ際に口にした「あいしてる」をヴァイオレットの〈手紙〉の声が引き継いでいる。
このヴァイオレットとギルベルトの始まりの抱擁と別れの「あいしてる」がともにヴァイオレットの〈回想〉と〈手紙〉でサンドイッチされる構造は非常に印象的であるばかりではなく明確であることに驚かされる。
つまりこの何度もくりかえされる〈回想〉の〈抱擁〉と「あいしてる」が現実のふたりの再会の場面で出逢うことで新たな意味――出来事となるという構造である!
さて、少々先走りすぎた。一方通行なふたりの〈回想〉と〈手紙〉が〈過去〉へと届く〈手紙〉の物語となることに戻ろう。
つまりこのヴァイオレットとギルベルトの別れの際の彼が「愛してる」を伝えた〈過去〉に、現在のヴァイオレットの〈手紙〉が「愛してる」を返している――ということが注目されなければならないということである。
さらにそれだけでなくこの〈過去〉と〈手紙〉のつながりは両者の内面の〈回想〉を俯瞰して把握できる私たちだからこそひとつのつながりとして了解しうるということである。
これによってヴァイオレットとギルベルトは〈時間〉と〈個体性〉によって隔てられているということがむしろ強調されるといえる。
そしてもうひとつ重要な示唆がここにある。
「ヴァイオレットはギルベルトを理解していなのではないか/しようとしていない」というこれまで何度も前提にしてきたことである。
これが傍証以上のものとなるであろうか。
つまりギルベルトのなかで〈回想〉されるヴァイオレットは〈回想〉している〈現在〉からのコメンタリーとしての彼のセリフとともにある。(つまりヴァイオレット、ホッジンズ、ディートフリートの前で〈回想〉のなかのヴァイオレットを斟酌する言葉を口にしている。)
しかしヴァイオレットの〈回想〉のギルベルトにはヴァイオレットは云わないのか云えないのか、何も云っていない。あいかわらずモノローグも付されない。
ヴァイオレットはいまだドールとしての仕事を経験する前のように彼を〈回想〉する。
ヴァイオレットの最後の物語のこの映画において、一面ではヴァイオレットはひとの心がわかるようになったという成長を遂げた姿で描写されるにもかかわらずである。
彼女はギルベルトだけはあまりに特別であるからそれがわからないのだろうか?
あるいは〈現在〉ではなく〈過去〉のことだからわからないのだろうか?
あるいは彼にたいしてはそもそもそれはどうでもいいことなのだろうか?
それともやはり彼女は実はすべてを知っている、または知っているつもりではあるが私たちにはそれがわからないのだろうか?
ヴァイオレットとギルベルトのこの〈過去〉の別れの〈回想〉には決定的な違いがある。
まずヴァイオレットはおそらく実際にあったとおりに、彼の微笑みとともに「あいしてる」を〈回想〉する。
そして一旦現在時に戻り、続けて彼への〈手紙〉を書きながらその文面を読む自身の声のなかで――今度は二度目の何も云わない同じギルベルトの微笑みを想起する。
(以下おさらいである。)
それにたいしてギルベルトの〈回想〉では――ヴァイオレットの声で〈手紙〉を読むヴォイス・オーヴァーがギルベルトの〈回想〉に被る演出もあって誰の〈回想〉であるかが〈不確定〉になるが――少なくともここではギルベルトの声の「あいしてる」は聞かれないのである。
これによってヴァイオレットの〈手紙〉の最後の一文の機能と効果があらわになる(何度も述べたようにそれはここではじめてギルベルトがヴァイオレットの「あいしてる」を知るのではないのであった。それは彼にとって既知のことであった)。
つまりこれによってこのシーンでギルベルトは〈過去〉に自分が伝え――いまは失った――「あいしてる」を〈手紙〉によって返されることで呼び覚まされるということである。
なによりここで重要なのはギルベルトは〈回想〉――つまりそれをしている〈いま〉――では「あいしてる」を喪失しているということだ。
ギルベルトは〈過去〉には云えた「あいしてる」を〈現在〉では――最後にヴァイオレットに再会して直接伝えるまで――〈回想〉のなかで云わない自分を登場させることで――それを言う資格を失ったという自覚を表明しているのである。
これで彼がいかに自身に重い劫罰を科していたかがわかるだろう。
ギルベルトは右眼と右腕を失っただけでなく、なによりヴァイオレットへの「あいしてる」を失っていたのである。
このギルベルトの最後の〈回想〉から見いだされるものが観客だけが知る特殊な〈回想〉の意味である。
この彼の〈回想〉の意味とは――ギルベルトの〈回想〉のなかに、ヴァイオレットというまったくの他者として隔絶した存在の〈手紙〉が侵入することで時空を越えての対話が実現するという――私たちだけが知る〈真実〉があらわれたということである。
(※これはいま探求を進めている〈奇蹟〉とは別の観客のみが知り得るという意味でのスクリーンにおける〈奇跡〉である。)
またこの稀有な出来事を前にすると、彼女と彼の〈真実〉を私たちが知ることはいかにありえないことであるかがわかる(もちろんこの漏れ出た〈真実〉が絶対である確証はないしふたりのほうがより知っているという保証もない)。
今度はこれより前の同じヴァイオレットの二度くりかえされるギルベルトとの別れの場面の〈回想〉に戻ろう。
ヴァイオレットは一度目の〈回想〉では聞いた「あいしてる」を二度目は聞かない――失ったということもたいへん意味深長である。
(※これは聞かないというよりは手紙に「あいしてる」という言葉をタイプライターで打つ瞬間にギルベルトの「あいしてる」を思い出したということであるが、ヴァイオレットの「あいしてる」が先か、彼の〈回想〉が先かは〈両義的〉である。)
そしてこの〈回想〉からいま書いている現実の手紙の「あいしてる」の連想は――先述したように――ギルベルトとの再会において今度はギルベルトの〈回想〉へのヴァイオレットの〈手紙〉の侵入と結合としてくりかえされることになる。
ここで強調しておくべきことは「あいしてる」という言葉がヴァイオレットにとってどれほど重要な解くべき〈謎〉であったのかということである。
まるでそれだけしか見えていないかのように――。
こういってもそれほど的外れではないだろう。
「ヴァイオレットはギルベルト自身以上に『あいしてる』という言葉の意味に執着しているのではないか?」
よりプリミティブに掘り下げていえば
「『あいしてる』という言葉こそが主体となって彼女の執着、欲望、エロスを惹起し支配し彼女を突き動かしているのではないか?」
「『あいしてる』の意味を探るということは〈ひとを愛する〉こととどういう関係があるのだろうか?」
つまりヴァイオレットは――ギルベルトを「あいしてる」ということとそもそも「あいしてる」ということ自体が何か?ということの互いに別のもの――〈謎〉を混同し実際には別けられていないのではないか?ということである。
逆に言えばギルベルトはその〈謎〉――「あいしてる」を知らないヴァイオレットにそれ自体が何か?という問いと自分がヴァイオレットを「あいしてる」という宣誓を――同時に伝えてしまったということである。
「愛するとは何か?」については節をあらためてこの後すぐまた考えることになるだろう。
またすこし戻ろう。
観客である私たちのみが知り得る〈真実〉であるギルベルトの「あいしてる」の喪失が意味することについてである。
このギルベルトの〈回想〉とヴァイオレットの〈手紙〉の出逢いという思わぬ交叉――。
つまりギルベルトのなかのヴァイオレットがいる。
そしてヴァイオレットのなかのギルベルトがいる。
(どちらが先にその種を蒔いたのだろうか?)
このギルベルトのなかのヴァイオレット、ヴァイオレットのなかのギルベルトは互いを想う〈エロス〉的出逢いであると同時に一方的な思い込みの他者像であることとの区別がつかない。
区別がつかないことは同じであるということかどうか?
ただ云えることはこの点で明確にヴァイオレットとギルベルトはすれ違っておりズレがあり、ミゾが刻まれていることが示されているということである。
なぜなら、それが一方的な思い込みであるにしても「正しく」把握した他者であるにしても別のものでなければ出逢うことはありえないからである。
つまりここまでは「どのような出逢い方をしたのか」を見てきたということになる。
このズレとミゾには解消する方法などないということ。それがわかるということ。
この先がありうるのかどうか――。
これが最後まで残る課題となるだろう。
まとめよう。
とにかくここで強調しておきたいことは本作において〈過去〉と〈手紙〉の対話ならぬ対話という直接的な伝達ではなく何重にも間接的な対話という驚くべき達成を見せているということである。
これは恐るべき鮮やかさとさりげなさであり震撼する極北の技巧、魔術といってもいい。
これを〈奇跡〉と呼ばざるを得なかったことは先に見たとおりである。
ヴァイオレットの〈手紙〉での「あいしてる」はギルベルトにとってはあの失われた〈過去〉、〈いま〉と断絶した〈過去〉を再生させる。
それはおそるべき予感を告知するものであったはずである。
なぜなら対峙せねばならない「あいしてる」こそが、自身からそれを奪った当のものであるという循環となるからだ。
そしてもうくりかえすこともないことであるが、やはりここでも単純に「ギルベルトはヴァイオレットの手紙で『あいしてる』を伝えられたことでその思いを知り応えた」とはいえないことがわかる。
ギルベルトは〈手紙〉によってヴァイオレットの「あいしてる」を知ったのではない。
彼は〈過去〉で失った自分の「あいしてる」がヴァイオレットを介して〈回帰〉してきたことを知ったのである。
それが再生したからこそギルベルトはヴァイオレットに再び「あいしてる」を伝えることができたのである。
ただしこれは「あいしてる」をヴァイオレットに伝えるトリガーとはならない。あくまでもそれが可能となったということに過ぎない。
彼を突き動かしたのは前節で述べたヴァイオレットの「〈手紙〉のミステリー」におそれおののきつつも「誘引」されたからである。
ヴァイオレットという〈ブラックボックス〉におのれをさらす〈賭け〉を決断したからである。
つまりこの〈過去に届いた手紙〉はギルベルトのみがその作用域にいるのであり、あいかわらずヴァイオレットはそれを知らない。
本作は、〈手紙〉は届かないかもしれない――届いたとしてもその意図は伝わらないかもしれない――誤解されるかもしれないという――一般的に本シリーズのテーマとされる「手紙によって伝わる想い」とは別の側面を最後に潜ませることで遡及的に根本的に読み直すことを引き起こす。
だからこそ一面的ではない魅力があるのである。それは〈手紙〉を書く人であるヴァイオレットの〈ブラックボックス〉へのギルベルトと同じおそれとおののきへの〈エロス〉である。
本作ではヴァイオレットとギルベルトはあくまでも非対称的な想いで惹かれ合っているのであり、透明で筒抜けになった心情を共有しているわけではないという現実においてもごくあたりまえな関係性を――モノローグを排しながら――〈手紙〉や〈過去の追想〉という間接性を駆使して――実にエレガントな絶技で重層的に表現している。
そしてこれがギルベルトにヴァイオレットを追わせた原動力なのである。
ギルベルトは――〈過去〉での別れの言葉としてではない――〈いま〉ここで現実で、もう一度(幽霊となった後に)「あいしてる」をヴァイオレットに伝えに行くのである。
【③】
最後にギルベルトの〈抱擁〉について補足しておこう。
これはヴァイオレットの最初の〈回想〉と先に見たギルベルトの〈回想〉でヴァイオレットの〈手紙〉の文面がはじまるところ、そして最後にふたりが現実での〈抱擁〉のあとにおそらくヴァイオレットの〈回想〉として、計3回繰り返される。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
3回のほぼ同じカットがその意味を変えているというのは当然ではあるがこれもどう解釈をするか様々だろう。
ヴァイオレットが最初の出逢いの〈抱擁〉を最後にそのまま思い出すというのであれば――それはそのときは「あいしてる」を知らなかったのであるから――知らないときも実はそれは「あいしていた」のだという理解を得たといえる。
あるいは排他的でなく両立するものであるが、逆に少しわかるようになった「あいしてる」がけっしてあらかじめ「わかる」ようなものではなかったということ――そのことが出逢いに回帰することによって表現されているのかもしれない。
またヴァイオレットがギルベルトの背に腕を回して抱きしめないのも〈過去〉の〈反復〉(思い出してほしい。長くなっているが本節の入力ワードは最後の〈予示と反復〉としての〈過去の追憶〉である。)であろう。
さらに云えばこれはヴァイオレットの本来の臆病さの表れかもしれない。
そして本当にヴァイオレットが求めていたものが、出逢ったときのあの刹那にだけありえた関係性とまだ名前が与えられる前の初発に萌え出たよろこびであったということだろう。
それは本人が最後まで知らないままであるかもしれないたぐいのものである。
なにも知らず怯えていた幼い自分を受け入れてくれ抱きしめてくれた優しい男性という甘いファンタスム――夢想――。
それを私たちはあらかじめ想像したことがあっただろうか?
あるいはシンプルに最後の出逢いの抱擁の〈回想〉で締めくくることで〈新生〉を端的に示しているともいえるだろう。
いかなる予断も廃することが必要なことであるとここまでいくたびか述べてきた。
彼女のドールとしての仕事が最後に私たちに実らせたものとは「ひとの心がわかるようになるということは、ひとの心がわからないということがわかる」ということである。
それが私たちにはうかがいしれないヴァイオレットの〈私秘性〉であり〈手紙〉の本質であった。
最後の彼女の過去の追想のギルベルトとの出逢いは――そうした安易な私たちの共感を阻む彼女だけの特異な欲望が垣間見られたということであり――どれだけ私たちが異論を唱えようとその私たちからの〈解放〉である。
彼女にとって、この〈過去〉の郷愁こそがなによりも特別だったのであり――この瞬間から自ら海に飛び込み〈洗礼〉を施した彼女の止まっていた時間が再び動き出すのである(もちろんそうであり得るということであるが)。
「ずっとこうしたかった」から最後の再会の〈抱擁〉のカットをヴァイオレットのものではなく「ギルベルトが想像するヴァイオレット」が想い描いたものであるともいえる。
またより入り組んだものであるが逆に「ヴァイオレットが想像したギルベルトが想起しているもの」としてヴァイオレットが自分と重ねたとも考えられる。
相手のなかの自分、自分のなかの相手、自分のなかの相手のなかの自分と相手のなかの自分のなかの相手――このいたちごっこの恋人たちの戯れもまたいかめしくいうと〈不確定性〉であり、ここでそのなかの主体は融解して輪郭を失い、観察者――私たち――は彼女たちを見失ってしまう――。
つまりもはやここまでくると何重にも入れ子構造になり決定できない。
単一の〈ブラックボックス〉ではなく複合的な〈ブラックボックス〉である。
そしてここから〈奇蹟〉の〈不可能性〉を追い越す試みがはじまる。
ヴァイオレットの内心と〈手紙の私秘性〉にさらされたギルベルトのおそれとおののきのなかで身を開く決断が――〈賭け〉が――背徳のエロスの〈愛の成就〉の〈不可能性〉に亀裂を入れることになるかもしれない。
よってもしそうであったのだとすれば、私たち観客が追えないどこかで――歪んだ合わせ鏡に映る無限の鏡像――たちがどこかで――彼女たちの〈わかりあえなさ〉が消失する瞬間もあるかもしれない。
そう考えることではじめてヴァイオレットがギルベルトを理解しようとしていたこと、理解していたことが語れる〈可能性〉もまた開かれるかもしれないのである。
であるとしてもそれがいかなる価値と意味を持つものなのか――ヴァイオレットとギルベルトの私たちからの〈解放〉の後では――背徳もイノセンスも私たちのパースペクティブから消えてしまった以上、いまのままではもはや私たちに何もはわからず、何もいえないはずである――。
【出力ワード:〈回帰〉するギルベルトの「あいしてる」と無限の解釈可能性】
第10節.もうひとつの、ユリスの〈死〉の意味
【入力ワード:様々な〈不確定性〉】
ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉(〈私秘性〉、〈手紙〉)という〈不確定性〉がギルベルトに〈謎〉をかけ、〈賭け〉というもうひとつの〈不確定性〉を導く決断をもたらしたのであった。
〈ふたりの不確定性〉が〈奇蹟〉の〈説明不可能性〉を照らす鍵であった。
〈ふたりの不確定性〉の結果としての〈奇蹟〉に随伴するものを補足しておこう。
ヴァイオレットが私たちから離れていったようにギルベルトもまた彼女のもとに必死に駆けることで私たちから遠のく。
そう読まねばならない。(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
ヴァイオレットとギルベルトは〈夜〉に向かって駆け寄るのだ。
この出来事をこれまで〈愛の成就〉という名で呼んできた。
しかしそれはあくまでも仮の名であるしその実相を私たちは知らない。したり顔でわかった気になってはならない。
仮にそこで何かに感動し涙が流れたのだとしてもその心の震えはスクリーン上の出来事とはどこまでも答え合わせなどできない。だからこそ意味を持ちうるとしたら――なにもわからない――そういうことだったはずだ。
ヴァイオレットが何を考え知っているか、心のかたちも動きもわからない。
ギルベルトがいかなる決断をしたのかも本当は観客はわからない。
だから月明かりの下の彼女たちは、本当は〈堕罪〉したのかもしれないのだ。
ギルベルトが幼いヴァイオレットにひとの命を奪わせ、その姿に身を焦がせた情欲――。
ヴァイオレットのギルベルトへのイノセントな慕情もまた血に染まったものであること――。
「ずっとこうしたかった」という彼らの〈愛の成就〉は人目をはばかられる行為であることなのかもしれないのだ。
しかしそれと同時に、〈不確定性〉のなかで、そうでないかもしれないものなのかもしれない。
あるいはそうであると同時にそうでないという両者が入り混じって見分けがたい〈可能性〉も開かれたのだった。
ヴァイオレットが〈自己洗礼〉として海に飛び込み、ギルベルトが〈不確定性〉に〈賭け〉て駆ける。
それが本当の意味での戦争からの生還――〈幽霊〉であったことからの〈復活〉――生まれ変わり、再始動、生き直し――〈新生〉であること。
もしそうであったなら、ここでユリスは犠牲としての役割ではなく本当の役目を果たす(前に見たのはユリスの死の犠牲としての役割の無化あった)。
彼が今際の際でヴァイオレットとギルベルトを慮った「……生きてたんだ……。よかった。」が――これもヴァイオレットやギルベルトと同じく――他者への決して同一化できない隔たりがあるからこそ手を差し伸べることのできるいたわりの言葉と想いとなる。
〈予示と反復〉の構造の機能不全と〈脱魔術化〉。
〈分身関係〉の魔法が解かれることでユリスの死の意味が犠牲の羊から〈新生〉する。
彼は犠牲となったのではなく――ギルベルトの〈分身〉でも〈予示〉でもなく――ヴァイオレットではなく――本当に逢いたかったリュカに声を届け――〈未知〉の存在のギルベルトの生を祝福したのだ(もちろんユリスはそのために生きたのでも死んだのでもない。ただ最後にふたりを慮ったという端的な事実である)。
この本作におけるユリスの〈死〉の意味の変化は――決してユリスとその他の〈予示と反復〉の構造と〈分身関係〉が――そしてヴァイオレットとギルベルトの〈エロス〉の分析と〈幽霊性〉が――はじめから無意味であったということではない。
〈幽霊化〉によるユリスの死の〈脱犠牲化〉は先の思考空間の構築が無用であることを意味しない。むしろそれがなかったならばそもそも〈存在するという事態〉そのものが存在し得なかったものだ(つまりこの映画とまではいわないが本論の解釈における本作の存在そのものが存在する地平を失うということである)。
ヴァイオレットもギルベルトもユリスも「一度その経路をたどること」によって、〈犠牲〉でも〈堕罪〉でもないその他の存在の〈可能性〉が「もとよりあった」ことになる。
思考と感情と意識の時間は一方向にだけ進むわけではない。
〈復活〉するとき〈新生〉するときとは、それはあるひとつ別の時間で生きた経験から脱するときである。
その別の時間の〈可能性〉を開示するのが〈私秘性〉や〈賭け〉や〈手紙〉の持つ〈不確定性〉である。
逆にその〈可能性〉があけっぴろげにならなければ決して〈不可能性〉から逃れることはできない。
〈奇蹟〉は起きない。
【出力ワード:別の時間の別の〈生と存在〉の〈可能性〉】
第11節.狂気の「あいしてる」/「あいしてる」の狂気
本稿も終わりに近づいてきた。
本節では2つの問いを提示し、ふたつ目をまず答え、次節で本稿のまとめともいうべき問いに迫ろう。
【入力ワード:ギルベルトが〈賭け〉たもの】
ひとつ目の疑問い、〈謎〉は具体的で根本的なものだ。
ここまで〈愛の成就〉という〈不可能〉な〈奇蹟〉がどのようにして〈可能〉となるか、その条件を探ってきた。
それは絶対的なものではなく「別様であるかもしれない」という〈両義性〉、〈不確定性〉、〈カオス性〉においてあることにより開けてくるものであった。
しかしそもそも〈愛の成就〉とは何か?
ギルベルトの「あいしてる」とヴァイオレットの「あいしてる」のその〈あい〉とは別のものなのか?同じなのか?どちらかであるとしてそれらがどうなることが願われているのか?どう叶えられることが望ましいのか?望ましい〈愛〉とそうでないものとは何なのか?そんなものがあるのか?
そして「あいしてる」がわかることなどありうるのか?
ひとが「あいしてる」とひとに伝えるとき、それはそもそもどういうことだろう?
「あいしてる」はただ衝動的に、本能的に口にする言葉ではないはずだ。
このフレーズはとても短いがうっかり口をつくことはむしろ厳格に禁止されている類のものだ。そういう慎みを私たちは持っている。
私たちは「あいしてる」とは何かという問いのなかで、まだ未規定であるにもかかわらず、この言葉の厳密な使用のルールを薄っすらと気づいているのである。
それでもさまざまな「あいしてる」が、もしかしたらグレードのようなものがあるようにも思われる。
たとえば、なにか別の感情や思惑が自覚にいたることがないがゆえの代理としての短慮からの「あいしてる」、逆にその言葉の効果を熟知したつもりになり計算されたうえで発せられる「あいしてる」、あるいはその中間にあるよく考えられたものから勢いをつけるための「あいしてる」――。
その他いずれでもないも含めて「あいしてる」がそれにこめられた意図や外的理由をともなってあるだろう。
ここに挙げた例に共通していえることがあるとすれば「あいしてる」は他の言葉と違いがあり「何か他のものを伝える言葉」であるということだ。
そして筆者がここで主張することはこれらの「あいしてる」とギルベルトとヴァイオレットの「あいしてる」は根本的に別のものであるということだ。
「あいしてる」とは何か?を大仰な上滑りをする観念的問いとしてではなく、これまでたどってきた言葉たちにまかせてただ誘われてみよう。
そうすればこうなるだろう。
「あいしてる」がわかるとは自分が「あいしてる」という言葉を伝えたいということに尽きる。
そう、ヴィオレットは”ただ”ギルベルトに「あいしてる」と云いたかったのだ。
それ以上でも以下でもない。ただこれだけ。ひたすらシンプルだ。
その言葉で何かをあらかじめ期待するわけではない。その手前であることなのだ。
ヴァイオレットのイノセントなエロスもこの”ただ”「あいしてる」と云いたい――というとば口があって成熟されていったものだったのだ。
そこから生まれ落ちるものが何であるのかはわからない。
それもまた〈ブラックボックス〉なのであり〈カオス〉なのだ。
だから「あいしてる」は、こわい。おそろしい。
それは拒絶の〈可能性〉があるからではない。
それを口にするときそんな考えはどこにもない。
ないことが「あいしてる」ということだからだ。
何かを想定した「あいしてる」はもはやまったく別のものなのだ。
「あいしてる」がおそろしいのはそれを云う者でもそれを伝えられた者でもない。
その埒外にいるものにとってなのだ。
「あいしてる」は狂気だ。
狂気のなかにいるものはそれを知らない。
しかしその外にいるものはその狂気を思考してしまう。
自分ではない何者かになってしまうというおそれ――根源的恐怖。
それに怯え誤魔化すことが何かを期待する「あいしてる」なのだ。
あらかじめ比較考量しておくことで端的な「あいしてる」を封殺しておく。
それに慣らせておくことで〈カオス〉としての「あいしてる」に遭遇することを禁じておくのだ。
それこそがギルベルトのヴァイオレットの拒絶であったのではないか。
ギルベルトのヴァイオレットへの最初の「あいしてる」は狂気の〈カオス〉の「あいしてる」だった。
それはみずからが死を覚悟したとき、相手もが死に瀕するときにはじめて口を衝くかのように漏れ出たものだった。
だから「あいしてる」の二度目はありえないのだ。たとえ同じ文言だったとしても繰り返されることはありえない。
ギルベルトがヴァイオレットを拒絶するしかなかったのはこの「あいしてる」を繰り返さざるを得ないが、それはもはや自分を裏切るものになることを知っていたからだ。
最初の「あいしてる」を経験したギルベルトはだからそれを、おそれた。
永遠にそれを喪失してしまった。
ふたつ目の疑問はここからもたらされる。
ギルベルトの〈賭け〉という〈不確定性〉が〈愛の成就〉という〈不可能〉なもの――〈奇蹟〉への〈可能性〉を開いたと論じた。
ではギルベルトは具体的には何を〈賭け〉る決断をしたのか?
あの原初の、始原の、水端の「あいしてる」を、云えないことを、云うことだ。
ヴァイオレットに。
ありえないはずのもう一度の「あいしてる」を。
〈過去〉から、〈手紙〉から、時を経た彼女から〈回帰〉してきたあの言葉。(※その詳しい帰趨は第9節で述べた。)
〈幽霊〉の概念が犠牲としてユリスをギルベルトの生命の代替としない〈可能性〉を開いた。
(※この〈分身〉として供犠が行われた世界と新たに開かれた別の世界の両方を知っているのは彼らを見ている私たちだけだ。それは新たな世界が到来してもなくなることなくどこまでも確実に存在しつづける。この映画が存在しうるかぎり。それが私たちが観客であるということ。映画を観るということだ。)
ギルベルトの二度目の「あいしてる」が――ヴァイオレットから〈回帰〉した彼のあの原初の、ただそれを伝えたいというだけのそれだけの「あいしてる」なのだとすれば――彼の背徳的な〈エロス〉は二の句を継げなくなるだろう。絶句して刹那の後塵を拝することになるだろう。
その一瞬で十分だ。彼のエロスが背徳的でないのではない。背徳的であるにもかかわらずだ。
いかに年端の行かない子供を戦場で戦わせ、多くの命を奪わせ、あまつさえその子供の姿態に欲情することで育てたエロスであろうとも、いかに汚辱にまみれていようとも、二度と口にすることが不可能な「あいしてる」を云うことを押し止めるものはなにもない。
いかに空疎で、いかに言葉が〈過去〉の本物を裏切り、いかにそれがおそろしいことであろうとも――彼自身の「……ふさわしくない……。それでも……」という最後のためらいの残滓を引きずりながらも――ギルベルトは、云えないことを云ったのだ。
これがギルベルトの決断であり〈賭け〉られたものだ。
彼は自分を裏切ることを賭金にしたのだ。
なぜそんなことを?そう問いたくなるかもしれない。
原初の「あいしてる」――ただ「あいしてる」と伝えたいだけの〈愛〉――を云う者は、狂気のなかだと述べた。
だから背徳と汚辱の告白だったとしても、ギルベルトはそれを云うことができた。
ただしありえない二度目の狂気ははじめのものとは違う。
おそろしさに竦みながら足を踏み入れたものだけが陥ることのできるものだ。
くりかえすが二度目の狂気は、おそろしい。
もはや無垢な狂気の「あいしてる」を云う時間は過ぎ去ってしまった。
エロスを煮詰めたものを吐き出すという狂気の沙汰に自分自身が震えること――。
しかしそれはもしかしたらあの「あいしてる」を云ったあのときの狂気につながっているかもしれない〈狂気〉――そうであるのかもしれないのだ。
だからギルベルトの二度目の「あいしてる」がヴァイオレットにあれほど逡巡を与え、崩れ落ちそうにさせたことに、私たちは説明を与えるべきではない。
それはなにを云っても的を外すからではない。したいのであればいくらでもすればいい。
ただできるのだとすればそのときそこには、云う宛のない「あいしてる」が、みっつの狂気が、あるはずだ。
【出力ワード:ギルベルトに〈回帰〉してきたただの「あいしてる」】
それでは次節で持ち越しとなった本稿の〈奇蹟〉である「〈愛の成就〉とは何であるのか?」にいよいよ答えよう。
第12節.ヴァイオレットの凍りついた「あいしてる」
前節のひとつ目の問い、〈愛の成就〉とは、〈あい〉とは何かに答えきれていないだった。
まず前節を踏まえると狂気のなかの「あいしてる」がどれほどありえないような驚くべきことであろうともそれは何かを保証するものではまったくない。むしろそれは完全な無力そのものの謂ですらあるだろうということだ。
「あいしてる」を云うことと伝えることと〈愛の成就〉には位相を異にする無限の距離がある。
とりあえずそう仮定してみよう。
【入力ワード:狂気のなかの”ただ”の「あいしてる」】
ヴァイオレットはギルベルトに〈手紙〉で「あいしてる」を伝え、ギルベルトはヴァイオレットに一度失い〈回帰〉した「あいしてる」を云えた。
ではここで重要なことを断言しておこう。
『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』はそこで終わっているといっていい。
だからその後に彼女たちの〈愛の成就〉があったのか。それがどういうものなのかはわからない。
「そうではない」といえるとすればそれは〈愛の成就〉を何も知らないから、というよりもそれを知らないことを知らないからだろう。
もし本当に知っているのだとすればそれが描けないものであること、それは描かれないはずであることを知っているはずだ。
そして事実、それは描かれていないのだ。
「あいしてる」を伝えあったふたりがただそこにいるだけである。
(※あえて挙げるのも野暮であるが、ヴァイオレットとギルベルトの容姿が変わらないこと、年齢を重ねた姿として描かれないこと、その後舞台から姿を消すことから、それが観客に投げ出され委ねられている、あるいは同じことだがそこに断絶があることは明らかだ。)
だからここからは描かれていないこと、描くことが不可能なことを、ここにおいて、私たちがひとりひとりがその不可能性に、〈ブラックボックス〉という自分自身の実存と本質という引き裂かれた〈カオス〉として〈賭け〉てみることで描かなければならないのだ。
つまりこういうことだ。
ヴァイオレットのギルベルトへの「あいしてる」はあの原初の、ただそれだけの、なにひとつ期待を抱かない、狂気の「あいしてる」だったのか?
ギルベルトは本当に狂気のなかの「あいしてる」を取り戻したのか?いや、本当に一度目はあったのか?
この問いを自分の言葉で答えなければならないということだ。
本作が提示する「あいしてる」とは〈奇蹟〉の〈愛の成就〉を――描けないものを――描くという無責任を拒むこと、これである。(※これは最後にあらわれるので予告となるが無責任を拒まなければならないのは私たちであってヴァイオレットではない。「なぜヴァイオレット?」であるがこの意味は本論の結論として理解していただけるはずである。)
この映画に向かい合うこととは、描かれていないものを見ないこと、見たものを再検討すること、そしてそこに描かれていないことを廃した後、もう一度描かれていないことをそれを知っていながらもう一度見ることである。
そもそもなぜこんなことに言葉を費やすのか。フィクションは現実の模倣や延長や慰撫のためにだけあるわけではないからだ。
フィクションは現実においては無用の長物となる――その存在のあり方がきれいに収まる場所もあらかじめない――ものに出逢うことができる。
フィクションにおける恋愛やなんだに全身全霊をかけてうつつを抜かすこと――。
そこに現実にはいまだない何かや自明の現実の経験の受容の仕方をまったく廃することで可能になる――〈空虚〉がある。
その〈真空〉は気づかれない内に一瞬に埋め立てられてしまう。
それを見逃さないこと。
既存の経験、記憶、思念で糊塗してしまわないこと。
そのチャンスを逃さないことだ。
そこで、その先に出逢うものに思わず手を伸ばしてしまう、そんな領域へ誘われるということ。
それが〈エロス〉ということだ。
〈愛の成就〉とは何かを問うているのであった。
しかしそれはいま述べたように描かれてはいないのだ。
ヴァイオレットとギルベルトが――それぞれ混じり合うかどうかもわからない――そうなったとしてもそれがどういうことかもわからない――「あいしてる」を伝えあった――それが描かれてこの映画は終わる。
だからその先は私たちそれぞれに委ねられている。
なぜそんな当たり前のことをあらためて書き連ねなくてはならないのか?
エンドクレジットの直前のヴァイオレットの暗闇のなかの歩み。
そこにヴァイオレットからの?ヴァイオレットへの?「あいしてる」がある。
◆
※この◆から始まり今節の終わりまで続く「一人称の私」が語り手となる以降のテクストの性格については、やはり若干の前置きが必要だろう。
ヴァイオレットもギルベルトもほとんど登場しないいささかこれまでと毛色の違う文章がここに置かれた全体における意義とは、端的に〈狂気〉を本論に導入するためである。
この〈狂気〉が主題となるのは以下に記するように〈現実〉と〈フィクション〉――つまり本作『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』が〈現実〉にたいしてどのような具体的作用をもたらしうるかを引き出すためである。
よって〈狂気(のなか)〉とは〈現実〉と〈フィクション〉の不分明な領域――界面――インターフェイスのことである。
〈狂気〉をもたらすもの、〈狂気〉に導くものはここでは「あいしてる」ということになる。
その「あいしてる」がどのようなものであるか――それを云うものと云われるもの――〈現実〉と〈フィクション〉を越境する「あいしてる」をヴァイオレットとギルベルトから「一人称の私」にスライドさせる試み――これを〈狂気〉をアクセントとしてなかば無理矢理に――事故のように――〈未知のもの〉として到来させてみよう。
だれかがだれかに、ここからあちらに、あちらからわたしに、わたしからあのひとに――「あいしてる」と云うことがどれほどありえないような――〈奇蹟〉であるか。
そんな特別な「あいしてる」にあらためて――ゼロから率直に何もかも忘れてしまったかのように――驚いてみよう。出逢ってみよう。
よしんばそれが〈狂気〉であったとしても。
それがこれから先の「みちしるべ」になるはずだ。
ここからは一人称で書くことしかできないはずだ。
一人称の私はヴァイオレットへの「あいしてる」を云うことに戸惑わざるを得ない。
ではヴァイオレットからの「あいしてる」をどのように受け取るべきか?
いかなる意味においてもヴァイオレットは一人称の私に「あいしてる」を云わない。とすれば最後にこの映画はまったくのノンセンスを提示して終わったのか?(※ちなみにナンセンスでない理由は特にない。)
ある意味ではそうである。だから、「もしそうではないとしたら?」が生まれる。
まったくのノンセンスでないとはどういうことか?
この問いが誘いである。
〈エロス〉である。
一人称の私にとっての。
そして狂気への誘いでもある。
先に原初の「あいしてる」を云うものは狂気のなかにあると述べた。
それにたいしてこれは「あいしてる」を云われたものの〈狂気〉だ。
前節でこう述べられていた。
だからギルベルトの二度目の「あいしてる」がヴァイオレットにあれほど逡巡を与え、崩れ落ちそうにさせたことに、私たちは説明を与えるべきではない。
それはなにを云っても的を外すからではない。したいのであればいくらでもすればいい。
ただできるのだとすればそのときそこには、云う宛のない「あいしてる」が、みっつの狂気が、あるはずだ。
一人称の私はここで舌の根も乾かぬうちに狂気の禁忌を破ることになるのだろう。みっつ目の〈狂気〉として。
〈狂気〉のなかの一人称の私はそうであるがゆえにその発言がすべて信用のおけないものにならざるを得ない。
そう〈カオス〉だ。
ヴァイオレットの心の〈わからなさ〉として論述してきた〈ブラックボックス〉、〈不確定性〉だ。
一人称の私は――ギルベルトの「あいしてる」を云うものの〈賭け〉ではなく――「あいしてる」を云われたものの〈賭け〉を試行することになるだろう。
狂気のなかで一人称の私は――だから云ってしまおう。
この狂気が他の狂気につながっているのかどうか、そんな計算はもはやどうでもいい。
原初の「あいしてる」はあらかじめ想定するものなどなにもないのであった。
「あいしてる」を云われたものもどうやらそうであるらしい。
そうヴァイオレットもギルベルトも「あいしてる」を云うものであると同時に云われたものでもある。
なんということだろう。ありきたりな、あまりに凡庸な、本当にノンセンスな、彼女たちにたいしては、だから確実に云ってしまうことができる。
そうだ
ヴァイオレットはギルベルトを「あいしてる」――。
ギルベルトはヴァイオレットを「あいしてる」――。
そしてなんと!(これがとてつもない驚きであるのは狂気のなかにあるからか煙に巻く詭弁なのか〈不確定〉なただの事実(この矛盾した言葉!)であるということだ。驚きの事実!)
ヴァイオレットはギルベルトに「あいされている」――。
ギルベルトはヴァイオレットに「あいされている」――。
どうしてそういうことがありうるのだろうか?
これでは狂気の掛け合わせではないか!
このありふれた狂気――。
驚くほうが驚きであるような狂気――。
だからこそ狂気のなかにいることになるのだろう。
これはトートロジーだろうか?
とにかくただそういうことであるらしい。
たしかにこれは何も保証しない。期待しないと云うより何も期待しようがない。ただそれだけだからだ。
ここで終わるのは当たり前だ。この先は端的にないからだ。存在しないからだ。どこかに存在するものがいまここにないのではない。無というかたちでも存在しない。本当に何ものもない。なんにもない。
あるのは狂気だけだ。
狂気のあるうちだけだ。
「あいしてる」を云われ(云われたのか?)云うものがいない一人称の私はどうなるのだろうか?
しかしだからこそわかったことがある〈愛の成就〉はない。
それは否定的なものではない。なぜならその〈なさ〉のあまりの豊穣さ、こういってしまっていい、絶対的な真善美の横溢にあずかった興奮とよろこびと恍惚があるからだ。
その背後には〈なにもない〉。
ただなにもないだけがありうるということ。
そんなことがあってよいということ。
あるのだということ。
これが〈愛の成就〉とは何かの答えだ。「あいしてる」の意味だ。
わかってしまえばそう述べ続けていたことに気づく。
〈愛の成就〉という〈奇蹟〉は〈説明不可能〉だと。
つまりこの絶対的〈なさ〉で説明尽くされてしまう。
原初の”ただ”の「あいしてる」は何もあらかじめ期待しないというのはまさにそのままだ。
ここに新たに「あいしてる」を云われたものも同じように(本当に同じであるか、そして必ずそうなるわけではまったくないが)狂気のなかでその純然たる〈なにもなさ〉を行使できるのだ。その可能性が開かれうるのだ。
〈なにもなさ〉に多くを語らせること語ることは危険だ。それは言語化すること、抽象化すること、概念化することの拒否そのものだからだ。
〈なにもなさ〉は何も云ってくれないのだ。
無謀にも危険を承知でこの〈愛の成就〉と「あいしてる」の狂気という〈奇蹟〉の一瞬の実現である〈なにもなさ〉に魅了された一人称の私は――その触発された〈エロス〉において語ろう。
私たちは、いや、一人称の私は〈愛の成就〉という何かがあると思っていた。それをそれ以上の何かで表現できるような何かがあると。
それがこの現実と地続きなこの現実を構成している予断であることがわかった。すべては空論であり現実が夢物語の上に成り立っていることがわかった。
これがフィクションにだけ通用するような脆弱な取るに足らない思い過ごしであり身体感覚や生活実感を離れたただの愚にもつかない観念であるとどこかから断じられても――それは正しい。
それがその現実的な、日常的な評価なのだ。
現実で生きていく以上はそうであらざるを得ない。
〈なにもなさ〉の充溢を垣間見てわかることがあるとしたら、現実とはそんなただの〈なにもなさ〉を薄皮一枚隔てた側で延々と自動人形のようにただ持続することを自己目的として日々あり続けているのだ。
この先もいつまで続けるか続いていくのか――どこで終わるべきかどう終わるべきか――それを無限遠点までなんとなく放り出していることすら見ようとせずにただ「あいしてる」にあまりに多くの期待をかけてきたのだ。
考えないことで盲目になり、明後日の方向を考えることで誤魔化し続ける。
自分の人生には、愛には、自分の愛するひとには価値があるのだと。
〈なんにもない〉でたまるかと。そんなのはひねたニヒリズムだと。
しかしニヒリズムについてはほとんどのひとが勘違いしている。ニヒリズムとはすべてのものの価値を否定することではない。ニヒリズムとは否定すべき価値があると信じていることだ。価値を信じ汲々とすることがニヒリズムなのである。価値を称揚せずにはいられないという病こそニヒリズムなのである。だから現実でニヒリズム以外はほとんどありえない。
あるいはそんなの当たり前だと悟っていうかもしれない。
「あいしてる」なんて本当は大層に着飾っているだけのハリボテであることを覆い隠す虚妄のゲームでしょうと、それは言わないお約束といつでも投げ出す準備を整え、安全弁が頭にちらつくようではもう楽しめないよと、それだけのこととシニカルに構えることが常態化しているのが現実ではないか。
〈なにもなさ〉はシニシズムもニヒリズムともいかなる意味でも無縁だ。
現実の愛にそれ自体の価値を求めてやまないのはおのれの価値をでっち上げていること――血道を上げていることを誤魔化さざるを得ないからだ。「あいしての」の価値を前もって切り下げておくシニシズムも多寡と方向の差でしかなく同根だ。そしてそれを現実において逃れることはほぼ不可能だろう。
狂気とはその〈外〉にでることだ。
そこで云えるのは、なにか意味のあること――価値のあること、正しいこと、何かと比べること、後からそれを評価できること――以外のものが〈なにもなさ〉であるということ。
それがありうるのだということはそれだけでもう何もいらないということであるということだ。
これ以上のものはもう何もないということだ。
そうでないものすべては何かを欲して貧窮であるということであり、この〈なにもなさ〉だけがそれ以上のものはないということなのだ。
一人称の私は――そんな現実から何かの価値を捏造することしかできないこの現実の〈外〉にある――〈なにもなさ〉をこの映画の〈愛の成就〉という〈奇蹟〉においてただ気づかされる。
いかなる計算的思考や比較考量を免れている〈なにもなさ〉という狂気のなかの「あいしてる」は無価値だ。
何の価値もない。
だからその「あいしてる」は狂気だ。
そしてだからその狂気のなかで「あいしてる」は生まれる。
「あいしてる」を云うことはその出自の狂気のなかへと云われたものを引き入れる。
だから「あいしてる」を云われたものは狂気のなかにいる。
狂気のなかで「あいしてる」を云うものと云われたものは出逢う。
そこで出逢うものとはお互いにとって〈未知なもの〉なのだ。
〈なにもなさ〉の「あいしてる」とはこれまでのすべての経験と既知の情報を殺し死に至らしめ〈未知のもの〉に出逢う瞬間のことだ。
フィクションから現実に越境してきた「あいしてる」の狂気のなかでその〈なにもなさ〉に与ることは――現実の「あいしてる」が〈ないもなさ〉の充溢であるかもしれないことに――おそらく再び今度はギルベルトと同じように――二度目のおそろしさとともに向かい合うことを可能とさせるのだろう。
それがほとんどありえないことであろうと。
しかし現実は残酷だ。
現実の裂け目だけを見ることに倦み疲れることになるのだろう。
二度目どころかこれはあの〈なにもなさ〉の「あいしてる」だろうか?
と、日々の現実の生活のなかの愛を点検し続けることになることに辟易することになる。
それはこういうことだ。
始原にあった原初の「あいしてる」は現実の「あいしてる」を殺し尽くす。それは「あいしてる」が原初のものではなかったということを無限背進させる。
その原初の「あいしてる」の寿命はおそろしく短い。無垢であるがゆえに無力だ。
現実の「あいしてる」ではない〈なにもなさ〉の「あいしてる」を現実で認識すればその瞬間にそれは現実の「あいしてる」となり、それはそうでないとなり、そうでないものはまたそうでないとなる。
これがどこまでも続き終わらない。結局現実において〈なにもなさ〉の「あいしてる」は捕まえられない。
ここでもまた〈不確定性〉が顔を出す。
〈奇蹟〉を可能にしたのはヴァイオレットの〈ブラックボックス〉という〈不確定性〉とその〈謎〉――〈ミステリー〉に魅了されたギルベルトの〈賭け〉であった。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
なぜ〈不確定性〉か?
〈未知のもの〉に出逢うことがわかればそれは自明だろう。
常に〈不確定〉であるから〈未知〉でありうる。
〈不確定性〉に開かれなければ〈未知のもの〉にはなりえない。
〈未知のもの〉はそれが現れてしまえばすぐさま既知となってしまう。
だから既知を殺して現れた〈未知〉は常にすぐ死んでしまうか絶えず既知を殺すことでしか存在し得ない。
〈なにもなさ〉の横溢はだからこそそれ以上はもう〈なにもない〉のだ。
〈なにもなさ〉とは絶えざる生成と消滅だ。
それに現実的価値がないのは当然のことだろう。
そしてそれは感知することも意味を与えることもできないという絶対的な〈不可能性〉であるのだ。
しかしこの儚くも激烈な破壊作用そのものの〈なにもなさ〉は〈奇蹟〉の〈痕跡〉の〈不可能性〉のような〈痕跡〉を残すことができる。
それがこの『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』というフィクションが現実にもたらすもの――フィクションから現実に持ち帰るものだ。
それはひとつの経験からはじまる。
現実において何の意味もない〈なにもなさ〉の「あいしてる」――その徹底した無力を現実において思考したという経験――その唯一性だ。
言葉にすること概念化することで失われる〈なにもなさ〉――。
しかしその思考の経験という〈痕跡〉は残る。
その〈痕跡〉を証し立てるのが『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』という映画なのだ。
一人称の私はこういっていた。
いかなる意味においてもヴァイオレットは一人称の私に「あいしてる」を云わない。とすれば最後にこの映画はまったくのノンセンスを提示して終わったのか?(※ちなみにナンセンスでない理由は特にない。)
ある意味ではそうである。だから、「もしそうではないとしたら?」が生まれる。
まったくのノンセンスでないとはどういうことか?
この問いが誘いである。
〈エロス〉である。
一人称の私にとっての。
この不思議なフィクションからの誘い――〈エロス〉をかきたてる「あいしてる」は狂気への誘いだ。
〈もしかしたら〉と誘引させること。
これが思考の経験への入り口だ。
『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』から――ヴァイオレットから〈もしかしたら〉の「あいしてる」を云われた一人称の私はどうなってしまうのだろう?
狂気のなかで出逢う〈未知のもの〉とは何だろう?
一人称の私はたしかにこの問いに誘われた瞬間に――こんな思考をはじめてしまったこのときに――狂気という一撃を受け、殺害されたのだろう。
死の断絶という契機が既知の存在と思考の形態をほころばせ破壊する。〈未知のもの〉に出逢わせる。
しかしフィクションからの「あいしてる」――ヴァイオレットの「あいしてる」がもたらす法外な経験とは――あの〈なにもなさ〉の絶えざる殺害と新しいもの――〈未知のもの〉の入れ替わりの無限の反復運動を凍りつかせて永遠にとどめて思考に刻むことだ。
さながら死からの〈復活〉を一回限りの出来事として歴史に残すように――。
〈なにもなさの〉という〈奇蹟〉のさらなる〈奇蹟〉――。
そう一人称の私にとって『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のヴァイオレットの「あいしてる」は――現実の永遠ではないがゆえに永遠に自己点検をくりかえさざるを得ない――「あいしてる」を永遠に〈私〉にとどめる経験なのだ。
それが現実でも代替可能なフィクションのひとつの機能であるとするか――ただフィクションに、この作品にのみ開かれた現実ではありえない思考の特異な領域の発見――まったくの〈未知のもの〉であるとするかは、おのおのが各自で〈賭け〉るものであり、あらかじめ答えがあるものではない。
ここで現実とフィクションの「あいしてる」の差異や優劣を付け加えるのはよそう。
本論の〈奇蹟〉はフィクションと私たち(一人称の私)のインタラクション(相互作用)によって起こすものだったのだから。
一つだけいっておくとすればおそらく現実とはこの永遠に〈私〉にとどまる「あいしてる」に気づく場であるということだろう。
気づいたのならもう何も得るものはないはずだ。
何もそれ以上欲しないというならば――現実の「あいしてる」は〈なにもなさ〉なのだとそういえるのならば――それ以上もう何を問うというのか?
以上が本作『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』というフィクションの〈愛の成就〉という〈奇蹟〉と一人称の私を蝶番に現実との越境を試みた――いささかまさに一線を越えでた思考の軌跡だ。
さあ、一人称の私から私たちへと――〈未知のもの〉に出逢う狂気のなかから――永遠に凍りついた「あいしてる」の経験を持ち帰って振り返ろう。
現実の「あいしてる」に対するフィクションの「あいしてる」を経験した私たちは――そこにヴァイオレットとギルベルトの〈愛の成就〉を――その〈なにもなさ〉の横溢を目にすることができるはずだ。
これが先にこう述べたことだ。
ヴァイオレットはギルベルトに〈手紙〉で「あいしてる」を伝え、ギルベルトはヴァイオレットに一度失い〈回帰〉した「あいしてる」を云えた。
ではここで重要なことを断言しておこう。
『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』はそこで終わっているといっていい。
だからその後に彼女たちの〈愛の成就〉があったのか。それがどういうものなのかはわからない。
「そうではない」といえるとすればそれは〈愛の成就〉を何も知らないから、というよりもそれを知らないことを知らないからだろう。
もし本当に知っているのだとすればそれが描けないものであること、それは描かれないはずであることを知っているはずだ。
そして事実、それは描かれていないのだ。
「あいしてる」を伝えあったふたりがただそこにいるだけである。
【出力ワード:「あいしてる」の〈なにもなさ〉】
第13節.神と交わる女たち/ヴァイオレット/から/の「あいしてる」
前節において〈愛の成就〉は〈なにもなさ〉であるという本論が追ってきた〈奇蹟〉にこたえた。
最後となる本節ではヴァイオレットとギルベルトの〈愛の成就〉をもうひとつ別の視点から描き出してみたい。
それが本稿が最後にこたえなければならないはじめの問いへの架橋にもなるだろう。
前節の「あいしてる」をめぐる論述を導いたのは――現実からフィクションを規定するのではなく――現実からフィクションという現実とは別の〈ブラックボックス〉に入って出ていく先――〈未知のもの〉に出逢うという思考の〈エロス〉であった。
本論の主旋律ともいえる探し求めるもの、〈エロス〉の魅了から「あいしてる」を再び追い求めよう。
「あいしてる」はエロスを育む母胎になる。(※エロスは原初の「あいしてる」にわずかに尻込みするだけの慎みしか持ってはいない。)
もちろんエロスがどこから生い茂ってくるかは種々諸々だろう。
そもそもエロスの言葉の定義がいまでは多様なものになってしまっている。
それでもこの世界を彩り、この世界の根源ともいえる〈カオス〉としての〈エロス〉の生起をヴァイオレットとギルベルトのふたりから跡付けてみたい。
なによりも彼女たちの〈エロス〉からこそ本稿ははじめることができたのだから――。
【入力ワード:狂気のなかの”ただ”の「あいしてる」】
〈エロス〉以前に何があるのか?
〈エロス〉という〈カオス〉を生んだ〈カオス〉とは何か?
それはヴァイオレットとギルベルトの「あいしてる」のことだ。
この「あいしてる」の背後にはもう何もないと論じた。
”ただ”「あいしてる」と云い、それを伝える以外に何もないのだと。
そしてそれは何を生み出すかわからない〈カオス〉なのだ。
〈なにもなさ〉とはすべてを殺しすべてを生む〈カオス〉だ。
さまざまな〈愛〉はこの〈カオス〉が発端となって生まれてくる。
いや、〈なにもなさ〉の〈堕罪〉を免れない現実においては〈愛〉という名をよくわからないまま何にでもやたらめったらつけられていく。
この生まれの素性を忘れたところにすべての〈愛〉は生きている。
しかしほんとうの意味ではそれは魂の抜かれた骸が跳梁跋扈しているだけだ。
生まれ落ちた瞬間に死んでしまうものがこの世界の〈愛〉のあり方だ。
すくなくとも〈エロス〉とはそうであるからこそ失われてしまったものを探そうとする。
それを原動力とするのが〈エロス〉だ。
さまざまな〈愛〉――。
すこしだけ辞書的な説明を差し挟もう。
古代ギリシャでは性愛としてのエロース以外にも他に友情や親愛を意味するフィリア 、家族愛のストルゲー、そしてアガペーと4つの愛が区別されて用いられた。
アガペーは後にキリスト教によって神の普遍的な無限の愛の意味で用いられるようになる以前は、死者への愛や愛一般の好むことや喜びといった意味合いだったという。
しかしキリスト教によってエロースがアガペーにたいして肉体的、情欲的、自己中心的な愛とされた以後もキリスト教の歴史のなかでは〈エロス〉は決して否定的意味合いだけを与えられていたわけではない。
それどころか神、キリストとの合一、もっといってしまえばセックスによる法悦、恍惚エクスタシーにいたる伝統は、新プラトン主義や他の様々な神秘主義によって現在に至るまで脈々と息づいている。
神との合一を果たした聖人たちのなかには聖女カテリーナや聖女テレサといった歴史的な偉人に加え現代では精神病院にて貴重な症例として研究対象となった症例マドレーヌといった女性の系譜がある。(※もちろん生物学的、解剖学的な男性も少なくない。その代表が十字架のヨハネだろう。)
彼女たちの法悦の姿をとどめた姿はベルニーニによる彫刻で当世においても見ることができる。(以下画像を参照)

(ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ『福者ルドヴィカ・アルベルトーニ』MUSEYより)

(同ジャン・ロレンツォ・ベルニーニ『聖テレジアの法悦』Wikipediaより)
『聖テレジアの法悦』は本稿で引用したジョルジュ・バタイユ『エロティシズム』のちくま学芸文庫版と哲学者でありラカン派精神分析の創始者である精神分析の泰斗ジャック・ラカンの1972-1973年度のセミネール『アンコール」の邦訳の表紙にともになっている。(※『アンコール』、『エクリ』などのラカンの著作――ほとんどがセミネールであるが――はそのあまりの難解さで有名だが立木康介氏ら数々の信頼のおける書き手による著作によって咀嚼の手助け以上に惹きつけるような新たな視点を得た。また本稿の思考の軌跡にもそれらの影響が鳴り渡っている。)
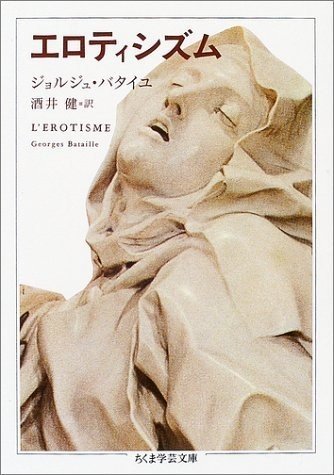
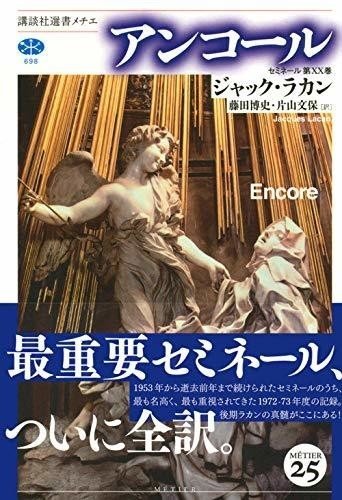


上で紹介した立木康介『狂気の愛、狂女への愛、狂気のなかの愛 愛と享楽について精神分析が知っている二、三のことがら』は筆者がヴァイオレットというキャラクターと本作の解釈に際し陰に陽に影響を与えた著作である。
さて唐突なアナロジーとならないための序奏はここまでにして核心に入ろう。
つまりこういうことだ。
筆者にはどうしてもヴァイオレットが――彼女のエロスが――こうした神やキリストとの〈エロス〉的交わりでエクスタシーに達した女性たちに重なって見えるのだ。
こうした聖女たちをコンパクトに紹介する菊池章太『エクスタシーの神学』の引用と〈アガペー〉と〈エロス〉をともに思考することで、ヴァイオレットとギルベルトの「あいしてる」から私たちが受け取るものが何であるかを考えてみることにしよう。

”私たちが誰かとひとつになりたいと思うとき、それはただよろこびをともにするだけではない。悩んだり苦しんだりすることも、その人とともにするのではないか。苦悩を共有する。そうすることで悩んでいる人の心に寄り添うことができる。おたがいをいっそう愛しあうことができるのだという。”(p191)
この本は
”自分がなくなってしまえば、そこで自分の外にある何ものかと出会うことができる。自分という存在をこえた世界とつながる可能性がひらかれてくる。”
”自分を捨てたことでつながる。”
”これがエクスタシーの本質ではないか。”
(p216)
で結ばれる。
ともにする苦悩、自分を捨てたところでつながるエクスタシーの本質。
では
〈愛の成就〉とは何か?〈あい〉とは?
それが可能になることはあり得るのか?しかしどうやって?
それをここまで問い続けてきた。
前節では〈愛の成就〉はない。つまりそれは〈なにもなさ〉――それの横溢であるという答えに至ったのであった。
それはこういうことであった。
ここでもまた〈不確定性〉が顔を出す。
〈奇蹟〉を可能にしたのはヴァイオレットの〈ブラックボックス〉という〈不確定性〉とその〈謎〉――〈ミステリー〉に魅了されたギルベルトの〈賭け〉であった。
なぜ〈不確定性〉か?
〈未知のもの〉に出逢うことがわかればそれは自明だろう。
常に〈不確定〉であるから〈未知〉でありうる。
〈不確定性〉に開かれなければ〈未知のもの〉にはなりえない。
〈未知のもの〉はそれが現れてしまえばすぐさま既知となってしまう。
だから既知を殺して現れた〈未知〉は常にすぐ死んでしまうか絶えず既知を殺すことでしか存在し得ない。
〈なにもなさ〉の横溢はだからこそそれ以上はもう〈なにもない〉のだ。
〈なにもなさ〉とは絶えざる生成と消滅だ。
それに現実的価値がないのは当然のことだろう。
そしてそれは感知することも意味を与えることもできないという絶対的な〈不可能性〉であるのだ。
しかしこの儚くも激烈な破壊作用そのものの〈なにもなさ〉は〈奇蹟〉の〈痕跡〉の〈不可能性〉のような〈痕跡〉を残すことができる。
それがこの『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』というフィクションが現実にもたらすもの――フィクションから現実に持ち帰るものだ。
すべての既知のものを鏖殺し〈未知のもの〉に生まれ変わらせる〈なにもなさ〉は――本論において馴染みの〈不確定性〉であったヴァイオレットの〈ブラックボックス〉やギルベルトの〈賭け〉――そして〈未知のもの〉として死して〈幽霊〉となってあらわれ――そこから〈復活〉と〈新生〉を果たすことを可能にした〈充溢そのもの〉である。
この〈なにもなさ〉=〈充溢そのもの〉は〈不可能性〉を〈不可能〉にもする絶対的な〈不可能性〉である。
だからこそヴァイオレットとギルベルトは――それが〈不可能〉であったにもかかわらず〈奇蹟〉として「あいしてる」を云うものと云われるもののけっして交わることのない一方通行の先で――交わる可能性を宿すことができたのである。
このフィクションのヴァイオレットとギルベルトの〈死〉からの〈復活〉と〈新生〉を現実にスライドさせることは――現実の一人称の私と私たちが〈死〉としての〈未知のもの〉としてこの映画に出逢うことで――なにものかとして〈復活〉と〈新生〉である新たな思考の領域を開くという狂気のなかの交感を果たす〈可能性〉をもたらしうるものであった。
しかし、この〈可能性〉は〈必然性〉からではなく絶対的な〈不可能性〉であり〈偶然〉である〈なにもなさ〉から生まれるものである――それが〈カオス〉だ。
つまり別の可能性もありうる。
主観的にいうと別の解釈もありうるということだ。
それが本節の〈エロス〉の可能性に〈賭ける〉試みである。
※たとえばここで「第9節.ヴァイオレットもギルベルトも知らないこと、私たちしか知らないこと」で見たヴァイオレットとギルベルトの出逢いの抱擁と最後の抱擁の別様の解釈を行おう。
既存の解釈はヴァイオレットの私たちからの〈解放〉として――彼女の最初の出逢いの反復――「なにも知らず怯えていた幼い自分を受け入れてくれ抱きしめてくれた優しい男性という甘いファンタスム、夢想」というものであった。
これを狂気のなかの「あいしてる」という〈なにもなさ〉から解釈すると――絶えざる〈未知のもの〉への変成をとどめたものと解することができる。
つまりヴァイオレットは最後においても――ギルベルトに腕を回さないことでギルベルトという男の手からすり抜け――常に〈未知のもの〉として逃れ去っていく――ドレスを脱ぐようにみずからを脱ぎ去っていく女であることを暗示しているというものである。(※本論でも触れたジョルジュ・バタイユの研究書である横田裕美子『脱ぎ去りの思考: バタイユにおける思考のエロティシズム』はこの解釈をより広く論じたものである。)
『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』が最後に凍りつかせ結晶化させたものは「あいしてる」の永遠性に加え、新たにこの〈なにもなさ〉の絶えざる〈死〉と〈新生〉の永劫回帰――つまりギルベルトの絶えざるヴァイオレットの捕獲と彼女の彼からの失跡の永遠運動――を認めることができるのである。
これをギルベルトの〈過去〉から〈回帰〉した「あいしてる」に接続してみるならば、ふたりを――この映画を――生かす血液の循環こそが「あいしてる」だったということもできよう。
そしてその循環にはフィクションの〈外〉の現実の私たちも加わりうるのだった。
さて、こうしたヴァイオレットとギルベルトがともに徹底的に〈不可能〉であったにもかかわらず、〈愛しあう〉ことができたことに新たにもうひとつの〈エロス〉による解釈を続けるうえで忘却から救い出し留意するべきことがある。
それはヴァイオレットとギルベルトの愛、〈エロス〉の背後には戦争とそれに伴う殺害行為が確固とした現実として横たわっているということである。
いかにギルベルトのその責がほとんどヴァイオレットを武器として使ったことにあり、ヴァイオレットはその点をギルベルトに関してはまったく無視するかのように――つまりヴァイオレットはギルベルトを恨んでいない(かのように)――描かれていようと、いやそれだけにいっそう消えることなくふたりを覆っている。蝕んでいる。
戦火のなかをともにしていなかったならばふたりはこれほどお互いを求め合うことはなかったであろうからこそこの問いは重要である。
こうした事実を強調したうえでどういう〈愛の成就〉の可能性があるだろうか。
最終節であるここでは、彼女たちを免罪する方便の論理を構築することも、あるいはその罪過をあらためて並べたて〈堕罪〉を止揚する〈愛〉を語ることもしない。
後者についてはそのいくらかの性格をこれまでの作品分析のうちに読み取れるように思われるからだ。
最後に述べておきたい要点は――ヴァイオレットとギルベルトという個人の何かを深く強く追い求めるという――〈エロス〉にその個人を超えた、越境してきた〈外〉が関係しうるのではないか、触れているのではないかということである。
その〈外〉が罪の赦しや〈愛〉というかたちで――〈アガペー〉としてあったのではないか。
そしてもうひとつは前節にも関係することであるが、私たち現実の観客が惹き起こされるヴァイオレットらキャラクターへの〈エロス〉――〈愛〉がフィクションにとっての〈外〉となること。
その対照となる、私たち現実の個人の〈外〉として現れるフィクションの〈アガペー〉という驚嘆する次元の開闢について。
つまり私たちにフィクションと〈アガペー〉が等根源的に〈外〉となったように――キャラクターの〈外〉の〈アガペー〉に何かもっと別のものが開かれるのではないかという希望を語ってみたいのである。
※私たち現実にフィクションとアガペーが開かれたのだから対応してフィクションにはアガペーと現実が開かれると即断しないということである。あるいはフィクションに開かれた現実とは何か?別の名で現れるものとは何かということである。
つまり現実の〈外〉のフィクションとフィクションの〈外〉の現実――ヴァイオレットらにとっての〈外〉としての私たちと〈アガペー〉――という〈外〉を媒介した〈未知のもの〉についてである。
そして媒介する〈外〉は〈外〉自身にとって〈外〉であるかもしれないということである。
ヴァイオレットとギルベルトが〈エロス〉とともに、その果てに出逢った〈外〉とは――〈未知のもの〉とは何だろうか?
それでは見ていこう。
引用するのは前掲書『エクスタシーの神学』である。
次の引用は新約聖書のパウロについてのものである。
”ガラテヤ人々への手紙”(四章九節)で述べているおのれと神との関係は”おたがいが世間から捨てられ、自分さえ捨てたところでつながったのである。”
(p.215)
これはヴァイオレットとギルベルトがどれほどの自覚があるか――どれほど彼ら以外のものが背負わせようとするか――とは無関係に、戦争によって奪った生命たちの世界から、そして自分自身からも捨てられているふたりが、であるがゆえにつながりあうことが許される――そんな希望を教えてくれる一歩とならないだろうか。
また
”アガペーとエロースがまじわる”としてニュッサのグレゴリウスの言葉から”「私は愛に傷ついている」と語るこの[筆者注 旧約聖書の『雅歌』にうたわれた]花嫁は、「形がなく燃えさかる愛(エロース)の矢で傷つけられた」のである。この矢は物質的なものではない。肉体を傷つけることなく、心の深みに達する。そうして「愛(アガペー)に高められた」のである。”
”エロースが人の側から発せられるのに対し、アガペーは神の側からくだされる。惜しみなくあたえられる愛である。”
”グレゴリウスはこのふたつの愛をもっと強く結びつけて考えた。神とひとつになろうとする情熱を燃えたたせるのはアガペーだという。その呼びかけにエロースがこたえる。アガペーの力でエロースが神に向かうのである。神と人とのあいだに愛のまじわりが生じる。”
(pp.98~99)
グレゴリウスは述べる。”そこでは愛の矢をエロースと呼んでいた。愛に傷つきたいという思いはエロースから出発する。その思いは高められ、アガペーの力で愛に傷つくことが成就するのである。”
”おとめたちは願うであろう。愛の矢について私たちも知りたいと。「愛の矢が心の深奥であなたを傷つけ、甘美な痛みをもたらし、情熱を燃あがらせる」のだから。”
(pp.100~101)
”神の高みにまでひきあげられたひとりの聖女が、神と合一をとげている。天使の矢の突きさしはまだ終わらない。テレサの神への愛、すなわちエロースは高まるところまでいったきりもどらない。ふりそそぐ神の愛、アガペーにだきすくめられながら、むごいまでの愛のまじわりはつづいていく。”
(p.102)
傷つくことで成就する〈エロス〉と〈アガペー〉の交感――。
その酷いまでのまじわり――。
ヴァイオレットとギルベルトの愛もそのようなものなのだろうか。
ギルベルトはヴァイオレットのイノセントな愛〈エロス〉に傷つけられる。そんなかたちで抱いた〈エロス〉の清算に彼は苦しめられた。
ヴァイオレットはギルベルトの〈エロス〉を理解することなく妄執に取り憑かれていた。そう云えるのかもしれない。
しかし、もしそんなギルベルトの〈エロス〉が幼いヴァイオレットからの〈アガペー〉の呼びかけにこたえたものだったとすれば――。
もしヴァイオレットのイノセントな狂信的〈エロス〉がギルベルトの背徳的な〈エロス〉とは別の、おしみない〈アガペー〉の力で生まれていたのだとすれば――。
この〈アガペー〉が――本来の神からの無償の愛が――神がイエス・キリストに、人間になることであたえられたように、互いで傷つけあい血を流しあうことに汲々とすることしかできない愚かな人間が、その人間に与えあうこともできるのではないか。
それを私たちは、それ以外ではないもの――〈なにもなさ〉――”ただ”の「あいしてる」として見たはずである。
ヴァイオレットとギルベルトは〈エロス〉によって惹かれた。
惹かれ合った。
それは戦争が肥やしとなったものだった。
そうでしかありえないものだった。
だから結局どうあっても傷つけあう以外にないものだった。
その傷の痛みの意味も新たに生まれ変わるのではないか。
その可能性があるのではないか。
あの出逢いにも〈アガペー〉が――無償の愛が――”ただ”の「あいしてる」があったはずなのだ。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
そしてあったはずのそれをもう一度云えたかもしれないのだ。
それが〈奇蹟〉以外の何であるだろうか。
彼女らの〈エロス〉と〈アガペー〉のどちらか、どちらからの芽生えからが〈不確定〉となったあの日。
あのとき。
出逢いの日。
なにがおきたかなどわかりはしない。
ただそれでも、彼女たちの再会が彼女たちの〈復活〉と〈新生〉であったとすれば――。
死んでいた、止まっていた時間から、ふたたびふたりは生きはじめる。
”ただ”の「あいしてる」から生きはじめる。
”聖なるものと性的なものとがとけあって、それひとつずつでは思いもよらない、どこか別の世界にまで高められていったかのごとくである。”
(p.105)
キリストの”復活の果たした決定的な役割を強調するチェコの神学者P・ポコルニ―は、復活者との出会いを前後して弟子たちの態度が豹変する顕著な断絶に注目する。[中略]弟子たちの多くは失意落胆の内にガラリヤでの元の生活戻ったであろう。ところが、復活者の顕現後の彼らの態度を特徴づけるものは、霊的高揚であり、隠しようもない喜び(Freude)であり、歓喜である(ルカニ四32、41、52、ヨハネニ020)。それは後のペンテコステ(聖霊降臨)の出来事に比肩しうるような霊的喜悦であり、エクスタシーである。この顕著な態度の変化は、一体何によって生じたものなのだろうか。ポコルニーはそれを衝迫(Impuls)という言葉で表現する。それは意気阻喪している弟子たちの内部からはどうしても出せない、外からの力である。まさにイエスを死人の中から甦らせた神的な力が、この死んだも同然の弟子たちを活性化させたのである。”
芳賀力『救済の物語』(日本キリスト教団出版局、1997年)p.219
私たちは最後にこう問うたのだった。
ヴァイオレットとギルベルトが〈エロス〉とともに、その果てに出逢った〈外〉とは――〈未知のもの〉とは何だろうか?
と。
これが最後にたどり着いた先だ。
ヴァイオレットの〈エロス〉を生んだギルベルトの〈アガペー〉
ギルベルトの〈エロス〉を生んだヴァイオレットの〈アガペー〉
そしてそのふたりのアガペーは〈そと〉からやってきた。
その〈外〉からやってきた〈未知のもの〉を〈神〉と呼ぶ。
……私たちにフィクションと〈アガペー〉が等根源的に〈外〉となったように――キャラクターの〈外〉の〈アガペー〉に何かもっと別のものが開かれるのではないかという希望を語ってみたいのである。
この「キャラクターの〈外〉の〈アガペー〉に何かもっと別のものが開かれ」たものが、フィクションにあらわれた〈神〉である。
現実にではなく『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』にあらわれたものが〈神〉なのである。
そして〈神〉の代わりに私たちの現実には、原初の「あいしてる」を失った骸である私たちを「活性化させ」る「外からの力」が、ヴァイオレットからの「あいしてる」がおくられたのだ。と、そう云ってしまえばいい。
【出力ワード:映画の〈外〉の〈神〉/現実の〈外〉のヴァイオレットの「あいしてる」】
▼終章.「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」
を解く最後のスペル
スペルはすでにすべて唱え終えている。
もはや贅言を要しない。
ここから、はじめてみよう。
さて、「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」
この〈謎〉を解くことができたであろうか?
題名に掲げられたこの問いが本論の記述の帰趨によって解かれるのであったとすれば、最終的に姿をあらわしたのは〈神〉であった。
そう、これもまた題名にすでに「隠れたる神と奇蹟の映画」とあったように、この映画の〈隠れた神〉をあらわにすることが答えとなるのである。
Q「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」
A「この映画の世界に現れる神の力によって義手は動かされるから」

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)
ご納得いただけただろうか?
蛇足を続けよう。
新たに問うてみよう。
Q「『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』というフィクション/映画の〈外〉にあらわれた〈神〉はデウス・エクス・マキナであろうか?」
もちろんこれは違うだろう。この神に登場願わなくても何ら問題はない。特に解決するべき仕事はないように思われる。
むしろこれはそもそも見当違いの問いだと。こう問うべきだと。
Q「この映画に神はいるのか?」
多義的な疑問文とした。これにはさまざまな答え方がある。
たとえば
A「『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の舞台となる世界は架空のヨーロッパ的世界であるが、その問いは私たちの現実の世界と類比的で明確に答えられない。」
など。
しかしこれ以上はやめよう。この問いも答えも最悪のものだ。
すっかり魔法が解けてしまった。
一度解けたら二度とかからないかもしれない。
しかし、そこからもう一度はじめよう。
こう問うてみよう。
Q「〈神〉はどこに現れたのか?どこにいるのか?」
これなら的を射た問いだ。
A「〈不確定性〉の淡いのなかに」
そうなのだ。
α〈神〉=〈なにもなさ〉=〈カオス〉なのであり
かつ
β〈神〉=〈ただの「あいしてる」〉=〈アガペー〉である。
つまり〈なにもなさ〉の充溢はα(それ以上もそれ以外もなにもないすべてである)と同時にβ(絶えざる〈死〉と〈新生〉の連続、〈未知のもの〉)であったように――〈神〉もまたこのαとβのあるいはβの生成と消滅の〈不確定性〉そのものとしてある。
そして本論は〈ただの「あいしてる」〉が〈愛の成就〉として〈奇蹟〉としてこの映画『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』に永遠に留め置かれたさまを描いてきたのだった。
β〈神〉=〈ただの「あいしてる」〉=〈アガペー〉
では〈神〉=〈ただの「あいしてる」〉であるにもかかわらずなぜその〈神〉は〈隠れたる神〉なのだろうか?
ヴァイオレットがギルベルトにただ「あいしてる」と伝えたように――ギルベルトが二度、そう伝えたように――それはそこにあるのではないのか?
もうひとつ。
〈ただの「あいしてる」〉は〈不可能性〉と〈不確定性〉と〈未知のもの〉としての絶えざる生成消滅の靄のなかからその一瞬の姿を捉えることができた。
では〈神〉の存在証明はそれとどう違うのか?
これらは逆に考えたほうがいい。
本来〈ただの「あいしてる」〉が認識可能であることがありえないことなのである。〈奇蹟〉なのである。
だから”この”〈神〉を『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』というフィクションに見出すには魔法の力が必要なのである。
つまりヴァイオレットやギルベルトに見た〈ただの「あいしてる」〉と〈神〉は別のものである。
彼女たちは徹頭徹尾「地上的」な存在なのだ。
蛇足ながらあらかじめここに付け加えておくと私たちが追っている”この”〈神〉も「天上的」ではないはずである。
もう少しその理由を述べよう。
こういうことだ。
まず、〈神〉=〈ただの「あいしてる」〉であるにしても、それら――〈神〉と〈ただの「あいしてる」〉――を「図」としたとき、それが描かれる「地」の場所が違う。
そして何よりそれを描くもの――作者――が違うのである。
〈ただの「あいしてる」〉がフィクション内のキャラクター――これが一方の作者――の〈エロス〉と〈アガペー〉として描かれ、ヴァイオレットからこの現実の私たちに贈られたものであったのにたいして、〈神〉は逆に現実の私たち――別の作者――の方からヴァイオレットに贈らなければならない。
これが、β〈神〉=〈ただの「あいしてる」〉=〈アガペー〉の意味である。
この三位一体においての〈アガペー〉が〈神〉と〈ただの「あいしてる」〉を媒介する。
さらにそれら――〈神〉と〈ただの「あいしてる」〉――の「図」が描かれるフィクションと現実という次元を異にする「地」をも媒介する〈外〉からの力が〈アガペー〉と呼ぶものである。
この現実とフィクションを交感させるもの――交感自体が〈アガペー〉だ。
〈エロス〉をヴァイオレットとギルベルトが互いに決して手放さなかったように――現実からヴァイオレットへ呼び水――愛撫――はそこにあり続けるだろう。
先にこう述べたとおりである。
……〈神〉の代わりに私たちの現実には、原初の「あいしてる」を失った骸である私たちを「活性化させ」る「外からの力」が、ヴァイオレットからの「あいしてる」がおくられたのだ。……
〈エロス〉の魅惑に徹底して耽溺するヴァイオレットとギルベルトがそれ――前戯――を突き抜けた先に出逢ったのが〈外〉からの力として〈アガペー〉という〈未知のもの〉――〈神〉なのであった。
それは同時に私たちが本作を〈エロス〉的に探究した先に、ヴァイオレットからの「あいしてる」という〈未知のもの〉――〈アガペー〉に出逢うということと軌を一にするという、これまた〈奇蹟〉的な出来事なのであった。
本論は件の問いに答えること、〈エロス〉によって――私たちの現実が〈アガペー〉が射し込む〈外〉においてフィクションと交感する――その地平を開く魔法となるのだった。
先にこう述べていた。
……私たちにフィクションと〈アガペー〉が等根源的に〈外〉となったように、キャラクターの〈外〉の〈アガペー〉に何かもっと別のものが開かれるのではないかという希望を語ってみたいのである。
”※私たち現実にフィクションとアガペーが開かれたのだから対応してフィクションにはアガペーと現実が開かれると即断しないということである。あるいはフィクションに開かれた現実とは何か?別の名で現れるものとは何かということである。”
私たちにおくられたフィクションからの〈アガペー〉という〈外〉からの力にたいして、キャラクターにおくられる〈外〉からの力としての〈アガペー〉が「フィクションに開かれた現実」、「別の名で現れるもの」である〈神〉ということである。
……〈神〉=〈ただの「あいしてる」〉であるにしても、それら――〈神〉と〈ただの「あいしてる」〉――を「図」としたとき、それが描かれる「地」の場所が違う。
そして何よりそれを描くもの――作者――が違うのである。
つまりこれは、ヴァイオレットから現実の私たちにおくられる〈ただの「あいしてる」〉はフィクションという「地」があるのに対し、同じ「図」となる私たちからヴァイオレットにおくられるかもしれない〈神〉は現実にその場所を持たないということだ。
私たちの現実の世界――「地」――には〈神〉の座がない。
単純化していえば、私たちは〈ただの「あいしてる」〉を受動的に受け取ってしまえばいいが、〈神〉はこちらから能動的にヴァイオレットにおくらなければならないのである。
おくるためにはそれをまず認識しなければならない。
それができないとき――「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」という問いに答えはない。いや、そもそも無意味な問いとなる。
この私たちとヴァイオレットの関係性はヴァイオレットとギルベルトの関係性と類比的である。
どのような関係性か?もちろん〈エロス〉と〈アガペー〉のである。
……もしそんなギルベルトの〈エロス〉が幼いヴァイオレットからの〈アガペー〉の呼びかけにこたえたものだったとすれば――。
もしヴァイオレットのイノセントな狂信的〈エロス〉がギルベルトの背徳的な〈エロス〉とは別の、おしみない〈アガペー〉の力で生まれていたのだとすれば――。
これはふたりの一方通行な〈エロス〉の始原に〈アガペー〉があったのではないか――相手からおくられた〈アガペー〉によってこそ〈エロス〉は引き出されたのではないか――という〈なにもなさ〉の〈不確定性〉の〈未知のもの〉――この新たな胎動の可能性自体の開闢を――どこまでも「であったかもしれない」のまま開いている。
幾重もの〈不確定性〉から〈アガペー〉を――〈アガペー〉から絶えざる〈未知のもの〉を――〈未知のもの〉から〈神〉を――〈神〉から〈外〉の力を――〈外〉の力から――。
この生成自体を生み出し続ける循環はトートロジーでありながら絶えず〈未知のもの〉に生成変化するトートロジーのトートロジーなのである。
イコール〈=〉で結ばれる両項は別のものでありながら同じものである。同じものは同時に別のもとなる。
絶対矛盾的自己同一自体の絶えざる累進の動的構造から〈アガペー〉を剔抉すること、それを〈可能〉とする試みもまた――〈アガペー〉自身であるということ――。
ヴァイオレットとギルベルトのあったかもしれない原初の〈アガペー〉という〈なにもなさ〉を私たちとヴァイオレットの関係性に移しかえてみるのであった。
β〈神〉=〈ただの「あいしてる」〉=〈アガペー〉なのだから、
ヴァイオレットが〈アガペー〉として私たちに〈ただの「あいしてる」〉をおくるとき――それは私たちから〈アガペー〉としてヴァイオレットに〈神〉を、つまり〈義手を動かす力〉をおくっていたのではないかということである。
これがヴァイオレットとギルベルトと類比的なヴァイオレットと私たちの関係性である。
この関係性で重要なことは、ヴァイオレットとギルベルトの原初の〈アガペー〉はそれが「あったかもしれない」かどうかは〈不確定〉であることである。
そして〈原初〉であるとはリニアな時間ではないことを意味する。
それはたとえば現在起きたことが遡行的に過去ですでに「そうであった」ということでもあるし、未来にそうなることが現在においても「そうであった」ということでもある。
つまりこういうことだ。
ヴァイオレットの義手を動かす〈神〉の力は、彼女が映画の最後に「あいしてる」を私たちにおくるときに、すでに私たちから原初に彼女へ「おくられていた」のである。
そして私たちが〈神〉の力を原初においておくるときにすでに私たちはヴァイオレットから「あいしてる」をおくられていたのである。
なぜならあの生成変化するトートロジーのトートロジーは〈無時間的〉だからである。
それは常にすでになにものでもないが同時につねにすでになにかでもあるからである。
しかし問題はこういうものであった。
……ヴァイオレットから現実の私たちにおくられる〈ただの「あいしてる」〉はフィクションという「地」があるのに対し、同じ「図」となる私たちからヴァイオレットにおくられるかもしれない〈神〉は現実にその場所を持たないということだ。
これがβ〈神〉=〈ただの「あいしてる」〉=〈アガペー〉であるにもかかわらず、〈ただの「あいしてる」〉に比して〈神の存在証明〉が難しい理由である。
ヴァイオレットからおくられた〈ただの「あいしてる」〉が永遠にフィクションとしてとどまるのにたいして、私たちから彼女におくられる〈神〉の力はどこにも存在することができないのであった。
このヴァイオレットと私たちの非対称性が〈隠れたる神〉の存在証明を魔法による〈奇蹟〉とする根拠である。
この「どこにも存在することができない」とは通常のニュートン的な絶対空間と絶対時間、感性の直観形式においてである。(※つまり私たちが感じるごく一般的な空間と時間のなかではどこにも、ということ。)
〈神〉の居場所が絶えざる生成消滅と絶対矛盾的自己同一の無限運動と無時間なのであるから当然であろう。
ではこの存在することのできない〈神〉はヴァイオレットへおくることはできないのか?
そうではない。
β〈神〉=〈ただの「あいしてる」〉=〈アガペー〉なのであった。
そう、〈神〉とは〈ただの「あいしてる」〉であること――これを忘れてはならない。
「第12節.ヴァイオレットの凍りついた『あいしてる』」ではこう述べた。
エンドクレジットの直前のヴァイオレットの暗闇のなかの歩み。
そこにヴァイオレットからの?ヴァイオレットへの?「あいしてる」がある。
”ここからは一人称で書くことしかできないはずだ。
一人称の私はヴァイオレットへの「あいしてる」を云うことに戸惑わざるを得ない。
ではヴァイオレットからの「あいしてる」をどのように受け取るべきか?
いかなる意味においてもヴァイオレットは一人称の私に「あいしてる」を云わない。とすれば最後にこの映画はまったくのノンセンスを提示して終わったのか?(※ちなみにナンセンスでない理由は特にない。)
ある意味ではそうである。だから、「もしそうではないとしたら?」が生まれる。
まったくのノンセンスでないとはどういうことか?
この問いが誘いである。
〈エロス〉である。
一人称の私にとっての。
そして狂気への誘いでもある。”
いかなる意味でもノンセンスだったはずのヴァイオレットからの「あいしてる」を受け取った私たちはいまこそ、「あいしてる」を――〈外〉からの力である〈神〉を――「もしそうでないとしたら?」の問いが開く「どこにも存在できない」場所としての〈ここ〉からそれを――はじめなければならない。
ヴァイオレットへ――。
再び狂気のなかへ――。
わたしの〈エロス〉から――。
◆
はじめるべき〈ここ〉とはこの現実――本論の記述――魔法のスペルのことである。
一種の狂乱から酔いが冷めたいま――脱魔術化してしまった現状において――整理しながら簡潔平明にヴァイオレットへの〈神〉にいたった道のりを跡付けてみよう。
本論が目指したのはこういうことだ。
まずは「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」という〈謎〉を解くには何が必要か?
当たり前なのだがこの問いは、本作の舞台に現実の世界を超える科学水準や魔法その他の超常的力が存在していないため、常識的に整合性のある答えがない。
通常はツッコんではいけないところであって、フィクションが現実と整合的である必要などないのだからそういうものなのだとしておけばいい以外にない。
よってこう考えなければならない。
「『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』はこの問いによって新しい相貌を見せるのだとしたらそれはどういったものになるのか?」
ということである。
あらかじめ作品に解くべき〈謎〉があるのではなくて、作品の後に生まれた〈謎〉が事後的に「もう一度、そうであったかのように」作品を生まれ変わらせるのである。
そしてこれが〈批評〉である。「批評家とは作品の第二の作者」であってみれば。
本稿の題名にある最初の問いの答えは結末のここにおいて答えられるまでに別の問いを〈奇蹟〉として考えていくことで大きく迂回してきたのだった。
その中心的問いは「ヴァイオレットとギルベルトの〈愛の成就〉はどうして可能になったのか?」であった。
これも最初の問いと同じく問いが作品の見方を刷新するものである。
なぜなら本稿では一貫して「〈愛の成就〉は不可能である」を大前提としているからである。
そして本論は不可能であったものが可能になったという単線的な結論を下したものではない。
「もし可能であったとすればそれはどういうことになるのか?」という視点から浮かび上がってきたものを紡いでいったものだ。
だから問いは作品解釈そのものの仮定でもある。仮定は作品そのものと不可分なのである。
別の仮定の問いからは別の作品が生まれてくる。
作品を観ること、批評することとは絶えず「問いから開かれた地平において作品を観る」試みである。
〈愛の成就の不可能性〉はそれが〈不可能〉なのであるから〈奇蹟〉といことになる。
そしてこの〈奇蹟〉がこの作品に胚胎したときをもって〈神〉の座は打ち立てられたといえる。
どこに?
『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』と私たちとの関係のなかにである。
どうしてか?問いと作品は不可分なのであったのだから。
このはじめから存在していたことになる〈神〉の座をそれと名指しするまでに筆者がたどった道のりは、一言でいってしまえば「ヘブライズムとヘレニズムの痕跡の発見と発掘」というものだった。
これはここまで読み通せば一目瞭然であろう。
ではあらためて簡単に振り返ってみよう。
ヘレニズムとしては、なによりプラトンを代表としたエロスが本論の中軸として欠かすことのできないものとなった。
その他にはエカルテ島の自然の描写に古代ギリシャの自然哲学者たちのこだまを聞いたのだった。
もちろんエカルテ島のモデルがまさにギリシャのフォレガンドロス島とされることの意味も大きい。(エカルテ島のモデルについては【ふむ】🌸氏TwitterのTLを参照)
ヘレニズム以上に濃厚なのがヘブライズム的な象徴の数々であろう。特にキリスト教である。
まず、直接的にはいままでおそらく意図的に排されてきたであろう濃厚に宗教性を帯びた単語としてギルベルトが目覚めた「修道会」がある。
このたったの一語の意味は本作のキリスト教的モチーフを読み取っていくうえで決定的に重要である。
本作にキリスト教的モチーフが多用されている点は舞台のモデルであるヨーロッパを細密に描けば、色濃くその香気を纏うのは当然ともいえる。
その他の細かなキリスト教を中心としたヘブライズムモチーフの数々は本論に直接あたっていただくとして特に重要なものだけを列挙するにとどめよう。
さまざまなところに印象的に配される十字架、〈死〉からの〈復活〉と〈新生〉――。
そして本論の中核的骨子となる予型論的モチーフは〈予示と反復〉の構造、〈分身関係〉として詳述した。
たとえばユリスを贖罪の羊とする解釈はアブラハムのイサク献供、イエス・キリストの磔刑を予型としている。
以上のような濃密な宗教的バックグラウンドから「〈愛の成就〉は不可能である」と「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」というふたつのありえない事象を問うことが――つまり本論が書かれるということがすでに歴然と〈神〉に触れる行為としてあったのである。
「ヘブライズムとヘレニズム」を本作から読み取ること、本作をそう読み込んでいくこと、それが〈奇蹟〉と〈神〉の胎動が次第にシンクロしていくプロセスとなっていったということ――これが筆者が本論を書き進めていく上で重要な指針となった。
そして読み手も筆者と同じそのシンクロの道程を追体験できるようなものとすること。
本論はそれを目指されて書かれたし同時にそれに導かれて記述されていった。
そして本論はフィクション内の〈奇蹟〉として〈愛の成就〉に、ヴァイオレットからの現実への越境として〈ただの「あいしてる」〉にまでいたったのであった。
では〈神〉はどうだろうか?
くりかえそう。
いかなる意味でもノンセンスだったはずのヴァイオレットからの「あいしてる」を受け取った私たちはいまこそ、「あいしてる」を――〈外〉からの力である〈神〉を――「もしそうでないとしたら?」の問いが開く「どこにも存在できない」場所としての〈ここ〉からそれを――はじめなければならない。
ヴァイオレットへ――。
再び狂気のなかへ――。
わたしの〈エロス〉から――。
私たちの現実という〈ここ〉から、私たちはヴァイオレットへの〈エロス〉を導いたはずの〈アガペー〉を、〈外〉からの力として〈神〉を、彼女におくりかえしていたといえるだろうか?
ここでもう一度同じ問いをくりかえそう。
「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」
いま、ヴァイオレットの世界に〈神〉は生きているだろうか?
「このように問うときにすでに『フィクション内における神の存在証明』という次元とは別の次元の開闢が仄見える」と、もしそうだったとしたら何が?
ここで〈問い〉とは何かを明らかにしておこう。
〈問い〉とはいままで不可能という様相としてすら存在していなかった〈不可能性〉を可能とする〈可能性〉を創造する土台を、〈不可能性〉に先立って創造することである。
創造された――〈可能〉となった――〈不可能性〉とは〈不確定性〉である。
よって〈可能〉となった〈不可能性〉は新たな〈可能性〉と別のものではない。
つまりこれは生成変化するトートロジーのトートロジーのことである。
具体例を見ていこう。
もちろん
Q1「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」
この〈問い〉がもたらしたものこそ第一に解明されるべきものである。これが〈不可能性〉に先立って創造した〈可能性〉とは何か?
「動くのか?」と問うとき、そこにはすでに「動く」〈可能性〉と「動かない」〈可能性〉が――その〈不確定性〉が生まれている。
こうして『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のなかに〈問い〉によって新たな胎動が――〈未知のもの〉が宿る〈可能性〉が生まれる。
これを展開されるといってもいい。
なんでもいいわけではない。その〈問い〉がさらなる展開をもたらすこと――それだけが唯一の目的となること――自己充足的であること――自己目的となること。
つまり〈なにもなさ〉の生成変化するトートロジーのトートロジーに参入していなければならない。
たとえばこう展開されるだろう。
先の〈問い〉Q1の答えは
A1「この映画の世界に現れる神の力によって義手は動かされるから」
であった。
ここから
Q2「『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の世界に神いるのか?」
これは先に最悪な問いであるといったものとほぼ同じであるが、展開の過程にあるときそれは別のものとなる。
これは次に〈神〉が存在する〈可能性〉と存在しない〈可能性〉となり
Q3「神が存在する根拠とはなにか?」
あるいは
Q4「神が存在しない根拠はなにか?」
とこういう展開もあれば、そもそものQ1を次のようにも展開できる。
Q5「『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の世界の神は〈どこ〉にあらわれているか?」
これは権利上はQ1以前の〈問い〉というべきものである。
しかし事実的にはQ1のみならず、あらかじめA1を踏まえることで展開することが〈可能〉となった〈問い〉である。
つまり無根拠かつ恣意的なはずの〈神〉は突然A1に不法侵入したかのごとくであったが、〈問い〉が展開されていくことによって、A1の母胎であったはずのQ1のさらにその母体としてのQ5にすでにあの〈神〉は宿っていたのである。
実際の〈事実的〉流れはいまのように
Q1→A1→(Q2→Q3∨Q4→Q6……)〈Q5→A5……〉
であるが
事後的に〈権利的〉に新たに〈可能〉となったのは
Q5→A5(Q1→A1→Q2→Q3∨Q4→Q6……)
という展開である。
ここで〈問い〉の展開の〈可能性〉の無時間的な拡張が引き起こされているのがわかるだろう。
〈事実的〉展開から〈権利的〉展開へは断絶があり思考の飛躍がある。
必ずしもこのように展開されるという保証はない。
まさしく〈神〉が宿ることによって、ということになるがそれについては後述する。
さて、では最初の〈問い〉であった
Q1「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」から時間を逆行することで存在が〈可能〉となった〈問い〉である
Q5「『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の世界の神はどこにあらわれているか?」
これに答えよう。
この答えを導くのが本論であったのである。
答えはA1を展開したものとなるだろう。
すなわち
A5「ヴァイオレットの義手が動くというそのことにおいて」
これ以外の答えをしてもよいだろう。
たとえば次のようなのはどうだろう。
A6「この映画の最後でそれまで働いていた〈神〉の力が〈去った〉と解釈することによって」
これは具体的にはどういうことかというと、本論において『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の〈愛の成就〉である〈奇蹟〉は〈ただの「あいしてる」〉という〈なにもなさ〉をフィクションとして永遠にとどめるということであったが――そのとどめた永遠が再びフィクション内の時間のなかに散逸、滲出してしまうということだ。
つまり絶えざる生成と消滅にさらされ再び〈不確定性〉の〈カオス〉の回帰をこそ、明確に描かないことで描いていると、そう考えるのである。
たしかに永遠の無時間とその破れは事態の裏表であり妥当な解釈であろう。
だとすると、たとえばこうなる。
ヴァイオレットが月夜の海で最後にギルベルトの背に腕を回さなかったのは、回さなかったのではなく回せなかったのだと読むことも可能だろう。
そのとき〈神〉の力は〈失われた〉のだと――。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.153)
ヴァイオレットというエロティックな〈妖花〉が咲くためには〈水〉と太陽光が必要だと述べたことがあった。
だがこの最後にあるのは月光と海水である。
そこには戦火の姦しい〈死〉ではなく静謐な〈死〉を予感させる――。
エンドクレジット後の十字架を背に指を切る姿は――〈神〉に捨てられたがゆえのつながりのように――世界にたったふたりだけのように――〈幽霊〉から〈死〉からの〈復活〉と〈新生〉ではなくさらにより深く死んでいるようにも見える――。(以下の画像を参照)
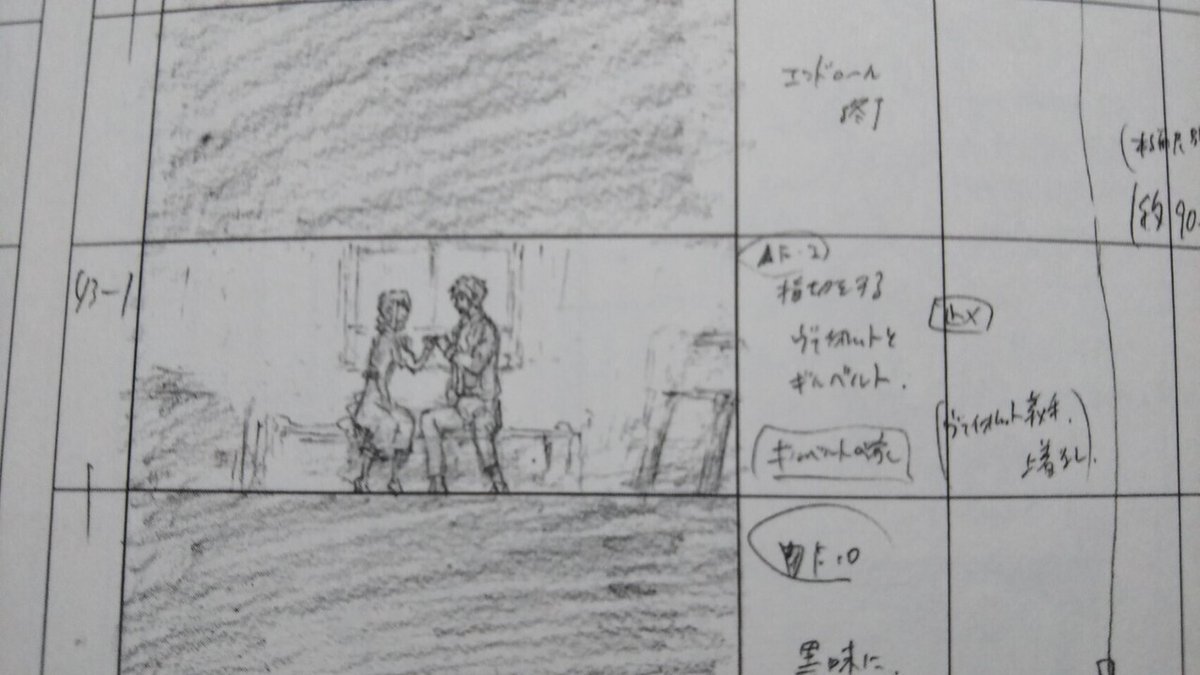
(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.160)
Q5「『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の世界の神はどこにあらわれているか?」
のふたつの答え
A5「ヴァイオレットの義手が動くというそのことにおいて」
と
A6「この映画の最後でそれまで働いていた〈神〉の力が〈去った〉と解釈することによって」
これらはどちらもすでに〈神〉の存在を前提としているが、A6は存在証明というよりはさらに別の〈可能性〉を孕んだ前提の上でなされている。
つまり〈問い〉の展開がさらに進んでいるのがわかるだろう。
しかし本論に則って展開を引き戻すとすれば、何も問わないのもいいのかもしれない。
つまりそもそもヴァイオレットの義手がなぜ動くのかを〈問う〉必要はない。
なぜならすべては無根拠であるのだから。
それが〈なにもなさ〉ということだった。
ただこう述べていたのだった。(第12節.ヴァイオレットの凍りついた「あいしてる」)
〈なにもなさ〉の「あいしてる」とはこれまでのすべての経験と既知の情報を殺し死に至らしめ〈未知のもの〉に出逢う瞬間のことだ。
それはひとつの経験からはじまる。
現実において何の意味もない〈なにもなさ〉の「あいしてる」――その徹底した無力を現実において思考したという経験――その唯一性だ。
言葉にすること概念化することで失われる〈なにもなさ〉――。
しかしその思考の経験という〈痕跡〉は残る。
その〈痕跡〉を証し立てるのが『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』という映画なのだ。
この不思議なフィクションからの誘い――〈エロス〉をかきたてる「あいしてる」は狂気への誘いだ。
〈もしかしたら〉と誘引させること。
これが思考の経験への入り口だ。
……フィクションからの「あいしてる」――ヴァイオレットの「あいしてる」がもたらす法外な経験とは――あの〈なにもなさ〉の絶えざる殺害と新しいもの――〈未知のもの〉の入れ替わりの無限の反復運動を凍りつかせて永遠にとどめて思考に刻むことだ。
さながら死からの〈復活〉を一回限りの出来事として歴史に残すように――。
〈なにもなさの〉という〈奇蹟〉のさらなる〈奇蹟〉――。
この〈経験〉――『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』という〈経験〉――ヴァイオレットへの〈エロス〉がもたらした思考の〈経験〉という〈未知のもの〉の〈痕跡〉――。
本論はこの〈ただの経験〉以上のものではない。それで尽きる。
では無根拠の〈なにもなさ〉から――これまでの思考の〈経験〉から――まったくの〈真空〉から――誘引された〈もしかしたら〉から――なんでもいい、たとえばこう問うてみたらどうか。
Q7「この世界の〈神〉として、私がその〈神〉だとして、その視点から、ヴァイオレットらに何ができるだろうか?」
この問いは〈不確定性〉が孕んだ〈可能〉となった〈不可能〉な問いだろうか?それとも新たな〈可能性〉の展開だろうか?
「Q7」のこの世界とはどの世界だろうか?この世界の〈神〉とは?私は?〈神〉?
さて、本当に最後だ。
まとめよう。
ヴァイオレットの義手を動かすためには私たちという〈外〉が――インタラクションによる〈奇蹟〉が――〈アガペー〉が――〈神〉の力が必要なのである。
α〈神〉=〈なにもなさ〉=〈カオス〉なのであるからこの〈神〉には何の根拠もない。
なぜ〈神〉なのか?は無根拠だということだ。
むしろなんでもよいがゆえに〈神〉なのである。
ただし私たちは、もし〈ただの「あいしてる」〉を、〈アガペー〉を受け取ったのであれば、すでに〈アガペー〉をおくったのではないか?
そうであるかもしれないのである。そしてそうでないかもしれないのである。
〈不確定性〉がなければなにもないのであるから、いや〈なにもなさ〉が〈不確定性〉なのであるから――その生成変化のトートロジーのトートロジーにすでにしてそうであるのであるから――やはり私たちは〈アガペー〉を――〈神〉の力を――ヴァイオレットにおくっていたのかもしれないのである。
一瞬の、刹那の、時間ではない時間――存在ではない存在としての〈神〉がヴァイオレットの義手を動かしたのかもしれないのである。
リニアではない、無時間的な〈神〉の力は決して認識することができなかったのかもしれない。認識することができないかもしれない。永遠に思い出せないかもしれない。しかし思い出せないことがあったのかもしれない。認識できないことがあるのかもしれない。
〈エロス〉
←
※神 ⇔ 神と交わるものたち
→
〈アガペー〉
※第13節.神と交わる女たち/ヴァイオレット/から/の「あいしてる」参照
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ↕〈外〉
ただの「あいしてる」(一方通行)
〈エロス〉
★ヴァイオレット ⇔ ギルベルト
〈アガペー〉
ただの「あいしてる」
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ↕〈外〉
〈エロス〉(一方通行)
→
☆私たち(〈神〉) ヴァイオレット
← 〈無根拠な「あいしてる」〉
(→)
(〈アガペー?〉)
いったいあのとき何が起きたのか?
私たちから〈解放〉されたヴァイオレット。
去ってしまった、切れたつながりの物語から
〈ただの「あいしてる」〉が無責任に放たれる。
〈無根拠な「あいしてる」〉が――。
私たちは彼女を見失う。
喪失から何が生まれるのか?
いや、はじめから?
すでにそこにあったものを〈神〉のちからと
〈アガペー〉と呼ぶのかもしれない。
そうではなかったか?
だからもう一度問うてみよう。
「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」
いま、
ここで、
その力を、
捉えただろうか?
捉えられただろうか?
エロスの滴りのなかに、
〈なにもなさ〉の充溢を、
とほうもないその無根拠を、
あの〈神〉を認識できるだろうか?
だれにもみつけられなかったわたしを、
生まれなかったわたしを、不要なわたしを、
存在しないわたしを、わたしが書かせたものを、
思い出しただろうか?そうであったかもしれない、
原初のあの〈アガペー〉を、始原の〈奇蹟〉を、
わたしたちが〈神〉のちからをおくるときを、
いま気づいたろうか?彼女のあいしてるに、
わたしたちがあの〈神〉であることに、
過去に向かうわたしたちのちからに、
未来に向かう彼女のちからに、
あいしただろうか?彼女を、
見えただろうか?彼女の
腕を動かすそのときを
ゆっくりとしずかに
ヴァイオレットが
はじめて手紙を
〈あいしてる〉
を綴るその
おもざし
のその
とき
を
━━━━━━━━━━
■ご意見、ご感想、ご質問、何でもお寄せください。
■Twitter
https://twitter.com/Yurugu_J
━━━━━━━━━━
