
ビジネスまっしぐらだった私が、デザインと人類学が重なる場所で気づいたこと
デザイン人類学という新しい流れ
人類学とは、人間の多様性を研究する学問で、ヒトの生物的側面と文化的側面を総合的に研究する。特に文化人類学は、他の文化を参与観察することで、自らの文化を捉え直す学問である。それは数字によって分析的に行われるものではない。日本のデザイン人類学の先頭を走る中村寛先生によれば「質的なことがらに溢れている人びとの生活世界をフィールドワークし、人と信頼関係を結び、彼らの叫びや言いよどみも含めた語りに耳をかたむけ、当人たちすら意識しない表情やしぐさや行動の微細な変化を観察し、言動の背後にあるものをつかみ、問いを立て」ることが、人類学のアプローチである。
この人類学が、デザインの領域で最近のキーワードになっていることを、私の周りのデザイナーとの会話だけでなく書籍や記事などの本数を見ていても感じられる。そして、私自身はこの領域にとても魅力を感じている。実は流行に疎く、新しいものを作ることはあまり好きではないが、このアプローチを通じたつくる行為、すなわち「デザイン人類学」にはワクワクしている。なので、本記事では、なぜ私がそう感じているのかを、いろんな視点から考えることを試みる。
一応領域を明示しておくと、ここでの「デザイン」という語句の意味は、狭義のそれの意味での意匠ではなく、広義の「問題の本質を発見し、それを解決するための設計をすること」とする。すなわち、エンジニアリングの対となるデザインではなく、アートの対となるデザインを意味する。
また、すでに市民権を得た「デザイン思考」とは異なる。それも共感的につくる行為であるが、人類学的アプローチは質的調査や参与観察をより深く実施し、哲学的洞察や認識論的反省を獲得することを目指している。
「すべてのデザイナーのかたわらに人類学者を――人類学者・中村寛」desigining
簡単な自己紹介
私は現在28歳で、もうすぐ29歳になる。京都大学工学部地球工学科都市工学を学んだ後、学部卒で鎌倉にある面白法人カヤック、株式会社リクルートでPdMを経験した後独立し、データ分析を得意として戦略構築や企画立案に複数携わってきた。いまは少しお休みをして、この領域に進むために日々勉強している。
わかるとは何か

まず、デザインという問題解決の行為は、問題の原因をわかった上で行われるか、もしくは問題をわかるために行われる。では、その「わかる」とは何か。
ここからデザインと人類学の関係が垣間見える。『人類学とは何か』の著者である人類学者ティム・インゴルドの"私たち"の世界の見方に関する洞察から考えてみたい。
人々によって感知されかつ演じられている世界は、彼らにとっては全面的に現実なのであるが、実際には、観念や信仰や価値から組み立てられる構造物であって、そうしたものがまとまって一般に「文化」と呼ばれるものが出来上がっているのだと、私たちは全知の権威を纏いながら宣言する。理性の光を浴びた私たちには、彼らが見ることができないものを見ることができるおかげで、私たちの世界を除いて、人間の世界はどれも文化的に構築されている。つまり、このように多様に構築されたものとは、一つの所与の現実の代わりになる偽物にすぎないのだ、と私たちは主張する。彼らの見方は意味の網の目に宙づりにされ、私たちの見方は客観的な事実に根ざしているというわけだ。私たちは、さまざまな人間の肖像画がかかった画廊の客であり、彼らは肖像画である。
つまり、私たちは客観的にこの世界をわかっていて、彼らは観念や信仰に応じて主観的に生きている。それは多様であるが、私たちが見えているものが唯一の現実で彼らのは偽物だと考えている。たしかに、私たちは以前より、そして彼らより、莫大な研究予算を持ち、数多の論文にアクセスできる環境がある。しかし、私が上記の文章を読んだ時、この「私たち」はわかっていて、「彼ら」はわかっていないのか、という疑問を感じた。ここでの「彼ら」とは、人類学のフィールドとなる、例えば"途上国"に住む方々のことで、「私たち」はそれを研究または閲覧できる"先進国"の人間、すなわち、ここにいる私たちである。
同時に、インゴルドはこのようにも書いている。
学者たちは学者でなければ理解できないことを説明できると公言する。(中略)私はそれに同意するものではない。(中略)決まった場所に他者を置いたり、「了解済み」として片付けたりしようとするものではない。むしろそれは、他者のいるところで分かち合うことであり、生きることにおける他者の実験から学ぶことであり、また人間の生がどのようななものでありうるのか、つまりその未来の条件と可能性について私たち自身が想像するものに、この経験を注いでみることである。私にとって人類学とは、こうした想像力と経験の関与を養分として成長するものである。
この「未来の条件と可能性について経験を注」ぎ、「生きることにおける他者の実験から学ぶ」姿勢を感じた作品がある。
先日デザインファームTakramさんの展示会に訪れた。完成品だけではなく、デザインプロセスを一般に公開していた。ノウハウを晒すということで非常に驚いたが、彼ら自身は真似できない価値があるという自信があるのだろう。もしくはデザイン領域の発展を切に願っているのか。本当に尊敬する。
そこで出会ったものが、文具メーカーKOKUYOさんの『HASA』。この制作過程にはもちろん緻密な計算など科学が取り入れられているが、同時に「この時代の人間にとってハサミとは何か」が研究され、表現されていた。実際にプロトタイプを何本も制作して感覚を試してみたり、家庭に訪問してハサミが家のどこにあるか、何本あるか、どのようなハサミが長く使われいるかを観察したという。まさにこれが人類学的アプローチである。
そこに置かれていた資料は民族誌のようで、もはや芸術であった。商品の展示会なのに人が流れず中々見れない、という状況がそれを表していた。

※designart展示会 にて筆者撮影
・『人類学とは何か』ティム・インゴルド
分断された認識に時々脅かされる

そもそも「わかる」という行為または状態はどのような過程で行われるのか。その前に、わかるための基礎的なプロセスである「分ける」を人間はなぜ行うのか、それによってどのような状態になっているのか。
「分かるとは分けること」とあるように人間は自らの経験と認識に基づいて、世界を分断する癖がある。そもそも、原初の人間は謙虚ゆえに、頼りない自分を認識して世界から分けることで、自らを変えていく自由を得た。
分断して選択を行うことで安心を獲得する。「自分の身体」「私たちの宇宙」「私たちの国家」などと自分のモノかの線引きをして、確実に自分のモノだという裏付けを欲する。ただし、「内」を明確することは同時に、「外」という切り捨てられるものをつくり、それを無意識的に自覚することになる。そして、認識に限界があることを知っているからこそ、その認識を広げたいと切実に願う。その欲求の結果、思想や科学が発展した。近年のインターネットやSNSでも、世界と知りたいという欲求がスクロールをさせていたり、もはやそれを刺激するアルゴリズムによって支配されているとも言えるだろう。
内にあるものを大事にしたり、外にあるものを考えないようにし、効率的にエネルギーを消費して生きている。そして、すべてを内だと認識したいが、現実では全ては手に入らないので喪失感を持っている。その結果、わかりやすいお金や権力に固執したり、逆に自分の手に入るモノだけを溺愛したりで、なんとか内にあるモノだけを見ようとする。そして、その無意識的な排除が、私たちが世界のほんの一部でしかないこと、それだけ頼りない存在にすぎないことを自覚させ、時々心を人質にして脅かしてくる。
思考のプロセス

次に、「考える」にはどのような過程があるのか。
Knowledge Brigdeの記事で分析されているように、イノベーションの研究等で思考のプロセスはたくさん研究されている。その中のGraham Wallasの『The art of thought』によれば、以下の4つのステージモデルがある。
Preparation:準備
Incubation :孵化
Illumination:照射
Verification:検証
簡単にいうと、(1)問題の特定と情報収集をした後、(2)一時的に寝かせて、(3)それを一貫した構造に仕上げて、(4)その構造を検証する、という流れである。その後にrecursion:再帰が含まれるものもあるが、多くの研究である程度一致している。
「2.孵化:一時的に寝かせる」と「3.照射:一貫した構造に仕上げる」を考える行為と捉えている人は少ない。思考のプロセスの一部であるが、意識的なコントロールができないので考えるという言葉がしっくりこない。だから、面白い。
「孵化」は制約から解放されて起こる
孵化の簡単な例としては、「鍵をなくした」「あの人の名前を思い出せない」といった時に、考えている間は思いつかないが、その後他のことをしている時に思いつく現象である。卵が温まって、新しい命が生まれる時のような、まさにそんな感覚から言葉が当てられている。
孵化の定義はSmith&Dodds(1999)によれば、「創発的問題解決の段階で、問題に対する初期作業後、問題を一時的に脇に置いておくこと」とされており、その効果は、意識的な制約から解放され、問題解決や思考の妨げがなくなることで、遠く離れた連想を見つけられたり、偶発的なヒントやデータを見つけられることにあるという。
「照射」はアハ体験。突然、一貫した構造になる。
照射という言葉は孵化に比べて馴染みがないが、言い換えると、洞察やインサイト、アハ体験とも言われる。
「準備」で論理的に集めた情報と、孵化で遠くから無意識的に集めた情報が断片的だった情報が一気に繋がり、突然一貫した構造になることである。実はこの記事もその瞬間があったから書いているし、たくさんの情報がある日繋がって興奮することは時々あるだろう。
Schilling(2005)によれば、照射とは「異質な心的表現間の予期せぬ結びつき」と表現されている。具体的には、スキーマが完成すること、すなわち、知識の枠組みが脳に沈殿することで、それ以後脳が省エネモードで認識できる状態になるということである。既存の結びつきが破壊され、もしくは破壊されなくとも、これまで結びついていなかったものの関係性という有機的な結びつきが新たな枠組みになった状態のことと理解している。「学習とは自己破壊である」という言葉もここに関連しているように思う。
洞察を得ることが大事だとした時に、いかにしてその瞬間を求める形・タイミングで迎え入れられるか。つまり、無意識的な活動をどう意図的に迎え入れられるか。
キャリアの良い展開方法に、クランボルツが唱える計画的偶発性理論がある。個人のキャリアの8割は偶発的な出来事から生じるという事実を背景に、その偶然を生かす人の特徴を5つ示している。好奇心、持続性、柔軟性、楽観性、冒険心が挙げられているが、まとめると、「新しい学びを続けながら、臨機応変な態度でわからないことでも楽しむ」ということである。
積極的受動性という態度も近い。受け身の立場でありながらも、意図的に状況を受け入れたり対応したりする姿勢で、自ら行動を起こすのではなく、状況の中で自分を調整し、流れに身を任せながらも積極的に関与する態度である。「開きながら待つ」というスタンスが、この二つに共通することであり、照射を迎え入れるということのヒントになりそうである。
「準備」の段階で仕入れるべき情報
前述の通り、イノベーションの研究では上記二つに焦点が当てられることが多い。でも、「準備」の段階にも大きなポイントがあるように思う。どのように問題を特定し、情報収集するか。実際、私自身がうまく思考できている時とできていない時で、この段階に大きな違いがあると感じている。スタートを切る準備ができているか、、ましてや観客席にいないか、ということを次に考えてみる。
・「超相対性理論」。特に「#19-#21考えることを考える」
・「創造性の心理学⑤|インキュベーションとインサイト」Knowledge Brigde
・『Creativity』 Mark A. Runco
・『The art of thought』by Graham Wallas
・「再帰的な事象についての心理学的考察」京都大学大学院教育学研究科紀要第49号 林 創
時と所と立場に応じた感覚がイシューを特定する
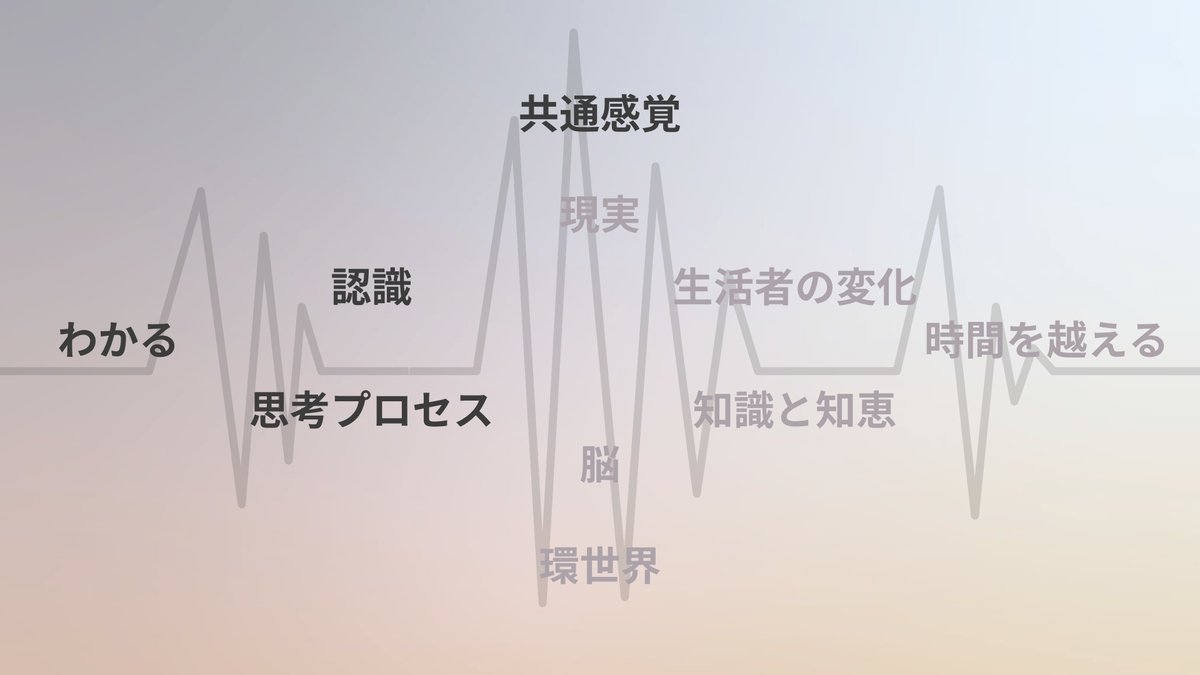
考えるために重要な「情報」。私は仕事柄もあって、情報の扱いに関しては比較的得意である。また、学生だった十年前より、大量の情報に簡単にアクセスできるようになった。しかし、その情報を適切かつ効率的に扱えているとは言い難い。情報の渦に巻き込まれていこともあるし、時には情報の海に入ることを恐れて情報収集を避けてしまうこともある。
そもそも情報を通じて何を獲得したいか。
おそらく一つは「知識」だろう。ここでは知識について分けることで考えるデカルト的知性である「クリティカ」とそれに対する概念の「トピカ」を浜崎洋介さんの論考を参考に考えてみる。
まず、クリティカが意味する知識とは、確実にして明証的な認識のことであり、真らしく見えるものはただそう見えるにすぎないもものとして排除される。
科学の世界ではその知識を駆使して進めることが重要である。そこで得られたものを科学的真理と呼べるが、この世界の真理を科学的真理しかないというのは、間違っている。科学とは科学的方法によって物事を考える学問にすぎない。これが今日、わかるの意味が小さいものに圧縮されているひとつの要因であろう。
なぜここまで科学的真理の存在感が大きいのだろうか。日本に焦点を当てて言えば、「神国日本」「大和魂」「日本人の器用さ」などを信じた末に訪れた惨めな敗戦が、信条の放棄、すなわち科学的真理の強化につながったという説がある。科学以外のことを信じた結果、より強い科学兵器を持つ国に敗れて、そこに原因を置いた、と少し飛躍的ではあるが、私は理解している。
この「クリティカ」に対してイタリア人ヴィーゴ「共通感覚」=「トピカ」の重要性を唱えた。ギリシャ語のtopos(場所)が語源であり、「話題の領域」や「視点」から派生して、時と所と立場に応じた五感の感覚である。そしてトピカは、どのような対象に対して真面目であるかを見極める力として重要であるようだ。ビジネスマン的に言えば、イシューを特定することだと言い換えられるかもしれない。
時と所と立場に応じた五感の感覚というのはどういうことか。その概念が示したいこと同様に明確に表すことができないが、例えばこうである。「甘い」という言葉は個別感覚=味覚である。ただ、共通感覚を通すと、「甘い音色」「甘美な情景」「甘言にのってはいけない」「考えが甘い」「人に甘える」など、時間的感覚、空間的感覚、倫理的判断まで応用される。
共通感覚とは、「sensus communis」の訳であるが、他者とcommonな感覚=常識という意味に加えて、五感で感じるcommonな感覚とも解釈すると上記の意味が理解しやすい。
チェスタントンは「狂人とは、理性以外のあらゆるものを失った人である」といい、アーレントは「動物的な五感を万人に共通する世界に適合させる感覚として共通感覚があったが、それを奪われた人間は所詮、推理することのできる、そして結果を計算することのできる動物以上のものではない」と言っている。また、クリティカの養成に目を向けてきたせいで、生き方に対する感受性や倫理的判断を失ったエリートが生まれている可能性はあるだろう。
上記の言葉は強烈なものであり、そこまでは思わないにせよ、理論武装された時に感じる畏れを含む寂しさや、何か大事なものが抜け落ちている感覚は、仕事の中で感じることは時々ある。
・真らしいもの」を見極める力―「クリティカ」と「トピカ」浜崎洋介
・『人間の条件』ハンナ アレント
・「大学における一般教養の役割:トピカとクリティカの観点から」 滝脇知也
三人称的な「認知」ではなく、一人称的な「行為」
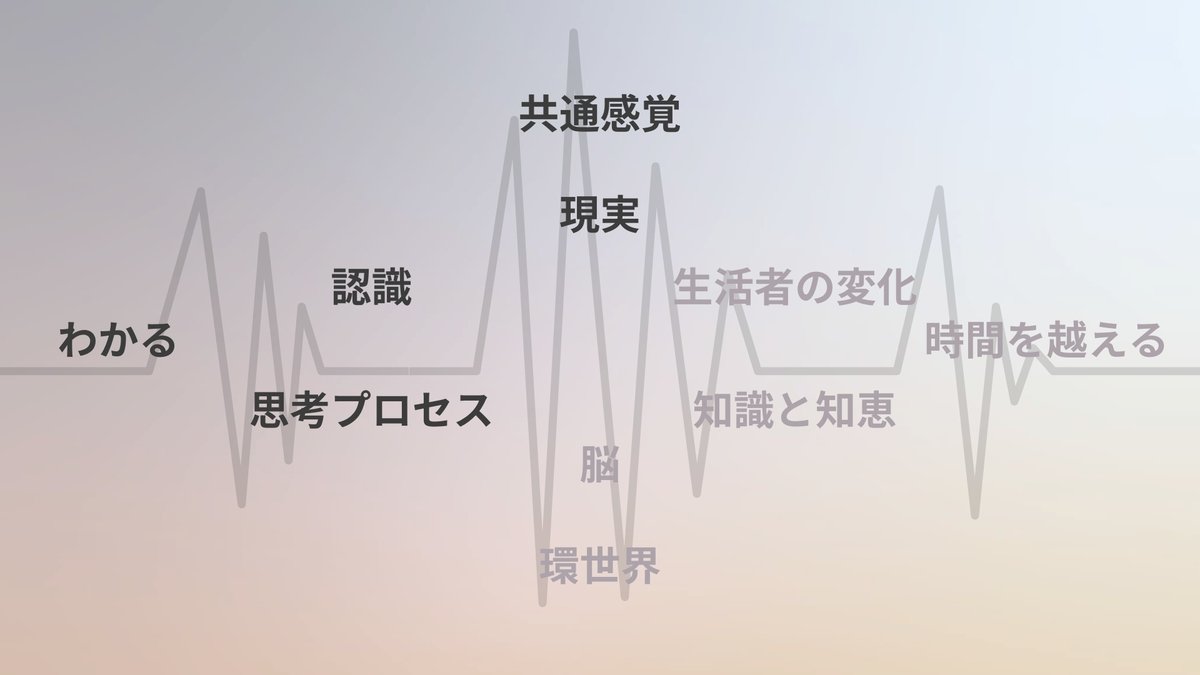
上記では情報を得た先にある知識の分類に触れた。ただ、その情報源は何なのか。言うまでもなく、この世界で起こっていることである。すなわち「現実」について考えてみる。
2021年に亡くなってしまった木村敏という精神科医は人間存在を探究し、「あいだ」という概念を使って人間学を構築した。その中で、「リアリティ」と対をなす「アクチュアリティ」という概念は、科学の対象や今日語られている物事から視野を広げてくれる。
リアリティ=Realityも、アクチュアリティ=Actualityも現実という意味であるが、ここでは、前者は「実在するかのように感じられる状態、現実」で、後者は「進行しているコトの中で、身をもって経験する現実」のことと考える。語源の「もの、事物」を意味する「res」と「行為、行動」を意味する「actio」を想像してもわかりやすいだろう。もしくは、個人的な感覚かもしれないが、「事実」と「現実」というイメージが近い。
そうした場合に、前者の観点は、相手をきちんと対象化して因果律を明確にし、科学的または分析的に扱う。その結果、過去形、物質的、客観的な認知を獲得する。三人称的な認知である。
一方で、後者の観点は、主体と客体を分離できず対象化できない。その結果、主観的となり、認知というよりは関係性のある行為となる。それは三人称的ではなく、一人称的で現在形である。
少し単純化された例で考えると、人類学者が祭りを研究するときに、その歴史や意味合い、経済効果などを記述するとリアリティになり、その過程で現地の方々に溶け込み、さらには祭りに没頭するという経験の中で感じている現実はアクチュアリティである。
そのように考えてみると、文字や画像で過去を映し出すリアリティばかりが流通する世の中であるが、あらゆる現象はリアリティの前に無数のアクチュアリティがあることがわかる。
さらに、一種の現実としての生命を考えてみると、アクチュアリティとしての生命は変化を基礎としており、それゆえに絶対的な単独性の感覚がある。さらに、その単独性によって孤独な生命の感覚として閉塞されることなく、アクチュアルな生命感をチャンネルとして、無限に多くの他者達、あるいは生きとし生けるものすべての間に開かれた連帯感を感じ取っている。つまり、単独であり連帯である。森の中に入った時に感じる孤独感と世界と繋がったような超越的な恍惚感は、これに根付いていると私は解釈している。
少し難しくなり過ぎたが、ここで考えておきたいことは、科学的発展はリアリティの存在を強化しているが、反対にアクチュアリティの存在を無視する傾向にあるということだ。そして、それは科学的真理を全ての真理と捉えていることに似ている。個人的には、それには限界と寂しさを感じていて、さらにはその事実を普段意識できていないことに危機感がある。(一方で、インスタグラムのストーリー等はアクチュアリティの表現を促してくれていると思う。)
・・「第16回:アクチュアリティとリアリティ」小田亮 首都大学東京・都市教養学部人文社会系社会人類学分野・教授
・「共通感覚=常識について」
・「1536夜 『あいだ』木村敏」松岡正剛の千夜千冊
思うことより遥かに多く感じている

知識と現実についての広がりを展開してきて、随分遠くまで冒険した。次は近く、いや内部の脳から考えてみる。思考も感情も、もちろん脳を通して生まれている。しかし、それはどのようなプロセスなのか。感じたものが全て存在しているのか。逆に、存在しているものを全て感じているのか。
私たちは、見たものがそこにあるものと思っているだろうし、何か感情の変化を感じた時その原因を特定したり、感情を表現したりする。すなわち、外にあるものを画一的に捉えていると思っていたり、その感覚を信じている。でも、実は脳という器官はありのままを写す鏡のようなものではなく、エラーを含む変換器になっている。
まず、五感や筋肉からの反応は「感覚神経」、臓器からの反応は「自律神経」を通して脳に送られる。この身体からの伝達をボトムアップ処理という。それとは逆に、記憶や予測という脳からの伝達をトップダウン処理という。ボトムアップ処理に対して、その生理的状態になっている理由をトップダウン処理で記憶や予測から確からしいものを推論する。この時のズレを予測誤差や自由エネルギーといい、それが最小化されるようにトップダウン処理が行われる。(もちろん、逆の順もあるし、相互的に作用している。)
「情動(=Emotion)」と「感情(=Feeling)」の定義から考えるとわかりやすい。情動とは生理的な反応であり、例えば、血圧が上がるなど主に内臓環境の変化のことをいう。一方で感情は、幸せや怒り、悲しみなど日常的によく使う言葉の意味であるが情動と対比できる定義においては主観的な意識体験のことで、情動と外的な状況を加味して主観的に感じている意識のことである。例えば、情動が同じだったとして、感情は異なりうる。情動というボトムアップに対して、トップダウンの推論があり、その結果感情が生まれる。情動は快・不快と危険・安全を早い経路で察知し、その後思考と結びつき因果推論した結果が感情である。
感情だけでなく、「見る」という行為も網膜像のボトムアップと脳の推論で成り立っている。全てのものが見えているわけでなく、脳内でイメージしたものが見えている。そして、脳内イメージと異なるものが誤差として認知される。ぼーっとしていても家にたどり着けるのはこれだからである。解剖学のある研究では、目の奥の視床から脳の視覚皮質へ感覚情報が送られるが、実際にはその逆方向の接続が10倍あることがわかっている。その接続が何を意味しているかは議論の余地があるが、「何が見えているか」の情報より、「何を見ようとしているか」の情報の方が多い可能性が十分にあるということだ。
ものを手に取るなどの「運動」も、取った後の筋肉等のトップダウンの感覚をイメージしながら、リアルタイムでの筋肉等からのボトムアップの感覚の誤差を反射弓が最小化することで取ることができる。逆に、自分でイメージできないもの=トップダウンの予測ができないものは、うまくできない。自転車に乗るのを覚える時もこのトップダウンの感覚を何百回のトライアンドエラーによるボトムアップの感覚の処理で獲得しているのだ。感情に関しても、経験したことがないことは推論、共感がしにくいことは、ここから納得できる。
何かを感じる時、捉える時、結果と原因を同時に感じているわけではなく、それが「推論」で成り立っているということであるので、その原因と結果の推論が間違うことがある。怒りを感じているが、本当の怒りの原因がわからないなどと。私は空腹が最大の敵で、お腹減っている時に何かが起こるとすぐに怒りを表現してしまうのだが、これは空腹の生理現象を間違って目の前のことに原因を推論して、怒ってしまっているということである。
実際に身体で感じたものとそこからの生まれる感情や思考は、変換器を通されて異なるものになる。つまり、どれだけ必死に想像しても、感じたいものしか感じられないし、見たいものしか見えない。だとした時に、なにかをつくる時、考える時、机に座って分析的に考える だけでは難しそうである。もっと感覚器官を利用する、人類学的に言えばレヴィ=ストロースの『野生の思考』で、「アクチュアリティ」的に一人称で体感しないと、「感じられない」「見えない」「わからない」ことがたくさんあるように思う。
・『脳の大統一理論: 自由エネルギー原理とはなにか』乾 敏郎 , 阪口 豊
・「#29脳科学で理解。私たちは「何を」見ているのか(ゲスト:乾敏郎)」 a scope ~リベラルアーツで世界を視る目が変わる~
・「能動的推論とAI」緒方壽人 (Takram)
・「世界に変えられてしまわないために」緒方 壽人 (Takram)
・「予測する脳」 緒方 壽人 (Takram)
・「生物から見た世界〜「環世界」とは何か」緒方 壽人 (Takram)
そもそも認識できる世界が異なる

ここまで、考えるプロセスの準備を起点にして、情報を得た先にある五感の感覚を共にした知識、情報源となる主観的で現在形の現実、それを処理するための脳の処理を展開してきた。
そして、最初の問いに戻る。「私たち」はわかっていて、「彼ら」はわかっていないのか。上記の話が一つに繋がる話として、世界の認識の違いを表す「環世界」という概念がある。
私はチワワを飼っているが、そうでなくても犬が私たちより嗅覚が良いということは全員が知っているだろう。手の中に餌を隠しても可愛い顔をして寄ってくる。そのような時、私たちは「嗅覚が強い」「鼻が強い」という。「強い」というと匂いをより大きな刺激として受け取っているということであるが、実はそれだけでなく感じられる匂いの種類が多い。
大気中には約四十万種の化学物質の匂いがあるが、人間に嗅ぎ分けられるのは、そのうち約千種類に過ぎない。一%未満である。
百年ほど前、生物学者のユクスキュルは、、「それぞれの生物がそれぞれの感覚や身体を通して生きている世界」を、ドイツ語のUmgebung(環境)とWelt(世界)から「環世界 Umwelt(ウンベルト)」と名付けた。「環」という文字はイメージしづらいが、「環状線」や「外環」など取り囲むイメージで、その生物を取り囲む主観的な世界ということである。
國分功一郎さんの『暇と退屈の倫理学』によれば、人間が認識できる世界は十八分の一秒で、映画のコマのスピードはそれ以上の速さで行われているから暗転しているのが認識できない。視覚だけではなくて聴覚も同様にそれ以上の振動を捉えることができない。でも、それは他の動物にとってはゆっくりな世界で、また他の動物にとっては速い世界である。ハエは人間の十倍以上の速さ(百五十分の一秒)、カタツムリは人間の半分以下の速さ(四分の一秒から三分の一秒)で知覚している。私の推測ではカメやナマケモノはもっと遅い。
時間の違いを想像するだけで世界の違いを感じられるが、五感全てが動物によって異なる。そもそも五感が人間の特性である。例えば、ダニは視覚がなく光覚でいい場所に登り、酪酸のにおいがあれば飛び込み、三十七度という温度で成功を認識し、体毛の少ない皮膚組織を触覚で探し吸血を開始する。これが順に行われ、これ以外の処理は行われない。これがダニの環世界である。
動物との違いを考えてきたが、人間も遺伝や生活する地域や文化で発達する感覚が異なるとしたら、一つとみなされている世界は一つなのか。上記の脳科学の話から、人間は全てが見えているわけではなく、各個人が見たいものを見ているということであれば、経験によって見えている世界は異なる。この意味で、世界は生物の数だけ存在する。
現実の出会い方と相槌の変化
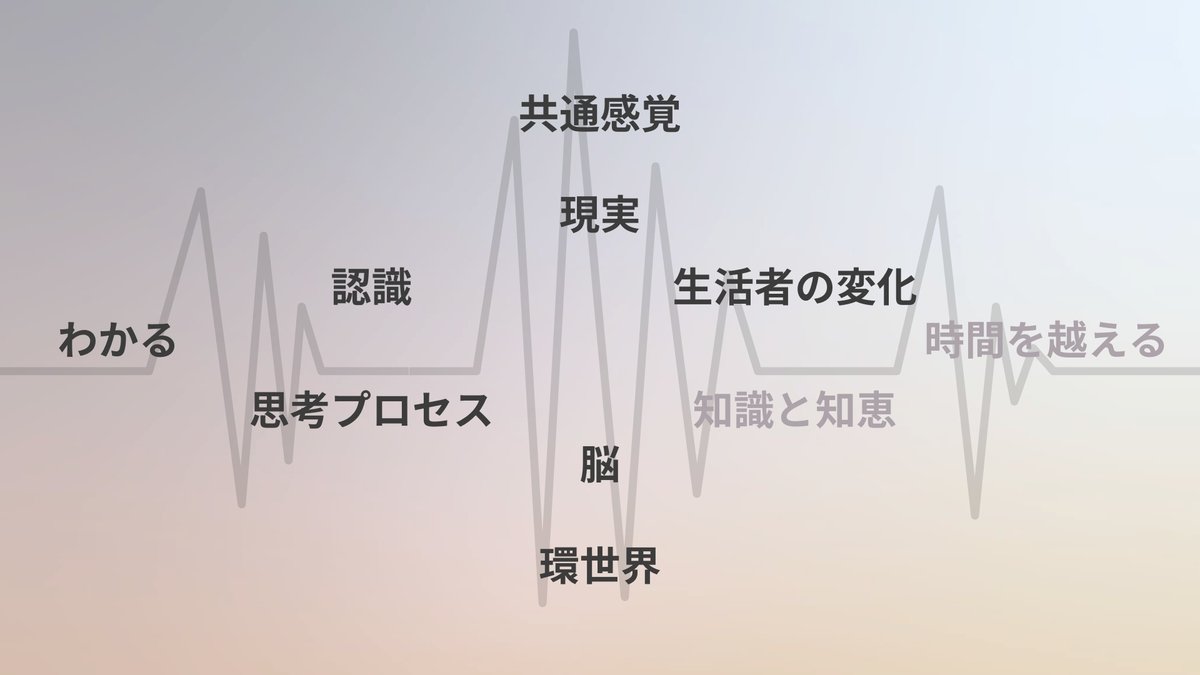
ここまでの章は、特定の科学的分野から考察してきた。ちょっと堅苦しいので、身近な変化からなぜデザイン人類学が必要とされる社会になってきているのかを考えてみる。『言語表現法講義』という本は名の通り、文章の書き方についての本であるが、そこに書かれている非常に興味深い二つの考察から変化を捉えてみる。
「ためす」と現実との出会い方
「ためす」には二種類あるという。「試す」と「験す」。後者を使う人はほとんどいないだろう。前者は「何か自分以外のものを使ってあるものを検証する」ことで、後者は「自分を使って何かを検証する」ことである。風の強さをお天気アプリで確認するのと、外に出て確認することの違いである。
インターネットが発達し、体感する前に現実との出会う。誰かが身体で出会った現実とインターネットを通じて私は言葉で出会う。そして共感したり、ヤイヤイ言ったりする。でも、本当に出会うには、私が身体で出会い直さななくてはならない。
つまり、頭先行で現実に出会うようになり、身体で現実に出会うことを省略できるようになったということである。
対立を回避する相槌
1990年前後で相槌の変化があったらしい。「あら、そうなの。」から「あ、そうなんだ!」に変わった。確かに私の周りでは、実感としても後者を使う人が多いように思う。
一見、そこから何か大きな示唆を得ることは難しいがこういうことだ。変化前の「あら、そうなの。」は「自分の考えは違う」ということが含まれている。一方で、変化後の「あ、そうなんだ!」は「相手の判断を尊重して、踏み込みません、私が勝手に納得しているだけで、私にも踏み込ませません。」という半独り言になっていて、対立を回避している。
ずかずかと相手の内面に入り込んだり、逆に入り込んだりすることに苦痛を感じるようになっている。対話をしよう、という流れはここからかもしれない。また、その原型は親にかまわれすぎた一人っこの心的状況だという。ここで、社会構造の変化が現れていることは非常に興味深い。
平野啓一郎さんが唱える「分人」という概念がある。一人の人間がひとつの「個人」ではなく、状況に応じた複数の顔を持った「分人」であるということである。これは上記と関連しているように思う。人が入りこんでもいい深さと自分しか入り込めない深さがあり、前者の深さは二重底のお弁当の具を変えるように、状況に合わせて入れ替えている。
自分と殻があるので、言葉と自分の関係も一対一ではなくなり、断定的な強い文章が好まれなくなってきたということもここに関連している。筆者が対象に言及しているが、読者をあまり意識しない、説得しようとしない、"フェミニン"な文章が好まれるようになってきたようだ。
つまり、この二つの考察をまとめると、他者との対立を積極的に回避するようになり、身体で現実に出会いにくくなったということである。
他者と深く共感することが減り、自分の身体感覚の記憶が少なくなったとするなら、脳のトップダウン処理がうまくいかない。すなわち、うまく推論できなくなる。もちろんもっと複雑な話であるが、もしデザイナーにもこの傾向があるとするならば、問題をきちんと認識することが難しくなっている。それ故に、人類学的アプローチで問題をきちんと五感で認識することが必要であるということである。
「知識は武装し、統制する。知恵は武装解除し、降参する。」

どのような情報を、どのように体感して、何を獲得するか、その結果の「わかる」とは何か、ということを考えてきた。これまでの思索に一本の筋を通す言葉を冒頭と同じ本『人類学とは何か』から引用する。「知識」と「知恵」に関する言葉で、非常に大胆に美しく表現されている。
知識はモノを固定して説明したり、ある程度予測可能にしたりするために、概念や思考のカテゴリーの内部にモノを固定しようとする。(中略)
知識が与えてくれるのは力、統制力および攻撃に抵抗する免疫力である。しかし知識の要塞に立てこもれば立てこもるほど、周りで何が起きているのかに対して、私たちはますます注意を払わなくなる。(中略)
それとは逆に、知恵があるとは、思い切って世界の中に飛び込み、そこで起きていることにさらされる危険を冒すことである。(中略)
知識は私たちの心を安定させ、不安を振り払ってくれる。知恵は私たちをぐらつかせ、不安にする。知識は武装し、統制する。知恵は武装解除し、降参する。知識には挑戦があり、知恵には道があるが、知識の挑戦が解を絞り込んでいくその場で、知恵の道は生のプロセスに対して開かれていく。(中略)
科学によって伝えられる知識に、経験と想像力の解け合った知恵を調和させることが人類学の仕事であると、私は信じている。
まさに私がここで考えてきたことは、「科学によって伝えられる知識に、経験と想像力の解け合った知恵を調和させる」ことだ。考えるプロセスにおける孵化と照射。知識における時と所と立場に応じた感覚。情報としての一人称的で主観的で現在形の現実。脳科学的な分析としての知覚の仕組みと、その結果としての環世界。
「時間を越える」ものをつくりたい

最後に、私は人類学的アプローチが社会がより豊かになるために必要とされていて、そこにチャレンジしていきたいと思っている。
『ROOTS OF FUTURE』というイベントの記事で書いた通り、デザイナー太刀川英輔さんはデザイナーの目標は「時間を超えること」。すなわち、普遍、不変であること。本当に良いものは形は変わらなくて良いからサステイナブルである。美は人類史よりも長い歴史を持つ。花は美しい。しかし、それは人間のために美しいのではなく、虫が寄ってきたくなる形を、人間が美しいと思っているに過ぎない。
と仰っていた。
流行に興味がない私は時間を越える商品・概念をつくりたい。デザインしたい。そのために、科学はもちろん、文化の歴史や人間の認識を含む人類について深く学ばなければならない。その上で、簡単にアクセスできる知識だけではなく、五感を持って体験し、三人称的な事実だけではなく一人称的な現実を共有することが重要だ。そして、時間を味方に開きながら待ち、環世界を行き来することで、何かをつくりたい。
その一歩として、この記事は経験と思考、複数の学問領域を往復して作成しようと取り組んだ。また、一部の先進的な企業がこういうアプローチをしているが、生活者としての私としてはまだそう感じられるものが少なくて寂しい。だから、そのような方々の仲間になれるように、学習と制作を往復していく。
影響を受けた資料
各章で引用または参考資料を記載したが、それ以外にも影響された資料がたくさんあり、その一部を記載する。私はデザインに対する人類学的アプローチがなぜ必要とされているのかを展開したので、デザイン人類学の探究は以下をご参考にどうぞ。
・松村圭一郎さん、レヴィ=ストロース、アルトゥーロ・エスコバルは議論の中心にいる方々なので、文化人類学に踏み込む方はぜひ。
・また、そもそも、この記事を書くにあたっての視点を大胆に動かすことの楽しみや、哲学的な感覚思考はそれぞれTakramの渡邉康太郎さんと『風の旅人』から影響を受けています。
・アラスカで研究されていた星野道夫さんや、社会学者の岸政彦先生のアプローチも、まさに知恵を体感できて勉強になります。とても大好きな二冊。
・母校の入学式における謝辞の「真美善」のお話は、四半世紀前のものなのに、まさに今回の話と重なるところが多い。
「学部入学式における総長のことば」 平成11年4月9日 総長 長尾 真
*本記事で触れた内容について、修正すべき点があればお知らせいただけますと幸いです。また、一緒に学びたい、仕事を依頼したいという方はプロフィールのリンクからお気軽にご連絡ください。
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!

