
前々から気になってた本ですが、
本田哲也 さん著『 ナラティブカンパニー』読み終わりました📚
YONEYAメタリックプリントを始めるにあたって社内で話し合いをしてきました。
今までは、
すでにお付き合いのあるお客様や、そのつながりからいただいたお話を形にする(=印刷する)のが、おもな仕事でした。
しかし、これからは違います。
請け負いをメインとして来た弊社としては、全く初めてのチャレンジをすることになります。
これまでとは違うアプローチで、
これまでとは違うお客様に向かって、
これまでとは違う機械を使って、
これまでとは違うサービスを提供する。
この局面を迎え、
我々はどういう心づもりで取り組むべきか、
どういう思いでお客様に接していくのか、
という「こちら側」の腹落ちがなかなかできません。
そんなときに触れたのがこちらの本でした。

ナラティブとは
◆ナラティブとは物語的な共創構造である
◆「共体験」「間合い」「自分らしさ」
◆「ナラティブは企業価値を最大化し企業を成長させる」
本文中、いくつかの実例を示されたところで感じたのは、
かっこいいブランドCMや、ホームページ上でのストーリー仕立ての紹介が、いかに見る側に伝わってないか。
いや、正確には「伝わってるかもしれないが、見る側の共感やアクションにつながってない」ということでしょうか。
互いに同じ価値観を共有しあえる関係性を築き、
感情的な距離を含んだ良い間合いで、
裏表のない一貫性のある行動を、
終着点を決めず永続的にとることで、
互いに価値を生みあうことができる。
ということだと理解しました。
ナラティブ実践のステップ
一番最初にあったのが「パーパスの設定」。つまり企業やブランドの存在意義です。
―弊社でいえば、メタリックプリントを「何のために」「誰のために」展開していくのか―
社内でこんな話をすることはこれまでほとんどありませんでした。
今回、なんとなくそんな話をしたかもしれません。
けれども、もっともっと深堀りした、突っ込んだディスカッションが必要だと痛切に感じました。
この「パーパスの設定」がナラティブの起点になると、ナラティブの目的ともいえる「パーセプションの形成」を目指すことになります。
つまり「認知だけではなく、認識の変容」。知っていただくと社会で、世の中で何が起きるか、何が変わっていくのか。
弊社でいえば、メタリックプリントがメジャーになることで「印刷と言えばメタリックプリントが当たり前」という世の中になったらいいな、という野望(といっていいものかどうか)が、これに当たるのかもしれません。
さらにこのあと「ナラティブスクリプトの作成」や「効果の測定」など、全部で5つのステップで実践をしていくことを本書では示します。
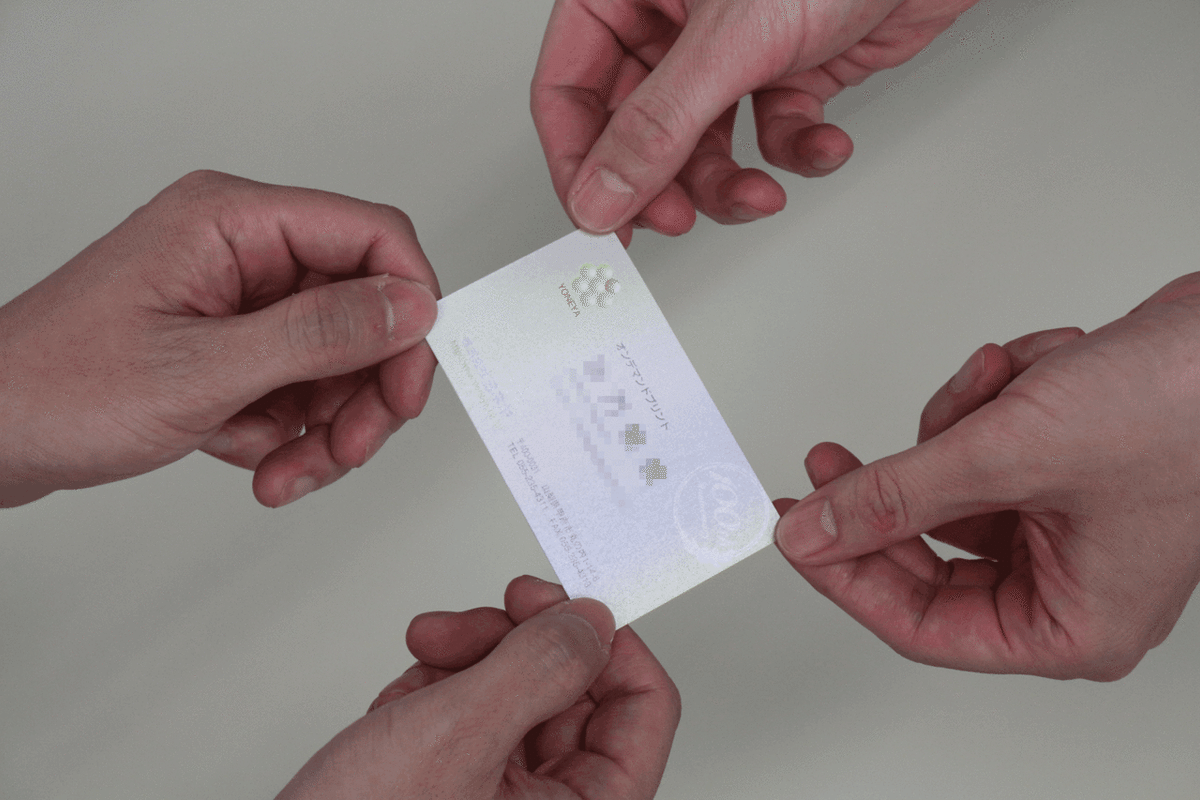
スタートアップにこそ必要なナラティブ
最後にこのように訴えたところに強く惹かれました。
言い換えれば、「ワクワクするような物語の力」と「認知されてない状況下で好ましいパーセプションを形成する」というナラティブが、企業やブランド、サービスの方向性を決める、ということでしょう。
YONEYAメタリックプリントの今後の命運を決めるといっても過言ではない、と勝手に意気込んでいますが、もっともっと読み込んで、弊社なりのナラティブスクリプトを作って、しっかり活かしていきたいと思います。
YONEYAメタリックプリント、どうぞご期待ください。
