
在宅介護と地震防災 ~介護者がつくる落とし穴と対策
昨晩はこちら神奈川県でも緊急地震警報が鳴り、肝を冷やしました。酒匂川の方には厄介な断層帯があるので、あの辺りの地震はたしかに怖い。南海トラフ?!な宮崎の皆さまと似たようなモードになっております。
そして本日、仕事の帰りにドラッグストアに寄ったらすでにトイレットペーパーが払底しており、日本人の伝統芸かな?と思ったついでに、そういえばこの話は書いてなかったな、と気づきまして急遽エントリー。
地震の際、命の分かれ目になるのは実は家具である、という話です。
在宅介護の際に移動する家具、それはベッド
高齢になり、在宅での暮らしが徐々に危なっかしくなったとき、寝室が2階にある方は徐々に1階に移動したほうが良い場面が増えてきます。特に、寝室は上にありながら、トイレが1階にしかないような場合は、転倒リスクを考えて、こちらとしてもそれをお勧めすることが多い。
特に夜間の頻尿などで頻繁に階段昇降をする状況は、試行回数が多いマイナス効果のガチャ(クジ引き)となってしまいます。そしてADLの低下に比例してその確率が上がる。
手すりなど、環境面の配慮でその確率を下げることもできるけど、あくまで2階で寝るメリットと天秤にかけて判断すべきことですからね。
そして、では1階に寝室を移動しよう。となったとき、寝具(ベッドを導入することが多いでしょうね)のレイアウトを決める際には介護者も関係します。というより、率先して決めていることも多いです。
さて、そんな寝室に、テレビや洋服ダンスなどを置いている方も多くいらっしゃいますが、そのレイアウト、利用者さんとの位置関係は本当に大丈夫ですか?
ガルとカイン・・・単位時間あたりの速度と距離の変化量
地震の揺れの大きさは、一般的に震度というもので気象庁から公表されておりますが、この震度、今はその場所での加速度と波の周期から割り出す仕組みになっているとのこと。以前は気象庁の中の人の体感だったらしいです。
その加速度の単位として、地震動についてはGal(ガル)という単位を使っております。何でもガリレオ・ガリレイの名前が由来らしいです。国際単位系では加速度はm/s2なのですが、ガルはcm/s2。
9.8m/s2で表される重力加速度は、980ガルとなります。
そこで過去のデータを見てみましょう。

厳密にはこれXYZ軸、3方向の合成波だと思うのですが、大雑把に言って大きい地震の際は地球に引っ張られるのと同等から3倍の加速度が瞬間的にかかるということですね。ちなみに2008年の岩手・宮城内陸地震の震源では、4022ガルが測定されたそうです。
この危険性を介護福祉士養成校などでお伝えするときには、ベッドの横にある家具をベッド直上の天井に吊るして、それを落とすイメージで、と言っております。そのくらいの勢いで、家具は転倒するだけでなく、ときには横に吹っ飛んでくるのです。
ただ、加速度はいまいち直感的にわからない。なので、kine(カイン)という単位を使って揺れを考えることもあります。
1カイン(cm/s)は1秒間に1センチメートル動くこと。つまり秒速ですね。
こちらのほうが体感的にわかりやすく、建物の破壊状況などとも一致しやすいという説もあります。
1995年 阪神淡路大震災(鷹取) マグニチュード7.3 169カイン
2007年 新潟中越沖地震 マグニチュード6.3 136カイン
2011年 東日本大震災 マグニチュード9.0 106カイン
2016年 熊本地震(益城町) マグニチュード7.3 94カイン
さらっと書きましたが、秒速1.7mですからね、阪神・淡路大震災の揺れの速度。時速にすると6km/hくらいだからたいしたことないように見えるかもですが。でもあなたの足元が、1秒おきに1.7m動いて戻って動いて戻って、の速さで揺すられる状況を想像すると、嫌ですよね。
というわけで、リアリティのある地震の揺れの話について書いたところで本題です。
倒れなければ、むしろ誰かを助けうるのが家具
レスキューに携わる方々の経験則として、住宅が崩壊したケースで助かった人がいた場所として知られているのが、三角空間と呼ばれるところ。家具などに落ちてきた梁や天井が引っかかることで生まれる、斜めの空間です。
先ほど、寝室の家具のレイアウトについて書いたのはこの話もあるのです。
簡単に潰れないだけの強度のある家具であれば、それが倒れないとするならその家具の脇の空間は、むしろ人を守ることになります。
なので、あまり高くない家具を、倒れないようにしたうえでベッドに平行に置くことは、実はおすすめできる話になるのです。
家具の固定は、コスパが高い耐震のくふう
というわけで、介護のための住環境整備に関わる人間としては、特に寝室と普段の居場所となる空間の、家具のレイアウトの判断とその固定について、介護者となる皆様にもチェックをお願いしたく思うのです。
そして、固定はできることなら、家具の上の方を金具でネジ止め。

ただ、家具の天板はあまり強度が出ない(だいたいが空洞になっている)事が多いので、側面の板の直上を狙って金具を付けます。そしてそこに壁側の下地が一致することはまずないので、補強板などで調整が必要になる。


こんな感じです。手すりの取付の技術と必要な技術がおおよそ同じなので、こちらとしては手すり工事と合わせてご依頼をいただけると、ありがたい業務でもあります。
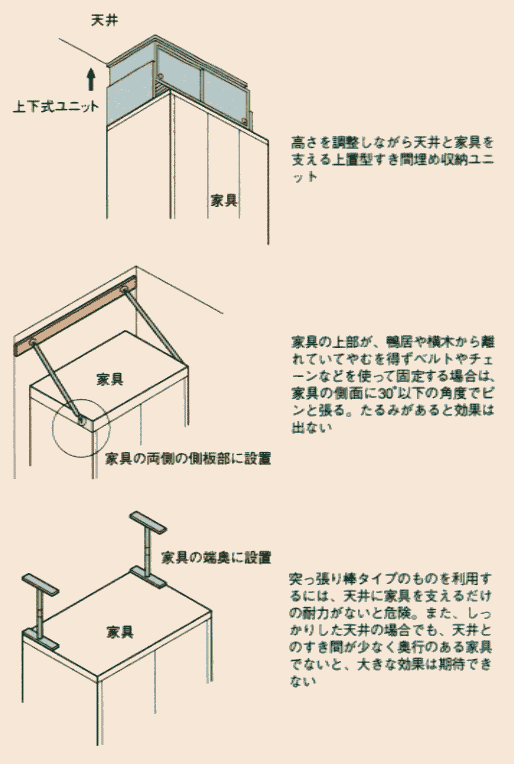
要注意なのがこれらの対策。特に、天井突っ張り棒は、天井の強度を頼るという点でちょっと怪しい。レンタル品の天井突っ張り手すりが、たまに問題を引き起こすことと同じですね。
できることなら、家具の上の面を壁に直結するのが、ベストです。
でも、こちらの過去のデータを見ていたら、こういう苦しい事例もありました。

壁ではなく襖だと、ネジ止めするのは鴨居しかないのでしたが、家具はそれより低い。なので固定に棚受けを使ってました。
これで、いきなり吹っ飛んで来ることはないとは思うのですが。こういった和風住宅の間取りの、襖で仕切られた壁の弱点はこれかもしれないですね。
完璧に仕事をやれる条件が、いつもあるとは限らないのが現場なのです。でも、やらないよりはずっといいとは言える。
せっかくのタイミングですし、ご利用者さんの介護ベッド周囲の家具について、在宅介護に関わる皆様には、改めてチェックしていただければと思います。
また、リスクとベネフィットだけではない、コストを交えたリスク論について、以前こちらに書いたのでご興味のある方は是非。迷う時の判断のよすがになります。
また、ちょっと古いサイトですが、先程の図はこちらからの引用です。たぶん阪神淡路大震災のあとの教訓をまとめたものが、消防庁のサイトにありました。
ちょっと見づらいですが、金具での固定の際の、引き抜き強度の目安など、こちらのお役立ち情報がありました。
ということで、お役立ち時事ネタでありました。
いいなと思ったら応援しよう!

