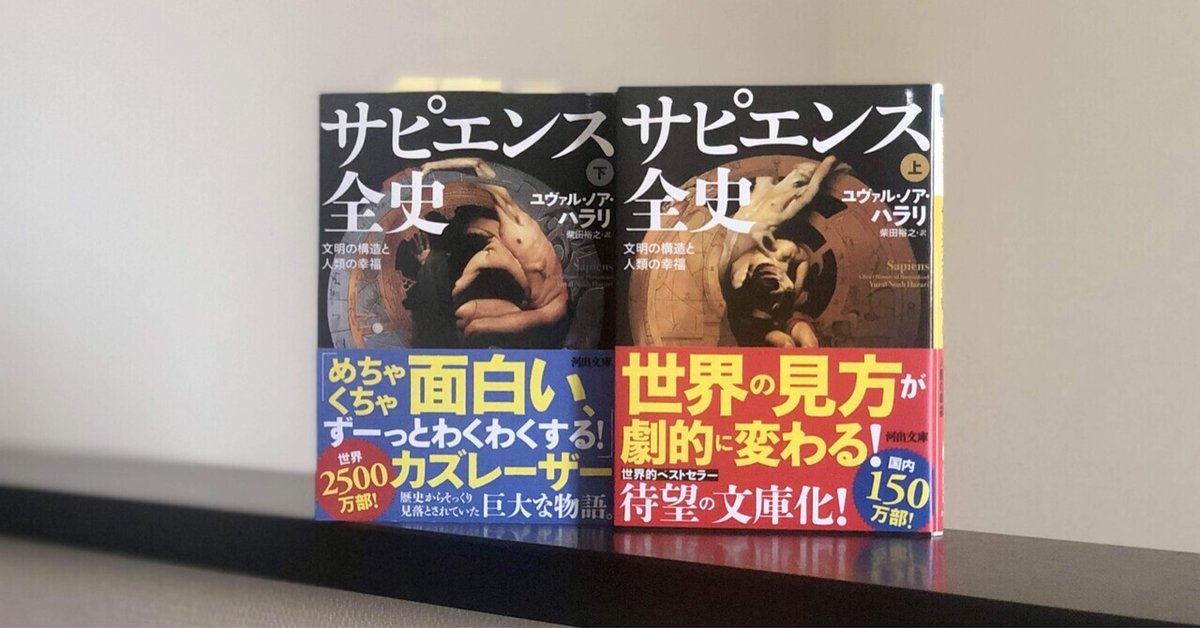
『サピエンス全史(上)(下)』(ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳、河出文庫)
読了日: 2024/4/10
以前から本書(単行本)を知っていましたが文庫版が出たので購読しました。
ホモ・サピエンスが巡ってきたながい時間を”認知革命”、”農業革命”、”科学革命”という3つの革命(第3部には”人類の統一”が入っています)に区分してとらえてゆくという志向はおおむね納得でき、ふむふむとなります。文字の発明により外部記憶が可能になった部分にも触れており、抑える点は抑えているとも感じました。最大公約数を探す意識でもって、様々な本を読でいくとこのようなまとめになるのだろうと思います。決して悪いわけではないのですが、現代の世界の状態からの視点で考察されており(ある意味当たり前だが)、サピエンスの(グレートジャーニーに限らず)冒険的な紆余曲折のようなワクワク感はない。つまり現代の状態への矛盾なき道程としてまとめられているようだ。
けれども、特に下巻に置いてですが、著者の思考的(あるいは思想的)バイアスがかなりかかっており、すんなり承服しがたい表現も散見されました。訳者あとがきに「目から鱗が落ちる」とありますが、かなりフィルターが掛かった論考と思います。以下にいくつか例を挙げてみます。
「ちょうど私たちが今日、恐竜を絶滅させたあの小惑星に感謝できるように」(下巻p.241)
「ノーベル平和賞は原子爆弾を設計したオッペンハイマーに贈られるべきだった」(下巻p.276)
「少なくとも死だけは平等だ、金持ちも権力者もみな死ぬのだと考えて、(貧しい人や迫害された人は)自らを慰めてきた」(下巻p.297、カッコは投稿者による挿入)
「国家や市場は、巨大化する自らの力を使って家族やコミュニティのきずなを弱めた」(下巻p.253)
「イスラムという巨大なコミュニティ、(…)国民は各国家に特有のの想像上のコミュニティであり、消費者部族は市場の想像上のコミュニティのことをいう」(下巻p.259-260)
二元論のキリスト教、イスラム教は聖戦を求めるが旧約聖書にはそのよう信仰は微塵も見られない(下巻p.33、著者はイスラエル人)。
歴史を完全な平衡であらわすのは無理なように感じますが、著者には白人至上主義的な思想もあるようにも思われます。そのように感じながら読み進めると、”サピエンス”の全史とは疑問が生じるような感じでした。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
