
肩関節インピンジメント~介入の適応は考えていますか?~
肩関節疾患を見るにあたり、必ず出会う病態といっても過言ではない”肩関節インピンジメント”
肩関節インピンジメントは拘縮、不安定性、スポーツ活動など様々な影響を受けて出現します。そして、肩関節インピンジメントには”関節外インピンジメント”と”関節内インピンジメント”が存在しています。

なので、”肩関節インピンジメント”といっても、何が原因となり、どこで生じているのかを考えて、評価・介入していく必要があります。
ではみなさん、少し考えて頂きたいのですが
すべての”肩関節インピンジメント”は
セラピストの介入により改善すると思いますか?
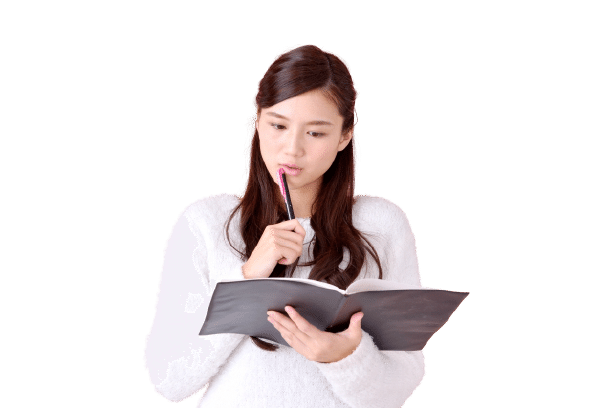
ここはかなり大事な部分だと、私は考えています。すべての疾患には適応があり、”肩関節インピンジメント”も例外ではないです。
今回の記事では、"関節外インピンジメントの評価と介入・適応”について、私なりの考えも含めて記載していきたいと思います。いつまで、経っても肩関節インピンジメントが改善しない理由がここにあるかもしれません。
~確認事項~
記事の内容は論文に沿って記載しております。記事の内容には、論文を読んだ私なりの解釈も含まれています。詳細に関しては論文をご自身で確認して頂きますようお願い致します。
1.肩関節インピンジメントの種類
肩関節インピンジメントには”関節外インピンジメント”と”関節内インピンジメント”の2つの種類に分けられます。

さらに、関節外インピンジメントには”肩峰下インピンジメント”と”烏口突起下インピンジメント”に分けられます。
今回は関節外インピンジメントに着目して記事を書き進めていきます!
1-1.肩峰下インピンジメント
肩峰下インピンジメントは肩峰と上腕骨頭の間で軟部組織(SABや腱板)が挟み込まれます。正常でも起こりうる現象なのですが、肩関節の過剰な使用、腱板断裂によるバイオメカニクスの破綻などの原因により腱板の炎症やSABの腫脹が伴うことで、疼痛が出現します。

例えば、上の図(右側)の様に”肩峰と骨頭の距離が減少している場合”や”運動時に骨頭の上方変位が伴う場合”には腱板やSABに圧縮、摩擦ストレスが生じ、炎症・腫脹が生じ疼痛が出現することが考えられます。
このような現象が生じている場合、以下の様な介入や対処方法があると思います。
「肩峰と骨頭の距離が減少している場合」
→肩甲骨の上方回旋誘導や棘上筋の伸張性改善など
「運動時に骨頭の上方変位が伴う場合」
→腱板筋や肩甲骨のトレーニングを行う、後下方の筋肉の伸張性改善など
1-2.烏口突起下インピンジメント
烏口突起下インピンジメントは”烏口突起と小結節間での組織の挟み込み”の事をいいます。主に肩甲下筋が影響を受けますが、上腕二頭筋長頭腱や烏口下滑液包、SABも挟み込まれる可能性は十分に考えられます。

烏口突起下インピンジメントが生じる原因としては
・烏口突起の形状
・肩峰と烏口突起の位置関係
・烏口突起と上腕骨頭間の距離
・後方筋群の短縮
・肩関節の不安定性や腱板損傷 etc...
烏口突起の形や腱板損傷を治癒することはできませんが、それ以外の現象が生じている場合、以下の様な介入や対処方法があると思います。
「肩峰と烏口突起の位置関係」「烏口突起と上腕骨頭間の距離」
→肩甲骨内転や後傾、胸椎伸展を引き出す介入など
「後方筋群の短縮」
→棘下筋や小円筋、三角筋、三頭筋の伸張性の介入など
「肩関節の不安定性」
→肩甲骨や腱板筋群のトレーニング、感覚トレーニングなど
簡単に”肩峰下インピンジメント”と”烏口突起下インピンジメント”の病態や原因、介入方法について触れたところで、今回の記事の本題に入っていきたいと思います!
「肩関節インピンジメントの介入の適応は?」
「インピンジメントはセラピストが全て改善できるのか?」

こちらをご覧ください!
ここから先は
ありがとうございます(#^.^#)

