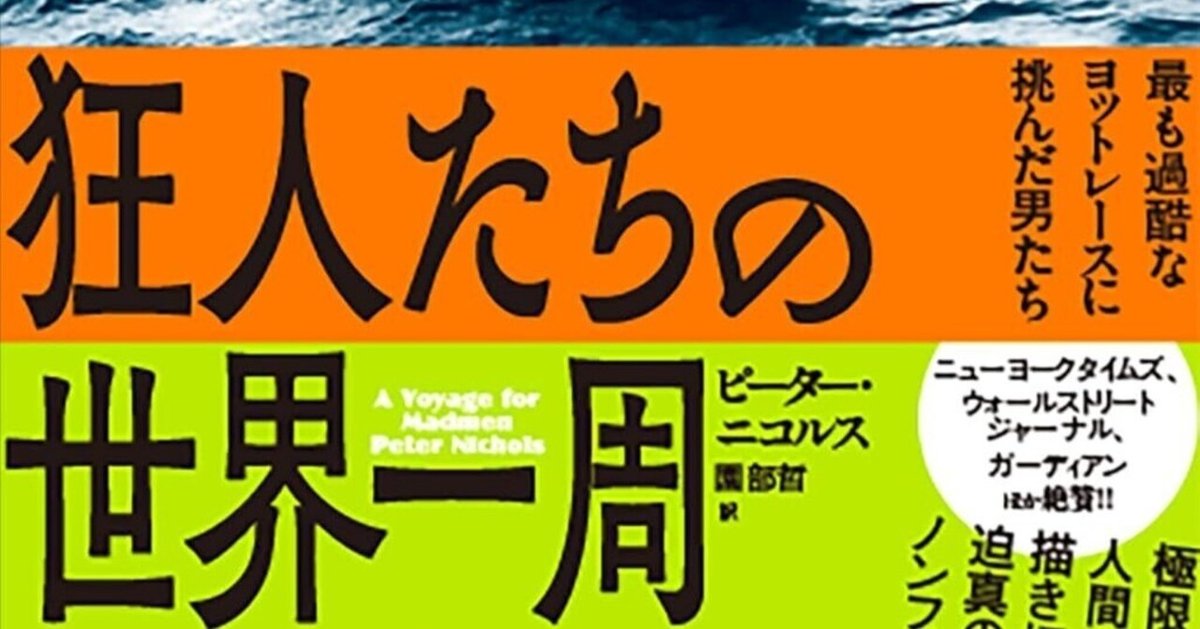
田畑智久評 ピーター・ニコルス『狂人たちの世界一周――最も過酷なヨットレースに挑んだ男たち』(園部哲訳、国書刊行会)
挑戦者は狂者か、はたまた勇者か――前人未到のヨット単独無寄港世界一周を目指して
田畑智久
狂人たちの世界一周――最も過酷なヨットレースに挑んだ男たち
ピーター・ニコルス 著、園部哲 訳
国書刊行会
■世界一周――それは誰しも一度は子どもの頃に憧れた言葉ではないだろうか。たとえば、『八十日間世界一周』を読みながら、異国情緒漂う各国の描写に魅了され、勇敢な挑戦者フォッグが約束どおり八十日間で世界一周を果たせるのか、手に汗握った経験がある読者も少なくないだろう。どこまでも果てしなく続く海は子どもにとって未知の世界であり、大海原へ漕ぎ出すことは尽きせぬ魅力に満ちていたはずだ。
しかし、子どもたちは大人になるにつれて世界一周が無謀な挑戦であることに徐々に気づく。見渡す限りの大海は、他人と接触する機会を奪われた場所である。数日ならいざ知らず、数百日を自力で生きのびることは果たして可能なのか。世界一周は非現実的で、夢物語に過ぎなく思えるかもしれない。
ところが、世界一周を単なる夢で終わらせず、実現させた男がいた。イギリス人のフランシス・チチェスターである。彼は一九六七年にヨット単独世界一周を達成し、しかも途中の寄港はオーストラリアでの一回のみであった。彼は瞬く間に国民的英雄となり、名声と金を手にした。では後世が挑むべきさらなる目標は何か。そう、ヨットによる単独無寄港世界一周の達成である。
一九六八年三月一七日にイギリスのサンデータイムズ紙が広告を掲載した。曰く、「同年六月一日から一〇月三一日までの間にイギリスを出発した者のうち、ヨットでの単独無寄港世界一周を最速で達成した者には賞金五〇〇〇ポンドを授与する。また、上記を最初に達成した者にはゴールデン・グローブ賞を授与する。ただし外部者による物理的な協力および、出発後の燃料、食料、水、装備品の積載は禁止である」という。あなただったら、このレースに挑戦したいと思うだろうか。長期間にわたる過酷な試練であることは想像に難くない。参加などしたくない、参加したがるのは狂人だけだ、ときっとあなたは考えるだろう。
しかし、このレースに果敢にも――あるいは愚かにも――九人の男たちが名乗りをあげた。一例を挙げると、イギリス人の電子技術者ドナルド・クロウハーストは自身の地位と名誉のために、フランス人の船乗り兼作家ベルナール・モワテシエは果てしなく広がる海への憧憬のために、またイギリス人の商船船長ロビン・ノックス=ジョンストンは自国の誉れを誇示するためにレースへの参加を決意した。時は冷戦、各国が第二次世界大戦後になおも覇権争いにしのぎを削っていた時代であった。アメリカとソ連の宇宙飛行士が宇宙開発において競争を繰り広げたように、フランス人やイギリス人のヨットマンも、人類史に偉業を残すのは自国でなければならないと躍起になっていた。年齢も国籍も航海経験も異なる男たちが、家族や友人と暫し隔絶されるのを承知の上で、それまでの職も名誉も顧みず、命を懸けた戦いに挑む。彼らは向こう見ずな狂者であると同時に、歴史に名を刻もうと果敢に挑む勇者でもあった。かくして書名の通り、「狂人たちの世界一周」が始まったのである。
意気揚々とレースに参戦した者たちは、数多の困難に襲われる。参加者が記した航海日誌であるログブックには、航海中の出来事が克明に残されている。外界と通信する際に頼みの綱となる無線は遅かれ早かれ故障し、見渡す限りの海に囲まれたヨットマンたちは想像を絶する孤独な状況に追い込まれる。また、船舶との衝突や座礁を避けるために昼夜問わずヨットを操縦するため、慢性的な睡眠不足に陥る。ほかにも、豪雨や乱気流といった予測不可能な天候、ヨットの故障やそれに伴う浸水、転覆など、ヨットマンたちは常に死と直結する恐怖に苛まれていたのだ。
自分は一体なぜ世界一周をするのか、ヨットマンたちが自身と向き合い思索に耽った記録もログブックに残されている。名声、賞品、賞金、それとも栄光のためだろうか。そもそも世界一周というのは、挑戦者が単に出発地から元の地に帰還するのに過ぎない試みであり、明白な目的などないのではないか、と考えだす参加者もいた。
それでもなお男たちがレースを続けるのは、海やヨットに対する愛情ゆえである。狂人たちの心が慈愛の精神に満ち溢れているからこそ、彼らは勇を鼓して偏西風が荒れ狂う南氷洋を航海し、「吠える四〇度線」、「狂う五〇度線」、「絶叫する六〇度線」と呼ばれる中緯度帯を身命を賭して怒涛の如く駆け抜け、我先へとゴールを目指すのだ。
最終的に、単独無寄港世界一周を達成できたのは九人のうちたったの一人である。ほかの挑戦者は、直前で脱落したり、遭難したり、果ては海に身を投げたりと、悲劇的な最期を遂げることになる。それぞれ誰なのか、予想しながら読み進めてほしい。本作は極上のノンフィクションであり、かつ極上のミステリーでもある。さあ、いますぐに本書を開き、航海に繰り出そう。
(埼玉県立浦和高等学校英語科教諭/翻訳者)
「図書新聞」No.3675・ 2025年2月15日号に掲載。https://toshoshimbun.com/
「図書新聞」編集部の許可を得て、投稿します。
