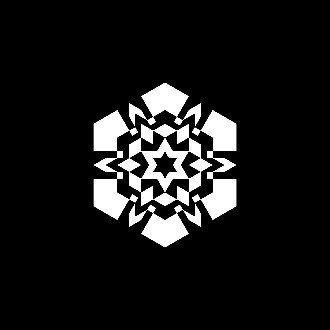【表現辞典】霊石典_名作家の文章〈21〉太宰治『音について』
霊石典
この記事は、私が編集している『霊石典』の派生記事です。名作家の作品の中から、『霊石典』収録の言葉が使われた印象的な文章を紹介します。言葉に興味を持つきっかけとして、あるいは、言葉をさらに深く理解する参考として、ぜひ本編の記事とあわせてお読みください。
太宰治『音について』(青空文庫)
そのアパアトに、気の毒なヘロインが、堪へがたい焦躁に、身も世もあらず、もだえ、のたうちまはつてゐるのである。隣の部屋からキンキン早すぎる廻転の安蓄音器が、きしりわめく。
この『音について』では、本や芝居の中で印象に残った音をいくつか紹介しています。引用した文章でも、キンキンという耳障りな音が、貧困にあえぐ女性をさらに苦しめています。
おもしろいのは、この『音について』の締めくくりです。
音の効果的な適用は、市井文学、いはば世話物に多い様である。もともと下品なことにちがひない。それ故にこそ、いつそう、恥かしくかなしいものなのであらう。聖書や源氏物語には音はない。全くのサイレントである。
市生文学とは大衆向けの小説のことですが、そういうものは音の描写が豊かだと言っています。音を効果的に使った文章はたしかに臨場感がありますが、擬音語や擬態語を多用してしまうと、表現が拙く感じられます。
◆
この記事では、[きんきん(キンキン)]が使われた文章を紹介しました。
ぜひ、本編の記事もお読みください。
過去にたくさんの記事を書いています。マガジンに分類しているので、そちらからご覧ください。