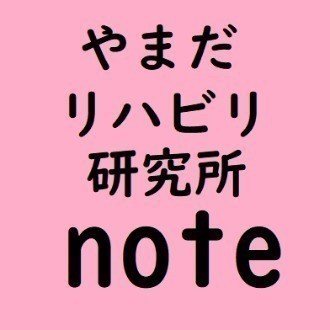コラム11「訪問看護からのリハ」と「病院や診療所からの訪問リハ」のこれからのあり方について考える2(2021年3月)
2021年3月21日12時14分に追記し文章を修正しました。
このコラムは以下のコラムの続編です
このコラムでは訪問看護からのリハについては「訪看リハ」とし病院や診療所・老健からの訪問については「訪問リハ」と表記しています。両方を合わせての訪問については「訪問のリハ」とします。
前回のコラムでは、軽度な利用者さんへの訪問によるリハビリテーションへの対応のことを書きました。
今回のコラムでは訪問看護ステーションからのリハビリテーションの将来性について考えてみます。
訪問リハと訪看リハの役割分担については以下のコラムにも書いています。
訪看リハの将来性で考えなければならないのは、今回の介護報酬改定議論で訪問看護ステーションの人員基準の変更が取り上げられたことです。
撤回はされましたが、議論として訪問看護ステーションの人員基準を看護師比率を6割とするというものが取り上げられました。2021年の介護報酬改定では結果として取り下げられましたが、体制加算としては6割が明記されました。
今後もこの問題はくすぶるでしょうね。
そうした6割問題だけではなく、今回伝えたいのは訪問リハでの改定に関することが、将来的には訪看リハにも影響を与えるのではないかという問題です。
それが以下のスライドです。

上記のスライドは訪問リハを実施するにあたって、セラピストの所属する事業所の医師の診療がない場合は減算するというものです。
訪問リハ実施事業所の医師ではなく、他院の医師が主治医の場合でも訪問リハは実施できますが、基本的には訪問リハを実施する医師が指示を書くにあたり診療が必要とのことなんですね。
これは、訪問リハにおいては通所リハとともにリハマネ加算1が基本報酬に包括され、事業所の医師とセラピストの連携が強化されました。「強化」されたのは医師の指示の明確化です。
これについては以下のような文言があります。

通所リハや訪問リハの指示には上記のスライドに提示されているものが含まれている必要があります。
そのことは2021年の介護報酬改定議論においても取り上げられており、セラピストが所属している事業所の医師の指示の方が明確な指示が多く、リハマネ加算に活かされているとの下記スライドが示されています。

さらには、訪問看護ステーションの人員基準の看護師6割問題では、これらのことも含めて議論され、訪問のリハビリテーションの指示はリハビリテーションのことをよく理解している医師が指示を行うべきではないかとの議論もなされました。
ここまでに提示したスライドから訪問看護ステーションの訪看リハの未来で最も懸念されることは以下の点です。
訪看リハにおいて懸念すべき2つの課題
ここから先は
フリー作業療法士として日々書いております。サポートは励みになっています。サポートなくてもお買い上げいただけますが、あると嬉しい。