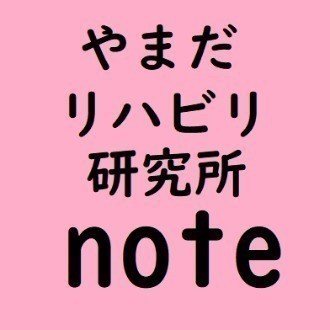コラム5「病院リハと地域リハをつなぐ」ということとは?
2021年1月31日追記
このコラムの解説動画を掲載しました。動画「その1」はコラム中ほどに掲載しておりどなたでも視聴いただけます。動画「その2」はコラムの最後の方に掲載しています。
誰かが動かなくてはいけないのだと考えている。
非常勤掛け持ちで働きながら考えているからいい加減な考えなのかもしれないし無責任かもしれない。
だけどOTの府士会で理事を経験し、自治体からの直接の依頼で地域ケア会議の助言者として関わり、通所介護のスタッフとして地域ケア会議の関係事業所側として出席したりしながら考えていることだ。
いろんな地域で働きながら、いろんな経験をしながらここ10年くらい
「病院リハと地域リハをつなぐ・変える」ことがメチャクチャ大事だと思っている。
回復期リハ病院も入院している患者さんの多くはその病院の半径数キロ圏内でしょう、もうちょっと広かったとしても20キロ圏内くらいかな。
そうして退院後はその地域に戻り必要であれば地域リハビリテーションが開始する。だからある意味病院リハは地域リハのスタート地点であり、地域リハの一翼を担っていると考えている。
だけど病院リハと地域リハが一丸となってその地域の住民をサポートできているかというと、けっしてそうではないエリアも多いだろうと思う。
そうしてそんな地域というかエリアに、リハの職能団体があったりして地域包括ケアや総合事業の研修会を開いていたり、地域包括支援センターがあったりして地域ケア会議が開催されていたりしているんだけど、それらのことがその地域を支援することに直結しているかというとそんなことはなかったりもする。
色々なリハビリテーションがリンクしていない
ここから先は
2,822字
フリー作業療法士として日々書いております。サポートは励みになっています。サポートなくてもお買い上げいただけますが、あると嬉しい。