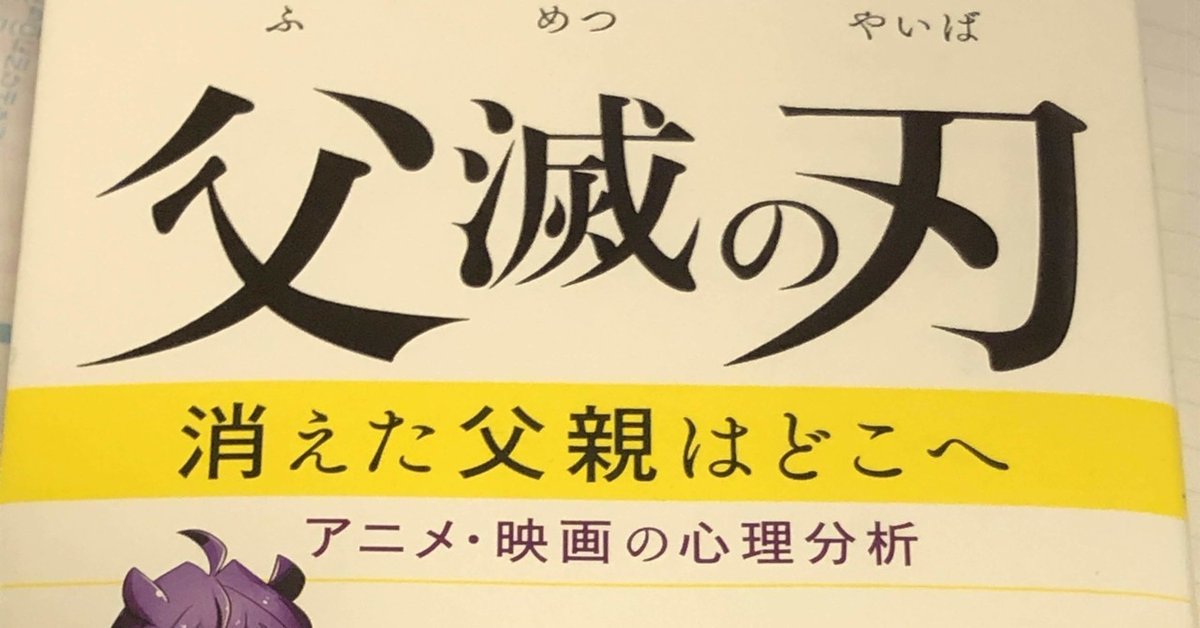
20.11.14【週末の立ち読み #6】僕たちの虚構はどこに向かうのか? 〜樺沢紫苑『父滅の刃』(みらいパブリッシング)を読む〜
前回の読書で、肝心なことが話せていなかったので、対比的になる書籍を探したところ、ちょうど良いものが本屋さんにあった。
名付けて『父滅の刃』。まさに某メジャータイトルに肖ったようなタイトルだが、それゆえに重要な書籍だろう。初版が2020年の8月で、まさに今を読むのに適しているコンテンツ評論集の一つだと、僕は思う。
著者は、『インプット大全』『アウトプット大全』で有名な、精神科医。精神科医が物語論を分析するというと、河合隼雄氏が思いつくのだが、案の定、ユング派の元型を用いた物語分析で、『ONE PIECE』をはじめとする多くの近刊・映画を含むエンターテイメントの物語構造を総括している。
なにぶん、非常に読みやすいため、ちょっとあっけない気もするのだが、前回の宇野常寛さんと、樺沢さんの探求のポイントは部分的に共通する。それは、「この混沌とした時代において、我々はどう生きるか?」という根本的な問いかけだろう。
ちなみに、物語分析を行う精神科医としてのユングや河合隼雄氏は、神話やファンタジー、児童文学を専らとしている印象がある。
筆者は上記二者をあまり読めていないのでこれ以上いうとボロが出るのであるが、物語が人の感動に直接関係あるものとしては、人生観や価値観、精神の構造に強い影響力があることはいうまでもないように感じている。
さて、前回のテーマが「母性」の肥大化と、それによる「父性」の退化を詳細化して言った内容であったのに対して、本書のテーマは「父性」の変遷そのものを主題とする。
個々の評論としては正直『母性のディストピア』の方が分析に独自性があるため、こちらは深みと危機感に欠けるのだが、良いポイントとして米国の西部劇から「父性」の変遷を辿り、国内外における「父性・母性」の表現のターニングポイントやイレギュラーケースを追いかけている点が挙げられる。そういう意味では、『母性のディストピア』をこちらと合わせて読むと非常に興味深い、複眼的な思考を育めるように感じた。
特に面白かったのが、『エクソシスト』(1973年)における「父性≒キリスト教における神」の無力の傾向が決定化された、という見方。この前後の年に「大いなる父」の落日を描く『ゴッドファーザー』と『ゴッドファーザーPART2』があることを思うと、トレンドとしては転換期に当たるのかもしれない。
奇しくも、ベトナム戦争が激化し、終盤に向かっていた時期と重なるこの時期には、(本書には書かれていないが)日本特撮においても『ウルトラセブン』(1967)、『仮面ライダー』(1971-1973)などと、単純明快な「科学による明るい未来」や「大義名分」のようなものが薄れつつあり、「不毛で正義の見当たらない戦争」や「敵に傷をつけられ(改造され)、世間に正体を隠して戦うヒーロー」などの像が確立しているころに合致するように思われる。
何よりレイチェル・カーソンが『沈黙の春』を書き、水俣病や他、致命的な公害が人を汚染し、ストックホルム会議で「かけがえのない地球」がスローガンとして挙げられた時期でもある。
ニクソンショックで金本位制の経済が変化し、中東の戦争で石油価格が高騰、とにかく先の読めない(おまけに目にも見えない)激動が世界中を駆け巡っていたのは確かだろう。ついでに、原発や核の恐怖が依然として存在し、それでいて日本という国家はアメリカの傘下で「守られている」ことを肯定的にも否定的にも自覚せざるを得なかった、ややこしい時期だ。
そんな時代に描かれた「父性」とは、もはや古びて時代の危機に適さない規範・制度・価値観だったのではないだろうか。
もっとも、著者は平成生まれであるため、上記の推測は近現代史のなけなしの知識を総動員したものである。その時代の空気感は、その時その瞬間に生きていてさえ(この現代だってそうだ!)わかりにくいというのに、ましてや当事者ではないのだとすれば、それなりの文献を読み、人の話を聞き、そして想像するしかないのだ。
ただ、その上で、父性が母性に向かおうとした傾向を仮定することはできる。「母なる大地」の常套句や、古代メソポタミアのティアマト神、ギリシャの始原の女神ガイアなどの「大地母神」と呼ばれるように、大地や自然を大切にするエコロジー思想は「母性」の復権・美化を汲み取れる。『風の谷のナウシカ』やスタジオジブリにおけるアニメーションが、宇野によって「母性のユートピア」と呼ばれ、同時に『機動戦士ガンダム』において女性的なイメージによって包括される世界観を「母性のディストピア」と評していく経緯も、ここからうなずける。
実際、本書で興味深いのは、どうやら『エクソシスト』以降に、ホラー・スプラッター映画で最後に女性が生き残り、悲鳴をあげたり、戦いを余儀なくされたりする作品が増加していると指摘している部分だ。
特に『エイリアン』では(個人的には『ターミネーター』シリーズも挙げたい)、「強い女性」という像も生み出している。ここにはもちろん、飛行機を自在に飛ばし、銃器も勇敢さも優しさも持ち合わせているナウシカや、女性パイロットとして巨大ロボット(モビルスーツ)に乗るララァ・スンも含まれている。
こうした表象とは裏腹に、『スターウォーズ』の旧三部作の立ち位置も面白かった。完全によく知れ渡ったネタバレではあるが、主人公が探し求めている「父親」が実は敵対している人物の正体だった! というものは、当時観客にかなりショッキングだったらしい。
もちろん原型としては過去から何千年も使い古された表象だ。しかし、『スターウォーズ』が「父性」観に強烈なインパクトを残したのは、「父親探し」のプロットの大衆化でもあったのだ。ここに、『母性のディストピア』の時代を描く、「肥大化した母性」と「矮小化する父親」の対立構造の少し違った側面が見えてくる気がしてくる。
要するに、立ちはだかる壁(試練)であり、強いリーダーシップであり、無言の信頼や絆であり、そして時代のヴィジョン、理念を示す「父性」は、それ自体がファンタジーに移行して行ったのである。
一方、庇護や保護を与え、人々を包括し、平等に愛する一方で倫理や道徳を押し付けていく「母性」の肥大化は、むしろインターネットやサイバーなものと繋がって(奇しくも仮想現実の代名詞として名高い「マトリックス」とは「母権制(マトリズム)」と関係のある言葉だ)、世界中に拡散していく。父性のファンタジー化に比較していうならば、母性のSF化と言っても良いかもしれない。
図らずも、「ナウシカ」や「ガンダム」、あと『母性のディストピア』的には「パトレイバー」も含まれるかもしれないが、これらの作品はSFだ。
一方で、本書における父性を顕在化したコンテンツを列挙すると、『スターウォーズ』や『コナンザグレート』、『ロードオブザリング』、『ハリーポッター』、『ナルニア国物語』、『パイレーツ・オブ・カリビアン』、『ONE PIECE』そして『鬼滅の刃』など。SFX技術が多彩な印象を受けるが、物語構造が神話や御伽噺に依拠するなどを考慮すると、ファンタジー寄りと言った方が分類上わかりやすいかもしれない。
SFとファンタジーの区別をつけること自体は非常に意味のない議論ではあるものの、あえて区別をつけてみると、SFは「社会の予言書」(=現実に肉薄する要素を持つこと)であり、ファンタジーは「どこかで見た景色を蘇らせる」(=幼心の風景、または原体験のイメージ)であると僕は思っている。
だとすると、もはや現代において、「母性」とは「逃れようがない良い子ちゃんづくしの平等社会」のメタファーであり、「父性」とは「もはや現実ではないと理解しながらもそうであって欲しい」願望を集約するシンボルでしかない、ということではないだろうか。
と、ここまで来ると、樺沢さんの本書の話をしているのか、宇野さんの『母性のディストピア』の話をしているのか、はたまた僕の勝手な妄想を語っているのかの区別が曖昧になってくるのだが(これが良いのだ)、これから先が、僕の個人的な感想になる。
残念ながら、本書はそれ単体ではあまり豊かな読書体験にはならない。先ほども書いたように、宇野さんの書籍の方が深堀と問題意識が痛烈で、読む側まで「その気」にさせられるような熱量が、少し薄く感じるからだ。
これは著者の樺沢さんが精神科医であるという立場からなのか、作家性によるものなのかはわからない。しかし、これを読みこなし、もう一歩深く楽しむには、同じように「父性」や「母性」の観点で時代を読み、漫画やアニメ、映画を読む評論家の眼が必要だ。
個人的には、本書を入門書にして、松岡正剛の『ルナティクス』(中公文庫)や『フラジャイル』(ちくま文庫)、リーアン・アイスラーの『聖杯と剣』(法政大学出版局)などをじっくり読んでから振り返ると、非常に楽しめるのではないか、などと期待している。
特に『聖杯と剣』はそれぞれが「母性」と「父性」のシンボルになっていて、「満たすもの=豊穣の器」としてのそれと、「切断するもの=決断の意志」としてのそれが、いかに人類史上で交錯したかという内容になっている。ここにはもちろん、キリスト教やユダヤ教のごとき「一神教=父性の宗教」以前の世界、バッハオーフェンの『母権制』(みすず書房など)やマリヤ・ギンブタス『古ヨーロッパの神々』(言叢社)が示した道が前提にある。こちらまで手を伸ばす必要はないのだが、この「母的なもの」と「父的なもの」の観念が連綿と続いているマクロな視点が、一体何なのかを疑ってみないと何も打開できなくなるように思える。
父も、母も、本来的には「役割」や「関係性」を示す言葉であって、それ単体で成り立つものではない。「父」という性別は存在しないし、「母」という染色体があるわけでもない。生物学が規定しているのは「オス(男性)」か「メス(女性)」か、だけであって、父性も母性も人間ならではの虚構=フィクションでしかないのだ。
そんな展開を見据えずに、茫然と現代の話をしていると、右も左も猫も杓子も同じ話を繰り返すハメになる。だから、本書の内容も、気付きはあれど、そこまで強い印象は残らなかった。
しかし、350ページ以降から、だんだんと面白くなっている。この前後でディズニーが発信する『アナと雪の女王』と『アラジン』について、「父性の消滅」というキーワードで、著者の思いが書かれている。これが非常に面白く感じたので、ぜひこの記事を読まれている方は、自身の目で確認してみて欲しい。
少しだけヒントを差し出すならば、今年の『ムーラン』はどういうことだったのか、ということだ。まだこちらの評価は知らないが、これまでの文脈を具に辿っていくと、予想できないだろうか。
そして一方で、僕が漠然と思うのは、現代社会の課題としてある「母性のディストピア」の以前には、「父性のユートピア」か「父性のディストピア」があったのではないか、ということだ。
そこには強烈な分断と、強固な規範と、強化的な進歩とがあったはずなのだ。では、その時代とは一体何だったのか? その反省こそが「母性のディストピア」の先駆けとなったのではないだろうか?
これはジェンダー論ではない。現代と現実を生きるためのフィクションの読み方のお話だ。評論の力をあなどってはいけない。
※2020/11/15 補足
もう少しこの手の話題に踏み込んでみたい方はそれぞれの著書の中での参考文献のほかに、河合隼雄『母性社会日本の病理』(講談社+α文庫)を読むとすごくわかりやすい。
本書における「父性の消滅・減退」と、宇野常寛『母性のディストピア』が指摘する「母性の肥大化」、または「妻・母的存在の献身・庇護によってのみ成り立つ矮小化した父性」の問題を淡々と指摘している。
▼以下、書誌情報▼
今回もAmazonからリンクを貼ります。
読みやすさ:すごい平易で読みやすい
面白さ:中くらい(補足知識や関連図書があると深読みが楽しいが……)
入手しやすさ:そこそこ(書店のサブカルコーナーやAmazonなどから見つかりやすいです)
ちなみに、図らずも私の書いてる作品も「父親の不在」から始まります。今回の読書もそのための資料だったりする。
