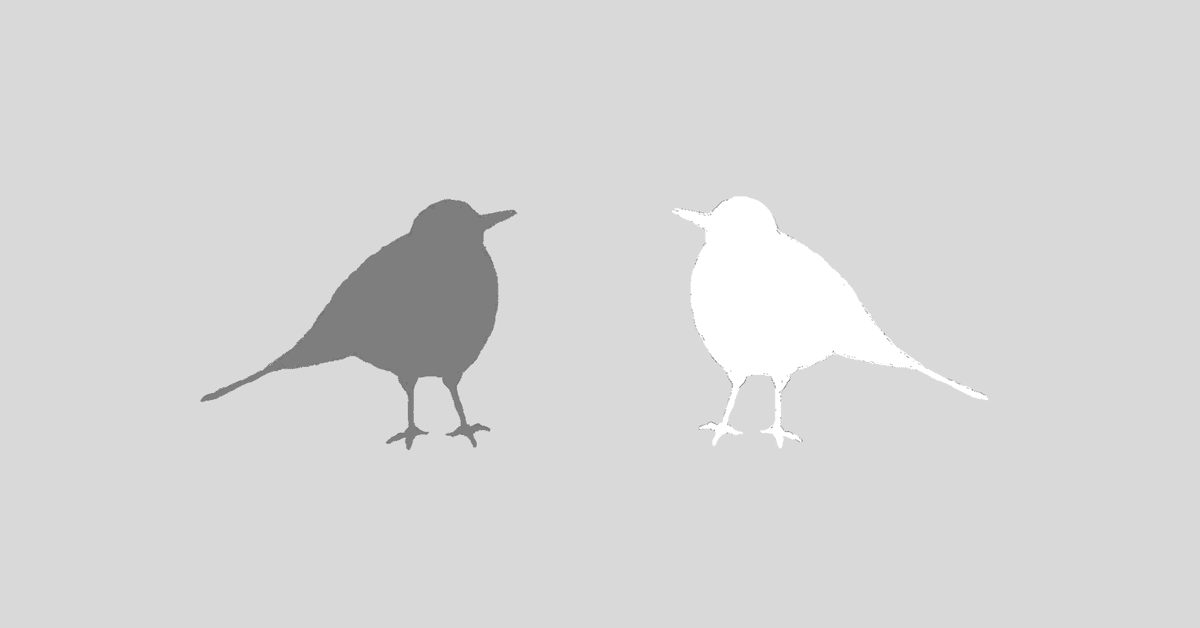
批評とは「その考え方はいいね」
自分で見聞きして良し悪しを見極める。ほとんどが瞬時の条件反射にちかい。一人ひとり個性があって興味の対象も受け取り方も違うので、その判断も温度差も十人十色で千差万別だ。書籍でも絵画でも音楽でも、自分の目にとまったものはそれを選んだ時点ですでに批評的だ。「それいいね」という動機があるからだ。誰かがその作品を選んで批評する場合も、そのこと自体が既に相当に踏み込んだ批評的行為である。他人の批評に触れてその捉え方をそのまま引き受けるのはたやすい。一方自分で一般化された解釈にまで辿り着くことは容易ではなく、またさらに自分の評価を誰かにことばで表現して批評として伝えることはさらに難しい。
批評とはある対象の価値、それをどのように捉えるかという基準を示すひとつの指標である。誰もが「その考え方はいいね」と首肯できる根拠が感じられないと独りよがりのただの感想に埋没して、相手にされないか隅に押しやられてしまう。他者の目を意識したある種の怖さがつきまとう。
良し悪しを判断するのは人間だ。対象そのものはただそこに在るだけである。批評する側が対象に介入する。批評は取るに足らないというレッテルを貼られると忘れ去られ捨てられて記憶からも遠ざかる。物理的な存在がなくとも人の記憶に残るものもあれば無に帰してしまうものもある。自分に関わることで何か一つでも他者の記憶の片隅にでも残るものはあるのだろうか。おそらく記憶の奥深くに閉じ込められて消えていくのだろう。人は他のものと比べたり自分のモノサシで測って良し悪しの前提を築く。分からないことがあるとまずは分類をしたくなる、比べたくなる。解釈をしたくなる、名前を付けたがる。なぜだろう。わからないと不安になるのだ。他人の評価に頼ってでもそのことを「わかった」こととして収めたい。自分の感性が良し悪しに鈍感であってわからないということは恥ずかしいことなのだ。知らなくても知っているふりをする。突き詰めていくと遥か昔に問答された「無知の知」や「我思う、ゆえに我あり」という哲学的な見方と批評が重なって見えてくる。
批評家の言質を素直に受け止めて自分の判断の根拠として利用してみる。また批判的にその批評をとらえて反面教師とすることもその批評家の自分にとっての存在意義がある。あの人がこう言っているから自分もそうだとか、みんなが言ってるからこう思うという発想は安直だがとても乗っかりやすい。無色透明な批評や解釈よりは多少癖の強い人や媒体が発した批評の方があてにしやすい場合もある。あてはめるモノサシは一つしかないと単線の見方に留まるが複眼的、鳥瞰的に俯瞰することもできるからだ。
批評というと本の書評や音楽評、美術評、演劇評、映画評または人物評や時代評など様々に対象が挙げられ拡がっていく。物の見方や考え方の指南を果たすことが批評の一端であるならば、文学作品もまた批評的な側面を持つ。ことばが物の見方を示す例としては、清少納言『枕草子』の春の段の描写は分かりやすい。小学校中学校の教科書でも定番中の定番として君臨する。日本人としての物の見方や感性を共有するほどの影響力を持つ。また読み書きそろばんや門前の小僧の時代、漢詩に親しむ素養は感情の発露をことばから先に体得する効用のためだと聞いたことがある。物の見方や感じ方のお手本というか指南というか理想形の具体例なのだろう。
最近の芥川賞作家の作品は小説でありながら小説という表現方法を使って世の中に批評的な一石を投じているようでもある。柴崎友香『続きと始まり』、九段理恵『東京都同情塔』、町屋良平『私の批評』など。小説なので読者の読み方に判断をゆだねるが、小説という手法を使った批評とも受け取れるし、受賞自体が評価されたというモノサシでもある。選考された候補作の中の代表なので読む側にとってはとても分かりやすい批評のシステムだ。最近はとくに批評を直接的に声高にすることを忌避する空気感がある。表向きには影を潜めているようにも受け取れる。がしかし地底の奥底ではマグマがうねっているようにも感じる。
このように捉えてみると芸術作品でも人物でもまたある時代でも、森羅万象すべてが批評の対象となりえる。批評は批判や批難ではない。批評しようとする側が、その対象を語りたいと選ぶ時からすでに批評は始まっている。批評家はなぜそれを選択したのかという「自分」にまず最初に向き合うことになる。そして、色々な人が様々な場面で時代を超えてものの見方や作品とその解釈の視点を語り継ぐことで作品や対象は独立して自立して歴史にその名を留める。時代を生き伸びた作品には伝説という命が吹き込まれていく。
批評は作品を通じて作り手と受け手の橋渡しをする。
芥川賞作家の朝吹真理子さんが、自身が小説と絵を表現することについて語っていた。作品完成に至る95%くらいまでは文章化されるか絵になるかはわからないそうだ。作家や作者の作り手側からは、内在する悶々とした作品に至るエネルギーは詩歌でも小説でも音楽でも、また写真や映画、演劇、美術などあらゆる種類の表現に昇華する。ゆえに批評は何に対しても対象になる。
たとえばピカソの一枚の絵を見てどのように自分で評価していいか不安になる場合の判断基準が示されると拡がった視野がある意味一般化されて共有される。つまり自己判断を諦めて世の中の価値基準を借用して安心してしまうという一つの妙薬が行き渡る。同じものを見てもその時の気分やその時の心の余裕で見え方は異なる。花の美しさは絶対的であるのに対して人間の感性は流動的で気まぐれである。
批評したいと思う対象が見つかった場合、歴史の風雪や時代の荒波を超えたその対象に対する見方や考え方に寄り添いつつ、自分なりきの「見え方」を添える意識で読まれてもいい日記や小説を著すように自分のことばで表現することが批評の第一歩であると思う。自分の色を出したいのであればキャラを出し作家性を全面に表すことだ。表現することは全て批評と括ってもいい。批評家がインフルエンサーであれば、その人の考え方や物のとらえ方が批評としてその瞬間には影響力を持つ。時間や歴史のふるいにかけられて、最後に残る誰にも迎合することのない批評や物の見方こそが文明の底辺を支え続け、無知の知から具体的な知の一歩を踏み出す勇気を与えてくれる。
花の美しさはそのもの自体に美が宿っている。その美しさを感得できるかどうかはその花を前にしたときの自分の責任である。見る目を持たなければ持つように努力すればいい。昨日までのピカソの絵や交響曲が今日は違ったものに見えたり聞こえたりする瞬間がある。あばたもエクボもまたその人の見方だが、黒いものが白く見えてしまうことにはならない自己責任の審美眼に磨きをかける研磨剤の一粒一粒が批評の使命でもある。
