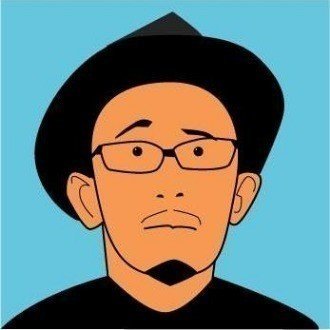クリティカル・ビジネス・パラダイム
おはようございます 渡邉です。土曜日は、すごい暑い一日でしたね。10月になってこんな暑い日がやってくるのかよ!と思いつつ、今日はすごく寒くてくれぐれも体調には気を付けていきましょう。
さて、そんな週末に 「クリティカル・ビジネス・パラダイム」- 山口 周 を読みましたので、今週はこの本を紹介します。
クリティカル・ビジネスとは?
先ず、この聞きなれない言葉ですが、以下のような定義がなされています。
社会運動・社会批判としての側面を強く持つビジネス
= クリティカル・ビジネス
周さんらしく、クリティカル・ビジネスへの理解を深めるにあたり、「クリティカル・ビジネスではないもの」について書かれているのですが、「クリティカル=批判的」の対義語としての「アフォーマティブ=肯定的」ということで、従来のシステム上で展開されるビジネスを「アフォーマティブ・ビジネス」としています。
もう一つ、「ソーシャル・ビジネス」との違いについては、以下のマトリクスで整理されています。
コンセンサスが
・取れていない| ー | クリティカル
・取れている |アフォーマティブ | ソーシャル
個人的課題 社会的課題
従来のソーシャル・ビジネスが、すでに多数のコンセンサスがとれた社会的な課題に取り組むの対し、クリティカル・ビジネスは、運動を開始した時点では、必ずしもコンセンサスが取れていないアジェンダに取り組むというものです。
では、具体的な企業例として、どのようなものがあるのか?ということで、2013年にアムステルダムで創業されたスタートアップ、フェアフォンが紹介されています。完全後発のスマートフォン・メーカーでありながら、ヨーロッパで着実にファンを増やし、市場で一ポジションを築いている企業になります。
どのようなスマートフォンか?ということになるのですが、ユーザー自身が部品を簡単に交換・アップグレード出来るスマートフォンです。これを聞いたときに、僕はとても欲しくなりました。現状では、スマホが壊れたり、古くなった場合には、メーカーの公式修理サービスを利用するか買い替えるかしか選択はなく、モヤる感がありましたが、仕方がない。と殆どの人が諦めていたかと思います。
フェアフォンはこうした慣習に一石を投じ、サステナビリティを体現したメーカーとして競争優位を得ているということです。また、フェアフォンの創業者達も、
「私たちがやっているのは、ビジネスというより『修理する権利を取り戻す』という社会運動なのです」
とインタビューで答えているように、正に「クリティカル・ビジネス」を行っているわけです。
クリティカル・ビジネス・パラダイムの背景
問題の普遍性と問題の難易度、それに経済合理性限界曲線については、周さんがnoteを書いているので、それを参照しつつ。
従来、経済合理性曲線の外側にあった課題も、共感の範囲を場所や時間を超えることで、曲線を上にあげることが可能になり、一気に取り組むべき問題となってくる。
また、価値観の変化は「ある時期を境に一気に変化する」傾向があるということです。下の図は、同調圧力がどのように個人の態度に影響を与えるかの研究結果だそうですが、同様に共感力のある市民の価値観はある一線を越えたところで、一気に多数派に転換する可能性があるということです。

このグラフを眺めていて、色々なことに応用できそうだなと思ったのですが、例えば学習曲線もこのような形を描くような気がします。気持ち的には、1次関数的に勉強すればしただけ、賢くなって欲しいわけですが、最初はそれほど、目に見えた効果もなく、ある一定の閾値を超えた段階で一気に色々なことがつながり、理解が進むということはありますね。
また、某企業の勤続年数(横軸)と支給される退職金(縦軸)もこのようなカーブをたどったような気がします。永きに渉り、会社に貢献してくれた人に対するある意味ボーナスであり、若くして退職していった人の分も積みあがる感じですね。
話は戻りまして、どんな大きな社会変化も最初は少数派によってけん引されているということです。少数派の意見や行動で多数派が影響をうけ、社会が変容していくようにできているということですね。
クリティカル・ビジネスの実践例
続いて、第5章よりクリティカルさの7パターンと具体的な事例を紹介していきます。
1.支配的価値観への批判
volkswagen 「Think small」キャンペーン。こちらのブログに詳しく書かれていました。
2.貧困と経済的不平等の解決
グラミン銀行(銀行)
3.気候変動・資源枯渇への対応
いわずと知れた patagonia(アウトドア用品)
4.企業倫理と透明性の向上
The Body Shop(化粧品)
5.労働者の権利と福祉の改善
モンドラゴン協同組合(協同組合にして企業連合体)
6.ダイバーシティとインクルージョンの推進
IKEAイスラエルによる「ThisAbles プロジェクト」
7.地域社会とコミュニティの生成
Brunello Cucinelli (イタリア発祥のカシミアブランド)
アクティビストのための10の弾丸
続いて、6章からはクリティカルビジネスの実践者が発揮している思考・行動様式について触れられています。
1.多動する
ここでいう「多動」とは、「体を動かす=物理的な多動」に限らず、「心を動かす=精神的な多動」も含め、自分にとっての当たり前を捨て、批判的に捉えなおしてみるきっかけとするということです。
2.衝動に根ざす
最も心を動かされるものを優先度の高いアジェンダとして取り組む。
内心に潜む核心を語れば、それは普遍に通じる
ー ラルフ・ウォルドー・エマソン(米国の思想家)
3.難しいアジェンダを掲げる
「容易なアジェンダよりも難しいアジェンダの方が達成しやすい」というパラドックス。その理由は以下の3つ。
1.共感の獲得
2.認知の促進
3.モチベーションの向上
4.グローバル視点を持つ
グローバルニッチというポジショニングを取ることで、一定規模の市場が存在する。例えば、日本国内で5%とすると、精々6M(120M×5%)人だが、グローバル先進国1.2B人を対象とすると、10倍の60Mに拡大する。
5.手元にあるもので始める
いきなるフルコミットするのではなく、サイドプロジェクトから開始する。その理由として、以下の3つが挙げられる。
1.リスクの低減:早く小さく試す、逆に大胆にリスクをとれる
2.ステークホルダーの誘因:始めることで、人が集まる
3.学習の加速:フィードバックは経営資源である
6.敵をレバレッジする
「運動はネガティブにせよ、ポジティブにせよ、情報を食べて大きくなる」批判を元にアジェンダを新たに知る人もいる
7.同志を集める
同じ価値観や優先順位を持つステークホルダーとの協働の利点
1.効果的な協働:素早く、ブレない判断。摩擦が相対的に少ない。
2.ブランドの強化と伝播:メッセージの有力な伝播者。
3.組織文化の形成:モチベーション向上や一体感を高める要因。
8.システムで考える
問題をシステムとして捉える。問題の発生する原因を局所的なものではなく、自分も含めたシステム全体にあると考え、システム全体を改変することを志向する。
9.粘り強く、そして潔く
基本的なアイデアに関しては、「粘り強く」こだわりながら、方法論は試しながら、「潔く」修正していく。
10.細部を言行と一致させる
追及する価値は、本質的な目的や信念に根ざすため、信頼性や誠実性が極めて重要となる。
・信頼性の確保
・競合との差別化
・持続的な関係の構築
・リスクの回避
・影響力の拡大
参考事例:NIKE 「Don't Do It」キャンペーン
今後のチャレンジ
最終章では、我々一人一人がどのようにクリティカル・ビジネスに関わっていけるかということについて書かれています。
1.フォロワーシップの醸成
リーダーシップというのは、フォロワーが生まれた瞬間に立ち現われ、リーダーになることができる。そういう意味でも、ファーストフォロワー(賛意を表明する最初の人)が重要ということです。そのことについて、よく引用される動画ですが、こちらを参照ください。
2.情報の拡散と共有
私たちには、声を上げる責任がある。「おかしいと思うことに対しておかしいと声をあげる」「醜悪だと思うことに対して、醜悪だと声をあげる」また、「美しいと思うことに対しては美しいと声をあげる」ことです。現代は、SNSやブログなど個人でも発信できるツールはたくさんあります。我々は微力だけれど、無力ではない。

3.クリティカル・ビジネス製品やサービスの利用
わかりやすいところでいうと、フェアトレード商品や環境負荷が低い商品を選択するということでしょうか?この際に大切なのは、他者を批判することなく、自分に出来ることからやっていこうということですね。
4.クリティカル・ビジネスへの関与
副業、ボランティアどのような形でも強く共感できるクリティカル・ビジネスに関わってみるということです。それにより、以下の4つのメリットが享受されます。
1.意味的価値の充足:自分の人生における働く意味を得ることができる
2.キャリアリスクの分散:「卵は一つのカゴに盛るな」ですね
3.学習の加速:単位時間あたりの経験密度を高め、学習を加速させる
4.社会関係資本の拡充:本業以外での人脈・評判・信用を拡充する
5.資金提供と投資
「資金提供と投資」と言われて、そんなお金はないとおもってしまうかもしれませんが、個人として関われる2つのアプローチがあります。
1.クラウドファンディング:少額からでも支援が可能
2.インパクト投資:企業の株もしくは、組み込まれたファンドへの投資
6.教育と学習
本を読む、講座やワークショップへの参加など関心をもって知ろうという姿勢が第一歩ですね。
7.ネットワーキングとコミュニティ
社会運動のモーメンタムを上げるには、問題意識を持つ個人という「点」がどうしがつながって「線」になり、「線」が交わり「ネットワーク」となる。同じ関心を持つ人同士がつながって、コミュニティを形成することが、クリティカル・ビジネスをより推進していきます。
というわけで、今週はクリティカル・ビジネスについて考えてきました。聞きなれない言葉でしたが、こうしてみると身の回りにも事例が多く見られますね。まずは、興味をもって知るところから始めてみましょう。
(2024.10.24)
いいなと思ったら応援しよう!