
黒澤明「どですかでん」_ 明日も踏んだり蹴ったり。だけど。
クロサワほど名誉毀損が激しかった映画監督は、この日本にいなかったと思う。
それだけ、全日本に限らず全世界から「次は何を撮るのか?」を期待されていた、始終動向を監視されていた、スーパースターだったことを証明している。
有名な「トラ・トラ・トラ」監督降板騒動(1969年)後、最初の作品
「どですかでん」を観た後の世間の反応はどうだったか。
「赤ひげ」「用心棒」の痛快な面白さを当時の客は期待していただけに
「こんなものしか撮れないのか」 と失望の色は非常に大きかったことと思う。
じっさい、本作は「トラ・トラ・トラ」の降板時に黒澤がノイローゼだったとの風評が映画界やマスコミに流れたため、健在を示す意味で急遽とった作品。
だからどうしても、小ぢんまりとした作品にならざるをえなかったのだ。
それが有り体に言えば「アクションを期待した」当時の客の期待を裏切った。
逆にいえば、ミニマムな作品だからこそ、監督のこころが色濃く現れた。
それは、どんなに無様であろうとも孤高であろうとする姿勢。
半世紀以上流れた今だからこそ、もう一度見直す価値がある。
原作は山本周五郎「季節のない街」。
原作は、時代小説の大家・山本周五郎には珍しい現代を舞台にした作品「季節のない街」、大人のための童話だ。
彼の代表作である「さぶ」や「赤ひげ診療譚」のテーマを「清貧」だとすれば、こちらのテーマは「貧窮」。スラム、はきだめ、貧民窟と呼んだ方が正解である「街」を舞台に、そこでぎりぎりの中で生活する人びとの群像を描いている。
(黒澤明は「街」を再現するために、東京の埋め立て地の一角、ゴミ貯め場の近くにロケセットを建てた。)
この「街」は外部との交流がほとんどない。
吹きっさらしの狭い土地の中で、互いに身を寄せ合って生きている。
とはいえ、「街」の住人は「自分以外は皆他人」の精神で孤絶しており
おおよそ「頼り」や「つながり」や「縁」という観念とは、程遠い世界。
だから、住人同士の絶妙なアンサンブルがある訳でもない。
「こんな人間もいるんですよ」と一人一人を淡々と紹介する、どうにも不思議な味わいしかしない、素朴な映画だ。
顔面神経痛が持病の上まともに歩けないが妻の悪口にはしゃきんとなる愛妻家や
日本刀を振り回す男を鎮めたり、泥棒に金を恵んだりする人生の達人が
主役となるイイハナシや
おとこ2人が何思ったか夫婦を交換し、翌日は何食わぬ顔して元の鞘に戻ってたり
お人好しが、浮気性の妻が作った大勢の子供らを、自分の子として扶養したり のコミカルな話もあるが
あとあと印象に残るのは、どちらかと言うと、悲惨な話の方だ。
「がんもどき」と「プールのある家」。 この二つの話は、悲惨なひとびとが、
更に互いに「断絶している/されている」残酷な図式を描かれている。
**「がんもどき」
**
かつ子は十五歳になる。同じとしごろの少女に比べると、背丈も低いし肉付きも悪く、胸も平べったいし腰も細かった。肌はつやのない茶色で、きめが荒く、腕や脛すねにはかなり濃い生毛が伸びていた。――きりょうもよくはない、どこがどうとはいえないが、ぜんたいとして少女らしい新鮮さがなく、生活の苦しさをつぶさに経験した中年の女、といったような印象がつよかった。
「季節のない街」山本周五郎 新潮文庫 269ページから引用
原作で、このような書き出しから始まる、不仕合せな少女のものがたりは
「貧乏」や「社会」のせいと言い訳できない、強いやり切れなさを残す。
黒澤監督は、これを強いストーリーテリングで語る。主役のふたりに、役者ではなく、素人を起用した甲斐がある。
冷酷な叔父にこき使われるかつ子(演:山崎知子)は、いつもうつむいて、人から顔を背けて、人への態度というものがはっきりしない。抑圧された環境の中で生きるうち、自分の思いをうまく言葉に乗せることが、できなくなっている。
はっきりさせないから、却って生意気だと叔父には取られて、ますます強くあたられる。
ある日、叔父の息子が、人目のつかぬうちに彼女を乱暴する。叔父は乱暴の後に気づく。そして、誰がやったのかと、問い質す。もちろん、かつ子は「誰のせいか」言い出すことなどできやしない。ことの当事者である甥は「俺は悪くない、かつ子が悪い」とけろりとしているのが、最悪。
誰のせいにもできないうち、混乱して、舞い上がって、自分で自分のことが分からなくなって、かつ子は、親しい酒屋の息子:岡部少年(演:亀谷雅彦)を刺してしまう。
数日経った。
幸い傷の浅かった岡部少年が退院して、かつ子のもとを自転車で立ち寄る。
岡部少年はあまり気にしてない風、却って内心で傷ついていることが伺える。
当たり障りのない会話の後で、彼は、「じゃあまた、いつかね」と自転車で漕いで去る。かつ子は勇気を出して、初めて本心からものを言う。「ごめんね」と。
だが待ってくれ、その「ごめんね」は絶妙な距離で彼には届いていないのだ。
かつ子は黙っていた。岡部少年は自転車を起こし、手を振って、ペダルを踏みながら、しだいに速力を早めながら去っていった。かつ子はそのうしろ姿を見送りながら、「ごめんね岡部さん」と口の中で呟いた。
「季節のない街」山本周五郎 新潮文庫 311ページから引用
一番伝えたい相手に一番伝えたい言葉は、届かずに終わってしまう。
「プールのある家」
小雨のけむる六月の午後、その親子が街をあるいてゆく。父親は四十歳ぐらい、子供は六歳か七歳であろう。六歳にしても並よりは小さいし痩やせているが、父親との話しぶりを聞くと、少なくとも七歳にはなっているように思えた。
親も子もぼろを着て、板のように擦り減った古下駄をはいている。着ているぼろは袷あわせとも綿入とも区別がつかない。
「季節のない街」山本周五郎 新潮文庫 142ページから引用
原作で、このような書き出しから始まる、そのひぐらしの父と子の物語は、徐々に事態が悪化した挙句、「自己責任」というほかない死を招く。
黒澤明は、これをビビッドな色彩で描く。生涯初のカラー作品の機会を有効に活用する。
はなしは単純だ:父がプール付きの住宅を建てるという、実現し得ない夢を語り続ける、子が父の話にうなづき続ける、それだけ。
駄弁っていてもお腹は減るものだ:食べ物をくすねてくるのは息子の仕事。父親?ただそれを待っているだけ。
「残飯」としか言いようの無い物体(黒澤監督はこれもいろどり豊かに撮すのだ)を、がっつく。味はもとより、安全にも無関心。
ある日、子供が「残飯」の中のご馳走であるしめ鯖にあたってしまう。
徐々に弱っていく息子、どうみても「ビョーキだ」と分かるのに、父は上の空。
言葉の洪水をわっと浴びせて、息子をただのイエスマンに
父親は「自分の話」を肯定するために息子を使っているだけ、とも取れる残酷な構図。
果たして、息子は急死する。
さすがに、愛息の死に、父はオロオロする。
文字通り黄色いガスが充満したゴミための中を、青い顔して子を背負い彷徨う。
これで、やっと夢から覚めるのかと思ったら。
彼は見ているのは、現実ではない 「プールのある家が出来上がった」夢だ。
彼は片手で、空間になにかを描くような手まねをしたが、すぐにその手をだらんと垂れ、同時に頭も低く垂れた。そうして、誰かそこに人がいて、その人間に語りかけるような調子で云った。
「大丈夫、きっと作るよ、きみがねだったのは、プールを作ることだけだったからな、――きみはもっと、欲しい物をなんでもねだればよかったのにさ」
雨のしずくがたれるので、彼はまた顔を手で撫で、眼のまわりをこすった。空はかなりくらくなり、仔犬はふるえながら、あまえるようになき声をあげた。
「季節のない街」山本周五郎 新潮文庫 175ページから引用
最後までこの男の妄想癖は治らず、現実と隔絶されたまま、終わってしまう。
断絶させられた人びと、突き放すか、それとも。
原作は、山本周五郎の不思議と透明感ある文体もあって、「陰鬱さ」は不思議と感じさせない。
それが、かえって、登場人物たち:卑小で、浅はかで、互いを避けて、「がんもどき」「プールのある家」に代表される孤絶している人々の印象を強く残す。
まるで僕らの「醜い部分」を凝縮させたかのような、にんげんたちばかりだ。
原作は、彼らを突き放すかのような一文でしめられる。
それは神の視点=山本周五郎の心の声であるかのよう。
恐ろしく、身震いさせられる、冷酷なほしのこえ。
空にはいちめんに星が輝いているが、そのまたたきは冷たく、非情で、愛を囁きかけるというよりも、傍観者の嘲弄のようにみえる。
「よしよし、眠れるうちに眠っておけ」とそれは云っているようであった、「明日はまた踏んだり蹴けったりされ、くやし泣きをしなくちゃあならないんだからな」
「季節のない街」山本周五郎 新潮文庫 417〜418ページから引用
もちろん、山本周五郎は、こんな酸鼻極まる世界を、素知らぬ顔で描く
そんな人間であるはずがない。
黒澤明はその匂いをわずかにかぎ取り、それを、原作の一編「街へゆく電車」に登場する六ちゃん(演:頭師佳孝)に投影させた。
ポスターの真ん中に配置していることから、彼が本作の「一応の主役」であるのは、間違いない。実際、彼は最初から最後まで唯一出ずっぱりの人物だ。
「街へゆく電車」
原作はこんな書き出しから始まる。
その「街」へゆくのに一本の市電があった。ほかにも道は幾つかあるのだが、市電は一本しか通じていないし、それはレールもなく架線もなく、また車躰しゃたいさえもないし、乗務員も運転手一人しかいないから、客は乗るわけにはいかないのであった。要するにその市電は、六ちゃんという運転手と、幾らかの備品を除いて、客観的にはすべてが架空のものだったのである。
「季節のない街」山本周五郎 新潮文庫 7ページから引用
歳不相応に純朴な六ちゃんの朝は、彼にしか見えない市電を整備するところから始まる。(パントマイムが、見事。)
そして「どですかでん」と音を連呼して、彼だけの市電を運転して、「街」の中を走り回る。雨の日も昼の日も、街の中の「見えない軌道」の上を走り回る。
それを街の外に住んでるガキたちは、彼を見下ろして「バカだなあ」と笑い物にする。世間の常識というものから、六ちゃんは「断絶」させられているのだ。
(母親はこのことに心を痛めて、念仏ばかり唱えてる。)
逆に言えば、「六ちゃんしか見えない世界」はそれだけ強固である、ということ。「プールのある家」の親父殿の妄想よりも更に強く、彼の中だけで閉じているということ。
世界が、彼には違って見えるのだ。
夕焼けは本物よりも赤く、青空は実際よりも青く、雨は現実よりも強い。
彼はその中を「どですかでん…どですかでん…」と駆けていく。
六ちゃんは、天使のような微笑みで、天使のように掛けていく。
つまり、六ちゃんは、スラムに降り立った「無垢の天使」なのだ。
だから最後、この悲惨な世界に、彼は些細な希望を残していく。
これは、原作にはない、黒澤明のオリジナルだ。
すべての登場人物のドラマが閉じた後で、仕事を終えた六ちゃんは帰宅する。
彼が車掌かばんを置くのは、電車をクレヨンで描いた絵が四方八方に貼りつけられた居間だ。「仏壇に祈りなさい」そう、おばさんに促されて、六ちゃんは部屋の扉をぱたんと閉じる。
瞬間、ぱっと、部屋の中が華やぐのだ。
赤に、黄に、青に、チンチン電車の色で、瞬くのだ。
(それは黒澤監督が描いた絵:本作のイメージコンセプトと同様に。)
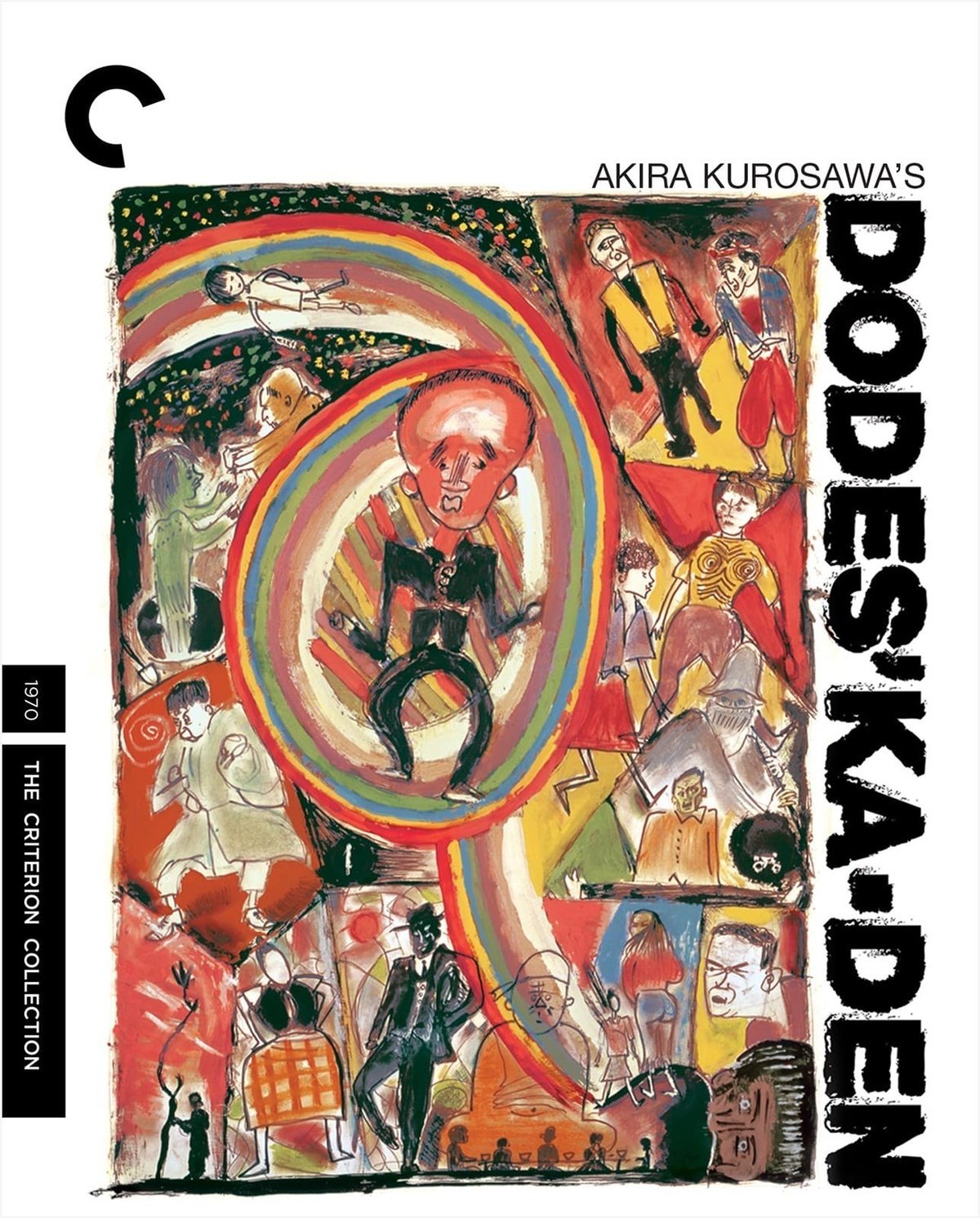
それは、六ちゃんを照らす光り、
いや、劇中すべての「孤絶させられた人たち」に差す光り。
他人の孤絶を、無理に救おうとせず、他人の個性として、受け入れる。
それもまた、人間愛としか言いようのないもの。それはちょうど、山本周五郎があとがきにこう書いたような。
――このノートを小説として再現しながら、作中の人物のひとりひとりに、私は限りない愛着となつかしさを感じた。この人たちはかつて私の身ぢかに生きていたのであり、かれらの笑い声や、嘆きや怒りや、啜り泣く声が、いまふたたび私のところに帰ってきたのである。それを歪曲わいきょくすることなく、できるだけあったままに私は写し取っていった。
「季節のない街」山本周五郎 新潮文庫 あとがきから引用
まとめると、
孤絶された人々をむごたらしく塗りたくった後、最後にその全てを許した。
その孤絶された人々の中心には、六ちゃん、そして山本周五郎と黒澤明がいる。
山本周五郎は文壇と距離を置き、文学賞はすべて辞退した(直木賞史上唯一の授賞決定後の辞退者にもなった)孤高を守った作家だった。(それでも、国内の大衆=読み手には支持された)
黒澤明は「赤ひげ」以降、「天皇」だの「傲慢」だの「わがまま」だの、しょーもない難癖つけられた挙句、業界から孤絶させられた作家だった。(しかし国外のファンが彼の復活を後押しすることとなる)
二人に共通してあったのは、矜恃と言うべきもの。
我一人かんせず、誰の声も届かないところで、心の丈を叫ぶ力。
「映画のことばかり考える」
ヘンクツと言われてもいい、黒澤監督が最後まで曲げなかった矜恃が
1975年の「デルス・ウザーラ」、1980年の「乱」、1984年の「影武者」という
神話の復活につながったのは、間違いない。
なお本作は、1970年のアカデミー国際映画賞にノミネートされている。
今回紹介した作品は・・・
どですかでん。
季節のない街。
いいなと思ったら応援しよう!

