
宮台真司×宇野常寛 〈母性〉と〈性愛〉のディゾナンス──「母性のディストピア」の突破口を探して(前編)
宇野常寛の著書『母性のディストピア』をテーマに、社会学者の宮台真司さんと宇野常寛の対談を3回にわたってお届けします。第1回では、戦後のパラダイムが過去のものとなり、〈近代〉のプロジェクトの頓挫が明らかになる中、劣化する社会への処方箋となりうる「戦後サブカルチャーの遺産」について議論します。
近代社会を覆い尽くす「母性のディストピア」の原理
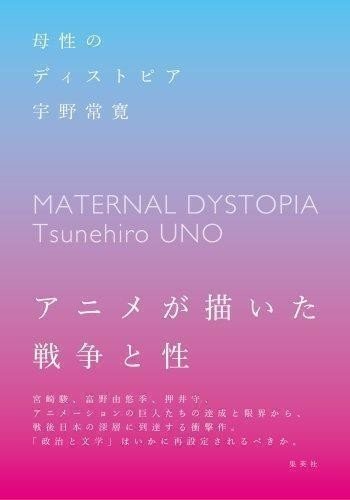
▲『母性のディストピア』
宮台 『母性のディストピア』を読ませていただきました。宇野さんのこれまでの著書の中では一番の力作だと思います。冒頭では、戦後史の総決算を、敢えて政治的言説として展開しておられます。印象的なのは「政治を扱うのはもはや政治的ではない」という諦念の宣言。全く同感です。
僕なりに理由を言えば、政治的コミュニケーションの動機が「皆のためになることを決める」という公的動機から離れ、「鬱屈した輩がスッキリしたいだけ」という私的動機に頽落しているから。政治的コミュニケーションが、状況に向けて研ぎ澄まされた表現でなく、「うまく生きられない、ギャー!」のごとき表出に堕しています。
「ギャー!」と叫ぶ輩の鬱屈の原因は、誤解されがちだけれど、貧困ではありません。ネトウヨとかぶるコアな安倍晋三支持層が実は「コガネ持ちでモテナイ人たち」(『週刊プレイボーイ』2014年3月31日号)であることが問題の一端を指し示します。結論的に言えば、神経症的な「不安の埋め合わせ」に過ぎないということです。
そこを最近出した性愛論(『どうすれば愛しあえるの: 幸せな性愛のヒント』)で分析してみました。性愛の志向は一般にコントロール系(=フェチ系)とフュージョン(=ダイヴ系)に大別されます。でも、これは性愛に関わる志向の分類というより、実はコミュニケーション一般に関わる志向の分類です。
コントロール系に育ち上がった人は、コントロールできない物事が多数あると感じる境遇に陥ると、強い不全感や劣等感に陥ります。そして、そうした不全感や劣等感を埋め合わせるために、コントロール感を得ようと、弱い者を見つけて噴き上がりがちです。排外主義的なウヨ豚(ネトウヨ)とは、そうした存在にすぎません。
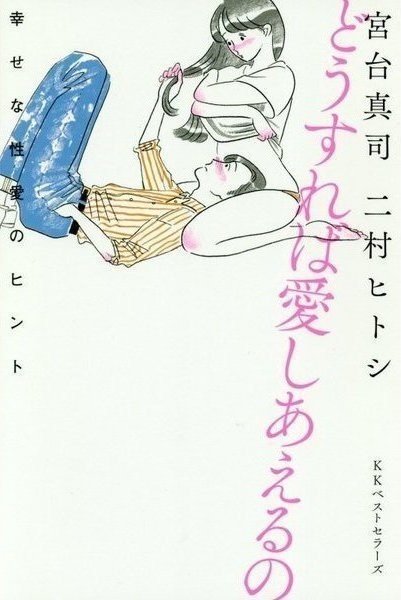
御存じのように、ブルセラや援助交際の存在を朝日新聞で紹介した1993年から、「社会の問題」と「実存の問題」を混同し、「実存的に許せない物事」を「社会的に許せない物事」であるかのように語る連中を、僕は「ヘタレ」と呼んできました。そのように批判することが、実は問題を明るみに出した動機の一つだったんですね。
25年前から既に「社会システムの問題」と「パーソンシステムの問題」とが、現になされるコミュニケーションの中で区別されなくなります。「社会という主語や目的語があるから社会のことを語っている」と思うのは勘違いになりました。それを指摘し続けてきた経緯があるので、宇野さんの問題設定は実に素晴らしいと感じます。
一見すると戦後文化史や大衆文化論の本ですが、「公的ないし政治的」に見える論説も、所詮はマザコン野郎の「私的ないし家族的」な噴き上がりに過ぎないと断じるこの本こそ、真の政治論であり社会論だと思います。「政治論を政治論として、社会論を社会論として展開すると、間違うぜ」という診断が、本書の出発点ですね。
まず伺いたいのは、「母性のディストピア」という問題は日本だけのものか、他国についても言えるのか、です。問いの背景は、今世紀に入って目立つようになった或るシフト、つまり、「欧米が進んでいて、日本が遅れている」のではなく「日本が課題先進国で、欧米が日本の後を追いかけている」という新しい理解へのシフトです。
仮に、新しい理解が正しく、先進国だと思われてきた国々が、どのみち日本の後を追いかけるしかないのだとすれば、戦後一貫して「母性のディストピア」を刻印されたアニメを含めた日本の表現群の存在を──それらを享受することの意味を──世界的にどう考えたら良いのか、という質問になります。
宇野 この本を書いているときは、正直、戦後日本の40年間のことだけを徹底的に考えていましたが、これは原理的な問題なので、今後、世界のあちこちで反復されうるでしょうね。
この本は戦後日本の精神史をアニメーションから考える、というかたちではじまってそこから後半はグローバル経済や情報社会の問題を論じていくわけですけれど、それはまさにこの日本の壊滅的な状況が世界のあちらこちらで起こり得ると僕が考えているからです。
おそらく今後に日本は課題先進国ですらなくなっていくでしょう。しかし今はまだ、違う。これから日本が終わっていくとしても、戦後日本の一時期にサブカルチャーの世界だからこそ生まれたユニークな思想や美学や技術を、それ自体が終わっていったとしてもどこか違う場所や領域でその遺伝子が生き残り、応用されていればいい、くらいのつもりで書いています。
宮台 確かに日本が終わるだろうということは誰もが明瞭に感じているでしょう。だからこそ、不安を埋め合わせるために「日本が一番」みたいなクズ本やクズ番組が、まじでペストのように蔓延している(笑)。実際それがフロイトやそれを下敷きにしたフランクフルト学派の学説に従ったオーソドックスな診断になります。
とはいえ、米国や欧州の没落も昨今では誰もが明瞭に感じています。単なる偶然ではありません。近代社会の全てが「母性のディストピア」なのではないか──。そんなふうに本書を拡張できるだろうと僕は思うのです。それには、「母性」の概念を「無自覚な依存」「見たくない依存」というふうに拡張すればいいだけです。
僕が「九条平和主義左翼」や「対米ケツナメ改憲右翼」を揶揄して来たように、日本は意識化を否認しつつ米国にドップリ依存して来ました。思えば、ウォラーステインの世界システム論が「先進国/後進国」図式を揶揄して来たように、「先進国」も意識化を否認しつつ周辺地域を含む世界システムにドップリ依存してきた訳です。
日本に限れば、米国支配ゆえに政治的独立が不可能な日本で、市民社会として自立したフリをするのが左翼、国家として自立したフリをするのが右翼です。左翼ゴッコと右翼ゴッコのフェイク。コスプレ左翼とコスプレ右翼のコミケ政治です。ならば、全てがフェイクであるような現実に耐えてどう尊厳を保つかが問題になる。
これが戦後のアイロニカルな──壮大な主題が矮小なモチーフに対応づけられる──課題であり、DVに耐える妻に依存する江藤淳も、無力な男を女が裏で助ける村上春樹も、少女だけが飛翔する宮崎駿も、未熟男子の成長への焦りに満ちた富野由悠季も、子宮の如き終わりなき日常に苛立つ押井守も、同じ課題の反復だ──。
本書を一言でまとめればそうなります。この反復を日本に特殊だと捉える発想に立つなら、「母性のディストピア」的な「無自覚な依存」「見たくない依存」から解き放たれた理想の「自立した近代」がどこかにあると想定する構えになります。でもそんな想定はデタラメじゃないかという理解が、既に世界に広く拡がっています。
経済学者ダニ・ロドリックが言う通り、理想の〈近代〉は、登場した順に言えば、主権国家と資本主義と民主主義のトリニティ。でも理想が可能だと思われていたのは、世界システムへの依存を「見ないフリ」ができた短期間だけ。グローバル化で各国で中間層没落が始まる90年代後半には、〈近代〉の不可能性が気づかれ始めます。
それから20年。「先進国」は今も〈近代〉が可能であるかのようなフリをしていますが、先にお話ししたトリニティなどあったタメシがない日本は、20年以上前からそんなフリができなくなっています。日本が落ちこぼれだからじゃない。〈近代〉がそもそもフェイクである事実が、「弱い輪」である日本で最初に露出しただけの話です。
宇野 その民主主義と資本主義の幸福な結託、具体的には「戦後中流」という階層とライフスタイルというものは究極的にはマーシャルプランとGHQの産物、第二次世界大戦後の西側社会でのみ成立した、極めて政治的に醸成された状況に過ぎない、ということですよね。
そういった構造が、戦後日本においては意図的に忘却されていた、または忘却したふりをされていた。これがこの本で僕が述べている「母性のディストピア」的な状況であるわけですが、そう考えたときに、つまりそれが政治的な作為に基づいたものであったと自覚し得る社会と、政治的な作為であることを忘却したふりをし続けてきた社会とのどちらを参照するのか。 まがりなりにも市民社会という建前が成立していた西ヨーロッパを参照していかにすればその奇跡的な状況が維持できるのかを考えるのと同じくらい、市民社会が成立しないままズルズルと社会を回してきた日本を、もちろん反面教師的に参照すべきだと思います。
ここから先は
¥ 540
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
