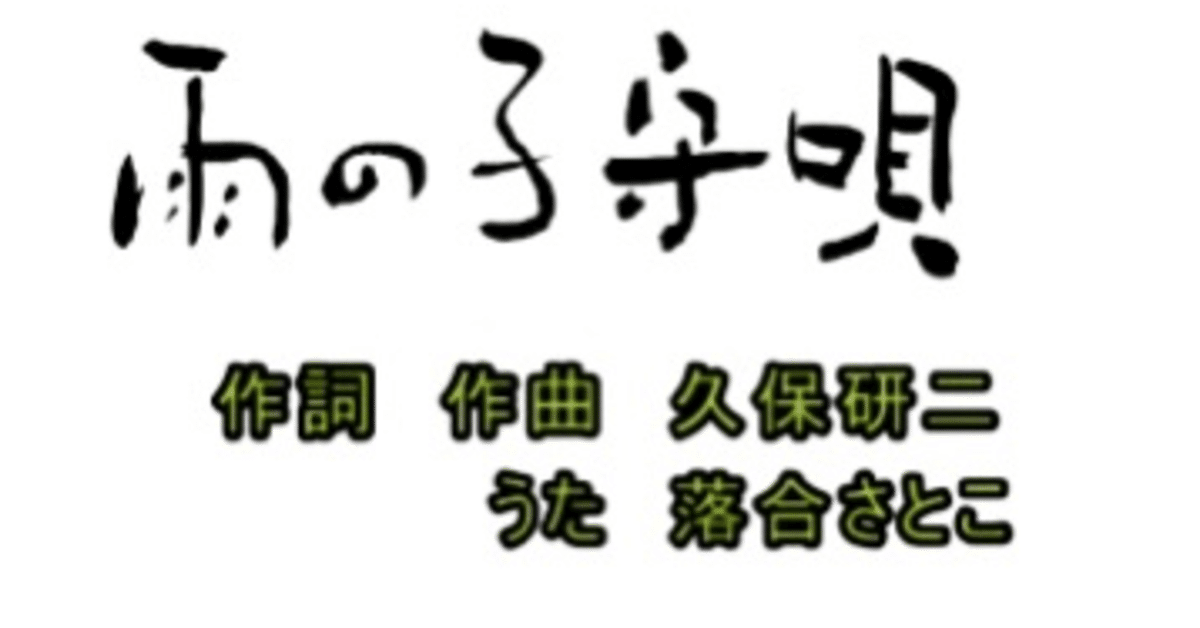
エッセイ 雨の子守唄 (山口でうまれた歌)
幼稚園に通った一年間のあいだに、自らに絶対と刻んで課した掟を破り、一度だけ人前で泣いたことがある。
喧嘩で負けたわけではない。
雨の日、暗くて辛気くさい廊下の下駄箱に染み付いた底なしの淋しさに突然気付き、たまらず座り込んでしくしくとベソをかいてしまったのだ。
学友の誰かが告げたのであろう、不覚にも気付いた時には先生の柔らかい手が肩にあった。
理由を問われたがうまく答えられるはずがない。それでも限られた人生経験とボギャブラリーを駆使して、精一杯繰り広げる意味不明な説明は、あらゆる他者に対し"抽象の極み"であったに違いない。
若く美しい先生は、他の園児とまったく異質の感受性を目の当たりにして途方に暮れ、迷惑が少し混ざった困惑をそのまま母に伝えた。
当時の私は、親にどう伝えられようが、叱られようが、評価されようが……そういうことをまるで気にしていなかった。ある意味親も大人も見切っていたふしがある。
とはいえ、自分に絶対的な自信があったのではない。それよりも自分自身に大きく支配されていたのだ。
だから私は親や教師より、雨の憂鬱さの方がずっと苦手だったのである。
雨の日に漏れ聞こえる音は、とびきり私の心をえぐった。それが音楽室のピアノでも、二階の窓のソプラノリコーダーでも、列車の音でも、雨だれでも、人の話し声でも、虫やカエルの声でもだ。
雲が見当たらない突き抜けるような快晴の真っ昼間でさえ、雨を想像するとたちまち景色にグレーのフィルターがかかった。
一度そう見え出すと、明るければ明るいほど逆に暗さが増す錯覚に陥った。
明るい雨と晴れた日の雨の違いも見抜くようになり、ついには晴れていても実際には降っていない雨が見え始めた。
精神が際どく振れていく。
やがて、夜に見る夢と昼間に見る夢があることを発見した。そしてその頃から私は次第に反対という概念がわからなくなってしまった。
わからなくなれば、しぜんと何でも疑うようになる。普通の子のように、接したものを素直に喜べなくなってしまったので、明らかに笑顔が減った。
北風と太陽の童話を読み強弱を疑った。
五条大橋の弁慶と牛若の決闘を知り大小の優劣を疑った。
次に競う意味を疑った。速さを競えばより早く人生を駆け抜けてあの世へ逝った者がこの世の勝者となるではないか……。
そしてその疑いはさらに尾をひく。
父方の祖父の葬式で大勢の人が声をあげて泣いたが、母方の祖父の死が病院から伝わったとき、誰一人として涙を流す者がいなかったのだ。
母方の祖父は大酒のみで酒癖も悪く、孫である私の目にも、人格者の要素は一片たりとも映らなかった。
けれども、あとに残った人を一切悲しませなかった生涯は、もしかすればかえって思いやりがある見事なものだったとは言えないだろうか。
幼い脳の中で、痛々しくも思考が24時間営業を始めた。
大人が悩んで語れば、それはそれで知的なものとして評価されるのかもしれない。善悪、陰陽、白黒、有無、阿吽。それらは反対ではなく、実は互換を意味するとなれば話はぐっと深くなる。
しかし幼稚園児の「わからなくなる」という状況は、大人のような概念上の問題とは次元が異なり、とことん現実的で切実な問題だった。
疑問は現実と重なり、現実は夢と交差し、不安定なままの記憶と認識が夢と現実の間を駆け巡る。加速すればするほど現実が後に置き去りになり、やがて転げ落ちるように、健康と社会生活の両方に支障が生じだしたのだった。
最も身近な存在であったはずの両親は、まず私を"嘘つき"だと見た。誇大妄想による虚言癖があると思ったのだ。
その次に、夢遊病や多重人格のような精神病を疑い始めた。仮に治療を望んでも、当時その分野に秀でた医師はほとんど見当たらなかったはずである。
やがて両親は、自分たちの手には負えないとあきらめて、天才となんとかは紙一重ということばに脅迫されるようになる。
そしてその頃から自分の子供を、腫れ物に触れるように扱いだし、私は親の変化を冷静に受け止め、時には傷つき、時には大いに利用した。
それは今から思えば身の毛がよだつような、醜悪極まりない所作であった。この点においては、私は太宰治にも負けない自信がある。
小学校にあがる前に私が死ぬと信じていたと、父が私に告白したことがある。
もちろん幼い私が虚弱体質で、何度も危篤寸前に陥ったということもその理由だが、本質はそこではなかった。
父が信じたのは一種の運命論のようなもので、実際にはなかった"天からのお告げ"のような、漠然とした塊の雰囲気に捕われていたからだった。
父の考えや話には、根拠や論理性が欠如しているうえに、一切それに気付こうとしないという致命的な欠陥がある。
けれども本人にとっては感覚的だが、直球の確信だったことだけはまちがいない。
やがて私は、父の予想に反して死なずに小学校にあがった。その頃からなぜか体質が一変して病気をしなくなったのだ。
最後のヤマが、幼稚園の末期に患った麻疹だった。けれどもそれと同調するかのように、徐々に非凡が平凡化していった。
無学な両親は、それを複雑に喜んだが、私は急激に劣化する自らの感性に、とまどいながら妥協するしかすべがなかった。
その妥協とは、自らの理想と現実とのギャップを、日々ごまかして埋め続けることだった。
その後の私の人生は、ごまかしとまやかしの繰り返しだったように思えてならない。
赤裸でむき身だった心臓にも、ほどなく薄い皮が張り産毛も生えた。
面の皮は誰よりも分厚くなった。それを成長と呼ぶのかもしれない。
それでも相変わらず雨は苦手なままだった。
さすがに、雨で泣きだすことはなくなったが、どうしてもうまく傘をさせない。いくら注意をしても、あきれるほどずぶ濡れになる。
五十を越えた今も、それは変わらない。
《雨の子守唄》 山口でうまれた歌
作詞・作曲 久保研二
①
ほんに小さな駅の夕暮れ
ピアノが漏れる 歌が染みだす
ほんに小さな心の隙間
ピアノが潜る 毛虫が浮き出る
ランララ ラララン ララランラン
ほらまた突然激しい雨だよ
走りださなきゃ逃げきらなくちゃ
②
ゴロンゴロンと空が転がる
カーテン裂けて 稲妻走る
ゴロンゴロンと布団の上で
自分の匂い 探して転がる
ランララ ラララン ララランラン
ほらまだお外は激しい雨だよ
てるてる坊主は 泣いているだけ
※
おねんねしなきゃ
良い子にしなきゃ
言いつけ守って
おねんねしなきゃ
布団の底に逃げ込まなくちゃ
あしたはきっと
あしたはきっと
あしたはきっと
晴れるから
