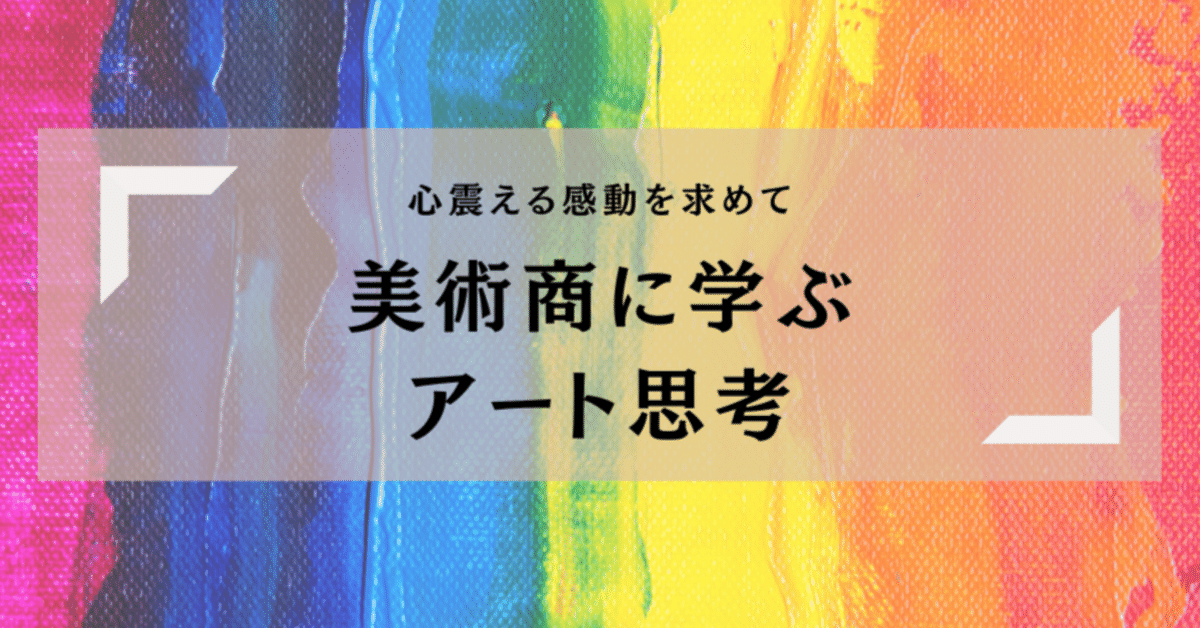
思想が宿る作品への気づきが暮らしに面白さを生む。加島美術vol.4
2023年3月21日、衝撃的なニュースが流れた。葛飾北斎の浮世絵がニューヨークのオークションでおよそ3億6千万円という記録的高値で落札されたのだ。その数年前には伊藤若冲の作品が約1億7千万円で競り落とされ話題となった。昨今、日本美術は海外でさらに高い評価を受けはじめている。私たち日本人は豊かな美術の土壌に暮らしながらも何かを見落としてはいないだろうか。今回は古美術の聖地である京橋に若くして日本美術の画廊を構える加島林衛氏を訪ね、4回にわけて話をうかがうシリーズの最終回となる。
AI技術の隆盛でいかに速く目的を達成するかというタイムパフォーマンスに注目が集まる一方で、対極として『アート思考』がブームとなっている。この言葉はさまざまに解釈されているが、ここではアートを鑑賞する感性を身につけ、感動に至ることができる技術だと捉えてみたい。ロジカルに割り切ることが良かれとされる時代だからこそ、感じる心を研ぎ澄ませ、美術品がもたらす味わいに身を任せてみよう。
■話し手
加島林衛(かしま しげよし)
1974年、東京生まれ。株式会社加島美術 代表取締役。

伊藤若冲を掛けた茶室の秘密
――今回はシリーズ最終回となります。暮らしのなかでの日本美術の楽しみ方についてお話をうかがいます。よろしくお願いします。
加島:よろしくお願いします。
――さきほど画廊に展示されていた北大路魯山人(きたおおじろさんじん。明治から昭和の日本の芸術家。多彩な分野で作品を創出したが、特に陶芸家、料理家として有名)の小皿を拝見しました。味があって、ちょっとしたスーツを買うくらいの値段だったので悩んでいます。ここへ来ると目移りして困ってしまいます。
加島:ありがとうございます。茶室の伊藤若冲(いとうじゃくちゅう。江戸時代中期の絵師。奇想の画家と呼ばれ色鮮やかでリアルな花鳥画で知られる)の掛け軸はご覧になりましたか。

出典:THE JAPAN NEWS
――はい。あちらは数百万円でさすがに手が出ません(笑)。美術館ならガラス越しに見る名品クラスを、間近でじっくり鑑賞できるのは夢のようです。床の間と一体となって絵が空間に溶け込んでいるようでした。店舗のデザインにもこだわっておられますよね。
加島:ええ、私はインテリアの専門家ではないのですけど、内装デザインというか建築が好きなものですから。2013年に今の場所に移る時「こんな感じにしてみたい」という方向性があって建築家と話し合いをしながら構想を練り上げました。ただ細かなディテールに関しては設備に関わってくるので、専門的な方とさまざまなタッグを組んで進めていくのが成功に一番近いやり方なのではないかと思います。それぞれプロはプロという役割がありますよね。
――例えばこのギャラリーに来られた方に建築的な部分で「ここを見てほしい」というところはありますか。
加島:特に2階はかなりこだわり抜いて作っていますね。私たちは美術商ですから美術品をお客様に紹介する仕事です。ただ往々にして陥りがちなのが作品一つ一つに力があって魅力的なものですから仲介する私たちが悪く言うとちょっとあぐらをかいてしまうということです。

つまり、さしたる努力がなくてもお客様の方がその作品の魅力に惚れ込んでお求めいただいてしまいがちなんですね。私はそれがどこか甘えなんじゃないかと思っていまして。美術品が素晴らしいことはもちろん大前提なのですが、さらにその作品がこのお店を通じて、より光を放つというか、もしくはまた違った側面でこういう見え方もするというきっかけが何か作れないかなというのが、そもそも内装を考える上で一番大事なことでした。
2フロアのうち1階部分は少し現代的で、2階がクラシカルな空間演出となっていますがどこか現代とも通じる感覚を意識しています。

2階には伝統を象徴する茶室を設けましたが、これは「組み上げ」と言って、一回京都で組んでそれをバラして運んでもう一度ここで組み直すやり方で作っています。さらにそこに茶人の方の力添えをいただいて書画がより引き立つ空間として作りました。 2階のほかのところも京都から職人さんたちに来ていただいて手がけていただいているのです。もちろん東京にも素晴らしい職人さんがいらっしゃると思うのですが、私がもともと京都にいたということもあるのでそちらのネットワークを生かしました。 壁はこだわりの一つです。通常は日本の伝統である聚楽壁(じゅらくかべ。京都の聚楽跡地で産出される土を使用した壁)で仕上げます。まず下地を作って下地塗りをして、その次に中塗りで最後に仕上げの本塗りを行うという、漆のように何層にも重ね塗りするわけですが、あえて中塗りで止めています。私が個人的にこの風合いが非常に好きなのでそうしているのです。


――作品が引き立ちますね。
加島:ええ、特に上からの照明があたりますよね。すると左官が上手いか下手かで光が歪んでしまうのです。この壁は京都の職人さんがしっかりやってくださってフラットで歪みがありません。これはとても大事な点で、作品を鑑賞する時に壁が少しでも歪んでいると影が出て視覚的に目にさわってしまうのです。
――そうでしたか。私の実家に床の間があって若冲を掛けたところを想像してみました。当たり前ですが格の違いとでもいうか絵に負けてしまいますね。いつもこの店舗へ入ると気持ちが落ち着くのは空間全体が醸す感性の豊かさに包まれるからですね。
加島:ありがとうございます。時々お客様からもご自宅の改装にあたってご相談を受けますよ。私もできる範囲でお話ししています。地方の方は割合床の間があったりするのですが、一からお作りになる時にはアドバイスとしてやはり建築家もしくは内装コーディネーターだけではなく、美術商にもちゃんと聞かれた方がいいと思います。
初心者におすすめの日本美術をテーマにした旅
――気軽に日本美術を学ぶとしたら、最初は何を手に取るのがよいでしょうか?
加島:書籍でしたらさまざまな出版社から『一から学べる日本美術』のようなシリーズが大人向けに出ていまして比較的入りやすいのではないでしょうか。
漫画でしたら『ギャラリーフェイク』というのがあります。日本美術だけではなくて西洋美術までいろいろなジャンルが網羅されていますし、はみだし者が活躍するという面白さがあってアート版の『ブラック・ジャック』のような感じです。美術の入り口としておすすめです。
――さきほど京都の話が出てきましたが、日本美術をテーマに旅をするならどのような場所がよいでしょうか。
加島:日本の各地には、その場所に根を張っている美術家がたくさんいます。どこがおすすめかというより、まずは自分が好きな作家を決めるのが優先で、次にそのゆかりの地を探していくというのがよいでしょう。
例えば円山應挙(まるやまおうきょ。江戸時代中期の絵師。現代の京都画壇に系統が続く円山派の祖)にハマったということにしましょう。それなら彼が活躍した京都から出身地の丹後地方へ行くなど足跡をたどるわけです。伊藤若冲であれば美術館で作品を見て歩くのもたまらないでしょうし、彼の歩んだ歴史に共感してみたいということであれば京都を拠点に墓所がある伏見の方へ行ってみるという風になると思うのです。
関東なら葛飾北斎(江戸時代後期の浮世絵師)をテーマにした旅もいいでしょう。狩野派(室町時代中期から江戸時代末期まで常に画壇の中心にあった日本絵画史上最大の派閥)もありますし、近代であれば横山大観(よこやまたいかん。明治期の日本画家。富士山を題材とした日本画は人気が高い)が生まれた茨城や、菱田春草(ひしだしゅんそう。同じく明治期の日本画家。若くして逝去したため「不熟の天才」と呼ばれる)の出身地の長野に行ってみるなど、それぞれの方がその魅力に取り憑かれた作家の足跡をたどる旅が楽しいのではないかと思います。
――それは面白そうです。関西と関東が中心になりそうですね。
加島:日本の文化でいうとやはり京都か江戸かと思いますけれど、個人の作家にとらわれなくてもいいかもしれません。例えば江戸期は鎖国で、当時はオランダとポルトガル、中国の文化だけは入ってきていました。その時代の貿易で取引された美術品などに興味を持った場合は、神戸もしくは長崎という風になると思うのです。
――日本中に広がっていきますね。
加島:そうですね。興味を持つものが果たして何になるかによると思います。戦国武将もいいですね。美術的価値というより歴史的価値になりますが、東北から九州の全国が対象となりますし、これで一つツアーができそうですね。
――旅と言えば日本各地で骨董市が開かれていますが、どのように楽しめばいいでしょうか。
加島:骨董市は東京でも関西の方でもいくつかやっていますからお好きな方は本当に足を延ばして地方まで足しげく行かれています。ただ一般の方が何かを学ぶという視点で行くとすれば、その場合はお店がいいかと思います。骨董市は基本的に販売イベントなので商品についての話ができても、他に雑談めいたことをできるような空間ではありません。掘り出し物を探したり、ちょっと気になるものがあるかなという感覚で行く場所ですよね。
私は、さまざまなところまで足を運んで追い求めるというスタンスよりは出会えるものは一つの運だと思っています。ですから東京の骨董市をちょっと覗いたとしても気に入るものや人にたまたま出会う場という感覚でいます。
――骨董市は規模の大小や多様なスタイルが混在しているので初めての方は戸惑うかもしれませんね。おすすめの骨董市はありますか。
加島:神楽坂に加島美術関連の現代アートのギャラリーがあって、新潮社さんによる「青花の会|骨董祭」という骨董祭の会場として年に1回場を提供しています。そのイベントは出店の皆さんも質が一定でしっかりしておられますし、並んでいる作品も魅力的なものがありますから行かれるにはいいのではないかと思います。
青花の会|骨董祭
https://www.kogei-seika.jp/seikafes/2023.html
あとは目白で開催される骨董市や東京美術倶楽部の古美術のイベントなどがありますが、買わないといけないという雰囲気がなくて比較的入りやすいです。
生活に芸術性を取り入れるために
――旅先で古い町を歩いたり、日本料理のちょっとした盛り付けを見たりすると日本人でよかったと感動が自然にわいてきます。日常的な衣食住と日本美術にはどのような関係があるのでしょうか。
加島:その話はそもそも芸術とは何から構成されているのかというところからスタートすると思います。つまり、美術作品や芸術の定義とは一体何かということなのですけど、答えをズバリ言うと「人が生み出すもの」なんですよね。
当然、絵画や彫刻、刀など自然のものに何らかの人の手が加わって、そしてそこに人のメッセージや感覚が宿り、そして後に私たち鑑賞者がそれに心を打たれるというものです。
洋服も焼き物も料理一つでさえも人が作り出すものなのですよ。さらにもう少しスケールを大きくすると建造物も芸術作品になりえると考えているのです。ただこれをひとくくりにして「人が作り出すものだったら、じゃあそこの商業ビルも芸術作品ですか」と疑問を持たれるでしょう。その時にもう一つ付加価値として作家の思想がどれだけ深くその作品に宿っているかで、芸術になるのか、一般的に消費される商品になるのかの境目なのではないかと思っています。
その点でいくと京都などのしっかりした料亭さんなどはそもそも料理にもしっかり真摯に向き合って、そしてその盛り付ける皿にもこだわり抜いていてそれこそ魯山人やさまざまな陶芸家のものを使うことでトータルに芸術としての基準を高めているのではないかと思います。
――私たちの普段の生活に芸術性を取り入れるにはどうすればいいでしょうか。
加島:芸術というものがとても好きだというタイプの方々に共通しているのが、ご自身の生活にも比較的こだわりがあることです。日常的に目に入ってくるもの、耳にする情報などを自然とふるいにかける習慣があるんですね。「本質的なところは一体どうなのだろう」というものにそもそも興味を持っておられるわけです。
例えばスタートとして焼き物を自分で作ってみる、または書をたしなんでみるなど、自分の範疇に関しては独創を生かしてつくってみるのもいいのではありませんか。
“住”で言うと普通の建売マンションとは一線を画したところに住んでみる。住まうことに対して思想とまでいかなくても意識やコンセプトのようなものを持ってみる。衣食住のなかでそういうものがしっかりしてくると芸術と生活の調和が取れてくるのではないでしょうか。作家の思想が深く宿っている作品と、一般的に消費される商品との境目に気づけるようになると思いますし、暮らしに面白さが生まれるのではないでしょうか。
――ありがとうございました。
株式会社加島美術
1988年創業の東京・京橋に店舗を構える画廊。中世から近代までの日本画・書画・洋画・工芸など日本美術を取り扱っている。定期的な販売催事や選りすぐりの優品をご紹介する日本美術を中心に取り扱う画廊。展示販売会「美祭 撰 -BISAI SEN-」、日本美術に特化したインターネットオークション「廻 -MEGURU-」、イベントなどを通じて新たな美術ファンの開拓を行っている。公共機関や美術館への作品納入も行なっている。
店舗住所:〒104-0031 東京都中央区京橋3-3-2
https://www.kashima-arts.co.jp/
「廻 -MEGURU-」とは
⽇本美術をもっと気軽に、安⼼して、正しく売買してもらうために2019年に始まったのが、⽇本美術に特化したオークション「美術品入札会 廻-MEGURU-」だ。国内外の美術品を売りたい⼈と買いたい⼈をつなぐプラットフォームとして、全国から出品された作品が揃う。2021年にはインターネットオークション「廻 -MEGURU- オンライン」がスタートし、アート初心者も構えず参加できる身近なプラットフォームへと進化を続けている。
「美術品入札会 廻 -MEGURU-」:https://meguru-auction.jp/
「廻 -MEGURU- オンライン」:https://www.meguru-online.jp/
取材・執筆:杉村五帆
執筆者プロフィール
杉村五帆(すぎむら・いつほ)。株式会社VOICE OF ART 代表取締役。20年あまり一般企業に勤務した後、イギリス貴族出身のアートディーラーにをビジネスパートナーに持つゲージギャラリー加藤昌孝氏に師事し、40代でアートビジネスの道へ進む。美術館、画廊、画家、絵画コレクターなど美術品の価値をシビアな眼で見抜くプロたちによる講演の主催、執筆、アートディーリングを行う。美術による知的好奇心の喚起、さらに人生とビジネスに与える好影響について日々探究している。
https://www.voiceofart.jp/
いいなと思ったら応援しよう!

