
アクティブ運用に押し付けられた冤罪と投資への5つの誤解㉑
本記事は現在、最後(オチ)以外は無料で読めます。
内容が参考になった方は是非、オチは購入していただければと思います。
私自身、noteで過去2年に渡って多くの投資・金融に関する記事を書いてきました。今回はそれらから抜粋して書いています。

真面目で、愚直に投資について、自分の人生について世の中で言われていることを鵜呑みにせず、真剣に考えたい人、耳の痛い意見にはお金を払ってでも学ぼうという意欲がある人を前提に書いていますので、予めご了承ください。
世に溢れるYouTuberやブログなどのどうしようもない結論だけを切り取った話を鵜呑みにしてしまった思考停止のにわか投資家やインデックス信者もしくは現在まだ投資経験が10年未満の初心者投資家で、あろうことかiDeCoやつみたてNISAを間違って”先に始めてしまった”人たちへの警鐘です。
これらに該当する方は気分をとても害される可能性が極めて高いです。

私は私の価値観、世界の見方をこの記事で書いています。
あなた方の価値観を否定するつもりはありませんので、あなたが自分でそうだと思う事を信じればよいです。

しかし読み終えた時、あなたの世界の見え方が少しでも変わったならオチまで買って読んで欲しいと思います。
ド正論の記事を書くと炎上や被害妄想のようなバッシングが起こることもありますが面倒くさいので、そういう方は決して読まないことをお勧めします。(私は警告しましたからね?)

そうなった場合には記事の無料公開を上の方へ引き上げるか記事の代金を値上げすることになりますので、他の方が読む機会を失うことになります。
尚、これらの現象を避けるために記事の共有(シェア)はご遠慮ください。
自分の行動には責任をもって下さいね。
尚、少しでもこのドSな内容をほんわかさせるためにマンガなどのシーンを散りばめています。
楽しんで読み進めて頂ければと思います(/ω\)

=================ここから本編================
いつの世もブームというものはあるものです。
そしてそのブームに浮かれている時に限って、バブルが弾けるというのはこれまでの人類の歴史を振り返れば呆れるほど何度も繰り返されてきたことです。
愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ
これはプロイセンの鉄血宰相ビスマルクの言葉ですが、愚者というのは自分で痛い目に遭わなければそれが問題である事にさえ気づけません。

賢者は歴史に学びます。
歴史とは自分以外が紡いできたものです。
つまり他者の経験から学ぶ事で、自身を成長させていくのです。
昨今で言えばこうした状況というのは「マスクの品不足」が多くの人の目に留まり、その分かりやすい例と言えるでしょう。

あれだけ品薄で高騰していたマスクの価格が暴落を始め、善意で国内生産という決断をした企業やお店などでも在庫がだぶつき始め投げ売りの様相が目立つようになってきました。
これは投資でも全く同じことが言えます。
投資においては昔から”素人までもが始めた頃が一番危険”というものがあります。
靴磨きの少年とある銀行家の話
有名なエピソードは好景気と空前の株高に沸く1929年、ある銀行家の男が米国ウォール街で街角の靴磨きの少年に靴を磨いてもらった時のエピソードです。
*米国は銀行と証券会社が一緒になった業務形態であることが多い。

靴磨きを始めながら少年は尋ねました。
「旦那は銀行の方ですよね?」
男が頷くと、少年は嬉々として
「株は儲かるんでしょ?僕もそろそろ買おうと思っているんですけど、旦那はどの株を買ったら一番儲かると思いますか?僕はいろんな人の話を聴いていると〇〇という会社のが良さそうだと思っているんですがね…」
男はこんな年端もいかない子供までもが株式投資に関心を持ち、挙句お金を投じようとすることに今の株高が危険なバブルに近づいていることを察して持っていた株式を、現金に換え始めました。
その数か月後、株式市場は未曾有の大暴落を経験。

NYダウが暴落前の水準に戻ったのは四半世紀後の1954年までかかりました。
この暴落をきっかけに世界恐慌、そして第一次世界大戦。
また後の第二次世界大戦という悲劇を招きました。
昨今の株高や投資ブームも時代背景が異なるとはいえ、不穏な状況が大変似ていると考えるのは考えすぎでしょうか。
特に危惧しているのがこれまで投資をしたことがなかった初心者投資家が投資をし始めていることです。
それは日本だけでなくアメリカなどでも起きています。

初心者たちの危険なミーム銘柄への加熱投機
アメリカではオンライン掲示板「レディット」などで、この銘柄をみんなで買おうと情報が交わされているやり取りで、ミーム銘柄(Internet meme。最近の日本語だとバズるのような言葉が近い)への過剰投資による株高が起きています。

アメリカではトランプ大統領が強制力のあるロックダウンなどによって失業給付などの大規模な助成金が労働者に配られ、働いている平時よりも現金を保有する労働者たちがこの一年ほどの間に急激に増えました。

加えて2021年1月20日に就任したバイデン新大統領は更に追加の給付を行いました。
そこに気軽に情報のやり取りができるスマートフォンやSNSの浸透した状況、またロビンフットのような売買手数料無料のアプリが登場したことで、手元の余剰な現金を投資に回そうとする動きが活発になりました。
近年、日本でも証券会社各社が競う様に手数料の過剰な競争を始めています。ネット証券などは「国際的な流れに乗る」とこうした動きを表明しています。
しかし多くの人たちが誤解をしてはいけないのは売買手数料が無料(もしくは格安)なことは投資をするかしないかの然したる要因ではないという事です。
また多くの人が勘違いをしているのがこうした株高による値上がりでお金を増やすことを「投資」だと思い込んでいる点です。
ミーム取引は投資ではなく「投機」または「ギャンブル」や「マネーゲーム」です。
いつかこの実態を伴わないマネーゲームは、株式市場と投資家自身にとんでもないしっぺ返しをしてきます。
※しっぺ返しをくらったのも私の経験談。
株価というのが株式市場の需要と供給によって値上がりや値下がりをするという当たり前のことを理解していれば、短期売買を繰り返すこうした動きは誰かが得をした分だけ、誰かが損をしている事になります。

この代表的な事例である2021年1月のロビンフット・ショックではゲームストップ*という企業の銘柄を空売りしていたヘッジファンドがその標的となりました。
*日本では平成初期の頃までに流行したテレビゲームショップやファミ通などのような関連出版をしている事業をイメージすると分かりやすい。

これは素人たちが声を掛け合ってミーム銘柄に投じるお金が莫大な資金となり、ヘッジファンドを懲らしめた…という単純な話ではなく、ヘッジファンドに素人たちが喧嘩を売った事になります。
こうした個人投資家の一部は、米メディアに「金もうけではなく金持ちを破綻させてやりたい」などと取引の理由を語っている。大手金融機関が牛耳る「ウォール街」を個人投資家が屈服させたとして、業界関係者から「金融界のフランス革命」(米ブルームバーグ通信)との声も出ている。
決してヘッジファンドが健全な投資をしていたかとは言えないかもしれませんが、余計に波風を立てる必要などないのです。
向こうは利益を上げるためには殺人以外ならなんでもやる連中です。
かつてヘッジファンドは英国の中央銀行、イングランド銀行でさえ破綻まで追い込んだのです。
彼らは最低一口1億円相当という途方もない富裕層らから余剰資金を集めています。(出資額1億以下のヘッジファンド運用は全て詐欺と考えてよい)

反撃や復讐、闇討ちをされなければよいですね。
ここまで理解できていますか?え?まさか…ついてこれていない?
ついてこれている方、理解できている方だけ先を読み進めてください。
手数料の低廉・無料化と国の目指す長期投資の明らかな矛盾

投資をする人は株高であろうとなかろうと、また手数料がかかろうと支払ってでも投資をしています。
まるで手数料がかかるから投資をしない人が多かったかのような報道を目にしたとしたら明らかなミスリードです。

手数料がかからないことで利益が出やすくなることはあり得ますが、利益が出やすいとしたら投資家はどんな行動を次に取るでしょうか?
興味深いことに手数料はかかった方が投資家の保有期間は長期化する傾向になります。
何故なら頻繁な売買に手数料がかかることを敬遠するからです。
しかし手数料が無料化や値下げが起きると何が起こるでしょうか。
短期売買を繰り返し利ザヤを稼ぐ人たちが増えないでしょうか?(笑)

政府と金融庁が目指した「貯蓄から投資へ」は、こういう投資のし方だったのでしょうか?
そもそも利益が手数料程度の幅でしか得られない投資とは、リスクを取ってまでする価値があるものなのでしょうか?(; ・`д・´)
それにも関わらず金融庁とその天下り先であるネット証券(SBI証券・楽天証券など)は結託をして、「コスト=悪」という構図をでっちあげて説明して、情報リテラシー*の低い日本人の若者たちの誘導にまんまと成功しました。

*インターネット上の情報を鵜呑みにせず、自分で咀嚼することができる能力
誤解がないように言っておきますが、私は資本主義社会である以上、誰もが投資をすることが豊かに暮らすためには避けては通れないと考えています。
しかし何事にも順序(ステップ)というものがあります。
金融庁を始めネット証券らが仕掛けた壮大で巧妙で愚かな罠は挙げればきりがありませんが、過去にも何度か書いた記事から抜粋して代表的なものをここでは5つほど紹介したいと思います。

第一、個人金融資産の構成比への誤解
第一に注目したいのは家計における金融資産の構成比です。
本来であれば、アメリカのように生活のためなどに配られた補助金が余剰資金として投資へ回る背景には、そもそもの米国の個人資産における現預金比率の低さにあります。

日銀・金融庁は昨今、各国の家計(個人)における金融資産の構成比を挙げ、日本では「現金・預金」に偏っていて、米国のように「株式・投信」にお金を回すべきだという議論を活発にするようになりました。

その結果、NISAやiDeCo、つみたてNISAなどの税制優遇制度が誕生しました。
世界は投資で成り立っており、投資をすることで世界の経済が持続的な成長をもたらす。
この指摘はもっともで、確かにその通りなのです。
しかしこの情報を受け取った政府・官僚と個人がそれを見て、じゃあ投資をしよう「iDeCoが良いか?つみたてNISAが良いか?」という行動を取ることに対しては慎重になる必要があります。

家計(個人)金融資産の構成比はその国全体での資産の配分を表している結果(リザルト)です。
この結果が導き出されるためには課程(プロセス)があります。
投資に限らずプロセスの中身を近年は十分に精査せず、または自分で理解せずに誰かが切り取った結論・結果にだけ着目・実行してしまう投資家がひたすら増加し続ける傾向にあります。
個人の”本当の資産の構成比”はこうした統計には隠れてしまいますが、大まかな傾向は予想することが可能です。

隠れているうちの一つは年収が高い世帯は預金比率が低く、年収が低い世帯ほど預金比率が高くなるというどこの国でも凡そ共通する現象です。
そして年収が高いほど保険に頼る部分が小さく、年収が低い世帯ほど保険の割合が大きくなる傾向があり、また年収が低すぎる世帯は保険にさえ加入が出来なくなるということも添えておきたいと思います。

当たり前の話ですがこの個人金融資産構成比というのは、生活を持続するのに必要なお金を差し引いて、また近い将来使う予定のお金も差し引いて、残ったお金が100だった場合に日米英ではそのお金を次にどのように割り振っていくのかという結果(傾向)を表しています。
しかしここにはグランドキャニオン並みの巨大な谷があります。

話を少し前に戻しますが、貯金に預けたお金をその先、どう割り振っていったらよいのか分からない日本人に対してこの家計金融資産構成比を見せて「投資にお金が回っていない」だから「投資をしよう」ではないのです。

家計における収支の全体像や、今後いつお金が必要になるのかを客観的に把握することは多くの一般人にとっては困難です。
特に家計簿さえつけていない収支の把握をする習慣がない人にとってはこうした行為は致命的です。

認知バイアス(偏向バイアス、確証バイアス)という大きな障害が待ち構えているからです。
これによって殆どの人は冷静な判断が出来なくなってしまいます。
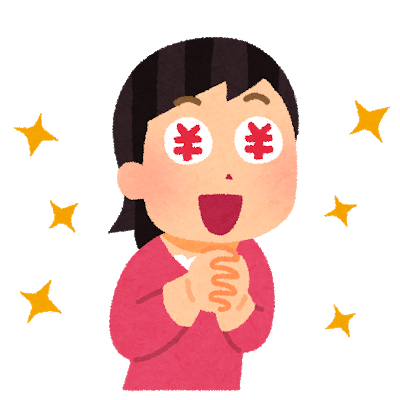
殆どの投資初心者においてリスクに対する認識は極端に甘く、また本来であれば投資に回すよりも先に考えなければならない問題を手付かずのまま投資にお金が増えることに目をくらませ、周りが見えなくなって取り返しがつかないことになるのです。
これも私自身の経験談です(笑)

またここでのリスクとは株価などの値動きだけではなく、必要な資金を必要な時に使えるようにすることを含みます。
このことを「資金の流動性」と呼びます。
代表的な事例は事故や災害、病気による治療からガンなどの大きな病気、働けないリスク、死亡リスクなどの想定されうるリスクです。
殆どの初心者投資家はまだ投資をするべき段階でないのにもかかわらず、投機的な資金を株式市場に投じています。
この想定されているはずのリスクが発生した時に、望まない価格で売却の必要性に迫られます。

こうした問題の多くは弱り目に祟り目。泣きっ面に蜂。
多くの場合に重なることが少なくありません。
この想定されうるリスクの最大の特徴は「起こる確率は低いけれど、一度起こったとしたら取り返しがつかないほどの経済的ダメージ」である点です。
さて、ここまで読まれて内容についていけたでしょうか?
ストレスをためるのは良くないですよ?

第二、ネット証券と対面販売の証券会社との違い

”最強の金融庁長官”と呼ばれた当時の森長官を始めとした金融庁は、対面販売(証券会社・銀行など)の証券外務員が購入時手数料を貪るために回転売買をしていると批判しました。

しかし金融庁が令和元年(2019年)に発表したデータによると投資信託の保有期間がぶっちぎりで短いのは金融庁が強く支持したネット証券の方でした。
(尚、令和2年の調査はネット証券が保有期間で大手証券を抜きました)

証券外務員の中にはそんな悪どいことをしている人が全くいないとはいいません。
しかし信頼が最も大切な証券外務員がそんなことをした日には顧客はその人を長期的には相手にしてくれなくなるでしょう。
私の知る限りでそういうことをやるのはむしろ銀行(ゆうちょ銀行含む)の方です(笑)
※個人的には銀行は絶対に保険・証券の相談をしてはいけない金融機関の筆頭と考えています。

まだ投資経験の浅い投資家が、大きな下落に晒された時、本当の余剰資金でないお金を投じている初心者投資家は右往左往します。
何しろ余剰資金ではないので、生活のためにこのお金を投じてからのごく短い期間で現金化して生活費や娯楽費のために充てようと安易に考えているからです。

しかし一度下落が起きると、生活などに回さなければいけないお金が足りない上に投じた資産も目減りしています。
生活が何よりの基盤ですから、こうして本来の望まないシーンで損をせざるを得なくなる初心者投機家はどの年代であっても後を絶ちません。

初心者ほどこうした時に冷静ではいられませんが、生活費がみるみる目減りしていく恐怖を実感したことがない素人はもはや投げ売りでも構わないとばかりに売却をしかけます。
するとこうした素人の売却が増えたのを見て、株式市場は更に株価が下がり下落・暴落の負の連鎖が始まります。
コロナショックなどはその典型例と言えるでしょう。

対面の証券会社やIFAの場合、証券外務員は市場の下落などのシーンで、顧客が売却をしたいなどと不安に感じた時にそれを引き留める役割を果たしています。

ネット証券には残念ながらそうしたことが原則出来ませんので、証券口座へ簡単にアクセスしてその場で売却手続きが出来てしまいます。

また対面販売の場合にはその資金が本当に余剰資金であるかのチェックや顧客のリスク許容度、運用目標や運用期間、その資金の使い道など幅広いヒアリングが可能です。
特に生命保険なども扱っている担当者の場合にはライフプランを把握していたり、リスクに備えた資金の優先順位の説明などもしてくれていたり、家計の状況を詳しく把握していることが多いので、それが本当に無理なお金かどうかを客観的に出来るという傾向があります。
(あくまでも相談者がお財布事情をオープンに打ち明けてくれている場合)

「誰が買っても同じ」と世間一般で言われるインデックス運用*ではなく、彼らは顧客のニーズに応じた付加価値の提案ができます。

*これもどういうものをどう組み合わせるのかでまるで運用成果もリスクも変わってくるのだが、学ぼうとしない人にはまるで理解できない未知の世界の話のように思えるだろうが。
また、顧客がまだ気づいていないリスクや過剰に投資へ資金を回そうとすることをいさめる役割も彼らが担当者である場合の役割です。

しかし彼らはボランティアで顧客の相談に乗っているわけではありません。
こうしたことをしてもらうためにはあくまでも相談料・顧問料を支払ってもらう相談者(クライアント)になるか、保険契約のお客様(カスタマー)などであることが前提です。
私自身、大学生で投資を始めた時には全く気にもしなかった話ですが、金融業界で働いて唖然としたことがあります。

証券業界におけるライフプランニング*は常に人生ノーリスクで無敵な状態を前提としているのです。このため、提案内容はつい過剰なリスクを取りがちです。
この状態ははっきり言ってアホです。
投資をしてお金を増やせばそのお金でリスクに備えられると痛い経験をしたことがない子供のような発想でいます。

子どものような好奇心を持つことは大事な面もありますが、投資は余剰資金でやるからやれるのです。
もし勘違いや間違って、余剰資金ではない生活資金や使い道の決まっているお金で投資をしてしまったとすると…それによって何が起こるか想像力がないというのは酒を飲んだのに車を運転しようという愚か者ほどに愚かでしょう。

他方、保険業界はリスクありきで先回りのライフプランニング*を行いますので、リスクバランスの面で良い提案ができるというのは、初心者投資家ほど本来は頼りにするべき存在です。
*地域差もあるがアメリカなどでは顧問契約か有料の個別相談であることも多い。ライフプランニング約3万円/回~、相談料は年収の1%くらいが目安。

近年では保険と証券を比較して比べる方もいますが、これはあり得ないほどおかしい比較の仕方です。
夢や目標が明確で進学を目指している学生と、大学になんとなく進学しようという学生が支払う教材費・教育費を比べてどちらがお金をかけなかったかを比べてマウントを取る事に本当に価値があるのでしょうか?
第三、コストやアクティブ・ファンドに擦り付けられた罪

またよく言われる「殆どのアクティブ・ファンドは長期運用においてインデックス運用に勝てない」という冤罪も未だに払しょくできていません。
インデックスが良い、アクティブが悪いではなく、そもそもの目的があっての投資であるはずなのに、何故そんな意味のない比較をして白黒つけようとするのでしょうか。

目的・目標があって努力する人の成績が、そうでない人とのテストの成績で上位かどうかの議論に意味はあるのでしょうか。
目的・目標を達成できればその成績が他の人よりも見劣りしようが然したる問題ではないでしょう。

学生時代の学習と同じように努力をしている人の成績が、必ずしもすぐに成果となるとは限りません。
しかもそのテストが本人の目指している大学や学科・業界に進学した先に求められる特化したもので、一般的な大学受験科目から乖離しているとしたら偏差値やテストの点数、平均点を下回ったとしてそれは「負けた」「無駄」なのでしょうか。

アクティブ運用はインデックス運用と元来、比べて運用されるものではありませんでした。
それはアクティブ運用が始まってから100年以上が経ってからインデックス運用は始まった歴史的背景からも明らかです。
元をたどればファンドの運用方針など千差万別であるのに、それを分かりやすくするために独自調査などを駆使して銘柄を選定・売買するアクティブ型と、上場している株式市場の指標に連動するパッシブ運用のインデックス型という表面の浅い所だけで白黒二つに分けることにそもそも無茶な話があります。

これは言ってしまえば価値観違いであり、宗教対立とも言えます。

広義では同じキリスト教であるカトリック(*アクティブ)とプロテスタント(*インデックス)の違いのようでもあります。*誕生の順番や教会=資産運用会社と見立てた場合の構造

資本主義による経済の持続的な成長という神の子イエス・キリストを拝みながら、その聖書の解釈の仕方や教義への見方がまるで違うこれのどちらが正しくてどちらが間違いという二元論は争いしかもたらしません。
他人が信仰しているものに勝手にいちゃもんをつけたり、改宗を迫ったりするのですからお互いにウザイのです。放っておけばよいのに。

しかし近年では資産運用会社にもアクティブ・ファンドと銘打っておけばその中身が実質的にほぼインデックスファンドであっても、手数料(信託報酬など)をインデックスより稼げるという内情があります。
自分たちで「アクティブ・ファンド」と銘打ちながら、インデックスの内訳を見ながらこの株が伸びそうだ、この株は伸びなそうだと少しだけ比率を変えてインデックスを上回るパフォーマンスを目指すファンドがあったとしたらどうでしょうか?

こうしたなんちゃってアクティブファンドは独自の企業調査などをするのではなく、パソコンなどでインデックス(ベンチマーク)を見ながら運用しているのです。
この狙いが当たればインデックスを上回るパフォーマンスが得られますが、外れればインデックスをパフォーマンスは下回ります。
これはつまりインデックスに勝つことを目的とした”投機”をしているのですから、本来のアクティブ運用とは言えません。
こうしたファンドマネージャーの風上にも置けない成果報酬ではなく給与所得のサラリーマン・ファンドマネージャーたちの打算もあり、なんちゃってアクティブ・ファンドが粗製乱造されていき、投資家はなかなかパフォーマンスが芳しくないファンドに手数料をしゃぶりつくされていました。
またインデックスを上回るパフォーマンスの追求でさえ、インデックスを見ながら運用しているのですから大して上回らないファンドも存在します。

車の運転がそうですが、センターライン(ベンチマーク)を見続けるとセンターラインに車体は寄っていきます。
本来、運転手(ファンドマネージャーもしくは投資家)が観るべきはセンターライン(インデックス、BM)ではなく、運用目的と運用目標であるはずです。

また長く保有すればするほど、証券の課税ルールと資産形成型の保険商品の課税ルールは異なるので、手取りやトータルで考えると証券会社では絶対に認めたくない不都合な現実が潜んでいます。
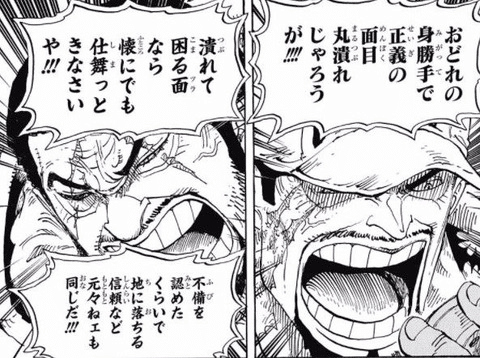
本来はお互いに手を取り合って顧客の資産形成のために補完をしあうべき保険と証券ですが、証券業界にとって目の上のタンコブだったのです。

アクティブファンドに押し付けられた冤罪とは、投資で失敗し続けた投資家たちの不勉強を棚に上げ、反省をしない国民の不満の眼を向けるため、本質ではない問題に全ての責任を押し付けてきた結果です。
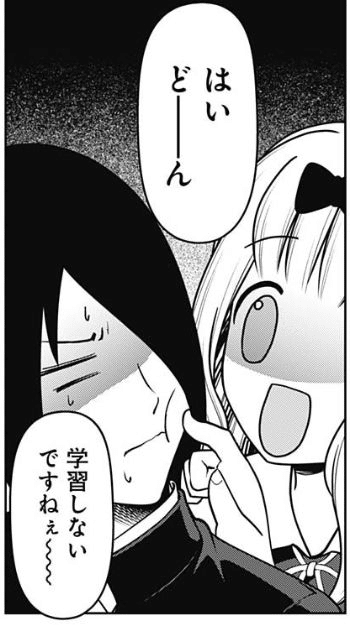
100本のアクティブ・ファンドの中でどんなにずば抜けて高いパフォーマンスを挙げるアクティブ・ファンドがあったとしても、その他99本のなんちゃってアクティブファンドがあると、それは1/100でしかなくなります。

真正のアクティブ・ファンドまでも糞味噌一緒にされたことが大きな要因になりました。
尚、先に紹介した”最強の金融庁長官”森元長官は退官後にコロンビア大学の非常勤教授を経て、現在アフラックの顧問をしており近い将来に噂されている合併協議のために天下りました。
間に別な所(コロンビア大学)を挟めば天下りじゃないのかといえば本質的に天下りですよね、これは。他にも同社には多数の省庁出身者が天下っています。
金融庁長官時代に「地銀の模範」としてさんざん持ち上げたスルガ銀行は不正融資などで、フィンテックの波にいち早く飛び込めと大号令をかけてコインチェックNEMの不正流出…。
森氏自身が全て悪いわけではないのかもしれませんが、最強の金融庁長官と呼ばれ、異例の3年目を務めた方の最後が膿というか責任全部背負わされた感じで散々でしたので、こういうのはなんだかなと思いますが。
金融庁や投資の学校を名乗るところでは、私の所のように世の中にはきちんとしたアクティブ・ファンドがあり、それを見極める方法や見抜く力、考える力を育てようとしないのでしょうか。
大勢が耳を傾ける都合の良い話が正しく、そうではない意見は間違っていると決めつけているのでしょうか。自分で何故、考えようとしないのでしょうか。

こうしたことをきちんと教育もせずに手数料無料化やインデックスファンドが良いという短期売買をまるで励行するような小手先の、安易な方向に舵を切った責任の押し付け合いを40年以上も続けてきました。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?

