
Remember who you are.
皆様、こんにちは。VCラボのさきみです。
5月の連休も終わり、先日、「連休明けに退職代行業者への依頼が殺到している」という記事を見ました。オンボーディング支援にも携わるさきみとしても、非常に気になる話題です。
入社直後に退職を決断する理由は、待遇などの環境面の要因が多い印象を受けます。確かに、説明会で聞いていた条件と違うとなれば、不安になるのは自然なことですね。
ただ、相談の現場では、条件面とは違った環境になじむ難しさが見られます。
※実際の事例をもとに架空事例をご紹介します。
間違いを直接指摘されないプレッシャー
4月は毎年、新入社員研修の依頼が増加します。ある担当企業の研修で、セルフケアとして睡眠の重要性をお話ししていたときのことです。
参加者の一人Aさんが「どうしたら朝起きられますか」と鬼気迫る表情で質問してきました。
Aさんの表情とは裏腹に、周りの同期たちは大笑いをしています。
きけば、Aさんは入社式早々遅刻をしたそうです。人事担当者は「ありえない!」と、それはご立腹で同期たちも震え上がっていたといいます。しかし、Aさんは直接は怒られませんでした。人事担当者は、離職やハラスメントの防止が頭をよぎり、「次は大丈夫だよね」と言うにとどめました。
それでも、人事担当者が激しく怒っていたことは同期から聞いているし、事あるごとに「次は大丈夫だよね」と念押しをされる…、もしかすると直接怒られないのは事態が深刻だからではないか。このような疑心暗鬼が大きくなり、Aさんは『起きれないから、寝られない』という状態に陥っていました。
Aさんと人事担当者、それぞれの思い
眠れていないAさんは、研修中もつらそうです。それでも、「自分が悪いから。遅刻しちゃいけないから」と頑張っていました。実は、この前日、睡眠不足がピークとなり、明け方から寝てしまって、また遅刻をしてしまったらしいのです。その際、人事担当者から「次はないって、言ったよね!」と強く言われ、Aさんはさらに萎縮していました。
「せっかく憧れていた会社に入れたのに、
最初でつまづいてしまった…。もうだめだ。」
さきみは、Aさんと一緒に、夜の適切な時間帯に眠れる方法を検討・実践しながら、人事担当者にも話を伺いました。「この遅刻騒動で、ダメ社員認定をされてしまいましたか?」と。
すると、人事担当者は
「いや、そんなことないです。あの通り、いい子ですよね。仕事・研修に対する真摯な姿勢も評価されています。だからこそ、変なところでケチをつけられちゃいけないと思っているんです。」
さきみは、Aさんと人事担当者のそれぞれに、今の自分の思いをお話しすることを勧めました。
Aさんは自分が十分期待されていることを実感でき、人事担当者は自分の言動がAさんの改善を阻害していることに気づいたそうです。
その後、Aさんは連休でたっぷり睡眠をとり、睡眠リズムもだいぶ適切になってきました。ギリギリになることはあっても、遅刻も今のところしていません。
「意味」の変化と自尊心の回復
Aさんは語ります。
「遅刻は当然してはいけないことだけれど、遅刻によって自分が全否定されたような気持ちになって苦しかったです。でも、人事担当者の方が、私のよさを発揮するためにも、社会人としての当たり前のルールを守ってほしいんだという親心のような思いでいてくれたことがわかって、どんなに嬉しかったかわかりません。まだ自分は求められているし、ここにいていいんだって。同期のいじりもエールに感じられるようになってきました。遅刻は鉛のような重しだったけれど、今では飛び越えられる岩くらいになっています(笑)」
Aさんの中で、「遅刻」の意味づけが変化し、それにより「自分」を取り戻していることを感じました。
現在、Aさんは精力的に研修を受け、同期をサポートし、4月とは別人のように「自分らしさ」を発揮しているそうです。
人事担当者曰く、「採用時のAさんに戻った(笑)」とのことでした。
「個」を取り戻す作業の重要性、そこにある思い
この出来事をきっかけに、さきみは『MBB:「思いのマネジメント」【………知識創造の経営の実践フレームワーク………】』を読み返しました。
さきみが管理職一年生のときに、VCラボの松本所長が紹介してくれた愛読書です。ありとあらゆることが数値化されて、その影響力が大きくなっている今、再度大切なことを教えてくれる気がします。
この中で、私が最も大切だと思っている言葉は…
Remember who you are.
です。人間の人間たるゆえんは、思索を重ねながら進化するところにあり、そして、あらゆる企業活動の始まりは「個」であると。
さらに、このようにも書かれています。
そもそも企業が「動機づけ」と称して、社員の創造性を引っ張り出そうとするのは間違っている。むしろマネジメントは、もともと人が備えている創造性が解き放たれるように支援しなければならない
組織に属するからには、そのルールに従い、周りと協調することが求められます。ただ、それは、あくまで皆が互いの力や創造性を発揮するための手段であり、目的ではありません。
特にあらたな環境に身を投じたとき、「何をすべきか」に目がいきがちですが、こういうときこそ、
「私は何者か」
「私はどうありたいか」
自らの行動の背景にある「思い」、「どうありたいか」を大切にすることで、目の前のことに終始していた近視眼的な姿勢から視野や時間軸が拡がり、まず焦りや不安が落ち着くと思います。
落ち着いて、もっと楽しく、ワクワクする気持ちで、自分が自分であるために何をしたらよいのか、考えを巡らせることができるはずです。
自分の心が動く「思い」は、きっと同僚にも響くでしょう。そこから、また同僚も自らの「思い」を振り返り、互いの「思い」がより深く大きなものへと成長していく、創造性の広がりにつながっていきます。
特に管理職が新たな部下を迎えるときには、「何をするか」よりも「どうありたいか」を意識してみると、部下の心理的安全性も高まります。
管理職自身が自らの「思い」を振り返り、言葉にすることにより、環境の変化に戸惑う部下の「思い」を引き出すことができ、その貴重さを共有する、部下はそもそも自分が価値ある存在であることが認識でき、安心感が高まると思います。
ちなみに、さきみは、これを管理職の”Welcome on board”の体現だと考えています。
それぞれの「思い」を尊重し、その重なり合いを見出すことで、互いを大切にし、創造性を発揮することにつながる…、改めて、VCラボで取り組んでいきたいことを確認できた連休でした。
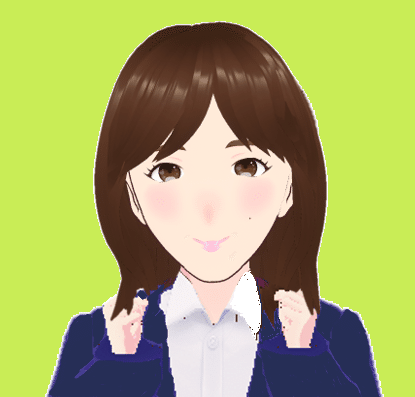
■さきみのプロフィール
ビジョン・クラフティング研究所 シニアコンサルタント
臨床心理士・公認心理師・1級キャリアコンサルティング技能士
お問い合わせ先:https://www.jes.ne.jp/form/contact
VCラボ ホームページ:https://vc-labo.jp/
