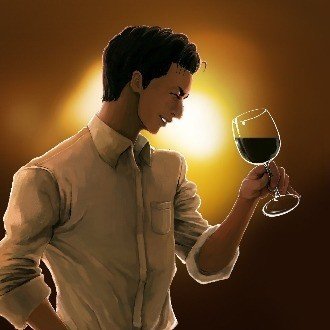先輩が接客について教えてこなかったこと その12 灰皿を出せ
「仕事ってのは誰かのためにやるもんなんだよ。決しておまえがやりたいからとか楽しいからとかでお金がもらえるもんじゃないんだよ」
今のご時世、タバコは嫌われ者の一つにもなっていますが、酒と煙というのは古くから一緒に嗜まれてきたものです。
「酒と煙草は飲んで通る。飲まぬとて銀(かね)が延びもせず」という言葉があります。
「酒やタバコをやらなかったと言ってじゃあお金が貯まるかと言えばそうでもない」みたいな意味なのですが、そういう言葉がこうして残るくらい、昔から酒もタバコも人の嗜好品として長く愛されてきたものだったわけです。
今ではタバコを吸えないバーもあると聞きますが、一昔前では考えられないことでした。当時の喫茶店とバーは、紫煙がくゆる中で時間を過ごす場所の代名詞みたいなもの。僕が小さい頃、おじいちゃんに連れられて喫茶店に行くと、妙齢のママが淹れた苦いコーヒーと共にタバコを味わうおじいちゃんの隣で週刊少年ジャンプを読んでいたものでした。
僕がバーで働いたとき、最初に覚えさせられたのは「お客様が席に座ったら灰皿とおしぼりを出す」でした。
恥ずかしながら僕はその仕事を覚えるのに数日を要しました。ちょっと店が忙しくなると灰皿を出すのが遅れ、マスターにカウンターの下で蹴飛ばされる日々。
「お客様が席に座ったら灰皿とおしぼりを出す」。言葉にしたら単純なこんな仕事が僕はすぐにできるようになりませんでした。
そして、それができるようになったら次に指示された仕事は「注文を受けたらすぐに伝票に書く」でした。これもできるようになるまでにまた数日を要しました。何も考えずに体が動くまで、一週間以上かかっていたかもしれません。
僕がこれまでに書いてきた「神々は細部に宿る」だの「お客様に尊敬されろ」だの「察するサービスはやめろ」みたいなことは到底教えてもらうような状況ではありませんでした。
店長から蹴られながら叱られながら、つまらないルーティンを覚える日々でした。毎日、できない自分を責めていました。
でもそのお店は僕の中で一番と言っていいほど、多くを学んだ店になりました。それはどういうことなのか。一個ずつそれを紐解いていきます。長くなりますがどうぞお付き合いください。
☆
「きついと思うだろ?仕事ってのはきついもんなんだよ。だからお金がもらえるんだよ」
僕がそのバーの系列店に、ヘルプで入ったことがありました。
ヘルプ、と言っても、オーダーを聞いて頼まれた料理を出すだけの仕事です。そりゃそうです、大した仕事もできませんから、まだ。
料理を出すだけ、とは言え、いつもバーカウンターの中でマスターに蹴られてばかりいた毎日と比べれば、シェフが笑顔で「これあそこのテーブルに出して」とか「ビール一つお願い」と言ってくれるような仕事の時間はとても楽しいものでした。
仕事終わりにマスターが様子をのぞきに来て、僕に「どうだった?」と聞きました。
僕は満面の笑みで「すごく楽しかったです!」と言いました。
するとマスターはこう答えたのです。
「君が楽しいかどうかはどうでもいいんだよ。それより大切なのはお客様が楽しかったかどうかだ。それが仕事だ」
☆
「でもさ、いつかどこかでやってることとやれることが、やりたいことに近づいてくるんだよ。そうなったら仕事は楽しくなるよ。」
とても厳しいマスターでした。
たとえばカクテルを作るとき、シェイカーの中にある液体をグラスに注ぐじゃないですか。注ぎ終わりのタイミングで僕がシェイカーを上に持ち上げ、液体を高いところからすーっとグラスに落とすような動作をしたとき、マスターは僕を蹴飛ばしました。
「おい、お前、そんなふうに作るなんて誰が教えたよ。どこの店の真似してやってるか知らんけど、その液体が落ちる間に温度が変わるとかお前考えてやってんのか」
また別の日のこと。カクテルをまだ勉強中だった僕に、お客様から「テキーラサンライズ」のオーダーが入りました。自分で作れる自信がなかった僕はマスターの下へ行って、「テキーラサンライズお願いします」と伝えました。
マスターは「この前教えたでしょ。できないの?」と言いました。
「すいません、自信がありません」
「いや、自信があるかどうかは聞いてない。できるの? できないの?」
「……できます」僕は勇気を振り絞って言いました。でも本当はレシピすらうろ覚えな状態でした。
僕がオレンジをカットしている様子をマスターは見ていました。マスターはものの数秒で僕のところに来て、僕の足をカウンターの下で蹴飛ばし「そんなこと教えてないだろ。もう下がってていいよ」と言い、テキーラサンライズを仕上げ、お客様にお出ししました。
僕は教わったことすらできず、教わっていないことを勝手にアレンジしてやっている自分を責められる日々が続きました。
自分なりに一生懸命、カクテルのレシピを覚え、ステアやシェイクの練習をし、ウイスキーの銘柄と特徴、金額を覚えようと努力していました。しかし、なかなかそれは生かされませんでした。
もしかしたら僕の物覚えが悪かったのかもしれません。それか、そもそもそんな短期間でできることではなかったのかもしれません。
ただ、僕にはそのどちらかを判別するだけの情報はありませんでした。僕とマスターのふたりの世界の中では、教わったこともできない自分がいるだけでした。僕には「やれること」なんてないんだと思う毎日が続きました。とてもじゃないけれど「やりたいこと」なんて考える余裕はありませんでした。
僕はそのバーで働くのが辛くなって、2か月で辞めました。
☆
「お客様がお前の接客で笑顔になって帰っていくんだよ。お前も楽しくなるんだよ。楽しませ方を覚えてお前も認められるようになるんだよ。それでお金もらえるんだよ。最高じゃあないか」
その店を辞めたあと、僕は銀座のレストランで働くことになりました。銀座のレストランには自分の知らない何か楽しいことがあるはずだ、のような期待を抱いていたような気がします。人通りの少ない朝の中央通りは、輝かしい未来を導いてくれる道のようにまで思えました。
勤務初日、僕の仕事ぶりは散々でした。
レストラン経験者ということで、同時に8テーブルを初日から持つことになりました。コース料理のみでオーダーを取る必要がほとんどないので、一人で8テーブルは可能です。
僕は料理を運んでいる途中で、別のテーブルのお客様からドリンクのオーダーを受け、また別のテーブルからも飲み物を頼まれ、頭が真っ白になりました。
今から3つのテーブルに料理を出さなきゃいけない。でも2つのテーブルからドリンクを頼まれている。もちろん体は一つしかない。僕は泣きそうな顔で店長に「すいません……あのテ、テーブルに、あ、あ、赤ワイン、を……」みたいにお願いしたのを覚えています。パニックでまともに言葉も出てこなかったんですよね。
料理がしばらくサイドテーブルに置かれたままで、お客様のもとに運ばれない様子を店長が見かねて、手を貸してくれました。そんな状態は次の日も続きました。少なくとも一週間は、今日一日何をしていたのか思い出せないほど、仕事に追われていました。
ただ、料理を出すだけ、ドリンクを持っていくだけの仕事が僕にはできなかった。
その店を辞めてから2年後くらいでしょうか。僕はとあるイタリアンレストランの立ち上げスタッフとして働くことになりました。
さすがにこのころには、まともに料理も出せるようになりましたし、同時に8テーブルだって回せるようになりました。ソムリエの資格も取り、ワインの提案にもそれなりの自信を持ってきた頃でした。
その店での3年目、いつものようにホールを眺めていて、ふと気づいたんですよね。
「あ、今このレストラン、ものすごく良い雰囲気で回ってる」
誰に言われるわけでもなく、自然とそんなことを思いました。店の様子を高いところから俯瞰できている、そんな感覚です。
3番テーブルのカップルは楽しそうにこのあと行くショッピングについて話している。5番テーブルのお客様は先ほどお出ししたワインについて語り合いながら、美味しそうに召し上がっている。7番テーブルのお客様はデザートを食べ終わって一段落して、たぶんあと2分後くらいに僕に会計を依頼するだろう。
そんな状態が一つ一つのテーブルに注目することなく、雰囲気として自分が把握できている。今、何もとどこおりがなく、おだやかな時間が進行している。それが手に取るように分かったんです。
起きている事柄はとても単純なことです。すべてのテーブルに適切なタイミングで料理が運ばれ、飲み物の不足がないだけです。言ってみれば、それは「バーカウンターでおしぼりと灰皿が置かれた状態」とまったく同じものでした。
僕は、「当たり前のことがやっとできるようになったんだ」と思いました。それと同時に「これは一人前になったと思っていいんじゃないか」と、なんだか嬉しくなりました。その日もお客様は、笑顔で店を後にしていきました。
☆
仕事というのは、とても単純でつまらないものが多いと思います。
僕が接客について体験した、素晴らしい現場での出来事をいくつかnoteに書いてきていますが、そんな瞬間は1年のうちに1・2回あるかないかです。仕事のほとんどは、つまらなく、単調です。
しかしながら、その単純なことがちゃんとできること、それが一番難しかったりします。僕は飲食業に勤めて「おしぼりと灰皿を出せる」ようになるまで7年かかったことになります。
それは逆に言えば、お客様が期待する成果を上げることが7年間できなかったことにもなります。つまり、十分な意味でお客様を楽しませることが、それまでできなかった。
当たり前のことが当たり前にできるようになるまでには、時間と苦労が伴います。それは仕方のないことです。仕事というのは、そうやって辛いことを誰かの代わりにするからこそ、対価としてお金がいただけるものだと、僕は勤めたバーのマスターに教わりました。
その価値観は今でも変わりません。僕は仕事というのはあくまで仕事だと考えています。自分が楽しいかどうかより、お客様が喜んでいるかどうか、それこそが仕事の目的であり目標でしょう。
それは自己実現のためでもないし、自分の「やりたいこと」を世間に表明するものでもありません。あくまでお客様に喜んでもらうこと、そのために辛いことをすることそれが仕事です。仕事とは「仕える事」です。
☆
嬉しいことに、仕事を通じて人は成長できます。僕が「おしぼりと灰皿を出せる」ようになったように、いつまでも何もできないと思っていても根気よく続けていればできることは増えていくものです。
それが積み重なったあるとき、視界が一気に広がります。狙ってお客様を喜ばせるにはどうしたらいいかが分かってきます。
それはなぜか。きっと当たり前のことをマスターしていく中で、今までどういうときにお客様が喜んだのかという経験が蓄積されていくからでしょう。
「できること」が増えてきたとき、お客様からあなたへの評価も高くなります。すると「やりたいこと」ができる機会も増えてきます。人によってそれが何歳の出来事になるのかはわかりませんが、僕はそれが29歳の時でした。飲食業を始めて7年後のことです。
飲食業というのは、辛い仕事です。労働時間も長く、給与も安い。世間的な評価も決して高くはありません。もう嫌だ、と辞めたくなるタイミングは多いと思います。
僕がいくつもの店を辞めてしまったように、辞めるという選択肢はあると思います。ただ、同時に「今の自分は当たり前のことができているのか」というのを自問自答してほしく思います。それがまだできていないのなら、せめて「おしぼりと灰皿を出せる」までは続けてみてほしいなと思うのです。そうしたら世界はもっと変わってくると、僕は信じています。
☆
僕がバーを辞めたあと、嬉しかったことがありました。
バーのマスターが、わざわざ僕の働いていたレストランに様子を見に来たのです。そのマスターにはどの店にいるかは話していませんでした。人づてに聞いて尋ねてきたのでしょう。
「え、どうしてこの店にいらっしゃったんですか。観光ですか?」
「ん? ここに美味しいお肉があると聞いて」
そんなふうに言っていましたが、今思い起こせばそんなことでたまたま僕が働く店に来るはずがないですね。
その店は、東京で僕が2軒目に働いた店でした。あとで分かったことなのですが、マスターはわざわざ1軒目の店に行って、僕がどこに異動したのか聞いて来たそうです。「観光ですか?」なんて聞いてしまった自分が恥ずかしいです。
そうやって厳しくも僕という人間のことを気にかけてくださったマスターがいたことで、僕は飲食の仕事を続けられたし、今でもこうして飲食業に対して思い入れを持ちながら生きています。
自分をどこかで見守ってくれる、素晴らしい上司との出会いというのも、仕事の醍醐味かもしれませんね。
では皆様も素敵なお仕事ができますように。ではまた。
写真:COFFEE BAR GALLAGE さまよりお借りしました。
ーーーーーーーー
このnoteは、Panasonicさま主催の #はたらくってなんだろう のコンテストに合わせて書いた記事です。
また同時に、私が昨年書き始めたマガジン「先輩が接客について教えてこなかったこと」の最終回としてずっと温めていた話でもあります。
そのマガジン自体は、私側の都合により第8回で更新が止まってしまっていましたが、コンテストの内容にインスピレーションを受けて、最終回ながら先にこの回を書くことにしました。
私の父はスター・ウォーズが大好きで、小さい頃はその映画の素晴らしさについてよく聞かされていました。なぜ初めがエピソード4なのか、それを熱く語る父の姿はよく覚えています。
かの映画界の天才と私を比べるのは非常におこがましくも思いますが、この最終回をふまえた上で残りの9〜11回がどう紡がれていき、またどう読まれてほしいと私が考えているのか、そんなことを頭の片隅で考えてくだされば幸いに思います。
なお、このマガジンのnoteは通常、有料での公開としていますが、今回はコンテストへの参加に伴い、無料エリアに全文を載せて公開いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
黒ワイン
※このnoteを有料マガジンに登録しても無料で読めるように、この下に有料エリアを設定しています。そのため、このnoteを単体で購入くださっても、以下には何も書かれていません。どうぞご了承ください。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?