
四十肩の最も簡単な治し方【クセトレ】コアを、インナーを攻める!
「この『うちわ扇ぎ』がなんで五十肩に良いのか? 」
今回は「うちわ扇ぎ」を運動に取り入れよう!がテーマです。
四十肩の最も簡単な治し方ーコアを、インナーを攻める!ーをお届けします。
※このnoteでは、整形外科医:歌島大輔が医学的根拠をもとに、わかりやく、かつ実践的な医療健康情報をお届けします。
ときどき出てくる「ふんぞり男」とは、その名の通り、ふんぞり返って態度がデカい患者さんです。
「うちわ扇ぎ」クセトレとは?
はじめに、先日いただいたコメントをご紹介させてください。
KOBIさん
「インナーマッスルトレーニングをやっていて、効いているのかな?という感じだったのが、極意の部分をよく見てやってみたら、全く感覚が違いました。インナーマッスルを発見したような気分です。継続します。ありがとうございます!」
こちらのコメントは、インナーマッスルトレーニングの動画に対するコメントです。
コメントいただき、ありがとうございます。
きっと、KOBIさんは今も継続してくださっていると思います。
でも、ですよ。
みんな継続できないんですよ、ホントに。
そして、僕も例外ではありません。
誰もが、カラダの不調を治療したり、予防したりする
セルフエクササイズの継続につまずきます。
その理由は超シンプル!

効果を実感しにくいのに、メンドクサイからです。
例えば、ジムでやる筋トレとか、ダイエットとかは効果を実感しやすいじゃないですか。
筋肉がバンプアップしたり、筋肥大して大きくなったり、体重が減ったり、体脂肪が減ったり。
でも、治療や予防目的のセルフエクササイズはそういうポジティブな変化があまりない。
特に予防なんて言ったら、変化がないのが良いことですもんね。
これは続くわけがないんですよ。
だから、今日は解決策を1つ持ってきました。

それが「うちわを扇ぐ」ことです。
あ、もちろん、うちわじゃなくてもいいです。
クリアファイルでも下敷きでもなんでもOK。
ふんぞり男「いやいや、それが何の解決になってんだ、意味不明だぞ、お前」
ナイス突っ込みです。
先ほど言いましたが、継続できない理由は効果を実感しにくいのにメンドクサイってやつですよね。
そのメンドクサイってほうを解決しようというのが
この「うちわ扇ぎ」です。
暑いとき、汗をかいたとき、風がほしいですよね。
最近ではMini扇風機を持ち歩く人も増えてきたように思いますが、それを逆にうちわにしませんか?ってことです。
メンドウも何も、顔に心地よい風を送るために、
つい「扇いでしまう」という状況をつくる。
そんな、ついクセになってしまうセルフトレーニングを
クセトレと呼んでいます。
肩のクセトレの代表が「うちわ扇ぎ」なんです。
ふんぞり男「まあ、確かにメンドウではないな。でも、それがなんで五十肩に効くんだよ」
はい、そこがこの動画のキモです。
いくらメンドクサくなくても、意味がないセルフエクササイズなんかやりたくないですよね。
でも世の中のセルフエクササイズ動画には、そういうものもあるんですよ。
なぜなら、医学的根拠がないからです。
エビデンスと言うと、かなりハードルが上がっちゃうんですが、
少なくとも、なんでそのセルフエクササイズが効果的なのか
根拠を積み上げていないものは、信用しないようにしてほしいなって思います。
ふんぞり男「そうは言っても、お前、ムダにハードルを上げてねぇか?」
ですね。
結局、世にあるセルフケアやセルフエクササイズも一つ一つを見れば、
エビデンスが確立されているモノなんかほとんどありません。
仮説レベルなんですね。
でも、その仮説の信憑性をどう高め、それをいかにクセにするか。
これを追求したのがクセトレですし、最後には、どうやって扇ぐのが良いのかを解説いたします。
この「うちわ扇ぎ」がなんで五十肩に良いのか?っていう根拠を解説していきます!
根拠1 うちわ扇ぎはインナーマッスルエクササイズ

まずこのうちわを扇ぐという動作。
特にわかりやすいのは手首を固定して扇ぐとどこが動いているかというと「肩関節」なんですね。
こっちに動くときは肩関節の「内旋」

そして、

こっちに動くときは肩関節の「外旋」という、内旋外旋をひたすら繰り返す動きなんです。
内旋と外旋っていうのは英語でいうと、肩のrotationという動きで、肩のインナーマッスルは「rotator muscle」と言います。
つまり、肩の内旋外旋をするときにメインで働いてくれるのは、肩のインナーマッスルなんです。
この継続がちょっと大変かもしれない基礎的なインナーマッスルエクササイズには、チューブをつかった外旋と内旋運動のエクササイズが含まれます。
それを癖になっちゃうレベルで簡単にしたのが、うちわ扇ぎだと思ってください。
根拠2 四十肩の原因「関節包は腱板と一心同体」

こちらの動画などをご覧いただくとわかりますが、四十肩の最も重要な原因は関節包という関節を取り囲む膜なんですね。
ここが炎症して、周りと癒着しながら分厚くなった結果、肩が上がらなくなったりしてしまうわけです。
ふんぞり男「じゃあ、インナーマッスルエクササイズなんかして意味ないんじゃないか?」
そう思いますよね。
でも、インナーマッスルの先端を「腱板」と言いますが、その腱板と関節包って完全に分離して、別物ってわけじゃないんです。
腱板ってそもそも何層にも繊維が重なっている構造をしていますが、その一番下のというか深い部分の層が関節包なんですね。
つまり、一心同体と言ってもいい関係なんです。
だから、インナーマッスルに刺激を加えるっていうことは関節包への刺激にもなりうるわけです。
ふんぞり男「ふーん・・・構造はわかったが、その刺激とやらが、四十肩を良くする証拠はあるんか?」
ときますよね。
ということで、次の根拠です。
根拠3:四十肩の可動域改善効果ありとする研究

これは、四十肩に対してインナーマッスルのエクササイズだけをした効果を測定した研究(*1)です。

インナーマッスルエクササイズの中でも「遠心性収縮」と「求心性収縮」という、トレーニングのやり方の違いを比べています。
まず「痛み」です。
研究結果をもとにグラフを作成してみましたが、ここでのポイントは遠心性収縮だろうが求心性だろうが痛みがかなり減っているってことですね。

「VAS」っていうのは痛みを10段階で数値化してもらう簡易的な痛み評価法ですが、どちらのグループも最初は7以上の痛みだったのが、2とか3台に落ちたってことです。
さらに、こちらは「前方挙上」前から腕をあげていく角度の変化です。

どちらのグループも最初は100°くらいしか上がらずでしたが、エクササイズ後は150°前後まで回復しているというデータです。
インナーマッスルエクササイズは、五十肩にも有効なエクササイズだってことなんですね。
そして、いよいよ、
具体的な「うちわ扇ぎ」法とは

クセトレで大事なのは「考えなくてもいい」ってことだったりします。
ですから、細かく肘の角度はこうで肩はこう・・・
みたいなことはまず置いといて、
常に机の上やカバンの中に、うちわか下敷きか何かしら扇げるモノを置くっていうクセをつけることが一番大事です。
結局どう扇ごうが、肩のインナーマッスルには刺激が加わります。
その中でもう一つ絶対に守ってほしいのは「痛くない扇ぎ方をする」ってことです。
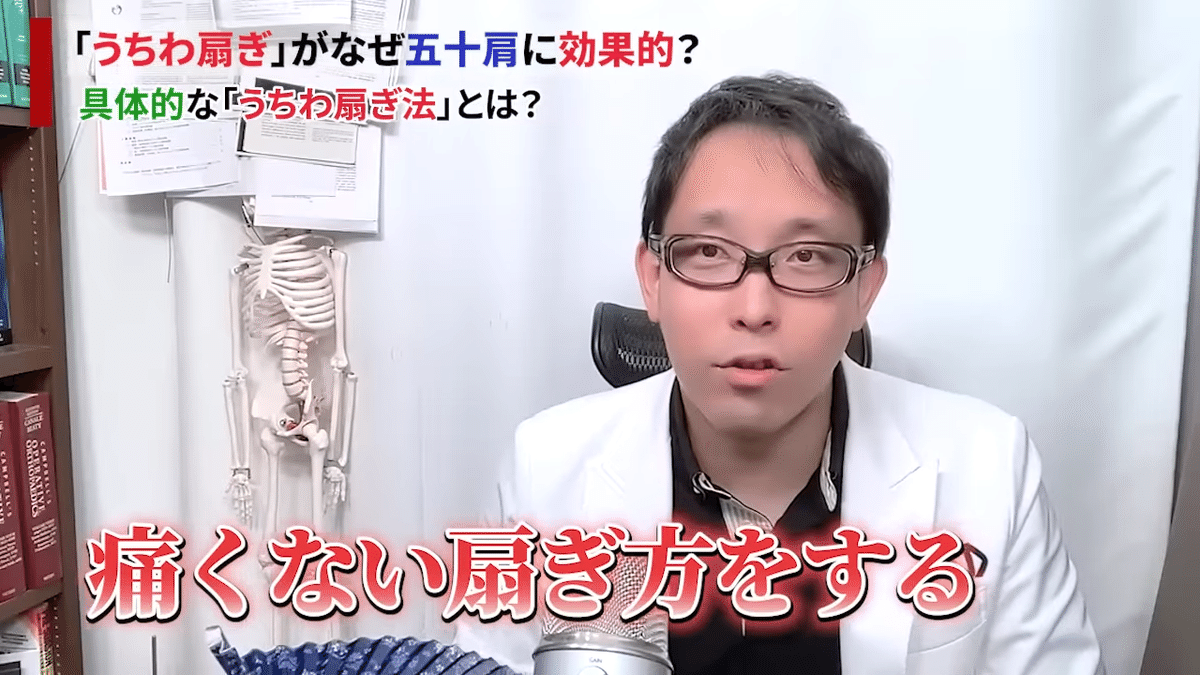
一口にうちわを扇ぐって言っても、いろんな扇ぎ方があるんですよ。
肘の位置
扇ぐ大きさ
手首で扇ぐのか
手首は固定して扇ぐのか、などなど。
でも、その中で最低条件の一番大事なのは痛くないことです。
これは徹底してください。
あと、できるだけ肘は脱力して脇にくっつけちゃうか、テーブルなどの上に肘を置いてください。
よく、うちわを扇ぐときってこうやると思うんですが、
これって三角筋っていうアウターマッスルが緊張している状態なんですよね。
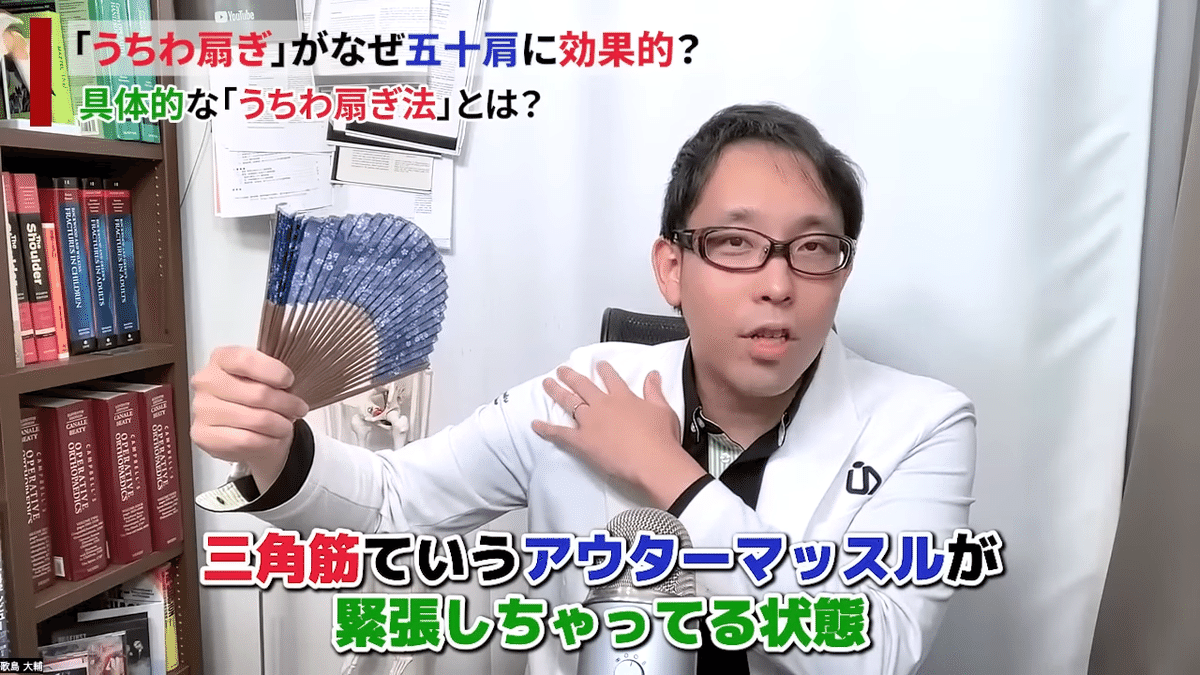
これだと上手にインナーマッスルが働きにくいので、三角筋は緩めておきたいんですね。
ですから、肘はどこかに置くか、おろしておくと考えてください。
実はこの「うちわ扇ぎ」は奥が深くて、様々な研究論文を集めながら、
こういう場合にもこういう効果が期待できるっていうことをお話していけたらなと思っています。
まずはお気軽に痛くない範囲で「うちわ扇ぎ」する習慣をつけるということからトライしてみてください。
クセにしたいので、何回何セットとかあえていいません。

ついやっちゃう環境を作って、ついやっちゃってください。
本日の一言

五十肩良くしたければ、うちわ扇ぎをクセにしよう。
🎁電子書籍「Shoulder Rule」プレゼント
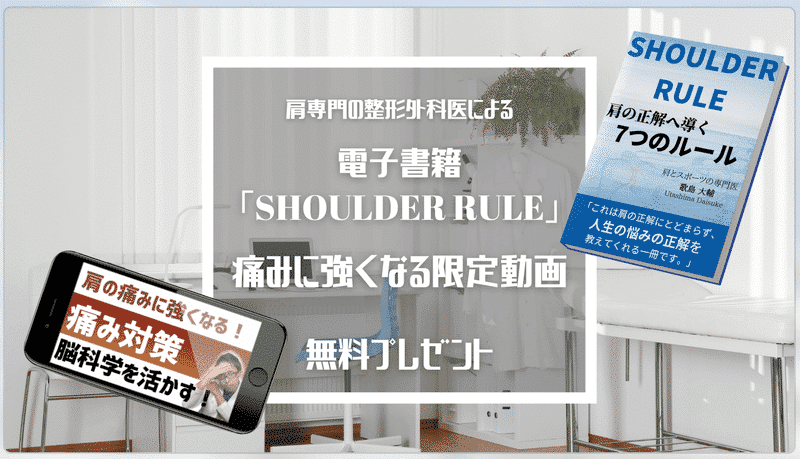
肩の治療に関する渾身の電子書籍「Shoulder Rule」をプレゼント中です。
さらに特別限定動画「痛みに強くなる!-脳科学的痛み対策トップ3」を追加プレゼントします。
詳細はこちら▼
🎁治療家さん向けプレゼント
電子書籍「レッドフラッグ100選」

危険な兆候・症状・疾患を一気に学べる▼
参考論文
(*1)Won-Moon Kim et al. Int J Environ Res Public Health. 2021 Effects of Different Types of Contraction Exercises on Shoulder Function and Muscle Strength in Patients with Adhesive Capsulitis
