
お持ち帰られ喫茶店❺【番外編】|お持ち帰られは図書室まで。ーオオカミくんと栞さんー
※画像はイメージ画像です。
※特に強制はしませんが、読者はお好みの人物を投影しながらお読みいただくと、よりお楽しみいただけます。

それは校舎の裏でも屋上でもない。
二次元や電脳空間でないのは無論のこと。
反響、鳴り止みません。
シリーズ『お持ち帰られ喫茶店』が、大好評です。これは、もう、じぶんでも認めぬわけには行きませぬのぬ。
なに、『のぬ』て。
いや、聞かれても困ぬのぬ。だって、意味などないのぬ。『ぬ』だけだと重いのぬ。『の』だとガーリーだからかもなのぬ。

(たぶんこの辺であなたも『のぬ』と言いたくなってのぬ)
全国百万人の童貞諸君!お待たせした。
今回は、君たちの遠い未来の話ではない。
あすにでも起こり得る出来事である。
わお!
あるよ、あるぜ、あるかもよ!
ラッキラボーイ!
童貞諸君、おおいに、期待に胸と、妄想に下半身を膨らませて聞いてくれ。
ほれほれーい。
で、この『お持ち帰られ喫茶店』は、いつも、こんな風にはじまる。

わたしは珈琲が好きだ。
だから上京後は喫茶店で働いた。
こうして物語の舞台が整った。

だが、今回の『お持ち帰られ喫茶店』、わたしが当喫茶店で働きはじめる前のことになる。
つまり上京前のはなしということ。
タイトルに【番外編】と付したのは、そういう理由からだ。
でもね、これは、あくまで、後の『お持ち帰られ喫茶店』へと繋がっていく重要なエピソードであることは間違いない(のぬ)。
これまで支持していただいた読者と童貞諸君の期待を裏切ることには、決してならないだろう。
だから、ゆるせ♡
では、今回の主役(ヒロイン)を紹介しよう。
図書室司書の本野栞だ。
彼女は、わたしが通う高校の常勤司書であった。
そして、もうひとりの登場人物を紹介しておく。国語教諭の森高先生だ。

「森高先生イメージ画」
高校時代、わたしには憧れの先生がいた。
国語の担当教諭である。
そう、森高先生だ。
森高先生は、わたしが高校二年のときに赴任してきた。彼女は、プジョーのカブリオレに乗ってやって来た。その、小さくも、可憐な花のような立姿と、繊細な硝子細工のような透明感と、どこか影がある表情に、わたしはつよく魅かれた。
一目惚れ、とはまた違った引力に惹きつけられたのだとおもう。
恋、と呼ぶには、あわすぎる想い。
年頃のわたしには、そのあわい泡沫に名前をつけることはできなかった。
彼女は、とある事情から図書室に在籍していた。残念なことに、別のクラスの副担任であった彼女は、わたしのクラスの国語担当でもなかった。接点なし。
ネ申は死んだ。
絶望したわたしは天に唾を吐いた。ぺっ。
数秒後、それは、わたしの顔をめがけて降ってきた。マイ・フェイスまでわずか数センチのところで、わたしは、それをよけた。
あぶ、あぶ、あぶないのぬー!
自業自得ぞ。
(あたま使えよーというネ申の声もよけてやった。ケッ。)
わたしは彼女と話したくて、わざわざ質問を拵えて、足繁く図書室へ通った。あの頃のわたしは、素直でなかなかかわいいやつであったのだ。
いまでは、すっかり汚れっちまったが。ケッ。
彼女と話す機会がある度に、わたしの胸の辺りでは、トクトクトクの音が強まった。気の利いたこと言って、彼女の笑顔を見れた日には、夕日までが桃色に染まった。そのようにして、うすい胸を焦がす日々が続いていた。

夏が来て、
地球は公転し、
夏が終わり、
秋の番が来た。
二学期がはじまった。
最初は小さな異変だった。
図書室に居るはずの時間に、彼女の姿が見えないことがあった。居たとしても、表情は曇りがちで、どこか、朧げであった。
何か負担を負っているのかもしれない。もしかしたら、夏休みの間に、彼女の身に何かあったのかもしれない。想像したくはないが、例えば、恋人との関係に悩んでいるのかもしれない。そんなことをひとり勝手に思っていた。
さらなる異変が起きるのに、それほど時間はかからなかった。繊細なものが崩れるときと同じように。彼女は学校から姿を消した。副担当のクラスでは、休職したとの説明があった。
彼女は、心を病んでいたのだ。
それは、わたしの通う高校へ赴任する前から、すでに起こっていた。復職と同時に異動が決まっての赴任だったのだ。図書室に席が与えられたのも、学校側の配慮であった。
こうして、のんきであほうなわたしの、昼と放課後のうきうきウォッチングは、あっけなく終わりを迎えた。お昼の長寿番組は、まだ、続いていたけどね。
失恋、と呼ぶには小さすぎるあわい恋心は、秋の空気に滲んでいった。

図書室に行く習慣だけが残った。
放課後、ひとつ空いた席に座る。
アンニュイな気分に浸る。浸るつもりはないが、浸るしかないこころがわたしの内側に残っていた。わたしは年相応に不器用であったのだ。
夕陽、窓辺、黄昏、青年。
「Uくん、そろそろ閉めるけど。」
栞さんがわたしに声をかける。
「ああ、そっか、帰ります。」
わたしは、栞さんに向き直り返事する。
「はやく戻って来るといいね。」
「え?」
「森高先生。」
「あー、うん。」
「元気出しなさい、少年。」
「少年じゃ、ねーし。」
「ごめんごめん、冷やかすつもりではないの。」
「うん、わかってるよ。」
「ただ、ちょっと、元気づけたかっただけ。」
「おれ、そんなに元気なさそう?」
「この世の終わりかって顔してる。」
「げ、そんなに?」
「うん、そんなに。」
「おわってねーし、世界。」
「そう、世界は終わっていない。よくわかってるじゃない。」
「おれの世界は無限に広がってるんじゃ。」
「そうそう、青年。きみの前途はあかるいぞ。」
「はは、うん、なんか、ありがと。」
「いえいえ。これも司書の務めですから。」
「それ、どんな務めさ?」
「うーん、ほら、悩める高校生がいて、その悩みはまわりの人にはどうすることもできなくて、でも、手に取った一冊の本によって、その悩みが解消されるなんてことが、あったりする訳。伝わってるかな?」
「おれ、いま、栞さんのこと、すげえなこのひとっておもってる。」
「いや、そんなすごいことは言ってないよ。」
「知的な女性にに見えてきた。」
「逆にいままでどう見えてたの?」
「そうだなぁ、元純粋な文学少女とか。」
「色々と反論したい点があるのだけど。」
「あー、文学じゃなくて物理学だった?」
「もう、口が回る子だこと。」
「生意気で、すんません。このとおり。」
「うふふ、まあ、いいけどね。」
「恩にきます。」
「いまは何か本、読んでるの?」
「読んでるよ、アゴタ・クリストフてひと。」
「ううーん、いい本だけど、いま、じゃないかもね。」
「じゃあ、元文学少女の方の、いまのおすすめは?」
「そうね、ちょっと待っててね。」
そういって、栞さんは書棚から一冊の本を持って来た。
「これなんて、どうかな。」
「キッチン? あー、読んだことないや」
「いまのきみにはいいかも。」
「ここで拒否したら?」
「感じ悪い高校生の烙印が押されます。」
「図書室だけに。」
「うふふ、そう、スタンプしちゃうぞ。」
「あながち間違いじゃないけどね。」
「そうでもないよ。」
「そうでもないって?」
「きみ、素直だもの。」
「こども使いされてんなぁ。」
「誤解、誤解。これでも頑張って元気づけてるつもりなの。」
「うん、それ、伝わってる、ありがと。あ、これ、すげえ、こころからのやつだよ。」
「いえいえ、どういたしまして。」
「じゃあ、これ借りてく。」
わたしと栞さんの間を、本が行き来しはじめた。それは、行き先が書かれていない乗車切符のようであった。わたしと栞さんは、その列車がどこへ向かっているかなど、露程も知らなかった。
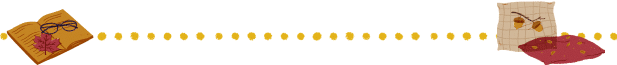
森高先生への思慕は、秋が深まるに連れて、その色彩に紛れ込んで消えた。空いた余白を埋めるように、わたしと栞さんは本の話を積み重ねていった。
その日の放課後、図書室はがらんとしていた。鍵は開いていたが、なかには誰もいなかった。わたしはいつものように奥の席に腰掛け、窓の外をぼんやり見ていた。夕日は、中庭の銀杏の葉をオレンジ色に染めていた。
「横顔、綺麗だね」
栞さんの声がする。
「ん?なんか言った?」
わたしが聞き返す。
「きみは、きれいな横顔をしてるねって」
「なにそれ、言葉のチョイス間違ってない?」
「適切な表現を選んでいます。」
「あたしゃ、女じゃないけどね。」
「うふふ、そういうつもりじゃないんだけどな。」
「そこは、格好いいねとか、シャープだねとか、ニヒルだねとかじゃない?」
「ニヒルはないな、U青年」
「ガーン!」
「ニヒルは、ガーンとは言わないでしょ。」
「ガーン!」
「うふふ、わざとやってるね、きみ。」
「バレたか。」
「さっき部屋に戻ったとき、Uくん、窓の外を眺めてたでしょう。」
「アンニュイな気分に浸っていたのさ。」
「キザな言い方、似合いません。」
「ガーン。もう、一生、使えないと思うまる子であった。」
「うふふ、案ずるな青年。」
「うぶなハートが痺れ、いや、砕けたわ。」
「ごめんごめん、ちょっと意地悪だったね。」
「海より深く反省してください。」
「はい、反省します。」
「よろしい。」
「こらこら。」
「てへ。」
「まったくもう。あのね、さっき、横顔に見惚れたってことよ。」
「あー、続いてたの、それ。」
「きみが逸らしてたんでしょ。」
「そうともいう。」
「伝えたくなったの、なんだかね。」
「ふーん、いいけど、それって、どうなの?」
「いいんじゃない。造形美だもの。実際、モテるでしょ、きみ。」
「モテる…ふーん、モテるねえ。」
「ん?なにか引っ掛かってる?」
「そのモテるはさ、実数を言ってる?」
「実数?」
「そ。何人に直接告白されたとか、付き合ったとかの数。」
「そういう訳じゃなけいけど、どうして?」
「おれの場合ね、ことごとく虎徹(こてつ)、あ、同じクラスのやつね、テンパーのコテツーね、あいつにストップかけられてるみたい。」
「え、それ、なんのストップ?」
「とある女子がいるとする。おれに気があるとする。奇跡的にね。でも、おれには女子遠ざけオーラが発動している。無意識にね。とある女子は、いいひとオーラ全開、あ、これ、意図的ね、の虎徹に相談する。相談者された虎徹はこう言う。『あいつだけはやめた方がいい』。ことごとく。だから、おれんとこまでは来ないこと多数。」
「あはは、阻止されてるってこと?」
「そ、そ、そ。三枚ブロックよりも暑い壁。」
「じゃあ、告白とかされないの?」
「されないこともないけど。」
「果敢にもブロックを破る女子がいるわけね。」
「まあ、いるっちゃいるけど。」
「けど?」
「それだけで終わります。」
「付き合うまでいかないってことか。きみ、恋愛に興味がない訳じゃないよね?」
「さかりのついた草刈正雄です、ぼく。」
「飢えてるわね。」
「ウォーン!」
「オオカミくん。」
「飢えたオオカミくんは、どっちかてと追いたいタイプ。」
「なるほどね。」
「You see?」
「I see.」
「よろしい。」
「こらこら。」
「てへ。」
「じゃあ、残念だね。森高先生来なくなっちゃって。」
「それは、すでに過去のはなしです。栞さん、良いかい、おれの未来は開けてるの。大きな海へと繋がってんの。そこには、まだ見ぬ美しい鰭を持った魚が泳いでいるわけ。いつまでも魚のいない水槽のなかで泳いでいたら会えない、そう気づいたわけ。You see?」
「I see.」
「よろしい。」
「うふふ。」
「な、なに、その笑い。」
「さあ、なんだろうね。」
「おとなは隠してばかりだぜ。」
「Uくんの素直さは、まぶしいのよね。」
「あー、おれ、そのうち神になるかもね。」
「神?なんの?」
「そりゃ、本でしょう、紙だけに。」
「あはははは。上手ね、きみ。」
「ぼかぁ、それくらいしか取り柄がない、しがない青年です。」
「横顔もきれいだけど。You see?」
「I see.」
「よろしい。」
「ずる。」

🐟゛ 🐟゛
図書室のひとつ空いた職員席が、わたしの居場所となった。栞さんは、気まぐれに現れては無遠慮居座るわたしを、彼女なりのささやかや気遣いで受け入れてくれていた。わたしのような無遠慮で小生意気ではぐれオオカミの性質を持った生徒には、そこは居心地の良い空間だった。
「Uくん、本好きなんだねぇ。」
「なに?いまさら?」
「図書委員でもないのに、よく飽きもせず来るなと思ってね。」
「あ、迷惑ならドロンします。」
「ううん、全然迷惑なんかじゃないよ。」
「よかった。実は、けっこう、気に入ってたりする、ここ。」
「図書室の司書として光栄です。」
「おれね、すげー読むの、本。だから、金欠高校生には天国だよ。」
「Uくん、最近は何読んでる?」
「最近はね、太宰治と夏目漱石、と言いたいところだけど、山田詠美の『ぼくは勉強ができない』と村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』とかかな。あと吉本ばなな。流行りに弱いです。」
「見込みあるなぁ、きみ。」
「なんの見込み?」
「大学生になったら、引く手あまたよ。」
「どーゆう意味?」
「モテるってこと。センスいいもの。大人になるとね、ある意味で、見た目や知性よりセンスが求められるものなの。」
「あれ、おれ、きょう誕生日だっけ?」
「そうなの?」
「いや、すげー、褒めてくれるから。」
「うふふ、褒めすぎたかな。なら、前言撤回。」
「ガビーン。」
「うそうそ。」
「てか、栞さん。」
「ん、なあに?」
「栞さんも知性とセンスあるよ。」
「あら、ありがとう。」
「それに、きれいだし。」
「な、なーにいってんの、いきなり。ませたことを言うなぁ。森高先生目当てだったくせに。」
「まあ、それは否定できない。けど。」
「けど?」
「言われるほど、尾を引いてないよ。」
「ほんとかしら。きみのこころは読めない。」
「司書なのに?」
「ふふ、きみが本だったなら、お手のものだったんだけどね。」
「残念でした。」
「くやしいなぁ。」
「あれ?ひょっとして、栞さん、それ、正月に食べるやつ?」
「え、なにそれ?」
「ヤキモチ、なんつって。」
「もぉー、いやなヤツ!」
「あはは、ごめんなさい。そういうお年頃ということで見逃してくれよーぅ。」
「もういいわよ、なんだかわたしだけむきになってるみたいだもの。」
「ムッキー、なんちゃって。」
「もう、前言撤回!」
「栞さん、ごめんね、だって、急に変なこと言うんだもん。おれ、ちょっと、ドキッとしちゃったよ。」
「それは…ごめんなさい。」
「いいよ、森高先生はさ、なんつーか、高嶺の花っての、いや、違うな、ほら、ふだん何もないところに、こう、ゆりの花があったりすると、わっ、てなるじゃん。その花が好き!とかな訳じゃないんだけど、見るとなんだかきれいだなあって思うじゃん。そういうやつ。」
「男の子にしたら、そうかもしれないね。」
「男の子扱いには異議を唱えたいところだけれど、まあ、付き合うなら栞さんかな。」
「え、なに、急に、こわいなー、高校生!」
「え、ダメ? 飢えたオオカミくんは素直さが売りなんだけど。」
「おとなをからかうんじゃありません。」
「からかってないよ。さっきはからかってたけどね。」
「んもう、Uくんて、将来どうなるのかしら。」
「興味あり?」
「うーん、正直なところ見てみたい気はするかな。」
「では、ご指導ご鞭撻、願います。」
「ふふ、その頃には、わたしなんておばさんよ。」
「それ、森高つながりのつもり?」
「じゃない、じゃない!」
「だったらさ、栞さん。」
「ん?」
「自分をそんな風に言うもんじゃないよ。自分で自分のきれいさを霞めるのは、不誠実だと思うんだ。」
「う…」
と言い、栞さんは自分の胸に手を当てた。
「ひゅんっ」
わたしは両手で弓を放つ仕草をした。
その放った矢が、いたずら好きなキューピッドの矢であったことに気づくのは、もうすこし先のことだった。互いの言葉は、すこしずつだが、確実に、互いの心を射抜いていた。それは色付く紅葉のコントラストが隠していたのかもしれない。

前線が停滞し、日本列島は、秋雨が降り続いていた。すすきは雨粒の重さで振袖草としての存在を増していた。しとしとしとと雨の音は図書室に広がる静けさを一層閉じ込めた。電気の点いていない部屋は、湿った枯葉の匂いがした。窓から差し込む薄明かりと陰翳の狭間に紛れている席に座り、栞さんは俯いていた。
「あれ、居ないのかとおもった。」
「ああ、ごめん、電気点けてなかったね。」
「もう帰るとこ?」
「ううん、まだ帰らないよ。」
「栞さん、顔のここ、縦線入ってるよ、ちびまる子ちゃんみたいに。」
「ああ、そんな?」
「大丈夫?体調か何か悪い?」
「ううん、体調は悪くないよ。大丈夫。」
「うん、まあ、詮索はしないけど、多感な高校生男子代表だから、感じるものはあります。ひしひしと。」
「そっか、さすがだね、Uくん。」
「心っていうか、気持ちの置き所って言うのかな。つまらないことなのよ。」
「心のなかにあるものに、つまらないものなんてない、という人がいたけど、それに一票。」
「そうね、そのとおりだと思う。」
「けど、栞さんは、つまらないことだと思ってる。思っちゃう栞さんがいる。」
「そのとおり。」
「じゃあ、おれが口出しすることじゃないね。」
「そのとおりよ。」
「どっちかってと、ひとりになりたい気分?それとも、だれかがいた方がいい気分?」
「そうね、こうして居てくれると、いいかもしれない。」
「うん、わかった。」
会話が途切れる。
沈黙が流れる。
雨音が響く。
無言だが無音ではない。
自然が奏でる太古の音楽。
文字にならない音楽は、時に、言葉にできない心にしずやかに寄り添い癒やす。それを聞くだけの耳を持つ人の心を。
「欠陥品なのね、わたし。」
ぼそと、栞さんが言葉を零す。
「欠陥品?」
わたしは、零れた言葉を拾う。
「昔ね、恋人だった人から言われたことがあるの。きみは欠陥品だって。」
「それを思い出してた?」
「うん、そう。こんな日には、ふとね。」
「忘れられないひと?」
「ううん、そうじゃないの、全然。あんなやつは、わたしから振ってやったんだから。」
「さすが、栞さん。」
「だけどね、言葉が残ってるの、心のどこかに。」
「喉に刺さった小骨のように?」
「ええ、そう、小骨のように。」
「じぶんではどうすることもできないね。」
「そう、困ったものね。だから、時々、それがこんな風にさせるのかもしれない。」
「繊細な心だね。栞さんは、きっと、他の人が何気なく見逃してしまうものもキャッチしているひとだ。」
「ふふ、ひょっとして、慰めようとしてくれてる?」
「力及ばずながら。」
「やっぱり、Uくん、見込みある。」
「あれ、逆に、慰めてくれてる?」
「ううん、そうじゃないの、Uくんと話していたら小骨が取れたみたい。だから、Uくんのおかげかな。ありがとう。」
「あれ、力及んだみたい。運がいい。一生分の運を使い果たしたかもね。」
「あら、それは大変。取り戻さないと。」
「栞さんの痛みが取れたならいいよ。」
「どこまでも優しいのね。」
「苦労してるんですよ、こう見えて。」
「そうなのね。うん、そうね。」
「小骨とれて寂しくない?」
「うーん、何かが無くなった感じはあるけど、寂しくはない、かな、いまのところ。」
「埋める準備だけはしておきます。」
「ふふ、本があるから大丈夫よ。」
「本が埋めてくれる?」
「そうね、恋人がわりでもさせるか。」
「司書だから?」
「そう、司書だから。物語がわたしを救ってくれるの。」
「文学的なこという!カッケーな。」
「ふふ、カッケー女よ、わたし。」
「じゃあ、おれも物語になれます?栞さんの。」
「ませてるわね。」
「よく言われる。」
栞さんは満たされないものを抱えていた。
それは、わたしも同じだった。そもそも、生きていることは満たされないことなのだから当然だとも言える。わたしたちはみんな必死になって、その満たされない部分を別の何かで満たそうとするし、そうでないなら、なんとかして隠そうとする。飽食の時代が飢餓を暗部に変えたように、わたしたちの持つ満たされないものは恥部に変えられてしまったのだ。周到に。
それが、ふたりを引き寄せていた。
「Uくんの貴重な運を使ってもらったお礼をするわ。」
「お礼?」
「ほんの気持ち程度だけど。」
「うーん、何か欲しくて言ったんじゃないんだけどね。」
「もちろん、それはわかってるの。ただ、わたしがね、何か形になるお礼をしたい気分なの。」
「高級羽毛布団でも?」
「ふふ、いいわよ。こう見えて、お金持ちなの、わたし。」
「キラーフレーズだなぁ。貧乏学生、只今、心を揺らしてます。」
「高級なチョコレートなぞはいかが?」
「あー、じゃさ、いっこ言ってみていい?」
「いいわよ。ひとつでも、ふたつでも。」
「おれ、シチュー食べたい。栞さんの作った。」
「シチュー?わたしの作った?」
「うん、そう。栞さんの手作りシチュー!」
「いいけど、お店のじゃなくて?」
「そう、お店のとかじゃなくて!おれね、事情により家庭の味に飢えてるの。しかもね、手作りシチュー、食べたことないの!いまどき、手作りシチュー食べたことない高校生なんている?シチュー自体、中学の給食が最後っていう可哀想なやつなの。You see?」
「I see.」
「そんなのどうですか?」
「オーケーよ。」
「すげー、うれしい!」
「そうしたら、家に招待しなきゃ。」
「遠慮なくお邪魔します。あ、なら、本棚みたい!」
「必然的にそういうことになるわね。」
「本屋行くより楽しみかも。」
「やだ、大袈裟よ。」
「司書の栞の本棚、こんなタイトルはどうでしょうか?」
「ふふふ、需要と供給のバランスがね。」
「ここに需要はあるよ。だめ?」
「いいよ。奮発しちゃう。」
「え、これ、真に受けていいやつ?」
「もちろん、そのつもり。Uくんさえ良ければ。」
「いま、ときめきが止まらんよ。」
「それは、シチューに?それとも本棚に?」
「両方! そこに栞さんも含まれる。」
「もう!調子いいなぁ。」
「見逃してくんさい。」
「Uくんの都合を聞きたいのだけど。」
「バイトない日ならいつでも。」
そうして、つぎの土曜日の午後に栞さんのアパートに行くことになった。彼女が腕を振るうシチュー、そこにコーヒーと本棚がついたスペシャルメニュー。ときめく高校生男子は秋色に染まる街路樹の横を自転車で駆け抜けた。


土曜日、午後二時、最寄り駅前。
本日晴天なり。
わたしは待ち合わせ場にいた。栞さんは青いカローラⅡに乗ってやって来た。財布を忘れてないが、そのままドライブするやつだ。
ふたりを乗せた青い車は、紅葉をみるために山の中腹にある森林公園へと向かった。方道三十分のドライブは、わたしの気分を高揚させた。儚げに移ろう季節の所為もあっただろうし、カーステレオから流れる抒情的な青い車の所為もあっただろう。
帰り道、スーパーに寄って夕飯の食材を買い込んだ。約束のシチューの食材。こんな些細なことが、わたしにとっては、初めての体験だった。誰かとドライブ、誰かと紅葉狩り、誰かと夕飯の買い出し、わたしの人生になかった彩りが、いっぺんに添えられた。
栞さんのアパートに着く。年代を感じさせる二階建ての建物。彼女の暮らす部屋は、螺旋状の内階段を上がった角の部屋だった。
「重いもの、お持ちします。」
「あら、そんなことどこで覚えたの?」
「栞さんに教育されましたので。」
「わたしはなにも教えてません。」
「色んな本を教えてくれたでしょ。おれの知らない世界や物語。」
「うん、そうだったね。」
「それは、間接的に、この世界のことを教えてくれたってことじゃない?そしてそれは、教科書に書かれていることなんかよりも、ずっと、おれの生きる糧になった。」
「きみ、高校生よね? わたしが高校生の頃ってどうだったかしら。そんな風に考えたかなぁ。」
「さて、どうでしょう。」
「はて、どうだったかしら。」
部屋へと招かれる。
彼女の暮らす部屋は広めの板張りのキッチンと洋室、畳張りの和室に分かれていた。洋室には簡素な机と簡素な照明器具と衣装箪笥、和室には木製のベッドと大きな本棚があり、どれもよく使い込まれ、手入れを施され、艶を放っていた。わたしの暮らす実家とはまったく違う丁寧な生活の匂いがした。わたしにとって、そのどれもが、居心地の良さを感じさせた。
「お茶を煎れるから、適当にくつろいでてくれるかな?」
「うん、じゃあ、本棚見ていい?」
「もちろんよ、それが目当てでしょ?」
「ピンポーン♪ それも、お目当てです。」
そこでおもむろに手にした一冊の本。わたしが生涯手元に置く本となったことを、栞さんは、今も知らない。
野菜を刻むリズミカルな音が、鼓膜を心地よく突く。ジュッと焼かれる野菜たちの匂いが気化された油に運ばれ鼻腔に届く。ポコポコとマグマのような小爆発に誘われ、わたしの心の中の溶融体も小さく爆ぜる。
「お待たせしました。」
からし色のエプロン姿の栞さんがわたしを呼ぶ。
「待ちくたびれました。」
わたしは本を閉じて、キッチンへ行く。
ふたりで準備を整えて、椅子に座る。
ふたりで手を合わせる。
「いただきます。」
「いただきます。」
「どうかな、Uくんのお口に合うと良いのだけれど。」
「もう、すでに、美味しいよ。」
「ひと口食べただけじゃない。」
「このひと口が、すべてを語ってる。」
「違いの分かる男か。」
「わからんけど、おれにとっては最高に美味しい。」
「ふふ、良かったわ。」
「さあ、栞さんも、遠慮なく食べなさい。」
「わたしが作ったんだけどー。」
「ありがたき幸せを噛み締めてます。」
「んもう、どうぞ、たくさん召しあがれ。」
「料理も上手で、本の世界に詳しくて、ごにょごにょな栞さん。」
「なによ、ごにょごにょって。」
「聞きたい?」
「気になるじゃない。」
「きれいな、だよ。」
「んもう! 学校の外だと口がまわるまわること。」
「円広志じゃないけどね。」
「ふふ、学校じゃないから、飲んでもいいかしら?」
栞さんは冷蔵庫から缶ビールを取り出す。
「どうぞ。おれも一杯いただくとしよう。」
わたしはテーブルのグラスを傾ける。
「こら、未成年。」
「ほら、お注ぎしましょう。」
わたしは手と差し出して栞さんから缶ビールを受け取る。
「きみはダメだからね。」
「仕方ないなぁ、まったく困ったひとだ。」
「そっくりそのままお返ししますけど。」
「ささ、ぐびっと、どうぞ。」
彼女はグラスに注がれた黄金色の麦酒を一気に飲み干す。ふぅと一息つくと、タンとグラスをわたしの前に置く。注げの合図に、黙って頷く。わたしは空になったグラスを黄金色の液体で満たしていく。彼女も黙って同じ動作を繰り返す。
「いい飲みっぷり。」
「意外と、カッケー女でしょ。」
(金輪際この人に逆らうのはやめておこう)
「心の声が、ダダ漏れしてるけど。」
「これは教師としては間違ってるのかもしれないけど、人としては間違ってはないの。」
「栞さんは司書でしょ。司書は、教師の教えないことを教えてくれる存在であるべき、少なくとも俺にとっては。」
「Uくんのこと、良いなって思っちゃってる。」
「それ、鈍感な高校生にもわかるように、もっとわかりやすくいうと?」
「こういうときだけ、子どもぶるのね。」
「てへ。憎たらしい? で?」
「わたし、きみのことが好きよ。」
「うん、どれくらい?」
「すごく好きよ。」
「ねえ栞さん、それを、文学的に言うと?」
「文学的に? さっきわかりやすくって言ったじゃない。」
「だって、司書でしょ。それも、おれが絶賛恋焦がれている。知ってるでしょ?」
「ええと、そうだな、たとえば、時期じゃないのにもみじの葉っぱが赤に染まるくらい。」
「うーん、なんか文学的過ぎるかも。じゃあ普段はどんな風に思ってるの?」
「普段はね、いつもの時間にきみが来ないと時計を見てそわそわするの。そうするとね、足の指が騒ぎはじめるの、むずむずむずむずってね。恥ずかしいな。これでいい?」
「いいね、そういうのたまりません。おかわりください。」
「調子に乗らない。」
「作戦失敗。」
「じゃあ、Uくんは実際のところどうなのかを聞かせてもらいましょうか。」
「うん、おれはね、昼も夜も授業のときも部活のときもバイトのときも、あー、いま、栞さん何してるかなぁってなる。家とかで本読んでるときなんかね、あー、栞さんは何読んでるかなぁってなる。毎晩、布団に入るとね、栞さんのこと思い出してんの。それでね、栞さんの裸とか想像して、すげえいやらしいこと考えちゃって、悶々として寝られなくなっちゃって、寝不足になってる。だから、おれ、栞さんのこと大好きなんだ。」
「ぐはっ。」
「なに、ぐはって?」
「やられたのよ、あなたの言葉に。」
「栞さんて、すぐ落とされちゃうひと?」
「わたし名前が栞のくせに、落ちないで有名なのよ、これでも。」
「でも、落ちた?」
「落ちたと思う。」
「思う?」
「落ちました。身構えてはいたんだけど、ものすごいストレートなやつに見事にとどめを刺されました。たったいま。」
「じゃあ、拒むものはなくなったって理解でいい?」
「…うん、なくなった。」
「おれ、飢えてるよ。」
「飢えたオオカミくんね。わたしの手に負えるかしら。」
「試してみる?」
「お腹も満たされたことだし。」
「そう。違うところも満たされなきゃ。」
「どうしよう、わたし、初めてよ、Uくんみたいなひと。」
「おれも、初めてです、栞さんみたいなひと。」
「どうかしらね。」
「お試しくださいませ。」
「真実を見極めるには試さないとね。」
「お手柔らかにお願いします。」
「それは、こっちの台詞よ、もう。」
わたしは待ちきれずに立ち上がり、栞さんの手を引く。栞さんは、まるで重力がなくなったかのように、すくと立ち上がる。彼女は、わたしが思っていたより、小さかったことに気がつく。わたしは彼女の背中に片手を回し、静かに抱き寄せる。
「…展開がはやいな、きみ。」
「嫌なら、待つこと可能なオオカミくんです。」
彼女はわたしの顔のすぐ下で首を横に振る。
そして、胸にぴたりと耳を寄せる。
「鼓動が、力強く、鳴ってるわ。」
「うん、ドキドキしてるのバレるね。」
栞さんが顔を上げる。
わたしは彼女を見つめる。
麦酒のせいか、彼女の瞳は潤んでいる。十七のわたしにとって、彼女の中に潜む女性性は、眩しくも、艶かしく、理性を酔わせるのに十分な効力を放っていた。
「キスしていい?」と、オオカミくん。
「そういうのは聞かなくていいの。」と、栞さん。
わたしは頷き、彼女に唇に口づける。それは、頬をつたって、耳へ。耳朶の形をなぞって首へと向かう。
彼女の熱を帯びた吐息が漏れる。
淫雛な成分が含まれた彼女の吐息は、わたしの色情を駆り立てる。芽生え始めた本能が徐々に開放されていく。
セーターの裾から手を入れて、彼女の背中に触れる。指で背骨をなぞる様にゆっくりと上行し、ブラジャーのホックを外す。わたしの手が乳房を弄ると、彼女は耐えきれず吐息を漏らす。
彼女は、わたしの首筋のあたりに頬をうずめながら、わたしのシャツのボタンをひとつずつ外していく。器用に、そして丁寧な手つきで。
わたしは彼女のコーデュロイのフレアスカートのジッパーを下げる。腰から解放されたスカートは、するりと足もとに落ちていく。
「かわいすぎる。」
「ばか。」
「好きにしていい?」
「ん。けど乱暴はだめ。」
「この本野栞だけは、どの本の栞よりも大切に扱います。」
「ふふ、うまいこと言うのがオオカミくんの手口ね。」
「はい、でも、経験不足は否めません。」
「そのくせに器用なんですけど。」
彼女の言葉を遮るように口づけをする。
セーターを裾をたくし上げる。白桃の皮を剥いたような白い乳房が露わになる。わたしは、露わになった果実にも口づけをする。彼女の乳房からは甘い桃の香りがする。
「だめ。」と、栞さん。
「だめ?」と、オオカミくん。
「つづきは、ベッドで。」
「焦らすね、ウォーン!」
オオカミくんは彼女を抱え上げ、きゃっと声を出す栞さんを和室のベッドへ運ぶ。もたれるようにふたりはベッドに倒れ込む。オオカミくんはTシャツを脱ぎ捨てると、栞さんに覆い被さり、桃の皮のように上着と下着を一枚一枚、剥いでいく。栞さんは、オオカミくんのズボンジッパーを下げると、手と足を使って下着とともに器用に脱がせる。
「やだ、大変。」耳元で栞さんが囁く。
「飢えてる証。」オオカミくんは栞さんの首にかぶりつく。
「責任とってあげる。」
栞さんの指がオオカミくんの性器を弄る。膨張を続ける性器を、栞さんは舌と唇でなだめる。オオカミくんは体の向きを変え、栞さんの陰部を指で優しく撫でる。彼女の一筋の裂け目からは、熟れた果汁のような体液が滴っている。それは蜜のような艶やかな光と芳醇な芳香を漂わせ、オオカミくんの食欲を誘う。
濃密な愛撫の時間が過ぎる。
淫靡な熱を帯びたふたりの身体が重なる。
ふたりは互いの手を強く握りしめる。
脈打つ突起物が、滴る裂け目の奥へと吸い込まれていく。
ふたりは、飽くことのない動物のように互いの肉体を貪り、欲に溺れる夜を明かした。
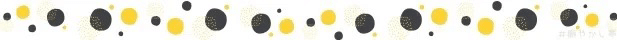
オオカミくんは、乳房香味は白桃のそれだと言うことを学んだ。世界の神秘の一つを知った夜であった。
こうして、オオカミくんのわたしは、司書の栞さんにお持ち帰られた。
この数年後、上京後に働くことになる喫茶店が『お持ち帰られ喫茶店』になるとは、このときは、まだ、露ほども知らないオオカミくんであった。
ーおしまいー

ーあとがきー
というわけで、この『お持ち帰られ喫茶店』も今回の【番外編】含めて5作品となりました。
なんやかんやで、評判いいから、来年の創作大賞に出してやろうと画策しています。ひひひ。
とはゆうても、実体験に基づく私小説であることに変わりない。続けるかどうかは、わたしの気分と筆次第なのだ。
まだまだ続きを読ませてへいの!
もっと、きゅんきゅん、くらはい!
終わりなんてやだ、さみしりーの!
という読者がおりましたら、わたしのモチベーションが爆上がりするようなコメントを届けてください。ん、なんのはなしですか。ヘイッ!カモンッ!コニCキノCO🛸
「つづくの? つづかないの?」

前作はこちら↓
※記事で用いられる画像はイメージ画像であり、当記事の登場人物とは無関係です。ご了承ください。
※誹謗中傷や迷惑行為などは、ご遠慮ください。然るべき対応をさせていただきます。
