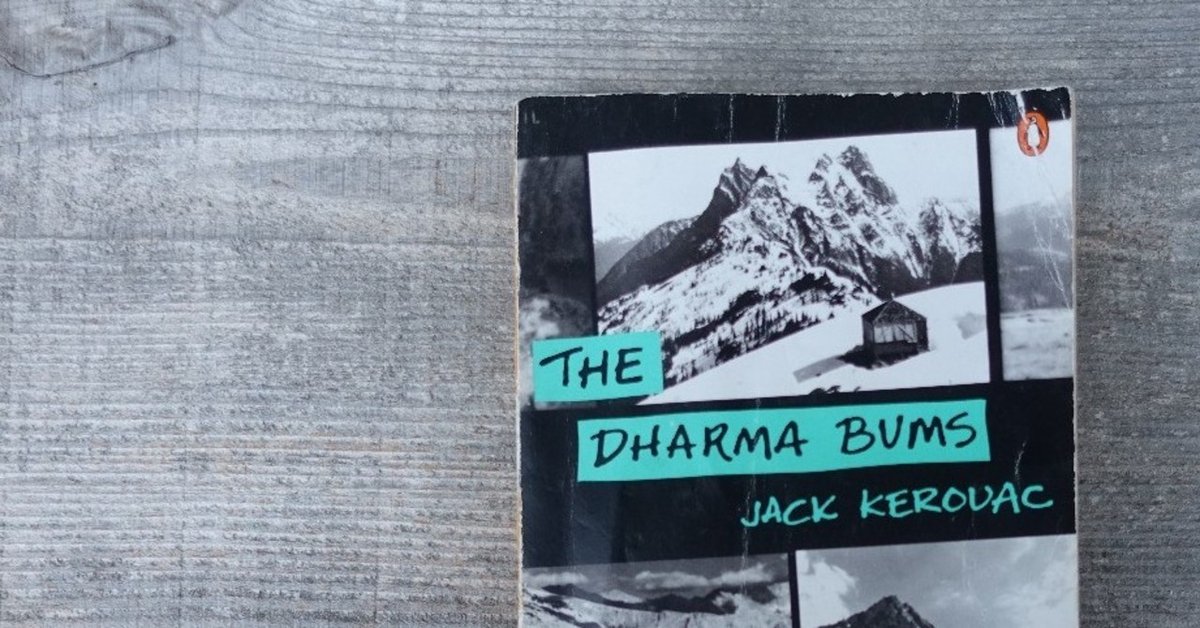
『ダルマ・バムズ』を読んだら山を歩かないわけにはいかなくなった
世界は広く、多種多様な生命がこの地球上で暮らしていると言っても、肉体的に僕たち人間にしか成しえていないことがある。それは二足をもって直立して歩行できるということ。カンガルーや鳥類、一時的には猿なんかも二足歩行まではできるが、直立二足歩行となると人間だけということになる。
僕が思考や思想、宗教、神秘的な部分を通して人間の持つ能力や可能性に興味を惹かれていった時、その「直立二足歩行を行う唯一の動物」としての人間を僕なりに突き詰めたいと思ったのは自然な感情だったように思う。野性、すなわち人間のかくあるべきという姿、自己に囚われずにありのままに自由自在である姿が、その美しき直立二足歩行の先に見えてくるのでは。そのように考えてすらいる。
そんな僕が歩くに至った経緯、そしてタイトルにある通りその二足を山に向かわせた経緯を私見満載、自己の経験たっぷりに記しておこうと思う。
歩く魅力を見つけづらい東京に生まれ育ち
積極的に歩くようになってからと言うものの、僕は、走ることよりも、歩くことに重きを置いてきた。学生時代は陸上部として中長距離走をやっていたこともあり、ハムスターのように同じところをぐるぐる回るという退屈さや、東京生まれだからこその窒息しそうな排ガスの中で呼吸を荒げるイメージが走ることにはあったからかもしれない。とにかく歩くという行為に一層の高潔さを感じたのだった。走ることも歩くことも同様に美しいと気付くまでは少し時間がかかった。
僕を直接的に歩かせたのは風情のある街並みや雄大な大自然というよりも、一冊の本だった。いかにも東京生まれ東京育ちの僕らしい頭でっかちなスタートだとも思うし、過去のものとなってしまった緑豊かな武蔵野、今や殺風景な関東平野にはそうさせることは出来なかったのだとも思う。
洋楽を通して出会ったジャック・ケルアック
その本との出会いは必然だった。英米の60-90年初頭のロックバンド(ガンズやニルヴァーナくらいまで)や古いブルースを好んで聞いていた僕は、次第にボブ・ディランばかりを聞くようになっていき、詩や言葉の世界とそれらが持つパワーに惹かれていくことになった。そしてディランが敬愛して止まなかったビート詩人、ジャック・ケルアックの代表作『オン・ザ・ロード』に出会う。いや、正確にはそれ以前にも知っていたが、ついに読んでみようと思ったのだ。
何かを求め、捕まえたと思っても実は何も得られていないというような、希望と失望の交差するアメリカの東西とメキシコまでも股にかけたケルアックの自叙伝的ロードノベルに自分を重ね、高校を卒業するまで本などろくに読んだこともなかったのに一気に読破しては、少しづつ自分の思考の断片を文章にするようになった(それは確かカリフォルニアに留学している時、20歳の時だったと思う)。
それまで読書感想文には最悪な記憶しかなかったにも関わらずだ。それからは本が大好きになるが、僕を歩かせた運命の一冊との出会いはそれから2年くらい経ってからだと記憶している。
運命の一冊との出会い
ある日、兄の部屋の本棚に並ぶ背表紙を眺めていた時、ケルアックの本があるのが目に止まった。
『ダルマ・バムズ(Dharma Bums)』
ダルマとは仏教用語で「法」を指し、
バムとは「浮浪者」または「何かに熱狂するもの」。格好良く言えば「求道者」を意味する。
「ああ、知らない本だな」と思い手にとったが最後、僕は一気に引き込まれていき、自分を取り巻く世界が大きく動いていくのを感じた。それまでの人生で行ってきたことや、考えていたこと、そしてそこから目指すものがその一冊にまとまっていたと言っても過言ではなかったからだ。大袈裟だけれども、この本を読むために今までの人生を生きてきたのではという感覚だった。
その小説はケルアックお得意の自叙伝型小説であり、舞台はアメリカ西海岸。その頃にはすでに仏教に深く入れ込んでいたケルアック(作中ではレイ・スミス)が京都の禅寺に修行に行くことになる詩人のゲイリー・スナイダー(ジャフィー・ライダー)と出会う。時代背景はビート文学を世に知らしめることとなるアレン・ギンズバーグの『吠える(Howl)』がサンフランシスコのシックスギャラリーで初めて読まれた時で、この歴史的瞬間の様子はそれを目撃したケルアックによってダルマ・バムズの文中にも描かれている。
仲間内では評判が良いにも関わらず、鳴かず飛ばずの作家だったケルアックの先を越すように、ギンズバーグの『Howl』が成功を収めている時(1951年に執筆されたケルアックのオン・ザ・ロードは、Howl出版の翌年1957年に世に出てはビート文学の代名詞となり、のちのヒッピームーブメントへと繋がっていく)、詩作と酒とジャズの合間にもケルアックは瞑想に時間を裂き、スナイダーと仏教談義に花を咲かせては、共にシエラネバダ山脈のマッターホルン・ピークに登り「山から落ちるなんてありえないぜ」という閃きを得た。そしてスナイダーの紹介でワシントン州のデソレーション・ピークの山頂でファイアールックアウト(Fire Lookout)として一夏働いて、山と向き合うことになる。
(Fire Lookout=夏の間、単身山小屋に暮らして山火事を見張る仕事。山火事の多いアメリカでは。こういった小屋が見晴らしの良い山中にあって、無線で交信し合う。2017年のアメリカ西海岸での山火事による被害は記憶に新しい)
自らの衣食住と思想をカバンに詰め込んでハイキングやヒッチハイクをするという
「バックパッキング」の起源の一つ
ともいっていい世界が描かれたこの小説を読み終えると(作中ではリュックサックレボリューションという魅惑的な言葉が登場する)、僕は歩きたい、もとい、歩かなくてはいけないというウズウズを止められなくなるのと同時に、禅を中心とした仏教の世界に傾倒して行くようになった。
それ以来僕にとって歩くことは座禅であり、祈りであり、思考であり、直立二足歩行への賛美であり、エクササイズであり、薬であり、環境に優しい移動手段他、ここには書ききれないくらいの効果を発揮してくれている。
いくつか実例を挙げてみると『純粋理性批判』のエマニュエル・カントは午前中は仕事をして、午後の決まった時間に散歩をしていたのは有名な話だ。あまりに時間に正確なので人々はそれを見て時計の針を直したという逸話も残っているほど。また、キルケゴールやルソーもインスピレーションを求めて散歩を日課にしていたそうだ。歩くことは僕にとっても思考を明晰にする最善の手段の一つで、頭が行き詰まった時はいつも体の軸たる丹田(下腹部)やリズムよく前後する足が新しいアイデアを手繰り寄せてくれる。
また、子供の頃から鼻炎持ちで、10代は鼻水と鼻づまりに溺れて育ったと言っても言い過ぎではないほど。片鼻のみが開通しているのが当たり前で、20代以降も東京のスモッグの中にいる時は特に症状がひどくなることがあったのだが、日常的に歩くように(走るように)なると両方の鼻の詰まりが取れ、快適な生活を送れるようになった。
その一方、仕事の関係でデスクワーク漬けになって歩かなくなると鼻の通りが悪くなるのだった。
山を歩くために山小屋バイトへ
そんなこんなでいくつかの歩き旅を敢行した後(登山ブームが到来している奥多摩へのハイクや、家から東京湾まで往復30キロ歩くとか)、僕は山小屋で働くことにした。何しろレジャーとして山に登るには、当時はお金がなかったので、だったら山で働こうと思ったのだ。もちろんケルアックが山で働いていた影響ももちろんある。
それまで働いていた飲食店を退職し、仕事を探すのが5月に入っていたこともあり、夏の山小屋の求人の多くは募集を閉じ始めていた。こじんまりした山小屋を希望していたのだがそういうわけにもいかず、少し大きめな北アルプスの山小屋で働くことになった(それは結果的にかなり大きい山小屋だった)。
それまでは登山なんて金持ちの道楽程度にしか思っていなかったものだから山の知識は皆無。働くことになったのは日本のマッターホルンとも呼ばれるらしい「槍ヶ岳」という山にある小屋だった。その時点でどの辺に位置しているかすら知らなかった。
小屋は標高3000mにあるらしい。それまでは学校の遠足での富士山5合目の標高までしか経験がなかった。マッターホルン・ピークを登ったケルアックへのちょっとした運命を感じたのはいうまでもない。
「登山経験、バックパック、雨具、登山靴は持っているか」の質問に全て「はい」と答えたが、全部嘘だった。嘘をつくのは大嫌いだが、その時は強い意志を持って嘘をついたのを覚えている。
とにかくモンベルで70Lのバックパックと寝袋をこしらえ、靴は中古のダナー(お金がなかったことと、頑丈で長く履けると思ったから)、雨具は貰い物、登山ウェアを買うにはお金がないので、古着屋でチノパンやウールのシャツなどを買った。ウールやダウン以外は化学繊維が当たり前の登山の世界のなかで、シャツは全てコットンのあり合わせだった。物の溢れるこの時代にあまり新品のものを買いたくないというのもあった。ケルアックが初めての登山装備を古着で揃えたという影響もあったのだと思う。
北アルプスの洗礼。そしてパラダイス。
入山当日は嵐に見舞われた。貰い物の雨具はその機能の多くを失っており、雨は中まで浸透してきて、頭のてっぺんから足の先までずぶ濡れとなった。寒さに震えながらの登山となり北アルプスの洗礼を受けるスタートだった。その後数日は深いガス以外は何も見えなかったが、ガスが晴れてみるとそこは楽園といってもいい空間が広がっていた。それからというもの、3ヶ月続いた仕事の休憩時には必ずと言っていいほど周囲のトレイルを歩き回る生活が始まった。
東の尾根へ、西の尾根へ、南の尾根を伝って大喰岳、中岳、南岳へ、谷を降って水場へ、そして山荘前の槍ヶ岳山頂へ。北アルプスの山岳曼荼羅は歩く喜びを覚えた僕にとってはまさに楽園のような環境で、仕事中もこの後の休憩時はどこに向かおうかと考えることで、一層仕事に精を出すことができたし、休憩後も爽快な気持ちで仕事に戻ることができた。
そして強い確信を得たのは、ケルアックが閃いたのと同様に、確かに「山から落ちるなんてありえないぜ」ということだった。
It’s impossible to fall off mountains you fool
山から落ちるなんてありえないぜ
トレイルを二本脚で歩き、山と親密さを増していくほどに、本当にその通りと思えてくる。それは山で滑落したり遭難することはあり得ないと言っているのではない。山と一体になって、調和しきった時の自己と山との境界が無くなる感覚。もはや自分が山となって、山が勝手に歩いてくれている感覚。厳しい行程で疲労困憊するも、悪天候に襲われるも、足を滑らせて転ぶのも、全て山との美しい一体化があってこそだし(僕も山で冷やっとした経験はある)、それがあることで一層雄大な景観を堪能したり、トランシーな爽快感がもたらされたりするものだとも思う。
だから「山から落ちるなんてあり得ない」
山と一体にならないなんてあり得ない。のだと思う。
カスタマイズする旅へ
こうして僕は自分なりにルートを作成しては徒歩旅行をするようになった。四国遍路からの大峯奥駈道や、南アルプスから八ヶ岳を経由して北アルプスを日本海まで歩いてさらに信州を歩き回ったり。これらの徒歩旅行はいつも次に僕が進むべき方向への道しるべとなってくれたし、それぞれ50日くらいの行程だったが、その濃密さたるや軽く見積もっても1年くらいに匹敵する経験だったと自信を持って言える。
それでも冒険家が歩いた行程や、登山家が到達した高みには足元にも及ばないのはもちろんだ。しかし、国家プロジェクトとしての未開の土地の開拓や、主要な山の初登頂や無酸素登頂までも基本的にはやり尽くされた現在、未知への旅というものはもう存在しないのだとも思う。しかし、社会にとっての未知がなくなったとしても、個人の中の未知はなくならない。
僕がやったような徒歩旅行はまさに自分の能力や学びに合わせて、自分でカスタマイズした旅であり、プロジェクトと言っても良いものだ。歩く距離も、宿泊や食事のスタイルも全部自分で決められる。別に社会の要請でもなんでもなく、自分の決断でしかない。
インターネットの普及とグローバリゼーションによって世界は個性を失ってきた。そんな時代だからこそ、パッケージされたツアー旅行ではなく、それぞれのスタイルに合わせた旅が個々の世界を大きく開いていくことになるのだろうと思う。僕にとっては徒歩旅行がそうだったのだ。テイラーメイドを生きる人と、その圏外に飛び出す人の二極化はこれからどんどん進んでいくのだろう。
そんな歩き旅は、僕にまた新しい発見を与えてくれた。僕は走ることの素晴らしさに気づいてしまったのだ。これだから旅は美しい。そしてその美しさは、足を使えば使うほどに解像度が増していくように思えるのは、多分主観でもなんでもないのだと思う。
