
【SLAM DUNK GI】36話「藤真健司の不思議な感情」
zizanion(ジザ二オン) 古代ギリシャ語で雑草を意味する。
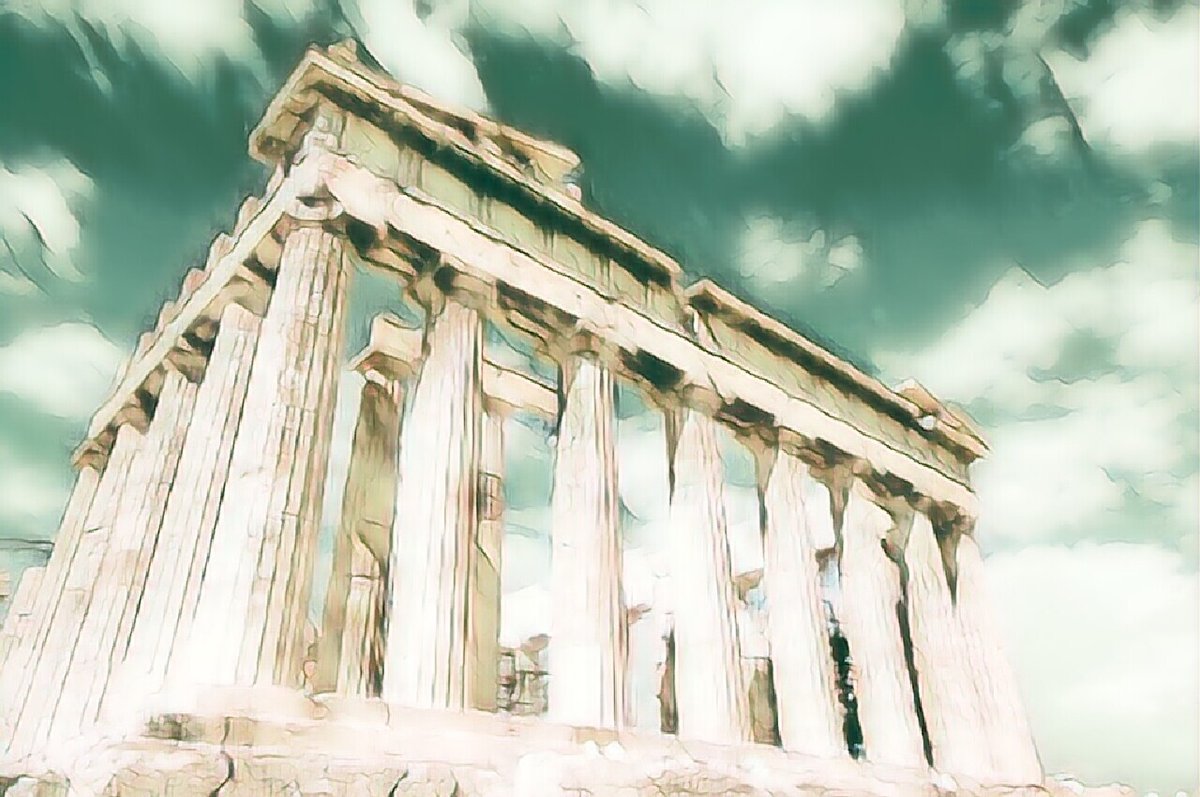
「ジザ二オン、、藤真、、、まさか。」花形
「ああ その通りだ。俺はストリートバスケのトップを獲るべく、ジザ二オンというチームに所属している。」藤真
「そうなんだな、、、、。確かお前にはJBAのチームからもオファーもあったんじゃ?」花形
「まぁな。花形 さっき人生何が起こるか予想が付かないものだなって言ったよな? 俺の話もしていいか?」藤真
「ああ もちろんだ。」花形
藤真健司にとって予想がつかなかった出来事とは?
「神奈川で俺達世代、、いや全国でといっても大袈裟じゃないだろう。」
「最強は牧紳一だ。それはお前も認めるだろ?」藤真

「ああ 俺達は最後まで勝てなかった。」花形
牧紳一、常勝軍団、海南大付属で当時17年連続インターハイ出場を決める。
同年代で同じ神奈川でひしめきあう牧と藤真は1年時からスタメンを勝ち取った。

その後、牧、藤真2強時代を築いたが、
ただ一度も翔陽は海南に勝てなかった。
藤真健司は牧紳一に勝てなかったと形容されることもしばしばあった。
帝王、牧と言われるが所以である。
一見、華やかな道を歩いてきたかに思える二人だが、
その道は実に対照的だったのである。
その関係は奇しくも大学時代も続いた。
そして大学になっても帝王、牧は健在だった。
大学3年時、二人の対決。牧は藤真を退けた。
「牧 お前、あいつの同級生だろ?国体ではチームメートだろ?何かいってやれよ(笑)」牧チームメート
「先輩、、、。茶化さないで下さい。」牧
「勝者が敗者にかける言葉なんてないですよ。」牧
試合終了後、牧が藤真に声をかけることはなかった。いや正確に言うとかけなくなったのだ。
事実、牧は陵南戦後、仙道彰に声をかけている。

藤真との対戦が積み重なる度、勝者と敗者のその重みは変化していった。
「でもな、花形。俺は牧のことを憎いなんて思わなかった。試合が終われば普通に話すし、こうやって街で出会ったたら声もかけるし、牧からもな。一緒に飲みに行ったことだってあるんだぜ(笑)」藤真
「へー意外だな。」花形
「牧のことを嫌いになんてならなかった。リスペクトしてたよ。あいつは孤高だが、そのプレッシャーに常に打ち勝っていったんだ。」藤真
さらに1年後、大学4年時、二人は対決した。そして牧は勝ち続けた。

「俺は高校、大学と最後まで勝てなかった。もちろん悔しかったよ。」藤真
「しかし勝負は終わってないはずだ。」花形
「牧のことを心底、リスペクトし、素直にすごいと思った。その時、不思議な感覚に陥ったんだ。」藤真
「牧紳一の価値を俺がさらにあげてやる。」
「ずっと戦ってきた俺が証明してやる。」
「牧・藤真時代は終わっていない。」
「それでJBAリーグを断ったってことか!?」花形
「ああ ストリートバスケ界でトップになる。それが俺にとっても牧にとっても価値をあげることになるんだってな。」
「かっこつけすぎか?」藤真
「別の道でトップになることで牧の価値もさらにあがるということか。」花形
「まぁな。それに牧との比較で俺は器用にこなせる。シュートレンジもドリブルもコートビジョンも、
より判断が早いストリートバスケに活かせると考えた。」藤真

花形は藤真が陥った不思議な感覚に理解をしめした。
それは自身がまた代理人となり選手の価値を引き上げる役目とリンクしたからだろう。
「zizanion(ジザ二オン) 古代ギリシャ語で雑草だったな。」花形
「はは(笑) さすがは翔陽ナンバーワンの頭脳だな。」藤真
「雑草。華があるお前には一見、似つかわしくない言葉だが、そのものなんだよな。」花形
「ああ 俺はエリートなんかじゃないさ。」藤真
「ジザ二オン、、、、。さぞかしいいチームなのだろうよ?」花形
「ああ。」藤真
「そう言えばよく知ってる奴と一緒にプレーしてるよ。」藤真

「陵南の 福田吉兆だ。」
「なんと!?、、、、運命のいたずらってやつ、、、だな。」花形
花形は桜木以下、桜木軍団、宮城リョータと時間を過ごすことが増えた。
当然、宮城リョータと福田吉兆の公園での再会のことも話を聞いていたのである。
