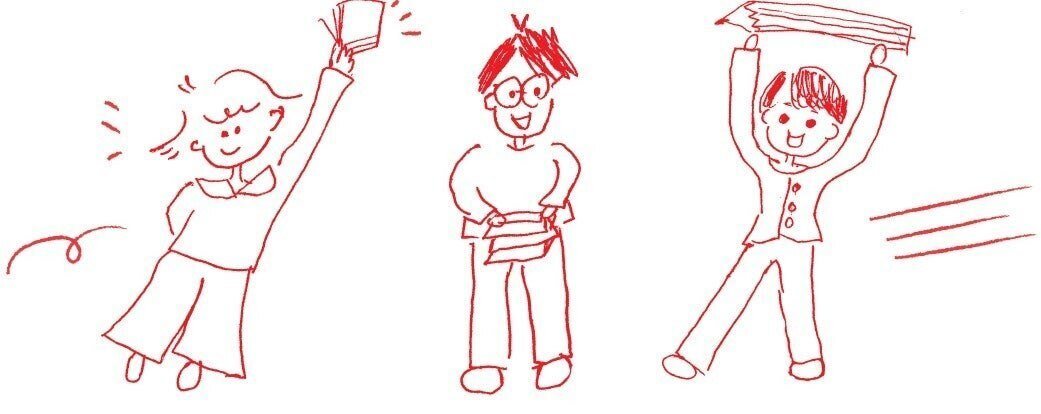図書館流通センター(TRC)に潜入! 前編
「本をめぐる社会科見学!」について
本がみなさんの手元に届くまでの道のりには様々な現場があり、そこにはたくさんの人による仕事があります。どれも意外と知られていないものばかり。そんな本のまわりの現場に突撃取材し、レポートをするのが、この「本をめぐる社会科見学」です。
取材をするのは作家・作詞家としてご活躍の高橋久美子さん。本を愛する高橋さんが本を愛する人たちのお仕事について、まっすぐ、丁寧に伝えます。
みなさんも一緒にまだ知らない”本の現場”を覗いてみませんか?
本のことがもっと好きになるきっかけになればうれしいです!
撮影・書き起こし:編集部
記念すべき第1回目は、いつもお世話になっている図書館についてです。
あの大量の本が、どこからやってきてどのように貸し出し可能になるのかを
潜入レポートします。
図書館に配本している本をまとめている場所だよ、と聞いていたので、古民家っぽいのを想像してしまっていた。ダンボールを広げてシールを貼ったりしているかな、ひょっとしたら私も荷詰めくらいならお手伝いできるかなあ、なんて。
同行のスタッフさんに「ここです」と言われ見上げた私は目を丸くした。

で、ででで、でか!
いち、に、さん、し……10階以上あるではないか。
出迎えてくださった仕入部の松村さんが、「もっと小さな家を想像していたでしょう?」と笑った。見学に訪れた人は、皆私と同じ反応をするようなのだ。
ここから約3時間に渡るTRCさんの見学ツアーをさせてもらい、この大きさが必要だということがよくよく理解できた。
子供から大人までみんなに開かれた図書館を目指すTRCさんのレポートです。
どんな図書館に行きたい?

1階には、横幅20メートルはある壁面まるごと本棚になったラウンジがあり自由に本を読むこともできる。図書館というよりカフェやホテルのラウンジのような開放感、永遠に読んでいられそう。TRCでは、図書館を建てるときの設計や、専用機器の導入などのコンサルもされているそう。なるほど、だからこんなに大きいのか。

最新のシステムの説明をしていただく中で、アナログな私が最も驚いたのが、ICタグと、それを読み取る機械だ。従来は、図書館司書さんが一冊一冊バーコードを読んで貸し出しチェックをするけれど、ICタグだと本を並べるだけで機械が一気に読み取ってくれるので司書さんを通さずとも、自動貸し出しが可能になる。
松村さん:「この棚は予約者にメールが飛んで自動貸し出し機で借りられるようになっています。5冊10冊になると司書さんがバーコードを読むのが大変ですが、それをしないで持ち帰ってもらえます。あと、予約をした本がどんな本かを誰にも悟られずに借りられる。私がダイエットの本を予約すると、”あの人ダイエットの本借りてる“と思われるわけですよ。笑」
高橋:「確かに。近所に住んでいたり、顔見知りだったりしますからね。個人の思想みたいなのも守られるんですね。」
松村さん:「あと大きいのは蔵書点検ですね。蔵書点検って毎回バーコードをピピピピって読んでいくので図書整理期間で2週間ぐらい休むのですが、その期間を本当に短くできるんです。 ICタグだと、こういうアンテナみたいなのでガ―って読むので、1日で何十万冊って読めます。」
高橋:「1日で何十万冊!? なんてことだ!それまでは司書さんたちが全部読んでたってことですか?」
松村さん:「はい、普段の蔵書点検はバーコードリーダーを持って一冊一冊読んでいく。それを、図書館のパソコンの中に入ってるデータの中から見つけていって、足りない本を探すという……。」
高橋:「大変ですね……。」
松村さん:「本がない!って探して、最終的に統計を出すんです。図書整理期間で10日とか2週間くらい休館になるのですが、この時間も短くでき、司書さんの負担も省けます。」
システム化と聞くと冷たいイメージだったけど、図書館の蔵書や利用者数も増えている今は、逆に司書さんとの必要なコミュニケーションを取るためにもありがたいシステムなんだなあと思った。地方の図書館から見学に来る方も多いようで、近隣の連動した図書館も案内してもらえるんだそうですよ。
1日300冊の見本をデータ化していく世界……
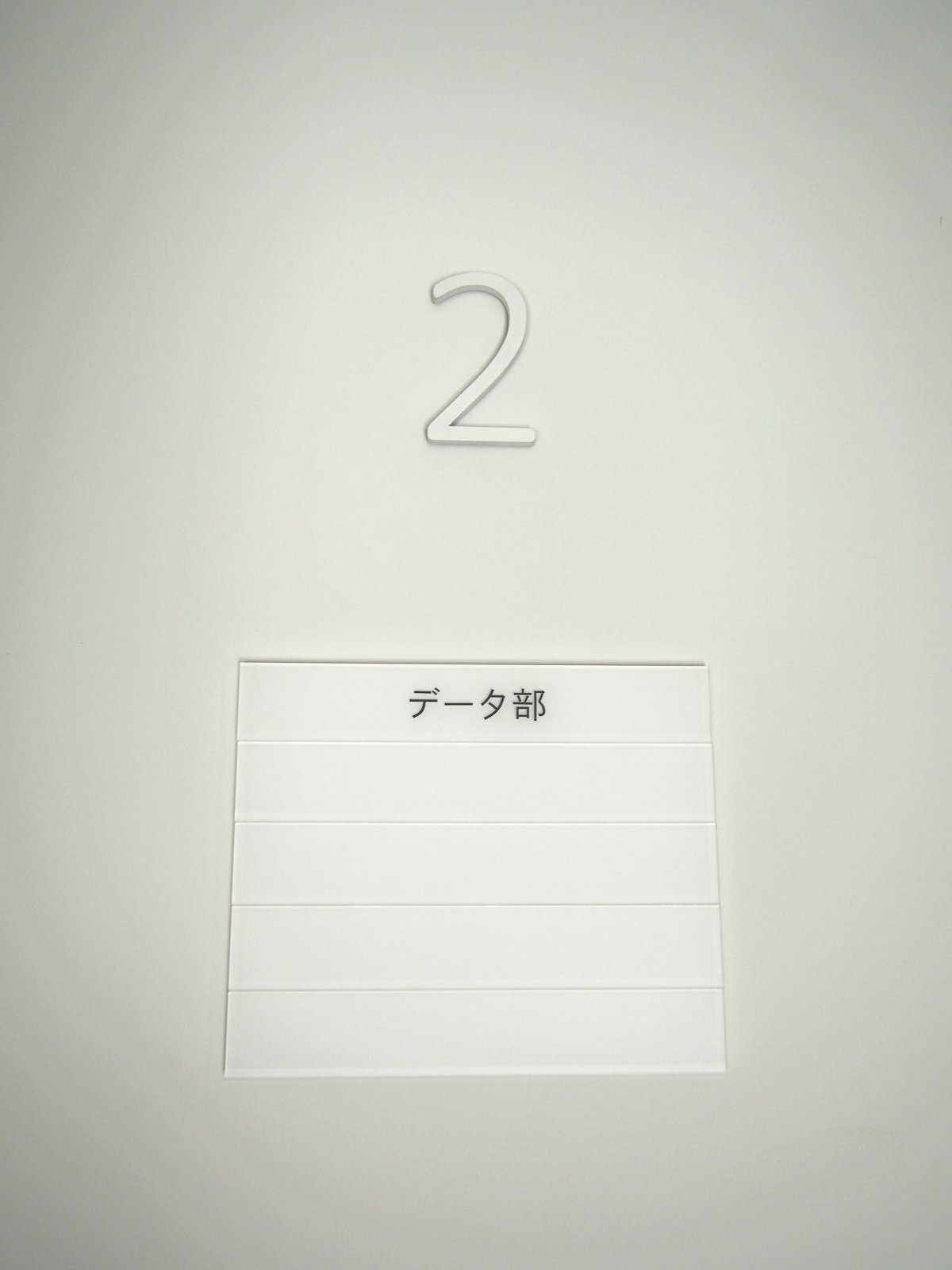
【データ部】
①新刊班
さあて、次はいよいよTRCの本丸であるデータ部におじゃまします。
ガチャリとドアを開けると、スタッフさんがずらーっと並んでデスクワークされていて、私はたじろいでしまった。その数、2階と3階を合わせると総勢100名はいるだろう。お邪魔させていただいた時はみなさん静かにそれぞれの机のパソコンに向かっている。

ここは、いわゆる図書カードを機械で読めるようにデータ化したもの(TRC MARC)をつくる部署である。ここでは松村さんに変わってデータ部の中村さんが案内してくださった。

中村さん:「1日だいたい300冊くらいの見本が来まして……。」
高橋:「300!」
中村さん:「そのうち個人向けの学習ドリルですとかを除くと、図書館向けの新刊書は200冊くらいです。それらのデータを作成しています。」
まだ本屋さんに並ぶ前の本が、朝と夕を合わせて6箱強運ばれてくるそうだ。担当者さんが、箱から自分のデスクに本を持ち帰って、一冊一冊基本のデータ入力をされていた。1階ではあれだけデジタル化の導入について聞いていたので、このアナログすぎる作業に私達は面食らってしまった。
私達がスムーズに本を借りるために、水面下では地道な作業が日夜繰り広げられているのだ。

企業秘密なのでドキドキしました。
中村さん:「まずは最初にISBN、タイトルはもちろん、価格などの基本情報を入れていきます。10名の担当なんで、1人約30冊ですね。図書館に並ばないものも登録はします。」
高橋:「パソコンがなかった私が小学生くらいの時はどうしてたんですか? 」
松村さん:「その頃はまだパソコン自体がそんなに発展してなかったから、司書さんが各自で本屋さんに本を直接買いに行って、図書館の事務所で目録規則に則って、書名、著者など全部自分たちで図書カードを書き起こしていたんです。」
高橋:「自分たちで書いてたんですね。しかも本屋さんに行ってたんですね。」
松村さん:「昔の新刊は今と違って活版印刷でやっていたでしょう。年間で多くても2万冊とかだったんです。それが、1980年代後半にDTPといって、パソコンの中でポンポン本を作れるようになったので、最多で8万2,000冊くらいにまで急激に増えたんですよ。そうすると、もう司書さんたちだけではどうしようもできなくなってしまって。」
新刊点数が4倍近くになっていたんですね。うーむ、物書きとしては頭の痛い話。でも読者としては選ぶ楽しみが増えますね。昔に比べると本の内容を表すキーワードが細分化され、いろんなキーワードで本が探せるようになっていたり、コンピューターの進化でタイトルの長さもいくらでも入るようになっている。映画「耳をすませば」のような図書カードを通してのやりとりにも憧れたけど、本との出会いの幅はぐんと広がっているんですね。
一冊の本が図書館に届くまでに関わる
人の手の数

②写真班
データ部の一番奥に見える黒いカーテンに囲まれた空間は、もしや暗室ではないか!?
まさか、1日300冊という新刊の書影をここで撮影して、新刊案内に掲載するということなのだろうか? 男性スタッフが2名出てきてくださった。

鈴木さん:「表紙画像とデータにリンクを付けて、読み取りが終わるとフォルダの番号が振られております。それから作業上の優先度に分けて、こちらでフォトショップを使って編集作業をしていきます。表紙が薄かったりすると変色したりしていますので、そこをフォトショップで直してあげて、実物に近いようにきれいに仕上げてあげます。ある程度まで溜まったら、夕方に画像をファイルにまとめて、印刷会社に渡します。」
高橋:「1日で何冊くらい撮影するんですか?」
鈴木さん:「300冊から350冊くらい、多い時だと400冊を超えますかね。まあ、ピークだと500近く行く時も。繁忙期だったり、休み明けに溜まってたりする時は多いです。(資料を見ながら)あとお盆明けが1,441! これは私も驚きました。」

暗室の帝王のようでした。
1,000を超える日もあって、そういうときは数日がかりになることもあるそうだ。1冊の本が図書館に並ぶまでに、こんなにたくさんの人の手をわたっているのだと思うと、本を世に出すというのが改めて特別なことなのだなと背筋の伸びる思いがした。
子どもたちが
たくさんの本に出会えるための“学習件名”

③内容・目次班
中村さん:「キーワードの作成で、小説ですとそれぞれの作品のタイトルでも検索したいじゃないですか? 目次ですとか内容ですとか。」
高橋:「え、目次でも?」
中村さん:「はい。そういったデータも此処の部署で作っています。」
④分類件名班
さあ、どんどんディープになっていきます。
次は一冊一冊の内容を確認してNDC(日本十進分類法)に則って分類記号を付与する部署です。検索用の言葉、キーワードも9つまで設けることができ、タイトルや著者名以外からも目的の本にたどり着けるようになっているんですね。

子どもたち、思う存分探求せよ!!
TRCが特に力を入れているのが児童書で、子どもが探したい本のキーワードと図書のキーワードをリンクさせるように設定している。さらに、調べやすくするために学習件名なるものを付与しているそうだ。例えば、カブトムシについて調べたいときに、「カブトムシ」と入れると、通常はそのタイトルの本だけがヒットするけれど、TRCでは「虫の生態」とか「昆虫図鑑」というタイトルの本の中でカブトムシについて書かれている部分についても同時に検索できる。1ページ以上にわたる内容は項目とページ数を付与し、ヒットするように作られているそうだ。子どもが検索しやすいように、本と出会えるように配慮されているのだなあ。担当さんに見せてもらった「昆虫変態図鑑」は学習件名が75項目もあり、1冊入力するのに1時間を要したそうだ!
スタッフの方と話をさせてもらうと、みなさん本への熱い眼差しを持っていて、本好きによってデータ整理されていっているのが印象的だった。

ご担当者さん:「高橋さんは同姓同名の著者の方と会ったことがありますか?」
高橋:「同姓同名の人にならあるけれど、著者となるとどうでしょう……。」
ご担当者さん:「現在9名、本をお書きになっている著者がいるようです。」
高橋:「ええ!9人も!」
ということで、中編では、さらに複雑な分類分けに突入しますよ!
図書館流通センター(TRC)に潜入! 中編
https://note.com/twovirgins/n/n0899b36db516
高橋久美子
1982年、愛媛県生まれ。
作家・作詞家。 エッセイ、詩、小説の執筆から翻訳、アーティストへの歌詞提供など幅広く活躍。 主な著書に小説集『ぐるり』(筑摩書房)、エッセイ集『暮らしっく』(扶桑社)、『その農地、私が買います』(ミシマ社)、『旅を栖とす』(KADOKAWA)、『一生のお願い』(筑摩書房)など。
弊社から出版された絵本『パパといっしょ』、『にんぎょのルーシー』では翻訳を担当している。
公式HP「んふふのふ」:http://takahashikumiko.com/top
📖感想、ご要望など自由にお寄せください!