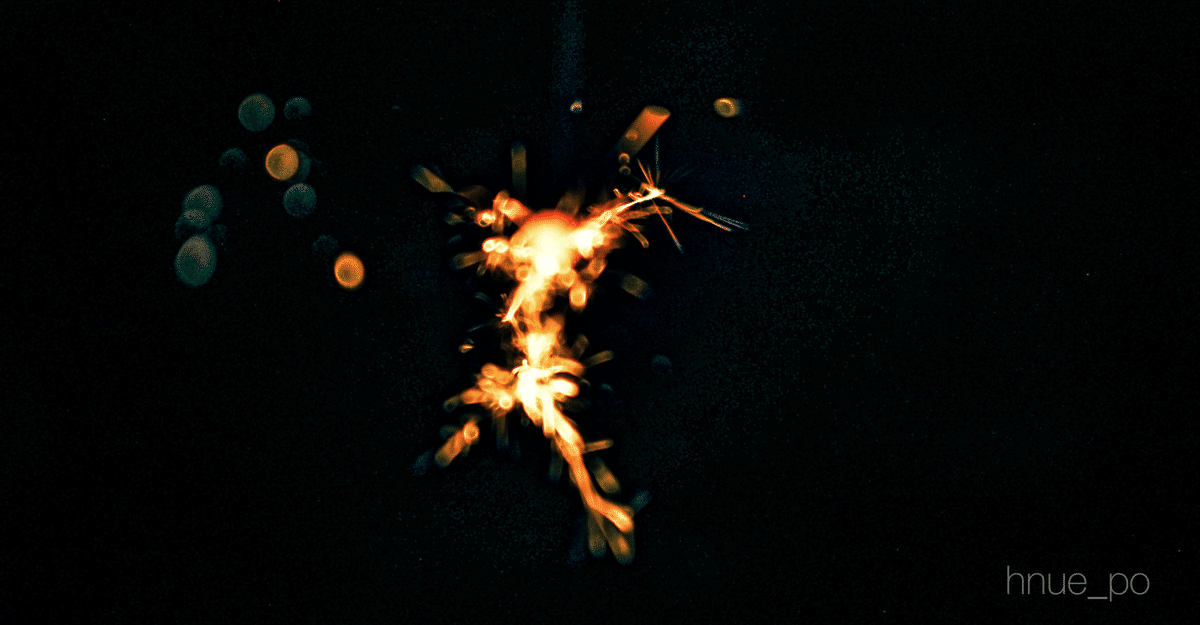
「エステティック」「美学・美術」という学問の成立まで
日本の「美術」や「美学」という言葉は、明治期の19世紀後半に西洋文化を輸入するその過程で生まれた言葉である。西洋の概念に日本の現状を当てはめ、西洋のエステティックに相当するものを作り出すべく、西洋語の翻訳として発明されたのが「美術」や「美学」である。
中江兆民(なかえちょうみん)は文部省の命により、フランスのユージェーヌ・ヴェロンの主著「L'Esthétique」を「維氏美学(いしびがく)」と題し、上下二冊、明治16年から17年にかけて刊行して、エステティックを「美学」と訳した当人でもあった。このときエステティックの訳語はいくつか試されていた。西周(にしあまね)はエステティック=美妙学(びみょうがく)が哲学の一分野であると論を展開した。美妙学以前にも「善美学」「佳趣論」といった訳を試みている。「善美学」には古代ギリシャの善と美は一致するという考え、「佳趣論(かしゅろん)」は、近代の美を判定する能力としての趣味を問う姿勢を説いている。
明治40年には哲学の専門的用語をまとめた「哲学字彙(てつがくじい)」が出版されており、エステティックは「美妙学」と記載されている。
西洋のエステティックの受容について大きな役割を担った人物に森鷗外がいる。明治時代の小説家として知られているが、ドイツ留学などで画家の友人もおり、帰国後には文学論、芸術論の分野で残したものは多く、西洋の「美学」の輸入に関して重要な論考を残している。鷗外はその中で、エステティックを「審美学」「審美論」と訳した。美しさと醜さを見分ける審美眼の考えから、「審美学」は美醜(びしゅう)を判別するための学問であると説いた。
実は「審美学」という言葉について、鷗外以前にフェロノサが明治13年から東京大学での西洋哲学の授業の中で、「道義学及審美学」という講義を行っていたことがわかっている。鷗外が最初にこの言葉を用いたのは、明治23年で自ら主宰(しゅさい)する評論雑誌「しがらみ草紙」に掲載したときである。この頃鷗外は東京美術学校で美術解剖学も講義しており、明治25年からは慶應義塾大学の「審美学」の講師もしており、同時にハルトマンの著書の一部を「審美論」として「しがらみ草紙」で訳出連載していた。
明治20年代は「美術」「美学」をめぐって、学校教育の場でも評論の場でも学問的な翻訳の場でも、鷗外は大活躍していたが、あくまで「審美学(論)」という訳語を使っていて、それは明治30年代半ばになっても変わらなかった。
エステティックは、人間がどのように美しさ判定するかを問う学問であって、人間の経験や感覚を超えたところに美しさの本質を求めるようなものではない、というのが鷗外の見解だったのかもしれない。
文豪、夏目漱石も美学の普及と関わっている。よく知られた「吾輩は猫である」のユニークな登場人物の一人に、迷亭(めいてい)という美学者がいる。迷亭が登場する第二話が雑誌「ホトトギス」で発表されたのは、明治38年のこと。迷亭のモデルだったかもしれないとされる夏目漱石の帝国大学大学院時代の友人、小屋保治(おややすじ)である。彼は明治33年に東京帝国大学文科大学哲学科の初の美学講座の教授になっていた。この国立の最高教育機関では、明治25年に「審美学」という講座名を「美学」に称し、翌26年には美学講座を設けていた。先に見た中江兆民の訳した「維氏美学」は文部省の命だったことを考えると、国レベルで採用されたのが「美学」という名称の理由と考えられる。
「美妙学」「善美学」「佳趣論」「美学」「審美学」といったいくつかの訳語が明治の初めから30年頃まで試されてきた。最終的に「美学」に落ち着いたのは、「美術」という言葉が定着していった頃に平行している。
日本への輸入のころ、西洋のエステティックが主要としていたテーマは、「美とはどういうものか、それを決めるのは何か、広い意味での美にはどのようなものがあるか、芸術とは何であり、美とはどのように関わるのか」ということ。つまり「美学」という名称は当時のエステティックという学の内容を簡潔に捉えていたものだといえるのではないだろうか。
いただいたサポートはHITOMOJIのコンセプトである“想い出の一文字を形に”を実現する為の活動資金として活用致します。
