
過去25年の流行語大賞が個人的に納得かどうか考えてみた。
こんにちは。
暇人の極み、トマトくんです。
あまりにもnoteに書くことが無さすぎるので、今回は「ユーキャン 新語・流行語大賞」について好き放題書いてみました。
元々は「これまでのアカデミー作品賞は納得か!? 個人的な好みだけで検証してみた。」というシリーズでやっていたことなので、もし流行語大賞の方が気に入ってもらえたら、そちらも併せて読んでもらえると嬉しいです。
2000年『おっはー』『IT革命』

記念すべき21世紀最初の流行語大賞は「おっはー」と「IT革命」だった。当時のことを何も知らない人間(特に10代)にとっては「おっはー」のような当たり前に使用する言葉が流行語大賞を受賞するというのも変な話だろう。そもそも「おっはー」と言うのは、週5で放送していた子供向け番組『おはスタ』で使用されていた恒例の当時の挨拶である。世代の人ならば、MCだった山寺宏一の音声で再生される人も多いだろう。
その中のコーナーのひとつで、元SMAPの香取慎吾が扮するキャラクター「慎吾ママ」というものがあり、慎吾ママも同様に「おっはー」を挨拶として使っていた。その後、少しづつ慎吾ママの人気が出てくると共に『おはスタ』の枠を飛び出していくことになる。
まずSMAPの冠番組『サタ★スマ』で、慎吾ママのコーナー「慎吾ママのこっそり朝ご飯」が作られた。慎吾ママが一般家庭を訪れ、母親の代わりに、冷蔵庫内にあるもので朝ご飯を作るというもの。『サタ★スマ』は、視聴率20%越えの高視聴率番組であったため、これによって「おっはー」は瞬く間に子供が使う挨拶から老若男女に愛される挨拶へと変わっていった。
また香取慎吾が慎吾ママ名義で発売した楽曲『慎吾ママのおはロック』は累計売上130万枚以上というミリオンセラーを達成し、誰もが「慎吾ママブーム」の到来を感じたであろう。実のところ、この「おっはー」の大賞受賞は、言葉そのものよりも楽曲の大ヒットに向けて贈られたものという認識の方が正しい。近年で言うところの「うっせえわ」や「ありのままで」などがまさにそれである。慎吾ママのポップなキャラクターと、一度聞いてしまうと頭から離れないキャッチーな音楽、「おっはー」という言葉の使いやすさ。納得の大賞受賞である。
一方の「IT革命」も、インターネットやSNSという言葉が市民権を得てしまった今となっては聞き慣れない言葉だろう。そもそも「IT革命」が大賞を受賞する5年前、1995年には既に「インターネット」という言葉がトップテン入りを果たしている。ITとは情報技術(Information Technology)の略なので、インターネットそのものとは全く異なる言葉なのだが、5年経って今更革命とはどういうことなんだ、という話である。しかし、調べてみるとあっさり答えが書かれていた。
1995年時点でインターネット利用者は全世界で約4000万人程度であった。多いには多いけれど、今と比べると決してそうとは言えない。1998年にはAppleから初代「iMac」が発売されて一躍ヒット商品となり、1999年から日本最大級の電子掲示板サイト「2ちゃんねる」が開設されたりなど、2000年から突如インターネット利用者が急増し、経済発展・成長が見込まることになった。また、1998年頃からアメリカではインターネットの株価が急激に上昇する「ITバブル」というものが起きており、その波が日本にも到来したと言える。そして生まれた言葉が「IT革命」。ニュースや新聞でも頻繁に利用された言葉だし、こちらも納得も納得の受賞である。
ただ翌年2001年に起きたアメリカ同時多発テロをきっかけに、IT関係の株が著しく下がってしまい「ITバブル崩壊」が起きてしまったことも一応伝えておきたい。「おっはー」と「IT革命」、どちらかひとつを選べと言われたら、僕は断然「おっはー」を選ぶ。単純に使いやすいという事もあるが、視聴率やCDの売上など数字として目に見えて流行っていたことも好感触だ。
ちなみに朝日新聞社が提供する現代用語事典『知恵蔵』が開催していた「Word of the Year(ワード・オブ・ザ・イヤー)」では、「IT」が大賞受賞している。2位が「おっはー」、3位が「ミレニアム」である。選考委員特別賞には田島寧子さんがシドニーオリンピック400m個人メドレーで銀メダルを獲得した際に発した「めっちゃくやしい!」であった。
というわけで、「おっはー」と「IT革命」の大賞受賞は納得という結果になりました。
2001年『小泉語録(米百俵・聖域なき構造改革・恐れず怯まず捉われず・骨太の方針・ワイドショー内閣・改革の「痛み」)』

2000年代初頭の流行語を語る上で欠かせない存在、それが小泉純一郎である。2001年4月に第87代総理大臣となってからというもの、彼の支持率と注目度は凄まじく、何を発言してもワイドショーで取り沙汰されていた。まさに「流行語の生みの親」であった。
まず小泉語録として共に受賞した6つの言葉をそれぞれ解説する。一つ目は「聖域なき改革」である。これは小泉純一郎が掲げていた経済政策スローガンのことで、本人たちは「新世紀維新」とも称しており、そちらの方でも知られている。そもそもこの時期の小泉純一郎は「官から民へ」や「改革なくして成長なし」など、ワンフレーズ政治で「構造改革」路線を貫いており、「聖域なき改革」はその代表的な言葉であった。
次に「米百俵」だが、こちらは小泉純一郎が所信表明演説の締めくくりとして「米百俵の精神」の故事を引用したことから来ている。「聖域なき構造改革」を断行するため「今の痛みに耐えて、明日をよくしようという米百俵の精神こそ、改革を進めようとする今日の我々に必要ではないでしょうか」と述べたことで脚光を浴びた。同様に「恐れず怯まず捉われず」も所信表明演説で使われた言葉である。
「改革の痛み」も「今は苦しいが、構造改革を行えば、いつかはよくなる。だから、国民には構造改革による『痛み』には絶えてもらって、何があっても改革を断行する」という姿勢から由来している。ここまでは一応納得である。
しかし、問題は後のふたつだ。「骨太の方針」は、2001年6月の経済財政諮問会議にて立案された「経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」の際に使われた言葉だ。しかし、この方針は竹中平蔵が立案者である故にそちらのイメージが強い。「ワイドショー内閣」に関しては、小泉純一郎の言葉ですらない。とにかくこの中に混じっている違和感がすごい。
これらが小泉語録に含まれるのなら小泉純一郎が推進する「聖域なき改革」に抵抗する勢力「抵抗勢力」や、小泉内閣発足とともに入閣した塩川正十郎財務大臣のニックネーム「塩爺」も小泉語録として扱っていいだろう。そもそもこの年は、上記の「抵抗勢力」や「塩爺」の他にも、インターネットを使った政治活動を指す「e‐ポリティックス」がトップテン入りするなど、政治絡みの言葉が多数話題になった1年でもあった。小泉語録の大賞受賞は、言葉そのものよりも、政治が話題になった《時代》を象徴する人物であるが故に贈られた大賞とも取れる。
個人的には自民党総裁選にて発言した「自民党をぶち壊す!」発言や、首相就任直後の夏場所にて、前日の負傷を押して出場し、22回目の幕内優勝を勝ち取った横綱貴乃花光司に対して送った「痛みに耐えてよく頑張った! 感動した!おめでとう!」から由来する「感動した!」の方がインパクトが強くて好きだ。小泉語録の中で未だに生き残っている言葉と言っても過言ではないのに、トップテン入りすらしていないなんて不可解にも程がある。小泉純一郎本人ですら「感動した!」が1番のお気に入りで、これが選ばれなかったことに驚いたらしい。
「小泉語録」自体は納得だけど、完全に審査員たちの好みで選ばれた6個なのが心の底から気に食わない。若干不満が残る受賞である。僕なら素直にこの年は「感動した!」を選ぶ。また知恵蔵も「ショー・ザ・フラッグ」と並んで「感動した!」をWord of the Yearの選考委員特別賞に選んでいる。やはり「感動した!」が妥当な判断だと思う。またWord of the Yearの大賞は「同時多発テロ」であった。「流行語」には選べないが、Word of the Yearとして選ぶには確かにこれは適切だろう。
というわけで、「小泉語録」の受賞自体は納得だが、選ばれた言葉が不服という結果になりました。
2002年『タマちゃん』『W杯(中津江村)』

来ました。みんな大好き「タマちゃん」。タマちゃんとは、2002年8月に多摩川に現れたオスのアゴヒゲアザラシのこと。タマちゃん見たさに大勢の見物客が多摩川に詰めかけ、様々なグッズや企画が展開された。マスコミでは「タマちゃんフィーバー」と称されるほどの人気を博し、このフィーバーはタマちゃんが完全に姿を消した2004年前半まで続いた。その後も「タマちゃんは海に還ったのかどうか」「どこへ行ったのかどうか」という議論でしばらく持ち切りになっていた。
2002年の9月には、宮城県歌津町の伊里前川にワモンアザラシの子どもが現れて「ウタちゃん」と名付けられたり、2023年の1月には大阪湾の淀川河口で発見されたマッコウクジラに「淀ちゃん」と名付けられるなど、20年以上経った今でもタマちゃんフィーバーの余波が残っているほどである。消えてしまってもなお、国民に愛されるタマちゃん。最高すぎる。
また最近は、オランダの野生アザラシ保護センターが行うYouTubeライブ、通称『アザラシ幼稚園』が話題になっているが、このライブが日本人に刺さったのも、少なからずタマちゃんの影響はあると思っている。日本人はアザラシを愛することを遺伝子レベルで刻まれているのだ。
最近の「村神様」や「ひふみん」「フワちゃん」など、名前やあだ名が流行語大賞を受賞することに懐疑的に思っている層も一部にはいるのだが、正直タマちゃんレベルのブームになると誰も文句を言えないだろう。ちなみにこの年は、松井秀喜の愛称「GODZILLA」も特別賞を受賞している。ってか特別賞ってなに…?
そしてもうひとつの大賞は、世界中が熱狂した「W杯」。こちらは「2002 FIFAワールドカップ」の略称で、2002年5月31日から6月30日にかけて日本と韓国で共催された17回目の大会のことである。日本で開催していたし、単純に盛り上がったのも分かるけれど、17回目にして今更なぜ流行語大賞受賞…?と疑問に思う人も多いだろう。その秘密はカギカッコの中に書かれている「中津江村」に関係している。
説明しよう!中津江村とは大分県日田市にある一部の地域のことで、人口1382人、世帯数494という典型的過疎地域である。W杯の際に経済効果を狙って誘致を行った結果、アフリカのカメルーン代表のキャンプ地に選ばれたのだ。しかし、カメルーン選手団の中津江村入りが予定より5日遅れたことや、『ニュースステーション』にてメインキャスターである久米宏が「いちばん小さな自治体のキャンプ地」として着目したこと、そして当時の村長である坂本休さんが様々なメディアで取り上げられたことなど、W杯をきっかけに中津江村は全国的に知れ渡ることとなった。
ただ中津江村での受賞ならまだ分かるのだが、なぜW杯としての受賞にしてしまったのか…正直、理解不能である。もちろん、ベストテンに「ベッカム様」が入っているようにベッカムブームが起こったり、そもそもサッカーが白熱していたのは分かるけどさ。W杯が終了した7月以降はほとんどW杯関連の話題は聞かなくなったし、一時的なブームでしかなく、W杯および中津江村はこの一年を象徴する言葉としてはかなり弱いと思う。
流行語かどうかは置いておいて、この年最も耳にした言葉は「拉致」だろう。年がら年中「北朝鮮工作員による日本人拉致問題」がワイドショーを賑わせたいた。中でも9月17日に平壌で行われた小泉・金会談の直前に、北朝鮮側が拉致被害者の安否にかかわるリストを提示し、それまで否定していた「拉致」を認めたことで言葉の勢いは加速した。5人の生存者と、8人の死亡者が発表され、10月15日には生存者の5名が日本への一時帰国を果たした。
またW杯の際にも、日本と韓国の共催という理由で拉致の心配がなされていた。「拉致」は不安を煽るマイナスな言葉なので、流行語には相応しくないという意見も分かる。しかし、この年を象徴する言葉を選ぶなら「拉致」が一番相応しいだろう。「タマちゃん」も「W杯(中津江村)」も、言葉というよりも語句なのだ。流行ったモノ・コトではあるが、流行った言葉ではない(タマちゃんは現象の名前と見れば納得)。
とは言ってもだ。Word of the Yearは「拉致」が受賞したのだが、2位には「ワールドカップ」が、選考委員特別賞には「タマちゃん」と「ベッカム様」が選ばれている。単純に一番流行ったという理由で選ぶなら、個人的には「タマちゃん」が妥当だろうと思う。
というわけで、「タマちゃん」の大賞受賞は納得、「W杯(中津江村)」の大賞受賞は不服という結果になりました。
2003年『毒まんじゅう』『なんでだろう〜』『マニフェスト』

なんということでしょう。3つも大賞を受賞しているじゃありませんか。しかもそのうちの2つは政治関係の言葉だ。世間の心に残る言葉を使わなければならない政界はやはり流行語の分野では強い。
まず「毒まんじゅう」とは、2003年9月に政界引退を決意した野中広務が発した言葉で、橋本派の会長代理であった村岡兼造が自派の藤井孝男ではなく森派の小泉純一郎の支持に回ったことを非難する際に「毒まんじゅうを食らったのではないか」と発言したことから由来する。政治の世界において野中さんの影響力が凄まじいのは理解しているし、流行語大賞の選考員たちが日本の政治腐敗に警鐘を鳴らしたいという意図も分かるのだが、流石にこの言葉は1ミリも流行していない。
言葉のインパクトこそあるが、そもそも使い道が無さすぎる。いつどのタイミングで「毒まんじゅうを食らったみたいだね」なんて使うんだ。元々は批判の言葉なので、言われた方も何も嬉しくない。過去には「凡人・軍人・変人」や「ブッチホン」などもゴリ押しで受賞させているし、流行語大賞が選ぶ政治関連の言葉は酷いものが多い。2015年にトップテン入りした「アベ政治を許さない」や、2016年の「保育園落ちた日本死ね」なんかは未だに語り草である。トップテンならまだしも大賞は絶対にない。
そしてもうひとつの政界ワード「マニフェスト」。日本語では「政権公約」という意味で、かつては単に「公約」と呼ばれていた。語源はラテン語の「はっきり示す」から来ており、期限や財源、数値目標、プロセスなどが明かされた具体的な公約のことを言う。
2003年の統一地方選挙にて、元三重県知事の北川正恭が「マニフェスト」の必要性を提唱したことでこの言葉が広く知られるようになる。また衆議院議員選挙で民主党が政権公約として「マニフェスト選挙」を掲げたことで、世論の関心が高くなり、大幅に獲得議席数を増やすこととなった。結局それから20年経った今でも政界でこの言葉は使われるし、流行語を超えてすっかり定着してしまった印象すらある。使い勝手も良いし、実際みんな使ってたし、「毒まんじゅう」と違いこちらの大賞受賞は納得だ。
そして最後に「なんでだろう」。ニチエンプロダクション所属のお笑いコンビ「テツandトモ」の代表ネタで、「なんでだろ〜」と歌いながら日常の何気ない疑問について繰り広げる漫談で大ブレイクを果たした。「昆布が海の中で出汁が出ないのなんでだろう」とか今聞いても面白すぎる。
この年は様々な企業とタイアップ効果し、大人から子供まで誰もが歌と売り付けを完コピできるほどの人気だった。2003年と言えば丁度『エンタの神様』が始まった年でもあり、お笑いの枠ではダンディ坂野の「ゲッツ!」や、はなわの「SAGA佐賀」なども流行していた。比較するものでもないが、やはりショートネタブームの先駆けとなり、未だに誰もが歌えて踊れる「なんでだろう」はすごい。これまで現れた数々の一発屋芸人の中でも一線を画すネタだろう。
この年からひとつ選ぶならば、僕は迷わず「なんでだろう」を選出する。「マニフェスト」も悪くないが、言葉のみならず動きや音楽も流行ったところが好感触だ。一方の知恵蔵は「マニフェスト」の方をWord of the Yearに選んでいる。
というわけで、「なんでだろう」と「マニフェスト」の大賞受賞は納得だが、「毒まんじゅう」の大賞受賞は不服という結果になりました。
2004年『チョー気持ちいい』

常にセットで選ばれていた流行語大賞であるが、単一での大賞受賞は1997年の『失楽園(する)』以来である。「チョー気持ちいい」、もはや説明不要の言葉だと思うが、一応解説しておく。栄光の架橋で日本中が沸いた2004年アテネオリンピックにて、競泳競技・男子100m平泳ぎに出場した北島康介が金メダルを獲得した際の発した言葉である。
元を辿れば北島康介は、前回のシドニーオリンピックで日本記録を更新したにも関わらず4位に終わっており、雪辱を晴らすことに注力していた。そして今回のアテネオリンピックで、世界記録保持者のブレンダン・ハンセンを0.17秒差でおさえ、1:00.08というタイムで金メダルを獲得したのだ。未だに五輪屈指の名場面として語られる瞬間だ。そりゃチョー気持ちいいはずである。真似もしやすいし、大賞受賞は納得でしかない。知恵蔵のWord of the Yearも、大賞こそ「ヨン様」だったが、「チョー気持ちいい」を選考委員特別賞に選んでいる。ランキングでも渡辺恒雄の「たかが選手が」に続いて3位である。
しかし、この手の流行語関連は、毎回オリンピックの熱に浮かれすぎているというか、思い出補正で選んでしまう部分は少なからずある。流行ったというよりは、インパクトがあった言葉大賞と化している。同様にスポーツ関連で流行語大賞を選ぶならば、正直「気合いだー!」や「ハッスル!ハッスル!」の方がメディアではよく取り上げられていた印象だし、真似もされていた。
言葉として流行ったという意味では、2004年の小泉内閣を象徴する言葉「サプライズ」(武部勤がまさかの自民党幹事長に抜擢されたことが「サプライズ人事」と呼ばれた)や、イラクの日本人人質事件にて広まった言葉「自己責任」、流行語大賞のノミネートから漏れたことで当時物議を醸した長井秀和の決めゼリフ「間違いない」の方が適切だろう。
ただどれも「チョー気持ちいい」を越えるインパクトはない。さらっと日常会話で使用できる分、却って流行しているという感覚が薄まったのだろうか。恥ずかしながら「間違いない」は未だに使っていて、長井秀和の真似をしているとバレるかどうかのチキンレースを一人でよくしている。
というわけで、「チョー気持ちいい」の大賞受賞は納得という結果になりました。
2005年 『小泉劇場』『想定内(外)』

出た。再び小泉純一郎だ。とにかく2005年の小泉政権は凄まじかった。小泉劇場のクライマックスである「郵政選挙」が行われた年だ。2005年9月の衆議院議員選挙において、小泉純一郎は「郵政民営化」に反対する「造反組」の自民党候補者を党として公認しないばかりか、その選挙区に民営化に賛成する、「刺客」と呼ばれる対立候補まで立てたのだ。
佐賀県をはじめ、各地で大臣経験もあるようなベテラン議員が無所属になり、新顔の自民公認候補と戦うという異例の選挙戦となった。よって選挙は盛り上がり、小泉自民党が圧勝。この選挙で当選した自民党の新人議員83人は「小泉チルドレン」と呼ばれた。
また小泉チルドレンの中でも、さらに小池百合子などの女性議員を指す「くの一候補」や、杉村太蔵を指す「ヒラリーマン」、麻生太郎や福田康夫、安倍晋三を指す「ポスト小泉」など、選挙関連のワードがとにかく尽きなかった。たとえ流行語の生みの親と呼ばれようとも、ここまで来るともはや恐ろしいまである。国民の目をあの手この手で引きつける小泉首相の劇場型政治手法はメディアで「小泉劇場」と持て囃された。
時を同じくして、ライブドアの社長である堀江貴文(通称ホリエモン)も、郵政民営化反対の刺客候補として亀井静香の選挙区である旧広島6区に立候補した。ほんの数ヶ月前までニッポン放送の買収をめぐりフジテレビと争いを繰り広げており、その際に様々な媒体で「想定の範囲内」という言葉を連発していた。その他、ノミネートの段階でも「敵対的買収」や「ヒルズ族」「富裕層」などホリエモンを象徴する言葉が沢山選出されていた。2005年は小泉純一郎と堀江貴文、2人の年だったと言っても過言ではないだろう。大賞を受賞した「小泉劇場」と「想定内(外)」は地続きの流行語なのである。
まあ「想定内(外)」の受賞は想定内だ。上半期を象徴する人物だし、受賞して当然である。しかし、「小泉劇場」はと言うと…、コレジャナイ感がすごい。2001年の小泉語録のように、数々の流行語を一纏めにするのに丁度良かった言葉なので選んだとしか思えない。どう考えても「郵政民営化」や「小泉チルドレン」の方がよく耳にしたし、これを流行り言葉としていいのだろうか。
まだ「郵政民営化」をスルーするのは理解できる。小泉劇場と郵政民営化はイコールに等しい。しかし、小泉チルドレンは無視するのは(トップテンすら入らなかった)極めて不可解だ。毎日のようにワイドショーで皮肉のように扱われていたし、「○○チルドレン」という言葉自体も未だに何かを揶揄する言葉して根強く残っている。マイナスなイメージが強いから劇場の方で受賞させたのだろうか…。
もし僕がこの年からひとつ選ぶならば間違いなく「郵政民営化」を選ぶが、なるべく言葉としての流行を推薦していきたいので「想定内(外)」ということにしておこう。
ちなみに知恵蔵のWord of the Yearは「郵政民営化」で、選考委員特別賞は「想定の範囲内」となっている。やはり2005年を象徴するワードは、このふたつしかないのだ。
というわけで、「想定内(外)」の大賞受賞は納得だが、「小泉劇場」の大賞受賞はちょっとだけ不服という結果になりました。
2006年 『イナバウアー』『品格』
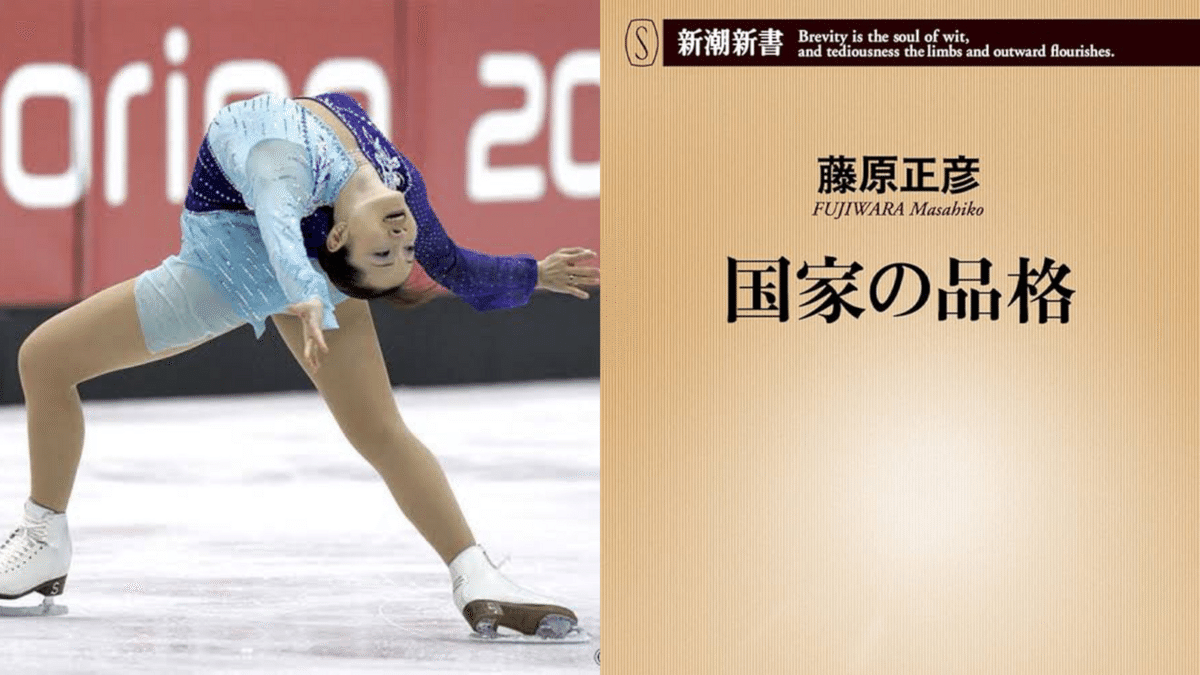
イナバウアー。すっと耳に馴染む良い言葉だ。今更説明するまでもないが、これはフィギュアスケートにおいて、足を前後に開き、爪先を180度開いて真横に滑る技のことである。(ほとんどの人は「イナバウアー」をするとき身体を後ろに反らせるが、これは全く関係がない技である。後に「レイバック・イナバウアー」という名前が付けられた)。50年代に活躍した旧西ドイツの女性フィギュアスケート選手イナ・バウアーがこの技を発明し、彼女の名前がそのままで技名になっている。
「イナバウアー」という言葉が注目されるきっかけになったのは2006年のトリノオリンピックのこと。フィギュアスケート・女子シングル競技において、イナバウアーを得意としていた荒川静香が、フリースケーティング本番でその技を披露。そのまま日本人選手唯一の金メダルを獲得して、日本中を沸かせたのだ。
何よりも奇妙なのは、イナバウアーという技は、競技では決して加点されることのない技なのだ。これによって更に技への注目度が増すきっかけとなった。そりゃトリノオリンピックで唯一の金メダルを獲得すれば、そのときに披露した得意技が広まるのも当然のことだろう。NHKアナウンサーが発した「トリノの女神は荒川静香にキスをしました」という実況もセットで話題となった。
オリンピックが終わってから年末までみんなが真似をしていた記憶がある。自分もずっと真似していた。言葉だけではなくポーズもセットで流行ったことで、目に見えて「流行」しているのが分かったのはとてもポイントが高い。
そしてもうひとつの大賞『品格』。こちらは2005年11月20日に数学者・藤原正彦の著書『国家の品格』が発端となったもの。発売以来、新書史上最速の190日で200万部を記録。現在は265万部を超えるミリオンセラーとなっている。その後、2006年には坂東眞理子の『女性の品格』が大ヒット。
他にも『会社の品格』や『日本人の品格』『自分の品格』『親の品格』『男の品格』『遊びの品格』『ヤマダ電機の品格』『英語の品格』『横綱の品格』など、『○○の品格』と冠する本が立て続けに出版され、「品格ブーム」なるものが巻き起こった。翌年ではあるものの、テレビドラマでも『ハケンの品格』が人気を博し、瞬間最高視聴率28.9%を記録した。
この1冊が様々な「品格論」に火を付け、「論理よりも情緒を」という言葉と共に、日本人が備えていたはずの美しい品格について、世の中に一石を投じるものとなった。
確かに「品格ブーム」は新書界隈における一大ムーブメントではあったが、大賞を獲るほど流行したのかと言われると少し怪しいラインではある。普段から本に触れることのない人たちには間違いなく届いていない。トップテンなら一切異論はないのだが、限定された場所・場面でしか使用出来ないものが大賞に選ばれるのは違和感がある。大賞は「イナバウアー」のみで良かったのではなかろうか。
というわけで、「イナバウワー」の大賞受賞は納得だが、「品格」の大賞受賞は不服という結果になりました。
2007年『(宮崎を)どげんかせんといかん』『ハニカミ王子』

この年はそのまんま東こと東国原英夫の年だった。第17回宮崎県知事選挙(2007年1月21日投開票)へ無所属で立候補し、当選。有効票数は266,807票。宮崎日日新聞社が行なった世論調査は、支持95.2%だった。お笑いタレントであることや、過去の不祥事であまり良い印象がなく泡沫候補とされていたのを跳ね除けての当選であった。
東国原は宮崎県の方言である諸県弁を駆使して、自身で「宮崎のセールスマン」と名乗り始め、「脱タレント」を印象付ける選挙活動を展開していた。報道番組やワイドショーでも連日報道され、多くの特集が組まれた。もちろんメディアにも積極的に出演していた。バラエティ番組に出演しすぎて批判さえされていた。
そして2007年2月15日。「オール野党」とも評される県議会で、所信表明演説を行なった。その様子は宮崎放送で午前9時55分から生中継(所信表明演説の中継は県議会史上初)され、普段は埋まることのない60の傍聴席を埋め尽くすなど、異例づくめの所信表明演説となった。
その際に東国原英夫が発した「宮崎をどげんかせんといかん」というフレーズは幾度となくマスコミに取り上げられ、注目を集めた。これは「どうにかしないといけない」という意味なのだが、本来は「どげんかせんないかん」という発音が正しく、間違った形で広まって、間違った形でノミネート・受賞に至った異例の流行語大賞となった。
一方の「ハニカミ王子」であるが、僕はこの言葉が嫌いだ。というのも昨年甲子園で活躍した斎藤佑樹こと「ハンカチ王子」の二番煎じだからだ。青色のハンカチで顔の汗をぬぐう行為に注目が集まり、斎藤佑樹と同世代の野球選手は「ハンカチ世代」とも呼ばれるようになった。
その愛称にあやかって名付けられたのが、プロゴルファー・石川遼の「ハニカミ王子」である。
高校生となった2007年に行われた「マンシングウェアオープン KSBカップ」にアマチュア枠で初出場し、日本のプロゴルフ大会においての史上最年少優勝を達成。男子ツアーでのアマチュア優勝は「中四国オープン」で優勝した1980年の倉本昌弘以来で、史上2人目の快挙だった。またこの優勝は、世界最年少優勝記録(15歳245日)としてギネス世界記録に認定された。
その優勝インタビューで照れくさそうな言動を見せる石川遼に対して、瀬戸内海放送アナウンサーがインタビューの最中にふと彼を「ハニカミ王子」と呼んだことが全ての始まりとなった。前述の「ハンカチ王子」と響きが似ている面白さも相まって、この愛称は瞬く間に定着したのだが、当時からオリジナリティがなく、パクりでしかないこの愛称にモヤモヤしていた。
もし去年「ハンカチ王子」が大賞を受賞していたら、絶対にこちらは獲れていなかったであろう(元を辿れば、去年のノミネートが発表された際に高野連から「アマチュアである高校野球が受賞するのは不適切」という謎の圧力がかけられて「ハンカチ王子」の大賞が遠ざかってしまったのが受賞を逃した原因と言われている)。
当時の肌感では、小島よしおの「そんなの関係ねぇ」やIKKOの「どんだけぇ〜」がめちゃくちゃ流行っていたので、大賞を逃したときはとてつもない衝撃を受けた記憶がある。子供だからよく真似していたと言うのもあるが、その年最もブレイクした芸人・タレントであること、汎用性が高く非常に使いやすいこと、酔っ払ったおじさんもへろへろになりながら真似をしていたことなど、様々な要素が合わさってどちらかが大賞を受賞するのは間違いないと思っていた。ただ「どげんかせんといかん」も一応タレント発の言葉なので、そこと比較したときに負けてしまったのだろうとは思う(「どげんかせんといかん」は、世相を含めて2007年を最も象徴する言葉だし)。
もしくは「KY(空気が読めない)」である。元々は2ちゃんねる上で使用されていたネット用語であり、携帯電話やメールの普及によって世間にも浸透し、会話にも使われるようになったという理想的な流行語である。その後、「JK (女子高生)」や「PK(パンツ食い込む)」「ggrks(ググれカス)」「kwsk(詳しく)」など、日本語の各イニシャルを組み合わせた言葉も「KY語」「KY式日本語」と呼ぶようになる。個人的には面白くて使っていたのだが、こちらはトップテン入りをしなかった。「そんなの関係ねぇ!」も「どんだけぇ〜」も「KY(空気が読めない)」も比較的年齢層の高い選考員たちには響かなかったのだろう。
というわけで、「(宮崎を)どげんかせんといかん」の大賞受賞は納得だが、「ハニカミ王子」の大賞受賞は不服という結果になりました。
2008年『グ〜!』『アラフォー』

これは明らかに弱い年だ。面白いワード自体は沢山生まれたのだが、これという決定的なものがなく、それが大賞にも反映されてしまった気がする。まず受賞した二つから触れていく。
「グ〜!」とは、ピン芸人 エド・はるみの代表的なギャグである。親指を突き立てて色気のある声色で「グ〜!」と呟く。多分「Good」という意味。それ以上でもそれ以外でもないのだが、それがとてもキャッチーで真似したくなる。
それに彼女は約20年続けていた演技の仕事を一時中断して41歳でお笑い養成所に入学。2008年2月に放送された『爆笑レッドカーペット』の3時間スペシャルで優勝したことをきっかけに、44歳で大ブレイクを果たすという異色の経歴を持っている。『24時間テレビ』のチャリティーマラソンランナーも務め、一躍時の人となった。
もう一方の「アラフォー」とは、「アラウンドフォー」の略で、「40歳前後の女性」を指す言葉である。天海祐希主演のTBS系ドラマ『Around40~注文の多いオンナたち~』から広まり、元々ファッション業界で使われていた「アラサー」をもじったものとなっている。既にアラサーという言葉が存在し、使われていた以上、新語としても、流行語としても非常に中途半端な印象がある。
その他、トップテン入りした中で大賞受賞のポテンシャルを秘めていたのは「あなたとは違うんです」だろう。福田康夫内閣総理大臣が辞任会見の場でマスコミに向けて発した言葉で、辞任自体の唐突さや当時の彼の評価の低さもあって「チンパン辞意」や「辞任党」など盛んにネタにされていた。こちらは当人の福田康夫が受賞を辞退したため(と言うか、授賞式に来るわけがなかったので)、大賞を逃す結果となった。正直これが一番流行った言葉だと思う。
ノミネートの中では「サブプライム」と「何も言えねぇー」辺りは明確に流行っていた認識があり、なぜトップテン入りすらしなかったのか不可解である。サブプライムとは、アメリカ合衆国における低所得者向け住宅ローンのこと。アメリカの住宅バブル崩壊により、サブプライムローン関連証券を大量に購入していた大手投資銀行「リーマン・ブラザーズ」は、多額の損失を抱えて倒産。これが100年に一度の経済恐慌と言われた「リーマン・ショック」を引き起こすこととなった。2008年の日本、いや、世界を象徴する言葉なのである。
そして「何も言えねぇー」は、我らが北島康介が、北京オリンピック 男子100m平泳ぎにて人類史上初「59秒の壁」を破る58秒91の世界新記録を樹立し、金メダルを獲得した時のセリフである。男子100m平泳ぎの大会2連覇は世界初、平泳ぎの同一種目の大会連覇は日本人としては鶴田義行以来76年ぶりのことであった。
同年に行われた「アスリートイメージ評価調査」では、「2008年に最も活躍した」アスリート1位、「2008年に最も注目度が増した」アスリート2位、、イメージ総合ランキング1位に選ばれた。オリコンが「好きなスポーツ選手」についてアンケート調査を実施した際にも、男性部門1位で選ばれた。2008年を象徴する人物の一人なのである。
「グ〜!」や「アラフォー」が流行っていないとは言わないが、この年は、もっと時代を、世相を反映した流行語が沢山あったはずだ。どちらかひとつを選ぶなら間違いなく「グ〜!」だが、個人的には北島康介に「何も言えねぇー」で二度目の大賞受賞を獲ってほしかった。
というわけで、「グ〜!」の大賞受賞は納得だが、「アラフォー」の大賞受賞は不服。そして「何も言えねぇー」か「あなたとは違うんです」が大賞を獲るべきだったという結果になりました。
2009年『政権交代』

単一での受賞は2004年の「チョー気持ちいい」以来、5年ぶりである。新語・流行語かどうかは置いておいて、「政権交代」はこの2009年を象徴する言葉としてはこれ以上なく最適な言葉だと思う。それは日本から見ても、世界から見てもだ。
「政権交代」とは、文字通り「政権」の「交代」のことである。1955年から2009年まで、(一時期の例外をのぞき)日本では自由民主党の長期政権が続いていた。しかし、8月30日。第45回衆議院議員総選挙において民主党が圧勝し、9月16日には民主党政権が誕生した。その民主党圧勝の原動力となったキャッチフレーズが「政権交代」なのである(結果的に「政権交代」と言うよりは、「政権後退」って感じではあったが…)。
また同政権は、予算の無駄遣いを無くすために公共事業などを削減した「事業仕分け」や、官僚主導から政治家主導の政治を実現すると公約した「脱官僚」などもトップテンに選出され、政局の転換に関連した流行語が多く選ばれた(その割に蓮舫の「2位じゃダメなんですか?」は選ばれなかったけど、これは11月に生まれた流行語らしい)。
日本で「政権交代」が巻き起こった要因のひとつに、間違いなく前年のアメリカ大統領選挙の影響がある。民主党のバラク・オバマが共和党のジョン・マケインを破り、2009年1月20日に初のアフリカ系・有色人種の大統領としてアメリカ合衆国大統領に就任した。
そんなバラク・オバマ陣営のキャッチフレーズが「イエス・ウイ・キャン(そうだ、私たちはできる)」、及び「チェンジ!」なのである。そう、「チェンジ」なのだ。正直「政権交代」より「チェンジ」の方がよく真似されていたし、流行語のイメージが強い(流行の発端が2008年であることや、そもそもアメリカ発祥の言葉であることなど弱点はあった)。
他に流行語らしい流行語を挙げるとするならば、昨年末の『M-1グランプリ』で準優勝し、大ブレイクを果たしたオードリー春日の「トゥース!」があるだろう。人差し指を突き立てて「トゥース」と言うだけなので非常に真似しやすく、汎用性が高い。特に子供たちの間で大流行した。他にも「ヘッ」や「鬼瓦」「アパー」「あべし」「カスカスダンス」など、キャッチーなギャグも多く、まさに2009年の顔だった。当時の僕は(周りも含めて)、間違なく「トゥース!」が大賞を獲るだろうと予想していたため、トップテンにすら入らなかったのは大きな衝撃だった。
もしくは「新型インフルエンザ」(H1N1)もある。発生源はブタの間で流行していたウイルスで、4月にメキシコで流行が初確認され、その後すぐに世界的大流行となった。5月にはカナダに研修に行った日本の高校生グループの感染が確認され、徐々に日本国内でも広がっていき、6月にはWHOがパンデミック(爆発的流行)を宣言した。
流行語としてはマイナスな要素が多すぎるため、大賞に選ばなかったのは妥当な判断だが、2009年を象徴する言葉として「政権交代」と肩を並べても遜色はない。ただ「政権交代」も「新型インフルエンザ」も時事であって、流行語とは言い難い。やはり個人的には「トゥース」が一番流行語らしい流行語だと思う。
ちなみにBIGLOBEが発表した「2009年重大ニュース&流行語ランキング」(投票数 2069票)では、1位が「新型インフルエンザ」、2位が「トゥース!」、3位が「草食系男子&肉食系女子」、4位が「政権交代」となった。
というわけで、「政権交代」の大賞受賞は別に納得ではあるけど…という結果になりました。
2010年『ゲゲゲの〜』

はい。これは僕が過去トップレベルに激萎えした流行語大賞ですね。今までは多少なりとも納得できる要素はあったけれど、『ゲゲゲの〜』に関してはいつどこで流行った言葉なんだよとブチ切れましたね。そもそも『ゲゲゲの鬼太郎』が先にある以上、新語ですらないからね。
「ゲゲゲの〜」を簡単に説明すると、漫画家水木しげるの妻・武良布枝が著した自伝エッセイ、及びそれを原案としたNHK朝の連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』から由来する言葉である。週刊連載のマンガ『墓場の鬼太郎』を『ゲゲゲの鬼太郎』と改題したころから、二人の超極貧物語がサクセスストーリーへと転じて行く話である。
ドラマの初回視聴率は14.8%と過去最低であったが、徐々に上昇していき、最終回に番組最高の23.6%を記録。Twitter上でも連日感想が飛び交い、放送終了後には連続テレビ小説で初めてザテレビジョンドラマアカデミー賞最優秀作品賞を受賞し、高い評価を得た。社会的反響も大きく、主演俳優である松下奈緒と向井理はともに本作品でブレイク。原作小説も50万部を突破。境港市の水木しげるロードは、中高年層や若者のグループなどでにぎわい、入り込み客は年間370万人となった。
また本作の主題歌であるいきものがかりの『ありがとう』は、初動・累計売上ともにこれまでの最高であった「YELL/じょいふる」を上回って自己最高記録を更新。いきものがかりとしては初めて着うたフルでミリオンを突破した楽曲で、この曲が収録されているベストアルバム『いきものばかり〜メンバーズBESTセレクション〜』は140万枚以上を売り上げるロングセラーとなった。
ドラマ自体が社会現象を巻き起こしたことは認めるが、やはりどう考えても「ゲゲゲの〜」というワードは流行っていない。どうしてもこの現象に賞を与えたかったのだろう。無理に言葉を絞り出した結果の「ゲゲゲの〜」だった。こんな中途半端なものに大賞を与えてしまうくらいなら、最初から『ゲゲゲの女房』で受賞させるべきだった。
個人的には、天才的な謎かけで一世を風靡したWコロンねづっちの「ととのいました」が一番「流行語」としてはしっかりくるかな、とは思ったけれど、謎かけや「ととのいました」という言葉自体は昔からあるものなので目新しさがない。それに謎かけって簡単には真似できないから大きな流行になりづらかった。
ととのいました。流行語と掛けまして、禁煙と解きます。その心は、どちらも「衰退/吸いたい」が付き物です。とまっちです。
話を戻して。「AKB48」や「食べるラー油」なんかはメディアでもよく取り上げられていたし、とんでもない経済効果を叩き出したが、そもそも流行り言葉ではないし、『ゲゲゲの女房』に比べると少し見劣りしてしまう。「〜なう」なんかが一番時代を反映しているような気もするけれど、SNSに疎い選考委員たちが選ぶわけがない。どれもしっくり来ない。個人的には「ととのいました」か「〜なう」なんだけどなあ。難しい。
BIGLOBEが発表した「2010年流行語大賞TOP5」では、1位が「AKB48」、2位が「戦場カメラマン」、3位が「ととのいました」、4位が「なう」、5位が「ゲゲゲの女房」となった。
というわけで、「ゲゲゲの〜」の大賞受賞は『ゲゲゲの女房』は流行ったけれど、「ゲゲゲの〜」という言葉は1ミリも流行っていないので不服という結果になりました。
2011年『なでしこジャパン』

2011年を語る上で忘れてはいけないのが、3月11日に発生した「東日本大震災」だ。トップテンには、「絆」や「帰宅難民」「3.11」「風評被害」など、震災や原発事故に関する言葉が並だ。日本中が暗く重い自粛の空気に包まれていた中で、我々に大きな希望を与えてくれたのが「なでしこジャパン」であった。
「なでしこジャパン」とは、2011年6月26日から7月17日にかけて、ドイツで開催された『2011 FIFA女子ワールドカップ』の女子日本代表の愛称で、優勝候補のドイツやアメリカを破り、日本代表として初のFIFA主催の世界大会優勝という快挙を成し遂げた。
その後、団体としては初の国民栄誉賞を受賞。紫綬褒章や、日本プロスポーツ大賞、毎日スポーツ人賞、報知プロスポーツ大賞、日本スポーツ賞、ビッグスポーツ賞、朝日スポーツ賞など、数々の賞を受賞した。そのうちのひとつに新語・流行語大賞もあるのだ。
しかし、「なでしこジャパン」という愛称は今に始まったことではなく、2004年には既に採用されており、なんならその時に一度、新語・流行語にノミネートされているのだ。七年ぶり二度目のノミネートで大賞を受賞するという謎すぎる事態となってしまった。
確かに「なでしこジャパン」は活躍したが、別に流行語ではない。人気があるとか活躍したとか思っている人は沢山居ても、流行ったという認識も持つ人はほとんど居なかったと思う。無理にその年の世相を反映しようとするあまり、強引に流行語として扱っている感が否めない。
かと言って、適切な大賞もパッとは思い浮かばない。世相を反映するのなら「東日本大震災」関連の言葉が最も相応しいのだろうけれど、どれも暗いものばかりだし、「なでしこジャパン」と同じく流行とは言い難いものばかりだ。強いて挙げるなら、ACジャパンによる公共広告作品『あいさつの魔法。』にて流れる「ぽぽぽぽーん」だろう。
ACジャパンの2010年度全国キャンペーンのひとつとして、2010年7月から2011年6月まで展開された。テーマは「挨拶の励行」であり、小学校低学年までの子供を対象に、挨拶をすることの楽しさを伝えている作品となっている。
そしてキャンペーン期間内に東日本大震災が発生してしまった影響で、この作品は他のACジャパンの作品とともに頻繁にテレビで流されるよあになり、各種ニュースサイトで取り上げられるなど反響を呼んだ。一部では流れすぎて「トラウマになる」とすら言われていた。自分もノイローゼになりそうなほど耳にしていたのだが、正直めちゃくちゃ真似していたのもまた事実である。またネット流行語大賞では金賞に選ばれている。
きっと「ぽぽぽぽーん」の文字を見たときに東日本大震災を彷彿とさせるからノミネートから外してしまったのだろうが、同じくACジャパンの公共広告作品「こだまでしょうか」はトップテン入りを果たしているため、モヤモヤする。かの有名な金子みすゞの詩から引用されたものであり、新語ですらない。どうしても言葉のチョイスに選考員たちの高齢化を感じてしまう…。
または「直ちに…」もある。東京電力福島第1原子力発電所事故が発生して以降「直ちに健康に影響を与えるレベルではありません」といったように、ニュースで頻繁に使用されるようになった。テレビでニュースが流れると毎度のように言われていたし、日経テレコン21が『日本経済新聞』の中で「直ちに」及び「ただちに」が登場した回数を調べてみると、1ヶ月で20回程度から90回近くにまで跳ね上がっていたという。間違いなく流行語と言っていいはずだが、「ぽぽぽぽーん」と同様の理由で選ばれなかったのだろう。もはや「不謹慎」や「自粛」が流行語だったとも言える。
この年の大賞・トップテンに選ばれた言葉、全てをひっくるめても、個人的には「承知しました」が2011年に最も流行った言葉だったと思う。2011年10月期に放送された日テレ系水曜ドラマ『家政婦のミタ』で使われているセリフで、本作の最終回は40.0%を記録し、21世紀に放送された日本のテレビドラマとしては、初の40%超えであった。
この高視聴率を背景に、職場や学校などで「承知しました」「それは業務命令でしょうか」「それはあなたが決めることです」などのドラマ上の決まり文句が流行し、ロケ地である千葉市動物公園の入園者数が増加するなど「ミタ現象」と呼ばれる現象がが起こった。流行どころか、大流行である。
しかし、10月から12月にかけて放送されていたドラマなので、流行ったのも下半期。流行語大賞のノミネートが発表されるのが10月のため、そもそも選ばれるはずがなかった。選考委員たちはノミネートから洩れた言葉を救済する機会を与えない姿勢を貫いていて、翌年に改めてノミネートされたり、追加ノミネート、追加受賞が認められたケースは一度もない。アカデミー賞のように翌年に授賞式を開催すればいいのに、11月にノミネートを発表し、12月に大賞を選ぶなんてどういう考えなのだろう。その年1年間に発生した「ことば」のなかから選考するはずなのに、1月から10月までの間に流行った言葉しか対象にならないのは、流石に違和感を抱いてほしい。
というわけで、「なでしこジャパン」の大賞受賞は不服という結果になりました。
2012年『ワイルドだろぉ』

2008年の「グ〜!」以来、5年ぶりのお笑い界からの大賞である。流行語を獲った芸人は消えると本格的に言われ始めたのも大体この辺りからだと思う。「ワイルドだろぉ」とは、ピン芸人 スギちゃんの代表的なギャグで、1.5リットルのコーラの蓋を外したまま持ち歩いたり、長袖の袖を引きちぎって半袖にしたりなど、取り返しのつかない行動をしたあと自虐的に呟く一言である。このネタで『R-1ぐらんぷり 2012』に出場し、準優勝を果たすと一躍脚光を浴び、その年最もブレイクした芸人となった。
子供たちの間では「だぜぇ」「だろぉ?」のようなワイルド口調が流行し、当時としてもこれじゃなかったら他に何があるんだよ!というレベルで流行り散らかした。納得も納得の大賞である。
対抗馬を無理矢理挙げるなら、野田首相の「近いうちに…」だろうか。8月の会見にて野田首相が「近いうちに国民に信を問う」と発言し、衆議院解散を確約したが、3ヵ月以上にわたって何も起こらず、「近いうちに解散」という言葉ばかりが流通した。野田首相は衆議院の解散時期について問われるたびに「近いうちに…」という言葉を連呼していて、もはや弄られ待ちの状態であった。近年で言う、森友学園問題の「忖度」や、岸田首相の「検討する」のようなものだ。
2012年の政界を象徴する言葉であるため、スギちゃんの「ワイルドだろぉ」が無ければ間違いなく「近いうちに…」が受賞していただろう。あまりにも「ワイルドだろぉ」が圧倒的すぎる。文句なしの大賞だ。
というわけで、「ワイルドだろぉ」の大賞受賞は納得も納得の結果となりました。
2013年『今でしょ!』『お・も・て・な・し』『じぇじぇじぇ』『倍返し』

まさかまさかの衝撃。新語・流行語大賞が始まって以来、史上初・史上最多の4つの大賞です。いくらなんでも多すぎだろ!と思いますけど、でも納得なんですよね。この年は過去に類を見ないほどめちゃくちゃ流行語が豊作だったんですよ。
まず「今でしょ!」。予備校『東進ハイスクール』のテレビCMにて、林修先生がふてぶてしい表情で「いつやるか? 今でしょ!」と言い放つのがお茶の間に受け、すぐに様々なメディアでパロディが制作された。現在にも続くように、林先生はこれを機に売れっ子の仲間入りとなった。
そして「お・も・て・な・し」は、9月7日に行われた国際オリンピック委員会(IOC)総会にて、フリーアナウンサーの滝川クリステルが日本社会に根付く歓待の精神を「お・も・て・な・し」と宣伝し、それがきっかけで日本での五輪開催が決定したというもの。流行するには少し遅い時期ではあったが、五輪招致決定のインパクトや、「お・も・て・な・し」が世界的な流行語となっていたことなども相まって、誰も不満は抱かなかったと思う。
「じぇじぇじぇ」は、NHKの朝の連続テレビ小説『あまちゃん』で幾度となく発せられる岩手県三陸地方の方言で、驚いたり戸惑ったりするときに使う言葉のこと。「倍返し」は、TBS日曜劇場『半沢直樹』にて、半沢が反撃するときに発する台詞「やられたらやりかえす。倍返しだ!」から来ている。
前者はロケ地となった岩手県久慈市に観光客が殺到し、約33億の経済効果をもたらした。後者は最高視聴率が44.1%を記録し、平成ドラマ史上No.1になった。どちらも大きな社会現象を巻き起こし、1994年の「同情するならカネをくれ」(ドラマ『家なき子』)以来、19年ぶりにドラマ発の台詞からの大賞が誕生した。
やはり納得の4選である。しかも上記の4つのみならず、トップテンには「アベノミクス」や「PM2.5」「ご当地キャラ」「ブラック企業」「ヘイトスピーチ」など、どれもこれも2013年を象徴するような言葉ばかりが並んでいる。それだけに留まらず、ノミネートにも「激おこプンプン丸」や「DJポリス」なんかがあったりして、かなり拮抗状態だったことが見て伺える。絶対にひとつに絞ることなんてできない。獲るべくして獲った4つなのだ。ちなみに個人的によく真似していたのは「今でしょ」と「倍返し」のふたつだ。
というわけで、「今でしょ!」「お・も・て・な・し」「じぇじぇじぇ」「倍返し」の大賞受賞は納得の結果になりました。
2014年『ダメよ〜ダメダメ』『集団的自衛権』

はい、ふざけ散らかしてるね。「集団的自衛権」と「ダメよ〜ダメダメ」の並びは明らかに政治的意図が垣間見えてる。確かに「集団的自衛権」は、7月に安倍内閣が行使容認を閣議決定するまで白熱の議論が展開され、嫌というほど耳にした言葉ではある。武力攻撃を受けた国家と密接な関係にある第三国が、共同して防衛対処に当たる国家の権利のことで、1945年には既に発効されている権利である。こんなもの流行りでもなんでもない。今更これを新語・流行語とかふざけるなという話だ。
ちなみに「集団的自衛権」は、史上初の大賞受賞者辞退というアクシデントに見舞われた言葉でもある。今までそういった場合は、別の言葉を大賞に選んで必ず誰かに賞を与えるようにしていたのに、「集団的自衛権」だけはゴリ押しで大賞を与えていて、それが何とも小賢しい。無理矢理にでも「集団的自衛権」「ダメよ〜ダメダメ」の並びを作りたかったようにしか思えない。政治的な話ではなく、流行語大賞が納得かどうかの話として言わせてもらうが、めちゃくちゃ気持ちが悪い。
もう一方の大賞「ダメよ〜ダメダメ」は、お笑いコンビ・日本エレキテル連合の代表的なコント「未亡人朱美ちゃんシリーズ」で、朱美ちゃんがおじさんからの誘いを断るときに何度も連呼する言葉。大晦日に放送された『ぐるナイおもしろ荘 若手にチャンスと愛を誰か売れて頂戴SP!!』で準優勝し、一躍ブレイクを果たした。
その年始まった『Yahoo!検索大賞 2014』でもお笑い芸人部門を受賞するなど、誰もが認める売れっ子となった。こちらは納得の大賞だ。と言うか、「ダメよ〜ダメダメ」だけで良かった。
まぁ。個人的には「ありのままで」が大賞でも良かったんじゃないかな?と思うのだが、どうやら選考委員たちは『アナと雪の女王』を誰一人として観ていなかったため大賞に選ばなかったらしい。これに関しては普通に意味が分からん。ふざけんなすぎる。このあたりから選考委員たちの酷さが露呈していくことになる。
というわけで、「ダメよ〜ダメダメ」の大賞受賞は納得だが、「集団的自衛権」の大賞受賞は不服という結果になりました。
2015年『爆買い』『トリプルスリー』

2015年、最も報道されていたニュースと言えば中国人観光客による「爆買い」だろう。2月の春節休暇に中国人観光客が日本を訪れ高額商品から日用品まで様々な商品を大量に買い込む様子を「爆買い」と表現し、多くの日本メディアがそれを取り上げていた。
中国メディアによれば春節期間中、日本を訪れた中国人観光客は45万人にのぼり、消費額は66億元(1140億円)を記録。日本企業にとって最高のビジネスチャンスとなっていた。「爆買い」という言葉自体は2000年代後期からたびたび目にしていたが、2015年にそのピークが訪れる形となり、少しずつ言葉が認知され、広まっていった理想的な流行語となった。
その後は中国人観光客関係なく、物を沢山大人買いすることを「爆買い」と表現するようになり、その使いやすさからも未だに使われている。もはや定着してしまった感すらある。
それに比べて「トリプルスリー」って…。日本プロ野球において打者が同一シーズンに「打率3割・30本塁打・30盗塁」以上の成績を記録することで、ソフトバンクの柳田悠岐とヤクルトの山田哲人の二人が同時にトリプルスリーを達成して話題となった。凄いことではある。それは間違いない。しかし、65年前の1950年に岩本義行と別当薫が同時に達成しているし(この当時はトリプルスリーという言葉は存在しなかった)、日本プロ野球では10人が、メジャーリーグでは25人が達成していて、今更囃し立てて流行語大賞を受賞させるほどのものでもない。
「品格」でも書いたが、そもそも限定された場所・場面でしか使用出来ないものが流行語の大賞に選ばれるのは違和感がある。使いやすさ、汎用性こそが流行語の最たるものだと思っているので、いつどこで使うんだよとしか思えない。野球ファンですらもこの大賞に首を傾げた人は多いだろう。
更に酷いのは、2015年まで選考委員長だった鳥越俊太郎が「表彰式で発表されるトップ10のうち年間大賞受賞者は式への出席が必須で、出席できない場合は表彰式が盛り上がらないので大賞から外れる」、「2015年の選考では「五郎丸」に年間大賞を与える予定だったが、本人が出席できないということで急遽トリプルスリーに変わった」と語った。まあひどい。どれだけ流行ったかより、誰を呼び、誰を与えたいかで選ばれる賞なのだ。しょう(賞)もない…なんつって。この年は「爆買い」のみの大賞で良かった。
というわけで、「爆買い」の大賞受賞は納得だが、「トリプルスリー」の大賞受賞は不服という結果になりました。
2016年『神ってる』

2年連続の野球用語の大賞。「神ってる」とは、文字通り「神がかっている」の略である。広島東洋カープの鈴木誠也が2016年6月17日・18日のオリックス戦で両日ともサヨナラホームランを打ち、プロ野球史上10人目となる偉業を成し遂げた。
2016年に残した数字は打率335、29本塁打、95打点。堂々の成績でベストナイン、ゴールデン・グラブ賞を受賞。緒方孝市監督はそれを「神ってる」と表現し、それが話題となった。1991年以来、25年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした広島東洋カープの快進撃を象徴する言葉となった。
ただ。ただそれだけである。「神ってる」なんてものは前からインターネット上や中高生の間ではもはや当たり前のように使っていた言葉であり、高齢の選考委員たちは野球界でそれが使われたことに新鮮味を感じただけなのだ。
この年は語りたいことが沢山あるので、少し長めに書かせてもらう。まず2016年最初の衝撃的なニュースと言えば、やはり「ゲス不倫」だろう。1月、タレントのベッキーとバンド「ゲスの極み乙女。」のボーカル 川谷絵音との不倫が『週刊文春』にスクープされた。ベッキーはレギュラー番組やCMが非常に多く、好感度の高い芸能人の一人だったため、その衝撃は凄まじかった。
この報道をきっかけに、『週刊文春』に狙われることを「文春砲」と呼ぶことが広まり、自身がその文春砲のターゲットになっていることを知ったベッキーが、LINE内で「文春」を無理矢理直訳して「センテンススプリング」と表現したり、など話題が尽きなかった。
狩野英孝の六股疑惑や、乙武洋匡と5人の一般人女性との不倫、ファンキー加藤とアンタッチャブル柴田の元妻とのW不倫、三遊亭円楽の不倫などなど、何かと著名人の不倫報道があると年がら年中「ゲス不倫」と報道されていた。
その他の話題では、7月22日に日本でサービスが開始された「ポケモンGO」か。スマートフォンのGPS機能を使用しながらポケモンを捕まえるアプリだ。日本を始め、世界各国で社会現象が巻き起こした。AppStoreでのダウンロード数は36か国で首位となり、経済効果は2016年だけで9億5,000万ドル(約1090億円)となった。また5つのギネス世界記録を樹立した。
「2016年 ヒット商品ベスト30」では第1位、第29回DIMEトレンド大賞受賞、2016年度ネット流行語大賞銀賞、第3回Yahoo!検索大賞 カルチャーカテゴリ ゲーム部門賞受賞など、2016年のトレンドとして新聞や雑誌、ネットメディアにも取り上げられていた。外に出れば道行く人たちがみんな「ポケモンGO」をしている状態であった。ただ、それに伴う交通事故やトラブルなどが続出したということもあり、社会問題としても取り沙汰された。
もうひとつの社会現象と言えば、新海誠によるアニメ映画『君の名は。』の大ヒットだろう。8月26日に公開されてすぐさま圧倒的な映像美と内容の面白さが口コミで話題となり、公開から1ヶ月以上が経っても劇場はほぼ満席という状態であった。
そして公開から28日で興行収入が100億円を突破し、日本のアニメーション監督では宮崎駿に続く2人目の快挙となった。日本国内での興行収入は最終的に250億円を超え、当時の日本歴代興行収入ランキングでは『千と千尋の神隠し』『タイタニック』『アナと雪の女王』に次ぐ第4位となった。全世界での興行収入合計は3億6,102万ドルに達し、『千と千尋の神隠し』の2億7,500万ドルを抜いて、日本映画として史上最高記録となった。
映画の公開より2か月早く発売された小説版は、10月20日に累計発行部数が100万部を突破し、2016年推定売上部数文庫部門年間1位となった。またRADWIMPSの主題歌・挿入歌どれも大ヒットし、サウンドトラックアルバムはロングセラーを記録。「前前前世」のMVのYouTubeで再生回数3億回を越えている。
それだけではなく、舞台となった岐阜県飛騨市には3万6,000人もの観光客が訪れ、その経済効果は253億円に達したという(ただこれに関しては『君の名は。』だけではなく、同じ年に公開されたアニメ映画『聲の形』や『ルドルフとイッパイアッテナ』も岐阜県を舞台にしていたことも影響している)。『君の名は。』はトップテン入りこそ逃してしまったものの、「聖地巡礼」は見事にトップテン入りを果たし、しっかり社会現象の爪痕を残すの結果となった。
もうひとつエンタメからトピックを取り上げるなら「PPAP」(ペンパイナッポーアッポーペン)だろうか。古坂大魔王扮するシンガーソングライター・ピコ太郎の楽曲で、9月にジャスティン・ビーバーが自身のTwitterで「お気に入り」とツイートしたことで世界的に火が付き、米「ビルボードHOT100」に日本人として26年振りとなるチャートインを果たすなど一躍時の人となった。
2013年の「お・も・て・な・し」が9月から発生した遅咲きの言葉だったのに対し、世界的な流行だっため大賞を受賞できたように、「PPAP」も大賞を受賞できるポテンシャルを秘めていただけにトップテン入りで留まってしまったのは少し残念だった。が、まあ仕方ないか。
2016年は政治の話題も盛んだった。例えば多くのメディアの予想を裏切って、ドナルド・トランプがまさかの次期アメリカ大統領に当選してしまったことから始まる「トランプ旋風」や、新都知事として就任まもない小池百合子によって話題となった「盛り土」や「都民ファースト」。政治資金問題の記者会見で舛添要一が連発した「第三者の厳しい目」などなど。当時は大炎上し、今となっては語り草となっている「保育園落ちた日本死ね」なんかもこの年である。
「マイナス金利」や「アモーレ」等、2016年を象徴するような言葉がトップテンに並ぶなか、なぜ大賞が寄りにもよって「神ってる」なのだろうか。まじでいい加減にしてほしい。個人的に一番言葉として流行ったなと思うのは「ゲス不倫」なのだが、マイナスな言葉だから避けたのかな。
というわけで、「神ってる」の大賞受賞は不服という結果になりました。
2017年『インスタ映え』『忖度』

いやぁ〜、これは久々に一切文句のない大賞ですね〜。本当に久々ですね〜。久々なんてこと本当はあってはならないんですけどね〜。どうせどちらも納得だから軽く説明だけしておく。
「インスタ映え」とは、Instagram映えの略称で「見栄えが良い」「写真が映える」という意味。特に若年層の間で流行った言葉で、インスタ映え目当てに様々なフォトスポットや飲食店に経済効果をもたらした。
しかし、写真を撮るだけ撮って食べ物をほとんど食べずに捨ててしまったり、観光スポットに若者が押し寄せて荒らしてしまったり、おしゃれなものに群がる様子を「インスタ蝿」なんて揶揄したり、一種の社会問題とまで化した。
この年もうひとつの社会問題と言えば、森友学園問題である。大阪市内で幼稚園などを経営していた学校法人『森友学園』が、大阪府豊中市の国有地を売却する際に、鑑定価格より大幅に値引きされていたことが明らかになり、これをきっかけに様々な問題が湧き水のように溢れ出してきたのだ。
また安倍晋三の妻・昭恵夫人が、開設予定の小学校の名誉校長に就任していたことが発覚し、売却に政治家たちの関与が疑われたり、籠池泰典前理事長と妻が国や市から多額の補助金をだまし取っていたことなどが発覚し、論点がどんどん拡散。マスコミも森友学園問題を連日大きく取り上げることとなった。そこで一躍注目を集めたのが、「忖度(そんたく)」という言葉である。
忖度とは、他人の心情を推し量ること、または推し量って相手に配慮することという意味。3月23日、籠池康博理事長が証人喚問ののちに日本外国特派員協会で行った記者会見で、「口利きはしていない。忖度をしたということでしょう」「今度は逆の忖度をしているということでしょう」と発言し、検索数が急上昇した。
この「忖度」という言葉は、使い勝手の良さからか、森友学園問題だけに留まらず、様々なメディアで引用された。中でも饅頭に「忖度」の文字を刻印した「忖度まんじゅう」なんかも発売され、初代だけで約20万箱、シリーズ累計で30〜40万箱を販売するなど大ヒット商品となった。
もしマイナスな言葉を選んでいい世界線だったら、きっと「このハゲー!」や「一線を越えていない」は良いところまで行っていただろう。「このハゲー!」とは、元衆院議員の豊田真由子が、秘書への暴言や暴行について報じられ、その際に録音された音声が拡散されたときのもの。そこで「このハゲーッ!」発言がワイドショーやSNSを賑わしたのだが、性別や年齢に関係なく、人の外見をあのように揶揄する言葉は公共の場で使われるべきではないとして、「ちーがーうーだーろー!」の方がノミネートされたのだ。当時死ぬほど真似していた身としては「なんでそっちだよ」と思ったけれど、理由が理由なので仕方ないか…と肩を落とした記憶がある。その上、わざわざ別に言葉に変更しておいてトップテンにすら選ばれなかったのだから悲しい。
「一線を越えていない」は、元SPEEDで自民党の参院議員だった今井絵理子が、既婚者の橋本健神戸市議との不倫が報じられた際に、記者会見で発した言葉。「本当に一線を越えていないのか」「そもそもどこからが一線なのか」非常に曖昧な表現が物議を醸した。その後も数々の芸能人の不倫が報じられる度に、この言葉が使われるようになっていき、今となっては不倫を否定する定番フレーズとなっている。
マイナスな言葉として並べるのは少し違和感があるが、この年は小池百合子の「排除いたします」という言葉が好きだった。よく真似していた。「希望の党」の結党を発表した会見で、自身の政治方針と異なる他党からの合流希望者に対する処遇について、「排除いたします」と回答した。この「排除」という言葉が「きつすぎる」「傲慢」などと有権者の反感を買い、勢いは一気に失速し、結果も大敗に終わった。小池百合子らしいパワーワードで面白かったのだけど、選ばれないのは致し方ない。少なくともノミネートされた「アウフヘーベン」よりは流行ったと思うんだけどな。忖度かな。
とは言っても、上記のどの言葉も「インスタ映え」と「忖度」に比べればそこまで大きく流行ったわけではないし、どのみちこの世界線ではノミネートされていても大賞は受賞できていなかったはず。「インスタ映え」と「忖度」のふたつはどちらも流行語であり、社会問題でもあるという如何にも選考委員たちが好みそうな非常にバランスの良い大賞だ。
というわけで、「インスタ映え」と「忖度」の大賞受賞は納得という結果になりました。
2018年『そだねー』

「そだねー」、この言葉を見ると脳内で『DA.YO.NE』が再生される。「そだねー」とは、平昌オリンピックカーリング女子日本代表『ロコ・ソラーレ』が、試合中に「そだねー」や「押ささる」「〜かい?」など北海道の方言を多用して戦術を話し合っていたことから瞬く間に広まった言葉で、ロコ・ソラーレには「そだねージャパン」という愛称も付けられた。
また、第5エンド終了後にある7分間のハーフタイムでイチゴやバナナ、チーズケーキなどを食べていたことが「もぐもぐタイム」呼ばれ、そちらも話題になった。メンバーが食べていたチーズケーキ(赤いサイロ)は注文が通常の10倍近く殺到する事態となったという。
生中継されたNHK総合のテレビ視聴率は準決勝・韓国戦で26.4%、3位決定戦のイギリス戦では25%の番組平均視聴率を記録。3位が決定した22時43分の毎分瞬間視聴率は42.3%という高視聴率で高い注目を集めた。
この年は、辛うじて6月の『2018FIFAワールドカップ』で「大迫、半端ないって!」が再注目されたくらいで、「そだねー」以外に特にこれと言って大きな流行語がない年であった。
個人的に「そだねー」は割と真似して使っていた方なので、「そだねー」の大賞受賞は納得という結果になりました。
2019年『ONE TEAM』

「ONE TEAM」とは、ラグビーワールドカップ日本代表でコーチのジェイミー・ジョセフ・ヘッドが掲げたスローガンのこと。日本ラグビー史上初の決勝トーナメント進出となったことで、日本中がラグビーに熱狂していた。ミーハーではあるが、自分もそのうちの1人である。
職場の朝礼や学校の集会などでお偉いさんが「みんなもラグビー日本代表のようにワンチームで…」なんて取ってつけたように使ったりはしていたと思うけれど、この言葉自体が大きな流行語だった印象はない。ラグビー関連の言葉で言えば「笑わない男」や「ビクトリーロード」「ジャッカル」「ノーサイド」「桜の戦士」なんかも広く知られるようになったが、「ONE TEAM」はその中で一番話題になった言葉、程度の認識ある。
あくまで自分から見た世界の話ではあるが、この年を象徴する言葉として、代表的なものが3つ存在すると思っている。そしてその3つともがトップテンから漏れている。その不遇な3つを紹介していきたい。
まずは「上級国民」だ。上級国民とは、旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三が、東京・池袋で乗用車を暴走させ、母子2人が死亡、9人に重軽傷を負わせた通称「池袋暴走事故」で広まった言葉だ。多くの類似事故では、運転手はその場で現行犯逮捕されるにも関わらず、飯塚幸三は90歳と高齢であることや、事故による怪我もあって身柄を拘束されることがなかった。
それに、飯塚幸三は元高級官僚で退官後も業界団体の会長や大手機械メーカーの取締役などを歴任し、事故の4年前には瑞宝重光章を叙勲していたりなど、「上級国民」だから特別扱いを受けているのだ、と揶揄されるようになった。
さらに、元々この言葉は2015年7月に東京オリンピック・パラリンピックのエンブレム盗作問題で知られるようになったネットスラングで、実はこの年、すでに一度ノミネートを受けている。SNSやネット掲示板などで頻繁に使われていた言葉が広まって、新聞やワイドショーなどでも使用されるようになった、まさしく「流行語」なのである。
そして二つ目は「NHKをぶっ壊す!」である。国政政党に躍進した「NHKから国民を守る党」および党首・立花孝志のキャッチフレーズで、主に子供たちの間で流行した言葉である。これは2001年の自民党総裁選にて小泉純一郎が発言した「自民党をぶち壊す!」からの引用だが、そちらを知らない層にとっては新鮮だったのだろう。個人的には結局二番煎じでしかないし、言ってる人が言ってる人なのであまり好きな言葉ではないけれど、流行したという意味では最も相応しい言葉だと思う。
最後は「松本、動きます」だ。トップテンに「闇営業」が選ばれたことが象徴するように、この一年は芸人たちの間で密かに行われていた反社会的勢力の会合に参加した闇営業問題が明るみになった。そのなかで雨上がり決死隊・宮迫博之や、ロンドンブーツ1号2号・田村亮らが、7月20日に謝罪会見を行い、それを受けてダウンタウン・松本人志が「後輩芸人達は不安よな。 松本 動きます。」という旨の投稿をし、その年最もいいねがついたツイートとして話題となった。
しかし、結果として松本人志が目に見えて吉本に何かしたということはなく、有言不実行の例として扱われることもある(松本自身はこれについて明確に否定しており、見えないところで色々やっていたらしい)。「闇営業」がトップテン入りするのなら、「松本、動きます」が選ばれても良かったんじゃないかと思う。
「上級国民」も「NHKをぶっ壊す!」も「松本、動きます」もネガティブな印象の方が強いせいで、ポジティブな話題だった「ONE TEAM」に大賞を持っていかれた節はあると思う。
というわけで、「ONE TEAM」の大賞受賞は別に納得だけど、流行ったかどうかで言えばもっと上がある…という結果になりました。
2020年 『3密』

2020年、最大のトピックと言えば「新型コロナウイルス(COVID-17)の世界的流行」だろう。前年 2019年12月初旬に、中国の武漢市で最初の感染者が報告され、それから僅か数ヶ月ほどの間にパンデミックと言われる世界的な流行となった。日本では、2020年1月15日に最初の感染者が確認され、3月頃から感染者が急増した。
夏頃には既にコロナ関連の話題が席巻しており、トップテンだけでも「アベノマスク」や「アマビエ」「オンライン○○」「Go To キャンペーン」などが選ばれた。ノミネートでも「新しい生活様式/ニューノーマル」「おうち時間/ステイホーム」「クラスター」「自粛警察」「濃厚接触者」「テレワーク/ワーケーション」「ソーシャルディスタンス」が候補に挙がるなど、コロナ用語のオンパレードである。
その中でも特にインパクトが強かったのが、大賞を受賞した「3密」だろう。拡大初期に首相官邸・厚生労働省が掲げた標語「3つの密を避けて行動を」のことで、それぞれ「① 喚起の悪い密閉空間」「② 多くの人の密集する場所」「③ 近距離での密接した会話」(密閉・密集・密接)のことを指す。
また、小池百合子が報道陣からコメントを求められた際に、密集する報道陣に向かって「密です!密です!」と注意喚起を行う姿も話題となり、その後海外在住の日本人大学生によって「密ですゲーム」なるものまで作られた。「今年の漢字」にも「密」が選ばれており、もはや流行語の域を通り越して国民全員の共通認識として「3密」があったのだと思う。
個人的には「ソーシャルディスタンス」(社会的距離)が最もよく使い、耳にした言葉なのだが、選ばれないのは仕方ないか。ほとんど同義語で、さらにキャッチーさのある「3密」が大賞になったのだからそこまで不満もない。
ちなみに、ORICON NEWSが行った『一足早い『新語・流行語大賞』予想2020』では、「ソーシャルディスタンス」が1位、「3密/密です」が2位、「ステイホーム」が3位、「コロナ禍」が4位、「鬼滅の刃」が5位となっている。
というわけで、「3密」の大賞受賞は納得という結果になりました。
2021年『リアル二刀流/ショータイム』

ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平が、1試合で「指名打者・先発」として出場することを「リアル二刀流」とし、その様子が海外では「ショータイム」と持て囃された。
大谷は打者で46本塁打100打点、投手で9勝という活躍を見せ、野球の神様ことベーブ・ルースの「2ケタ本塁打&2ケタ勝利」を103年ぶりに塗り替える…ことはできなかったものの、満場一致でア・リーグMVPに選ばれた。これは、日本選手ではマリナーズ時代のイチロー以来2人目となる快挙であった。
まぁこれは自分が無知なだけなのだと思うが、「リアル二刀流」はまじで一度も聞いたことがなかった。「二刀流」はあるが、「リアル二刀流」は初耳だった。大体「リアル」と書いてしまうと、宮本武蔵を指す言葉になってしまうでは…?と思ってしまう。刀を二本持っていない時点で、それはリアル二刀流ではない。
2021年が大谷フィーバーに沸いていて、コロナ禍の中で常にポジティブな話題を提供してくれていたという事実は間違いなくある。感謝してもしきれない。ただ選考委員たちがどうしても大谷翔平に大賞を与えたくて、無理やりふたつの言葉をくっ付けたとしか思えない。
そもそも大谷翔平の「二刀流」はずっと前から言われていたことで、2013年の時点で既に一度流行語大賞にノミネートされている。それに「ショータイム」も、大谷がロサンゼルス・エンゼルスに移籍した2018年に「翔タイム」としてノミネートを受けていて(どちらも受賞及びトップテン入りは逃している)、今更取り沙汰されることでもない。
いや、まだ「ショータイム」は理解できるか。海外では「SHOW TIME」と呼ばれていて、その語感の面白さも相まって鮮明に記憶に残っている。よく海外の実況が「ショータイム!ショータイム!」と叫んでいるのを耳にしていた。
もし「ショータイム」の並びで大賞に選ぶのなら、「リアル二刀流」ではなく、「オオタニサーン」だったのではなかろうか。こちらも海外の実況が頻繁に発していた言葉で、何故かさん付けだったり、イントネーションがクスッときたり、主にSNSで活発に取り上げられていた。
個人的なこの年の予想は(記憶が正しければ)、本命「SDGs」、対抗「うっせえわ」、大穴「ゴン攻め/ビッタビタ」くらいに思っていた。コロナ関連の言葉は前年ほどインパクトのあるものがないため、まず大賞はないだろうと予想。大谷関連の言葉は、上記でも書いたように「よく耳にしていたけど、昔から言われていたものばかりだしなぁ」という理由でスルーしていたため、いざ大賞が発表されたときはひっくり返った。
わざわざ説明するまでもないと思うが、一応予想で挙げた3つの言葉も軽く解説しておく。「SDGs」とは、国連で定められた世界的な目標「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals)「貧困をなくそう」や「ジェンダー平等を実現しよう」、「住み続けられるまちづくりを」などが細かく設定されている。世界的な取り組みというだけあって、メディアでは頻繁に取り上げられ、学校では授業や教材で扱われることもあった。予想の中では唯一トップテン入りすらしなかったのだが、もしかすると流行で終わらせてはいけないという考えがあったのかもしれない。
次に「うっせえわ」である。もともとニコニコ動画などで歌ってみたを投稿していた歌い手・Adoのメジャーデビューシングル1作目『うっせえわ』のことである。公開されるや否や、その刺激的な歌詞やキャッチーなメロディが大きな話題を呼び、TikTokやTwitterなどのSNSで急速に拡散された。瞬く間にYouTubeの再生回数は1億回再生を突破、ニコニコ動画では500万回再生を記録。デジタルセールスは累計30万DLに達し、ストリーミング再生回数は3億回となっている。主に若者たちの間で流行した曲なのだが、コロナ禍で肩身の狭い思いをしていた大人たちにもそこそこ共感を呼び、老若男女に愛される曲となった(嫌いな人はとことん嫌いな印象もあるが)。
そして「ゴン攻め/ビッタビタ」。こちらは東京2020オリンピックで新種目となったスケートボード競技・ストリートで解説を務めた、プロスケートボーダーの瀬尻稜氏による言葉。「ゴン攻め」とは、で手すりや階段など、トライするのも怖いような障害物をガンガン攻めているという意味で、「ビッタビタ」とはぴったりハマっていたという意味である。世間的には大きく流行したわけではないのだが、今までにない新しい言葉であることや、言葉のインパクトの強さ、そしてスケボーのルールを詳しく知らない多くの視聴者を虜にしたという意味でも、個人的には好印象だった。
話を戻すが、Yahooニュースが行った『2021新語・流行語大賞、あなたが選ぶなら?』というアンケートがある。35,944人が投票したうち、1位は「ショータイム」で14.5%(5,227票)だった。続いて2位が「副反応」で11.3%(4,074票)、3位が「SDGs」で9%(3,234票)、4位が「リアル二刀流」で8%(2,889票)、5位が「うっせえわ」で7.9%(2,851票)だった。
Yahoo民の年齢層はそこそこ高く(と言うか、ほぼ選考委員たちと同年代だと思うので)、若干の偏りはあると思われるが、しっかり「ショータイム」が1位である。まぁ人によってはかなり納得の流行語大賞なのだと思う。
一方で、高校生新聞が行った『「流行語大賞2021」を中高生が選んだら』では、1位が「副反応」で63.9%、2位が「SDGs」で51.0%、3位が「マリトッツォ」で49.5%、4位が「うっせえわ」で48.0%、5位が「推し活」で45.0%となった(少し話は逸れるが、一体これは何を意味する%なのだろう)。
また、大賞を受賞した「リアル二刀流」と「ショータイム」の二語は、どちらも18位タイで12.4%という結果になった。Yahooニュースと高校生新聞、バランス良くどちらにも選ばれていたのは「副反応」「SDGs」「うっせえわ」の3つだけである。本来ならこの中から選ばれるべきだったと思うが、大谷フィーバーの最中では流石に「ショータイム」でも文句は言えないか…。ただどうしても「リアル二刀流」という気持ち悪い言葉だけは受け付けられない。
というわけで、「リアル二刀流/ショータイム」の大賞受賞は「リアル二刀流」は不服、「ショータイム」は納得という結果になりました。
2022年『村神様』

2年連続の野球用語の大賞ですね。2015-2016の悪夢再び。「村神様」とは、日本選手シーズン最多となる56本のHRを記録し、三冠王、史上初5打席連続HR、通算150本塁打、2試合連続HRなどを史上最年少となる22歳で達成した東京ヤクルトスワローズ・村上宗隆の愛称のこと。
トップテン入りまでは確実とは思っていたけど、まさか大賞まで受賞するとは…。過去に「イチロー(現象)」や「タマちゃん」「ハニカミ王子」が獲っているからあれですけど、あだ名ですよあだ名。ただの愛称。大きな経済効果があったり、グッズが売れまくったり、あだ名を通り越してひとつのムーブメントの名称になっていたのなら分かるんですけどね。別にそんなことも無かったですよ。活躍したには活躍したんですけどね。精々トップテン入りで十分ですよ。そんなに野球が好きなら、もう潔く野球大賞に改名すればいいんじゃないですかね。
じゃあ一体、この年は何が受賞するべきだったかと言うと…「ブラボー!」しか考えられないだろう。FIFAワールドカップ 2022 カタール大会にて、日本代表がドイツを2対1で下し勝利するという歴史的快挙を成した際に、長友佑都がずっと連呼していた言葉である。
その後、優勝候補のスペインも撃破し、待ってましたと言わんばかりに再びこのワードが炸裂。これらの一連の勝利は「ドーハの歓喜」と呼ばれ、W杯の熱狂も相まって「ブラボー!」を真似をするファンが続出した。
問題は、この言葉が流行したのが11月23日からという部分である。流行語大賞のノミネートは11月4日に発表され、大賞とトップテンを発表する表彰式は12月1日に行われる。下半期の短い期間とはいえ、「ブラボー!」は2022年最も流行した言葉と言っても過言ではない。やはり、その年1年間に発生した「ことば」のなかから選考するはずなのに、1月から10月までの間に流行った言葉しか選考対象にならないのは、この賞の大きな欠陥である。
Yahooニュースが行った『2022新語・流行語大賞、あなたが選ぶなら?』、7,980人(なぜか前年から大幅に減っている)が投票したうち、1位は「ヤー!パワー!」で23.4%(1,870票)だった。続いて2位が「きつねダンス」で12%(961票)、3位が「青春って、すごく密なので」で10.5%(836票)、4位が「村神様」で9.1%(730票)、5位が「知らんけど」で6.7%(531票)だった。もちろん「ブラボー!」はノミネートされていないので、選択肢にすらない。それに投票数が少ないため、2位以下はほとんど団子状態である。
一方、高校生新聞が行った『「流行語大賞2022」を中高生が選んだら』では、1位が「SPY×FAMIRY」で60%、2位が「オミクロン株」で55%、3位が「知らんけど」で52%、4位が「きつねダンス」で41%、5位が「ヤー!パワー!」で39%という結果となった。Yahooニュースと高校生新聞、どちらにも選ばれていたのは「ヤー!パワー!」「きつねダンス」「知らんけど」の3つであった。
また、集英社が行った『ネット&街頭で300人に聞いた「あなたが思うホントの流行語大賞2022」』というアンケートもあった。票数が300票と少ないものの、16歳から60歳までの幅広い年齢層で街頭調査を実施したため、最も年齢による偏りがないアンケートと言える。1位は「けつあな確定」で36票、2位は「ブラボー」で31票、3位は「SPY×FAMILY」で15票、4位は「チェンソーマン」で14票、5位は「ちいかわ」で12票だった。いや、うん。めちゃくちゃ偏ってた。
もし、ノミネートされた言葉の中からひとつ大賞を選ぶなら、「知らんけど」が一番「流行語」のような気がする。関西からじわじわと広まっていき、会話や文章でも気軽に使えるという点が良い。ただ「ブラボー!」がノミネートされていたら、迷わずそっちを選んでいた。
というわけで、「村神様」の大賞受賞は不服という結果になりました。
2023年『アレ(A.R.E)』

「アレ」とは、阪神タイガースの岡田彰布監督によるもので、選手が「優勝」を意識しすぎないように表現した言葉である。というのも、この言葉の誕生は2008年まで遡る。
2008年の阪神タイガースは、開幕5連勝を皮切りにシーズン前半で好調を維持し続け、7月9日には2位に最大13ゲーム差をつけて首位を独走していた。選手及び阪神ファンは優勝を確信し、他球団も優勝を半ば諦めていたなかで、巨人の猛追撃が始まりまさかの優勝を逃してしまうという出来事があった。そのときの監督がまさに岡田彰布監督だったのだ。これ以降、関西(特に阪神ファンの間)では、優勝という言葉を決して口にしてはいけないという暗黙の了解が生まれた。
それから2度目となる阪神監督への就任で、チームスローガンは『A.R.E.』に決定(こちらは「Aim! Respect! Empower!」の略とされている)。この「アレ」パワーが功を奏したか、阪神は18年ぶり6度目のセントラル・リーグ優勝、38年ぶり2度目の日本一を実現させたのだ。
「アレ」を目前にしたあたりから、タイガース推しのお店や商店街ではアレセールが行われ、様々な企業から大量のアレグッズが販売された。中でもパインアメをもじった「パインアレ」や、のりつくだ煮「アラ!」をもじった「アレ!」(そのまんますぎる)などが話題となった。
過去の「トリプルスリー」や「神ってる」「リアル二刀流」「村上様」のせいで、本当に流行ったものまで野球用語だからという理由で嘲笑されてしまうのが心の底から悲しい。もしかしたら盛り上がっていたのは関西人だけかもしれないが、体感として久々に流行っている印象のあった野球用語だったので本当に勿体ないと思う。
Yahooニュースが行った『2023新語・流行語大賞、あなたが選ぶならどれですか?』、12,771人が投票したうち、1位は「アレ(A.R.E.)」で35.7%(4,554票)だった。続いて2位が「憧れるのをやめましょう」で
17.8%(2,274票)、3位が「エッフェル姉さん」で7.1%(910票)、4位が「ひき肉です/ちょんまげ小僧」で6.6%(841票)、5位が「別班/VIVANT(ヴィヴァン)」で3.9%(501票)だった。
この年はワールドベースボールクラシック(WBC)もあったため、上位ふたつ、野球関連の一騎打ちのような状態となっている。「憧れるのをやめましょう」は、WBC決勝戦の試合前、侍ジャパンの大谷翔平が円陣で放った台詞で、この言葉で侍ジャパンを全勝優勝へと導いた。また大谷は今大会のMVPにも選ばれた。「アレ(A.R.E.)」でも「憧れるのをやめましょう」でも、どちらも野球が大盛り上がりとなった1年を象徴する言葉として相応しい。いや、やはり関西人としては「アレ(A.R.E.)」一択である。
というわけで、「アレ(A.R.E.)」の大賞受賞は納得という結果になりました。
2024年『ふてほど』

「ふてほど」とは、テレビドラマ『不適切にもほど!』の略称。昭和から令和の時代にタイムスリップした主人公が価値観の違いに戸惑いながらも奮闘するコメディドラマである。
その面白さから瞬く間に人気を博し、放送された日には毎回トレンド入り。Creepy Nutsの主題歌『二度寝』もヒットし、河合優実は本作でスターの仲間入りとなった。確かにニュース番組や新聞などでは度々ドラマの人気にあやかって「不適切にもほどがある行為…」のような使われ方をしていた記憶もあるが、「ふてほど」という略称自体は全く聞いたことがない。きっと「闇バイト」や「性暴力」「裏金問題」が話題になった一年を象徴する言葉として「ふてほど」を選んだのだろうが、にしても無理やりだ。
ドラマで言えば、Netflixシリーズ『地面師たち』や朝ドラ『虎に翼』の方が圧倒的に話題になっていた。挙句の果てには、授賞式で主演の阿部サダヲが「自分たちでは一度も言ったことがない」と吐露してしまう始末。少なくとも例年はまだ野球界隈で流行った言葉ではあったものの、ここまで来るといよいよ流行語大賞の終わりが見えてきたような気がする。
この記事を読んでもらえば分かるのだが、今年の僕の予想は「50-50」か「もうええでしょう」のどちらかだろうと踏んでいた。授賞式の直前にも軽くパブリックサーチをしてみたが、やはりこのどちらかを推している声が多かった。あわよくばダブル受賞もあるだろうと思っていた。既に3年連続で野球用語を大賞にしてしまっていたから、今年は「50-50」を選びづらかったんだろうな…なんて思ったり。
Yahooニュースが行った『2024新語・流行語大賞、あなたが選ぶならどれですか?』では、4,750人が投票したうちの29.6%(1,405票)が「50-50」を選んでいた。圧倒的1位にも思われたが、意外にも「裏金問題」が27.3%(1,295票)と僅差まで迫っていて驚いた。
ちなみに「もうええでしょう」はたったの2%(95票)だったのだが、この言葉に関しては投票する媒体を変えれば大きく順位が動くと思う。というのも「はいよろこんで」や「猫ミーム」「BeReal」といった若年層向けのコンテンツが尽く下位に選ばれているので、X(旧Twitter)やInstagramを中心としたSNSで再度投票を呼びかけてみれば間違いなく上位に上がってくると思われる。
ちなみに「ふてほど」は0.8%(36票)で、かなりの下位。せめて「ふてにもほどがある」と正式名称で受賞させていれば印象は違っていたかもしれないのに、本当に勿体ない。結局「ふてほど」だけでは誰にも伝わらないし、これからも使うことは一生ないだろうな。
というわけで、「ふてほど」の大賞受賞は不服という結果になりました。
以上、「過去25年の新語・流行語大賞が個人的に納得かどうか考えてみた。」でした。かなり長くなりましたが、最後までご愛読ありがとうございました。
以下、僕の理想の流行語大賞一覧です。
2000年「おっはー」「IT革命」
2001年「小泉語録(米百俵・聖域なき構造改革・恐れず怯まず捉われず・改革の「痛み」・自民党をぶち壊す!・感動した!)」
2002年「タマちゃん」
2003年「なんでだろう」「マニフェスト」
2004年「チョー気持ちいい」
2005年「想定内(外)」「郵政民営化」
2006年「イナバウアー」
2007年「どげんかせんといかん」
2008年「何も言えねぇー」
2009年「トゥース!」
2010年「ととのいました」
2011年「ぽぽぽぽーん」
2012年「ワイルドだろぉ」
2013年「今でしょ」「おもてもなし」「じぇじぇじぇ」「倍返し」
2014年「ダメよ〜ダメダメ」
2015年「爆買い」
2016年「ゲス不倫」
2017年「忖度」「インスタ映え」
2018年「そだねー」
2019年「ONE TEAM」
2020年「密です(三密)」
2021年「ショータイム」「うっせえわ」
2022年「ブラボー!」
2023年「アレ(A.R.E.)」
2024年「50-50」「もうええでしょう」
