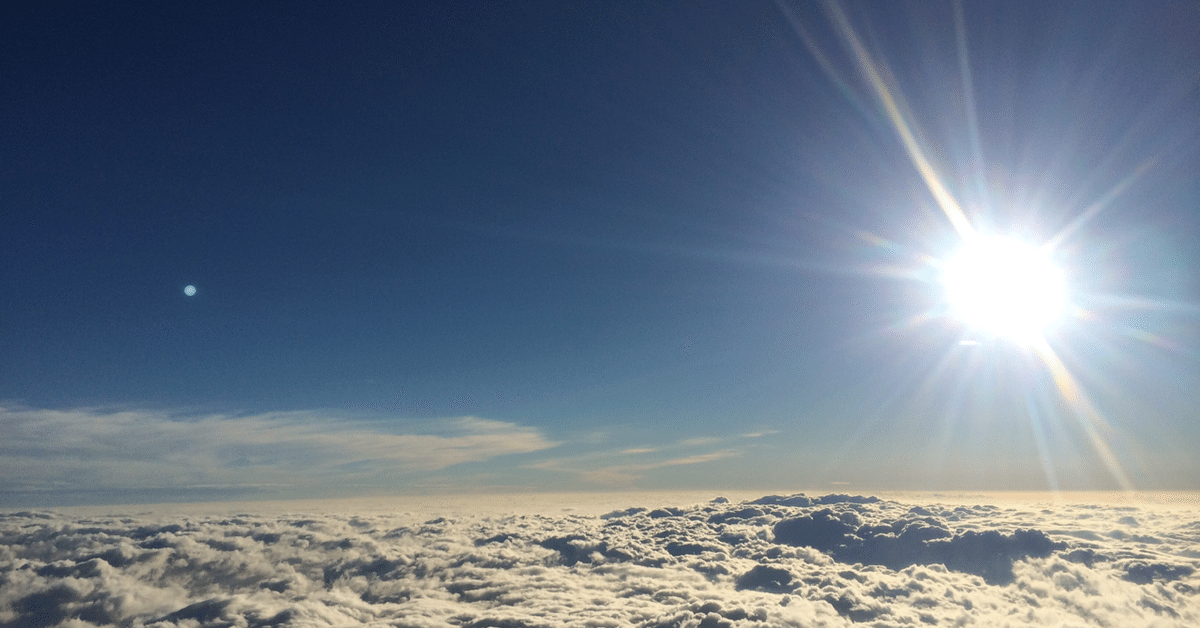
やっぱり、未来は明るいと思う
私が欲しいのはおカネではなく、みんなで迎える明るい未来。このご時世に何を?と思われるとは思うけど、ほんとにそうなると信じてる。
そのために(仮称)「知識共創社会」という本を書こうとしている。現時点で、身の回りの人たちの何人かは関心を持ってくれていそうなので、私にとってはそれで十分だけど、ひょっとしたらマルクスの「資本論」のような、多くの人を動かす本になるのかもしれない。
もし、本当に価値のあることなら、長きにわたって成長を続ける、サクラダファミリアのような本になると嬉しい。そのために、現時点のアウトラインを示しておこう。
私は(マルクスっぽいけど)そもそも社会の土台が変化しつつある、という共通認識を作ることから始めようとしてそう。
— 廣澤知也 (@hirosawatomoya) August 20, 2021
「知識論」と取れるようなものを書こうとしている気がする。
それゆえ、構造たる資本主義が変わりつつある、というところか。(用語あってるかな?)https://t.co/QDlkkElJ0p
以下に構成を簡単にまとめる。三分冊になるのか、第二編と第三編をそれぞれ二分割するのかは、成り行き次第と考えている。
第一編:基礎理論
知識共創社会の根幹をなす理論を整理する。基本的なパーツは、「ヒト・モノ・アイデア」の新しい経済学、SECIサイクルで表される知識創造理論、心理的安全性をもたらすのに大切なポジティブ心理学。だいぶコンテンツは差し替えるけど、着想を得たのは、ドラッカーさんの『ポスト資本主義社会』
また、知識共創社会の前の社会を支えた、資本主義と国民国家について振り返る。とくに、その原動力となった、資本主義について、その起源と衰退を(必要となる範囲で)追いかけたい。ここで、特に参考にしたのは、ウォーラーステインさんの『近代世界システム』
結果として、資本主義とそれに従属した国民国家は、知識共創と民主主義に取って代わられる、というのが私の見立てでもある。
この結果、以下のマクロなメカニズムとミクロなサイクルが説明されることになる。


第二編:共同体論と組織論
基礎理論に適合した、共同体と組織のあり方について整理する。共同体のありかたとしては、ベーシックインカムを導入した国の株式会社化が、重要な選択肢になると考えている。また、組織のあり方としては、ティール組織が望ましいと感じている。
第三編:日本のこれまでとこれから
このような知識共創社会に、必須となる民主主義が一朝一夕に成り立つものではないことを、日本の歴史を振り返ることで把握したい。おそらく100年単位の時間が必要となる。また、知識共創社会への移行に伴って、日本では、持続可能な社会・感染症に強い社会を構築できると思う。
参考文献
今後、いくつか差し替えるかもしれないけど、参考にしたのは以下の本たち。
いいなと思ったら応援しよう!

