
【実験・検証室】 012:線幅×階調×線数
「繊細な細い線で表現するデザイン」を印刷データにする際、その線はデータ上どこまでも細くすることができます(…と言っても限界はあります)。
しかし印刷することを想定しているなら、ある程度の線幅がある方が安心です。何故かというと、条件にもよりますが線がかすれる・線が消えるなどの不良を招く場合があるからです。

ネット印刷会社などでは、印刷データにおける線幅の推奨値を公開しており、条件にもよりますが、0.3pt(≒0.1mm)以上の線幅を推奨しているところが多いようです。
では条件とは何か。
細い線の印刷再現に関係してくるのは
・線の太さ(線幅)
・線の色の濃さ(網点の階調)
・スクリーン角度(網角)
・スクリーン線数(線数)
・用紙の種類
などが挙げられます(その他印刷段階でも諸条件はありますが今回は割愛)
この中で、イメージしづらいと思われる、
【スクリーン角度】と【スクリーン線数】について少しご説明します。
【スクリーン角度】は、CMYKの各色が持つ、任意の網点の角度です。
「網角」などとも呼ばれます。一般的には、CMKを30度ずらして、目立ちにくいYを15度ずらして重ねます。※1
この角度差は、モアレという網点の干渉による意図しない不良を避ける効果があります。
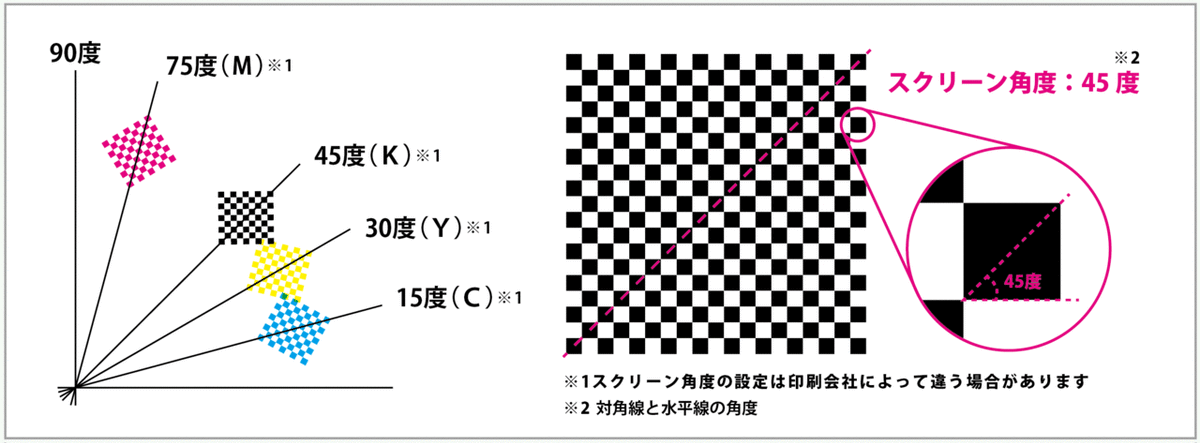
【スクリーン線数】は、印刷の精細さを表す尺度です。線数と略して呼ぶことも多いです。
各印刷会社の取扱商品や、各社の考えによりまちまちですが、一般的によく用いられるのが175線です。これは網点が“スクリーン角度方向に測定すると 1インチ(≒2.54cm)に175個入っている”という意味になります。
1インチに280個の網点が並んでいる場合は、280線ということです。

(補足)
お客様からご入稿いただく印刷用データは、印刷をするために印刷会社で網点化されます。スクリーン角度・スクリーン線数は共に網点化する過程で設定されるので、データ作成時に作成側が設定するものではありません。何らかの理由でスクリーン角度・スクリーン線数の指定がある場合は、印刷会社に相談してください。
細い線を表現するときに関わっていそうなこれらの尺度。
実際にこれらは線の再現性にどの程度関係しているのか、
実際に見てみないとイメージできない!
というデザイナーの皆様のために
検証
線幅と線数の組み合わせで、線の再現性は変わるの?
いくつかの網点の階調で比較してみよう。
検証スタート
事前模索
まずは、分析サンプルを幅広く集めるためのテスト印刷をすることにしました。
●線幅 Adobe Illustrator 2020 (ver.24.0.2)で作成できる最細幅の
0.001pt~ 確実に印刷で出ると経験上把握している1.0ptまで
●色数 スミ1色(スクリーン角度は45°)
●階調 白地(紙色)に、スミ100% / 80% / 60% / 40% / 20%の線と
スミ100% / 80% / 60% / 40% / 20%の地色に、白色(紙色)の線
●線数 弊社使用のRIP、ApogeePrepressで出力実績のある、
85線・175線・280線
●用紙 OKトップコート+ / OKトップコートマットN
OKプリンス上質 / ヴァンヌーボV スノーホワイト
●インキ 通常オフセット用油性インキ

網角による影響がわかるように、「正円」と「放射した線」を絵柄としました。こちらのデータで印刷テストをして、最終的な検証資料に採用する箇所を選定します。
結果、0.005pt以下は見た目ではほぼ違いがわかりませんでした。
これはオフセット印刷において、インキの標準膜厚が1ミクロン(=0.001mm=約0.0028pt)であることが関係しているかと思います。
網点にインキの膜が覆っているイメージをしていただけるとわかりやすいかと思いますが、上から見たときに線の幅は、だいたい(網点の幅+1ミクロン)x2の太さになるため、微細な網点においては差異が識別できないレベルであるからと考えます。
ちなみに、用紙による差異は若干はあるものの傾向はほぼ変わらない事から、検証物では1種類(コート紙)のみを採用します。
検証物

こちらを検証物として印刷します。
●線幅 テスト印刷で、太さによって差が見え始めた0.01pt~1.00ptまで
●色数 スミ1色(スクリーン角度は45°)
●階調 白地(紙色)に、スミ100% / 80% / 60% / 40% / 20%の線と
スミ100% / 80% / 60% / 40% / 20%の地色に、白色(紙色)の線
●線数 弊社使用のRIP、ApogeePrepressで出力実績のある、
85線・175線・280線
●用紙 OKトップコート+ (135kg)
●インキ 通常オフセット用油性インキ
印刷結果
印刷しました。

線数別(85線/175線/280線)3種類
まずは、全体的に見てみます。
実物を見ていただくとわかりますが、同じ線幅・同じ階調(網%)・同じ線でも、線が綺麗に出ていたり出ていなかったりしています。途切れ途切れになったり、消えてしまったりしていますね。
これは、前述した「スクリーン角度」が関係しています。

100%のベタの場合、網点と網点の間に隙間がないので問題ないですが、網の場合は、任意の場所にある網点の上をうまく通っている線は綺麗に表現され、網点を避けるような場所を通る線は途切れ途切れになったり、消えてしまったりします。

例えば線数が175線だと、145μm四方のスペースのなかで網点の大きさが変化していきます。
145μm = 0.145mm ≒ 0.4pt
一般的に言われている「線幅0.3pt以上」という条件は、この辺りから理解できます。
次に、線数別に比較して見てみます。
下の画像は【線幅0.05pt/スミ網80%】部分を線数ごとに撮影したものです。

実物を見ていただくとわかりますが、同じ線幅・同じ階調(網%)でも、線数によって見え方が違うのがわかると思います。
白地(紙色)にスミ80%の線で表現している方(右側)は線数が高い(高精細である)ほど線の途切れが少なくなっているのがわかります。
80%のスミ網に白線で表現している方(左側)は、線数が低いほど網点の存在が目視で確認できるため、明確な評価はしにくい状態です。
それぞれ同箇所を拡大(50倍ルーペで撮影)したのが下の画像です。

各線数の網点の大きさの違いが見えるかと思います。
線数が高い(高精細である)ほど網点が細かく配置されているため、前述したように網点の隙間を通る確率が少なくなり、線が途切れたり消えたりするリスクが減ることに繋がっていきます。
また、拡大した画像で見ると、網に白線を表現している方は網点がどの位置にあろうとも、白線が途切れていないのがわかります。ただ、網の%が低かったり線数が低い場合などでは、白線とのコントラストが低いために白線を視認しにくい状態になっていると言えます。
裏面
今回の検証資料はデザイナーのための印刷研究所初の、両面印刷です。
裏面には、線幅0.01pt、スミ40%のデータ上全く同じオブジェクトを等間隔で並べていますが、前述した通り、配置されている網点にデータの線がどのように掛かるかによって、線の出方が変わってくることがわかるサンプルになっています。

同じオブジェクトなのに、位置が違うと出方も違う
今回はスクリーン角度が45°なので、0° / 45° / 90° / 135°の角度のライン上では、線が全て同じ出方をしていることも見ていただけます。

点線上は見え方が同じ (スクリーン線数=45度のため)
補足
高精細にすると、網点が細かいため写真のように微細な表現が可能になったり、網点が重なる面積が減るために濁らずクリアな色再現が可能になるなどのメリットもありますが、インキの転移性が不安定になったり、特にシャドウ部分(色の濃い部分)のドットゲイン量が高くなるなど、色再現のコントロールが難しいというデメリットもあります。

網点を知ることで、繊細な表現における不安の解消にも繋がります。
実際の印刷資料で線の出方をご確認ください。
