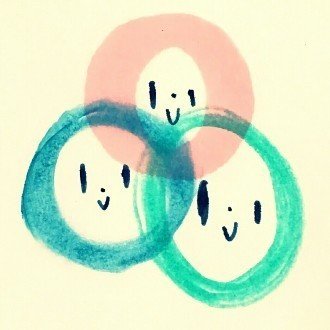[随想詩] 自己充足と相互承認としての世界
数学の世界の初めに空集合があるように、宇宙の初めには無限小の一点があり、空集合がゼロから初めてイチ、ニ、サンと無限への階段を歩み続けるときに、宇宙は一挙に爆発して素粒子の踊りを始める。
渾沌の玄妙空無なる道(タオ)から生まれいでたぼくたちは、不可思議な個別性を背負って旅に出ることになった。
個体という容れ物の中に臓器と魂を収めて、やがて訪れる死という次の旅立ちのときまでを、浮き世でヤドカリのごとく仮住まいをして過ごす運命だ。
ちっぽけや一つの命を携えてぼくらは、自分の欲求をどうにか充たすことから始めて、この世での姿を形作ってゆく。
そして自分というものの存在に気づくころにはすでに、他者という鏡に映された我が身というものが、もともとの自分からほとんど区別もできないほどに他者を自分の中に取り込んでしまっているのだから。
きみを認めることは、きみに映し出されるぼくを認めること。
ぼくを認めることは、ぼくに映し出されるきみを認めること。
だからぼくらは自分を充たすことで世界を充たし、互いに認め合うことで世界の残酷さをも認めることにする。
もしも地獄があるのだとすれば、この世界そのものが地獄に違いないと、あるとき気がついてしまったからには、この浮き世とかいうやつは、地獄にしてはなんて素晴らしく、なんて生ぬるい世界なんだろうと思うことにも度々なるわけだけど、地獄と天国の重ね合わせとしてのこの世界は決してフラットな空間ではないし、科学技術がフラットな領域を広げれば広げるほど、しわ寄せがシャープに際立ってゆく。
もちろん人間以前や人間以後の自然環境にだって、統計と確率に支配された無意味な偶然と不条理な必然によって地獄はそこかしこに現れるのだから、それをこの世の条理として認め、
「そういうものだ」
と受け留める以外に正しい態度は見つからないのだし、けれど、だけれど、と言ってぼくたちの中の三歳児は諦めきれずに駄々をこねるのです。
駄々などいくらこねても切りがないので、たとえ霧の中、前が見えなくてもダダとしてダダダとして、こねようもないのに無意識の底に眠る記憶の残像をこね続け、言葉では届くはずのないあなたの心の奥深くへと狙いを定め、虚空に散っていくばかりの言葉のつぶてを投げ続け、辛丑(かのとうし)の立春の日、ガンガーのほとり、菩提樹の木陰で、滔々と流れる水縹(みはなだ)色の水面のあちこちに白波のちらちらと立つのを眺めながら、しゃがみ込んだ足に少しばかりの痺れを感じていたのです。
いつもサポートありがとうございます。みなさんの100円のサポートによって、こちらインドでは約2kgのバナナを買うことができます。これは絶滅危惧種としべえザウルス1匹を2-3日養うことができる量になります。缶コーヒーひと缶を飲んだつもりになって、ぜひともサポートをご検討ください♬