
複雑な課題に困ったら、ディファインシートを書いてみよう[TOKYO CREATIVE COLLECTION]講演レポート
こんにちは、UIデザイナーの星野です!
2024/9/10に東京で開催された[TOKYO CREATIVE COLLECTION 2024]にて、UIデザインチームが所属するデザイン開発部の倉増ゼネラルマネジャーが登壇しました。
この記事では、講演内容とイベントの様子をレポートしたいと思います!

TOKYO CREATIVE COLLECTION とは?
TOKYO CREATIVE COLLECTIONはViViViTさん主催のデザインエキシビジョンです。 日本中のデザイナーやクリエイティブな人たちが集まり、それぞれが実践的なナレッジをシェアしあう、デザイナーにとって熱いイベントです。私も心を躍らせて参加しました!
会場に入ると、超満員で立ち見がでるほどの大盛況!次々と興味深いセッションが続き、弊社倉増が登壇する際も、大勢の方がメモを片手に集まってくださいました。

講演タイトルは「複雑さと対峙するUIデザイン」。
複雑化する課題に対して、東芝のデザイナーたちがどんなことを大切にして、複雑さと向き合っているかを、事例を交えながら紹介しました。
講演内容をレポートしますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

複雑さってどういうこと?デザイナーになにができるの?
簡単な東芝の事業紹介の後、「複雑さとは?」というところから講演が始まりました。
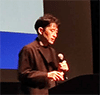
倉増:私たちデザイナーが直面する仕事は、どれもみんな複雑ですよね…。それは、ビジネスや技術、人の価値観(BTC)がそれぞれに多様化していて、相互に影響しあっているからです。なので、どれか一つに部分的に取り組んでも、思わぬ悪影響がでたり、頑張ってもムダになってしまったり…それが難しいところですよね。ではデザイナーはどう複雑さに向き合ったら良いのでしょうか?東芝のデザイナーは、どんなアプローチで取り組めばいいのか、どういうマインドで向き合うべきなのかといったデザイン活動の要件を定める際に「BTCを俯瞰する」ということを大切にしています。


ふむふむ、たしかに、年々課題が難しくなっている実感があります…。難しさに対してどういうアプローチをしているのか、東芝が進めるデジタル乗車券サービスによる新規事業の実証実験の事例を交えた紹介が始まりました。
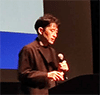
倉増:この実証実験にあたり、事業部門から来た依頼は、「改札機で使用されるQR乗車券の読み取り用タブレットの画面デザインをしてください」というものでした。
しかし、いきなり画面デザインを始める前に、このプロジェクトの目的に立ち返ってBTC全体を見渡して何をすべきか考えてみるというステップを挟みます。それが、東芝のデザインチームでやっている問いのリフレームです。


確かに私たちは定例のレビュー会を通じて、ビジネスや開発の視点で依頼内容を捉えなおす、ということをやっていますね。そのメリットについて、引き続き説明が続きます。
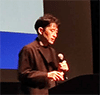
倉増:事業価値の検証という目的に立ち返って、改めてBTC全体を俯瞰しました。そこには、このプラットフォームを社会実装したいビジネスの狙いがあり、プロバイダーとユーザーをバランスよく集められるかが課題だし、顧客の鉄道事業者さんにとっては、それで利用客は増えるのか?とかオペレーションの課題は出てこないのか?が気になる。また、導入における技術的な課題はないか実現性を確認したいなど、BTCそれぞれの課題が見えてきたのです。
それに気づいたデザイナーは、当初の依頼だった画面デザインだけでなく、スコープを拡げることを事業部門に提案しました。この提案を理解してくれた事業部門と、改めてリサーチから課題の洗い出し、新たな要件の定義までを行うことが出来ました。

BTCを俯瞰することで、それまで見えていなかった別の課題が見えてくるということは私自身も経験がありますね。でも、依頼内容に対して事業部門にモノ申すのって、ちょっと勇気がいりますよね…!

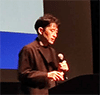
倉増:事業部門に対する「目的に立ち返ってみませんか?」という提案は、「え~そこから?」とか「それ必要?」といった反応が返ってくることもあります。しかし、デザイナーの仕事=画面のキレイ化や使い勝手を良くすることだけと思っている相手に対して、デザイナーがビジネス視点での提案や議論をすることは、“デザイン”の可能性を理解してもらう良い機会にもなります。これは、今後のデザイン業務や“デザイン”に対する期待の広がりにもとても重要なアクションだと考えています。

たしかに、地道に粘り強く相手に伝えていくことで、社内でも少しずつ“デザイン”というもの認識が変わってきました!デザイナーの活動の幅が年々広がっていることを実感しています。
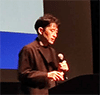
倉増:こうしたプロセスから、タブレットの画面デザインだけでなく、[サービス利用客を増やすためのポスターやWebサイト]のデザイン、[駅でのオペレーションの負荷を減らす駅構内の誘導施策]、[改札で滞留をおこさない画面デザイン]など、当初のスコープとは異なり、UIを広く顧客とのタッチポイントととらえた様々なソリューションに広がりました。

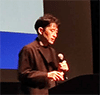
倉増:最初の依頼を、そのまま取り組んで終わることもできたかもしれない。でも、目的に立ち返って、BTCを俯瞰してデザインすべきことをみんなで再定義したことで、より本質的な効果のある様々な取り組みを実現することが出来たのです。

タブレット画面のデザイン依頼をリフレームして、コミュニケーションの施策に拡大していったということですね!
続けて、目的に立ち返るための仕組みとして東芝のデザイナーが使っている「ディファインシート」について紹介しました。
東芝のデザイナーが複雑さに向き合うための秘訣
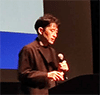
倉増:目的に立ち返って全体を俯瞰する習慣を身につけるために、私たちが使っているのが“ディファインシート”と呼んでいる一枚のシートです。左上には、ビジネスの狙いや技術導入の狙いなど、製品サービスのプロバイダーの意図を書きます。その下には、それを使うユーザーが求める価値や要求を書きます。そして右半分には、それらを成立させる為にデザインとしてやれること・すべきことをデザイン活動の要件として書いていきます。

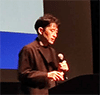
倉増:このディファインシートを、プロジェクトの始めや、要件定義や情報設計、表層のデザインなどの節目のレビューで、繰り返し使っていきます。最初は、左の狙いと右のデザイン活動の要件が整合しなかったり、依頼をそのまま書いてしまうなどうまく書けないデザイナーもいます。しかし、レビューの場でディファインシートに沿って繰り返しリマインドすることで、デザイナーたちはそれぞれの目的に沿った要件設定やそれと整合するデザインアウトプットが出来るようになっていきます。デザイナーの成長にも、効果的なプロジェクトの推進にもとても意義のある仕組みだと感じています。


私も「ディファインシート」を書くようになってから、提案の精度が高まってきたような手ごたえを感じています。個人でなんとなく思っているだけではなく、チームで共通認識をもって宣言することが具体的なアクションにつながるんですよね。みなさんにもぜひ試してもらいたいやり方です!
講演の最後はこんな話で締めくくられました。
“コンパス”を手にして複雑さに挑もう!
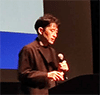
倉増:複雑さと立ち向かうには、「無意識の前提を疑ってみる」「目的に立ち返り問いを再定義する」「BTCの全体感をもってデザインする」、これが大切だと思います。もはや、目的地にたどり着ける正解のような地図はありません。目的を踏まえて、全体を俯瞰した大きな方針をコンパスのようにしてデザインしていくことが、複雑さに挑んでいく一つの方法と考えています。

講演を終えて
講演後には、社会インフラのデザインやデザインプロセスに関心を持ってくれた多数の方が、直接話をしに来てくださいました!

倉増:今回の講演の依頼を受けて、何の話をしようかと考えた時、最初に思い浮かんだのが「ディファインシート」でした。ディファインシートを使ったレビューを始めてから、UIデザインチームの成長を実感していたからです。
何をデザインするかは、私たちが決めるのではなく、BTCの掛け合わせの中で決まっていくものです。それらを俯瞰することなしには、うまくいかないと感じています。その視点があれば、間違った方向には進まず、突き詰めれば良い成果にもつながります。チームのみんながそれを証明してくれているので、今回共有しようと思いました。
正直なところ、こんな話に興味を持ってもらえるか心配でした。しかし、リアルな事例を交えた話には多くの方が興味を持ってくださり、講演後には大勢の方と色々な話ができました。私にとっても非常に有意義で、ホッとする時間でした。社会インフラのデザインに興味を持つ人が増え、東芝のデザインには成長の機会がたくさんあると感じてもらえたら嬉しいです。
いかがでしたか?
倉増ゼネラルマネジャーが登場する過去記事は以下です。社会インフラを担う企業のデザイナーとして、どんなことを考えてデザインに取り組むべきなのかをお話しています。
講演の中でご紹介した事例について、以下にも記事があります。デザイナー自ら語っておりますので、ぜひご覧ください!
では、また次の記事で!

