
東京一極集中からの脱却とは言うけれど、地方は何をしたらいいのか。
↓のオンラインセミナーでお話した内容をNoteにまとめた記事です。
※https://www.timr.or.jp/toshimondai/backnumber.html
【本講座のアーカイブ配信をこちらからご覧いただくことができます】
※2021年10月末まで公開
後藤・安田記念東京都市研究所YouTubeチャンネル

※2021.11.1 冊子になりました!こちらから購入できるそうです。
冒頭部分の椎葉村についての紹介はこちらの記事からご覧ください↓

今回こうした機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日は宮崎県椎葉村から繋いでおります。お時間を少しいただきまして、私の方からは椎葉村の実態について、それから、広井先生からございました、地域分散型社会についてお話しさせていただきたいと思います。
地方としては、分散型社会が良いと大変共感するところであります。
しかし、東京からすると「地方」は1500以上ある。
じゃぁ地方はどうすればいいのかについて、
私が今考えていることをお話しさせていただきます。

まずはこちらのグラフをご覧ください。

ひょうたん型ともいえる特徴的な形をしていますが、これは地域の特性上とある部分の人口が極端に少なくなっているのが原因です。
椎葉村には高校がないので、中学校を卒業すると全員椎葉村から外にでることになり、その部分の人口がいない状態になっています。
そして一回出た椎葉村出身者がなかなかUターンしないという厳しい現状もあります。
椎葉村は日本三大秘境といわれるほど山深い生活をしています。下の地図をご覧ください。

赤丸の部分が村の中心部で、村内唯一の中学校もこのあたりにあります。

それぞれの小学校までとても離れているし、それぞれの小学校区ごとに方言が残っているほどで、1つの集落は山に断絶されている立地です。村唯一の中学校では、生徒の7割が寮生。
この立地は合理的に考えると不便極まりない地域であることは間違いありません。
もっとローカルな部分に視点を移してみたいと思いますが、

私が住んでいる小崎地区の人口グラフです。20代から40代がこれだけしかいません。あと20年したら人口は半減し、集落維持の活動を行える人口は50人程度となります。
客観的に見ると、この先の暮らしが大変になることは明らかですが、当事者である私たちはどう感じているか…
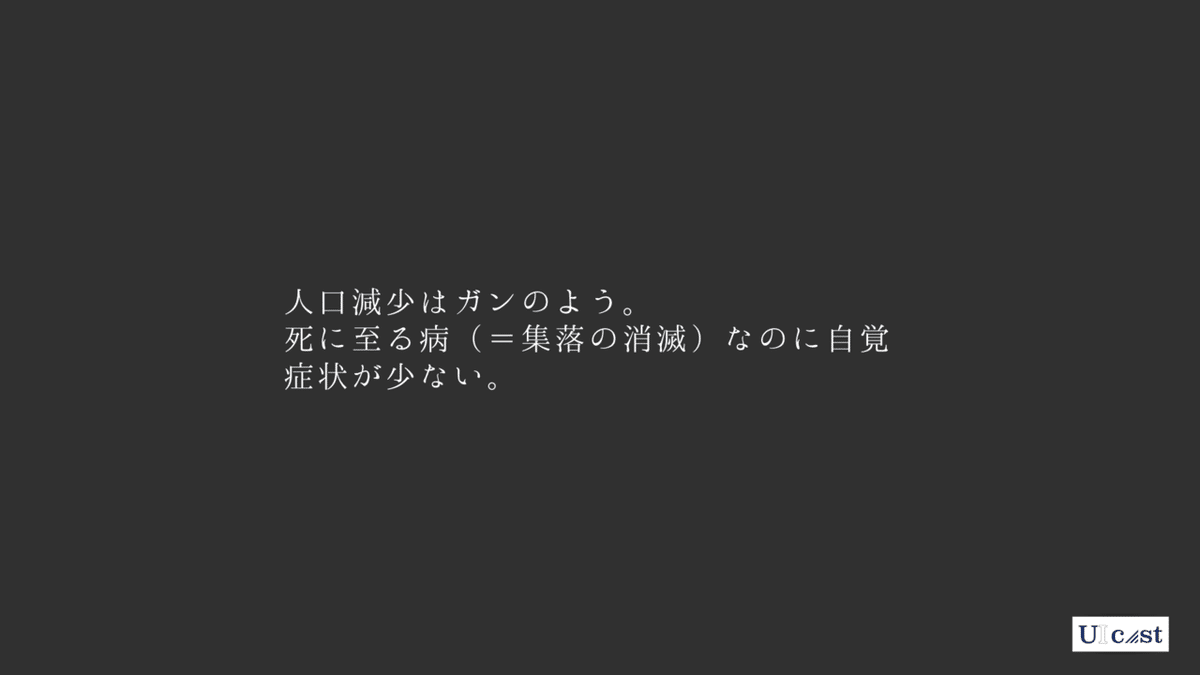
人口減少はガンのようで、死に至る病(=集落の消滅)なのに自覚症状がないというのが正直なところです。

当事者である私たちは「来年もきっとだいたいこのメンバーで神楽を舞い、似たような年になるんだろうなぁ」くらいの感覚です。
なぜなのか。

年を重ねて穏やかに亡くなっていく高齢者の死から、人口減少によって集落の存続が危機的状況にある自覚が全く生まれないからです。
高齢者が亡くなること=自然なことであり、災害などで多くの人が亡くなるような「悲しい事実」ではないからです。
伝統芸能の観点からも「自覚症状が生まれないこと」について考えてみたいと思います。

神楽を舞っている舞台の裏では、婦人会のみなさんが手打ちそばを作っています。
出汁をつくるのはAさんとBさん。
蕎麦打ちはCさん
火の番はDさん のように専門家がそれぞれに存在していて、この人たちだからこそ作れるとても美味しいお蕎麦を毎年みなさんに提供しています。
こうした「地域の伝統」は、高齢のため徐々に活動から退き、若い世代が継承した後、上の世代の人たちが亡くなる、というサイクルで受け継がれてきました。
引退しても聞くことができるから、切迫した状況(伝統が途切れる状況)にない。
ごっそりいなくならないからこそ、死に至る病(=集落の消滅)であることに気づけないのです。

これまで人口減少について、真剣にいろんなことを考えてきましたが、これをやったら改善するという特効薬はありません。
私はずっとここに住み続けたいと思っています。だけど半分になった人口で今と同じ暮らしなんてできない。このままだとただ住みたいのにそれが叶わなくなる時がきてしまいます。

これまで自治体(椎葉村)が一生懸命UIターン創出に取り組んできたことは重々承知しています。
でも、自治体任せではやはり限界があると感じています。だからこそ、もっとスモールでローカルな発想の転換が必要なのではないでしょうか。

令和2年に小崎小学校が閉校し、跡地になにを作るのか話が上がっています。
住民の方に意見を聞くと、「グランピングをしたら?」「ジップラインを作ったら?」「簡易宿泊を作ったら?」など、成功している他の地域の事例が目に付くようで、様々な意見がでます。
私は20年後に人口が半減する地区で住民主体の観光サービスを展開するなんて無謀すぎると感じています。

私たちに残されている時間と労力は限られているからこそ、わき目を振らず「移住定住」に注力すべきではないかと思っています。私が地区の人に提案したいのは「小崎地区ベッドタウン化計画(小崎地区人口1%戦略)」というものです。
中心部から少し離れた距離にあり、通勤などで不便を感じない立地です。
移住者が6世帯入っている小崎地区において、住民の気持ちを引っ張っていくためのみんなが達成をイメージできる実行可能な計画と指針をつくってみました。1年に2世帯ずつ増えれば、最低限の機能を維持することができます。
(追記:2021.07.19 地区計画策定ワークショップにおいて、「小崎地区人口1%戦略」を目標にしていくことが決定しました)

なぜ自治体主体ではなく、地区主体で行うべきなのか。

例えば、空き家バンクを例にとって考えてみたいと思います。
空き家バンクに登録したあと、変な人が入ってしまったら、その責任は貸主にあると考える方が多いようです。
全員知り合いの状況で、問題が起きないように保守的になる気持ちもわかります。ですが、「〇〇さん(あるいは役場)がへんな移住者をうちの地区に入れた!」という意識では、この問題は進展しませんし、集落は空洞化していきます。
そうではなくて、「地区として移住者を呼び込む努力をしている中で、このトラブルについてはどうしていこうか。」と考えられるようにするために、集落単位で空き家見込みについて計画的に考えていく必要があると思います。

集落の人が村外に向けて移住定住の促進をしていくのはハードルが高いので、村外から呼び込む部分は行政に任せ、集落は「定住させること」に注力していく方法を提案しています。
定住するためには、困りごとを解決できる「相談役」の存在が不可欠です。この部分まで行政職員がケアしていくことは現実的ではありませんし、異動のリスクもあります。
この役割を住民(地区)が持ち、一緒に住んでいく当事者として関係性を築いていくことが大切です。

私たちは今、間違うことはできません。
20年後にここに住み続けるためには、どの「地域」も知恵を振り絞らなければ「持続可能性」は途切れてしまうと思っています。
地域の方の諦めた気持ちを引き上げることから、一歩一歩着実に、思い描くゴールに向かえるよう実践していきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。
天野
