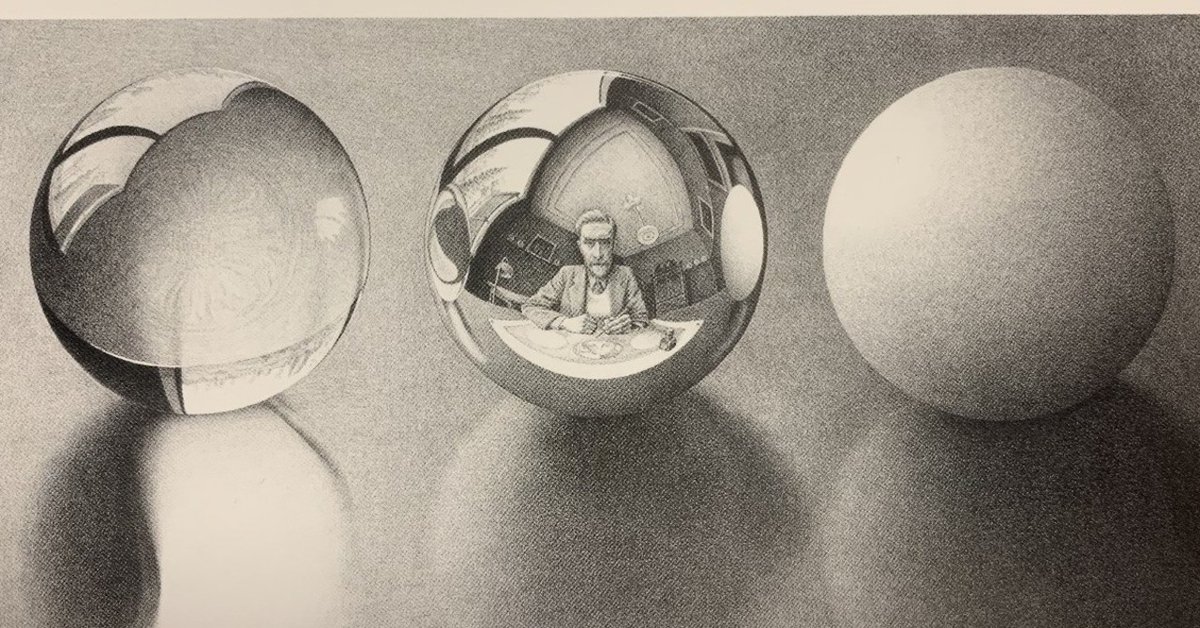
思い込みとどのように付き合うか?『知ってるつもりーー無知の科学』(3)
『知識の錯覚』が起こる状況は、周囲のもの・場所・環境や関わっている人々から生まれてしまう。
そして、『無知』『知識の錯覚』『知識のコミュニティ』こそがこの本の主題である重要なポイントだ。では、『無知』は悪なのだろうか?最初の記事においても書いたが、アクセルにもブレーキにもなる『無知』は必ずしも悪とは言い難い。
無知は腹立たしいものかもしれないが、問題は無知そのものではない。無知を認識しないがゆえに、厄介な状況に陥ることだ。
本文にはこう綴られ、本当の問題は無知に対して無知であることだ。そして、『無知と錯覚を評価する』ことが読者に勧められる。ただ、この評価ということばが厄介だ。
一口に評価と聞くと今までの学習の総括としてのペーパーテストや、給料を決める査定、など「一つのものさしで対象を断定的に計測する」という風に捉えられてしまうかもしれない。
しかし、ここで意味している「評価」はそれとは異なる。
英語で言うならば「assessment」
実はassessmentの語源は「sit(座る)」であり、assessmentの本当の意味は、「近くに座ってよく観察する」ということなのだ。
『無知と錯覚を評価する』ということは、「私のこの無知がだめ、この無知は良い」という風に断定的になるのではなく、「この部分が無知であり、この部分は錯覚であり、程度はどのくらいだ」という、「自分の無知や知識の錯覚を観察し、どのような状態か知るために情報を仕入れる。」プロセスのことを指しているのだ。
自分の思い込みを完全に捨て去ることは人間である限り難しいが、その程度を知ろうと努力することはできる。そうすることで、許容できる範囲に失敗をとどめ、改善点を明確にし、行動し続け、成功へと至るためのコツとなるのかもしれない。
いいなと思ったら応援しよう!

