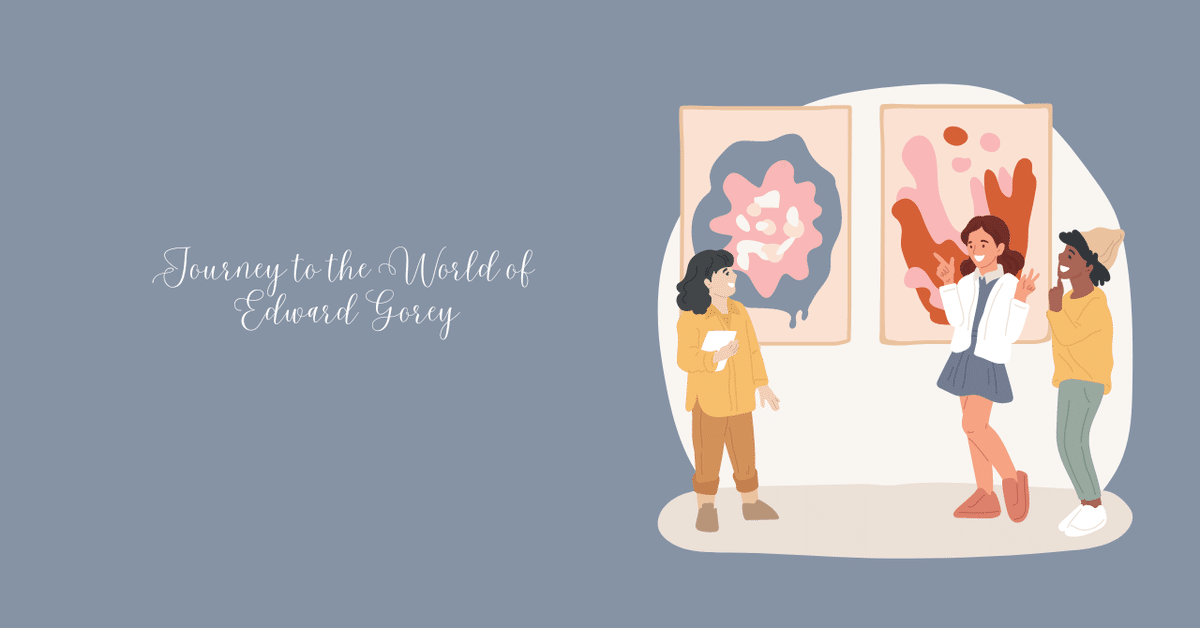
エドワード・ゴーリーを巡る旅
先週末、電車に揺られて、奈良まで「特別展 エドワード・ゴーリーを巡る旅」を見に行ってきた。

数年前、黒い傘を差し、黒いシルクハットをかぶった死神と、その前にたたずむたくさんの子どもたちの集合写真のようなイラストに、言い知れない恐ろしさと、ゾクゾクする魅力を覚えた。
アルファベット順に子どもたちが一人ずつ非業な死を遂げていく、『ギャシュリークラムのちびっ子たち』という絵本の表紙だった。
この作品は誰が作ったんだろう?と興味を持ったのが、絵本作家 エドワード・ゴーリーとの出会い。
それから図書館で絵本を借りて、どんどんダークな世界観に惹かれていって……。そんなときに、今回の展示会を知った。
最初は横須賀ですると聞いたもんだから、「関西ではしないのかなぁ」と残念に思っていたのだが、奈良ですると聞いてからはワクワクが止まらなくなり、初日の次の日に行ってきた。
まず、びっくりしたのはゴーリーの絵の緻密さ!
今まで絵本でしか見たことがなかったので原画を見るのが初めてだったのだけれど、原画は思ったよりも小さな紙に描かれていて、その中に線画のような点描のような、とにかく細かく細かくペンが入れられていた。
なに、この世界観!
基本的に黒と白のモノクロなのに全然単調じゃなくて、表現力が豊かなこと、豊かなこと。どうやったら、空とか、波の様子とか、あんなにドラマチックかつ繊細に描けるんだろう。
そして、わかるようでわからない絵の数々。じーっと見ていると、沼にはまっていくようになる。こうやってゴーリーの世界から抜け出せなくなっていくのか。
後、驚きとともに納得したのは、ゴーリーが日本好きだったということ。
彼は日本に来たことがないけれど、日本の文学や絵画が好きで、源氏物語は愛読書だったそう。
ゴーリーの絵の中にも日本文化の影響が見られるそうで、例えば、『ずぶぬれの木曜日』では、日本の浮世絵のように雨が線で表現されている。
ゴーリーの絵を見ていて、どことなくメランコリックというか、懐かしさ、もの悲しさを感じるのは、日本の「もののあわれ」が入っているからなのかなぁ……なんて思ったりした。

最後に、ミュージアムショップで『音叉』という絵本を記念に買った。
考えてみるとけっこう恐ろしい物語なんだけど、展示で見たときに、主人公のシオーダが海の底で出会った怪獣の上に勝ち誇ったように乗っているラストの絵が心に残った。
音叉というと演奏前に音程を取るために使う器具だが、なんで音叉という題なのかははっきりとは書かれていなかったように思う。
だけど、この絵本を読んでいると、ボワンボワーンと波紋のように何かが広がっていく感覚を覚えた。後味が良いような悪いような、シオーダも勧善懲悪なキャラクターとは言えなくて。でも、手元に置いておきたい一冊だと思った。

シオーダは、これで良かったんだろうか。
月夜に思いを馳せる。
