
SESから自社プロダクト開発へ ~スタートアップへの挑戦~
トドケール社員を紹介する入社者インタビューシリーズ。今回は、トドケールが提供するSaaSの開発を担う保田和馬さんに、入社の経緯やトドケールでの仕事内容について伺いました。
■ 自己紹介
保田 和馬(Hoda Kazuma)
三重県出身。筑波大学大学院で理論物理学を専攻し、新卒から6年ほど派遣技術者としてAWSとバックエンド開発に従事。2024年8月にトドケールにジョインしてからは、前職の経験を生かしてインフラとバックエンドを担当している。大阪オフィスのゴミ箱にピッタリ合うゴミ袋を日々探し求めている。

ー 現在の仕事内容を教えてください。
トドケールではバックエンド開発とインフラ構築・運用を担当しています。具体的な職務としては、新しい機能の開発や顧客の要望に応じたシステムのアップデートのほかに、システムのコスト削減やパフォーマンス改善など、エンジニア目線で改善可能なポイントを見つけて優先順位をつけて日々対応しています。
ー トドケールと出会うまでのことを教えてください。
自分は三重県の出身ですが、大学院が茨城県だったので、就職は自然と東京になりました。正直に言えば、就職活動はあまりうまくいかず、卒業後は技術者派遣の会社に落ち着きました。仕事の中で開発業務への興味が強くなり、インフラとバックエンドを軸に勉強して、技術を磨くようになりました。
技術者派遣では長期間お客さんの会社に常駐してAWSとアプリ開発をしていました。色々とやらせてもらえる環境はとても面白かったのですが、6年も経つと段々、「これでいいのかな。。。?」と考えるようになっていきました。同時に、技術者派遣の会社では自社の社員という立場と派遣先の技術者という2つの立場があり、そろそろ「派遣社員を管理するマネージャー」になるか「現場技術者のリーダー」になるかを選ぶ必要が出てくる時期に入るはずが、自分は現場で一人で好きに開発作業をしていたことで、そのどちらのスキルも十分に身についていないと感じるようになりました。一時期、ほかの現場のスタッフの管理や評価を任されたこともありましたが、正直上手くできたとは思えませんでした。
そんな中でもっと事業の中で仕事をして、自分の多面的なスキルを磨きたいと思って転職活動を始め、トドケールに出会いました。
■ 入社して感じるスタートアップの醍醐味
ー 次の職場にトドケールを選んだ理由を教えてください。
転職先を選ぶ時の軸は自社プロダクトであることはもちろんでしたが、そのほかには以下の3つだと思います。
プロダクトの内容と成長性
会社の雰囲気
技術スタック
まずはプロダクトの内容と成長性ですが、初めてトドケールのサービスを聞いたときは想像もしなかった領域のユニークなサービスだと思いました。ただ、総務の現場の仕事を効率化すると同時に社員の負荷も減らすことができる、さらにはそこに集まる社内荷物の情報を使って色々な拡張性があるのではないかと可能性を感じました。
会社の雰囲気は当時のCTOの方とお話をして、とても良い雰囲気だと感じました。ただ、スタートアップにはよくあることなのかもしれませんが、CTOの方がとある事情で私が入社したときには退社してしまっていました。入社直後はこれからどうなるのか少し不安でしたが、そこから会社の体制を立て直すことに危機感をもってコミットするチームには団結力を感じました。
また、入社半年程度にも関わらず、会社の成長に合わせて自分の給与額が上がったり、資金調達で社内の雰囲気やプレッシャーが変わっていく様子には自分がスタートアップで働いていることを実感しました。今は自分の成長以上にこれからの数年間で会社がどう変わっていくのかが楽しみです。
技術スタックは前CTOの方からお話を聞いていて、自分がこれまで培ってきた技術を存分に生かすことができると感じて選考に進みましたが、オファー面談の際にバックエンドやインフラ関連の大きなプロジェクトがあるということを聞いて是非やりたいと思い入社を決めました。新機能の開発のみでなく、顧客の増加に合わせてインフラ構成自体を変えてしまうなどの大胆な構想を聞いていましたが、現在実際に全部とっかえるくらいの覚悟をもってプロジェクトが進んでおり、刺激的なチャレンジができていると感じています。

■ エンジニアとプロダクトが同じ方向を向いている
ー 前職もエンジニアをしていたと思いますが、いわゆる派遣で働くエンジニア(SES)と自社サービスを作るエンジニアにはどのような違いを感じますか?
エンジニアとしてどちらが良いということはないですが、違いがあるとすれば、今の立場ではエンジニアとプロダクトが同じ方向を向いていると思ってます。
例えば、今はAWSの料金(コスト)を下げるための改善であったり、レスポンス速度を改善する改善だったりを日常的に行っています。特にレスポンス速度のようなシステムの基本的な性能は顧客に利用を継続してもらうためには重要で、売り上げに直結する要素だと思っています。週次のスプリント報告で空いた時間に改善を実施したことを報告すると、「ありがとう」のような感謝の声をビジネスサイドからもらうことができます。
振り返って、派遣でエンジニアをしていた頃はそういったレスポンス速度の改善ポイントを見つけても、プロジェクトとして予算をもらっていなければ手を付けることができませんでした。
また、細かいデータの持ち方などもこれまでは「実際どう使われているのかはさておき、こうして欲しいらしい」というところまでしか(工数的にも)踏み込めない場面もありましたが、今ではむしろ「わからないまま進めると絶対にあとで苦労する」というマインドセットで仕様の理解や新機能の設計に臨める環境があります。
また、顧客との距離という観点でも大きく違うと思います。委託で開発を受けているときは、プロダクトのエンドユーザーとお話をする機会はあまりなく、私は委託元からもらう仕様に沿ってプロダクト開発をしていました。そのような体制では、開発した機能が顧客からどのような評価を受けているのかはわかりませんでした。
今はカスタマーサクセス(CS)の方が顧客からのフィードバックを集めてきてくれるので、ビジネスサイドと連携しながら今のプロダクトに磨きをかけることができています。
実は最近トドケールは大阪にサテライトオフィスを開設しており、大阪在住の私はサテライトオフィスに出社したり、自宅から作業をしたりというハイブリッドで働いているのですが、月に1回はビジネスサイドの方が大阪に出張に来ます。その時にはカスタマーサクセスが隣で顧客と打ち合わせをしているのを聞いて、「自分が作った機能がどのように顧客に利用されているのか」を知ったりすることもできました。ビジネスとプロダクトという2つのチームが相互に連携しながら、顧客の声に基づいてプロダクトを改善していくというプロセスは受託開発では経験できないものだったと思います。
ー 現在働いているチームについてどう思いますか?
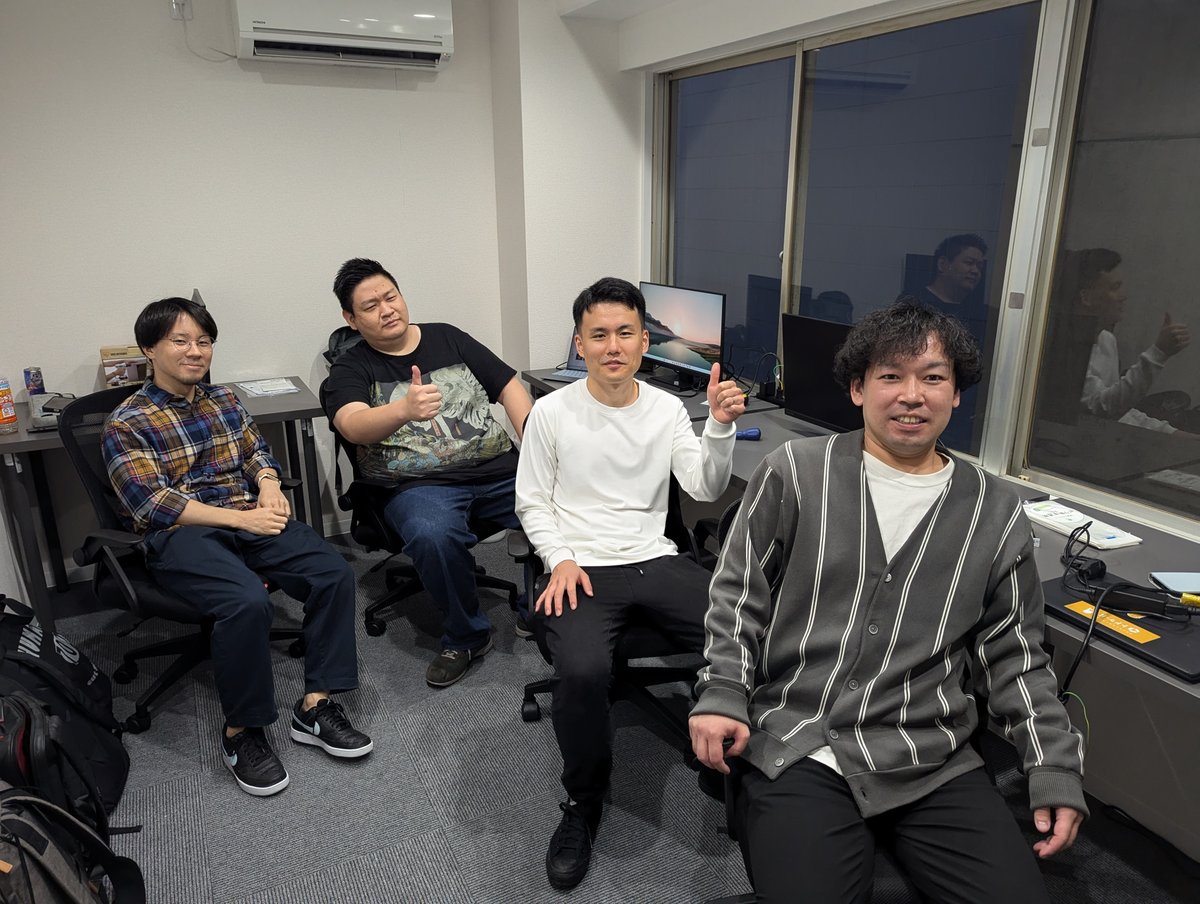
最初、3人しか社員のエンジニアがいないと聞いてびっくりしましたが、QAなどを外部に外注したりと効率化をしていて、意外と回るなという印象です。細かい実装とかについてはそれぞれの責任で行っていますが、システム全体の問題については課題感を共有できていて、ディスカッションをする際にも問題の概要くらいは全員が理解しているあたりにスモールチームの良さを感じます。そして、完全に分業というわけではなく、複数のエリアに手を出しながらお互いを助け合い、チームとしてうまく機能できていると思っています。自分もインフラとバックエンドが基本ですが、それ以外をやらないと言うわけではありません。トドケールが掲げるバリューにある「境界線を越える」という言葉の意識を感じることができる瞬間が多くあります。
ー 最後に自分の目指すエンジニアのキャリアと応募を考えている候補者の方へトドケールのアピールポイントを教えてください。
今後、自分としてはインフラとバックエンドをさらに極めていきたいと考えています。AWSの知識やアーキテクチャの知見など、そういうところのナレッジをもっと蓄えたいと思っています。
アピールポイントは、色々なチャレンジができることだと思います。すでにある程度の規模で動いているものがあって、それを一回ぶち壊して作り変えるくらいのチャレンジをしようとしています。大胆な取り組みに興味がある人は是非応募してほしいです。改善ポイントがいくらでもある状態だと思うので、自分のプロダクトへの貢献を感じられる瞬間に興味がある人は是非応募をご検討いただけると嬉しいです。
