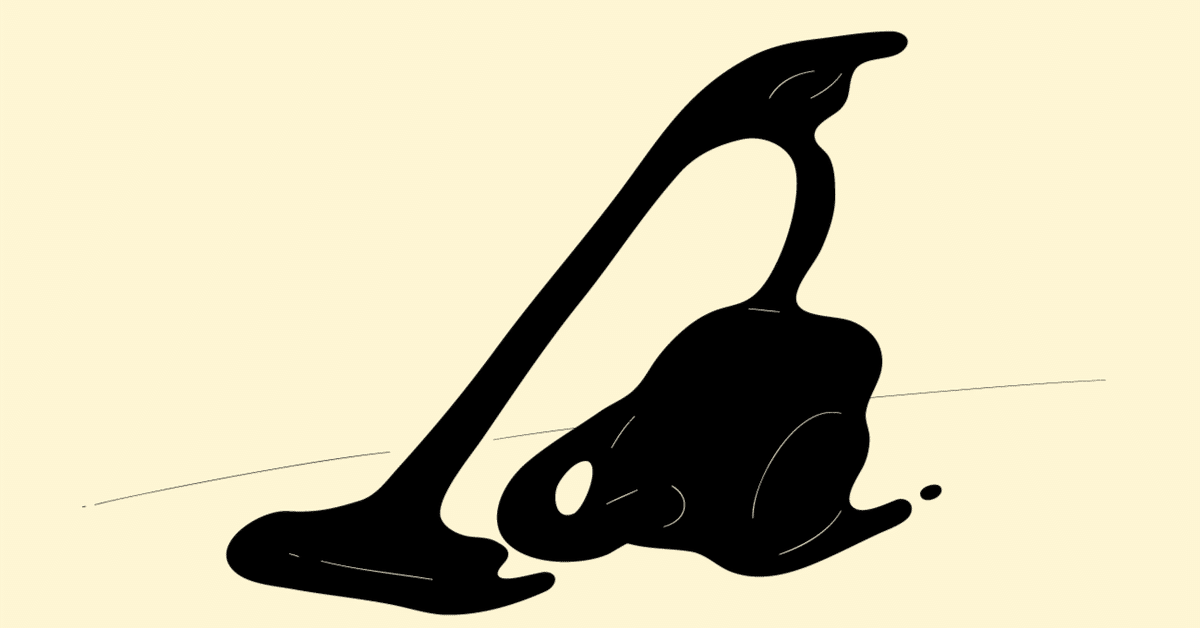
掃除機かけについて調べてみた。
訪問介護員として現場で掃除機かけをするようになって、いつか調べようと思って調べてなかった正しい掃除機かけについて今日は調べてみました。
掃除機かけなんて誰も教えてくれないし、正しいと言われている方法を知っておくと色々いいかなぁと思いましたので。
部屋のお掃除では、掃除機をかける手順が効率に影響してきます。
掃除機がけで鉄則なのが、入口に対して、部屋の奥の方から手前に向かってかけるということ。
部屋の入り口から奥に向かって掃除機をかけてしまうと、せっかく掃除をした部分を歩いたり、掃除機が移動することによって、ゴミを広げてしまいます。
また、部屋をいくつかの長方形にブロック分けをして、ブロックごとに掃除機をかけていくと、効率的に進めることができます。
実際、靴下にゴミがくっついてたりして運んでしまうので、掃除機をかけた後は踏まないようにしていますが、僕は結構気になるので2回くらいは往復させて掃除機をかけています。1回の往復じゃ取り切れない事の方が多い印象です。
で、僕自身はブロック分けしてブロックごとに掃除機をかけてます。
なので、掃除機かけをした後に踏まないように区分けをイメージして、踏んだ場合は踏んだ場所を改めて掃除機かけてます。
あんまり考えすぎても時間が勿体ないので、いまでは直感で初めてしまう事の方が多いのと、長い方なら1年近く掃除をさせてもらっているお宅もあるので、そういう意味ではかなり効率的になったと思います。
あとはダイソンの吐き出す排気が強力すぎてゴミをまき散らしてしまうパターンもあるので、排気の向きも注意が必要な時があります。
手早く掃除機をかける方法として、ゆっくりかけるというのは、矛盾していると思われるかもしれません。
ところが、短いストロークで素早くかけた方が、ゴミを吸い残しが多く、さらに疲れてしまうため、あまり効率的とはいえないのです。
吸い口を前に出して手前に戻す、1往復にかける時間の目安を5秒ほどにすると、掃除機の吸引力がきちんと発揮されて、少ない回数でキレイになります。
これも実際にゴミがちゃんと取れるのは記事の通りでゆっくり前後させた方がよく取れます。
ただ、素早く動かしている方がテキパキ仕事してる感じが利用者さんにあるので、そういう感じの方の場合は、テキパキやりつつで緩急つけて利用者さんが見ても満足してもらえるように、実際にゴミも取れるように工夫はしています。
換気は掃除機がけが終わった後に
掃除機は床に落ちたゴミを吸い取る道具のため、ゴミが舞い上がった状態では効率よく吸い取れません。掃除機をかけるときは部屋の窓を閉めた状態で行いましょう。
なお、同様の理由から、可能であれば扇風機やエアコンも止めておきます。舞い上がったゴミは掃除機がけが終わった後に窓をあけて外に出しましょう。
これは知らなかったしあまり意識してなかったので勉強になりました。
なるほど、窓開けながら掃除機かけるのが普通のような感じがしていましたが、終わってから換気した方がよさそうですね。
掃除機をかける時間帯は朝がベスト
チリやゴミを吸い取るために掃除機をかけるなら朝がベストです。とくに、家族がいるなら、ほかの人が起きる前に掃除機をかけてしまいましょう。
ゴミは人の動きや空気の流れにより舞い上がるため、日中は空気中に浮遊しています。しかし、就寝時など人の動きが落ち着くと、ゆっくりと床まで落ちてきます。
そのため、他の家族が寝ているうちに掃除機をかけると、効率よくゴミを吸い取ることが可能です。
これもちょっと驚き。
朝イチでの掃除機かけ、みんな寝てるさなかの掃除機かけ!
たしかにゴミが落ち着いている状態ってみんな寝静まってしばらく経った後ですもんね。
当事業所でもお一人だけ8時のお掃除で伺っていますが、ご本人も朝イチから綺麗になって昼間はやりたい事出来るのでありがたいって言ってもらえています。
ダニ退治の掃除機がけは夜がオススメ
カーペットや畳など、ダニ退治と掃除機がけを一緒にしたいなら夜がオススメです。ダニは夜行性のため、日中はカーペットなどの奥に身を潜めています。
しかし、夜になるとエサを求めてカーペットや畳の表面に出てくるため、そのときにダニ駆除剤などを使用し、合わせて掃除機をかけると効率的です。
ダニは夜なんだぁ・・・。
いずれにしても昼間の掃除機かけって一番非効率って事なのかぁ・・・。
ダニ退治については、遮光カーテン等で部屋を暗くしても似たような効果が得られるとの事なので、部屋暗くしてやるのもいいですね。
早朝も夜間も掃除機の騒音は気になりますしね。
部屋の奥からドアの順番でかける
部屋の奥からドアに向かって掃除機をかけると、一度お掃除したところを再度通らなくてよいため効率的です。まずは、部屋の奥まで掃除機を移動させましょう。
押すだけでなく引くことも意識
掃除機は押したときにゴミを掻き出し、引くときに掻き出したごみを吸うため、押すだけでなく引くことも意識することが大切です。このとき、ヘッドと床が平行になっていることも確認してください。
掃除機をかけた部分に重なるようにかける
また、掃除機のT字ヘッドは中央部分の吸引力が強いため、左右は吸い残しの可能性があります。ヘッドの左右が通過した部分も、もう一度、ヘッドの中央部分で吸い込むことでキレイにお掃除できます。
たしかに引くときの方がよく吸う気がしてました。
やっぱりヘッドの部分でも真ん中が一番吸うんですね。
ちゃんとゴミを吸ったか目視しながら往復させてるので、あまりヘッドの部分を重ねるというのは意識した事はなかったです。
掃除場所に合わせてノズルを付け替える
掃除機はヘッドのアタッチメントを変えることで、よりお掃除しやすくなります。先端が細くなっているすきまノズルは、家具の間やソファの隙間のゴミ取りに適しています。
また、ブラシの付いたブラシノズルを使用すれば、ゴミを掻き出したり、小物類の吸い込みを防止したりすることが可能です。そのため、フィルター類や、サッシの溝、家具の上のゴミ取りがしやすくなります。
ヘルパーで使うとしてもスキマノズルくらいかなぁ、掃除機本体にブラシがついてるのがあれば取りにくい埃とかは使いますけど、スキマノズルが手軽かなぁ、ないお宅もあるし、逆にスキマノズルだけしかないお宅もあったりします。
あと気を付けているのは、フローリングや畳の上に絨毯やカーペットが敷かれている場合、あまりに大きいのは外周に掃除機のヘッドを入れて吸うようにしています。小さいマットとかはどけて下も掃除機をかけますけど。
フローリング
フローリングはゴミが舞いやすいため、先にドライタイプのフローリングモップをかけてから掃除機がけをするとよいでしょう。これで、床のゴミが舞い上がるのを防止しながらお掃除できます。
溝にそって一方向に掃除機をかけると、入り込んだゴミが取りやすくなります。
フローリングのゴミは、隅の方に溜まるため、人通りの少ないところほど、念入りにお掃除しましょう。
フローリングの部屋は確かに四隅や家具のスキマにゴミがたまりやすい印象です。
しかも小さい塵のようなゴミが掃除機で吸えてない場合もあるので、拭き掃除は絶対やった方がいいですね。板の間の拭き掃除はやってて明らかに綺麗になるので楽しいですし、立ってると見えない汚れやゴミも良く見えて綺麗にするのが本当に楽しいです。
カーペット
カーペットやラグは毛足の間にゴミやダニが溜まりやすいので、十字に掃除機をかけるのがポイントです。
始めに、全体を一方向に掃除機がけします。終わったら、向きを90度かえ、今度は横から全体に掃除機をかけていきます。このとき、パワーは強にしておきましょう。
縦・横に掃除機をかけることで、埋もれたゴミもしっかり吸い取れます。
カーペットは十字なんですね。
ゴミが取れにくい場合は十字にかけてましたが、今度から十字を意識してみようそうしよう。
畳
畳は目に沿って優しく掃除機をかけましょう。目に沿うことで、ゴミが取りやすくなるだけでなく、畳が傷みにくくなります。また、畳と畳の間などは、すきまノズルのヘッドに変えてお掃除すると効率的です。
畳みのスキマはスキマノズルが大活躍ですね。
畳みはなぜか十字で掃除機かけてましたね、結構傷つきやすいみたいなので優しく掃除機かけるようにしよう。
掃除機をかける頻度
掃除機をかける頻度は家族の人数や状況によっても異なるものの、目安は3~4日に1回です。このくらいの頻度だと、掃除機がけの負担を軽減しつつ、キレイな状態を維持できます。
もし、共働きで家に居る時間が短いご家庭なら、1週間に1回、週末にまとめてお掃除すれば問題ありません。
また、小さなお子さんやペットを飼っている家庭では、毎日掃除機をかけていることもあるでしょう。もし、電気代を節約しつつキレイをキープしたいなら、雑巾などのほかの掃除道具との併用がオススメです。
普段はフローリングモップや箒、粘着シートで目立つゴミを回収し、3~4日に1度念入りに掃除機がけすれば少ない回数でもキレイな状態を維持できます。
週1回の掃除のお宅が多いのですが、毎週掃除に伺ってますけど、結構ゴミたまってますから記事のように3~4日に1回くらいのペースがベストかもですね。
ただ、同じ独居の方で、同じ週1回のお掃除でも、ごみのたまる量が全然違ったりするので、そういう掃除だけとっても同じ環境っていうのは無いんだなぁって思っています。
かけ方ひとつで吸い取り量が変わります。
やりがちな例としては、力を入れてゴシゴシと素早く動かして掃除機をかけている方をよく見かけます。
これでは、掃除機の性能を発揮しきれないばかりか、疲れる割にゴミの集塵量も少なくなります。
掃除機をかけるスイングスピードは、使用機種や床材によっても異なりますが、基本的に畳一畳分を約8往復(3分の1重ねがけ)で40~48秒、一往復5~6秒以上かけてゆっくりかけます。
参考例ではありますが、ペット雑誌「ねこのきもち」編集部と簡易的な実験をしたところ、掃除機をゆっくりかけた時とやりがちな例の時とでは、ゴミのとれる量に大きな差が出ました。
やはりゆっくり往復させるのがベストのようです。
記事の方にはゆっくりと手早くやった場合のゴミの量の写真もあるのでよかったら参照してみてください。
しかし、一往復5秒となるとかなりゆっくりですね。
やりがちな例として、ゆっくりかけていても手前に来ると早くなったり、前後のスイングスピードがばらばらだと、汚れの取り残しにつながります。
スイングの前後幅については、「往復路とも同じ場所を通り、スタンス肩幅、1歩踏みだした姿勢でラクにスイングできる程度」が安定して良いと思います。
その後、横移動して同じ動作を繰り返し、むらなく掃除機をかけます。
この際に、手を引きすぎたり押し出しすぎたりすると、ノズルが浮き上がり汚れの吸い取り量は減少するので注意しましょう。
引くときの方が吸い込みが良いので、引くときこそゆっくりを意識した方がよさそうです。
T字ノズル(ヘッド)を裏から見ると、吸い込み口は中央にあります。
そして機種により構造が様々あります。
通常タイプの他に、タービンブラシなど回転ブラシ式と言った、各メーカーや機種により工夫されているものもあります。
この、ヘッド形状によっても掃除機操作に違いが出て来ます。
機種により違いはありますが、基本T字ノズルは左右の両端に行くほど吸引力が落ちやすい構造となっています。
汚れの取りこぼしをなくすためにも、往復路の後に横移動して、T字ノズルは重ねてかけると良いでしょう。
おお、やっぱりT字ノズルは重ねかけが良いみたいです。
最近の掃除機は、勝手に前に行くやつとか、びっくりするくらい軽い掃除機とかあるので面白いですけど、T字のノズルは大して変化ないというか、ほとんど同じ形状ばかりですね。
こちらの記事ではカーペットの毛の倒れている向きとかもチェックして掃除機をかけるとよい内容などもあるので、結構本格的な内容になってますので、よかったら参照してみてください。
流石にヘルパーの支援でそこまでは限られた時間内では難しいので、僕にとって必要な情報はこのくらいかなぁ。
ちょっと明日からの掃除で今日の学びを活かしていきたいと思いました。
