
【連載】Fredの「あさがや人文知」〜オンボーディング編〜
悩むことを手放さない経営者、Fred(フレッド)。スタートアップ経営はそもそも迷うことの連続だが、Fredはその逡巡を歓迎しているように見える。悩むことは苦しいこと。であるなら、悩みは無くしたいと思うのが人間の本能のはずである。
しかし、苦しみに止まり続けるFred。なにが彼を突き動かし、どうしてそんなことが可能なのか。答えはきっとFredが学んできた「人文知」の中にあるに違いない。そう見立てを立てた同じく悩みがつきない人事担当・Cap(キャップ)が、どうせなら自分の悩みに付き合ってもらおうと、Fredと一緒に悩み合う連載企画をスタート。それがこの『あさがや人文知』です。
第2弾のテーマは「オンボーディング」。TimeTreeのオンボーディング施策についても交えながら、Fredの中で蓄積・発酵された人文知からヒントを得たいと思います。一緒に悩んだ先に何があるのか、それともなにもないのか。きっと答えは提示できませんが、ぜひ一緒に悩んでいってください。
コミュニケーションにバフをかける『ニックネーム制度』?

──まず今回『オンボーディング』をテーマとして選んだ理由から話しますね。オンボーディングって大切なものだ、という社会的な共通認識があると思っていまして、TimeTreeでも様々なオンボーディング施策を行っています。
そうですね。
そんなオンボーディングについてFredと一緒に考えることで、オンボーディングの新たな価値や、今後TimeTreeが行うべきオンボーディング施策のヒントが得られたらうれしいと思っています。と、いうわけでオンボーディングって大切ですよね?
大切だと思いますよ。
──改めてオンボーディングの重要性を言葉にすると、どういったものになるでしょうか。
なんだろうね。まだ自分の中の話すエンジンがあったまってないのでつらつら話していくけど、ウチの施策だと『Welcome Program』があるじゃないですか。
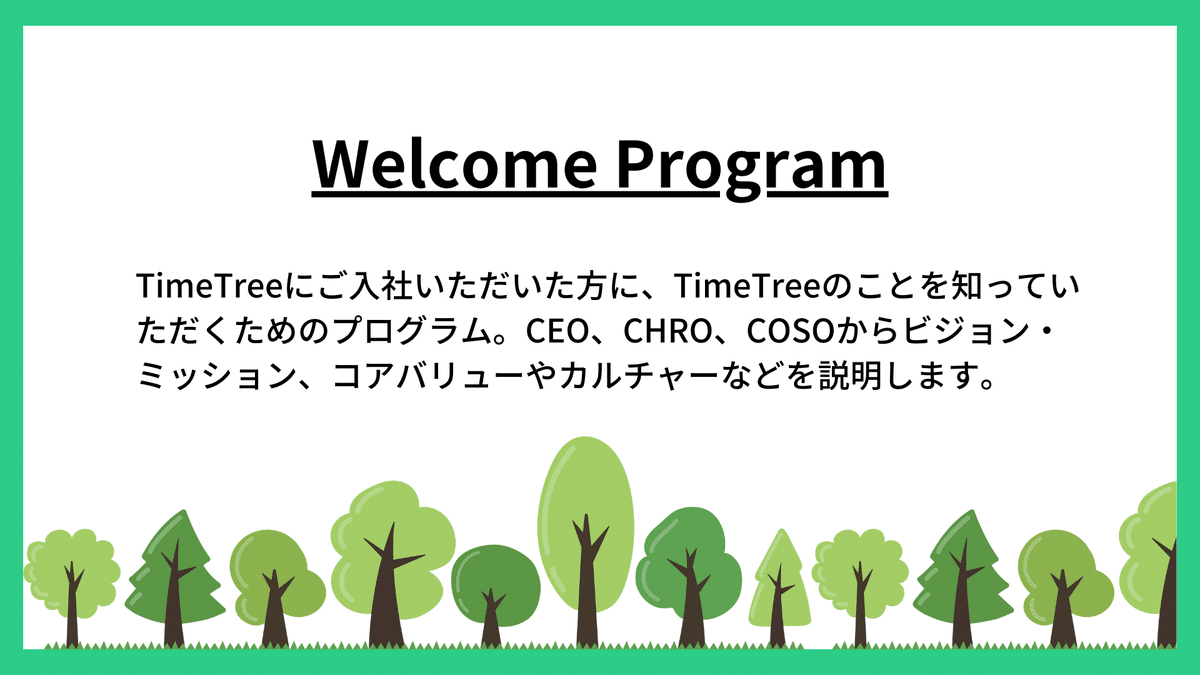
あれはなんのためにやってるかというと、TimeTreeのミッションやビジョンを腹落ちしてもらうためなんだよね。ミッションとかビジョンって会社のHPを見にいけば書いてあって、それを読めばある程度理解はできる。
けど、完全に理解してもらえてるかというと、そうじゃないと思ってて。完全に理解という表現が正しいかわからないけど、ミッションやビジョンはそこに至った経緯や思いがたくさん詰め込まれているので、ちゃんと説明しないとわかってもらえないものなんだと思っています。
会社によって目指しているものって全くの別物なので。そのことをまず知ってもらって、早く馴染んでいただくためにやってる。それがオンボーディングの重要性にも繋がるんじゃないですかね。
──なるほど。
あとはTimeTreeの特徴的な施策として『ニックネーム制度』がありますよね。元々は僕がカカオジャパン時代に採用されていた施策なんだけど。出向2週間前ぐらいに「自分のニックネームを考えておいて」と言われて焦った記憶がある。
──僕はTimeTreeではじめてのニックネーム制度を体験しているんですけど、最初は違和感ありました。自分のニックネームを決めるのは意外とむずかしいですし。Fredはニックネーム制度に違和感なかったんですか?
あんまりなかったんだよね。というのも、バンドやってた時に同じような体験をしてたから。本名で呼ばれることはなくて、その時のニックネームだったり、バンド名そのもので呼ばれることもあった。
──バンド時代にニックネーム制度を経験してたのか……。
ニックネーム制度の良いところは、気軽にコミュニケーションをとってもらえることなんだよね。例えば、僕はコミュニケーションがあまり得意ではなくて、会社の上司や同僚と距離を縮めることがむずかしいタイプなんです。
けど、ニックネームで呼び合う会社だと「自分はコミュニケーションが苦手である」って思わないんですよ。なぜかというと、僕の本名は「深川(ふかがわ)」なんだけど、そうすると当たり前なんだけど、上司や同僚からもずっと「深川くん」と呼ばれるんですね。
けど、すぐにあだ名で呼ばれる人っているじゃないですか。コミュニケーションが得意で、周りと打ち解けるのがはやい人。あだ名をつけてもらうことによって、さらに人から声をかけられやすい存在となっていく。
──はい。
僕はそっちのタイプじゃないので、制度として強制的にニックネームをもらうことによって、自然と声をかけてもらえる存在に近づけると思うんですよ。
──おもしろい!
「深川くん」ではなく「Fred」になると、不思議と壁がなくなって声をかけやすくなる。人間が変わるわけではないけど、「深川くん」と「Fred」は異なる存在なんですね。だから声をかけやすい存在になれて、コミュニケーションにバフをかけるというか、そういったメリットがあると思っています。
──分人主義的な発想ですね。
そうそう。上司の懐に飛び込むのがうまい人や、同僚の輪に自然となじめる人なんかはそういったメリットを感じにくいかもしれないけど。僕みたいに苦手な人は効果を実感できると思いますね。
──……僕はおそらく前者な気がします。
Capはそうだよね(笑)。
──なのでそういったコミュニケーションにバフをかける、みたいな視点はなかったので目から鱗でした。僕が感じているニックネーム制度の良いところは、先ほどの分人主義的な話にも通ずるのですが、その人のバックボーンを良い塩梅に消してくれるところだと思っています。
その人がどこの大学を卒業して、前職でどんな仕事を成して、みたいな過去の経験をうまい具合に薄めてくれる。僕は今年の2月入社なのですが、TimeTreeって本当にフラットな関係性のある会社だと感じていて、その要因としてニックネーム制度はとても大きいと感じています。最初は「え〜ニックネームか〜!こわいな〜!」と思ってましたが(笑)。
たしかに。弟が文化人類学者なんだけど、パプアニューギニアでフィールドワークした際、集落に入る時に名前をもらったらしいんだよね。なんだったっけな……。「鳥の名を関する…鳥と狼のなんとか…」みたいな。ちょっと今思い出せないんだけど。
──『BLEACH』みたいでかっこいい。
適当なこと言うと弟に怒られちゃうな。それもニックネーム制度に近い話で。ようは「これまでとは異なる場所にあなたはやって来たんですよ」というメッセージでもあるわけですよね。
「忘れる」社会って良さそうじゃない?

さっきの集落の話でいくと、集落の外に出ていく話も興味深くて。大前提として、僕はTimeTreeのメンバーに辞めてほしくないと思ってます。当たり前だけど。けど、実際そうはいかないじゃないですか。
──そうですね。
組織をコミュニティとして考えると、コミュニティ内のメンバーが固定されてる状況もよくない。そうなった時に、良い見送り方も考えた方が良い気がしてて。
──なるほど。おもしろいですね。
ある集落では居づらくなった人は集落からふらっと出ていき、となりの集落に移動するらしいんです。そしてほとぼりがさめた頃に、自然と元いた集落に戻ってくる。だから集落から出ていくことを大袈裟に扱わないんです。
──すごい。
それぐらいカジュアルに人の移動があってもいいと思うんですよね。転職してその会社と水があわないことってよくある話だと思うので。
──環境を変えて輝くことって多々ありますからね。
集落の話でいうともう一個おもしろい話があって。Aという集落に鯛夢釣子(たいむつりこ)氏がいるとして、その人がBという集落の家族として迎え入れられたとする。その後、残念なことに鯛夢釣子氏人が病死したら、A集落は激怒し武器を持ってB集落に進行するらしくて。
怒りの雄叫びをあげながら進行するから、B集落はめちゃ恐怖しながら生活することになる。
──おだやかじゃないですね。
結末としては、A集落はB集落はいく道すがらで満足し、引き返すらしいんです。
──なんと。
怒りが発散されるんでしょうね。
──疲れもありそうですね。
ありそう。何が言いたいかというと、こういう「発散する」とか「忘れる」っていう行為がシステムとして組み込まれているのが良いなと思ったんです。
──なるほど。とかく今は『デジタルタトゥー』という言葉があるように、忘れることが構造的に許されない社会ですもんね。
ね。そう言えばこの前『TimeTreeラヂオ』で『哲学クラウド』の上館さんと「許し」について話してたんだよね。やばい、オンボーディングとかけ離れてきちゃった。
──この企画らしくていいと思いますよ。ちなみに、今話してもらったカジュアルに外に出ていくことが実装された社会において、オンボーディングはどのようになっていると思いますか?
う〜ん。変わらないんじゃないかな。
──(笑)
デタラメを言える。それが良いオンボーディング?

──今回オンボーディングがテーマだったのでずっとオンボーディングについて考えてたんですけど、「どういうオンボーディングを提供すればいいか」といった会社目線でしか考えていないことに気づきました。
なるほど、たしかに。
──そのオンボーディングが効果があったのかどうかって、受けた本人じゃないとわからないし、かつ、効果があったかどうかは後になってからしかわからないものだなと。そこで、新入社員の方がどういった状態になってれば「オンボーディングが成功した」と言えるのかを考えてたんです。Fredは『乱数発生法』って聞いたことありますか?
はじめて聞いた。
──僕は精神科医の中井久夫さんが好きでよく本を読んでいるんですが、『乱数発生法』は彼の著書の中で紹介されていたものです。相手の精神状態をはかる手法で、といってもむずかしいものではなく、1〜9までの数字をデタラメに言ってもらうシンプルな方法。「1、8、4、6」といったように。
どういったシーンで使われるかというと、一個の例としてヒマラヤに登る山岳部を想像してください。数人のチームがレシーバーで連絡をとりながら登っている。登頂するかどうかのときに、リーダーがメンバーに『乱数発生法』を行います。「数字をデタラメに言って」と。
そこでメンバーが「1、2、3、4、…」と言ったら「すぐに下りなさい」、となるらしいんです。つまり、デタラメを言えない状態ってのはかなり危険な状況であると。
おもしろい。
──これは登山に限った話じゃないと思うんです。オンボーディングの話にこじつけると、新入社員の方がデタラメを言えるかどうか、冗談を言えているかどうか。それが「オンボーディングが機能しているか」のひとつの指標になるのではないかと。
たしかに。おもしろいね。オンボーディングを受ける側の視点、僕も忘れてたかも。今の冗談を言えるかどうかの話でいうと、僕が言ってる「スベるのも仕事」は的を得ている気がしてきたな。
──だと思いますよ。CEOがスベることによってメンバーが発言しやすく、冗談を言える雰囲気が作られると思うので。
心理的安全性の話にもつながるよね。いいね。「新メンバーが冗談を言えているかどうか」は目安になりそう。思えば『First MTG』もそこに寄与している気がする。

──そういえば先週、前職の同僚と会ったんですが、TimeTreeのオンボーディング施策について話したらその手厚さに驚かれたんですよね。この力の入れ具合はどこから来ているのでしょうか?
もしかすると転職に対する認識の違いかもしれない。僕にとって転職はひとりでインドに行くようなもので。
──ははあ。
場所はもちろん言葉も文化も違う。そんな場所にひとりで行くわけだから困って当たり前だと思うんです。
──そうか、「転職の重さ」が違うのかもしれないですね。会社によって人も共通言語も組織文化も異なり慣れるのが大変だと思うので、僕も転職は「インドに行く」派です。
新たなコミュニティに入るってことだからね。集落の話に戻すと、弟はパプアニューギニアにフィールドワークに行った時に、誰かの家族となってコミュニティに入ったらしくて。
もちろん、転職はそこまで重い話ではないけど、そういった面もあると思う。こういった考えはTimeTreeの『メンター制度』にも生かされていると思います。

──2人のメンターをつけるのも珍しいですよね。けど、ひとりでインドに来ているのなら妥当な気もしてきました。
オンボーディングは社会実験?

──なんというか、TimeTreeってその人の丸ごとを尊重する文化があるじゃないですか。人の統合性を重んじるというか。
そうだね。けど、やさしさでやってるわけじゃないんですよね。その方がメンバーが自身のリソースを最大限発揮してくれると思ってるんです。例えばウチには『ブルーロック』が好きで推しているPdMがいますが、その熱量や知識を活かして「推し活」関連の企画をしてくれたりとか。
そういったことって、その人が個性を発揮してくれてないと実現でき
ません。そして、個性を発揮してもらうにはビジネスパーソンとしての側面だけでなく、プライベートな側面も出せる環境じゃないとむずかしい。Capの言うところの統合性を大切にしているのにはそういった理由があります。
──やさしくするのが目的でなく、個人を丸っと尊重することがパフォーマンスを最大化させることにつながると信じていて、それを実行してるってことですよね。
まさにそう。社会実験をしてるイメージ。
──時間も迫ってきたので最後にそれっぽいことを聞かせてください。TimeTreeのオンボーディングの課題や「今後こういうふうにしていきたい」などあれば教えてください。
そうだな……。パッと思いつかないけど、強いて言えば僕ももっと関わりたいと思っているんですが、忙しくてできてないってことですかね。むかしはウェルカムプログラムもひとりでやってたんだけど、忙しくなってメンバーに頼って分割してもらいました。
──なるほどなあ。どうしましょう。Fredに分裂してもらうとか。
AIの分身つくって、分身がスベるとか。
──スベるためのAI良さそう。あ、ちょうど時間ですね。Fred、本日はありがとうございました!
ありがとうございました!
「オンボーディング」について悩むための一冊
Cap推薦
インタビューでも触れた中井久夫さんの著書です。精神科医として活動された中井先生の叡智が凝縮されています。治療としての話ではあるのですが、日々の生活に生かせるノウハウや考え方がたくさん記載されています。組織に興味がある人もきっと楽しめる一冊です。
Fred推薦
文化人類学ってどんなもの?というのを知りたい方にぴったりの教科書です。いろいろな社会において、自然とは?性差とは?血縁とは?死とは?なんなのか?どのようなものとして存在しているのか?などについて書かれています。
