
クラスでの話し合い
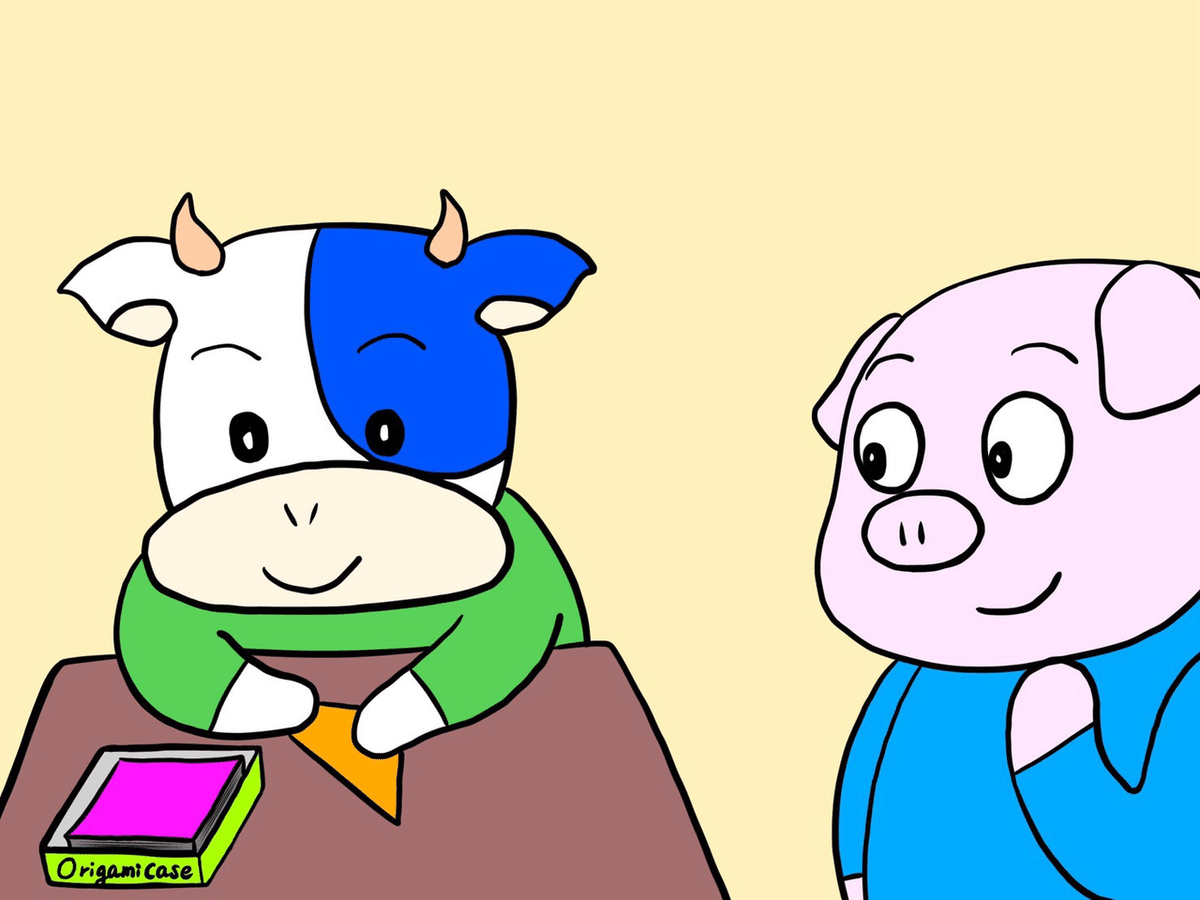
ウシはいつも休み時間になるとひとりで教室のすみっこでおり紙をおっていました。
あるとき、ブタはそんなウシに話しかけてみました。
「ウシくん、いつも何を作っているんだい?」
「あ、ブタくん。花をおっているんだ。」

ブタはウシの手先のきようさにおどろき、作り方を教えてほしいとウシにたのみました。
ウシはえがおでうなずき、毎日、ほうか後のだれもいない教室でブタとおり紙をしました。
ふたりは友だちになりました。
ある日、がっきゅういいんをきめるための話し合いがクラスで行われました。

手をあげたのはニワトリとウシでした。
ニワトリはクラスの人気もので、友だちがたくさんいました。
一方、ウシは友だちが少ないので、クラスのみんなはウシがりっこうほしたことにおどろきました。
みんなは、たすうけつできめることにしました。
「ニワトリくんがいい人!」
はい、はい、はーい!
たくさんの手があがりました。
じつは、ウシとニワトリのどちらがいいかきめられないクラスメイトもいましたが、まわりの子につられてニワトリに手をあげていました。
「ウシくんがいい人!」
ウシに手をあげる人はだれもいませんでした。

ブタは、ウシががっきゅういいんにふさわしいと思っていました。
おり紙をおそわっている中で、ウシのわかりやすくせつ明することができる力を知ったからです。
しかし、ニワトリに手をあげるクラスメイトにつられて、ニワトリにひょうを入れてしまいました。
だれかが言いました。
「やっぱり、ニワトリくんの方がいいよね!明るいし!」
「うん!ウシくんって何考えているかわからないし!」
「なんでりっこうほしたんだろうね?」
「目立ちたかったのかな?」
「ブタくんもそう思うよね?」
ブタは言いました。
「う、うん。そ、そうだよ…。そうだよ!ニワトリくんがいいにきまってる!ウシくんはがっきゅういいんなんてむいてないよ!」
みんなのいきおいにおされて、ブタはつい思ってもないことを言ってしまいました。

その日のほうか後、ブタはウシにあやまりに行きました。

しかし、ウシはわらって言いました。
「だいじょうぶだよ。ぼくは友だちが少ないから、みんなは人気もののニワトリくんをえらぶだろうと思っていたよ。
もしがっきゅういいんになったら、にゅういんしているおばあちゃんに知らせてよろこばせたかっただけなんだ。
かわりに次のテストでいい点をとって、おばあちゃんをよろこばせることにしたよ。
それに、ブタくんの立場もよくわかるよ。
みんなが同じことを言う中で自分だけちがうことを言うのはむずかしいからね」
ブタは見すかされたような気もちになりました。そして、ウシのことがもっとすきになりました。
「ウシくん、きみはすごいなあ」

次の日、学校がおわると、ブタとウシはおり紙の花たばをウシのおばあちゃんにプレゼントしに行きました。
ウシのおばあちゃんは目を細めており紙と子どもたちをこうごに見つめ、うれしそうにわらいました。
解説
バンドワゴン効果とは、まわりの人がしているから自分も同じことをしようという心理が働き、その行為をする人が増えれば増えるほど、さらに需要が高まるという作用です。この物語では、何人かのクラスメイトはウシとニワトリのどちらに票を入れるかはっきりと決まってはいませんでしたが、多くがニワトリに手を挙げたために、ニワトリの方に人気が集中しました。
没個性化とは、集団の中で自分への注目度が低下した状況下において、普段は抑制されていた非合理的、刹那的、攻撃的、反社会的な行動が発生しやすくなるという現象です。この物語では、多くのクラスメイトがウシを悪く言う中でブタにも同じ行動が求められ、ブタは咄嗟にウシを悪く言いました。
何を選択するかは自由ですが、周りに流されて主体性を失ってはいけません。何が最もふさわしいのか、何があなたやみんなの利益になるのか、自分で考えて選択しましょう。周りの風潮に抗うのはこわいかもしれませんが、せめて、自分の行動によって誰かが傷つかないように気を配ってみましょう。
参考:"bandwagon"
David McRaney."Deindividuation"
