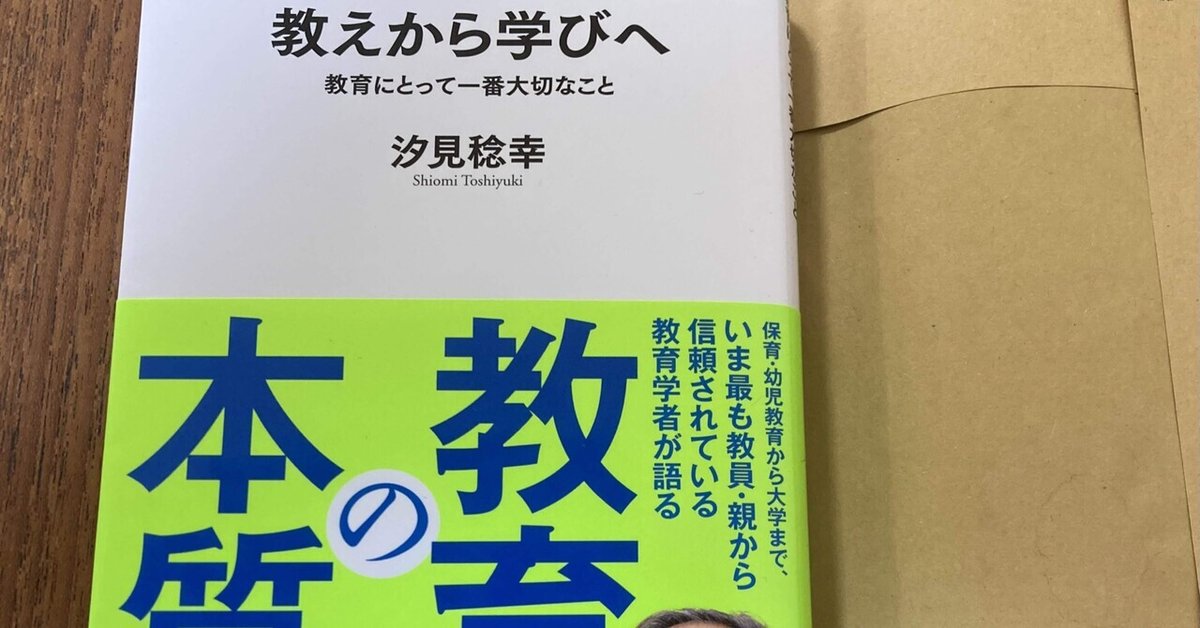
ブックレビュー【教えから学びへ 汐見稔幸著】
この本をとにかく読んでほしいと、とある友人が言ってきました。
noteにブックレビューを書くのは初めてです。緊張します。
端的に言うと、素晴らしい本でした。全ての教育関係者(とくに若い人)に読んでほしい本でした。
教員時代に私はこのようなことをよく考えていました。
「指導案って書く意味があるのだろうか…」
学習指導案とは、「児童生徒の学びたいこと」と「教師の教えたいこと」をつなぐための設計図です。
引用:http://www.manabi.wakayama-c.ed.jp/tokusi/sse_hb05gaku.pdf
引用すると、以上のようになるようです。
「児童生徒の学びたいこと」と「教師の教えたいこと」をつなぐ設計図…
そもそも、指導案っているのか?いらなくねw?と思いながら、書いていました(笑)なので、私は下手くそ…指導教諭の先生には「かんべ先生はいつまでたっても上手く書けない」と匙を投げられていました。。。あはは。
指導案は「教え」をどう深めるかというものだと思っていました。つまり、引用部の後者の部分です。それって、自分が起こり得ること(子どもたちがやりそうなこと)を事前に想定して、その器の中で子どもたちを転がすこと?って考えていました。それってどうなの?少なくとも、私は先述にようには考えていませんでした。
「教える」から「学び」へ移す
汐見先生は、冒頭部分から、
原理を「教える」から「学び」に移せばいい
汐見稔幸『教えから学びへ』河出書房新社、2021年、P6
とおっしゃっています。
主体は誰なのかというのが大事な観点かと思います。主体はやはり「子ども」であるべきです。
私の教員時代も、「教員である自分がどのように教えるか」ばかり目がいっていました。
「教える」ことよりも「学び」にフォーカスすることで、子どもに焦点がいきます。子どもの考えは十人十色。そこに教員は身を委ねれば良い。(それを教員が上手くファシリテートできるかが腕の見せ所)
「当事者意識」をもつこと。
2030年は「VUCAの時代(予測困難「Volatility」で不確実「Uncertainly」、複雑「Complexity」で曖昧「Ambiguity」)」と言われている中で、PISA(学習到達度調査)を出しているOECDはキーコンピテンシーから進化して、エージェンシーという概念を重要なキーワードとして発表しました。
OECDは、「変化を起こすために、自分で目標を設定し、振り返り、責任をもって行動する能力」と定義しています。
筆者はエージェンシーを「当事者性」と訳しています。
自分自身が困っていることを理解し、人に助けてもらうところを明確にし、そして自分の中にある良さを認めていく。そうすれば、そのことを理解してくれる人たちがいるコミュニティで助けを求めることができるようになり、それまで困っていたことも困らないようになっていくのです。
汐見稔幸『教えから学びへ』河出書房新社、2021年、P67
「当事者意識」をもつためには、座学だけでなくあらゆる体験を通して、自分ごとに落とし込んでいく「学び」が必要なのかと感じました。
「語義」と「意味」を区別すること
著書では、言葉の意味には、「語義」と「意味」に分かれると主張されています。
私は、
「語義」とは「第三者も理解できる言葉の意味」
「意味」とは、「自分個人が感覚的に理解できていること」
というように私は理解しました。
「意味」より「語義」に重きを置きすぎているのではないかと主張されています。
意味は、一人ひとりが独自に持っている好奇心や感性によって、周囲の世界や他者に対してある価値づけをしていくことで見出されるのです。
汐見稔幸『教えから学びへ』河出書房新社、2021年、P154
語義は語義として、意味は意味として、分けて考えること。
意味を自分のものとするように体感的に得られる学びを提供することが大事なのは私も共感しました。
自分が考えたこと、まとめ
友人が教えてくれたこの本は目から鱗が落ちる名著でした。何度も読むべき本です。
子どもが自分事として、世界を見つめる体験を何かできないか。
あらゆる体験を通して、学びを提供できるように自分ができることは何だろうか。
自分たちも自らが主体となって、学び続けねばならない。
これらを感じました。
