
できるときに、できることを。
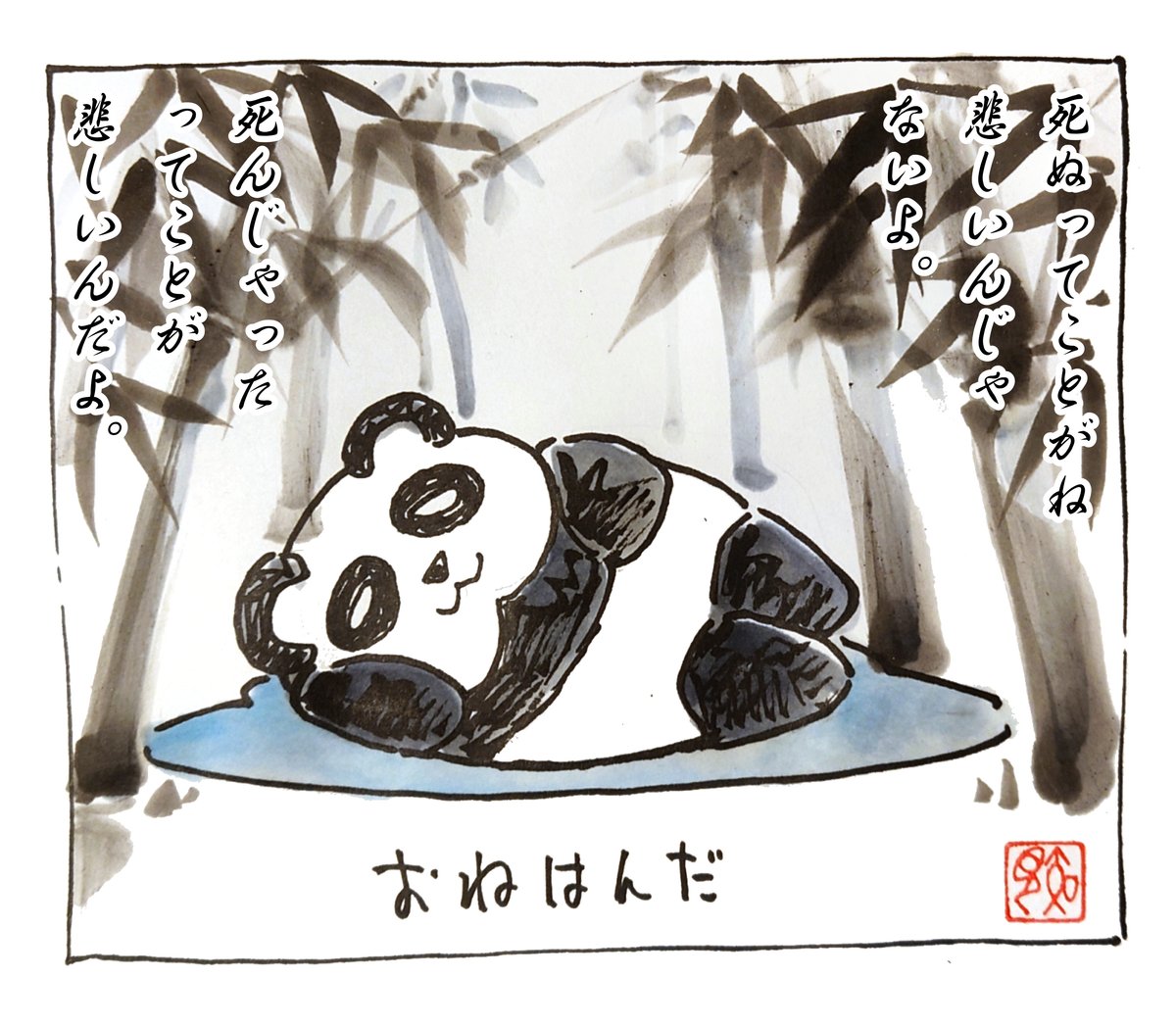
みなさま、こんにちは。
創作系寺嫁のゆかでございます。
今日は、地域の女性防災の会に、はじめて出席してまいりました。
というのも、そんな活動をしている会があると知ったのが先月のことだったのです。
なにしろ、怖がりなわたくしですので、いつか必ず来ると言われている南海トラフが、もう本当に怖い。
何が怖いって、どんな被害が起きるかも分からないのに、いつ来るかも分からないんですから、毎日どきどきしながら生きているような状況です。
なので、少しでもその怖さを減らそうと、いろいろな対策や可能性について知っておこう、と思っていたのです。
なんとか、防災グッズを思いつく限り揃えて、防災ボックスと緊急持ち出し箱を完成させたのが、先日のこと。
さて、地域では何をしているのだろうとドキドキしながら、会の扉をたたい
たのが本日でありました。
例によって、一歳七か月(いつの間にかもうそんなになっていました)のむちゅめをスリングに放り込んでお昼寝させながらの参加ですが、みなさま暖かく迎えてくださいました。
本当に、子どもを連れて行っても嫌な顔をされず、むしろ喜んでいただけるというのは、わたしみたいな母親にとってありがたいことこの上ない話です。
まず、なるほど、と思ったのが、地域住民が互いに仲良い状態を作るのが、防災の第一歩、という考え方です。
避難所に集まった人が、見知らぬ人ばかり、というのはどうしても気づまりになります。
必要な救援物資を、必要な方に届けるにも、個人情報が必要です。
田舎のプライバシーのなさは、たまには嫌な気分になることももちろんあるでしょうが、
「あそこの子、まだおむつの時期よね」とか、
「あそこのおじいさん、寝たきりだったからきっとおむついるわね」とか、
そういう情報が地域で共有されているということは、いざ災害に遭ってしまったときに、手を差し伸べてくれるきっかけになります。
大きな地震に遭った人の、防災に対する考え方の本などを読んでみても、おおよそ、地域住民でなんとかしなければならなかったときに、互いのことを知っている間柄の方がスムーズに行った、と書かれてあるのです。
私たちも、お寺として何かできることはあるのかな、と思いながら、いろいろなことを考えさせられる時間になりました。
とりあえずは、まだむちゅめが小さいうちは、他人を助けるような余力がなさそうなので、余力がある人が他の人を助けてもらえるように、自分たちのことは自分たちでできるように少しでも対策をしておくのが、当面、我が家の目標かな、と思います。
もし、むちゅめがもっと大きくなって、余力が出てきたころに災害が起きた場合には、私も余力となれる程度の知識を蓄えておくのが、今の私にできることなのだと思いながら、強風の中を自転車で帰ってきたのでした。
