
エコロジーに他者感覚を
こんにちは、本多です。お寺の住職、大学での教鞭、それからテラエナジーの創業メンバーとして取締役をつとめています。僕は小学校のとき、アメリカに住んでました。帰国子女、つまりリターニーでもあります。仏教×電気×世界。毎日考えることでいっぱいです。noteでは、日常で感じたことや考えたことをできるだけ素直に言葉化したいと思います。ゆっくりしたときに読んでもらえたらうれしいです。
相手は自分と同じような存在
テラエナジーの電気をつかうと、再エネ率の高い電気が供給され、あわせて支払った電気料金の2.5%が登録された団体に自動的に寄付される。テラエナジーの電気は再生可能エネルギー由来電源の比率は82%を越えていて、寄付団体である「ほっと資産」の数も42を越えた。電気料金をおさえながら、これらに同時に取り組むことは今のところ、普遍度の高い貢献だと思う。
こうした仕組み作りを起業当初から目指してきた。もちろん、株式会社として利益も追求しなければならない。それでもできる限りギリギリとのところまでつめてみようと思った。
そこで大事にしているのは、他者感覚(たしゃかんかく)だと思う。他者感覚とは「他人を他人の立場に立って自分として理解すること」だ。他者感覚の根っこには「相手が自分と同じような存在である」という気づきがある。他人を自分より上とか下とか見ていては、他者感覚はなかなか育たない。
ただ、僕たちは、すべての他者を自分として理解するような立派な他者感覚を持ち合わせていない。そこで自分たちの及ぶ範囲で、それをやってみようと努力している。寄付先団体の「ほっと資産」の営業では、特にそうした方面に力を入れている。その団体が困っていること、成し遂げたいことをできるだけ細かく聞くようにしている。
他者感覚の発想は、現代社会主流のものとはいえない。今の主流は「上からの倫理」だ(これについてはのちほど述べる)。
そこで他者感覚を軸に、善悪を組み合わせながら模索するテラエナジーの活動を、エコロジーの視点から紹介する。
「上からの倫理」ではなく
さきほども述べたように、世界では「上からの倫理」が主流だ。「上からの倫理」とは次のようなもののことだ。
「困っている人がいる。だから助けるべきだ。」
一見するとこれは正しいことを言っている。というか、どこにも間違いはない。
ところがこの種の倫理は、燃料切れを起こす可能性がある。なぜなら「困っている人」は無限に存在するからだ。また、困っているかどうかを判断するには「基準」が必要だ。その「基準」が正しいかどうかは、さらなる「基準」を必要とする。こうして「基準」の「基準」の「基準」…としているうちに、困っている人を助けることが出来なくなってしまう。正しい判断とは「時のもの」であり、時が経てば跡形なく去ってゆく。
もう一つ、「上からの倫理」は善悪にもとづいた行動をとることを指示する。「〇〇は正しく、〇〇は正しくない、だから△△せよ」と。つまり「〇〇すべき」というかたちを人々に要請する。それはやがて「〇〇しなさい」と強制になってゆく。結果的に「〇〇してない」人を攻撃してしまうことにつながる。
「上からの倫理」は今日、非常に強いものとなっている。他人の責任において自分が行動するという構図になってしまう。「△△さんが言ってたから」などの理由づけでしか動けなくなるのだ。結果的に「やってあげた」「やってあげてる」など被害と加害へと対立する。
環境問題についても、一歩間違えれば「上からの倫理」に凋落してしまう。「〇〇すべき」を強調すると、取り組んでいないように見える人を善悪の天秤にかけてしまいかねないのだ。
冒頭で他者感覚について触れた。他者感覚とは「相手が自分と同じような存在である」という気づきにもとづいている。仏教には「同体の慈悲」という、仏の慈悲をあらわす考え方がある。それは、次のような事例にたとえることができる。
料理をしているときに包丁で左手の指を切ってしまったら、どうなるか。傷口があらわれたその瞬間に、右手が飛んできて傷口からの出血をおさえるだろう。このすばやさは「キズがあるから、傷口をおさえるべきだ」と頭の中の指示を待ってから発生するのではない。「やるか、やらないか」を天秤にかけて判断するよりも早く、右手が傷口をふさぐのだ。なぜ早いかと言えば、右手も左手も体の一部だからだ。つまり、右手にとって左手は他者感覚なのである。
僕は「環境問題と仏教」を研究している。そこで強く感じるのは「上からの倫理」ではない方法を模索することが大事だということだ。
環境問題の解決を「上からの倫理」から切り離そうとした哲学者がいる。ノルウェーのアルネ・ネス(1912-2009)だ。北欧哲学界の巨匠ネスは、ディープ・エコロジーの提唱者としても知られる。ネスは、ガンジーの行動から活動することの大切さを学び、スピノザの哲学から世界の見方を学んだ。
ディープ・エコロジーは気候変動問題の解決を考えるうえでも非常に有効だ。そこでネスの思想の大枠を紹介しよう。
ネスのディープ・エコロジー
エコロジーには、近視眼的なエコロジー(シャロ―・エコロジー)と深く長期的なエコロジー(ディープ・エコロジー)がある。シャロ―・エコロジーは目先の目的を達成することに特化したエコロジーである。
シャロ―・エコロジーとはたとえるなら「SDGsウォッシュ」のようなものである。「SDGsウォッシュ」とは、SDGsに取り組んでいることのアピールには忙しいが、実際には17の課題解決にはほとんど関心がない、見せかけのSDGs活動のことである。
同様に、目的と手段が混同されたエコロジーも、シャロ―・エコロジーである。たとえるなら「ただ、やってるだけ/やらされているだけ」のエコ活動である。「やってるだけ/やらされているだけ」の活動では、個々の豊かさや活動のエンゲージメントが失われる。こうした一連のエコロジーは近視眼的でありシャロ―・エコロジーへと転落する。結果的にシャロ―・エコロジーは「上からの倫理」を要請する。
一方、ディープ・エコロジーは、近視眼的なエコロジーから距離を置く。目先の利益ではなく、全体的なヴィジョンにもとづいて行動することすすめる。なので、ディープ・エコロジーの運動は、長期的かつ持続可能でなければならない。長く続くためには、その根本によろこびや豊かさを必要とする。
したがってディープ・エコロジーでは、我慢したり、無理を強いて窮屈な思いをするような運動は採用しない。あくまで個々にとっての「気づきawareness」を基調とするのだ。
「気づき」についてネスは、それは「生命(いのち)がともに繋がっている」という共感意識を得ることだという。自分が網の目のように複雑な生命の関わりのなかにいるという「気づき」を得ることだ。生命の「気づき」は、さきほど紹介した「お互いに等しい」という感性がなければ生じないだろう。
ネスは若い頃、科学の実験で誤ってビーカーに入り込み、死にゆくハエをじっと眺めたという。すると、まるで自分が死ぬかのような感覚を抱いたという。ハエの死を自らの死に重ね合すことができるたのは「お互いに等しい」という感性が発露したからだろう。ネスはそうした感性の経験を取り戻すことが、エコロジーの中心にあると言ったのだ。
このように、生命の洞察をエコロジーの中心に据えようとしたのがディープ・エコロジーである。ディープ・エコロジーは「宗教的だ」と揶揄されることもある。というか、ネスこそはエコロジーにおいて宗教や哲学は不可欠だと積極的に語った人物なのだ。宗教や哲学は価値の原理を説くからだ。
最近、環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんの発言を聞きながら、ずいぶん哲学的になってきていることを感じる。彼女が始めた活動が大きくなればなるほど、グレタさん本人の心の深い部分での考察(哲学)が不可欠であることを彼女自身が感じているようにも見える。
まんじゅうを食べてみよう
テラエナジーの活動は、今日主流の「上からの倫理」ではないところとは別の道を模索している。それは「相手が自分と同じような存在である」ということを基盤に、いろいろと工夫をこらしながらサービスを提供している。
「相手が自分と同じような存在である」という実感は、実は頭で考えてもなかなか得ることができない。経験してこそのものである。
それはちょうどまんじゅうやスウィーツを食べるようなものである。食べてみて、食感や味覚を含めて味わうことができる。
ところが「上からの倫理」は味を先に教えてくる。「甘いよ」「やわらかいよ」「温かいよ」・・・万人にとっての味覚を押し付けてくるのだ。しかし、頭で味覚を理解しても、体はそれを味わってはいない。味覚は経験できていないのだ。
気候変動問題の解決も、社会課題に貢献することも、まだまだ教えられた味でしかない。そこで一度食べてみることをおすすめする。その根っこには、きっと他者感覚があるはずだ。
*
本多 真成(ほんだ しんじょう)
1979年生まれ。大阪八尾市の恵光寺住職(浄土真宗本願寺派)。龍谷大学大学院を修了し、私立大学の客員教授をつとめる。院生時代は「環境問題と仏教」の思想史研究。専門は宗教学。TERAEnergy取締役。
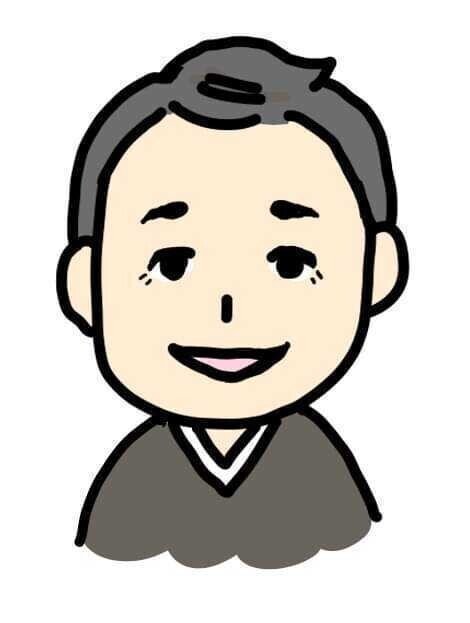
*
テラエナジーでんきのWebサイトはこちら
https://tera-energy.com/
3分で完了!テラエナジーでんきのお申込みはこちら
https://tera-energy.com/form/#anc-top
