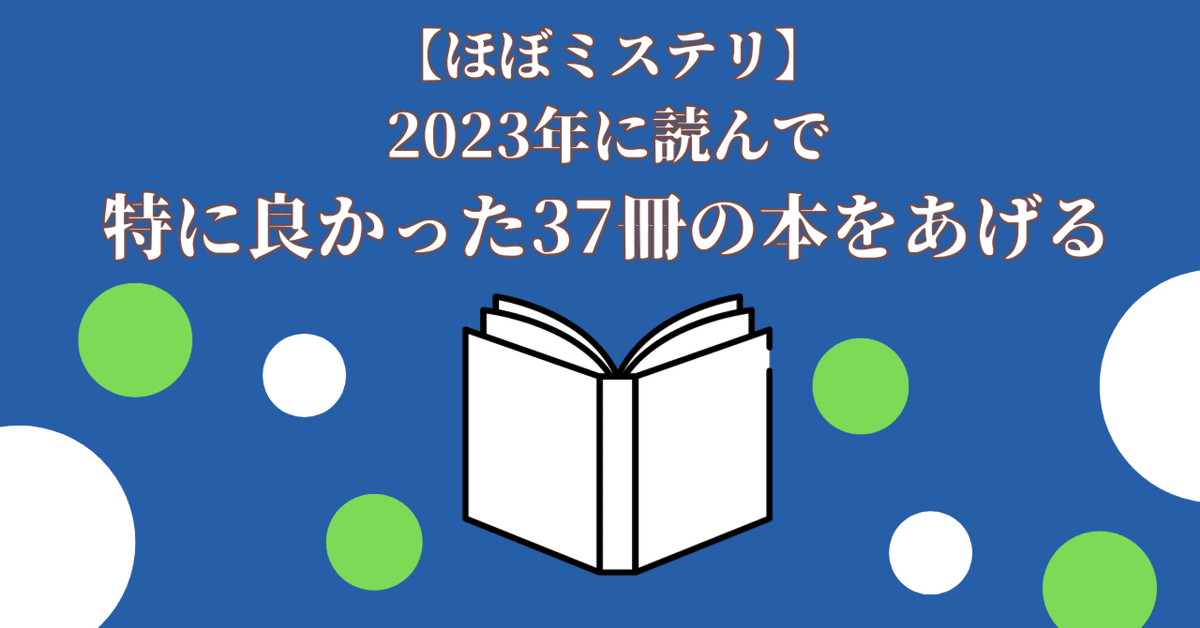
【マジで良い】2023年に読んで特に良かった本を37冊あげていく
2023年も面白い本をたくさん読んだ。
なかでも特に良かった37冊を、読んだ順に紹介していく。
本によって感想文のボリュームに差がある点、多くの本のあらすじを紹介していない点にはご注意。
早川書房『真珠湾の冬』(ジェイムズ・ケストレル著、山中朝晶訳)
今年最初に読み終わった本。白人男性と日本人女性が殺害された事件を追う刑事。容疑者の逃亡ルートを突き止めてマニラ・香港方面に向かうが、折しも真珠湾攻撃、太平洋戦争が勃発し……というあらすじに惹かれた。『FIVE DECEMBERS』という原題が示す通り、すごくすごく長い旅路だった。不安定な国際情勢や陰謀に翻弄されつつも、殺されてしまった人たちがいて、苦しんでいる遺族がいるという原点をずっと忘れない主人公・刑事マグレディの姿に胸が熱くなる。読了後の満足感はいまでも忘れない!
早川書房『鹿狩りの季節』(エリン・フラナガン著、矢島真理訳)
2022年度アメリカ探偵作家クラブ賞最優秀新人賞受賞作。「狭い共同体の中で絡み合った複雑かつしょうもない人間関係」の話を読みたいならこの本がおすすめ! 人はちっぽけなものを守るために嘘にしがみつくし、本人にとってはそれが何よりも(時には他人の命よりも)大事だったりするということを芯から実感できた。登場人物の大半は「うわぁ」となるリアルなイヤさがある(狭いコミュニティに属していた人なら共感できると思う)が、そうでない人たちもいて、そういう人たちの今後の人生に少なからず光が差しそうなラストになっているのが良かった。冒頭の謝辞で、筆者がありとあらゆる人に感謝しまくっているのも面白い。
アストラハウス『マーロー殺人クラブ』(ロバート・ソログッド著、髙山祥子訳)
出だしから「これは面白い話になるな!」と確信できた英国ミステリ。キャラクター・謎・物語という、私が思うミステリの「心技体」が超見事に極まっていた。特に、ジュディス・スージー・ベックスの主人公トリオがめちゃくちゃカワイイ! ジュディスは77歳。昨年あたりに読んだ『木曜殺人クラブ』、『かくて彼女はヘレンとなった』もそうだが、シニアが主人公のミステリは良作が多いと思う! 内容からは外れるが、文字の大きさと濃さがちょうど良くて読みやすかったのも印象的。
岩波書店『幕末百話』(篠田鉱造著)
「今年の特に良かった本」のなかでも一等良かった本。幕末維新を目の当たりにした人たちが語る、「あの頃こんな経験してさぁ……」というエピソードトークを集めた実話集。敗走して命からがら逃げ延びた彰義隊の参加者、当時の横暴を懺悔する元侍、よくわからないままお客の丁髷を切った床屋、辻斬りに殺されかけた町人、銭湯で適当に相槌を打っていたら「公方様悪口」の濡れ衣を着せられて拷問にかけられた夫婦など、幕末ならではの面白い話がポンポン出てくる。高圧的なお役人、災害、疫病、辻斬り、急激な時代の変化といった理不尽に脅かされながらも、それでも一生懸命したたかに生きていった民草に愛おしさを感じた。何度も読み返したくなる一冊である。
河出書房新社『死について! あらゆる年齢・職業の人たち63人が堰を切ったように語った』(スタッズ・ターケル著、金原瑞人、野沢佳織、築地誠子訳)
『幕末百話』に続くインタビュー本。救命救急士、元死刑冤罪者、原爆被爆者、退役軍人、元麻薬常習者など、本当にあらゆる年齢・職業の人たちが、自身が直面した「死」と「生」について生々しく語っている。家族の訃報が相次いだ自分にとって、考えを整理するきっかけとなってくれた。死を通して生を、過去を通して未来を、他者を通して自己を見るようになれる鏡みたいな本だと思う。
東京創元社『ダイヤル7をまわす時』(泡坂妻夫著)
トリックがとんでもなく良い短編集! 種も仕掛けしっかり見せられているにも関わらず、毎話解明パートでビックリさせられる。技巧派ミステリで発生しがちなクドさがないし、登場人物はみんな人間臭いし、ストーリーも面白いし、とにかくバランスが良い。泡坂妻夫面白すぎ。奇術師と呼ばれている理由がよくわかる。「ダイヤル7」と「芍薬に孔雀」が特に好きだった! 「広重好み」もお気に入り。
早川書房『死と奇術師』(トム・ミード著、中山宥訳)
1936年のロンドンを舞台とした、なかなかお目にかかれない袋綴じつきミステリ。読了後は抱いてたワクワクがすべて満たされて超幸せな気分になれた。主題となる謎は奇抜なものではないものの、掴めそうなのに掴めない蜃気楼のようで凄く惹きつけられる。袋綴じ部分を読んだ時の「パズルが完成する感」も最高! 古い時代のロンドンが舞台のミステリというのは、事件の顛末がしみじみとしていて趣き深い作品が多いように感じる。
東京創元社『金庫破りときどきスパイ』(アシュリー・ウィーヴァー著、辻早苗訳)
『死と奇術師』に続き、舞台はロンドン。今度は第二次世界大戦中という時代設定である。金庫破りのエリー&堅物のラムゼイ少佐の主人公コンビがとにかくカワイイ! 主人公たちがカワイイ小説は良作って決まっている。タイトルからわかるとおりスパイものということで、ハラハラさせられる場面もあったが、ラストはかなりじぃんとさせられた。シリーズものらしい。
早川書房『ミルク殺人と憂鬱な夏』(フォルカー・クルプフル、ミハイル・コブル著、岡本朋子訳)
帯で「迂闊」と紹介される田舎の刑事・クルフティンガーを主人公としたドイツミステリ。クルフティンガーは本当に迂闊なのに加え、部下にはちょっとナメられているし、奥さんには頭が上がらないしとなかなか情けないおじさんだが、事件に真摯に向き合う姿を見ているうちに「この人なんかカッコよくない?」という気分になる。「Milchgelt」という原題もかなり良い。田舎のゆる~い事件簿かと思いきや、大資本に押し潰されゆく農業という文化への熱い想いと危機意識を読者にぶつけるある種の社会派ミステリだった。その辺の農家への愛情のこもった視線は、シャーロット・マクラウドの〈シャンディ教授〉シリーズ味があった。
早川書房『哀惜』(アン・クリーヴス著、高山真由美訳)
今度は英国ミステリ。『ミルク殺人と憂鬱な夏』と同様、想像よりかなりアツい内容だった。ストーリーは記録のように淡々と進んでいくが、だからこそ読んでる私自身が素直にリアクションできた気がする。真相が明らかになったときはほとんど冷静ではいられなかった。第二作があるらしいのうれしい!
東京創元社『日本怪奇実話集 亡者会』(東雅夫編集)
暑くなってきて、怪談が読みたくなり買った、明治末期~昭和初期の怪談実話短編集。21世紀の怪談はリアルすぎて怖いので苦手だが、昔の日本の怪談は怖いというより情緒があるのでどちらかというと好き。やはりどの話も深い情念が関わっていて、読んでいるこちらも心を動かされた。
河出書房新社『世界最悪の旅』(アプスレイ・チェリー=ガラード著、加納一郎訳)
アムンセンとの南極点到達競争に敗れ、ほぼ全員が死亡したスコット探検隊の冒険を記録したノンフィクション。書いているのは、スコット隊に参加しながらも第一帰還隊に編成され、生還したチェリー=ガラードである。南極の旅路はまさに(チェリーが言うとおり)「世界最悪の旅」だったが、ところどころで隊員たちが仲良く助け合っている様子が描かれているのが癒しだった。それだけに冒険の結末が悲しい……。
東京創元社『折鶴』(泡坂妻夫著)
「泡坂妻夫ってこういうのも書くんや!」と驚かされた短編集。技巧を凝らしたミステリという点では『ダイヤル7をまわす時』と同様だが、今回のメインテーマは男女の機微である。『亜愛一郎』シリーズや『ダイヤル7をまわす時』とはまた味の違った滋味、苦味を感じられた。全編に渡って男女がエモすぎ。泡坂妻夫面白すぎ。表題作ではちゃめちゃに号泣した。あまりにも切ない。
東京創元社『人類の知らない言葉』(エディ・ロブソン著、茂木健訳)
今年読んだSFのなかで特に良かった本。「テレパシーで会話する異星人と接触し、友好な関係を築いている近未来」という舞台設定と、「主人公リディアはテレパシー通訳士」という人物造形、「リディアが専属通訳を務めていた異星人の文化担当官が、リディアの酩酊中に殺害された」というストーリーにかなり興味を引かれた。翻訳がかなりクールで、世界観の独特さが最大限引き出されていたように思う。主人公がアホ気味ながらジメジメしておらず、口が悪いというのもかなり良い。私にSFを楽しむ素質があることを教えてくれる本だった。
文藝春秋『幽霊ホテルからの手紙』(蔡駿著、舩山むつみ訳)
なんとなくホラーにはまったので買った中国発のサスペンス・ホラー。著者は「中国のスティーブン・キング」と呼ばれているらしい。目の前で起きているのは夢なのか現なのか、目の前にいるのは生者なのか死霊なのか、自分は狂っているのか正気なのか、すべてがわからなくなる不思議な感覚に陥らされた。
ハーパーコリンズ・ジャパン『チョプラ警部の思いがけない相続』(ヴァシーム・カーン著、舩山むつみ訳)
ここ数年アツさが続いているインドミステリ! なんと赤ちゃんゾウが相棒役である。ものの数ページで主人公チョプラさんのことを好きになり、序盤の定年退職シーンでチョプラさんの部下たちと一緒に涙ぐんでしまった。インドミステリの主人公は熱血の善人が多い気がする。あと部下が良いキャラしてがち。ページ数が物足りなくなるくらい面白かった! シリーズものらしく、次の話も是非とも日本語で読みたいものである。
早川書房『ミセス・マーチの果てしない猜疑心』(ヴァージニア・フェイト著、青木千鶴訳)
読んでいて1ページたりとも安心した気分になれないサイコミステリ。過剰な自意識や理想の自分と現実とのギャップなど、嫌な心理描写ばかり思い当たる節があってヒリつきまくった。カバーデザインと内容のマッチ具合すごい! 猜疑心や強迫観念、被害妄想に憑りつかれたミセス・マーチは手助けが必要な人だとは思うが、平気で人を見下すし妬むし憎むので、心からの同情はなかなかしにくい。ゾッとするしギョッとするけど、目が離せない。でも目を逸らしたくなる。それがミセス・マーチである。
東京創元社『卒業生には向かない真実』(ホリー・ジャクソン著、服部京子訳)
ここ数年の夏休みの風物詩。衝撃という言葉すら生ぬるいシリーズ最終巻。歯ァ食いしばって読んだ……。2回目は読めない気がする。あまりにもインパクトが強い。
東京創元社『Y駅発深夜バス』(青木知己著)
「こういうのが堪んなく好きなんだよ~!」と大満足できたミステリの短編集。ストーリーも登場人物もトリックもすべて良い塩梅。雰囲気もチャラついてなくて、かつ古臭くなくて私好みだった。「猫矢来」と「九人病」がとくに好き! 「特急富士」もかなり良い!
筑摩書房『怪を訊く日々』(福澤徹三著)
怖い話読みたい欲が高まって買った怪談実話集。21世紀の怪談はやっぱり怖い……。それでも惹かれてしまうのは、ひとえに暑すぎる夏のせいである。
新潮社『インスマスの影』(H・P・ラヴクラフト著、南條竹則訳)
『シャーロック・ホームズとミスカトニックの怪』というクトゥルフ×ホームズの激おもろパスティーシュ本が出た際に、クトゥルフのことを何も知らないことに気付いて予習として買った本。設定が入り組んでいて喧しそうだなと思っていたが、読んだら別にそんなことなかった。「異次元の色彩」、「ダンウィッチの怪」は結構好きなストーリー構成。「冒涜的」という感覚を100%理解できていたら、もっと楽しめた気がする。しかし表現がいちいち大仰なのがだんだんクセになってくる。「やつら」がことごとく「悪臭」を放っているのなんなの?
岩波書店『説教節 俊徳丸・小栗判官』(兵藤 裕己編集)
久々に読んだ古文! 読みやすかったし面白かった。「御前にて腹十文字にかき切り……鹿の臥処となすべし」とか「はやくいとま(はやくこの世からいとまを取らせよ)」とか、なかなかのパワーワードが出てくるのが古文の良いところ。
早川書房『郊外の探偵たち』(ファビアン・ニシーザ著、田村義進訳)
コミックライター兼編集者の小説デビュー作。かつてはFBIの敏腕プロファイラーだったが、いまは4人の子どものワンオペ育児に疲弊する妊娠中のアンドレア、落ち目のジャーナリストのケニーという「いまはイケてないコンビ」を主役にしたミステリ。序盤はのんびりしたテンポのように思えたものの、真実が明るみになるにつれて次第にストーリーに引き込まれていった。アメリカに蔓延る多様な差別を取り上げているのも好ポイント。ぜひ2作目も読みたい!
東京創元社『ナイフをひねれば』(アンソニー・ホロヴィッツ著、山田蘭訳)
今年の本命!!!!!! 大大大大大大大大好きなホーソーンシリーズ4作目!! もう4作目なのに天井知らずの面白さ! 先に原典予習済みだったが、それでも訳わからないくらい楽しめた。アンソニー・ホロヴィッツは留まることを知らない天才である。表紙デザインも好き! 来年上半期に英国で出る5作目の「Close to Death」も本当に楽しみ!!!
東京創元社『レイトン・コートの謎』(アントニイ・バークリー著、巴妙子訳)
英国ミステリ。この本もかなり良かった!! 1925年に出たということで、クラシックな雰囲気がありながらも、ユーモアたっぷりで読んでいてずっと楽しかった。犯人当て小説で犯人を外すことは滅多にないのだが、この本は完全に私を騙した。何度も読み返したくなる一冊!
東京創元社『蔭桔梗』(泡坂妻夫著)
『折鶴』に続き、男女の機微を描いた泡坂妻夫の短編ミステリ。濡れた石畳のようなつややかさと、しっとりした感じがあって何とも良い。この人が描く男女からしか得られない栄養素は絶対にあると思う。泡坂妻夫面白すぎ。
早川書房『渇きの地』(クリス・ハマー著、山中朝晶訳)
「オーストラリアが舞台の話って読んだことないかも」と思って買ったオーストラリアミステリ。本当に、さまざまな意味で重厚で、一冊読み終わったときにはもう半年くらい経ったんじゃないかというくらいの満足感と疲労感を覚えた。読み終わって解るタイトルの深みがすごい。『真珠湾の冬』っぽい気配するなと思ってたら、翻訳の人が一緒だった!
東京創元社『死の10パーセント』(フレドリック・ブラウン著、小森収、越前敏弥、高山真由美訳)
全13編のアメリカミステリの短編集。万事小粋で気が利いており、サクサク読み進められた。「ジャック・リッチーのびっくりパレード」でも感じたが、アメリカの短編集を読んでいると、コーヒーとベーグル(クリームチーズとブルーベリーのやつがいい)が欲しくなる。
東京創元社『帆船軍艦の殺人』(岡本好貴著)
第33回鮎川哲也賞受賞作。イギリス軍の戦列艦ハルバード号を舞台とするちょっと特殊な密室モノである。かなり高まった期待を悠々と超越する良いトリックだった。『名探偵と海の悪魔』、『シナモンとガンパウダー』に続き、「大海原が舞台のミステリにハズレはない」と実感させてくれる一冊。
早川書房『夜間旅行者』(ユン・ゴウン著、カン・バンファ訳)
ダークツーリズムの闇を描いた韓国ミステリ。最初は「本薄くない?」と思った(全221ページ)が、最終的に「このボリュームで良かったわ……」と心底ホッとした。ずっと悪い夢の中にいるような内容で、誰に肩を叩いて起こしてもらいたいと願わざるを得なかった。
原書房『リバタリアンが社会実験してみた町の話』(マシュー・ホンゴルツ・ヘトリング著、上京恵訳)
自由至上主義者たちが集団で移住してきたニューハンプシャーの田舎町グラフトンの顛末を描いたノンフィクション。「どうしてこうなった」と「そらそうなるわ」の交互浴。アメリカはほんまにぶっ飛んだ要素を抱えているということをイヤというほど実感させられた。すべての章で熊が出まくっており、熊被害が相次ぐなかで読むといろいろ考えさせられる部分もあった。トキソプラズマ(ネズミに感染すると、ネコに対する恐怖心を薄れさせるらしい)に関する面白く、また興味深い考察も出てくる。
早川書房『サークルストーンの殺人』(M・W・クレイヴン著、東野さやか訳)
面白いらしいとは知っていたが、どハマりしてどうしようもなくなることがわかっていたので避けていた英国ミステリ。しかし、とうとう引力から逃れられなくなったのでシリーズ全作まとめ買いした。これはその一作目。やっぱりどハマりした。どタイプすぎる物語・登場人物・謎で、もう何て言ったら良いのかわからない。新たな宇宙爆誕!!!! やはり主人公コンビがカワイイ作品は名作なのである。残りページが50%くらいの地点では「この先まだなんかあるん!?」となったし、残りページが5%くらいの地点では「もう終わっちゃいそうやけど大丈夫!?」とハラハラさせられた。原題の「The Puppet Show」はあまりにもキツい。その理由はぜひ自分の目で確かめてほしい。
東京創元社『11枚のとらんぷ』(泡坂妻夫著)
新装版とのこと。表紙デザインが可愛くてお気に入り。泡坂妻夫面白すぎ(今年4回目)。なんでこんなに面白いの?
中央公論社『漱石先生と私たち』(小宮豊隆著)
夏目漱石先生の関連本!! 先生の素直で可愛くて我儘で真剣なお人柄が伝わってくるのは勿論、同時に著者・小宮の果てしないLOVEと、小宮自身の可愛げも感じられるハイパー良本。正岡子規のおもしれー男ぶりも堪能できる。
早川書房『ブラックサマーの殺人』(M・W・クレイヴン著、東野さやか訳)
『サークルストーンの殺人』に次ぐシリーズ2作目。前作とはまた違った鮮烈さがあってかなりアツかった! 出だしでめちゃくちゃ引き込まれて一気読みし、ラストのラストで「たはは」と笑わされた。ポー&ティリーの主人公コンビが良すぎる。応援したくなる。
早川書房『キュレーターの殺人』(M・W・クレイヴン著、東野さやか訳)
『サークルストーンの殺人』の3作目。今回は本当に本当に本当にハラハラさせられた!! 終盤はハラハラしすぎて泣きそうになった。
早川書房『グレイラットの殺人』(M・W・クレイヴン著、東野さやか訳)
『サークルストーンの殺人』の4作目。前作で電話越しにのみ登場したメロディ・リー特別捜査官がいよいよ主人公たちの前に現れ、めちゃくちゃ心が躍った。アツさが留まることを知らない。仕掛け・動機・感情など、いろいろな要素がこれまで以上に複雑で、すべて解き明かすまで本を閉じたくないという気分にさせられた。これで現在日本で出ているシリーズをすべて読んでしまったが、この先どうすればいいのかわからない。ホーソーンシリーズと同じように、原典を買って先に読み、翻訳版が出るのを待とうかといったところである。
現在は岩波書店『最新世界周航記』を読んでいる最中。その後に東京創元社『案山子の村の殺人』、早川書房『元年春之祭』も控えており、年末も退屈せずに済みそう。
2023年はノンフィクションとホラーにちょっとハマった年だった。また、例年よりもタフな日々が続いたが、それでも落ち込まずに過ごしてこられたのは、面白い本のおかげである。今年私が読んだ本(ここで紹介した以外の本も含む)に一瞬でも関わってくれた皆さま、ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。何卒!!!!!!!
◎文=山﨑
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
