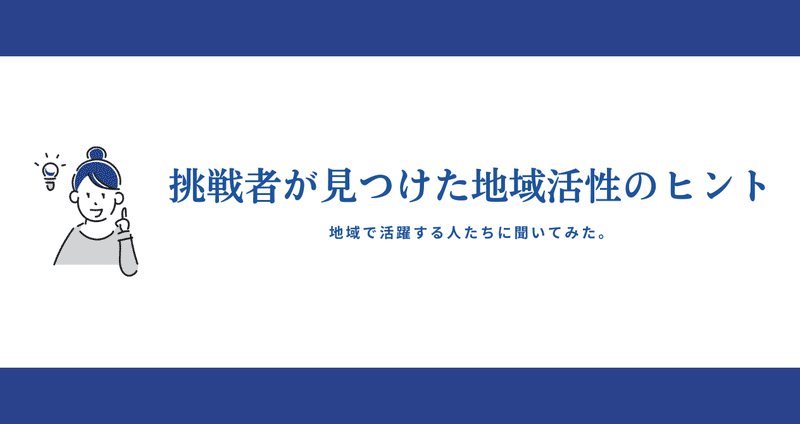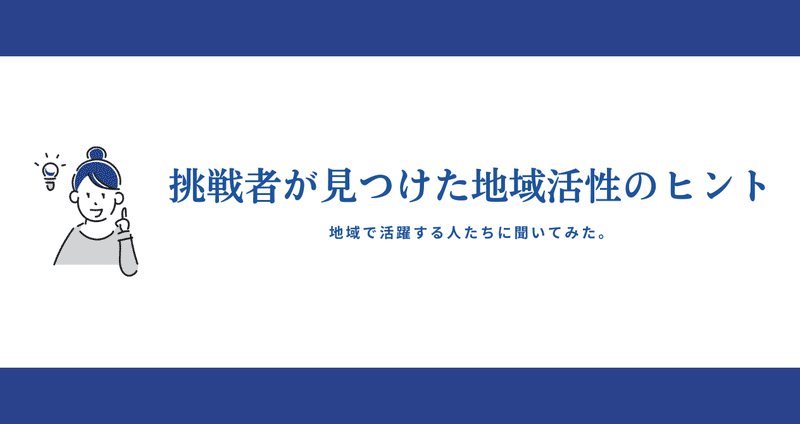「苦労した木の魅力を伝える」まな板から始まる日本の自然回帰【ワンダーウッド】
都会での忙しい暮らしに疲れてくると、人は「自然」を求める。定期的に海や山に行きたくなったり、公園で緑に囲まれて癒されたり。自然の息吹に触れることで心身がリセットされて、また日常生活を頑張れたりする。
今回お話をお伺いした一枚板ブランド「WONDERWOOD」の代表・坂口祐貴さんも、「人間は自然と共生するべき」ということを痛感する一人。彼が多忙により都会での生活に疲れ果て、出合ったのは「一枚板」。木の温もりに触れて、健康的な心と生活を取り戻した。現在ではそんな一枚板を世に広め